塾長ブログ
2025年06月
2025.06.25
テストの見直しをしよう!テスト直後の見直しが勉強を深める
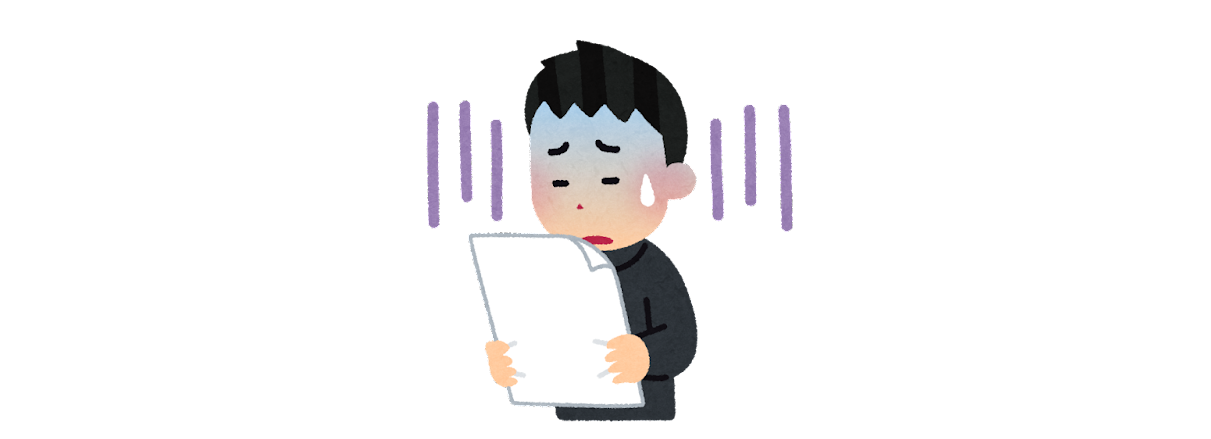
中学ではちょうど定期テストが終わり、高校ではこれから定期テストというタイミングだと思います。
中学生は一つの難関を終えてほっとしていることでしょう。
高校生も来週、再来週あたりにはテストが終わり解放感に浸っていることと想像します。
でも、テストはやったら終わりではありません。
実はテスト後の見直しが子供たちの学びを深めてくれるチャンスなのです。
だから、テストが返ってきて、その点数を見て一喜一憂して終わりではもったいない。
特にテストの点数が悪かったときは、悲しんで終わりにしないでほしいです。
結果が悪かったときこそ、自分を顧みて改善てきる絶好の機会です。









人間の記憶は回数×インパクト
例えば交通事故の現場など、頻度は少なくても非常に印象深い出来事であれば、一回でも詳細に覚えているものです。
一般的に言われる「トラウマ」などはその例です。
また、掛け算の九九のように、単調で何の面白みのないこと(インパクトの薄いもの)でも、何回も何回も回数をこなすことでいつの間にか身に付けることが出きます。
このように人間の記憶とは、回数とインパクトによって大きく変わってくると言えます。
そして、記憶が脳内に刻まれ長期記憶となれば、たとえ長い間忘れていても何かの拍子に次々と記憶を再構築することができます。
しばらく忘れていた歌を何かのきっかけで耳にしたとき、続けざまに全ての歌詞が思い出されるなどといった経験はございませんか。
この記憶の仕組みをうまく利用すれば、勉強もより深く定着させることができます。
そして、テスト直後というのは、この最高の機会なのです。
定期テストを通してエピソード記憶を作る
定期テストは生徒たちが一生懸命頑張って準備をして受けます。
テスト中も含めて、全身全霊を傾けたこの経験は、生徒たちの頭に強烈なインパクトを残します。
本気で取り組んだからこそ、その結果を見たときの喜びも悲しみも大きな印象として残ります。
このように個人の体験が一つの物語のようになり記憶となったき、これがエピソード記憶になります。
エピソード記憶が記憶を促す
人間は記憶するとき、目的のものそのものを覚えるより、何か他のものと関連づけて覚えた方が覚えやすいという傾向があります。
定期テストとその勉強を通じて行ったこと、考えたことはエピソード記憶となりますから、テストが終わったときに、この経験と学習内容をうまくつなぐことができれば記憶は促されます。
頑張ったのに問題が解けなかったときは非常に悔しいでしょう。
そして、このときテストの見直しをすると、この悔しさがインパクトになり、見直した内容をより深く脳裏に刻むことができます。
もちろん、正解した解答も同様です。
努力が報われた喜びも脳への大きなインパクトになります。
先ほど述べたように、テストを通じて得られた強烈なインパクトが記憶を促進するのです。
一方、テストが済んで何もしなければ、エピソード記憶と勉強との結びつけができず、勉強が記憶されないだけでなく、エピソード記憶も失われてしまいます。
だから、テストが戻ってきたときに間違った問題をもう一度確認するという作業は、学習内容とエピソード記憶の紐づけるはたらきをし、より効率よく勉強を進めることができるのです。
悪い結果は必ずしも悪いことではない
悪い結果が出たとき、単純にその結果に怒ったり悲しんだりするだけで、他に何もしない生徒が少なくありません。
確かに出てしまった結果は変えられませんが、これを次の学びへの教訓として役立てられれば、悪い結果もただ悪いだけにはなりません。
「失敗は成功の基」などといいますが、失敗を失敗で終わらせるか更なる飛躍につなげるかは生徒次第です。
定期テストで結果を出すことは大事ですが、勉強はそこで終わりではありません。
その後も続き、また新たな課題に取り組まなくてはなりません。
入試などもっと先の目標もあります。
したがって、定期テストが悪かったからと落ち込んで終わりにするのではなく、この機会を無駄にせず利用し、自分にとってプラスになるように持っていくのが賢いやり方です。
「テストで間違えが多いというのは、そこから学べることも多い」と考えて、前向きに勉強に活用してください。
毎回のテストの後のちょっとした心がけですが、これが積み重なったときその違いは非常に大きいです。
勉強は今だけを考えるのではなく、将来を見据えながら生かせるチャンスは全て貪欲に活用しましょう。









勉強は毎回の定期テストで終わりではなく、その後も続きます。
これまで学習したことが基となって新たな学びが生まれます。
一度出てしまった結果は変えられませんが、そこから学んで多くのことを得られれば、マイナスの結果を次のプラスに転じることができます。
そのためにもテスト後の見直しは重要で、全ての生徒に是非やってほしいと強調します。
もし、一人で見直すのが難しいという人は葛西TKKアカデミーが協力します。
一人でも多くの生徒がたくさん学べるようにと考えていますので、遠慮なくお声がけください。

























2025.06.07
”捨て問題”はテスト戦略の一つですが注意が必要です

「捨て問題」って聞いたことありますか。
塾でテストの戦略として使う言葉なんですが、しばしば生徒もこの言葉を口にします。
しかし、そのときの「捨て問題」の意味は間違っていることもあるので皆さんも注意してください。









「捨て問題」とは
そもそも「捨て問題」とは何でしょうか。
それは時間に限りのあるテストにおいて、難しい問題に時間を割かれ、本来自分が解ける問題に取り組む時間が無くなることを防止するため、難易度の高い問題、自分の能力をはるかに上回る問題は最初から放棄し、その分の時間を自分の力で何とかできる問題に当てるというテスト戦略です。
本当は全ての問題に全力で取り組み全ての問題に答えるのべきですが、制限時間内で全問解答ができない状況もあります。
そんな中で最大限の点数を得るためにはどうしても問題を選ばないといけません。
では、どのように問題を選択すればいいのでしょうか。
ほとんどの人が解けないような難問は、それができなくても成績順位にはそれほど影響しません(上位を目指している生徒は別ですが)。
なぜなら、みんなができない問題を自分が落としても、他者との点数にあまり差がつかないからです。
それならば、このような問題は最初から手を付けないで、その分の時間を自分ができる問題に割り振って、着実に点数を取っていこうということです。
逆に、みんなができる問題を落としてしまうと、他の多くの人から差をつけられることになり、成績も一気に下がってしまいます。
だから、誰もができる問題は絶対にできなければなりません。
しかも、最初から全問を解くことを放棄している訳ですから、全て解ける受験生に対しては不利な条件で争わなくてはいけなくなります。
ある意味背水の陣を敷くということです。
このように「捨て問題」というテクニックは特定の問題(それによって得られる点数)を犠牲にして、確実に取れるものを取っていこうというものです。
この他にも授業や問題集をやるとき、生徒の目指すレベルや実力を鑑みて、必要ないと判断した時は何問や応用問題をしないで、基礎に時間をかけることもあります。
そうすることで絶対に身に付けておかなければならない勉強を時間をかけてしっかり行うことができます。
これも一種の「捨て問題」と言えるでしょう。
間違った「捨て問題」とは
しかし、「捨て問題」(通称「捨て問」)を生徒たちが口にするときは注意が必要です。
なぜなら、「捨て問題」を誤解して、解く必要のない問題と捉えていることが多いからです。
塾などで「これは捨て問だからやらなくてもいい」と聞き、「捨て問」という言葉を覚える生徒がいます。
このとき、経験の少ない生徒はどの問題が「捨て問」で、どの問題が絶対に解けなくてはいけない問題かを区別できません。
そして、単純にやらなくてもいい問題があるんだと勘違いし、「捨て問」という言葉を使って勉強しない理由にしてしまいます。
その結果、自分が苦手な問題、面倒くさい問題、やりたくない問題、ちょっと難しそうな問題、これらを全て「捨て問」と認定し問題をしない口実にしてしまう。
このように勉強を回避する言い訳として「捨て問題」に生徒が言及する場合は、テストの点数を上げ成績をよくするための戦略としての「捨て問題」とは違い、生徒の勉強を損なう恐れがあります。
やりなさいと言っても「これは捨て問だからやらなくていいんだ」なんて言われたことはありませんか。
これは完全に本人の誤解で、全ての問題を自分の都合で「捨て問」にしていいとわけではありません。
先生が長年の経験に基づき、各生徒の学力や目標を考慮して、どの問題を「捨て問題」にすべきか判断するからこそ完璧ではないにしろ最大の勉強ができるのです。
繰り返します。
本来は全ての問題に取り組むべきですが、状況が許さない場合において苦肉の策として「捨て問題」を決めるのです。
生徒が自分のやりたくない問題を「捨て問題」として、自分が努力しなくてもできる問題しかしなくなってしまった場合、その生徒は困難を乗り越えて自分を成長させるチャンスを自ら放棄していることと同じになってしまいます。
これでは勉強の意味がありません。
勉強は分からないから、できないからこそするものです。
できるものしかしなければいつまで経っても成長も上達もなく、成績が良くなるはずがありません。
勉強は「α+1」
よく勉強は「α+1」と言われます。
αは自分の今の実力、これに1足したぐらいがちょうど学習にはいいというものです。
余りにも自分の今の実力からかけ離れたものはやっても理解できませんが、少し難しいくらいなら無理のない努力で学習を深めることができます。
この「α+1」の問題を「捨て問」と言ってやらなければ、いつまで経ってもαはαのままだし、ましてや楽な問題「α-1」なんてやっていたら成長どころか退化してしまいます。
勉強はやればいいというものではありません。
きちんと正しく丁寧にやらなければなりませんし、面倒くさがって楽をしようとすると自身を伸ばす機会を失い、後々自分がつらくなります。
困難や苦労を乗り越えた先に生徒一人ひとりの成長があり、勉強はそのための手段であり、自分を高める修行における試練だと考えてほしいです。
その点を理解すれば、「捨て問題」を勉強回避の方便にすることがいかに愚かしいか分かるのではないでしょうか。









勉強において、出された問題は本来全てやるべきです。
問題を解くことによって学んだ知識が定着し、より確実な力として様々な事柄に応用が効くようになります。
その結果、自身の能力を向上でき、より多くのことができる(学校の勉強に限らす)大きな人間に成長できるのです。
貪欲に問題に取り組み、自身をどんどん磨き上げるチャンスと捉えてください。
しかし、状況によってはそれが許されないときがあります。
そんなとき、対応策の一つとして「捨て問題」という方法がというわけで、決して最善策というわけではありません。
そして、「捨て問題」の区別は長年の経験がある者でないと適切にできず、生徒が自分の気分や好みで決めていいものではありません。
したがって、先生の指導に基づかないで生徒が行う「捨て問題」は、せっかくの学びのチャンスを不意にし、勉強を深める機会を逃す恐れがあるので十分気をつけましょう。
「捨て問題」と生徒が口にしたときはなぜそれが捨て問題か問いかけ、「捨て問題」の本当の意味を説明し誤解のないように願います。

























- 1 / 1

