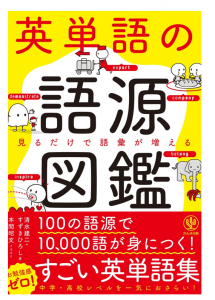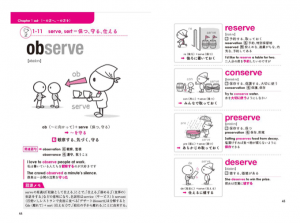塾長ブログ
2018.11.29
図画工作など他塾でない授業も行います。個々のニーズにお応えする個別指導塾葛西TKKアカデミーは五教科のみではありません。
生徒一人ひとりに合わせた授業を提供する個別指導塾葛西TKKアカデミーは、他塾にはない授業も行います。











葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは、皆様の要望に可能な限りお応えすることをモットーとしております。
よって五教科だけでなく、他塾ではやらないような教科の指導も行います。
ということで、そんな一例として現在、図画工作の指導も行っています。
写真は授業で扱った自動車や飛行機の工作、水彩画です。
生徒も非常に楽しんでいます。
今まで平面的でしか描けなかったのが、立体を意識できるようになったり、色を一色でべったりと塗っていたのが、一つ一つの陰影や質感まで考えられるようになりました。
ピンセットや紙やすり、ニッパーなど触れたことのない道具も器用に使えるようになりました。
経験を積めばもっと上手になることでしょう。
他にも折り紙やクレヨン画もやりました。
今後も様々なものを作っていきたいと考えています。
作品を作ることを通して特に発想力を育み、道具の使い方も身に付けてほしいと思います。
これらは授業以外でも、生活の色々な場面に役立つものだからです。











多彩な授業内容が自慢の葛西TKKアカデミーは、他に作文指導や面接の指導なども行っています。
直接学校の教科に関わることだけでなく、何でもご相談いただきたいと思います。
全ての人の力ないなりたいと考えていますので、気軽にお問合せください。
2018.11.07
冬期講習生徒募集中!何と新規生は無料!冬休みを利用して、皆様の勉強のお手伝いをします。特に受験生は冬休みをどう過ごすかで、合否が分かれます。この機会をお見逃しなく!
来月には冬休みが始まります。
この長期の休みを利用して、葛西TKKアカデミーは冬期講習を行います。
小学生から高校生まで対応いたします。
冬休みの課題をするもよし。
今まで学校で分からなかったところの確認をするもよし。
新学期に向けて予習をするのもいいでしょう。
また、受験生は本番直前の最後の頑張りとして、冬期講習を利用してください。
更に、自習はし放題で、授業でないときも勉強ができます。
もちろん分からないところは遠慮なく先生に質問して構いません。
先生が親切丁寧に教えてくれます。
家ではなかなか勉強しづらいと思いますので、葛西TKKアカデミーを第二の勉強部屋として使ってください。
しかも、疲れたら休憩エリアでお菓子とドリンクを自由にいただけます。

葛西駅より徒歩3分。
アクセスも便利な個別指導塾、葛西TKKアカデミーです。
〈ここでキャンペーン情報!〉
お問い合わせの際に「まいぷれ江戸川区を見た。」とおっしゃってください。
もれなく次の得点がついてきます。
 今だけお得、五大特典
今だけお得、五大特典
・1セット(授業5回分)が無料で体験できます。
・更に入塾してご兄弟、友人を紹介していただければ、1人に付き2000円、2人で5000円、授業料を割引!
・今、入塾すれば授業料30%OFFのキャンペーン中。
・入会費20000円が無料!
・自習し放題!
つまり、無料で冬期講習が受けられ、更にキャンペーンと紹介割引を利用すれば、何と個別指導でありながら授業料が一万円以下になることも可能!
是非、お見逃しなく。
特に中学三年生には受験に向けた授業を準備しております。
一般入試に加え、推薦入試のサポートも致します。
進路相談も承りますので、
進学にお悩みの方は気軽に葛西TKKアカデミーにいらしてください。
上記以外にも、様々な授業の用意があります。






























2018.10.31
今日はハロウィーン、日本でもお馴染みになってきましたが、そもそもハロウィーンって何でしょう。
クリスマス、バレンタインデーに続き、日本でもハロウィーンが定着しつつあります。
最近では毎日のようにニュースで仮装した人たちが町を練り歩くのが見られます。
ところでハロウィーンとは何なのでしょうか。
単に仮装を楽しむ日ではありません。










ハロウィーンはケルトのお祭りが起源と言われています。
10月31日はケルト人の大晦日に当たり、この日に秋の収穫を祝うお祭りが行われていました。
この一年の終わりの日の夜に、死者の魂がこの世に戻り、また魔女や悪霊が悪さをするとも信じあれ、悪魔払いの意味合いもありました。
時代が下り、このお祭りとキリスト教が融合してハロウィーンになったと言われています。
11月1日は「万聖日(諸聖人の日)」というカトリックの祝日で、全ての聖人と殉教者を記念する日とされ、キリスト教でも死者の魂がこの世に戻ってくると考えられています。
魂が帰ってくるという意味では、日本のお盆に似ていますね。
この日にお墓参りをしたり、亡くなった人に祈りを捧げたりします。











なぜ仮装をするのでしょうか。
死者の魂と共に、悪霊や魔物もこの世にやってきて、この世の魂をあの世に連れて行こうとすると考えられています。
よって、お化けの格好をして仲間を思わせて、自分の魂が連れていかれるのを防ぐのです。
だから、女子高生やマリオやスーパーマンなどの仮装は意味なさそうですね。











「トリックオアトリート」はどうして始まったのでしょうか。
元々ヨーロッパで、仮想した子供たちが歌いながら、さまよっている魂のために、「ソウルケーキ」という干しブドウ入りのパンを一軒一軒訪ねらながら集める習慣がありました。
そして、何も差し出さないとこの子供たちや霊がいたずらをすると考えられていました。
1900年代初期にある子供が「Trick or Treat!」と言い出し、1952年のディズニーアニメの中でこのセリフが使われたことにより、世界中に広まったとされます。
仮装をする人は増えていますが、日本ではまだ家を練り歩いてお菓子を集める子供は少ないですな。
各家庭もお菓子を用意していなかったりして。
お菓子メーカーはハロウィーンパッケージのお菓子を盛大に売り出していますし、お寿司など関係のない業界も便乗しようと頑張っていますね。
日本ではバレンタインデーと同じように商魂あってのハロウィーンでしょうか。









お祭り好きで宗教に節操のない日本では、新たな騒ぎの口実としてハロウィーンが広まって見えます。
日常に楽しみを求めるのはいいのですが、くれぐれも行き過ぎのないように、マナーを守って楽しんでください。
こうやって異文化も取り込んで、人々の暮らしも変わっていくのだと実感しています。
お化けにいたずらされないように気をつけて、皆さんもHappy Halloween!



























2018.10.23
生徒がドールハウスを作りました。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは図画工作の指導も行います。
本日は小学生の生徒がドールハウスを作ったので紹介します。
縦9㎝、横14㎝、高さ14㎝くらいの大きさですが、細部まで作り込まれています。
これは市販のものですが、生徒が強く希望したので作ってみました。

小学生には難易度が高いので、わたしも手伝いました。
この大きさで、クッキーやハーブの入った袋、メニュー表など小物もしっかり作りました。

どうしても細かい作業は大変なので、わたしがしましたが、それ以外のところは本人が一所懸命に頑張って完成させました。
特に壁や屋根の質感は最高にできたと思います。
建物の内部も精密にできており、完成品は見ごたえのあるものに仕上がったと思います。
本人も満足したようで、また別のを作りたいと言っていました。











個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、生徒の要望に可能な限り応じています。
この図画工作の授業も生徒の希望によるものです。
たまたま今回は難しいものをしましたが、普段は紙や木の棒など簡単なものでの工作もしますし、絵もクレヨンや水彩絵の具を使ったものも行っています。
技術の向上も大事ですが、色々想像し工夫して実現できるような指導を心がけています。
とにかく生徒が楽しんでもらえれば何よりと考えています。











皆様も、どんなことでも構いませんから、気軽に相談してください。
他の塾ではやらないようなことも、小規模個人塾なのでできる場合があります。
無茶ぶり大歓迎!






























2018.10.12
日本語教育の必要な生徒の中退率が高く、進学率や就職率は非常に低いことが分かりました。彼らに対する支援の不足が原因と思われます。
先日、ニュースで文科省の行った調査結果について発表がありました。
日本語教育が必要な生徒に関するものです。
外国からの移住や帰国子女の生徒で、十分な日本語教育ができていない生徒がどのような状況にあるものかを調べました。












そこで分かったことは、日本語教育が必要な公立高校生のうち、9・61%が昨年度に中退していました。
2016年度の全国の公立高校生の中退率は1・27%で、日本語教育が必要な生徒は7倍以上の割合で中退していました。
また、高校からの進学率は平均の約6割で、就職する場合は平均の約9倍の確率で非正規の仕事でした。
言語の壁がこのような結果を生み、支援の不足が背景にあると指専門家は摘しているそうです。
在籍している学校が日本語教育が必要だと判断した子どもは、16年5月に全国の公立小中高校などに約4万4千人おり、過去最多でした。
このうち高校生は外国籍の生徒が2915人、日本国籍の生徒が457人の計3372人で、10年前の約2・6倍です。
近年は急増しており、調査対象となった昨年度は4千人近くが公立高校に在籍していたとみられます。












外国人労働者の増加などに伴い、日本語教育が必要な子どもは今後も増える見通しで、支援の必要性が指摘されています。
特に高校は小中学校と比べても不十分とされています。
このような生徒は日常会話は問題なくできるのに、(授業中の勉強の日本語は理解できていないことがよくあります。
これは、そもそも授業中に使っている日本語が特殊だからです。
よって、日常会話でがしゃべれるからと言って、先生の言っている内容分かるとは限りません。
やはり、専用の訓練が必要です。












上記のような生徒のために、葛西TKKアカデミーでは日本語教育も行っています。
言葉ができないから勉強についていけず、学校を辞めなくてはいけない、進学をあきらめなくてはならない、正規雇用もしてもらえない。
これでは子供たちがかわいそうです。
そのようなことにならないためにも、葛西TKKアカデミーは全ての生徒の支えになれるように頑張りたいと考えています。






























2018.10.09
毎年恒例の「国語に関する世論調査」が発表されました。「なし崩し」の意味は分かりますか。本来のものとは違う意味で言葉を使っている人が増えています。
毎年秋になると文化庁による「国語に関する世論調査」の結果が発表されます。
いつも興味深く見ているのですが、言葉が本来のものとは違う意味で使われてることが増えているのが分かります。
今年もいくつかの慣用句や語句に関するアンケートが行われました。
そこからは日本語が変化しているんだということが分かります。
日常的に使っている言葉でも、実は意味が違っていてびっくりすることがあります。











皆さんは次の言葉の意味が分かりますか。
檄を飛ばす
やおら
なし崩し
「檄を飛ばす」は「自分の主張や考えを、広く人々に知らせて同意を求めること」で正しく回答した人は全体の22.1%で、本来の意味ではない「元気のない者に刺激を与えて活気付けること」を選んだ回答が67.4%となりました。
また、「やおら」は本来の「ゆっくりと」という意味を答えた人が39.8%で、逆の「急に、いきなり」と答えた人が30.9%でした。
いずれも以前よりも間違った意味を答えた人が減っていますが、それでも少しで全体の誤答率は以前として高いです。
今回新たに「なし崩し」に関する調査も行われました。
「借金をなし崩しにする。」などと使いますが、間違った意味の「なかったことにする」と答えた人が65.6%で、正しい「少しずつ返す」の19.5%を大きく上回っています。
非常に興味深い結果でしたが、皆さんはどうでしたか。
正しい意味を言えましたか。










更に、新しい言葉の使用についても調べてありました。
ほぼほぼ
後倒し
上から目線
タメ(タメ口)
立ち位置
ガチ
どれも高齢層では使うことがないようですが、若年層ではかなり普及しています。
私も「後ろ倒し」は聞いたことがありませんでした。
このように世代間で言葉の使用が異なるのには、日本語特有の事情があるみたいです。











日本語は変化の激しさで、世界的にも珍しい言語です。
大陸の国では、侵略されるたびに言語が奪われる経験があり、アイデンティティとして自分の母語を守ろうとする傾向が強いのですが、日本ではそのような経験と心配がないからか、逆に変化を楽しみ、わざと新しい言葉を生み出しているように思えます。
毎年「流行語大賞」が決められるくらい次から次へと言葉が生まれ、そして死んでいくのです。
和歌や俳句、回文やダジャレなど、日本人は伝統的に言葉遊びが本当に好きです。
このような文化を持つ日本語を大切にしたいと思います。
ただ、個人的に気になることは、言葉の変化よりも言葉の貧困です。
以前触れたことがありますが、日本人の言葉の数が減っているように思えます。
その原因は現代特有の環境(SNSなど)や合理性、意味だけ伝わればいいという考え方などがあると思います。
しかし、いつも同じ表現では微妙なニュアンスが伝わりません。
最近の若者はその点はあまりこだわらないようです。
美味しくてもまずくても「やばい」ですから。

でも、言葉はそのまま思考に結びついているので、言葉の貧困は思考の貧困につながります。
白か黒しか言えなければ、感情も怒るか笑うの極端の二択になってしまいます。
しかし、現実はその中間に幅広いグレーゾーンがある訳で、そこがつかみ取れなくなってしまいます。
社会生活を考えたとき、言葉の豊かさは非常に重要だと思います。












この調査は他に、「国語や言葉への関心」や「句読点や符号の使い方」「メールの書き方」「外来語についての意識」などについて結果も公表しています。
興味のある方は文化庁のサイトをのぞいてみてください。






























2018.10.06
図書紹介『英単語の語源図鑑』。英単語を覚える時、同じ部分を持つものが多いなと感じたことはありませんか。その理由を知ると単語が覚えやすくなります。
本日紹介する図書は、清水健二著『英単語の語源図鑑』です。
英語の勉強をするとき、共通する部分を持つ単語が多いなと感じたことはありませんか。
export express expand
attention observation condition
他にも「ad」「im」「ment」「er」「sion」など。
実はこれには意味があるのです。
それはどのようにしてこれらの言葉ができたかを考えると分かります。
例えば「ex」は「外へ」という意味を持つ接頭語、単語の頭について意味を受け加える言葉です。
ex+port(運ぶ)・・・輸出する:国の外へ運び出す
ex+press(置く)・・・表現する:自分の中から外へ印象を置く
ex+pand(広げる)・・・拡張する:外へ広げる
こうすると「ex」のついている言葉は共通の意味を持ち、まとめると一度にたくさん単語が覚えられます。
記憶するには意味づけが重要ですから、語源を知ることは有効です。
ここから他の単語に結び付けて、更に単語を覚えることができます。
先ほど「export」をしましたが、「ex」を「中へ」という意味の接頭語「im」に変えると「import」となります。
「port」は「運ぶ」でしたから、「中へ運ぶ」という意味になり「輸出する」という言葉になるのです。











『英単語の語源図鑑』はこのような語源と結びつけながら、英単語を説明してあります。
しかも、「図鑑」とあるように、言葉の本でありながらイラストをふんだんに使っているので、非常に分かりやすくなっています。
このように一度にたくさんの英単語が覚えられますし、イラストがあるので印象に残り覚えやすくなっています。
語源から言葉の本質が分かるので、その基本的意味から派生した他の意味も理解できます。
こうして意味を持たせた言葉は脳が記憶しやすいので、単なる丸暗記よりも効率よく身に付けることができます。










収容単語数は1000ほどですが、基本的な言葉が多く、第一歩としては十分でしょう。
今後も続編を出版し語数も増やすようです。
英語中級車でも、この本を使って単語を見直すとより理解が深まり、「そういう訳だったのか。」と実感納得することができるでしょう。
初級の方のみならず、単語を見直し整理をされたい方、基礎単語を増やしたい方にもおすすめです。
2018.10.03
日本人がノーベル賞を受賞しました。受賞した本庶教授の言葉は学びの本質をついていました。
先日、ノーベル医学・生理学賞で日本人の本庶教授が受賞されました。
本庶教授は免疫学の権威で、免疫細胞を利用した、がんの新しい治療法を発見しました。
これまでがん治療は、外科手術、薬物療法、放射線治療の三つでしたが、それぞれに問題も抱えていました。
これらに第四の治療法として、本庶教授の療法が加わりました。
患者自身が持っている免疫細胞を活用し、がん細胞を攻撃し治療する。
元々がん細胞は自身の細胞なので、免疫細胞はがん細胞を攻撃することはできませんでしした。
これを薬品により攻撃できるようにしたのです。
このようにして患者の本来持っている力でがんを撲滅する治療法を生み出したのです。









今回の受賞に伴い、行われた記者会見の中で興味深い言葉が聞けました。
研究に当たり大切にしていることを聞かれたとき、「何か知りたいという好奇心」と「簡単に信じない」とおっしゃっていました。
この二つは当塾でも大切にしていることで、勉強もただやるだけの作業にならないよういつも心がけています。
だから、人間本来持っている知的好奇心を大切にし、それを刺激し満たすことを目指しています。
そうすれば勉強も楽しくなりますし、理解も深まります。
学ぶ喜びを大事にしたいと考えています。
現在の教育では、様々な制約や条件でこれが経験しずらい環境にあると思います。
効率と結果ばかり求められ、勉強の本質まで掘り下げる余裕がなくなっています。
その他、物理的条件など様々あり、みんなが楽しめる学びは難しくなっています。
今回の受賞で、社会的にこの点の改善がなられるといいと思います。
二つ目の「簡単に信じない」というのも大事です。
今の生徒は従順すぎることが時々あります。
言われたことを素直に受け入れ、言われた通りする。
それはそれでいい子なのですが、従うことばかり身に付いてしまうと、自分で考えることができなくなってしまいます。
この言葉は全てを疑えと言っているのではありません。
とことん追求し、本当に自分が納得できるまで努力しろという意味です。
本当に納得するまでは、たとえ先生の言うことでも、おかしいと思えば反論するくらいの熱意がほしいです。
こうすることでより理解し、考える力も付いてきます。
そして、自分に確信が持てるまでやる根気を持つということでもあります。










元々子供はいろんなものに興味を持ち、不思議に思いなぜかと常に聞いていました。
少なくとも小学校低学年までは、このような子供が多いと思います。
しかし、いつのころからか子供の中の好奇心の灯が小さくなっていくのです。
中には完全に消えて、学びに対して無関心になってしまう。
これは非常にもったいないことで、子供たちの持っている可能性を大きく狭めることになります。
子供たちの経験が好奇心や学ぶ喜びを失わさせ、そのような経験を与える環境が子供たちの周りにある。
本当に重大な問題です。
このような状況を変えるために、葛西TKKアカデミーは、子供たちが明るい顔で学び、学びの本質をつかめるように努力しています。



























2018.09.27
都立桜町高校の演劇の公演に行ってきました。
先週の日曜日、9月23日に都立桜町高校演劇部の公演がありました。
当塾の生徒が演劇部で、ありがたいことにお誘いを受けましたので、喜んで行ってまいりました。
このように声を掛けてもらえるのは本当にありがたいことで、生徒とのつながり、人と人との関係を大切にしてきてよかったとつくづく実感しました。
これがこの塾の特徴であり、今後も生徒や家庭との結びつきを大切にし、末永くお付き合いのできる塾にしたいと考えております。









この公演は現在行われている、東京都高等学校文化祭の演劇部門地区大会の一環としてで、都内各所で次の週末まで開催されています。
優秀な学校は地区大会から都大会、関東大会、全国大会と進んでいくわけです。









ちなみに、この公演は蒲田の日本工学院専門学校で行われました。
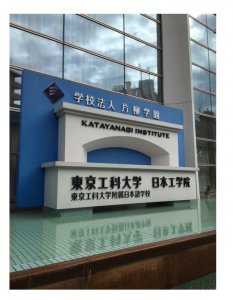
この学校は日本工科大学の系列の学校で、校舎は新しく清潔感があり、今風の建物になっていました。
随所に学生の作品が展示してあり、勉強の成果がうかがい知れます。
立地も駅に近く、利便性に富む町の中にあるのでいいです。
工学系の勉強を考えている方は、一考の余地ありです。









演目は「××の子」というもので、家庭内に問題を抱える親子、そんな家庭を持つ生徒に向けられる偏見と悪意のないいじめという敏感な問題を鉄道部という変わり者の集まりを通して、コメディータッチで描いた物語です。
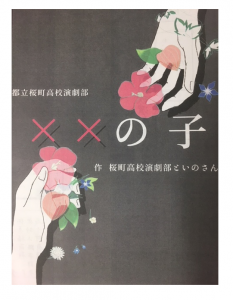
主な登場人物は高校生で、器用に世間を渡れず葛藤し苦しむ時期の子供たちを上手く演じていたと思います。
笑いを誘いながらも、重い問題をしっかり訴え、物語をまとまりのある結末に導いているので、非常に良い脚本であったもいます。
見る方も十分に楽しめましたし、すっきりとした気持ちで見終えることができました。
高校生と言ってもしっかり頑張っているなと感心しました。
喜怒哀楽もきちんと演じ分けられていましたし、時には迫力もありました。
どの生徒も満喫して楽しそうでした。
もちろん舞台の上に立っている者だけがこの演劇の主役ではなく、表には出ない裏方の役割も決して忘れてはなりません。
観客からは分かりにくいですが、しっかりとして裏方もいないと演劇は成り立ちませんからね。
他にも指導する先生や、多くの方々の協力もあってこその成果だと思います。









今後も生徒とのつながりを保ち、このような機会には積極的に参加したいと思っています。
ただ勉強を教えるだけ、受験に合格させるだけでなく、一人の人間を育て、その人生に大きく関わるのだという自覚と責任を持って、この塾をやっていきたいと考えています。
また何かありましたらご報告いたします。











2018.09.26
先日、9月24日はお月見でした。実は、年中行事って受験でよく出るんですよ。
先日、9月24日はお月見でした。
十五夜とも呼ばれ、旧暦の8月15日辺りに出る満月の夜のことです。
中秋の名月と言い、日本人はその見事な月を眺めながら歌を詠んだりしました。
今回のお月見はあいにくの曇り空でよく見えなかったようです。
その前日に見て、わたしも十五夜に気づいたのですが。










お月見を始めとする年中行事は、実は受験でよく出る話題です。
特に中学受験では、社会や国語などで出てきます。
各行事の日にちや由来、何をするのかなど問われますが、学校などであえて授業中に学ぶことはないと思います。
つまり、勉強というより、一般常識として聞かれるのです。
しかも、意外と年中行事に関する問題は多いです。
だから、知ることは必要です。
あえて勉強として学ぶよりは、実際に年中行事として家庭で実践された方が、子供も実体験として理解し、いい思い出にもなるので、家族みんなで楽しみながら、由来などを話し合うといいでしょう。
日本の伝統文化を学ぶことにもなり、日本的な考え方が分かってくると思います。
最近はクリスマスやバレンタインデー、それからハロウィーンなど西洋の年中行事も浸透してきているようで、こちらも子供たちに体験されるのがいいと思います。









現在行われている教育改革では、「考える力」を重視します。
年中行事を通して日本人の心を考える問題も当然想定されます。
年中行事に限らず、経験を通した学びは知識ではなく知恵として蓄積されるので、「考える力」を育てるには非常に大事になります。
皆さんも家族で年中行事を楽しみながら、子供の「考える力」を養いましょう。