塾長ブログ
2026.01.01
新年あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。
皆さまは新年の最初の一日をどのようにお過ごしでしょうか。
よい年明けを迎えられたことと思います。
葛西TKKアカデミーは去年に引き続き、本年も生徒たちの支えになれますように、全力で頑張りたいと思います。
特に開校以来10年という節目に当たる今年は、何か記念になるようなことをしたいと考えております。
ご期待ください。










いよいよ新年の幕開けです。
2026年になりました。
去年に引き続き、皆様には葛西TKKアカデミーをご愛顧いただけますように、心からお願い申し上げます。
これまでと変わらず一人ひとりの生徒に向き合い、全ての生徒が明るい未来を歩めるように尽力したいと考えております。
今年の受験
今年は二名の高校受験生がいます。
二人とも受験勉強のスタートが遅かったせいで、例年よりはスケジュールが遅れていますが、一所懸命頑張って入試本番に間に合うように頑張っています。
本日も実は授業があり、冬休み中はほぼ毎日です。
でも、遅れを取り戻すにはこれくらいやらないといけないので、大変なのは分かりますが何とかついて来てほしいと考えています。
一人は推薦入試も受けるので、厳しさも人一倍です。
推薦入試を受けるかどうか相談があったとき、「いい加減な気持ちで受けるならやらない方がいい。やるなら本気でやらないといけない。しかも、一般受験の勉強と同時進行なので相当の覚悟が必要だ」と告げました。
しかし、本人がそれでも挑戦してみたいというので、その対策を請け負うことにしました。
実際、推薦入試対策が始まり、本人もその大変さが実感として分かってきたようですが、初心を忘れず最後まで貫徹してほしいと思います。
面接の応答や振る舞い、小論文の書き方の練習とその習得を目指して奮闘中です。
若いうちの苦しい経験は人を大きく成長させます。
上手くいこうといくまいと、この経験は彼女にとって大きな意義があると思います。
私が支えるから、逃げることなく最後までやり切りましょう。
その後は都立高校の入試本番です。
今年は2月21日です。
泣いても笑っても、もう後わずかです。
後悔することのないように、今を全力で頑張ってください。
全員持てる者の全てを出し尽くし、決して悔いのない受験をしてほしいと思います。
「やるべきことはやった、後は天命を待つだけ」と言えるくらいであってほしいです。
やるべきことをやっていれば、どんな結果になっても納得はいくはずです。
今年のTKKアカデミーは
そして、入試が終われば、新しい年度が始まります。
みんな進級し、新しい学校、新しいクラスでまた勉強です。
気持ちを切り替え、この一年を無事に過ごされるように祈っています。
先ほど述べたように、葛西TKKアカデミーは10周年を迎えることになります。
今は多忙で身動きが取れないような状態ですが、受験が終わり落ち着いたらいろいろと体制を整えて、より充実した皆さまの力になれる塾に生まれ変わる予定です。
具体的には先生の数を増やし、もしこれまで以上に生徒が集まるようでしたら教室の拡大も視野に入れないといけないと考えています。
さらに進化した葛西TKKアカデミーにご期待ください。
そして、10周年を記念するイベントを実施したいと考えています。
まだ何をするか具体的に決めてはいませんが、教室内のイベントだけでなく外に出て何かできればいいなと思っています。
もし皆さまから、何かいいアイデアがありましたらお知らせください。
最後に午年ってどんな年?
最後に午年とはどのような年なのでしょうか。
一般的にエネルギー溢れ、活発で情熱的になれる年だそうです。
馬のように前進でき、行動的になることで様々なチャンスがつかめそうです。
そして、人とのつながりを広げるにもいい年のようです。
つまり、積極的に動き、大きく飛躍できる年ということでしょう。










2026年が始まりました。
この新しい年に期待と不安で心躍らせる人はたくさんいると思います。
葛西TKKアカデミーも新たな出会いにワクワクしております。
どのような縁でどのような人に巡り会うのでしょうか。
辛いことや苦しいこともありますが、少しでも前向きになって、未来ある子どもたちの光になれますように頑張ります。
特に今年は午年ということで、飛躍の年です。
偶然にもこのような年に10周年という節目を迎えられたことに、何か縁を感じずにはいられません。
何か記念となり、子どもたちの思い出に残る一年にできればと思います。
今年も葛西TKKアカデミーをよろしくお願いいたします。






























2025.12.31
一年間、多くの方々に支えられ誠にありがとうございました
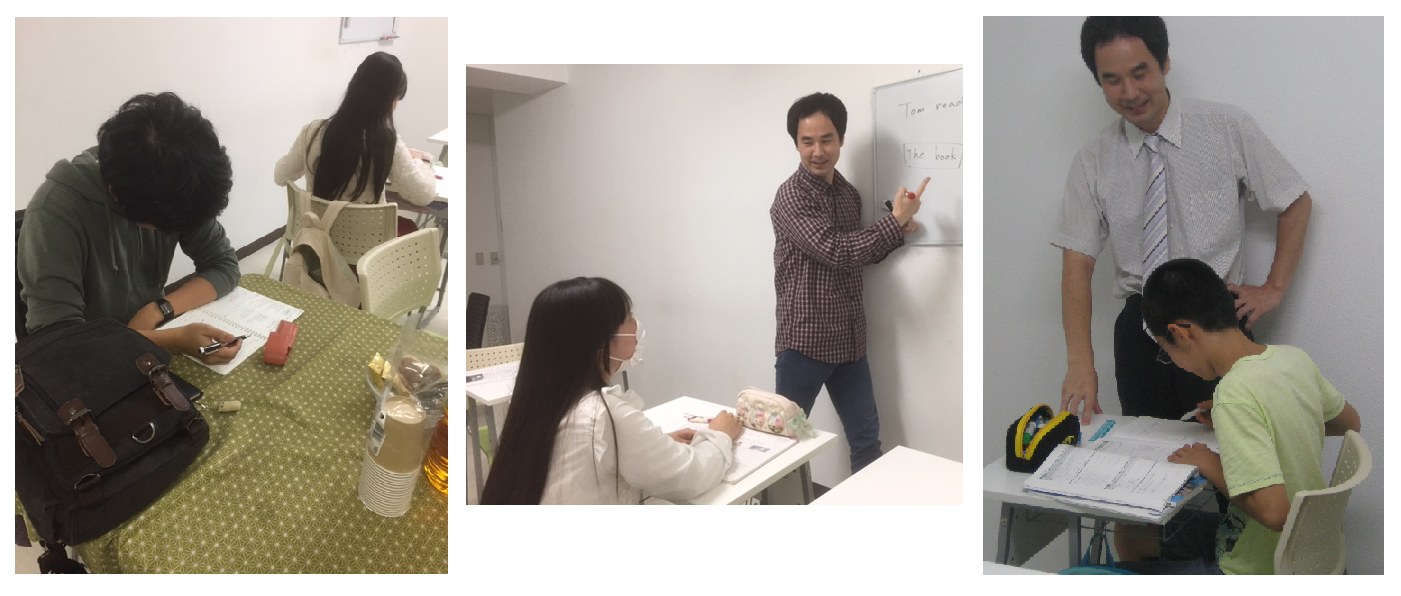
本年中は多くの方々に支えらえ、葛西TKKアカデミーも何とか無事に一年を終えることができそうです。
誠にありがとうございました。
まだまだ十分ではありませんが、多少なりとも生徒たちの力になれたことに感謝しております。
そして、新しい年もこれまで同様に、いや、それ以上に皆様のお役に立てるよう引き続き精進してまいりたいと思います。









今年一年を振り返ってみると
いつも大晦日になって感じるのですが、今年も一年が非常に早かったような気がします。
年が明けて受験勉強が追い込みになって、右往左往していたかと思ったら、あっという間に年末です。
高校受験では、推薦入試を希望していた生徒が二人とも合格し、本当によかったです。
推薦入試は倍率も高く、一般の学力試験と違い小論文と面接で決まるので、推薦入試専用の準備をしなくてはなりません。
しかも、一般入試の勉強もしつつです。
だから、推薦入試を受けるということは非常に困難な道に挑戦するということです。
しかし、生徒自身がやってみたいという意思を示しましたので、TKKアカデミーとしてもその対策の授業を設けました。
大変だったと思いますが、生徒たちの努力が報われて非常によかったと安堵しました。
その後は怒涛の一年でした。
とにかく生徒の増加が著しく、現在の一人体制ではきつくなってきました。
これまでは授業料をできるだけ低く抑えるために私一人でTKKを回してきました。
しかし、このように需要が高まっている現在、いよいよ来年は一緒にこの塾を盛り上げてくれる新しい先生を見つけなければ要望にお応えできなくなってきたと感じています。
ここまで多くの家庭が葛西TKKアカデミーに期待を寄せてくれるとは想定していませんでしたので、一度やり方を見直して、これまでの教育の質を落とさず規模を大きくする必要があるなと思います。
来年は10周年の年でもありますので、葛西TKKアカデミーが大きく生まれ変わるときなのかも知れません。
このように日常のオペレーションだけで多忙な一年でしたので、今年は通常の授業以外のことがあまりできなかったのが大きな反省点であります。
特に毎年行っていた夏休みの特別企画、葛西TKKアカデミー工作教室が実施できなかったことは非常に心残りでした。
本当はやりたかったのですが、あまりにも毎日が忙しくて工作を考え試作する時間もなく、最終的に断念という悲しい結果になってしまいました。
来年こそは事前準備を早めにやって、工作教室を開催できるようにしたいです。
そのためにもやはり、一緒に葛西TKKアカデミーを盛り上げてくれるパートナーはほしいものです。
遅くとも受験勉強が落ち着いた2月には、募集を始めないといけないと考えています。
また、今年はインフルエンザの猛威で多くの生徒がお休みになったことも印象的でした。
平年よりも暑さが続き、結果としてインフルエンザの流行が早まり、しかも、学校を中心に感染が広がりました。
TKKアカデミーの生徒も次々とインフルエンザにかかり、お休みになりました。
葛西TKKアカデミーは欠席をすると必ず振替授業をすることになっています。
今回は欠席があまりにも多く、生徒も増えたせいで、振替授業の時間確保が困難ですが、必ず全員の振替授業を実施しますのでご心配なく。
TKKの年末年始
実は本日大晦日も葛西TKKアカデミーは授業を行っています。
特に今年の受験生は受験勉強のスタートが遅かったため、通常葛西TKKアカデミーが提供している受験対策に比べ日程が大幅に遅れています。
そのため、年末年始も休むことなく授業を行っています。
つまり、明日、正月も授業です。
大変ですが、生徒も理解しついて来てくれているので、私も頑張るしかありません。
受験合格に向けて熱心に勉強に取り組む生徒たちの夢がかなうように、葛西TKKアカデミーも休むことなく彼らを支えていきます。
特に一月は推薦入試の本番があります。
今年もチャレンジする生徒がいますので、小論文と面接の練習の真っ最中です。
みんなの努力が実るように応援していきたいと思います。








年が明ければ早々に推薦入試、そして高校の一般入試と続きます。
個別指導塾葛西TKKアカデミーの受験生たちも最後の追い込みに入っております。
何とか全員の夢がかなうように、私も全力を尽くす所存です。
そして、ありがたいことに葛西TKKアカデミーを期待して入塾する生徒が増えた件に対して、これまで通り生徒一人ひとりに向き合い、各々に合った学習ができるように、葛西TKKアカデミー自身の充実と拡大が新年の課題と考えています。
おかげさまで迎えらえることができる10周年。
何か記念になるようなこともしたいと、来年に向けてあれやこれや考えつつ、今年も締めくくろうと思います。
皆さま、本当にいつもありがとうございます。
来年も葛西TKKアカデミーをよろしくお願いいたします。
























2025.12.03
TKKの先輩が受験生のために高校の実態を話してくれました!

受験勉強のいよいよ佳境に入り、多くの生徒は目指す高校合格に向けて必死に頑張っていることでしょう。
葛西TKKアカデミーでも、例年と同じく何名かの高校受験生がいます。
多くの受験生がいろいろと不安や疑問を抱えていることと思います。
そんなとき、身近に経験者がいて質問に答えてくれると不安も解消され、さらに新しい情報が与えられるとそれが勉強の励みになることもあります。
そのようなこともあり、葛西TKKアカデミーでは毎年受験生のために受験経験者である先輩方をゲストに迎え、質疑応答する機会を設けるようにしています。
今年も去年の卒業生が来て、現受験生のために協力してくれました。









卒業生とのつながりに感謝
葛西TKKアカデミーでは受験生の疑問や不安に答えたり、合格への体験談を聞いたりするために、卒業生にゲストスピーカーとして来てもらうことがあります。
今年も去年の卒業生が、現在TKKアカデミーで頑張っている受験生のために協力してくれました。
こうやって卒業後でも声を掛けて、都合がつけば喜んで足を運んでくれることに本当に感謝しています。
受験生と年齢が近く、つい最近まで同じ試練を経験し乗り越えてきた先輩の声というのは、我々大人が話す言葉とは違う意味で受験生に影響力を持っていると思います。
実際の経験者だからこそ言え、実感を伴うその言葉は具体的かつ力強く、しかも同世代だからこそ共感しやすい。
これは私たち大人には出来ないことでしょう。
だから、時にはこのような機会を設けることが重要で、毎年可能であれば先輩方に来ていただき、後輩のために一肌脱いでもらうように声掛けをしています。
同じ目的に向かって協力してくれるとしても、様々な人が関われば考え方や見方も多様になり、より広い見識から受験生も受験や自身の人生に向き合えると思います。
何でも大人が一方的に力を加えるのではなく、時には自分以外の人間に立場を譲ることも大事です。
言葉というのは、「何を言うか」よりも「誰が言うか」が重要なときもあります。
その言葉を言うにふさわしい人に言ってもらうことが必要なとき、今回のように快く引き受けてくれる葛西TKKアカデミーの先輩方の存在に本当に感謝しております。
葛西TKKアカデミーの貴重な財産です。
この場で「ありがとうございました」と申し上げます。
偶然にもピッタリの先輩
今回来てくれた先輩は偶然にも、現受験生といろいろな点で関係の深い先輩だったようです。
私も後から知ってびっくりしたのですが、両者は同じ中学校で部活も同じ本当の先輩後輩でした。
受験生のお姉さんとも知り合いで、より親近感がわくものでした。
さらに目指す受験校も同じで、同じように二学期に入ってから当塾で受験勉強をスタートし、同じように一般受験のみならず推薦入試も受ける予定です。
まさにピッタリの先輩だったわけです。
遅れて始めた受験勉強だからこそ、人一倍勉強も大変です。
そんな厳しい状況の中で、さらに推薦入試も目指すということ。
個人的には一般受験に集中してほしいのが本音ですが、本人がその大変さを理解し受け入れ、それでもなおチャレンジしたいというのでしたので、私も同意しサポートすることにしました。
ちょうど一年前のこの先輩も同じ状況で、しかし、彼女は本当に頑張って両方の準備を怠らず、最終的には推薦入試を見事合格しました。
この経験が今年の受験生にいろいろ役立つ情報を提供してくれると考えました。
また、志望校が同じなので、この受験生が目指す学校の最新の様子を知ることができるとも考えました。
いろいろな意味でこの受験生にふさわしい先輩だった偶然に感謝です。
実際に話したこと
このように思いもがけず縁の深い先輩に来ていただくことになりました。
そして、葛西TKKアカデミーで実際に会って本人同士自由に質疑応答の時間を設けました。
ここは完全に生徒に任せて話をしてもらいましたが、同じ中学に通い同じ高校を目指す者ということで共通の分かり合えす話題も多く、楽しく盛り上がっていました。
私としては先輩の体験談として、どのように勉強してきたかとか、受験のコツなど質問してくれればと期待していたのですが、実際は違っていました。
高校がどのようなものか、校舎の汚さや高校生がどのようにおしゃれをしているか、厳しい先生はいるのか、カッコいい先輩はいるかなど、受験とは直接関係のない質問もして、少しこけてしまいそうになりました。
もちろん、面接でどのようなことが聞かれたかとか、TKKアカデミーでの対策がいかに役立ったかという話もあったのですが、このような今どきの中学生が気になることを生々しく包み隠さず話せる機会があるのも悪くはないかと感じました。
このような話は私には到底できないものですから、そういう意味では貴重な情報を得られたと言えるでしょう。
受験生のやる気がアップ!言葉は誰が言うかが肝心
受験生の帰宅後、お母様からLINEをいただきました。
先輩と話をして「頑張る」と本人が言ったそうです。
LINEから、自分の子どもがやる気になって本気で受験勉強に取り組もうとしていることが分かって、お母様も本当に嬉しかったのでしょう、その喜びが文面からも読み取れました。
本人のモチベーションが上がり、「絶対に合格したい」という気持ちが強くなったのが今回の最大の収穫ではないかと思います。
周りがいくら言っても、本人が勉強しなければ当然結果は出ないわけですから。
今回の場合、私や保護者がいくら口を酸っぱくして言っても、ここまでのやる気を引き出せたかというと、それはかなり怪しいです。
でも、実際に高校に通っている先輩の正直な生の声だったから、本人の心を動かせたのだと思います。
言葉というのは、時には「何を言った」かではなく「誰が言ったか」が肝心なときがあります。
同じ言葉でもふさわしい人が言わないと心に伝わらないことが多いです。
そういう点で、今回の企画は受験生にとって非常にプラスだったと考えます。
今後もこのような機会を設け、いろいろな角度から受験生を支えていきたいと改めて感じました。









このように受験生が世代の近い経験者から話を聞き、直接学校の様子をうかがい知る機会というのはなかなかないのではないでしょうか。
葛西TKKアカデミーだからこそ、そのつてを使って出会う機会が作れたと自負しております。
ここが葛西TKKアカデミーの特徴であり強みとも言えるでしょう。
そして、それを可能にしてくれる生徒とのつながりをこれからも大切にしていきたいと思います。
このような卒業生だけでなく、保護者を始め地元の人々など多くの人たちに支えられて葛西TKKアカデミーは存続できております。
このようなつながりを持てたことに心から感謝いたします。



























2025.11.12
インフルエンザの流行で学級閉鎖も!今一度予防と対策を

最近、目に見えてインフルエンザの流行が分かるようになってきました。
インフルエンザにかかって休んでいる生徒が増え、いくつかの学校では学級閉鎖が行われているようです。
かく言う葛西TKKアカデミーの生徒も何人かインフルエンザで休んでいます。
ということで、再度、インフルエンザの予防と対策についてお話したいと思います。








今、中学校では期末テストの時期です。
この時期にインフルエンザにかかってしまうと、当然テストは受けられません。
もちろん追試はありますが、点数はいくらか減点されて出されると思います。
これはもったいないです。
また、受験生も追い込みの大事な時期です。
ここで寝込んで何日か受験勉強ができなくなると、やはり大きな痛手となります。
そうでなくてもインフルエンザはかかっていいことはありません。
だからこそ、しっかりと予防しリスク回避をしなくてはいけません。
万が一かかったとしても、適切に対処することでダメージを軽減できます。
繰り返しになる部分が多いとは思いますが、もう一度確認していきましょう。
今年のインフルエンザ
今年のインフルエンザは例年より一ヶ月以上早く流行しているそうです。
11月11日は全国の患者数も6万人に迫る勢いです。
今年は「香港A型」が流行っているらしく、これは感染すると重症化しやすくワクチンも効きにくいという特徴があるそうです。
例年よりこんなに早く流行している原因として考えられるのが、今年の猛暑で体力が落ちているところに、急に秋の寒暖差の激しい日が続いたことです。
これで自律神経やホルモンのバランスが崩れ、免疫が弱まったのではないかと考えられます。
インフルエンザ予防の基本
インフルエンザ予防の基本はやはり次の通りです。
1.うがい手洗い(アルコール殺菌)
2.マスク
3.十分な睡眠休息と栄養補給
4.予防接種
5.適度な湿度
6.早目の対応(医師による診察)
7.日に当たり適度な運動
インフルエンザの予防接種を受けたり、マスクをしたり、外出から帰ったら必ず手洗いうがいをしたりしましょう。
そして、不必要に外出せず、できるだけ人ごみを避けてウィルスをもらわないようにしてください。
まだ体が慣れていない季節の変わり目は特に、外に出る時は暖かい服装で風邪を引かないように気をつけましょう。
ただし、室内にいる時は上着を脱いで汗をかかないようにしてください。
汗が冷えると体温が奪われ風邪の原因になります。
家族や友人など身近な人で風邪の人がいる場合は、マスクなどをしてもらいうつされないようにしてください。
遠慮して言わないで、こちらが風邪になっては大変です。
特に受験生は一生に関わる失敗の許されないテストですから、遠慮して風邪をうつされ勉強ができなかったり試験場受けられなかったりしては取り返しがつきません。
ここは自分を守ることを最優先してください。
また、受験勉強で忙しいとは言え、十分な睡眠は必要です。
体を休めないと病気に対する抵抗力が弱まります。
できれば6時間は睡眠時間を確保してほしいです。
十分な睡眠は記憶の定着にも大きく関わり、勉強ができるようになるためにも必要不可欠です。
さらに、十分に栄養を取りバランスのとれた食事をすることも体を強くしてくれます。
特に風邪にはビタミン類が有効と言われています。
したがって、野菜や果物を摂取することはインフルエンザ予防にも重要です。
そして、朝食を抜くということは絶対にやめてください。
忙しいからと言って朝食事を取らないと、いつまで経っても体が目覚めず、脳もエネルギー不足で十分はたらかなくなります。
これではインフルエンザと戦えないばかりか、勉強もできません。
朝食は余裕を持ってよく噛んで、しっかり食べて学校に行きましょう。
このように病気の予防と勉強の効率の両面から、食事と睡眠は気を付けなければなりません。
もしうまくできていないようでしたら、今の状況を記録し目に見える形にしましょう。
そうすれば自分がいかに悪い状況にあるのかが分かります。
こうして自覚すれば対策を講じることは容易です。
最後に、勉強ばかりで家に閉じこもりっきりもよくありません。
適度に休憩時間を作り、軽い運動をすることは血行をよくし頭をすっきりさせましょう。
目が覚めて勉強に再び集中できると同時に、体内の免疫力も上がります。
また、精神的な健康も大事です。
不安とストレスの多い時期、散歩などの気分転換などでうまく発散し、安定した精神状態でいることも大事です。
要は、勉強と息抜きのメリハリをつけるということです。
長い受験勉強をやり切るにはこの両方が必要です。
インフルエンザにかかってしまったら
もし少しでも体調がおかしいと感じたら無理はせず、すぐに医師に診てもらってください。
病気を甘く見ないで迅速に行動し、適切に対処することで生活への悪影響を最小限にできます。
早い対処が肝心です。
無理して何もしないまま生活をしていると、自身は元より周囲の人間まで病気に巻き込んでしまうので、周りに大きな迷惑を掛けてしまいます。
医師のところへ行って適切に対処して早く治し、一刻も早く勉強に再び取り組めるようにしましょう。
風邪の引き始めは特に、水分補給とビタミンなどの栄養補給をしっかりしてください。
ワクチン注射をまだしていない人も、しないよりはましなので、今からでも受けに行ってください。
予防は最大の対策ではありますが、そうは言っても万全ではないので、運悪くインフルエンザにかかったときはひどくなる前、病状が軽いうちに速やかに治しましょう。








病気にかかって何もいいことはありません。
特に人生の大事な時期を迎える受験生は、この大切なときの病気になって貴重な時間を不意にすることだけは避けたいものです。
そのためには予防が一番です。
しかも、本人が気をつけるだけでなく、周囲の人間も受験生のために協力して、インフルエンザを回避してください。
これが最善策です。
それでもかかってしまったら速やかに病院に行ってください。
受験生は悔いを残さないよう体調管理にに気をつけましょう。
また、受験生でなくても病気で通常の生活ができなくなることは大きな損失です。
どうか体に留意して、皆さん勉強に励んでください。






























2025.11.08
11月24日は都立高校入試のスピーキングテストがあります

二学期もかなり進み、そろそろ期末テストの時期です。
高校受験をする生徒にとって非常に重要な定期テストです。
なぜなら、このテスト結果が三年二学期の成績に大きく影響し、この成績が受験に必要な内申点になるからです。
しっかり準備して内申点が一つでも上がるように頑張りましょう。
ところで、今回の話題はその後に実施される英語のスピーキングテストです。
現在、都立高校入試では2月下旬に学力テストが行われますが、それに先駆け今年は11月24日に英語のスピーキングテストが行われます。
教育委員会の方針で、英語の「話す」力も受験の評価に加えるべく2023年から行われています。
本日はこのスピーキングテストについて議論したいと思います。








現在、都立高校入試で英語のスピーキングテストが行われていることをご存知でしたでしょうか。
大学の共通テストが始まったときに、英語のスピーキングテストが導入されるのではないかと話題になりましたが、こちらは批判と反対の声が多く、実施延期という形で今も行われていません。
一方、都立高校入試では導入され数年になります。
結果として、中学生の英語ではこれまで疎かになりがちであった発音やコミュニケーション能力もしっかり勉強しなくてはいけなくなってきました。
英語の「話す」能力の指導や生徒の学習方法の問題もありますが、やはり高い公平性が求められる受験においてスピーキングテストの評価をどのように行えばいいかで疑問や反対がありました。
しかし、これらの批判にこたえることなく、都立高校入試ではスピーキングテストが始まり、現在に至っております。
スピーキングテストはどんなテスト?
都立高校入試で扱われるスピーキングテストは「ESAT-J」と呼ばれています。
タブレット端末を使い、受験生はヘッドフォンをマイクを付けて、音声の指示に従って試験を進めていきます。
試験は大きく四つのパートに分かれ、それぞれ与えられた課題に発生をしながら答え、マイクを通してその音声が録音される仕組みです。
録音された音声はとある場所に集められ、訓練を受けたネイティブスピーカーにより、定められて手順に従い評価されるみたいです。
フィリピンに送られるという話も聞きますが定かではありません。
そして、採点結果によってA~Fまでの6段階にランク付けされ、Aが20点、Bが16点と4点刻みで点数が付けられ、Fは0点となります。
これが一般入試の点数1000点満点に付与され、その結果1020点満点で合否の判定がなされます。
受験を受けた生徒の話では
これまでESAT-Jを受けた生徒の話は次のように話していました。
会場に受験生は集められ何十人かが同じ教室で一斉に受験するそうです。
試験は配布されているタブレット端末を使い、ヘッドフォンとマイクが接続されて、個々にタブレット端末を操作しながら進めていきます。
一応ヘッドフォンはしているものの、他の受験生の声は聞こえるらしく、それを聞きながら答えることもできるそうです。
受験生は前半後半に分かれて、前半のグループが終わると入れ替わって後半のグループが試験を始めるみたいです。
また、ニュースによると音声の不具合などが発生し、一律追加点になったという話も聞きます。
結構トラブルは発生しているらしく、高校受験の一端を担うにはまだテストが稚拙なように思われます。
テスト内容は?
先ほども申したように、ESAT-Jは大きく四つのパートで構成されています。
まず、パートAはそれほど長くない英語の文章を音読する問題です。
実際に発話する前に30秒の準備時間があり、そこで文章を黙読して内容を確認します。
平均的な中学3年生ならそれほど苦労しないで読めるくらいの文章で、2問出されます。
パートBは英語で質問されたことに対して与えられたイラストを見ながら答える問題です。
ここでの準備時間は10秒です。
全部で5問出されます。
店員と客、友達同士などよくあるシチュエーションが設定され、そのような状況でうまく自分の考えを伝えられるかコミュニケーション能力が試されます。
パートCは与えられたイラストを見て、そこからどのような物語なのかを理解し、それを英語で説明する問題です。
30秒の準備時間があります。
1問出されます。
イラストしか与えられていないので、イラストから情報を読み取り、これを自分で英語として組み立てて説明しないといけません。
とっさの表現力が重要です。
最後のパートDは英語の質問を聞きながら、自分なりに応える問題です。
質問は「夏休みに何をしたいか」とか「どこの国に行きたいか」などのオープンクエスチョンです。
60秒の準備時間があります。
こちらも1問です。
自分の意見や考えを言うだけでなく、その理由や説明も必要です。
短いスピーチの形を取る場合もあるので、論理的な思考を表現力が必要になります。
対策は?
全体として必要とされる英語は特別なものなく、日頃から普通に学校で英語の授業を受けていればある程度の得点は可能と思われます。
しかし、これは「普段から」きちんと発音やアクセント、文の抑揚やポーズまで意識してまじめに身に着けていないといけません。
日頃いい加減な発音で英語を勉強していて、試験直前になって正しい発音に直そうとしても一朝一夕には直りません。
つまり、1年生のときからコツコツと手を抜かず発音の習得を積み重ねることが大事です。
とは言え、受験直前になってしまった受験生にはどのような対策ができるでしょうか。
学校でも何度かシミュレーションがあったと思います。
そのときのことを思い出し、まずは機器の操作の仕方を確認してください。
頭の中で何度も繰り返し、本番のとき、機械の操作でつまずいてパニックにならないようにしましょう。
市販の問題集や教本を使って、同じ問題で構いませんので何度も解いてみてください。
問題を解くというより、もう答えを聞いて何度も発話する。
とにかく声を出すのが大事です。
大抵音声がついていると思いますので、それを聞きながら自分の発音やアクセント、イントネーションやポーズを確認しましょう。
英語独特のリズムに慣れましょう。
音声を聞きながら真似するシャドーイングが効果的です。
もし英語が堪能な人が周りにいれば、その人に協力してもらって自分の英語を聞いてもらいアドバイスを受けましょう。
答え方のコツ
それでは実際にテストで答えるとき、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
各パートごとに考えてみます。
パートA
文章を読むだけの問題ですが、発音や話し方に関してそれほど厳格でも内容です。
多少の引っかかりや間が空いてしまったり、リズムやイントネーションが多少間違えていたとしても、おおむね時間内に読み終えることができれば、それほどの減点にはなりません。
言い直しがあっても相手の理解の妨げにならない程度であれば大丈夫です。
よって、自信を持って大きな声ではきはきと読み上げることが大事です。
知らない単語が出てきても、最悪ローマ字読みなどでそれっぽく発音すればいいと思います。
一番良くないのは、分からないから、間違えたからと引きずって沈黙になってしまうことです。
パートB
相手の質問に答える問題なので、前提として正確に質問を聴き取る必要があります。
特に英語は、最初に「when」「who」「where」「what」「how」などの質問の言葉がきますから、質問の始めは特に集中して聞いてください。
聴き取れたとしても、「何を答えていいか分からない」、「どう答えたらいいのか分からない」という人がいます。
ここでも一番良くないことは何も言葉を発しないことです。
あまり深く考えず、自分が本当にそうは思っていなくても、とりあえず何か答えましょう。
その答えに対してさらに質問がある訳ではないので、その場しのぎの回答で結構です。
文で答えるのが難しかったら、単語だけでも構いません。
黙っているよりはずっとましです。
パートC
個人的には受験生にとってこのパートが一番難しいような気がします。
まず、イラストを見てその内容を把握しなくてはなりません。
そして、仮に把握できたとしても、そのストーリーを英語で表現できなくてはいけません。
単に読むだけ、一文を答えるだけとは違い、文脈のある文章なので、いくつかの文を有機的につなぎ、筋の通った話を作る必要があります。
だから、つなぐ言葉を多く知っていると有利です。
それぞれのイラストに2~3文言うように心がけるとといいです。
大雑把な名無しの流れを考えたら、それに一つ二つ情報を加えるような気持ちで答えるといいでしょう。
発話するだけ、一文作るだけで精一杯の生徒には非常にハードルの高い問題かも知れません。
でも、単文を並べるだけでも沈黙よりはましで、部分点はあると思います。
また、イラストの解釈は個人の裁量の余地がありますので、自分の表現できる範囲の内容に解釈し、なるべく簡単な英文で答えるのも一つの方法です。
あまり難しく考えず、機転を利かせると案外中学で習った英語でいろいろな表現ができることに気づくはずですが、そうなるまでには訓練と経験が必要です。
普段から積極的に英語のコミュニケーションをとる機会の少ない生徒には厳しいかも知れません。
パートD
ここでは質問に対して自分の考えと理由を答える問題です。
答え方のパターンとしては、自分の考えを述べ、その後「because」などを使って理由を述べます。
理由が言えなくても、最低自分の意見は答えましょう。
また、意見や理由の内容そのもので減点されることはないので、正直に答えなくても自分が回答しやすい意見を言えばいいと思います。
いい理由が見つからなければ、うまく意見を裏付けるような理由をでっちあげるのも一つの方法です。
独りよがりの意見でいいです。
この回答に対して反論されることはないので、事実と違えたとしても大きな問題ではありません。
「こんなことを言ったらダメかな」なんて考えないで、自信を持って大きな声で答えてください。
また、非常によく使える便利なフレーズを事前に多く覚えておくことも、表現力を広げ回答をしやすくしてくれます。
今からでも、これまで習った役立つ表現を確認し、覚え、そして使えるようにしておきましょう。








いよいよ都立入試が始まるという感じです。
その口火を切るのが英語のスピーキングテストであるESAT-Jです。
入試は来年二月だと思って準備していない受験生はいないとは思いますが、試験である以上全力で臨んでください。
1020点中の20点とバカにしてはいけません。
1点違えば順位は変わります。
下手をすれば何十人も入れ替わってしまいます。
今は期末テストの勉強で忙しいかもそれませんが、それが終わったら直前のESAT-Jに向かって集中して勉強してください。
1点でも疎かにすることなく、「しまった」と後悔することもないように、まずは入試の第一回戦頑張ってください。
























2025.10.05
明日は十五夜、お月見!日本の伝統行事は受験でもよく出ます

今年の十五夜は明日10月6日!
中秋の名月とも呼ばれていますよね。
天気予報によると東京は雲が広がりやすいものの、雲の切れ間から満月を見ることができそうです。
突然の雷雨の可能性もあるようなので、お月見には傘の用意があるといいかも知れません。
雲のすきまから真ん丸な美しい月が現れるのを待ちながら、夜空を眺めるのもいいかもしれませんね。
美しい丸い月が見れますようにお祈りいたしております。









そもそもお月見とは何なのでしょうか。
十五夜とも呼ばれ、旧暦の8月15日辺りに出るの夜に満月を味わうことです。
中秋の名月と言い、日本人はその見事な月を眺めながら歌を詠んだりしました。
因みに、日本人は月の黒っぽいところ(海と呼ばれていますが、実際に水はありません。)を見て、ウサギが餅つきをしている姿を想像しました。
南アフリカではロバやワニに見えるそうです。
アラビアでは吠えるライオン、ヨーロッパでは紙の長い女の人やカニなど国や地域によって、その見え方が変わっていきます。
これは違うものを見ているというより、見えているものを何と結びつけているかという文化的な違いによるものです。
(例えば虹の色は日本では7色と言いますが、他の国では違う数になっています。)
月を見ながらこんな話をしてみるのも楽しいと思います。
ウサギが当たり前と思っていたら、それは日本だけで他にもいろいろな考え方があるんだなんて気づくときっと面白いでしょう。










ところで、お月見を始めとする年中行事は、実は受験でよく出る話題です。
特に中学受験では、社会や国語などで出てきます。
各行事の日にちや由来、何をするのかなど問われますが、学校などであえて授業中に学ぶことはないと思います。
つまり、勉強というより、一般常識として聞かれるのです。
しかも、意外と年中行事に関する問題は多いです。
だから、知ることは必要です。
あえて勉強として学ぶよりは、実際に年中行事として家庭で実践された方が、子供も実体験として理解し、いい思い出にもなるので、家族みんなで楽しみながら、由来などを話し合うといいでしょう。
日本の伝統文化を学ぶことにもなり、日本的な考え方が分かってくると思います。
最近はクリスマスやバレンタインデー、それからハロウィーンなど西洋の年中行事も浸透してきているようで、こちらも子供たちに体験されるのがいいと思います。









現在行われている教育改革では、「考える力」を重視します。
年中行事を通して日本人の心を考える問題も当然想定されます。
年中行事に限らず、経験を通した学びは知識ではなく知恵として蓄積されるので、「考える力」を育てるには非常に大事になります。
皆さんも家族で年中行事を楽しみながら、子供の「考える力」を養いましょう。





















2025.10.03
意外と知らない都立高校入試の合否判定方法

夏休みが終わり二学期が始まりました。
受験生にとっては本格的に受験勉強に取り組む時期です。
大変ですが競争である以上、少しでもライバルに差を付けなくてはなりません。
そのためには毎日の勉強が重要になってきます。
苦しいでしょうけど、後5か月ほどの辛抱です。
本気で努力すればきっと報われますから、自分を信じて頑張ってください。
ところで今回は都立高校の入試に関して、その合否はどのようにして決まるのかご紹介いたします。









受験生を始め保護者の方々もよく知らないという人が多いようなので、ここで一度ご説明したいと思います。
意外と複雑なのできちんと理解していただきたいです。
都立高校の入試の得点の出し方
都立高校の入試得点の出し方は少し複雑です。
合否判定は受験生が課せられた点数をいかに多く取るかで決まります。
そして、その得点の基本的な大きな部分に当たる要素が二つあります。
調査書点(内申点)と学力検査点です。
さらに、現在では学力試験に先駆けて英語のスーキングテストが11月に行われ、こちらもマイナーな部分にはなりますが、評価に含まれるようになりました。
結果、都立高校の入試は合計1020点満点で評価され、そのうちの300点が調査書点、700点が入学試験の点数である学力検査点になり、スピーキングテストが残りの20点を占めます。
これら全てのパートで獲得した点の合計点で合否が判断されます。
つまり、調査書点が高いと当日の学力試験の点数が多少悪くても合格できますし、調査書点が低いと試験当日にかなり頑張らなくてはいけないということになります。
また、これは同時に調査書点だけ、学力検査点だけでも合格は難しいことを意味しています。
したがって、普段の学校の勉強をしっかりやって内申点を上げつつ、入試本番のテストに向けた勉強もしないといけないという二方面作戦に受験勉強はなるというわけです。
まとめると、一般的には次のような計算式によって受験生の得点が算出されます。
そして、この総合点の高い受験生から順番に合格が決まります。
入試の総合点={300×(主要5教科の調査書点合計×1+実技4教科の調査書点合計×2)÷65}+{700×5教科の学力検査点合計÷500}+スピーキングテストの点数(20点満点)
このように式だけ見てもよく分からないかもしれませんので、もう少しそれぞれ詳しく解説していきます。
調査書点とは
調査書点とは何かご説明します。
調査書点とは調査書の内申点から算出されます。
通知表にある5段階評価の数字をそのまま点数にします。
これを主要5教科は合計点を1倍、実技4教科は合計点を2倍して合計が調査書点になります。
つまり、9教科オール5であれば65点になります。
オール4であれば52、オール3であれば39、オール2であれば26、オール1であれば13です。
この65点満点のうち何点取ったかを割合で出し、それに300をかけたものが調査書点に基づく部分の得点になります。
実技4教科は調査書点が2倍にされるので、この部分の得点を上げるには、主要5教科より実技4教科を上げたほうが効率が良いということになります。
ちなみに、調査書点が1上がれば1000点の入試総得点のうち約4.6点上がるということになります。
(ちなみに、学力検査点では1上がると1000点満点では1.4点しか上がりません。)
1点で合否が分かれる入試では、この得点は非常に大きいのです。
調査書点がいかに重要かお分かりいただけたと思います。
私立高校受験でも調査書点は重要
また、私立高校の入試でも調査書点が大きな意味を持ちます。
基本的に各私立高校は受験するために必要な調査書点を提示しています。
すなわち、その基準となる調査書点に達していない生徒は、その高校の受験ができないということになります。
調査書点が高ければそれだけ多くの私立高校が選択でき、低ければ嫌でも選択の幅は狭まります。
ましてや9教科の成績の中で一つでも「1」がついていると受験資格がなくなるという私立高校は非常に多いので、「1」を取ることだけは絶対に回避しないといけません。
このように私立高校でも志望校選びに調査書点が大きく影響します。
間違えても「私立高校の受験だから調査書点は関係ない」とは考えないでください。
入試当日の学力試験
二月に行われる入試当日の学力テストに基づく部分は次のようになっています。
国語、数学、英語、社会、理科の5教科各100点満点で合計500点のうち何点取れたか、その割合を考えます。
これに700をかけて算出された得点が、入試当日の学力テストの部分の得点、学力検査点となります。
全体の7割を占める学力テストは、やはり高得点を取りたい部分です。
他の部分と違って、ここは試験を受けるまで確定しない部分です。
つまり、ギリギリまで伸ばせる可能性のある部分を考えることができます。
内申点が悪くても、ここで挽回できれば逆転も夢ではありません。
本当に自分の目指す学校に合格したいのであれば、多少内申点が悪くても最後まであきらめずに受験勉強を頑張るのも一つの作戦ではあります。
ESAT-J:英語のスピーキングテスト
最後に、ESAT-Jと呼ばれる英語のスピーキングテストについてお話します。
これは令和4年度の都立入試から導入されました。
パソコンやタブレット端末などを使って、生徒が英語の問題を口頭で答え、その録音した解答に基づいて評価がなされるものです。
今年度は11月23日に実施されます。
ESAT-Jの結果は最高評価のAから最低評価のFまでの6段階で評価されます。
そして、それぞれのランクごとに点数が配分され、最高点は20点、最低点は0点となっています。
20点とマイナーな部分ではありますが、合格をより確実にするためには1点でも多く点数を取る必要があります。
だから、スピーキングテストを大した点数ではないからと見くびってはいけません。
不合格になったとき、泣くに泣けなくなります。
何事にも全力で挑戦し、受験という難関を突破しなくてはいけません。
日本では英語を話す環境があまり整っておらず、学校でもあまりうるさく指導されることもありません。
でも、発音や受け答え、発信などは机上の勉強とは違いすぐにできるようになるものではありません。
習得までには練習と時間を要します。
だから、日頃から英語のスピーキングもいい加減にしないで、常に発音や抑揚、表現などを気にかけながら英語を話すように心がけましょう。
繰り返しますが、小さな部分だからと軽く見ないで、合否判定に関わる以上は手を抜かずに準備してください。










以上、都立高校の合否判定に関わる説明をしました。
お分かりになりましたでしょうか。
結構複雑なので分かりにくいかも知れませんが、そのときはいつでも葛西TKKアカデミーにお問合せください。
入試についてよくわからない、志望校決定に悩んでいる、その他質問がある方も遠慮なく葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。
自分の現在の状況と目指す高校の状況をよく分析し、何をどのようにしなければならないかしっかり考えてください。
願書提出の締め切りまでは、まだ時間があります。
人生に大きく影響する大事な試験ですから、後悔することのないように頑張ってください。






























2025.09.07
今日の深夜は三年ぶりの皆既月食!せっかくなので実際に見て感動を!

明日9月8日、深夜午前1時30分頃から午前5時頃にかけて、日本で3年ぶりの月食が見られます。
部分月食から始まり、全体が地球の影に覆われる皆既月食のピークは午前3時ごろです。
全国的に見られるようなので、時間になったら南西から西の空を眺めてみてください。
周りに建物がない見晴らしの良いところに出れば、観測は容易だと思います。
後はお天気次第です。
一応、天気予報によると雨はないようなので、月食が見れると思います。
曇っていても、運よく晴れて雲の切れ目から月が見えるといいですね。










ぜひ実際の月食を自身の目で
夜の遅い時間帯ではありますが、それほど頻繁に見られる現象でもないので、できれば自身の目でこの天体ショーを堪能していただきたいと思います。
幸いにして、日曜日なので夜に備えて夕方辺りから寝て、深夜から朝にかけて起きているということもできると思います。
少なくとも、目覚ましをかけて皆既月食の前後30分から1時間くらい起きて、観測してもいいのではないでしょうか。
眠いかも知れませんが、せっかくの機会なので直接見てほしいです。
後でテレビなどを通してみるのと生で見るのでは、印象も大きく違います。
この経験が子どもたちに感動を与え、自然に対する興味がわき、知的好奇心が刺激されれば、学校の勉強に対する姿勢も変わってくることが期待できます。
今回の月食は地球の本影に完全に月が入ってしまいますので、赤銅色の月に見えるはずです。
このような色の月を「ブラッディームーン」と呼ぶそうで、普段の白い月とは違う赤い月をお楽しみください。
月食とは
月食とは地球の影に月が入って、月の表面上に地球の影が落ちてできる現象です。
日食が物理的に見た目上太陽を覆いかぶさるのと違って、月食は地球の影が月にかかっているだけなので、完全に暗くなることはありません。
暗いところとの境界線ははっきりとはしておらず、月全体が地球の影に完全に隠れても、ぼんやりと月自体はが見えます。
今回は地球の影が完全に月全体にかかるので皆既月食となります。
地球と月との位置関係によっては、月の一部しか地球の影がかからないときがあります。
そのようなときは部分月食と呼ばれます。
また、皆既月食のときに月が赤暗く見えるのは、波長の長い赤い光が地球の大気に散乱されずに通過し、屈折してそのまま月を照らすからです。
ちょうど夕焼けが赤くなるのと同じです。
身近な自然に触れる機会を
日食と月食は中学校の理科の時間に扱われる項目で、当塾でもよく解説します。
しかし、机上の勉強では実感もなく、興味もわかないかもしれません。
このような天体ショーを自分で目撃すれば、きっと何か感動でき心に残るものがあるはずです。
このような特別なイベントに限らず、日常においても身の回りのちょっとした自然に目を向けてください。
少し気をつければ、知の感動は日常にあふれています。
何気ない見過ごしていたものに、何か新発見があるかもしれません。
そうでなくても、純粋に花をめでたり、昆虫や動物の不思議さに触れることができれば、もっと知りたいという意欲がわきます。
このように自身の経験が学校の授業と結びつくと、勉強はもっと楽しくなります。
これは理科に限ったことではありません。
どの教科も自身の経験とつながったとき、それは生徒にとって現実のものとなり、より強く心に刻まれ理解も実感を伴って深まります。
大事なのは発見し、実感し、想像することです。
そうして思いを巡らせ、自分なりの解にたどり着いたとき、人間の知的喜びは最高潮となります。
そして、このような経験が沢山積み重なれば、知的好奇心も高まり、勉強がますます楽しくなるはずです。









勉強が嫌いな生徒たちは、勉強が苦痛に感じるようです。
しかし、勉強を苦痛に感じる必然はありません。
それは生徒の個人的な感じ方であるのは、苦痛に感じない生徒もいることから明らかです。
では、問題はどうして苦痛に感じるのかということ。
勉強には創意工夫が必要です。
生徒に勉強を苦しめるやり方で教えれば勉強が嫌になるでしょうし、逆に楽しいもの、喜びとして教えることができれば勉強が好きになるでしょう。
こここそが教える者の腕の見せ所です。
固定概念にとらわれることなく、自由な発想と想像力を働かせましょう。
今回の月食を実際に見るというような、体験というのもは生徒が勉強に対して興味を持たせる手軽な方法の一つです。
「何だろう」「不思議だな」「どうなっているのだろう」「やってみたい」「できるようになりたい」という知的好奇心への刺激は、実は家庭でも意外とできるものです。
親子が一緒に何かする。
料理でも工作でもハイキングでもいい。
どうか皆さん、そのようなチャンスを逃さず、一緒に考え話し合ってみてください。
ときには分からないふりをして、さりげなく生徒をガイドして、そして生徒ができたときは大いに褒めるというパフォーマンス力も必要になります。
これも学びを促すテクニックの一つです。
こうして日常の「a-ha体験(そうか!という体験」を増やすことが、生徒の自分から進んで学ぶ力につながります。
























2025.09.01
高校見学で注意すること!自分の将来の母校を決めるために必ず参加しましょう

夏休みも終わり二学期が始まりました。
しかし、学校説明会、学校見学を行うまだ高校はたくさんあります。
自分の目指す学校がどのような学校なのか、本当に自分の希望する通りの学校なのか知るためにも、ぜひ参加してください。
そして、そこに通う生徒、教える先生たちに実際に会い、生の声を聞きましょう。
後悔しない間違いのない高校選びのために重要なことです。
そこで今回は、実際に訪れて学校が本当はどのようなものなのかを知る時に注意すべき点をお話します。









1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認
入れるならどこでもいいというわけではありません。
入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認する必要があります。
資料を見て、コースやカリキュラムについて分からないことは必ず聞いてください。
授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。
直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。
さらに、高校卒業後の進路についても質問するべきです。
高校は長い人生における通過点であり、その先の人生の方向付けに大きく関わる場所でもあります。
自分の可能性を広げるためにも、高校で何ができて、それが後の人生にどのように影響するか考えましょう。
具体的に資格取得など、在学中にできることを確認してください。
2.学校の施設や設備を確認
プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。
特に最近の猛暑は異常であり、そんな環境の中でも生徒たちは勉強しないといけません。
快適な環境が学習に与える影響は大きく、学校の設備次第で勉強の効率が大きく上がります。
勉強が第一の生徒にとって、学校の設備は非常に重要なものです。
また、部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。
図書館やパソコンも大事です。
特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。
さらに物理的な設備だけではなく、カウンセリングなどの心理的サポートの有無もチェックできるといいです。
自分汚将来のために適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。
3.構内掲示や清掃状況を確認
掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。
掲示物がきちんと整理され見やすいか。
廊下や教室が綺麗に掃除されているか。
少し細かすぎるように感じるかも知れませんが、こういうところに学校の姿勢や考え方が現れます。
そして、そこから生徒の日常の営みも想像できます。
自分が学校生活を送るとき、本当に気持ちの良い環境で勉強に励むことができるのか考えてみましょう。
また、部活の賞状などからは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。
課外活動でのこれらの成果は、その学校の強みを表しているとも言えるのです。
4.公開授業は見た方がいいです
公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。
公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。
よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。
だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。
ただ、最近は公開授業が普段の授業の様子を見せるというより、エンターテインメント化しているところも多くあるので注意してください。
受験生の気を引くために、普段やらないような実験をしてみたり、いつもと違う方法で授業を勧めたりだと、受験生にとっては高校選びの参考にはなりません。
そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。
案外正直に話してくれるものです。
ダメ元で声を掛けてみるのもいいでしょう。
思わぬ情報を入手できるかも知れません。









学校見学は高校を知る重要な機会です。
事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。
後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。

























2025.08.08
気温がぐんぐん上昇40度を超えのところも!熱中症対策をしましょう

すっかり夏になり、ニュースは連日の暑さを伝えています。
日本でも一部地域で40度越えの観測史上最高気温を記録しており、これまでにないような大変暑い夏休みとなっています。
こうなってくると猛暑の中で勉強しなくてはならない生徒たちの健康が、非常に心配になってきます。
毎年ニュースで熱中症による死者が報じられ命にもかかわる問題なので、本日は熱中症について考えてみます。









いろいろ調べてみると、熱中症とは高温多湿の環境に置かれたときに起きる様々な症状の総称とわかります。
その症状はめまい、吐き気、顔のほてり、筋肉のけいれんなどがあります。
熱中症予防
対処法としては、こまめな水分補給が第一です。
最近では学校でも水筒を持参させ、いつでも水分補給ができるようになっているところもあります。
ただの水よりスポーツ飲料のような塩分や糖分を含むものがいいでしょう。
汗を活発にかき、知らず知らずのうちに水分や塩分は失われていくので、喉が渇いてなくても水分補給をしましょう。
取り過ぎはいけませんが、食事で失われた塩分を取るように気をつけましょう。
また、暑さに負けない体を作るためにも、普段の食事に気を遣い、バランスの取れた食事をしましょう。
体力を維持するためにも十分な睡眠は大切です。
暑くて夜眠れないようでしたら、エアコンや扇風機を付け、通気性のよい寝具を使いましょう。
これは寝ている間の熱中症の予防にもなります。
直射日光を避け、風通しの良い環境を作りましょう。
服装も通気性のよいものを選び、下着は吸水性や速乾性のよいものにしてください。
冷却シートのような体を冷やす製品を活用するのも有効です。
体育や部活、外出などでどうしても炎天下に出ないといけない場合は、こまめに休憩を取り水分補給をしましょう。
実際にはなかなか難しいかもしれませんが、気温などに注意しながら熱中症の予防を心がけてください。
熱中症になったら
もし熱中症にかかったと思ったら、すぐに風通しの良い日陰やエアコンの利いた部屋に行って安静にしましょう。
衣服を脱いで、首の両側や脇、足の付け根を保冷材などで冷やすと体温が下がります。
水で体を濡らしうちわであおぐのも体を冷やします。
水分補給ですが、できればスポーツドリンクの方が塩分も同時に補給できるのでいいでしょう。
症状がひどい場合は救急車を呼んで、速やかに病院へ行きましょう。









東京は連日真夏の暑さです。
毎日のように熱中症のニュースが飛び交っていますが、くれぐれも無理せずご注意ください。
こんな厳しい環境で勉強をしなくてはならない生徒たちは大変ですが、健康に気をつけながら頑張ってください。
特に受験生は勉強も大事ですが、体を崩さないように体調管理をしっかりしましょう。
この時期に病気などで勉強に手がつけられなくなると、受験に大きく響きます。
過酷な環境で無理をしないで、熱中症対策をしてこの酷暑を乗り切ってください。
葛西TKKアカデミーのエアコンの効いた涼しく勉強しやすい教室も利用してください。
いろいろな観点から、いつも皆様の勉強をサポートします。
























- 1 / 84
- »

