塾長ブログ
2025.07.21
時事問題を考えよう!

時事問題とは、現在起こっている社会問題や人々の間で取り上げられている話題などです。
時事問題は政治、経済、国際情勢など多岐に渡ります。
学校の五教科で現時点での時事問題に触れることはあまりないと思います(近年の時事問題ではあるかも知れませんが)。
しかし、時事問題を考えることには利点がいくつかあります。
本日はそのことについて考えみたいと思います。











1.受験対策として
受験において時事問題が関係するのは、推薦入試などで行われる面接でしょう。
自分について、中学生活について、高校ではどのように過ごしたいかなど聞かれますが、時には時事問題について質問されることがあります。
そんな時に「分かりません」では元も子もありません。
時事問題を知っているということに加え、自分なりの問題に対する意見が求められます。
でも、事前に時事問題についての知識や理解があれば答えることは可能でしょう。
だから、普段から時事問題に興味を持ち、いろいろと考え自分なりの意見を用意しておけば、質問されたときに上手く答えることができます。
また、一般の入試でも近現代史や現代文では時事問題に関係するもの(さすがに試験直前の時事問題とはいきませんが)が出たりします。
新しい指導要領が発表され、教育改革が進む現在の学校教育においては思考力が重視されるので、入試問題に時事問題を絡めた問題が出されることは想像に難くありません。
そのときも、時事ネタに対する予備知識があれば、解答はかなり容易になります。
以上の点において、受験の準備として普段から新聞やテレビなどのニュースで時事問題に目を通し考えることは重要と考えられます。
2.コミュニケーション能力の向上のために
時事問題とは大人も共通して話題にできるので、時事問題を利用して親子や友人同士で議論するのもいいです。
ニュースなどから正確に情報を捉え、必要であれば様々なツールで情報収集する。
情報収集能力の訓練になると同時に、どうすれば相手に正確に情報が伝えられ、自分の考えを理解してもらえるかという発信力の練習にもなります。
相手の意見も正しく捉えないといけないので、双方向の伝達であるコミュニケーション能力の向上にもつながります。
自分の考えを間違えなく相手に伝え、相手の意見を正確に理解する力は学校生活のみならず社会に出てからも必要で、人生おいて最も大切な能力の一つと言えるでしょう。
3.読解力と論理的思考の訓練として
新聞やニュースなどの時事問題を利用して読解力が高められることができます。
同時に、理解した情報からどのように考え、その考えを相手に伝えるかを工夫することは、論理的思考、判断力、表現力といった現在文科省が新制度の入試において求める力の鍛錬にもなります。
多くの文章や資料を読んでデータや資料を読み解く能力が高め、語彙を増やすことで知識を高めれば、自身の思考の世界が広がり論理的な考え方に慣れ、新しい意見やアイデアがどんどん浮かぶようになるでしょう。
4.人間関係の深化
時事問題について議論することで、参加しているメンバー内の相互理解と絆が深まります。
普段分からなかったが、この人はそんな風に考えるのだと知って驚かされるかもしれません。
これは話し合って初めて分かることで、時事問題がそのきっかけとして最適と考えます。
お互いの意見を交換することで、今までそこまで関わっていなかった人との仲が深まり、より多くの人との関係を持つことができます。
また、親子であれば子供との壁が低くなり、子供が何かの問題に巻き込まれたときの早期発見につながることも考えられます。
特別に時事問題を話す時間を設ける必要はありませんが、食事のときの会話の一つとして話題をふってもいいと思います。
そこで子どもの知らなかった問題の背景やいきさつなどを説明できると、やはり親に対する畏敬の念は深まるのではないでしょうか。
子どもが親を尊敬し、親は子どもに対して慈しみの心が持てれば、家庭も円満になるでしょう。
意見の相違があったとしても口論ではなく話し合いという形で解決できるので、思春期特集の親子の対立も回避できます。
5.知的好奇心を高め、勉強に興味を持たせる
これは葛西TKKアカデミーでは最も重視することの一つですが、時事問題と通して知的好奇心を高めることができます。
常に「なぜ」「どうして」という姿勢で時事問題を見ると、物事に興味関心がわいてきます。
クイズを解くように、自身で問題を掘り下げ、その背景を知ることもできます。
このようにして、一つのことをきっかけに多くのことを学べるのです。
そして、謎が解けたとき、達成感と満足感が生まれ、プラスの循環を生み、もっと学ぼうと積極的になれるのです。
人から言われる勉強は苦痛です。
子供にそう仕向ける大人も苦痛です。
本人が自主的に学んでくれれば、お互いにストレスを抱えることなく良好な関係を保つことができます。
このとき大人は「聞き役」もしくは「アドバイザー」に徹してください。
下手に答えを与えたり、自分の考えを押し付けるのは決してよくありません。
学習意欲を減退させ、逆効果になります。
求められたときに「個人的な考えだけど、こんな風にも考えられるのじゃないかな」という具合で、考え方の一例として提示するのはいいと思います。
こうして知的探求心を育てれば、全ての分野において学びが楽しくなり、いろいろなことに対して自主的に学べるようになると思います。











日本では家庭内で政治や社会の話をするのは場違いのように思われることがよくあります。
ところが欧米は逆に家庭で積極的に時事問題を話し合い、子供たちが社会の現実と問題に目を向け学べるようにしています。
よって、皆さんのご家庭でも遠慮なくこのような話題をしていいです。
これまで見てきたように、時事問題を通して子どもの教育にプラスになることは非常に多いのです。
時事問題で社会や理科、国語などの学習を深めると同時に、人間としてこれからの社会を生きていくのに必要な能力を身に付てくれることを願います。
家庭で協力して時事問題に触れることが、子供たちの勉強のみならず、人としての成長の一助になってくれれば幸いです。






























2025.06.25
テストの見直しをしよう!テスト直後の見直しが勉強を深める
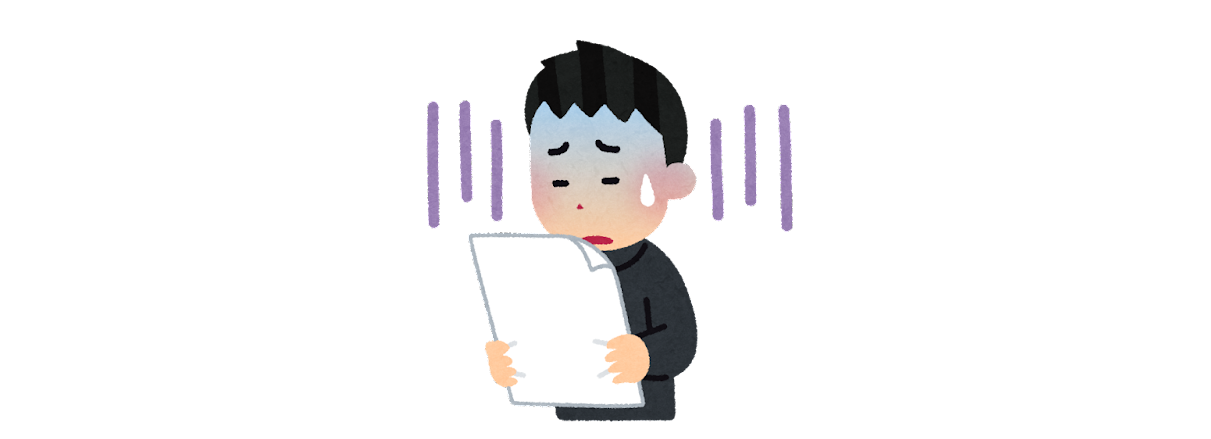
中学ではちょうど定期テストが終わり、高校ではこれから定期テストというタイミングだと思います。
中学生は一つの難関を終えてほっとしていることでしょう。
高校生も来週、再来週あたりにはテストが終わり解放感に浸っていることと想像します。
でも、テストはやったら終わりではありません。
実はテスト後の見直しが子供たちの学びを深めてくれるチャンスなのです。
だから、テストが返ってきて、その点数を見て一喜一憂して終わりではもったいない。
特にテストの点数が悪かったときは、悲しんで終わりにしないでほしいです。
結果が悪かったときこそ、自分を顧みて改善てきる絶好の機会です。









人間の記憶は回数×インパクト
例えば交通事故の現場など、頻度は少なくても非常に印象深い出来事であれば、一回でも詳細に覚えているものです。
一般的に言われる「トラウマ」などはその例です。
また、掛け算の九九のように、単調で何の面白みのないこと(インパクトの薄いもの)でも、何回も何回も回数をこなすことでいつの間にか身に付けることが出きます。
このように人間の記憶とは、回数とインパクトによって大きく変わってくると言えます。
そして、記憶が脳内に刻まれ長期記憶となれば、たとえ長い間忘れていても何かの拍子に次々と記憶を再構築することができます。
しばらく忘れていた歌を何かのきっかけで耳にしたとき、続けざまに全ての歌詞が思い出されるなどといった経験はございませんか。
この記憶の仕組みをうまく利用すれば、勉強もより深く定着させることができます。
そして、テスト直後というのは、この最高の機会なのです。
定期テストを通してエピソード記憶を作る
定期テストは生徒たちが一生懸命頑張って準備をして受けます。
テスト中も含めて、全身全霊を傾けたこの経験は、生徒たちの頭に強烈なインパクトを残します。
本気で取り組んだからこそ、その結果を見たときの喜びも悲しみも大きな印象として残ります。
このように個人の体験が一つの物語のようになり記憶となったき、これがエピソード記憶になります。
エピソード記憶が記憶を促す
人間は記憶するとき、目的のものそのものを覚えるより、何か他のものと関連づけて覚えた方が覚えやすいという傾向があります。
定期テストとその勉強を通じて行ったこと、考えたことはエピソード記憶となりますから、テストが終わったときに、この経験と学習内容をうまくつなぐことができれば記憶は促されます。
頑張ったのに問題が解けなかったときは非常に悔しいでしょう。
そして、このときテストの見直しをすると、この悔しさがインパクトになり、見直した内容をより深く脳裏に刻むことができます。
もちろん、正解した解答も同様です。
努力が報われた喜びも脳への大きなインパクトになります。
先ほど述べたように、テストを通じて得られた強烈なインパクトが記憶を促進するのです。
一方、テストが済んで何もしなければ、エピソード記憶と勉強との結びつけができず、勉強が記憶されないだけでなく、エピソード記憶も失われてしまいます。
だから、テストが戻ってきたときに間違った問題をもう一度確認するという作業は、学習内容とエピソード記憶の紐づけるはたらきをし、より効率よく勉強を進めることができるのです。
悪い結果は必ずしも悪いことではない
悪い結果が出たとき、単純にその結果に怒ったり悲しんだりするだけで、他に何もしない生徒が少なくありません。
確かに出てしまった結果は変えられませんが、これを次の学びへの教訓として役立てられれば、悪い結果もただ悪いだけにはなりません。
「失敗は成功の基」などといいますが、失敗を失敗で終わらせるか更なる飛躍につなげるかは生徒次第です。
定期テストで結果を出すことは大事ですが、勉強はそこで終わりではありません。
その後も続き、また新たな課題に取り組まなくてはなりません。
入試などもっと先の目標もあります。
したがって、定期テストが悪かったからと落ち込んで終わりにするのではなく、この機会を無駄にせず利用し、自分にとってプラスになるように持っていくのが賢いやり方です。
「テストで間違えが多いというのは、そこから学べることも多い」と考えて、前向きに勉強に活用してください。
毎回のテストの後のちょっとした心がけですが、これが積み重なったときその違いは非常に大きいです。
勉強は今だけを考えるのではなく、将来を見据えながら生かせるチャンスは全て貪欲に活用しましょう。









勉強は毎回の定期テストで終わりではなく、その後も続きます。
これまで学習したことが基となって新たな学びが生まれます。
一度出てしまった結果は変えられませんが、そこから学んで多くのことを得られれば、マイナスの結果を次のプラスに転じることができます。
そのためにもテスト後の見直しは重要で、全ての生徒に是非やってほしいと強調します。
もし、一人で見直すのが難しいという人は葛西TKKアカデミーが協力します。
一人でも多くの生徒がたくさん学べるようにと考えていますので、遠慮なくお声がけください。

























2025.06.07
”捨て問題”はテスト戦略の一つですが注意が必要です

「捨て問題」って聞いたことありますか。
塾でテストの戦略として使う言葉なんですが、しばしば生徒もこの言葉を口にします。
しかし、そのときの「捨て問題」の意味は間違っていることもあるので皆さんも注意してください。









「捨て問題」とは
そもそも「捨て問題」とは何でしょうか。
それは時間に限りのあるテストにおいて、難しい問題に時間を割かれ、本来自分が解ける問題に取り組む時間が無くなることを防止するため、難易度の高い問題、自分の能力をはるかに上回る問題は最初から放棄し、その分の時間を自分の力で何とかできる問題に当てるというテスト戦略です。
本当は全ての問題に全力で取り組み全ての問題に答えるのべきですが、制限時間内で全問解答ができない状況もあります。
そんな中で最大限の点数を得るためにはどうしても問題を選ばないといけません。
では、どのように問題を選択すればいいのでしょうか。
ほとんどの人が解けないような難問は、それができなくても成績順位にはそれほど影響しません(上位を目指している生徒は別ですが)。
なぜなら、みんなができない問題を自分が落としても、他者との点数にあまり差がつかないからです。
それならば、このような問題は最初から手を付けないで、その分の時間を自分ができる問題に割り振って、着実に点数を取っていこうということです。
逆に、みんなができる問題を落としてしまうと、他の多くの人から差をつけられることになり、成績も一気に下がってしまいます。
だから、誰もができる問題は絶対にできなければなりません。
しかも、最初から全問を解くことを放棄している訳ですから、全て解ける受験生に対しては不利な条件で争わなくてはいけなくなります。
ある意味背水の陣を敷くということです。
このように「捨て問題」というテクニックは特定の問題(それによって得られる点数)を犠牲にして、確実に取れるものを取っていこうというものです。
この他にも授業や問題集をやるとき、生徒の目指すレベルや実力を鑑みて、必要ないと判断した時は何問や応用問題をしないで、基礎に時間をかけることもあります。
そうすることで絶対に身に付けておかなければならない勉強を時間をかけてしっかり行うことができます。
これも一種の「捨て問題」と言えるでしょう。
間違った「捨て問題」とは
しかし、「捨て問題」(通称「捨て問」)を生徒たちが口にするときは注意が必要です。
なぜなら、「捨て問題」を誤解して、解く必要のない問題と捉えていることが多いからです。
塾などで「これは捨て問だからやらなくてもいい」と聞き、「捨て問」という言葉を覚える生徒がいます。
このとき、経験の少ない生徒はどの問題が「捨て問」で、どの問題が絶対に解けなくてはいけない問題かを区別できません。
そして、単純にやらなくてもいい問題があるんだと勘違いし、「捨て問」という言葉を使って勉強しない理由にしてしまいます。
その結果、自分が苦手な問題、面倒くさい問題、やりたくない問題、ちょっと難しそうな問題、これらを全て「捨て問」と認定し問題をしない口実にしてしまう。
このように勉強を回避する言い訳として「捨て問題」に生徒が言及する場合は、テストの点数を上げ成績をよくするための戦略としての「捨て問題」とは違い、生徒の勉強を損なう恐れがあります。
やりなさいと言っても「これは捨て問だからやらなくていいんだ」なんて言われたことはありませんか。
これは完全に本人の誤解で、全ての問題を自分の都合で「捨て問」にしていいとわけではありません。
先生が長年の経験に基づき、各生徒の学力や目標を考慮して、どの問題を「捨て問題」にすべきか判断するからこそ完璧ではないにしろ最大の勉強ができるのです。
繰り返します。
本来は全ての問題に取り組むべきですが、状況が許さない場合において苦肉の策として「捨て問題」を決めるのです。
生徒が自分のやりたくない問題を「捨て問題」として、自分が努力しなくてもできる問題しかしなくなってしまった場合、その生徒は困難を乗り越えて自分を成長させるチャンスを自ら放棄していることと同じになってしまいます。
これでは勉強の意味がありません。
勉強は分からないから、できないからこそするものです。
できるものしかしなければいつまで経っても成長も上達もなく、成績が良くなるはずがありません。
勉強は「α+1」
よく勉強は「α+1」と言われます。
αは自分の今の実力、これに1足したぐらいがちょうど学習にはいいというものです。
余りにも自分の今の実力からかけ離れたものはやっても理解できませんが、少し難しいくらいなら無理のない努力で学習を深めることができます。
この「α+1」の問題を「捨て問」と言ってやらなければ、いつまで経ってもαはαのままだし、ましてや楽な問題「α-1」なんてやっていたら成長どころか退化してしまいます。
勉強はやればいいというものではありません。
きちんと正しく丁寧にやらなければなりませんし、面倒くさがって楽をしようとすると自身を伸ばす機会を失い、後々自分がつらくなります。
困難や苦労を乗り越えた先に生徒一人ひとりの成長があり、勉強はそのための手段であり、自分を高める修行における試練だと考えてほしいです。
その点を理解すれば、「捨て問題」を勉強回避の方便にすることがいかに愚かしいか分かるのではないでしょうか。









勉強において、出された問題は本来全てやるべきです。
問題を解くことによって学んだ知識が定着し、より確実な力として様々な事柄に応用が効くようになります。
その結果、自身の能力を向上でき、より多くのことができる(学校の勉強に限らす)大きな人間に成長できるのです。
貪欲に問題に取り組み、自身をどんどん磨き上げるチャンスと捉えてください。
しかし、状況によってはそれが許されないときがあります。
そんなとき、対応策の一つとして「捨て問題」という方法がというわけで、決して最善策というわけではありません。
そして、「捨て問題」の区別は長年の経験がある者でないと適切にできず、生徒が自分の気分や好みで決めていいものではありません。
したがって、先生の指導に基づかないで生徒が行う「捨て問題」は、せっかくの学びのチャンスを不意にし、勉強を深める機会を逃す恐れがあるので十分気をつけましょう。
「捨て問題」と生徒が口にしたときはなぜそれが捨て問題か問いかけ、「捨て問題」の本当の意味を説明し誤解のないように願います。

























2025.05.11
GW特別企画TKKピクニックに行ってきました
葛西TKKアカデミーでは通常授業だけでなく、機会を見ては生徒たちと交流し、普段とは違う学習を行える規格も実施しています。
今回はゴールデンウィーク特別企画と称して、希望する生徒たちと一緒に初夏のピクニックに出かけましたので、そのご報告をしたいと思います。
最近は忙しく、遅い報告となってしまいました。










出発!
5月4日㈰10時に葛西TKKアカデミーに集合!
今回はお母様一人を含む小学生が中心の総勢9名のピクニックとなりました。
まず妙典駅に移動して、そこから江戸川に沿って河川敷を歩き、篠崎ポニーランドまで向かうコースです。
途中寄り道をしながらゲームをしたり、自然に触れながら工作をしたりと楽しく過ごせるよう計画しました。
妙典駅から篠崎ポニーランドまで、真っすぐ進めば30分ほどの道のりを1時間ぐらいかけ遊びながら歩いていく予定です。
みんなが集まったら葛西駅に移動し、東西線に乗り込みました。
日曜ということもあってか、車内はそれほど混んでいる訳でなく、他の乗客に迷惑を掛けることなく乗れて一安心でした。
地下鉄博物館がある土地柄か、男子生徒たちの中には鉄道マニアがいて、鉄道のうんちくをずっとしゃべっていました。
好きなものを語る子どもたちを微笑ましく思っていると、あっと言う間に妙典駅に着きました。
河川敷
妙典駅を降りてイオン市川妙典店を抜けると公園にたどり着きます。
さらに先に進むとバーベキューのできる一画があり、週末などはいつも人々でにぎわっています。
この日も例にもれずおいしそうなバーベキューの匂いが漂っていました。

そして、そこを過ぎると目の前に江戸川が現れました。
河口近くのこの場所は干満の影響を受けています。
私たちが訪ねたときは干潮に近かったようで、川の水位も下がり川底もかなり出ていました。
このような場所に行くのも珍しいのか、みんな一目散に土手を降りていきました。
まずは落ちている貝殻を拾い始めました。
川の水に触れ、水面に顔を出した石をジャンプしながら伝ったりとはしゃいでいました。
潮が引いたばかり干潟には水たまりも多く、小さな貝やカニが生息していました。
そのことを教えてあげると、子どもたちは私の捕まえたカニや貝を興味深げに見たり触ったりしました。
中には自分で捕まえようとする生徒もいました。
生きているヤドカリも見つけ捕まえてあげると、最初は分からなかったようですが、モソモソ動き出すとようやく理解できたようです。

なかなか自然の中で実際に生き物に触れる機会がないからか、予定以上の時間を妙典の河川敷で過ごしました。
まだまだ道のりはこれからなのですが、特に厳密に守らなくてはならないスケジュールでもないので、生徒たちの状態に合わせて、行程を進んでいこうと思います。
ゲーム、水切り&笹船
まだ出発地点の妙典からほとんど離れていませんが、時間は結構過ぎてしまいました。
とは言え、急ぐ旅でもないもないので、子どもたちの気のすむまで遊ばせながら、のんびり行程を進みたいと思います。
買い込んだ景品用の駄菓子がたくさんあるので、道中ゲームをしながら子どもたちに配るつもりです。
先ほどの場所を離れるためにじゃんけん大会をして区切りを付けます。
単純なゲームですが、景品がかかると子どもたちは大興奮。
素直に盛り上がってくれるので助かります。
江戸川に沿って歩いては道草を食って、気ままにマイペースのピクニック。
再び川辺に降りて水切りをしました。
周りにちょうど良い形の意思がなかったので、子どもたちは上手にできませんでした。
次回のチャレンジに期待しましょう。
また歩いてゲームタイム。
チームに分かれて全員参加のリレーです。
参加してくれたお母様も含めてのリレー。
人数合わせで一人が二回は知らなくてはならなかったのですが、スタート地点に戻っていなかったのでリレーする相手がいないというアクシデント。
こういう不慮の出来事も楽しい思い出です。
しばらく歩くと川沿いに笹が生えていたので、子どもたちを集めて笹船の作り方を教えました。
子どもたちは笹船を作ったことがないようで、作るのに苦戦していました。
確かにこの辺ではこんなことする機会も滅多にないでしょう。
結局私が作った笹船を子どもたちが川に流すという形となりました。


昼食
気がつけばもう正午でした。
「お腹がすいた」と子どもたちが言い始めたので、土手に座ってお昼ご飯にしました。
各自持ち寄ったお弁当をお菓子を食べて一休み。

みんなでワイワイ話しながら自由に食事をしたり、河原でまた遊んだり。
本当ならもう少し先で休憩を取る予定でしたが、かなり遅れてしまいました。
まだ道のりは長い。
でも気ままなピクニックもいいものです。
エネルギーを充填して再出発です。
出来なかったこと
道中、予定では花冠とブーメランを作る予定でした。
しかし、今年はもうシロツメナグサの時期は終わってしまっていたようです。
白いクローバーの花はもう見当たりませんでした。
ということで、今回花冠作りは断念。
同様にブーメラン作りも考えていて、必要な材料と道具は揃えていたのですが、工作をするような広場のような所が見つからず、こちらも諦めました。
スケジュールも遅れ気味だったので、また今度でいいかという判断です。
子どもたちは、歩きながら経験するいろいろなことで精一杯で、これらをやらないことを気にも留めていないようでした。
失望する様子もなかったので、ほっと一安心。
篠崎ポニーランド
そろそろ子どもたちにも飽きがきたみたいで、疲れも相まって歩みが少しずつ遅くなってきました。
寄り道しながらとは言え、もう三時間近く歩いていました。

でも、江戸川の水門を抜ければもうすぐ。
遠くに白い柵が見え、目的地の篠崎ポニーランドと分かりました。
長旅お疲れ様でした。
小学一年生の生徒も最後まで歩きとおしました。
えらい!
到着したときは午後一時前。
午後からのポニーの乗馬が午後一時だったので、結果的にちょうど良い時間でした。
乗り場に一列に並んで、ポニーたちがやって来るのを待ちます。
ゴールデンウィーク中ということもあり、TKK以外の子どもたちもたくさんいました。
ポニーがやってきていよいよ乗馬の始まりです。
小学生までの制限ですが、無料で乗り放題なので何回も子どもたちは乗っていました。
一人ひねくれものがいて「絶対に乗らない」と言っていたのですが、乗馬が始まるとみんなに混ざって並んで、結局6回も乗っていました。
素直じゃないのもかわいらしく感じます。
全員5~6回は乗ったと思います。
心いくまで乗れて満足できたのではないでしょうか。
帰路
気づけば午後2時を回っていました。
長距離歩いたせいか、一人具合が少し悪くなったみたいで、タクシーで帰らせることにしました。
小学生低学年の子たちと一緒に、先に帰路につきました。
残りの生徒たちは私と一緒に来た道を戻りました。
休憩をはさみながら、マジカルバナナをしながら、みんなで笑いながら歩いていました。
行きは随分長かったように思われた行程も、帰りはあっと言うまでびっくりです。
先ほどの妙典のバーベキュー会場に差し掛かり、酔っぱらった見ず知らずの人に絡まれるというアクシデントもありました。
子どもたちでなくて何よりですが、お酒はほどほどに。
妙典駅に着いて、再び東西線に乗って葛西に戻りました。
TKKアカデミーに着くと、タクシー組がもう着いていて、ホワイトボードに落書きをしたり、お菓子を食べたりして待ってくれていました。
生徒からリクエストがあったので、ブーメラン作りもしました。
簡単なのですぐ完成。
そうこうしているうちにお迎えの親御さんが到着し、ピクニックは解散です。









気ままなピクニック。
せっかくのゴールデンウィークなので何か企画をしなければと考えました。
普段できない経験だったのか、生徒たちはみんな目を輝かせていたのが印象的でした。
こんなに楽しいんでくれるなら、今後も機会を見てはイベントを行いたいと思います。
特に来年は葛西TKKアカデミー開校10周年になるので、何か記念になることをしたいと強く感じました。
このような生徒同士、生徒と講師である私、そして親御さんも含めて交流できるチャンスを持つのは非常にいいことだと思いました。
楽しい思い出ができただけでなく、お互いの接し方も変わってきます。
相手をより知ることで信頼が増し、後日談とはなりますが、塾での生徒の勉強に向かう姿勢に変化が見えたように思われます。
このように葛西TKKアカデミーは単に勉強を教える塾に留まらず、交流を深め様々な経験を通して人の成長を促すことができる塾になりたいと切に願う次第であります。



























2025.04.04
入学おめでとう!新年度そして新生活で気をつけること

4月に入り温かくなったり寒くなったり。
気温の変化に体がついていけない人も多いように見えます。
しかし、桜は少しずつ咲き始め、着実に春らしくなってきました。
4月は新年度になって最初の月。
進学して新一年生になった生徒もたくさんいます。
特に高校大学、そして一部の中学では入学試験を合格して新しい学校に進む生徒がたくさんいます。
皆さん、入学おめでとうございます。
今月から新生活を始める生徒たちに、心よりお祝い申し上げます。
それぞれの学校を卒業し、入学を迎えるまでの間は本当に勉強から解放され、のびのびと羽を伸ばすことができたのではないでしょうか。
勉強を忘れて思いっ切り自由な時間を過ごせるのも、長い学生生活の中でもこの時期くらいでしょう。
思い存分楽しんでください。
苦しい受験勉強を乗り越えてきたのだから、皆さんは十分楽しむ資格があると思います。
しかし、遊んでばかりで気を抜いて何にもしていないと新しい学校に通い始めてから苦労します。
今日は新生活始めるこの時期に注意すべき点を考えます。









やはり勉強
新しい学校では当然勉強の内容もこれまでとはけた違いになります。
しかも、新生活では勉強以外にも学校の過ごし方など新しく覚えなければならないことがいっぱいあります。
あまりの忙しさに心の余裕もなくなり、パニックに陥ることも。
だから、今のうちに少しでも勉強できるところは勉強してください。
教科書を見てよく分からなくても、「へー、こんなことをやるんだ」と知るだけでも大きく違います。
分からないことだらけの新生活に余裕を持って慣れていくためにも、今から始めて勉強の負担を減らしておくことをお勧めします。
また、受験が終わってから一切勉強しなかったという人もいるのではないでしょうか。
そういう人は受験勉強で身に付けたこれまでの学習内容をすっかり忘れてしまっているかも知れません。
全ての勉強がこれまで習ったことを基礎に積み上げられているのならば、忘れたまま新しい学校の授業を受けるのは危険です。
全く理解できずについていけなくなるからです。
だから、新学期が始まる前に最低限の基礎の確認はしておいた方がいいです。
生活リズムの調整
この時期に限らず、長期休暇中は生活が乱れがちです。
学校に行かなくてもいいということで、いつまでも夜更かししたり、起きる時間も昼を過ぎてしまったり、食事なども気まぐれで取って見たりと、生活のリズムが乱れがちです。
学校が始まるとこんな生活は続けられません。
一刻も早く生活リズムを整えて、新生活に適応しないといけません。
時間を整えるだけでなく、食事の不摂生を直し、運動不足を解消し、健康的な生活に戻さないといけません。
新生活は不慣れなことが多く、自分の思い通りにいかないこともたくさんあるので、過剰にストレスがたまります。
乱れたままこのような状況に突入してしまうと、より心身共に負担が増えます。
場合によっては適応できず、登校することさえできなくなることもあります。
せっかく受験を頑張って入った学校なのに、行くことができないなんてもったいないです。
早めに生活習慣を立て直し、新生活へのスムーズな移行ができるように準備しましょう。
新しい学校生活で必要なものはそろっていますか
学校が新しくなると新たに購入しなくてはならないものもあります。
制服やかばんなどは大丈夫ですが、文房具などの細かな備品は意外と気がつかず、揃えるのを忘れてしまったりします。
例えば、同じノートでも小学校と中学校では規格が違っていたり、教科によって全くタイプの違うノートをつかったりします。
前日の夜になって足りないことに気づき、慌てて買いに行かなくてはならなくなるようなことがないように、事前にしっかり考えてリストを作り、チェックしながら早目の用意をしましょう。
足りないからといって直前に買いに行っても、お店にあるとは限りません。
特にこの時期はみんなが同じものを買いそろえるので、品切れになっているところもたくさんあるので気をつけてください。
消しゴム一つを探しに、店を何件もはしごした挙句、結局なかったでは済まされません。
子どもの心理状態にも注意
新学期は希望とワクワクに満ちている生徒もいますが、新しい環境に不安になりおびえている生徒もいます。
そんなときは周囲の人間のサポートが欠かせなくなります。
そのためにも、子どもたちが無意識に出しているSOSのサインに気づけるように注意してください。
「学校に行きたくない」とぐずったり、表情が極端に暗かったりしていませんか。
小さな変化でも見逃さず、速やかに対応できるように、いつも以上にしっかり観察しましょう。
子どもが新しい学校で一番気にすることは、何と言っても人間関係と勉強でしょう。
これから見知らぬ人たちと一緒に生活するのだから、うまく溶け込めるか心配なのも当然です。
今の生徒は学校に入ったらすぐに、LINEグループなどを作って他の生徒たちとつながろうとします。
それほど不安であるということです。
現在はSNSが発達しているので、デジタルネイティブの彼らはこれらのツールを使って必死で、時には自分を押し殺してでも、友達作りにいそしむのです。
次に勉強ですが、生徒たちにとって自分たちの本分である勉強に行き詰まることは大問題であり、自分が新しい学校で今まで以上に難しい勉強についていけるのか悩むのも理解できます。
特に、これまで成績優秀だった生徒が多くの学校から同等に優秀な生徒が集まる新しい学校において、思っていた以上によい成績が修められずに愕然とすることもあるでしょう。
それまでが優秀であった生徒であればあるほど、その苦悩と絶望感は大きいようです。
勉強についていけないと感じ、周囲との差を実感し、プレッシャーとストレスで苦しむこともあります。
自己肯定感が落ち自信もなくなり、無気力になってしまっては大変です。
子どもの心理にどう対処するか
このようなときは叱りつけるのはよい方法とは言えません。
仮に一時的に成績が回復しても、常に「また成績が下がってしまったらどうしようか」という不安と脅迫概念にかられることがあります。
大事なことは、本人に「自分は一人ではなく、安心して全てを打ち明けられる人がいる」と分からせることです。
それは日常のごく些細な一場面、ちょっとした挨拶や笑顔で変わってくるものです。
そして、「自分にはどんなときにも手を差し伸べてくれる」という安心感が生まれれば、現状を受け入れ、冷静に事態を見つめ、解決策を模索できるようになるでしょう。
このときも一人で考えるのでなく、人生の先輩として誰かがヒントを与えてもらえるとよりいいでしょう。
今は時代の変化が激しく環境も大きく異なりはしますが、人間として悩み苦しむことは変わりないのだから、自身の経験を話してあげるのも、彼らにとって何らかの手助けになるはずです。
仮に絶対の解決策が見つからなかったとしても、共に悩みを共有できる人がいるというだけで、子どもたちは安心するはずです。
子どもたちが新年度の壁にぶち当たったとき、我々にはまだ多くのことができると考えましょう。
そう思えば、彼らに対処する方法はいくらでもあるはずです。









今回は新年度ということで、新しい学校生活を迎えるこの時期に注意すべきことを議論してみました。
大人であっても、新しい環境というのは不安なものです。
だからこそ、早めに準備をして最善のスタートを切れるように心がけましょう。
新しい学校は嫌なことや苦しいこともあるでしょうが、それだけでは決してありません。
明るく楽しい部分にも目をやりましょう。
疾風怒濤の青春時代は、苦しいことも楽しいことも子どもたちの血肉となり、将来社会に出たときの芯の強さになります。
何一つ無駄なことはないはずです。
何でもチャレンジしがむしゃらに生きることが許されるのも、きっとこの時代だけだと思います。
新しい生活を有意義に楽しんでください。
応援しております。




































2025.03.26
円谷英二「まず『できる』と言う!方法はそれから考える」子どもと接するとき考えさせられる言葉

「まず『できる』と言う。方法はそれから考える。」
これはウルトラマンやゴジラなどを生み、特撮の神様とも呼ばれた円谷英二の言葉です。
また、「ないものは作ればいい。」とも彼は言っています。
どちらの言葉も子供たちと接するときに非常に考えさせられます。









魔法の言葉
不可能と思われるほど限られた予算と製作期間でも、円谷英二は自身の持てる技術と知恵を総動員し、創意工夫しながら映画『ゴジラ』を完成させました。
今では撮影で当たり前のように使われるクレーンやミニチュア撮影、グリーンバック撮影も彼のアイデアが元になって生み出された技術だそうです。
現在ではあまりにも当然のように使われていて、なしでは考えられないような撮影方法も、当時ゼロから考え作り上げるとなるとどれほど困難か想像に難くありません。
しかし、このような技術も彼が言葉を実行したからこそ、今の私たちはその恩恵にあずかることができるのです。
楽観的で無計画のようにも聞こえますが、先の心配ばかりして一歩が踏み出せないのであれば、いつまで経ってもゴールにはたどり着きません。
まずは自分の立ち位置を決めて、そこから動き出さないといけない。
そして、実際にやってみれば「大したことなかった」なんてことはよくあるのですが、行動を起こすまでは怖くて勇気が出ずにどうしても知りごもりをしてしまう。
特に物事をまだ十分に理解できない子どもたちは、失敗を恐れなかなか挑戦できません。
そんなとき、この言葉は大いに力を発揮します。
ナイーブな子どもたち
人生経験の少ない子供たちには物事がどれほど困難か、人間の可能性がどれほどのものなのか正確に推し量ることは難しいです。
大人が言ってもなかなか確信が持てず尻込みをしてしまい、せっかくできるのにやらないということがよくあります。
特に最近の子供は慎重というか、臆病な点を強く感じます。
子供らしく若者らしく、失敗を恐れず無鉄砲に立ち向かってほしいのですが、自己肯定感が低く自分に自信を持てない生徒が多いように思われます。
または、チャレンジすることを面倒に感じ、その言い訳として自分を卑下する。
怠慢とも言えますが、それが自分の成長の機会を奪い、自分にとってマイナスになるということを理解するのも彼らには難しいようです。
さらに、とにかく失敗したくないという気持ちが強く、「失敗して笑われるくらいなら何もしない方がいい」と考える生徒も多いです。
これは自己へのプライドの高さ(保身)と相関するものとも考えられるでしょう。
これらの理由で、勉強に限らず何においても一歩が踏み出せないナイーブな生徒が増えているように思われます。
考えすぎず気楽にチャレンジ
子ども時代はある程度の失敗なら許される貴重な時期です。
これは若者の特権、未熟だからこそできること。
だから、この時間にいっぱい失敗してほしいと思います。
「失敗は成功の基」、学びのチャンスです。
失敗からたくさんのことが学べ、より人間として高みに至ることができます。
100点なんてつまらない、新しく得るものがないから。
テストの結果なんて悪くてもいい、そこから学んで大きく成長できれば。
つまり、テストや問題を解くのは学びのゴールではなく出発点なのです。
だから、結果だけ見て一喜一憂して終わることが多いですが、そこで終わってはもったいないです。
自分の至らぬ点を把握し、それを改善する機会として有効に活用すればいい。
「分からない」が「分かる」になった瞬間の喜びは何ものにも代えがたく、それを理解すれば「間違い」は怖いものではなく「楽しさ」のきっかけに変わるのです。
最終的にどちらに転んでも、自分次第で自身の糧にできる。
そうであるなら、深く考えずとにかくやってみましょう。
後はなるようになるし、大抵は心配するほどでもなく「こんなものか」と思えることも多いです。
でも、動かなければいつまで経っても何も変化はなく、自分を高める成長はできません。
円谷英二の言葉に勇気をもらい、まずは第一歩を踏み出してみましょう。
大丈夫、心配いらない、うまくいく。
大人の配慮で子どもたちが歩み出せるように
子どもが二の足を踏んでしまう理由に周囲の目があります。
特に自身のプライドを重視する思春期の子どもたちには、これは大きな行動要因になります。
だから、周囲から軽蔑されるかもしれないと自身の失敗を非常に恐れ、「失敗するくらいならやらない方がいい」と考え動かないことは生徒にはよくあることです。
問題が分からないとき「分かりません」と言わず、「言いたくないです」と言った生徒がいたことが思い出されます。
周りの大人は表面だけでなく深くまでしっかり見抜いて、子どもたちを正当に公平に評価しなくてはなりません。
彼らは成長段階発展途上であるということを私たちは忘れがちです。
それでも評価を下さないといけないのが現実ですが、そうならそのときの結果だけで判断し結論付けてはいけません。
そこにある成長の可能性に目を向けないのはいけません。
非難するのではなく、問題点を一緒に考え人生の先輩としての有益なアドバイスを与えてください。
大事なのは子どもたちを単に欠点を指摘することではなく、どうすれば彼らを伸ばせるかということです。
ここも難しいことですが、この点に注意を払いながら思慮深く接することを心がけましょう。
そうすれば子供たちとの間に信頼ができ安心感も生まれるでしょう。
子どもたちの「恐れ」を取り除き、歩み出せる勇気を持てるようにはたらきかければ、失敗を恐れず何事にもチャレンジができ、その経験が彼らを大きく育てます。
人間の強さは常に変化することで、成長して問題を克服できることです。
留まっていては変化できないので、子どもたちが安心して歩き出せる環境と社会づくりが、大人の重要な責務であると考えます。









失敗(間違い)は罪ではない。
子供のうちにいっぱい失敗(間違い)をし、学びましょう。
また、子供の失敗を許せる寛大な社会環境も大切です。
そのためには大人もゆとりがないといけません。
それは大人自身の問題なのですが。
そして、「間違いが怖いものではない」と分かれば、子どもたちは失敗を恐れず挑戦する勇気が持てるでしょう。
ちょっとうまくいかなかったからと自分を小さくしないで、不安に打ち勝てる強さと苦しさに耐えられる力を身に付けてほしいと思います。
そんなときに、この円谷英二の言葉を唱えてみましょう。
隠れていた一歩踏み出す勇気が湧いてきます。
「人生なるようになる、大丈夫」と。
最近の教育界でも「自己肯定感」と言うのはキーワードになっています。
子どもたちが自分を信じ積極的に前進できるよう、葛西TKKアカデミーは努力しています。
ご家庭でもこの言葉を思い出し、子どもたちに勇気が持てるようになれることを願います。
























2025.03.19
「アクティブラーニングって何?」これからの日本教育のキーワード!

学校教育は日々変化しています。
その時代時代で教育観が変わり、学習内容、指導方法が大きく変わることもあります。
日本の公教育の場合、特に指導要領改訂のタイミングで大きな変化が起こることが多々あります。
中でも現在の指導要領に代わってからの変化には目を見張るものがあります。
前例を見ないと言っていいほどの大改革と言われていますが、その中の要となるものにアクティブラーニングがあります。
文科省は社会に活躍できる人材育成を目指し、知識偏重の教育ではなく、学んだ知識を用いて答えが一つではない様々な問題に生徒が取り組める教育を目指すことが新学習指導要領から分かります。
この目標達成のために導入されたアクティブラーニングですが、実際どのようなものなのでしょうか。
これを取り入れることで学校教育がどのように変わるのでしょうか。









なぜアクティブラーニング?
例えば数学の方程式を解く問題であれば、誰がやっても答えが同じで決まっています。
しかし、「学校の部活動で部員が活発に取り組むようにするにはどうすればいいか。」という問題は決して答えが一つではないし、決まった正解がある訳でもありません。
でも、このような問題は私たちが生きる中でたくさん直面するものです。
今までの知識偏重の教育は、課題を与えられ解法も与えられて、それを処理するには大いに役立ちます。
しかし、今後はそのような機械的な処理はAIが担うので、人間はそうではない分野で活躍できなければならないと考え、今回の教育改革となった訳です。
アクティブラーニングってどんなもの?
では、実際にアクティブラーニングとはどんなもので、どのように子供たちに解答のない問題に取り組むようにさせるのでしょうか。
英語を想定してみましょう。
英語を学ぶのに先生が文法や単語などを基本的には教えません。
代わりに例えば、「発展途上国の人々が教育を受けられるようにすればどうすればいいか」という課題を与えます。
生徒たちは自分たちで「発展途上国の教育の実態」調べます。
そして、自分たちでどうすればいいか話し合います。
最後に英語でプレゼンテーションをします。
この過程で、英文の資料を読まなくてはならなくなれば、自分たちで単語や文法を調べます。
意見交換も英語で行い、自分を英語で表現するにはどうすればいいか考えます。
もちろんプレゼンテーションも英語なので、自分たちで調べ英文の原稿を作ります。
そして、どうしても先生の助けが必要なときは、先生に質問しアドバイスなどをもらいます。
今までのように与えられて覚えるのではなく、自分たちで必要に応じて調べ学ぶのです。
この過程で英語の知識だけでなく、論理的思考や途上国の実情などを学ぶのです。
そして意見交換では相手の意見を要約し正確に理解し、更に相手を説得するにはどうするかというディスカッションの能力も求められます。
こうやって英語の知識と運用能力を身に付けるのです。
アクティブラーニングの課題
これらの事柄を身に付けられるアクティブラーニングは非常に理想的な教育方法に思われます。
しかし、「問題はこれが効果的に実践できるのか」ということです。
アクティブラーニングにおいて教師の役割は知識を与えるというより、生徒が活発に学ぶように促すことです。
これには豊富な知恵と知識と多くの経験が必要です。
なぜなら、生徒の状況は一様ではないので状況に応じて臨機応変な対応が求められますし、授業を盛り上げるために時には冗談や笑いのネタなども言えないといけません。
課題も様々なのでどんな問題でも対応できる幅広い教養が必要です。
経験がないと、機転を利かせ生徒のモチベーションを高め、自分からやる気にさせるのも難しいでしょう。
また、生徒の行動に頼る部分が多いので、狙い通りの内容を身に付けさせるのも難しく、学習時間も今まで以上にかかるでしょう。
限られた時間で指導要領に書かれている全ての要項を習得できるかどうかは、生徒を暗示的に目的に向かって導けるかどうかという指導者の技量にかかる部分が大きいのです。
しかし、そもそも基礎的知識を身に付けさせるだけでも今まで精一杯だったのに、更にそれを使って論理的に展開し課題に取り組むまで持っていけるのでしょうか。
また、それぞれの生徒で異なる学力や性格、姿勢などをどのように評価すべきなのでしょうか。
よくあるのが、どうしても人前で発表するのが苦手で何も言えない、もしくは発表するのが面倒くさい、そんな生徒をどのように見なすかです。
相手の意見を面白いと思う、自分の考えを言うのが楽しくなる。
これは生徒の問題というより、そのような気持ちに生徒を導けるかという先生の問題とも捉えられます。
いかに生徒の知的好奇心を刺激し、授業を活気づけられるかによって、生徒の学びも大きく左右されます。
そう考えると生徒の勉強に向かう姿勢も先生の指導によるところが大きく、生徒の評価が低いということは先生の指導が悪いということもできます。
そもそも欧米などで実践されているアクティブラーニングですが、日本のように40人もの大人数で試みた例はありません。
ご存知のように無効のクラスはせいぜい20人程度で、このようなきめ細やかな教育をこんな大人数のクラスに適用させてうまくいくのかは、実は誰にも分らないのです。
先ほど述べた教員の経験の問題に加え、アクティブラーニングを行う環境も考える必要があると思います。
これまでの教育とは大きく違う教育になるのだから、それにふさわしい環境を整える必要があるのです。
ようやくオンライン授業用のWifiや端末などが公立学校でも揃ってきましたが、十分に使いこなせて活用できているかというと、そうとも言い切れません。
不十分な学習環境で果たしてアクティブラーニングを実施しても大丈夫なのかと心配にもなります。








他にもアクティブラーニングを実践するにおいてクリアすべき課題はたくさんあります。
上手くいけば非常に有効な教育方法ですが、そうでなければ結局基礎知識すら身に付かないリスクがあります。
そして、そのリスクは一人ひとりの生徒や先生によるところが大きく、下手をすれば個人差をより広げる教育になりかねません。
言い換えれば、学ぶ側も教える側もアクティブラーニングの意図をよく理解して授業を受けないと、その意義は薄れてしまうのです。
以上の点に注意してアクティブラーニングを有効に活用し、子供たちの学力向上につながってほしいと願います。






























2025.02.10
内田樹さんの『学ぶ力』を読んで:学びをより高める極意!

仕事柄、様々な文章を読むことが多いです。
そんな中、「なるほど、確かにそうだ」と気づかされたり、「そんな面白い考え方があったか」と感心させられることも非常に多いです。
このような自分にとっての新発見の機会にめぐ前れていることは、とても有難いことと常々感じます。
そこで今回は、私が「なるほど」と感じ、皆さんとも共有したい文章をご紹介したいと思います。








「学ぶ力」
以前、中学二年生の国語を指導したときに、内田樹さんの『学ぶ力』という文章に出会いました。
そこでは「学力」について議論されていたのですが、内田さんの言及する「学力」とは一般的な意味で使われている者とは異なるものでした。
この文章の要点をまとめると、およそ次の通りです。
まず、ここで言う「学力」とは、学校のテストの点数などで示される指標に基づくものではなく、「学ぶことのできる力(学ぶ力)」であり、自分の能力をどれだけ伸ばすことができるかという力です。
具体的にこの力を、学ぶことに対しどれくらい集中し夢中になれるかという度合いを測るために使われるものと述べておられます。
これは一般的に言われる学力と違い、個人的で他人と比べるべきものではないということです。
つまり、点数などで他人と比較できるものではなく、自身の中で昨日と比べどれだけの変化があったか、長い人生においてどれだけ成長したかという時間的変化においてのみ意味を持つものだそうです。
さらに筆者は「学ぶ力」を伸ばすための条件に付いても言及しています。
第一の条件は、「無知の自覚」です。
これは自分の学びがまだ足りていないと自覚があるかということです。
自分の足りなさを痛切に自覚してこそ、学ぼうという姿勢が生まれます。
第二の条件は、自分に教えてくれる「師」という存在を自主的に見つけようとすることであり、「あ、今人が私の師だ」と直感できることです。
ここで気を付けなければならないことは、この「師」という存在は学校の先生でなくても構わないということです。
直接会ったことのない亡くなった人でも、街行く人の中にも、さらには書物の中にでさえ、「師」となり得るものがあるのです。
最後の条件は、教えてくれる人をその気にさせることです。
これには学ぶ側の「無垢さ」「開放性」が必要で、学ぶときの「お願いします」という真っすぐな気持ち、「師」を見上げる真剣なまなざしとなって現れます。
この三つの条件をまとめると、「私は学びたいのです。先生、どうか教えてください。」と素直にはっきり口に出せる人が「学力のある人」と言えるそうです。
教える立場の人間として
子どもたちに教える立場の人間として感じるのは、勉強ができないと言われる子どもたちはほとんどの場合、知能が低いわけではないということです。
勉強ができない原因は知能ではなく、勉強に向き合う姿勢や考え方であることが非常に多いです。
ものごとに対する集中力、与えられたことを根気強く最後までやり遂げる忍耐力、相手の気持ちや意図を理解し行動する対応力など、学力テストでは測ることができない「非認知能力」と呼ばれるものが最近は注目されています。
これは「学習するために必要な力」として学力を高める土台となるものです。
そして、今回の「学ぶ力」もこの点に言及しているとも考えられます。
特に第三の条件である「教えてくれる人をその気にさせる」は非常に共感できる点です。
先生と言ってもなので、自分が一生懸命教えていることに対して、真剣なまなざしを送り頑張ろうとしている生徒には「より力になりたい」と思うものです。
逆に、何かと言って文句を言ったり不要な反論をしたりして、限られた授業時間を無駄に費やす生徒には、教える側としてもやる気が削がれるというのが正直なところです。
もちろん、プロとしてすべきことはしますがモチベーションが大きく変わります。
生徒としては無自覚なのかも知れませんが、このような抵抗が自身にとって大きな損失になっていることが分からないので、この文章を読んで考え方を改めてくれればと願うばかりです。
もちろん先生に対して媚びへつらえという訳ではありません。
素直に勉強に取り組み、少しでも多くのことを学ぼうとしてくれるだけでいいのです。
特別なことは必要ありません。
自ら頑張ろうという生徒は、教える側からすれば非常に健気で愛おしい。
だからこそ、少しでも力になりたいと思う。
そういう気にさせるものがあれば、人並み以上のことを教えてもらえる機会に恵まれるようになるという点で大いに賛同できます。
結果として、自身をより高め、能力を向上させることができます。
そういう意味では、筆者の言う通り学力を上げる大きな条件であると実感できます。








確かに「教えてくれる人をその気にさせる」は学びを深める極意のように思えます。
常に生徒と接し教えている身としては十分すぎるくらい心当たりがあり、内田さんの文章に納得してしまいます。
特に勉強が嫌いな生徒こそこの文章を読んで勉強にいそしんでほしいのですが、残念なことになかなかそうならないのが現実です。
勉強への不要な拒絶と反抗が、自分の首を絞めているのに気づけないのはもったいないです。
それは多くの大人が勉強に意義をうまく伝えられないからかも知れません。
経験の浅い若者は、大人が説明しても実感として理解できないものです。
エネルギーに満ちて可能性を多く持っている若者は、その活かし方を知らない。
でも、経験から知恵を少なからず身に付けたときには、可能性は小さくなり情熱も弱くなっていく。
なんと皮肉なことでしょう。
だからこそ、自分も彼らの「師」と足りえるように努めなければならないと身を引き締めると同時に、子どもたちも勉強を嫌がることなく純粋に学びを楽しみ自身の成長につなげられるように、周囲の人間はよく考えて行動しないといけないなと考えさせられました。
























2025.01.31
都立高校推薦入試合格おめでとう!

本日、1月31日は都立高校の合格発表の日でした。
葛西TKKアカデミーでも二名の生徒が挑戦し、推薦入試に向けた対策講座でこれまで頑張ってきました。
そして、本日二人とも見事合格の連絡が入ってきました。
本当にすばらしい。
うれしいかぎりです。
心からおめでとうと申し上げます。
これもひとえに生徒たちの努力の賜物です。
本人の頑張りがなければ決してなしえないことでした。
そういう意味では、彼らは堂々と自信を誇れる存在であると言えます。










上々の結果
これまでも何度か触れてきた通り、推薦入試は倍率も高く、試験内容も明確な正解が一つしかない5教科の一般入試と違い、小論文や作文、面接や討論など、受験生には馴染みの少ないものばかりなので対策しづらく、別の意味で難しい試験です。
また、各学校の校長が推薦する生徒たちが受ける試験なので、みんな成績の優秀な生徒ばかりです。
そのような状況でが合格を目指すわけですから、至難の業といっても過言ではありません。
葛西TKKアカデミーでは、文章の書き方から面接の振る舞い、回答の仕方など試される意義と目的も含めこと細かく説明してまいりました。
そうして理論を確立した上で、実戦を積み重ねるという方法で指導してまいりました。
同じ推薦入試を受ける葛西TKKアカデミーの塾生同士、お互いに見あって批評することで、自分の短所に気づき、他者の長所に学び自分にも取り入れるというやり方で、相互に技術を高めあってきました。
そうして臨んだ今回の推薦入試ですが、いい意味で予想を裏切られました。
先ほども述べた通り、推薦入試は狭き門であり、よほど大丈夫であろうと思える生徒でさえ落ちることがあります。
だから、今回の結果は非常に嬉しい誤算でした。
二人とも合格とは上出来です。
あまりにも嬉しいので今回ここで共有させていただくことにしました。
残りの一般受験の生徒も頑張れ!
今回の推薦入試の合格と受験生が志望校に決まったことはとても良い流れができていると感じます。
これで残りの一般入試の受験生も合格してくれれば何も言うことなしなのですが、こればかりはふたを開けてみないと分かりません。
とにかく先のことをとやかく考えても仕方ないので、入試直前の数週間を目の前の課題にしっかり取り組み、その積み重ねが合格につながるのだと信じて、毎日一歩ずつ勉強に励んでほしいと思います。
ここで気を抜かないように!
以前お話したことがありますが、合格した生徒はくれぐれも気を緩めないでほしいと思います。
確かにこれまでの苦労が報われ困難から解放されたのだから、羽目を外したい気持ちも分かりますし、自分たちの努力に見合う分だけ楽しい思いをしてもいいと思います。
しかし、気をつけてほしいのは、これで全て終わりではないということです。
いや、むしろこれからが始まりなのだということ。
推薦や私立に合格し早々と受験勉強を終了した生徒によくあることなのですが、受験が終わったからといって完全に勉強を忘れてしまい、遊びまくる生徒がよくいます。
でも、このような人が高校に入ってから苦労します。
高校の勉強は当然中学の勉強が基礎となっているので、その中学の勉強を忘れてしまうと、高校の新学期が始まったとたん落ちこぼれてしまう場合が非常に多いのです。
中学のとき優秀で推薦入試を合格した生徒が、高校が始まると意外と振るわなくなるのは、このような事情があるからです。
そうならないためにも勉強の習慣は継続し、むしろこのゆとりのある期間をチャンスとして利用して、これまでの中学の勉強を充実させ高校の勉強を先取りし、より他の生徒に差をつけるくらいになってほしいと思います。
また、未だに多くの受験生は受験勉強に頑張っているので、彼らへの配慮もお忘れなく。
もし逆の立場だったらと考えれば分かりやすいと思います。
浮かれる気持ちは分かりますが、彼らへの敬意と配慮も十分にお願いします。










何はともあれ、生徒が希望する進路に進めることは非常に喜ばしいことであります。
みんな本当によくやりました。
これでこれまでの厳しい日々から解放され一息つけます。
とりあえず今日はゆっくり休み心も体も整えて、希望満ちる新生活に向かって新たな一歩を歩み出してほしいと思います。
このようにこれまで苦楽を共にしてきた生徒が自分の望みをかなえ、更なる人生に向かって進んでくれることが分かると、私自身の苦労も報われたような気がして嬉しくもあります。
皆さんは素晴らしい生徒です。
今後の皆さんの人生が輝かしいものになることを祈っています。
そして、非力ではありますが、まだ私にできることがあればいつでも遠慮なく相談してください。
いつでも力になる用意があります。






























2025.01.11
今日は鏡開き!飾ってあった鏡餅を食べて霊力を取り込み無病息災!

1月11日は鏡開きの日です。
これまでも折に触れて日本の年中行事についてお話してきました。
今回は「鏡開き」についてお話しようと思います。









正月になる鏡餅を飾る家庭も多いことと思います。
また、商店や会社でも福を呼び込もうと、鏡餅を飾っているところがたくさんあります。
ところで、鏡餅はいつまで飾っておくのがいいのでしょうか。
一般には鏡開きの日までと言われています。
地方によって多少差異はありますが、基本的に1月11日となっています。
鏡開きの由来
正月に神様をお迎えするとき、その神様が家での居場所として鏡餅を飾るようになりました。
だから、神様が鏡餅に宿っている間は餅を食べてはいけないのです。
カピカピになってひび割れてもグッと我慢です。
1月11日になってお餅を割って、神様をお送りしてから、神様の依り代となりその力を宿した餅を食べることによって、その力を授かることができると考えられています。
こうして新しい一年も家族が無病息災であることを祈るのです。
鏡開きの起源は戦国時代の風習によるそうです。
「具足祝い」と言って、正月に刀や武具の前に鏡餅を供え、それを下ろして食べたそうです。
ただし、この「具足祝い」は本来正月二十日にやっていたそうです。
しかし、三代将軍徳川家光が1月20日に亡くなったため、関東では11日に鏡開きが行われるようになりました。
鏡開きのやり方!意外と多いNG
鏡開きは、鏡餅を木槌や手で割ります。
伝統的な鏡餅であれば、正月から飾っている間に硬くひび割れていきますので、思ったより簡単に砕けます。
もし乾燥が不十分でなかなか割れないときは、鏡餅を半日ほど水につけ、電子レンジで温めて柔らかくしてから、手でちぎるという方法もあります。
このとき絶対にやってはいけないことは、刃物で餅を切ることです。
これは、もともと武士の風習なので、切腹を連想させる刃物を使うことはよくないとされ、手や木槌などで割るようになりました。
また、「切る」が「縁を切る」につながるともされ、包丁などで決して切ってはいけません。
「割る」という言葉も縁起が悪いとされるので、末広がりを連想させる「開く」という言葉を使います。
だから、「鏡割り」ではなく、「鏡開き」なのですね。
さらに、せっかく神様が宿って霊力をいただいた餅ですから、これを残すこともNGです。
有難い力をいただいて、一年の無病息災を祈るわけですから、たとえ小さなかけらと家でも残さず全部いただきましょう。
このように、意外とやってはいけないことが多いので、鏡開きのときは気をつけてください。
どうやって食べる?
こうやって鏡餅を開いて食べるわけですが、どのようにしてお餅を食べればいいのでしょうか。
普通は雑煮にして食べますが、魔よけの意味を持つ小豆と一緒にお汁粉にして食べるのも伝統的な食べ方です。
細かくかけらになったお餅は揚げて揚げ餅やかき餅にすると美味しいです。
塩だけでなく、いろいろなスパイスを試して味のバリエーションを楽しみましょう。
最近はお持ちのアレンジレシピも増え、ピザなど洋風の食べ方もお勧めです。









ということで、今回は「鏡開き」について話しました。
歴史のある日本では年中行事もたくさんあり、その由来や意味を知らべてみるのも面白いものです。
日本文化をより深く知ると同時に、家庭での楽しい思い出作りと、親子の交流のきっかけにもなります。
また、学習という点から考えてみると、年中行事は中学高校の入試試験で出てきたり、学校の授業の一環として話題になることもあります。
だから、年中行事を知り理解することは、教育という観点でも大事となります。
まだ家に鏡餅が置きっぱなしになっていませんか。
このように「鏡開き」について話し、子どもと一緒に餅を実際に割って、雑煮やお汁粉をいただいてみてはいかがでしょうか。
きっとお腹もふくれて、親子で楽しい時間が過ごせると思います。





































