塾長ブログ
2022.12.27
今日はクリスマス!ということで私の好きなクリスマスソングBEST1(完全趣味回)!
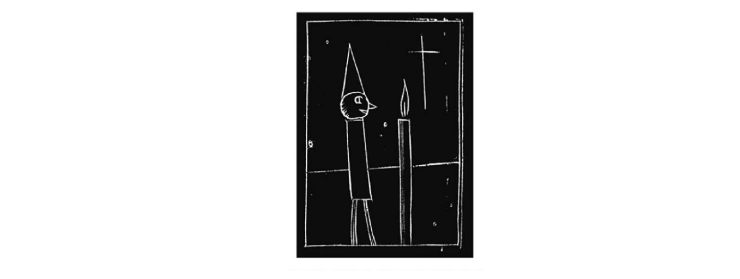
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
葛西TKKアカデミーではクリスマスでも勉強にいそしむ生徒たちがいます。
特に受験生は入試二か月前で追い込みに必死でしょうが、この聖なる夜にちょっと一息入れるのも悪くないと思います。
一息入れたら気分をリセット、気持ちをリフレッシュして、再び勉強に集中できるからです。
そこで今回は私の個人的にお勧めのクリスマスソングをご紹介!
この歌で全ての人の心が洗われたらと思います。
つまり、完全に私的趣味回です!









クリスマスはもう世界的イベントとなっており、日本でも社会全体でお祝いするのが恒例となっています。
大切な人との時間、そして愛する人への想いを分かち合い、クリスチャンでなくてもみんなで楽しくクリスマスを過ごす世帯がほとんどではないでしょうか。
日本にクリスマスが定着して久しく、今では当然のごとく毎年街全体がクリスマスに満ち溢れています。
そんな中でクリスマスソングも洋楽邦楽問わず毎年増え続け、今では数えきれないほどのクリスマスソングが存在しています。
そのような無限にも思えるクリスマスソングの中には皆さんそれぞれの思い入れやお気に入りがあり、そして中には特別な思い出が伴なって人々の心に深く刻まれたものもあるでしょう。
つまり、皆さん個人個人に特別なクリスマスソングがあるということです。
そんなクリスマスソングをお互いに分かち合い、その素晴らしさに触れ感動を共有するのもとても楽しいことではありませんか。
皆さんのスペシャルなクリスマスソングを教えていただけると嬉しいです。








前置きが長くなりましたが、いよいよ私の個人的クリスマスソングBEST1(変な日本語)発表です。
本当に悩みました。
メジャーなものからマイナーなものまで、昔のものから最近のものまで、そして日本のものから外国のものまで。
どれも甲乙つけがたい素晴らしいクリスマスソングばかり。
だから、ご紹介したい曲はたくさんあって、順位をつけることができず、今回は一曲だけにしました。
今回の選曲に関してのポイントは「隠れた名曲」です。
素敵なクリスマスソングなんだけど一般にはあまり知られていない、でも、心を揺すられるような楽曲です。
では、発表します。
私が選んだベストクリスマスソング(こっちの方が日本語的にもまし)は!
吉田美奈子さんの『CHRISTMAS TREE』!
これは吉田美奈子さんが1986年に出したアルバム『BELLS』に収録された一曲です。
吉田美奈子『BELLS』へのリンクはこちら
このアルバムは吉田美奈子さんが当時自主製作で3000枚という限定リリースしたアルバムで、当然今となっては入手がかなり困難なのですが、時折、ラジオから流れることもあります。
2002年に「もみの木」という曲が追加され、avexから再リリースされましたが、こちらも今は廃盤となっています。
2014年にもスペシャル限定版として発売されているようですね。
このアルバムの2曲目に収録されているのが、今回お勧めする『CHRISTMAS TREE』です。
クリスマスアルバムということで、全体にゴスペル調の重厚なコーラスが流れ、またそれに負けないくらい力強くも美しい吉田美奈子さんの歌声が、確かに私たちの心に何かを伝えてきます。
そして、後半の圧倒的な迫力で迫る荘厳なクライマックスはもう感動ものです。
これこそがクリスマスの持つ「祈り」の力ではないでしょうか。
大切な人、愛する人のために祈り続ける。
その行為の崇高さを私は感じ、心震えました。
皆さんはいかがですか。
「聞こえる?精霊の羽ばたきが
あなたにも微笑みかける
夜はもういつの日も素敵なChristmas
毎日が祈りときらめき
だから心込めて
Christmas treeに飾ろう」
(歌詞一部抜粋)
Merry Christmas!
素敵な夜を























2022.12.27
メリークリスマス!今日から葛西TKKアカデミーのHPがリニューアルされました!


今日はクリスマスでパーティーの家庭も多いことでしょう。
年に一度のイベントを心から楽しんでほしいと思います。
ところで、クリスマスという訳ではありませんが、葛西TKKアカデミーは本日からホームページが新しくなりました。

これまでの手作りホームページから大きく一新!
より見やすく分かりやすいホームページができました。
写真やイラストをふんだんに取り入れると同時に、入塾手続きや料金、授業内容など皆様が知りたい情報がしっかり詰まったサイトになっております。
そして、このサイトから葛西TKKアカデミーの目指す教育を理解していただき、現場の雰囲気も伝われば幸いです。

まだまだ不十分な点もありますので、より充実したホームページになるように、今後も引き続き改訂更新しながら、ブログも含めてホームページをアップデートしていきますのでご期待ください。







今回のホームページリニューアルに伴い、これまでまいぷれに掲載していたニュースを一部、ホームページへ移行することになりました。

まいぷれで過去のニュースが見れなくなっても、これまでのニュースは全てこちらの『塾長ブログ』から見ることができますので、ご安心ください。
まいぷれのページにも葛西TKKアカデミーのホームページへのリンクが掲載されていますので、是非、そちらからチェックしてください。







最後に、今回、葛西TKKアカデミーのホームページリニューアルに当たり、まいぷれのスタッフさんや塾生およびその家族、その他多くの方々にご協力いただき、誠にありがとうございました。
この素晴らしいホームページを生かして、より多くの人々が葛西TKKアカデミーを知っていただき、より多くの子供たちの未来を輝けるものにするお手伝いができればと考えています。
皆様の公私に及ぶご協力に感謝の意を表すると同時に、私自身もより良い社会作りに貢献できるよう、一所懸命に頑張りたいと思います。
これからも葛西TKKアカデミーをどうかよろしくお願いいたします。





















2022.12.27
言語習得の秘密が!”this・that・it”と”これ・あれ・それ”は同じではありません!
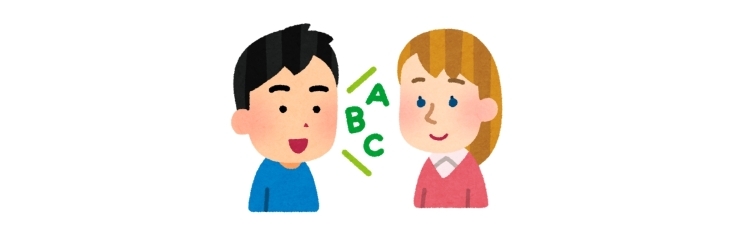
しかし、この教え方は必ずしも正確ではなく、後で分からなくなって混乱する生徒がたくさんいます。
英語の勉強のよくある誤解です。
辞書を調べるとthatには「あれ、それ」と書いてあり、itも「それ」と書いてあって、どうしてthatにも「それ」書いてあるのか、itとの違いは何か分からなくなった経験はありませんか。
今回はこのことについて説明したいと思います。








日本語の「これ・あれ・それ」
自分が話しているとき、自分に近く相手から遠いものを指すときは「これ」、自分からも相手からも遠いものを指すときは「あれ」、自分から遠く相手に近いものを指すときが「それ」なのです。
このように日本語では空間の位置関係を示すとき、自分(話し手)と相手(聞き手)を基準として「これ・あれ・それ」を使い分けるのです。
英語の「this・that・it」
英語の場合は自分からの距離で決まります。
自分(話し手)から近いものは「this」、自分から遠いものは「that」です。
では、「it」は中間かというと実は違います。
「it」はものを指しているのではありません。
「it」は先に出てきた語を指しているのです。
This is my book.
I bought it yesterday.
That is your book.
I didn't buy it yesterday.
このようにthisでもthatでも2行目ではitを使っています。
つまり、itは距離で決まるのではないのです。
これは前者では「my book」を指し、後者では「your book」を指しているのです。
ものそのものというよりは語(言葉)を指していると考えます。
以上のことを踏まえると謎が解ける!
「あれ」は自分からも相手からも遠いものを指す言葉、「それ」は自分から遠く相手に近いものを指す言葉。
だから、自分から遠いものを指すthatは「あれ」(相手からも遠い)にも「それ」(相手に近い)にも対応し、日本語の翻訳するときは相手との位置関係も加味して「あれ」と「それ」を使い分けないといけないのです。
また、itは距離とは関係なく前述の語(言葉)を指すと言いましたが、日本語の場合はその言葉との時間的距離関係で指示語が決まります。
時間的に近い時は「これ」、遠い時は「あれ」です。
「それ」は一般的に時間的距離に関係なく使える言葉で、だから翻訳のときは時間的距離を気にせず使える「それ」を採用しているのです。
つまり、英語の辞書に書いてあったthatの「それ」とitの「それ」は別物であったのです。
このように言語間の解釈の違いを正しく理解すれば言葉の使い分けも分かり、混乱することなく第二言語を学ぶことができるのです。
「第二言語学習は置き換え作業」という誤解
この「置き換え」が第二言語を学ぶことと勘違いしてしまう生徒がとても多いです。
よく「英語は単語さえ覚えればいい」という生徒がいますが、これは正にこの勘違いを象徴する発言です。
このように生徒が言うのは、第二言語習得が単なる言葉の置き換えではない点をしっかり正確に説明していない教える側の問題でもあります。
この誤解を生徒が真に受けて勉強を進めていくと、やがて彼らは「言葉の壁」にぶち当たり、置き換え作業では上手くいかない事実に直面し英語が分からなくなってしまいます。
言語を学ぶならconceptだけでなくnortionまで
同じ概念があったとしてもそこには当然ずれがありますし、時にはその概念すら一方にはない場合もあります。
これをconceptとnortionと言いますが、辞書を引くとどちらも「概念」書いてあるのではないでしょうか。
また、ややこしい話になっていますが、conceptとは社会や文化に関係なく人類が共通して持っている考え、そしてnortionとは個々の社会や文化に特有の考え、conceptの具体的な中身です。
例えば、「愛」という概念は人類全体が共有しているのでconceptです。
しかし、その「愛」が具体的に何を意味しているかは社会や文化で微妙に異なります。
男女の恋愛だけかもしれないし、親子や友人との親密な関係も含めるかも知れません。
同性や多彩な性別間でも成立するかどうかも、社会や文化で異なります。
このように一つのconceptに対してnortionは多様であり、言語を学ぶときはconceptだけでなくnortionまで理解しないといけません。
そして、自分の母語と比べnortionの違いまで知ることができれば、言葉を変換するときにそのずれを補正することができ、より正確なコミュニケーションと相互理解が可能となります。
二言語間の違いを把握して、対象言語の話者の考え方や社会文化まで理解する必要があるのです。
本来言語習得にはそこまで勉強する必要があるのですが、残念ながら学校教育ではそこまでするには限界があります。
だから、その限界を補って勉強しないと頭の中が混乱し訳が分からなくなるのです。
まあ、それも難しいのですが。








今回は英語の「this・that・it」と日本語の「これ・あれ・それ」の違いに注目し、言語習得の大事なお話をしました。
勉強は簡単ではありませんし手間のかかるものです。
でも、それを面倒と考えず新たな発見と考えれば、勉強に喜びや楽しみを見出すこともできます。
英語の勉強もそうで、暗記ばかりと考えれば辛くつまらないですが、より深く学びこれまで知らなかったことに気づければ学習者の世界も大きく広がります。
そして、言語は言語そのものから自分の世界を広げるだけでなく、今度は言語を使い自分の世界を更に大きく広げることができる強力な道具でもあります。
せっかく学校で学ぶのだから、単に英語の表層に留まるだけでなく、それを使って自分の視野を広げ、自身の成長に役立ててほしいと願います。





















2022.11.28
コロナウイルス感染者急増の影にインフルエンザも!受験生は特に注意!

先日、東京ではコロナウイルスの新規感染者が再び1万2000人を超えたそうで、再流行の兆しが見えます。
子供たちの感染も心配される中、受験生は特に注意しないといけません。
受験勉強が難しくなるだけでなく、入試そのものが受けられなくなる可能性もあるのです。
そして、毎年この時期はインフルエンザが流行り始める時期でもあります。
コロナウイルスにばかり目を奪われないで、より身近なインフルエンザ対策も重要です。
細心の注意を払ってウイルスをもらわないようにしないといけません。
コロナウイルスのおかげでマスクや殺菌用アルコールなどが普及し、一見、例年より予防がなされているようですが、それで油断してはいけません。
ましてや、コロナウイルスとインフルエンザの両方にかかってしまえば、免疫力の消耗に伴いより一層の重症化する恐れもあります。
とにかく、コロナウイルスに対してだけでなく、インフルエンザに対しても基本的な対策は最低限とらないといけません。
一般の生徒もそうですが、この時期一番注意しなければならないのはやはり受験生です。
できることは全てやって、万全の体制で入学試験に臨めるように頑張ってください。











コロナウイルス感染または濃厚接触者になると、インフルエンザと同様に一定期間はは自宅で療養または待機しないといけません。
これが受験日に重なると当然試験を受けることはできません。
これまでの努力が水の泡になってしまいます。
このようなことは絶対に避けなければなりません。
だから、少しでも危ないなと思えば無理をせず、早目に薬を飲んで安静にしましょう。
また、コロナウイルス感染の恐れがある場合は速やかにPCR検査を受けてください。
そして、ひどくなる前にお医者さんに診てもらいましょう。
コロナウイルスもインフルエンザも、感染してしまうとどうしようもなくなるので、常に自分の体調の管理に気をつけてください。
もちろん予防が一番大切です。











コロナウイルスやインフルエンザになってしまうと、とても大変です。
従って、予防が最も重要になります。
コロナウイルスやインフルエンザの感染対策として次のようなものがあげられます。
1.マスクをする
コロナウイルスもインフルエンザも感染予防の基本はマスクと手洗いです。
自分がインフルエンザにかかった場合はもちろん周囲の人間に感染させないためにマスクをする必要がありますが、例え感染していなくても、予防という意味でもマスクをしましょう。
コロナウイルスやインフルエンザには飛沫感染もありますので、マスクは口や鼻からウィルスを吸い込むのを防げます。
喉を潤す効果もあり、感染を防ぐ効果が高まります。
2.手洗いとアルコール殺菌
コロナウイルスやインフルエンザのもう一つの感染経路は接触感染です。
だから手洗いは非常に重要です。
ウィルスは水やアルコールに弱いので、これも有効な感染防止手段です。
外出から戻ったとき、トイレから出たときなど、こまめに手を洗いましょう。
また、とってやパソコンなど人が触れるところもこまめにアルコールで拭いて殺菌をするといいです。
3.3密を避ける
これまでそうだったように「密接」「密着」「密閉」の三つが重なるような場所は避けてください。
必要以外の外出は控え、人が多く集まる場所には行かないようにしましょう。
最近は規制も緩和され、多くの人々が外に出るようになりましたが、入試のことを考えると受験生は感染のリスクは極力抑えるべきなので、可能な限りは3密になるような所へは行かないでください。
4.生徒だけでなく家族全員が予防に徹する
子供の感染経路で一番多いのは家族からの感染だそうです。
よって、受験生を含む生徒たちだけが感染予防をしても、危険は十分には回避できないかも知れません。
親や周囲の大人も同様に、感染に対する対策を厳として毎日を過ごしてください。
特に受験生を持つ家庭では、子供が直接感染しなくても濃厚接触者になってしまうと通学もできませんし、場合によっては受験もできなくなってしまいます。
重要な時期だけに、周囲の人間が感染したというだけでも受験生に与える心理的影響は看過できないものとなるかも知れません。
心身ともに最高なコンディションで試験を受けてもらうためにも、大人も含めて感染予防に取り組まなくてはなりません。
5.加湿器などで湿度を上げる
インフルエンザウィルスは湿度に弱く、湿度が50%を超えると活性が落ちるそうです。
加湿器で室内の湿度を上げるとウィルスの予防になりますし、喉を乾燥から防ぎ潤いを与えるので、喉を守ることにもなります。
加湿器がなければ、濡れたタオルを干すだけでも違います。
6.やはり体力は重要
勉強で寝不足になると免疫力が落ち、コロナウイルスやインフルエンザにかかりやすくなります。
十分な食事を取らないで栄養が不足しても風邪にかかりやすくなります。
受験で忙しい時こそ、規律ある生活を心がけましょう。
健康な生活習慣を保ち、いつも十分な体力を確保していることがウイルスに対抗できる手段の一つになります。
5.適度に外出し日の光を浴びて軽い運動
感染防止とは言え部屋にずっといると気分が滅入ってしまい、精神衛生上よくありません。
外の空気を吸って、頭をスッキリさせるといいでしょう。
日光を浴びると免疫力も上がるし、軽い運動で血行もよくなりストレス発散になります。
ただし、人ごみに入ると風邪をもらう可能性があるので、不必要に人が大勢いるところに行くのはやめましょう。









コロナウイルスやインフルエンザにかかったなと思ったらすぐにお医者さんのところに行きましょう。
適切に対処して早く治し、再び勉強に取り組めるようにしましょう。
風邪の引き始めは水分補給とビタミンなどの栄養補給をしっかりしてください。
ワクチン注射をまだしていない人も、いないよりはましなので、今からでも受けた方がいいかも知れません。
ここは各家庭の判断にお任せします。
インフルエンザやコロナウイルスだけでなくどのようなことであっても、この時期に病気や怪我で勉強ができなくなることは受験競争から大きく後退することにつながります。
大変とは思いますが、先ずは自分の体調管理をしっかりして、その上で毎日の勉強に励んでください。




























2022.11.26
いよいよ日曜日は都立高校入試初のスピーキングテストが行われます
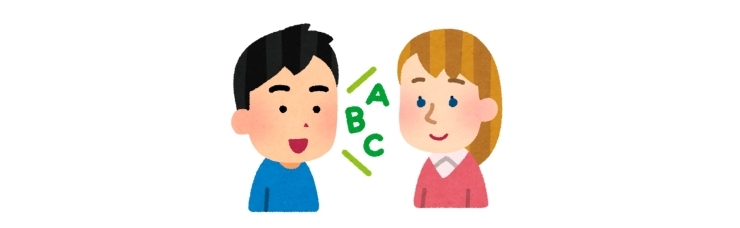
今度の日曜日はいよいよ都立高校の入試におけるスピーキングテストが実施されます。
賛否両論の中、もう行われるのは避けられないので、受験生の皆さんにはしっかりと準備していただき、最善を尽くしていただきたいと思います。
初めての試みなので、多くの人がどういうもので何をしてよいか分からないようです。
しかし、いきなりぶっつけ本番をやると絶対にうまくいきません。
よって今回はこのスピーキングテストがどのようなものか解説し、受験生の事前準備に役立てていただければと考えています。
是非、万全の態勢でテストに臨みましょう!









都立入試でのスピーキングテスト『ESAT-J』とは
東京都では都立高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加することになりました。
このスピーキングテストは『ESAT-J』と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します。
イメージとしては英検の二次試験の内容を対人ではなく、パソコンやタブレット端末などを利用して行う感じです。
試験内容
テストは四つのパートから成り、パートAは、カードに書かれた短い英文を読みます。
全部で2問あり、解答時間はそれぞれ30秒。
発声して答える前に30秒の準備時間があるので、この間に英文に目を通して、読む内容を確認したり、心の中で読む練習ができます。
本当に書かれてある英文が正しく読めるかどうかだけのテストです。
パートBでは図やイラスト、簡単な掲示物やチラシなどのビジュアルマテリアルを利用した問題になります。
全部で4問あり、そのうち3問はカードに関する質問に答える問題です。
解答時間は10秒で、その前に準備時間が10秒あるので、準備時間にできるだけマテリアルの内容を把握し、必要な情報がどこにあるかを確認できるといいです。
時間が短い分、質問に対する答えも簡潔なものになっているので、比較的答えやすいかもしれません。
例えばマテリアルを見ながら、明日の天気は何か答えるような問題です。
最後の1問はカードを基に受験生にミッションが与えられます。
自分の持っている英語力を駆使して、目的を達成するには何と言えばいいか答えなくてはいけません。
例えば、自分のほしい買い物をするには店員に何と言えばいいか答えます。
こちらも同様に、準備時間、解答時間共に10秒となっています。
パートCは4コマイラストの問題です。
この4コマのイラストを見て、英語で何が起こっているか答えなくてはいけません。
30秒の準備時間の後、40秒の解答時間が与えられています。
準備時間の間にどのようなストーリーかイラストから読み取って答えてください。
解答としては、各コマ一文ずつの英語で答えられるといいのではないでしょうか。
最後のパートDでは、質問が書かれたカードが与えられるので、それを読んで英語で答えます。
ここでは質問に対しての自分の意見とその理由が求められます。
例えば、「あなたが学校の一番好きな行事は何か、その理由も答えなさい」のような問題です。
こちらは準備時間が1分、解答時間が40秒となっています。
こちらも準備時間内で自分の意見をまとめておく必要があります。
以上が、現段階での試験内容になります。
例えばパートA、パートBは英検3級の二次試験に出てくる形式ですし、パートC、パートDは英検準2級以上の二次試験の形式になっています。
ただ、受けるのが幅広い学力差のある中学三年生なので、試験の難易度はかなり下げてあります。
これもコツさえ分かっていれば、それほど難しくないと感じています。
実施に当たっては、それぞれの決められた試験会場で、タブレット端末などにヘッドフォンマイクを通して音声を録音する形になるようです。
ESAT-Jの都立高校入試における評価法
ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。
試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。
この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。
評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。
そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。
送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。
つまり、調査書点に加えられるのですね。
その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。
これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。
・学力検査の得点
各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。
・調査書点
中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。
これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。
1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。
入試は1点で合否が分かれます。
だから、例え1点でも疎かにできません。
ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。
尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。
スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。










以上がスピーキングテストの説明になります。
誰もが受けたことのないスピーキングテストで、何もしないでいきなり本番にチャレンジするのは危険です。
不慣れな状態で危機の使い方も分からにようでは、試験中に操作でオロオロして実力は出せません。
事前に練習し、試験の内容と流れを理解して本番に臨んでください。
多くの生徒や保護者はまだ知らないことが多く、どうしていいか戸惑っていることと思います。
しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。
現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。
この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。
未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば問題ありません。
逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。
これまで1000点満点で決まっていた合否に、新たにスピーキングテストの20点が加わります。
たかが20点と侮ってはいけません。
この20点の差が受験生の合否を分けることはよくあります。
1点でも多く取れるように真剣に受験してください。
皆様のご健闘をお祈り申し上げます。




























2022.11.23
勉強or部活?部活を辞めて失敗する例

学校生活において勉強と同じくらい生徒にとって大きな問題が部活です。
勉強だけでなく部活に入ることで、単にその部活に関する技能習得だけでなく、様々な人と触れ合いから多くの人生に関する教訓を学べたり、学校生活における豊かな思い出作りができたりします。
学校の授業では扱わないような多くのことを知り、生徒たちの今後の人生に大きな影響を与えるようなこともたくさん学ぶ機会があります。
部活に参加しない生徒もいますが、部活にはそれなりの意義もあります。
しかし、そうした中で問題になってくるのが勉強と部活の両立です。
部活を頑張るあまり、肉体的にへとへとになり、家に帰ったときにはもうぐったりしてすぐに寝てしまう。
学校の授業中も居眠りして、教わることを聞き洩らしてしまう。
そんな状態をそのまま放置していると、勉強に手がつかなくなり分からないこともどんどん増え、結果的に成績が下がるという事態に陥ってしまう。
このような時に生徒や家庭の中には「部活を辞める」という選択肢を取る場合もあります。
それはそれで一つの問題解決の方法として悪くはないのですが、果たして辞めたからと言って上手くいくものではないということは注意しないといけない点です。
そこで今回は、勉強のために部活を辞めたけど上手くいかなかったパターン、デメリットをいくつか見ていきたいと思います。









1.部活を辞めても結局勉強しない
先ず、よくあるパターンの一つとしては、「やめたけど結局勉強しない」というものです。
部活があるうちは部活を理由に勉強から遠ざかっていたけど、いざ部活を辞めてその分時間ができても、結局勉強をしないということです。
いろいろな調査で学校の授業外の勉強時間を調べてみると、実はしっかり勉強している生徒は部活に参加していてもいなくても、ほぼ同等の勉強時間を確保しているという結果が出てきます。
つまり、勉強しないのは本当は部活のせいではないという事例が非常に多いということです。
勉強をやらない生徒は部活を言い訳に勉強をしないパターンが多いのですが、だからと言って部活がなくなってやらない理由がなくなっても、勉強しない生徒はやはり勉強しないのです。
部活を辞めでできた時間がゲームやSNSなど、本来の目的であった勉強に生かされないという結果に終わる。
これでは何のために部活を辞めたか分かりません。
むしろ、部活をやることで得ることのできた多くの事柄を放棄しただけになってしまい、生徒にとって何のプラスもありません。
このように部活で得られるメリットを諦めてまで勉強しようという覚悟がなければ、退部しても勉強せず何の効果もなくなってしまいます。
それならば部活を継続していった方が、むしろ生徒のためです。
ここでの失敗の原因は、本来生徒の勉強に対する考え方が問題なのに、それを部活のせいと決めてしまったことです。
2.毎日の生活に張り合いがなくなる
次のパターンは「部活を辞めて一つの目標がなくなり、毎日がつまらなくなる」というものです。
部活は練習が苦しかったり、時には人間関係で悩んだりもしますが、仲間と一緒に一つの目標に向かって日々頑張っていると、ある程度の充実感を得ることができます。
特に、試合などで少しでも結果が出れば達成感が生まれ、自分に自信がつき、その後の難局にも立ち向かう強さが身に付きます。
先生や監督、部活の先輩から次から次へと自分たちに指示が出され、何もすることがなくて暇だということは少なくなります。
しかし、部活を辞めたとたん、自分は何をすればいいか分からなくなり、部活中に得られた様々な喜びも消え、楽しいこともなく毎日を悶々と過ごさなくてはいけなくなる。
日々の生活に張り合いがなくなれば、当然勉強に対しての情熱もなくなり、結局、学校の成績も上がらないというパターンです。
このぽっかり空いた空白は生徒にとって結構大きく、喪失感は生徒たちを更に悩ませることとなります。
「何をしていいか分からない」「何をやっても楽しくない」「自分のやりたいことが見つからない」といった自分でもどうしていいか分からない感情が心の中に渦巻いてゆきます。
部活を辞めることで生じる、このような心理的作用は生徒に重くのしかかり、多くの場合「やめなければよかった」と後悔の念に駆られてしまいます。
3.人間関係が気まずくなる
部活を辞めても学校生活が終わる訳ではなく、その後も学校で部員たちと顔を会わせる機会はたくさんあります。
別に部活を辞めることは罪ではありませんから、そのことで部員たちから責められる筋合いはないのです。
しかし、やめ方によっては彼らとの溝ができることもあります。
これは事前にある程度想像がつくことではあります。
それでも部活を辞める決意をしたのだから、その後の人間関係がどうなっても受け入れる覚悟ができているはずですが、まだ人生経験の浅い生徒たちにとって実際はそう簡単なものではありません。
自分のわがままで退部したと非難されても仕方ないのですが、それを受け流すくらいの器量がある訳でもなく、生徒が退部を後悔する事例が多々あります。
例え非難されなくても、お互いにどう接していいか分からず、ぎこちない関係が続くことが多いでしょう。
これまで気楽に声を掛けたり遊びに行った仲間とうまく付き合えない。
日常何気なくすれ違ったり、視界に入ったりするだけでも、違和感をを持つようになりストレスも増大していきます。
部員だけでなく周囲の人間も自分によそよそしく感じられ、学校生活が非常に居心地の悪いものになってしまうかも知れません。
予想以上の気まずさに、やめなければよかったと感じる生徒も多いようです。
4.すべてにおいて逃げ癖がついた
部活は苦しい練習を耐え抜き、困難を克服して結果を出すことの大切さを学び、実際にそれができるようになる修行のような一面を持ちます。
粘り強さ、忍耐力、持続力、集中力、思いやりなど、今後の人生において重要な精神的成長を促す場でもあります。
しかし、部活を途中で辞めでしまうとこれらのことが身に付かないばかりではなく、何かにおいて「辞めればいい」という逃げの思考が根付いてしまいます。
その結果、何をやっても中途半端で、何一つ達成できない。
嫌なことに耐えられずに、すぐにあきらめ逃げてしまう。
このような人間になってしまったら、将来社会で生きていくときに大きな問題となります。
前向きな理由で辞めるのであればいいですが、単に苦しみから逃れたいだけの退部であれば、これはその生徒の人生を台無しにしてしまう決断と言えるかも知れません。








勉強と部活の両立は大変ですが、できるに越したことはありません。
しかし、もし両立ができず部活を辞めようと考えるならば、慎重に考えてください。
部活を辞めたとき、その後の自分に何が起きるかよく考えましょう。
そして、本当に退部が問題解決の決め手になるのか、他に方法はないのか吟味してください。
少なくともやめるならそれなりの覚悟がないと、自分にとってマイナスになることが多いですので気をつけてください。
学校生活において部活も勉強と同じくらい大事です。
学校生活の悩みなどあれば、それも葛西TKKアカデミーにご相談してもらったも構いません。
少しでも皆様の支えになれればと願っております。






















2022.11.15
都立高校の入試問題傾向と対策:理科編
2022/11/14

都立高校の入試問題を解説し対策を考えるシリーズも最後の理科となりました。
どの教科も同じですが、事前にテストの出題パターンを知り対策と練るのは、入学試験で高得点を取り合格するためには必須の条件です。
今回もこれまでと同じく、大問ごとにどのような問題が出るか考え、どのように対策するかお話したいと思います。








大問1
大問1は5~7問程度の小問題から構成されています。
それぞれが異なる分野から満遍なく出ます。
よって、毎年どの分野が出るか絞るのは難しいですが、どれも基礎的な問題ばかりなので、学校の教科書をよく見直して、学習事項の確認をしてください。
応用はほぼないので、基礎をしっかり正確に身に付けてください。
よって、ここの難易度は高くないので、ぜひ落とすことなく、できれば全問正解を目指してほしいです。
簡単だからと侮ってはいけません。
どの受験生もできるからこそ、ここでこけてしまうと受験競争で大きく後退してしまいます。
確実に全問正解を取るつもりで、緊張感を持って問題を解いてください。
意外と実験器具や操作に関する問題が出されます。
器具の使い方、実験で操作するときの注意点となぜそうしないといけないかという理由までしっかり押させてください。
大問2
大問2ではレポートの形で、身の回りの出来事に絡めて(そういう体で)問題が出されます。
問題自体は難しくなく、各分野から満遍なく出題されています。
知っているかどうかがカギとなる知識問題が多く、ここでも教科書をよく読んで、学んだことが正確に身に付いているか確認してください。
問題中にあるレポートは出題に向けた形式的なものであると同時に、文章の読み取りを誤ってしまうと、解答も間違えてしまう可能性がありますので、慎重に読み解く力も必要です。
基本的に選択問題で、語の組み合わせで答えが決まることもありますので、解答は難しくありません。
大問1と同様に正答率が高い所なので、できるだけ落としたくないパートです。
先ほども申したように、誰もが解ける問題群だからこそできて当然で、逆に落としたときのダメージは大きいので、確実に解けるようにこその充実に力を入れてください。
大問1と2だけで全体の4割近い点数になるので、ここで確実に正解し得点の底上げをしましょう。
大問3~6
ここからはそれぞれの大問で各分野に特化した問題がいささか深く問われます。
教科書などで基礎を固めたら、ワークや問題集の応用問題をしっかりやって、応用力を身に付けましょう。
記述問題も出ますが、よく授業中やテストで聞かれるような内容なので、練習問題をたくさんやれば頻繁に出てくるので、そのときにしっかり理解し覚えましょう。
他の教科でも言及しましたが、記述問題は部分点があるので、0点か満点かの他の問題と違って、書けば何かしら点数になるので必ず挑戦してください。
多くの受験生が面倒くさがってやりませんが、書き方に慣れてしまえばどうということありません。
むしろ、進んでやらない生徒が多いということは、そこをやれば他の受験生に対して差がつけられるということなので、合格を確かなものにするためにも是非やってください。
また、計算系の問題も出ます。
これは理科で習ったことを正しく理解していれば解けます。
特に割合や比、距離と速度などの計算にはなれておく必要があります。
ここでも応用レベルの問題練習をすることをお勧めします。
問題に慣れていないと、その場で解法を考え付くのは難しいと思うので、事前に多くの問題に触れて、様々な考え方、解き方に親しみましょう。








大問3~6はそれぞれの分野から出題されるので、各分野の勉強するポイントを簡単に触れていきます。
地学
大きく「火山と鉱物」「地震」「地層」と分けられるでしょう。
「火山と鉱物」に関しては火山の仕組みとそこからできる岩石の特徴を覚えることが大事です。
特に鉱物の種類は意外と聞かれることが多く、その組成から何色でどのような組織になっていて何という名前がついているかまで覚えておくといいです。
また、地震に関してはP波とS波の伝わる速度とそれに関連して震源の位置や地震の発生した時刻を答えさせる問題がよく出ますので、できるようになってください。
後、「震度」と「マグニチュード」の違いや「震源」と「震央」など紛らわしい概念にも注意してください。
「地層」はその位置からできた順を考え、更にそうなった環境の変化まで聞かれることがあります。
中に含まれる示準化石や示相化石から、それらが何を意味するのか覚えましょう。
気象
気温と飽和水蒸気量から湿度を求めたり、温度を下げることで露店からどれだけの水蒸気が水として発生するかなどの問題がよく出ます。
飽和水蒸気量の曲線を使った類題をたくさんやって考え方をマスターしてください。
雲のでき方と前線、気象のデータを使った天気の変化を問う問題が出やすいです。
温暖前線や寒冷前線の仕組みを理解し、天気図を見て日本の各地の天気がどのように変わっていくかが分かるようになってください。
また、日本を囲む気団の勢力変化が日本の季節にどのような気候をもたらすかも知る必要があります。
天文
太陽の軌道や見える星の日周運動および季節ごとの星座と地球、太陽の位置関係などがよく出ます。
特に内惑星(特に金星)の見掛けの変化はよく聞かれるので、頭の中で整理しておきましょう。
日食、月食に関する問題は出題率が高いです。
生物
消化酵素や神経伝達に関する実験がよく出ます。
それぞれの実験から何が分かるのか、なぜそのような操作をするのか、それらを比較することで何が分かるのか理解できるようになりましょう。
消化吸収の仕組みをよく理解してください。
同様に光合成と酸素・二酸化炭素、そしてブドウ糖の合成についての実験も出ます。
特にこの実験では使う指示薬を正しく覚えることが必要です。
循環器系では血液の流れる経路とそれぞれの地点における血液の特徴(酸素含有量など)を分かるようにしてください。
遺伝と発生では、メンデルの法則からどうしてそのような形質がその割合で出現するか説明できるようにしてください。
交配実験は比較的よく出る話題です。
他に動植物の体の仕組みと増え方、生物同士のつながりと生態系もきちんと勉強しておきましょう。
化学
化学は理科の分野の中でも出題率が非常に高いものの一つです。
実験と絡めた問題が多く、その実験も多岐にわたります。
必ず化学反応の仕組みを理解してください。
電気分解や参加などの実験の他に、イオンと電池に関するものも頻繁に出題されており、各電極に発生する物質が何か、どうしてそうなるのか理解しておかないといけません。
酸とアルカリの中和実験もよく出ます。
実験の結果から理由などを考えさせるだけでなく、実際に計算し数値を出させる問題も多く、比やグラフを上手に使って計算ができるように練習しましょう。
実験操作の手順や注意点に関する内容も理解してください。
記述で求められることがよくあります。
物理
物理も非常に出題頻度の高い分野です。
台車を坂から転がせて速さの違いを考えさせる問題はよく出ます。
同様に力の合成や分解、仕事の原理なども押させておきましょう。
慣性、作用反作用とつり合い、エネルギーの変化、特に運動エネルギーと位置エネルギーを問う問題や実験もよく勉強してください。
また、レンズと像に関する問題、音波とオシロスコープ、電気(電流・電圧・抵抗)と左手の法則の関する実験の問題も事前に繰り返し練習して解けるようになっておきましょう。








以上、理科の都立入試の問題を分析してみました。
出題パターンはだいたい同じで、出題内容も比較的ひねった問題は少なく、よくあるタイプの問題が多いので、過去問や都立入試の想定問題集などをたくさんやって、理科に対する理解を深めると同時に、問題の解き方や考え方を身に付けてください。
基本は教科書ですから、先ずはそこで三年間の学習項目の基礎を充実させてから、過去問などの類題に取り組んでください。
身近な事柄や自然現象に注意し、これまで習ったこととどのようにつながるか普段から考えていると、都立入試で出てくるような身の回りの出来事に絡めた問題も分かりやすくなります。
これで5教科分の傾向と対策は終わります。
これらを参考に受験勉強に役立てていただけるとありがたいです。
英語のスピーキングテストが目前に迫ってきています。
以前にもニュースで触れましたが、今度、こちらも再度まとめて書きたいと考えています。
今週が期末テストの学校も多いと思います。
特に受験生にとっては内申点の決まる大事なテストです。
ここで内申が上がると受験がかなり楽になりますので、ぜひ頑張って内申を1でも上げるようにしましょう。
特に実技4教科は、それぞれの評定が2倍になって内申点に計算されるので、5教科だけでなくこちらも手を抜かないで勉強してください。
それでは、皆様のご健闘をお祈りいたします。





















2022.11.14
都立高校の入試問題傾向と対策:社会編

都立高校の入試問題を扱う本シリーズですが、今回は社会です。
社会も好き嫌いが分かれる教科ですが、都立高校の入試問題はある程度パターンが決まっていますので、各大問ごとにそのパターンを検証し対策を考えていきます。
先ほど「好き嫌いが分かれる」と述べましたが、受験でうまくいくコツは苦手を作らないことです。
苦手教科はやりたくないから好きな教科ばかり勉強して、できる教科とできない教科がはっきり結果にも表れる受験生もいますが、そのような人は十分注意をしないといけません。
詳しくは別の機会で話しますが、受験では、「特に目立って良い成績の教科はないが悪い成績の教科もない」よりも「できる教科とできない教科がはっきりしている」の方が強いです。
要は平均を上げるということで、苦手教科ほど(嫌でも)勉強しないといけないということです。
少し話がそれましたが、それでは社会の各大問を見てみましょう。









大問1
大問1は地図を使った問題です。
地図をもとに、問題中の人物の歩いた経路を考えたり、ある地点から見える景色を写真の中から選んだりします。
重要なのは地図記号などをきちんと理解し、その地形を正しく掌握できるかどうかということです。
地図を見ながら、頭の中で情景を想像する力が必要です。
他に日本地理、世界地理、歴史、公民から基本的問題が2問出されます。
難易度は低いので、どの分野も教科書をしっかり読んで基本的な用語とその意味などをしっかり理解してください。
特に歴史ではその史実を知っているかだけでなく、起こった地図上の位置も聞かれますので、場所と合わせて覚えてください。
大問2
世界地図上の国に関する問いが出されます。
雨温図の都市を見つけ、それを含む国名を答えさせる問題が出ます。
雨温図の気温が凸か凹かで北半球か南半球かを判断します。
後は気温と降水量の特徴から都市を見つければいいのですが、それぞれの気候をきちんと把握し、世界地図のどのあたりが何気候かも分かっていないといけません。
次に各国の資料(生産量や輸出入量、出入国者数、発電量など)を見て、問題文に示されている国を見つける問題がでます。
各国の産業や社会状況などを理解し、特に各国のキーワード(羊といえばニュージーランドのような)からその国か判断できるようになりましょう。
消去法などを駆使して選択肢を減らしていけば、正解を見つけるのはそれほど難しくありません。
大問3
大問3は日本地理の問題です。
世界地理同様に、日本の地理的特徴を捉え、雨温図から各気候が分かるようにしてください。
そして、各地域の地理、産業、社会文化などの特徴を動的に理解し(時代の移り変わりに伴う変化)ましょう。
各都道府県の特産物や人口の特徴を、こちらも世界地理同様に、キーワードを中心に覚えましょう。
こうして、問題中の資料から要求される都道府県を特定できるようになってください。
また、提示された資料から理由を考えさせる問題では、資料が何を示しているのかをしっかりと明記し、そこからどうしてそのような事実が浮かび上がるのか、きちんと説明できる論理展開と表現力を身に付けましょう。
これは実際にたくさん書いて練習すればできるようになります。
他の問題もそうですが、資料を読み取って答える問題は、事前に覚えなければ解けない問題と違い、その場で読み取れさえすれば解ける(変化とその理由、因果関係を考える)問題なので、サービス問題です。
しかも、記述は自分の自由に書くことができるし部分点もあるので、記述問題は必ずやってください。
大問4
大問4は歴史の問題です。
文章が引用され、その中の一部ごとに関連した問題が出されます。
歴史的事件の起こった順番を問う問題、または、ある事実が年表のどの範囲で起きたかを問う問題が出ます。
ここは歴史的出来事をただ覚えるだけでなく、全体の流れを押さえましょう。
その時に、「○○が起きたから××が起きた」など、それぞれの出来事のつながりと因果関係が分かると覚えやすいし理解しやすいです。
そして、何時代の出来事か(多くの場合は細かい年まで覚えなくて、だいたいいつ頃で十分です)を覚えていれば、比較的答えるのは簡単です。
なぜか分かりませんが、江戸時代の政治改革は本当によく出ますので、順番だけでなく誰が何をしたかも正確に覚えましょう。
また、資料を使った記述問題も出ますので、地理と同じように資料をしっかり読み取り、それが何を示しているのか考え、そこから問題が要求する答えを上手く導き出してください。
繰り返しますが、部分点があるので記述問題は嫌がらずに必ず何か書いてください。
白紙が一番もったいないです。
大問5
対問5は公民の問題です。
憲法や人権、政治や経済とどの分野からも一通りバランスよく出されます。
歴史と同じく文章が出て、その中の下線部に関連する問題が出されます。
憲法や人権の基本的考え方、政治と財政の仕組み、少子高齢化問題と福祉、消費生活など、基本的な事柄をしっかり身に付け、実践問題を通して自分の実力が本当に発揮できているか確認してください。
よく分からなくなったら教科書やワークに立ち返り、何度も何度も確認し正確に理解しましょう。
「衆議院の優越」や「文化的で最低限度の生活」「三権分立」「戦後の日本経済の動向」「現在の国際情勢と日本への影響」など基本的なことがよく聞かれます。
大問6
最後は社会の各分野がいろいろと絡みあった総合問題になります。
オリンピックや自然災害などの実際にあった出来事から地理や歴史を絡めたり、国際社会や環境問題から地理や公民を絡めたりと、問題もかなり工夫されています。
地理的歴史的知識も必要ですが、大事なのはそれらをどのように組み合わせて考えることができるかです。
この辺りは単純に覚えるというより、それらの習得した知識をいかに活用して答えを導き出せるかという問題なので、実際に多くの問題に触れながら、多様な解き方や考え方に慣れておく必要があります。








以上、社会と見てきました。
社会は覚えなければならない用語が多く、そこが受験生も苦労する点ですが、入試に関してはそれだけではダメで、覚えた知識をいかに上手く使い、出題者の意図を読み取り答えられるかが重要になってきます。
また、覚える問題だけでなく考える問題もできるように練習し、特に記述問題は最初からあきらめずに、積極的にチャレンジしてほしいです。
書けば何かしら点数になりますから。
二学期の期末テストが終われば本格的に受験勉強一本となります。
苦しいとは思いますが、勉強がやればやった分だけの結果が出ます。
そんなに長い期間ではありませんので、何とか苦しみに耐え、試練を乗り越えて、来春には笑って新しい学校生活が迎えられるように祈ります。
応援しています。
頑張ってください。
助けが必要な時はいつでも遠慮なく、葛西TKKアカデミーにご連絡ください。
いつでも受験生の味方です。






















2022.11.10
TKKアカデミーの卒業生に再会!TKKはつながる!

葛西TKKアカデミーは小規模個別指導塾であり、これまで何人もの生徒がここで学び、卒業していきました。
諸事情あり、一筋縄ではいかない生徒たちばかりでしたが、小規模個別指導塾ならではの親密で信頼感のある関係を築くことができました。
どの生徒もかなり苦労させられましたが、今となってはいい思い出でもあります。
単純な勉強指導だけにとどまらず、時には親子ともども悩みを聞いたり、時には提出書類の作文を見てあげたり、時には生徒たちのイベントや発表に出席したり。
塾の中だけでなく、いろいろな場面で関わることができました。
別に何かの計算があってとかではなく、純粋にそうしたい、そうした方が相手のためになると思ったうえでの行動でした。
彼らと本気で関わったからこそ、熱意が伝わり、そして、苦楽を共にした間柄だからこそ信頼ができ、その後もつながりが絶えません。
最近ちょっと、昔の生徒と再び関わることがあったので、少しお話したいと思います。









小学生だったあの生徒がお母さん!
長いことこの仕事を続けているとびっくりすることが沢山あります。
先日、道端で偶然、ある卒業生に会ったのですが、彼女は小さな赤ちゃんを抱いていました。
この生徒は小学生の時から高校生を卒業するまで、ずっと指導をしてきた生徒でした。
小学生の時からK-popにはまっていました。
当時はまだK-popと言っても今ほど普及してはおらず、ブームのはしりのはしりでした。
彼女から韓国のアイドルの話を聞き、ときにはDVDを借りて聞くこともありました。
このように彼女は先見の明に長けており、常に流行の先端を走っていた感じでした。
高校生になればJKとして、ナイトプールの話をしてくれたりと、こちらの方もたくさん教わったものです。
小学生の時、彼女からもらった年賀状は私の宝物の一つです。
高校卒業して進学するのかと思えば、美容の勉強がしたいと専門学校へ。
大学進学を考えて小学校からエスカレータ式の私立学校へ通わせていた親は驚くと同時に、それでも彼女の気持ちを尊重ようと、入学を許してくれました。
専門学校が終わっていよいよキャリアを積み上げるかと思った矢先、何と妊娠し結婚するという話を聞きました。
私もびっくりですが、理解ある親の助けもあり無事出産したと報告を受けました。
そして、先日塾の近くを歩いていると、偶然彼女に出会いました。
腕の中には小さなかわいい命が。
本当に生まれて間もなく「小さい」という印象が強く、親に似て目のパッチリとした男前さんでした。
自分も娘が生まれたときを思い出してしまいました。
以前、お父様(赤ちゃんのおじいさん)が写真を見せながらニコニコ、デレデレしながら話していた顔を忘れません。
出産前にわざわざTKKを訪ねてくれて、妊娠と結婚の報告を受けました。
小学生のイメージが私には残っているので、少し変な気分でもありますが、いつの間にか時は過ぎ、こうやって世代は移っていくのだなあと感じたものです。
実は次の日には身近なものだけで結婚式を挙げるそうで、出産が終わって一段落したのでちょうど良いと思いました。
最後に「大きくなったらTKKで勉強しようね」と言うとにこっとしてくれたのが何とも微笑ましかったです。
普通の子より感性が強く、自分をしっかり持っているので家族ともぶつかることも多かったですが、不思議と私には素直で、いろいろな話をしてくれ、私の言うこともよく聞いてくれました。
ある意味波瀾万丈という形容が似合う生徒ですが、その分しっかりとした考えを持っていて、立派な女性にに育ちました。
以前、少し夫婦の会話を聞きましたが、彼女が本当にしっかりして、旦那様も尻に敷かれるところようにも見えましたが、多くの経験を積みいろいろなことが考えられる子なので、いい家庭ができるのではないかと楽しみでもあります。
本当に長い付き合いで、これは彼女に限ったことではあらいませんが、家族全体で仲良くさせていただいているのは、とてもありがたいことです。
いつも前向きで、自分の夢に向かって進む彼女がアイドルに!
最近、別の生徒からも連絡がありました。
彼女は本当に頑張り屋さんで、自分の大好きな演劇に非常に熱心で、将来は舞台で役者になりたいと言っていました。
高校もいろいろ悩みましたが、引き続き演劇部に入り、卒業してからも演劇のレッスンを受けたり、関連の仕事をしていました。
進学やいろいろな募集時の志望理由を書いたり、面接でどう受け答えするかなど、その後もいろいろな場面で頼ってくれて、本当に信頼してくれていると感じ嬉しかったものです。
在籍中も彼女の舞台発表があるたびに足を運んで見に行ったものでした。
彼女に限らず、何か生徒たちの発表会や演奏会などがあれば、喜んで行きました。
生徒たちの頑張る姿を見たいし応援したいから。
そして、毎回、生徒たちの完成度の高さに驚き、心から楽しむことができました。
そして、先日久しぶりに連絡を取り、事務所を変わって、今は小学校の頃からの夢だった「アイドル」として活動していることを知りました。
ちょっと前、仮面ライダーの映画のエキストラとして出演していたと聞き、「本当に自分の信念に従ってやりたいことを頑張っているなあ」と感心したのですが、今度はアイドルと夢を追い続け努力する彼女に敬意を表するばかりです。
まだゆっくりと話はできていませんが、いろいろと忙しそうです。
しかし、自分の好きなことであれば、どんな困難でも立ち向かえるし、彼女は心の強い女性ですから、自分の納得のいく人生を歩んでくれると信じています。
と言っても、人生何が起こるか分かりません。
時には自分の手に余る絶望的な事態が待ち受けているかも知れませんが、そんな時はすぐにTKKを思い浮かべてほしいです。
ここには本気で応援し、支えようと思っている人がいることを忘れないでほしいと思います。
今日もイベントがあるようですが、残念ながら今回はテスト前ということもあり、どうしても外せないので行けませんでした。
しかし、代わりに私の家内と娘が行くので、盛り上がってくれることを期待します。
また別のイベントが催されるときは、今度こそ生きたいと考えています。
夢に向かって進み続ける人は素敵です。









他にも書きたい卒業生はたくさんいるのですが、今日は長くなりましたのでここまでとします。
卒業後もつながり、お互いに連絡を取り合い、近況報告を聞いたり協力をしてもらったり。
その時々でみんながそれぞれなりに頑張り活躍する姿を見るのは非常に光栄なことであります。
葛西TKKアカデミーは人間の関係を重視します。
出会えた人々を大切にし、ずっとつながり支えあえればどんなに素晴らしいことでしょう。
有難いことに塾だけの関係にとどまらず、塾外でも様々な場面で生徒やその家庭と関わらせていただいています。
お陰さまでこちらもいろいろ助けてもらうことがあります。
このような人と人のつながりに支えられて葛西TKKアカデミーは成り立っています。
多くの方々に心から感謝いたします。






















2022.11.08
今日は珍しい皆既月食!理科でも習いますが自然の神秘を実感しましょう!

ご存知ですか。
今日は皆既月食が起きます。
このニュースを読むころには、この天体ショーが終わっていないことを祈るばかりです(事前に書くのを忘れていました、すみません。 )
)
今日は、本日の大イベント、月食についてお話します。








非常に稀な天体ショー
通常よく見られる月食は部分月食で、月の一部が地球の影に入り暗くなる現象です。
しかし、今日の月食は珍しい皆既月食で、月の全てが地球の影に入って暗くなります。
前回の皆既月食が2014年10月8日、次回が2235年6月2日ということで、十年に一回くらいの頻度になるでしょうか。
今日は天気も良いようなので、是非外に出て自然の神秘に触れてみてはいかがでしょうか。
今日の月食は18時9分に始まり、19時16分に皆既月食となるそうです。
そして、20時42分まで続き、21時49分に月食が終わるらしいです。
東京では、月が東の空やや低いところから次第に高く昇っていくときに見られ、全過程を肉眼で観察できるそうなので、可能であれば最初から終わりまでしっかり観察してください。
東京では街明かりが明るく、高いビルも多いので観測しにくいかもしれませんが、めったにあることではないので、是非、観測に適したスポットを見つけてほしいです。
後はタイミングよく雲が出ないことを祈るばかりですね。
しかも、今日は月食だけでなく「天王星食」も起きるというおまけつきで、プレミアム度が更に増しています。
今回の月食の最中に月が天王星を隠す「天王星食」も同時に起こるそうです。
月が他の惑星を隠す「惑星食」も珍しい現象で、この二つの「食」が重なるというのは大変稀なことらしいです。
調べてみると、前回、月食中に惑星食が起きたのは1580年7月26日で、この時は月食と土星食が同時に起きたそうで、実に442年前のことになります。
また、次回、月食と惑星食が同時に起こるのは322年後の2344年7月26日で、これも土星食らしいです。
因みに「皆既月食×天王星食」と限定すると、計算するのも非常に困難なくらい貴重な現象のようです。
とは言え、天王星を肉眼で観測するのは困難で、天体望遠鏡が必要となるでしょう。
それでも、目の前の月食を愛でながら、実際には見えないが現実に起こっている天王星が月に隠れる様子を想像してみるのも一興ではないでしょうか。
季節は秋ですし、風流を楽しむにはいい季節です。










月食とは
ここで簡単に月食について説明します。
太陽と地球、そして月が一直線上に並び、地球の影に月が入って、月の表面上に地球の影が落ちてできる現象です。
日食と違って影が月を隠しているので、暗いところとの境界線ははっきりとはしておらず、陰に隠れてもぼんやりと月が赤っぽく見えます。
なぜ、赤っぽくなるのでしょうか。
先ほど述べたように、日食と違い月食は何かもので月そのものが遮断されて見えなくなるのではなく、地球の影が月にかかるだけです。
陰の中と言えども月の影形は一応目に届きます(遮るものがないので)。
また、太陽からの光も、地球大気を通過する際、わずかに屈折し月を照らします。
その光が反射し、月食中であっても月の姿を薄く照らして、我々の目に届けてくれます。
ただし、波長の短い光(青など)は大気を通るときに散乱してしまい、散乱しにくい波長の長い光(赤など)だけが届くので、月が赤っぽく見えるのです。









自然を愛でる心と意義
日食と月食は中学校の理科の時間に扱われる項目で、当塾でもよく説明します。
しかし、机上の勉強では実感もなく、興味もわかないかもしれません。
このような天体ショーを自分で目撃すれば、きっと何か感動で心に残るものがあるはずです。
このような特別なイベントに限らず、日常においても身の回りのちょっとした自然に目を向けてください。
少し気をつければ、知の感動は日常にあふれています。
何気ない見過ごしていたものに、何か新発見があるかもしれません。
そうでなくても、純粋に花をめでたり、昆虫や動物の不思議さに触れることができれば、もっと知りたいという意欲がわきます。
このように自身の経験が学校の授業と結びつくと、勉強はもっと楽しくなります。
これは理科に限ったことではありません。
どの教科も自身の経験とつながったとき、それは現実のものとなり、より強く心に刻まれ理解も実感を伴って深まります。
大事なのは発見し、実感し、想像することです。
そうして思いを巡らせ、自分なりの解にたどり着いたとき、人間の知的喜びは最高潮になります。
このような経験を沢山すれば、知的好奇心も高まり、勉強が楽しくなるはずです。









個別指導塾葛西TKKアカデミーは常に生徒たちが楽しくなる授業を心がけています
つまらなくならないように、いろいろ工夫します。
勉強は苦しみではなく、喜びなんだと思えるように努めています。
このように知的好奇心を刺激することは、ちょっと工夫すれば家庭でもできるのです。
親子が一緒に何かする。
料理でも工作でもハイキングでもいい。
不思議だなと思えることはたくさんあります。
どうか皆さん、そのようなチャンスを逃さず、答えを教えるのではなく一緒に考え話し合ってみてください。
そうすれば子供はどんどん学びに飛び込んできますから。
今日は文字通り天文学的数値の滅多にない天体イベント。
この機会を逃さず、貴重な貴重な夜をお楽しみください。
そして、家族で知的好奇心を刺激してみてください。

























