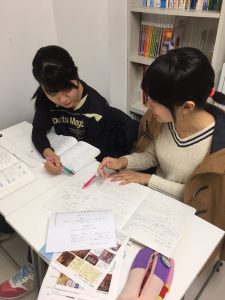塾長ブログ
2016.12.09
またお花をいただきました
2016.12.07
高校生頑張っています
2016.11.23
紅葉狩り
11月20日、高尾山に家族と紅葉狩りに行きました。
当初は筑波山に行くつもりでしたが、当日マラソン大会のため通行止めで行けないとわかり、急遽変更です。
晴天で、気温もこの時期としてはとても暖かだったので、想像はしていましたが、行ってみると予想を超える混雑でした。
ふもとから山道まで人がいっぱいで、ケーブルカーも70分待ち。
歩いて行った方が早いです。
海外からの観光客も多く、本当に山の中かと思うほど。
きっと渋谷や新宿と変わらない混み具合です。
紅葉はかなり進んだ木もあれば、まだの木もありました。
6~7分くらいでしょうかね。
小さい子を連れての山歩きは大変、途中で疲れて抱っこして登るはめになりました。
しかもこの混雑、足元は湿って滑りやすく、きっと明日は筋肉痛ですね。
何とか中腹まで登りました。
山からの風景はこんな感じです。
都会の街並みが小さく見えます。
久しぶりの山登り、自然に抱かれ、少しは気分もリフレッシュできたでしょうか。
この大混雑と小さいのを連れていること、それから時間を考えて、山頂に行くのは断念しました。
また次回、人が少なく時間に余裕があるときにもう一度チャレンジです。
子供は疲れて、下山では抱っこしたままぐっすり寝てしまいました。
頭をぐらつかせながらスヤスヤです。
久しぶりの家族サービスは大変でしたが、思い出に残る一日でした。
2016.11.02
「意味あるの?」
先日、ある生徒が「こんなに模試をやって意味あるの。」と言っていました。
やりたくない気持ちを疑問に転嫁して何気なく放った言葉だと思います。
こうして自分の気持ちに正当性を与えようとしたのでしょう。
果たして「意味」はあるのでしょうか。
物事には本来意味はありません。
ただ人間は全ての事柄に意味を見出さずにはいられない生き物だと思います。
「私は雨女だから・・・」
その人が雨を降らすわけないのだから、その人と雨の間には何の関係もありません。
しかし、そこに意味を付けて、いろいろな言い訳にしたり、話題を広げたりします。
人が意味を持たせたのです。
よくあるニュートンの逸話(本当かどうかは疑わしいですが)もそうです。
リンゴが落ちることそのものに意味はありません。
しかし、そこに意味を見出そうとして万有引力の発見につながるのです。
つまり、人類の発展にも「意味づけ」が大きな力を持つのです。
話は戻って模試もそうです。
ただやって終わりでは大した意味はないでしょう。
他のことをやった方が有意義かもしれません。
しかし、ただやるだけではなく、分からなかったところを見直し、理解し、自分の知識・学力向上のきっかけとするならば、それは意味あることです。
勉強もそうです。
ただ問題を解くだけでなく、そこから最大限に何を学べるか考え、積極的に学習すれば、それは大きな意味を持ちます。
以上のことから結論として私が言いたいことは、「意味」はそこあるのではないんだということ。
自分たちが何にでも積極的に見出していかなければならないんだということです。
つまり、「意味」があるかないかは本人次第なのです。
2016.10.26
スケジュールカレンダー開設
やっとスケジュールカレンダーができました。
思っていたより苦労しました。
このホームページは自分で全て作っているのですが、知識のない素人がやると大変ですね。
おかげでブログの更新もなかなかできませんでした。
これからは以前のように、より頻繁に更新していくつもりです。
さて、スケジュールカレンダーですが、その日の授業の確認ができます。
生徒の授業がいつあるか一目でわかりますし、どの時間が空いているかもわかるので、時間変更や追加授業の場合は参考になります。
また、通常授業以外に模試や特別授業、学校の定期テスト等の情報も提示します。
以上、いろいろ便利になっていますのでご活用ください。
スケジュールカレンダー
是非登録して、いつでもチェックできるようにしてください。
よろしくお願いします。
2016.10.26
季節の変わり目
夏が終わりもうすっかり秋。
そして冬の足音も聞こえてくる今日この頃です。
昼間暖かいと思ったら、急に朝晩冷え込んだりして、大人のみならず子供たちも体調を崩しがちです。
特に受験生にとって健康管理は大事です。
寝るときは暖かくして風邪を引かないようにしましょう。
病気になると何もいいことはありません。
勉強も大切ですが、健康であってこそです。
くれぐれも体をご自愛ください。
2016.10.16
葛西まつり
2016.09.20
「凡ミス」、「普通に○○」
最近、生徒に限らないかもしれませんが、気になる言葉があるので触れてみます。
テストの後、「凡ミスばっかりしちゃった。」
遅刻してきて、「普通に遅刻しました。」
どうして宿題やってこなかったかと聞くと、「普通にムリ。」
「凡ミス」といっても、だから減点が免れるわけではないし、遅刻やムリなことは「普通」ではありません。
言葉自体、どことなく矛盾をはらんでいるように聞こえます。
それでも生徒は平気でこれらの言葉を使います。
これらの言葉の背景にはどんな心理があるのか考えてみます。
「凡」も「普通に」も当然、仕方ないことというニュアンスがあるのではないでしょうか。
「だから、これ以上議論しても仕方ない。」
「この問題について話し合うのはもう終わり。」
「自分が悪いのはわかっているけど、もう責めないでほしい。」
という気持ちの表れではないでしょうか。
単純に本人の心の弱さのせいと結論付けてもいいのですが、問題は別にもあると思います。
このような思考は、自己弁護と責任回避のために現実が直視できず、現実への分析と対応ができなくて、人に言われるまで行動ができなくなってしまっていることこそ懸念すべきではないでしょうか。
重症になると、たとい人に指示されても、先ほどの自己弁護と責任回避が再び現れ、結局行動ができなくなる。
本人も現状が悪いことはわかっているし、対策を講じなければならないのもわかっている。
それでも動けないのです。
では、どのように生徒に対応すればいいのでしょうか。
正直、「分かりません。」というのが今の私の答えです。
ただ、これは個人の原因というより社会的風潮、環境の問題ではないのかという気はします。
社会という大きなシステムが、子供たちをそうさせているのではないでしょうか。
子供に限らず、大人もそうなのかもしれません。
この問題の因果についての考察は別の機会に話したいと思っています。
皆さんの貴重なご意見等、聞かせていただけると幸いです。
2016.09.17
緑のカーテン ザ ファイナル
2016.09.06
中間テストの勉強
中間テストが近づいてきました。
勉強の方ははかどっていますか。
定期テストのポイントは二つ。
まず、提出物は必ず終わらせ、期限を守って出すようにしましょう。
これが成績に直結しますし、出せば評価してもらえるのでお得です。
計画立ててやりましょう。
できればテスト前まで待たず、学校で習ったときにその範囲をした方が、余裕を持って勉強できます。
もう一つは、教科書、ワーク、ノートをしっかり繰り返し確認しましょう。
定期テストは授業の内容が出るので、基本的にこの三つを確実に見直して内容を把握していれば大丈夫です。
他の問題集などをやる前に、学校の教材をやって、授業でやったこと、先生が話したことを思い出しながら勉強するといいでしょう。
そして余裕がある場合にのみ、問題集などで確認、演習をして力を伸ばしてください。
時間はあまり残されていませんが、以上のことに重点を置いて勉強しましょう。
分からないときは遠慮なく葛西TKKアカデミーで質問してください。
全力でサポートします。
塾生でない方も、この機会に当塾を体験してみてください。