塾長ブログ
2022.09.13
中高生のスマホ活用術!スマホは便利な道具でも注意も必要

子供たちを囲む環境は、私たちがそうだったころとは大きく違います。
当時なかった技術や考え方が登場し、今までの方法が通用しない場面が多々あります。
その代表的なものがスマホです。
スマホは便利な道具です。
道具だからこそ、それをいかに使うかで私たちの生活は大きく左右されます。
それは生徒も同様です。
スマホの弊害も多く指摘され、時には子供たちが犯罪に巻き込まるという大きな危険性をはらんでいます。
しかし同時に、うまく使えば今までにない便利な道具で、私たちを大いに助けてくれます。
生徒たちと話をすると、彼らがいかに上手にスマホを活用しているかが見えてきます。
1.勉強で分からないことを調べる
勉強で分からないことがあれば、以前は教科書で調べ、それでも分からないときは人に聞くしかありませんでした。
でも、聞く相手がいないときは分からないままにせざるを得ませんでした。
今はインターネットで何でも調べられます。
英語の単語はもちろん、言葉の意味、時には問題の解法まで分かります。
葛西TKKアカデミーの生徒たちもよくスマホを使って調べています。
そのこと自体は議論の余地がありますが、自分で問題解決できる一つの手段を手に入れているのです。
2.友達同士で質問
lineなどは時と場所を選ばす多くの友達とつながることができます。
それを利用して、生徒たちはお互いに分からない問題を質問しあっています。
分からない問題をline上に流せば、誰かが答えてくれる。
このネットワークを利用してテスト勉強や宿題をやっている生徒はたくさんいます。
3.情報交換と収集
同様に勉強以外の情報交換も活発です。
例えばテスト範囲が分からないとき、lineで流せばメッセージを読んだ誰かが教えてくれます。
授業で聞き洩らしたこと、進路で分からないこと、色々な情報が行き交っています。
また、授業で黒板に書かれたものを撮ったり、友達のノートを撮ったり。
こうやって生徒たちは必要な情報を友達から入手するのです。
4.写メなどを使って簡単に記録
写メや簡易メモ機能を使って、様々なことを記録します。
勉強や授業のことはもちろん、課題の内容や予定など、スマホで簡単に記録し、必要な時にみることができます。
私の時代は、もしメモや配布されたプリントをなくしたしまったら絶望的になり、もう一度先生に申し訳なさそうに聞くしかありませんでしたが、今の生徒たちは先ほどの情報交換ツールを使ってこれらの記録を手に入れられるので、割と気楽です。
5.交友関係の拡大
今の生徒たちは簡単に人的ネットワークを広げられます。
以前驚いたのは、進学した時に入学以前の登校時にメールアドレスなどを交換し友達になることです。
一度会って相手のことはよく分からないのに、とにかくその場でアドレス交換をし登録するのです。
彼らにとって、この人脈作りは死活問題のようで、情報交換ができなかったときは不安にさいなまれるみたいです。
「もうみんなグループを作ってしまって、自分はその中に入る機会を逃したから、学校生活はずっと独りぼっち。」と入学前や新学期前から心配していました。
私からすると学校が始まる以前に友達になるのも驚きですし、学校生活が始まれば嫌でも一緒になるわけだから、自分が心がければ一人にはならないと思うのですが。
彼らはそうは考えないようです。









他にもいろいろあるようですが、今の生徒たちはそれなりにスマホを利用することも知っています。
上記の事例を見ると、何か他力本願のようで一人では何もできまいのかと思いますが、それができる時代だからそうなるのでしょう。
先に触れたように犯罪や架空請求、依存性など問題も多くあります。
大事なのは新しい環境に適応し、その利点を最大限に発揮し、危険性を最小限に食い止めるリテラシーです。
スマホは道具なので、良くも悪くも使う人次第です。
生徒たちとよく話し合い、自分たちに有益になるよう使っていただきたいと思います。




























2022.09.12
部活をやっている生徒は受験に有利or不利?!

部活をやっている生徒の親御さんから、「自分の子供は部活で忙しく勉強の時間も他の子より少ないけど大丈夫なのか」とよく相談を受けます。
「部活をやると勉強が疎かになるから入試でいい学校に入れない」と言って、部活に参加することをよく思わない人もいます。
果たしてどうなのでしょうか。
本当に部活は勉強にマイナスなのか、部活をすると勉強ができなくなるのか考えてみましょう。










部活は受験にプラスorマイナス
結論から申し上げますと、部活は受験に直接かかわらないので、部活をやっていれば受験に有利ということはありません。
都大会や全国大会で優秀な成績を修めたのならば、総合所見や部活動の記録において触れられるかも知れませんが、これもスポーツや芸術系の推薦を受けるのでなければ、一般入試においてさほど合否に影響を与えないと思います。
部長、副部長経験者も記録はされますが、合否判定の評価にはなりません。
一部私立高校の入試で内申点に「1」加算されることもありますが、部活をやって記録を残して「1」得ることと、部活よやらず勉強に集中して内申点を多く上げることを考えると、受験という範疇に限って言えば、後者の方がずっと効率がいいように思えます。
部活動などによる内申点への加点はあくまでも「おまけ」と考えて、部活を頑張ってこれで合格を勝ち取ろうとは夢にも思わないでください。
部活にかける時間、エネルギー、費用があれば、その全てを受験に回した方が受験には有利です。
なぜなら、部活は直接入試の合否に関わらないからです。








では、部活は受験において無意味でしょうか。
これに関しては、大きく次の三点から否定できます。
1.受験への間接的な効果
受験が中学で学んだ知識量のみで合否が決まるのならば、部活動に時間を費やすことは入試で合格する妨げになるだけかも知れませんが、残念ながら受験はそんなに単純ではありません。
精神的に未成熟な中学生では、特に精神が受験勉強及び入試に与える影響が非常に大きいのです。
部活は生徒たちの心の成長に大いに貢献します。
受験勉強は非常に苦しくつらいものです。
時にはその苦痛から逃げ出したくなることもあります。
そんな時、部活でつらい練習を耐え抜いた経験があれば、受験勉強の苦しみも乗り越えることができるでしょう。
この忍耐力は部活をしている生徒の方が一般的にあると言えます。
受験のストレスやプレッシャーに打ち勝つことのできる強い心が育ちます。
また、効率のよい勉強をするには集中力というものが不可欠です。
これも部活を通じて養うことができます。
自分の最高のパフォーマンスを引き出すために、ここ一番で集中力を高める。
いい例がオリンピック選手です。
学生のオリンピック選手もいますが、その多くが学業においても優秀な成績を修めています。
これは自分のやるべきことを受け止め、短い時間に集中して勉強しているからです。
最後に目的に向かって必要なノルマを自覚をもってこなしていける責任感も部活から身に付けることができます。
受験勉強には自分に足りない勉強を一つずつこなしていくことができないといけません。
自分のやるべきことをきちんとできるのも受験勉強に必要な要素です。
忍耐力、集中力、責任感というのは入学試験を受けるときも同じです。
試験を受けている最中でもこれらが切れてしまえば、自分の力を100%発揮することはできません。
このように部活は、英単語を覚えたり方程式が解けるようになったりと直接受験勉強に役立ちはしませんが、受験勉強と合格をより確実にするための要素、勉強の土台としての要素を養うのに非常に有益です。
実際に部活をしている生徒は、それまで成績がいまいちでも、部活引退後急激に成績が上がることが非常に多いです。
それは部活を通じて勉強に必要な精神が育っているからだと言えるでしょう。
2.充実した生活への効果
更に、部活をすることで日々の生活を充実させることができます。
運動をした方が精神的安定も生まれますし、肉体的にも成長期の生徒たちには有益です。
部活で思いっ切り体を動かし、ぐっすり眠れることはストレスを発散し、健全な精神を保ちます。
部活を通じて苦難を共にした仲間がいれば、それは生徒一人一人の安心感にもつながりますし、この仲間意識を上手く利用すれば、同じ入試という試練に立ち向かうとき助け合うこともできるでしょうし、ライバルとしておtが害に切磋琢磨することもできます。
部活をしないで一人孤独に受験に挑むのもいいですが、このような苦楽を分かち合う仲間意識は部活で得られることがあります。
ただ、この仲間意識が馴れ合いにならないように注意する必要はありますが。
部活で心身ともに成長し、充実感のある生活を送り、苦楽を共にした仲間ができれば、つらい受験勉強も乗り越えられるし、後の人生で振り返ったときに良い思い出にもなります。
そして、これらの経験がその後の長い人生においても強く生きる糧になると思います。
受験という短い期間ではなく、人生という長い目で見た場合にも、部活をすることは十分意義があると考えられます。
3.人生の学びとしての効果
部活では、生徒たちは自分とは違う多くの人々と関わらないといけません。
そして、様々な人々と良好な人間関係を築くにはどうすればいいか学ぶことができます。
最近は特に、SNSの発達などにより、昔と比べて様々な人々と接する機会が減っているように感じます。
自分が分かり合える同質の人間としかつながらず、異質な人とは相互理解に手間がかかるので関わらないということも簡単にできてしまうからです。
昔は家族も多く三世代だったり、多くの近所の人との関わり多かったりして、嫌がおうにも老若男女様々な人々と付き合わないといけない場面が多々ありましたが、今は違います。
そんな現状において、部活は多様な人物と触れ合い、良好な人付き合いの方法を学べるチャンスでもあります。
人付き合いは長い人生において重要な問題ですが、受験勉強においても効力を発揮します。
これが上手ければ多くの人の助けが得られるからです。
特に勉強を教えてもらうとき、上手に人と交流ができれば多くのことを教えてもらえます。
こうした点も部活をしないで受験勉強のみに日常を捧げる生徒には得難いものでしょう。








今回は受験と部活というテーマで考えてみました。
本当に受験勉強という視点のみで議論するなら、部活は時間の無駄かも知れません。
しかし、部活で生徒が得られるものは、実は受験勉強を裏で支えるのに重要なものが沢山あることが分かります。
更に、部活で身に付くことの中には、受験勉強という狭い視野でなく、人生という大きな視点で考えたとき、人生を豊かにしてくれるものも数多くあります。
受験勉強という一点のみにおいて、部活を捨てるというのは何だかもったいないような気もします。
実際、部活をしないから必ずしも成績が上がるという訳でなく、むしろ部活をやめてできた時間をゲームなどの遊びに使い、反って成績が下がるということもよくあります。
要は本人の自覚しだいということも忘れないでほしいです。
以上のことを踏まえて、入試を目指す生徒として部活をどのように捉えるべきか見直してみるのもいいかも知れません。





















2022.09.10
重たいランドセル、人間関係、スマホ・・・今どきの環境が子供たちの健康に大きな影響を与えています

我々が育った時とは大きく異なる環境で、今の生徒たちは育っています。
その結果、子供たちの成長や健康に害が出ているようです。
スマホやインターネットが普及し私たちの環境は大きく変わりました。
学校の教育方針も同様です。
つまり、子供たちは私たちが経験したことのない環境の中で生きているのです。
従って、私たちが想像しなかった悪い事態が子供たちに起こっています。











1.持ち物
最近特に取りざたされているものの一つに生徒たちの持ち物の問題があります。
ランドセルは年々改良されより軽く丈夫になっています。
しかし、教科書やノート、ドリルなどの教材は以前(特に「ゆとり教育」のころ)に比べ格段に多くなっています。
学習指導要領の改訂により、教科書のページすすが増え、サイズも大型化しています。
昔みたいに教科書が上下に分かれておらず、一冊の厚みも増えています。
時には体操着や上履き、ピアニカや粘土も持たなければならず、平均で7.7㎏の荷物を持たなければならないと言われています。
パンパンになったランドセルを背負って、よたよたと通学路を休み休み歩く小学生の姿が目撃されます。
7.7㎏と言えば、自分の体重の4分の1くらいになるので、疲れて当然です。
中学生では更に教科書は増えます。
更に「置き勉禁止」(学校に教材を置いておくのを禁止すること)なので、毎日生徒は全教科の教材を持って往復しなければなりません。
よく後ろにこける生徒がいるそうです。
2.SNS
この問題は生徒を疲れさせ活力を奪ったり、登下校中ふらふら歩いて事故に巻き込まれるだけではありません。
背中に重い荷物をかるわなければならないので、どうしても前傾姿勢になります。
前かがみの姿勢は重い頭を支える首の負担を増やし、肩こりを引き起こします。
また、猫背になり、頭痛や腰痛を発症することもあります。
子供はまだ骨格がしっかりしていませんから、重すぎるカバンは大きなダメージになります。
精神面からの子供たちへの影響も見過ごせません。
今の生徒たちは面と向かった人間関係だけでなく、SNSなどを使った人間関係も重要になっています。
そして、常にSNSを通じてグループに触れていないと大きな不安を感じるようです。
そんな中で、第三者には分かりにくいいじめにある生徒も多いです。
グループから外されるのが怖い、自分がいじめられる立場になるのが恐ろしい。
結果、生徒たちは常に空気を読んで全体が期待する役割を演じなければならなくなっています。
SNSには逃げ場がなく、一日24時間つながっているので、気の休まる場所がありません。
彼らを取り巻くぎくしゃくとした人間関係が、より生徒たちを委縮させる。
更に親の期待や成績など、様々なストレスにさらされ肉体に影響が出る子供もたくさんいます。
腰痛に頭痛、肩こりに円形脱毛症まであります。
3.スマホ老眼
「スマホ老眼」も子供たちの間で増えているようです。
スマホのゲームなどで目を酷使して、目の調整機能が落ちることを「スマホ老眼」と呼ぶそうです。
焦点がなかなか合わなくなるだけでなく、更に症状が悪化すると近視、頭痛、肩こり、集中力低下が起きてきます。現在学校ではIoT化で授業でもタブレット端末やパソコンを使う機会が増え、子供たちの目に対する環境はより厳しくなります。
2時間以上スマホを連続して使うと相当の負担になるそうです。










世の中がめまぐるしく変化する時代、私たちが経験したことのない環境に、子供たちはさらされています。
その結果、子供たちは心身共に非常に大きな負担を受け、健康を害するものが増えています。
これは環境の問題なので、社会全体で取り組むべきです。
しかし、第一歩としては身近な大人が、自分の子供を始めとする子供たち一人ひとりに、丁寧に対応していくべきでしょう。






























2022.09.09
明日は十五夜、お月見!日本の伝統行事は受験でもよく出ます

今年の十五夜は明日9月10日!
中秋の名月とも呼ばれていますよね。
天気予報によると東京は雲がかかって見えにくいようです。
でも、雲のすきまから真ん丸な美しい月が現れるのを待ちながら夜空を眺めるのもいいかもしれませんね。
運良く見れれば感動もひとしお。
一瞬でもいいから、美しい丸い月が見れますようにお祈りします。









そもそもお月見とは何なのでしょうか。
十五夜とも呼ばれ、旧暦の8月15日辺りに出るの夜に満月を味わうことです。
中秋の名月と言い、日本人はその見事な月を眺めながら歌を詠んだりしました。
因みに、日本人は月の黒っぽいところ(海と呼ばれていますが、実際に水はありません。)を見て、ウサギが餅つきをしている姿を想像しました。
南アフリカではロバやワニに見えるそうです。
アラビアでは吠えるライオン、ヨーロッパでは紙の長い女の人やカニなど国や地域によって、その見え方が変わっていきます。
これは違うものを見ているというより、見えているものを何と結びつけているかという文化的な違いによるものです。
(例えば虹の色は日本では7色と言いますが、他の国では違う数になっています。)
月を見ながらこんな話をしてみるのも楽しいと思います。
ウサギが当たり前と思っていたら、それは日本だけで他にもいろいろな考え方があるんだなんて気づくときっと面白いでしょう。










ところで、お月見を始めとする年中行事は、実は受験でよく出る話題です。
特に中学受験では、社会や国語などで出てきます。
各行事の日にちや由来、何をするのかなど問われますが、学校などであえて授業中に学ぶことはないと思います。
つまり、勉強というより、一般常識として聞かれるのです。
しかも、意外と年中行事に関する問題は多いです。
だから、知ることは必要です。
あえて勉強として学ぶよりは、実際に年中行事として家庭で実践された方が、子供も実体験として理解し、いい思い出にもなるので、家族みんなで楽しみながら、由来などを話し合うといいでしょう。
日本の伝統文化を学ぶことにもなり、日本的な考え方が分かってくると思います。
最近はクリスマスやバレンタインデー、それからハロウィーンなど西洋の年中行事も浸透してきているようで、こちらも子供たちに体験されるのがいいと思います。









現在行われている教育改革では、「考える力」を重視します。
年中行事を通して日本人の心を考える問題も当然想定されます。
年中行事に限らず、経験を通した学びは知識ではなく知恵として蓄積されるので、「考える力」を育てるには非常に大事になります。
皆さんも家族で年中行事を楽しみながら、子供の「考える力」を養いましょう。





















2022.08.25
二学期!しかし二学期初日は子供たちの自殺の多い日でもあります

夏休みも終わり、都内では今日から二学期が始まる学校も多いと思います。
しかし、この二学期初日というのは統計上子供たちの自殺の最も多い日でもあります。
今日はこの点について考えてみたいと思います。








長期休暇の終盤には大人でも、通常生活に戻る不安を感じ憂鬱になりがちです。
子供たちも夏休みの休日モードから通常モードに戻れるか心配になります。
ましてや勉強嫌いの子供にとっては、これまで解放されていた勉強にまた縛られるので、嫌な気持ちが増します。
また、一学期にいじめなどにあって学校に行くのがいやだった子供には、夏休みの間会わなくて済んだ嫌な生徒と再び顔を会わせないといけないのです。
人間関係がうまくいかず、いじめられたり無視されたりするのではないか。
勉強がより難しくなって、自分はついていけるのか。
そのことで親や先生から叱られるのではないか。
いずれにしても不安やストレスの増える時期なのです。







では、自殺に陥る子供たちの心理状態を考えてみましょう。
自分を分かってくれる人はいない、誰も助けてくれない、頼れない。
独りぼっちなんだ。
思春期の子供にはありがちな孤立感という心理状態です。
だから、誰にも相談せず、一人で問題を抱え込み、どんどん大きくなっていく。
外部からの新たな考え方が入ってこないので、自分の中で問題を深刻化してしまう。
また、自分の居場所がないと疎外感を感じることもあるでしょう。
そして、自分はこの世に存在する意味のない人間だ、価値のない人間だと卑下してしまう。
更に、このような状況は今後の人生でも変わらず、ずっと続くように感じてしまう。
未来への希望が持てず、生きる気力、一体と願う力が弱まってしまう。
ならば、いっそのこと死んだ方がましと考える。







いじめに苦しむ生徒などは、苦しい現状から逃げるために、自殺という選択肢を選ぶこともありますが、自分のできる唯一の抵抗として、自殺という手段を選ぶこともあります。
現実では抵抗できないから、自分が死ぬことでいじめた生徒が罪悪感にさいなまれ苦しむことを期待する。
しかし、ことがそのように運ぶかは不確定だし、おそらく一過性で終わり、いじめた子供も時間がたてば忘れてしまうでしょう。
実際自分の命を犠牲にしてまで効果のある方法には思えませんが、視野がせまくなっている当事者には最後の希望なのでしょう。
または、いじめられてなぜ自分がこんな目に合わなければならないのかという怒りが、何もできないふがいない自分に向かい、自分を傷つける行為に及ぶこともあります。








自殺に至るにはそれなりに追い詰められ、その状況から自殺以外の選択肢はないと判断する心理があるのです。
これを理解し、子供たちの尊い命が犠牲にならないように、我々は対処していかなければなりません。
子供たちの自殺に向かう兆候、それを防ぐにはどうすべきか。
未来のある若い命が失われることのないよう、心から願います。





















2022.08.19
イベント紹介『化石ハンター展』夏休みは特別展がいっぱい!

夏休みも終盤に入ってきましたがいかがお過ごしでしょうか。
勉強や遊びも大事ですが、夏休みだからこそ行われるイベントもたくさんあります。
そんな特別な展示や催しに出かけて、日頃なかなか味わえない経験をするのもいいでしょう。
イベントを通じて得られる特別な感動が子供たちの人生を大きく変えることもあります。
よって、この長期休暇を利用して様々なイベントに参加し、子供たちの心に多くの刺激を与えてあげることをお勧めします。








毎年そうですが、今年もいろいろなことが予定されているようです。
そんな数ある夏の特別展の中で葛西TKKアカデミー紹介するのは『化石ハンター展』です。
上野の国立科学博物館で現在行われている特別展で、10月10日までやっていますのでまだ日程的に余裕があります。
ご時世柄、入場にはオンラインによる事前予約が必要なので注意してください。
立地も上野公園内なので、アクセスも非常に楽です。








このイベントはアメリカのロイ・チャップマン・アンドリュースが、1922年に中央アジアのゴビ砂漠で大規模な化石の調査を行ったのを記念して開催されました。
本展では彼の生い立ちから始まり、この有名なゴビ砂漠での成果を展示してあります。
大発見と言われるプロトリケラトプスとその卵の化石もあります。
そして、彼の業績に刺激を受け、彼のような化石ハンターを目指した人々の成果も見ることができます。
恐竜や哺乳類の数多くの標本はその大きさや奇抜さから、驚くこと間違いなしです。
実は、彼がこの大規模調査を行ったのは、恐竜の化石発見のためではなく、彼の師が提唱する「哺乳類の起源はアジアにある」という言葉を立証するためで、本来は哺乳類化石の収集と調査が目的でした。
インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突をした際、地形が変化し、それに伴いアジアの気候も変化しました。
ヒマラヤなどの高地が誕生し、そこに暮らす哺乳類が寒冷気候に適応した結果、後の氷河期に拡散して生き延び、動物相の変化をもたらし、現在のように哺乳類が繁栄するようになったと考えたのです。
これを「アウト・オブ・チベット」説と言うそうです。
非常に興味深い考え方ですね。
この「アウト・オブ・チベット」説の裏付けを得るために行った大調査ですが、この展示ではその調査の様子やそれに関連した哺乳類の標本化石が見られます。
史上最大の陸生哺乳類といわれる「パラケラテリウム」の化石は圧巻です。
史上最大というだけあって本当に大きい!
キリンかと思うくらい。
サイの仲間なのですが、今のサイとは全く違うすらりと高い背にビックリです。
また、他にも多くの哺乳類化石や標本がありますが、中でも人気なのは、今は絶滅してしまった「チベットケサイ」という、全身が長い毛で覆われ大きな角を持つサイの生きていた様子を表した生体モデルです。
世界初公開ということ、全身骨格の圧倒的に大きな角などもありますが、最大の人気の理由はこの生体モデルなのではないでしょうか。
これは親子のチベットケサイが復元されていますが、ここには次のようなストーリーが表現されているそうです。
「生まれて初めて見る雪はしゃく子供のケサイ、そして、お母さんケサイはその様子をそっと見守ってあげている。その一方でお父さんケサイは家族を守るように外敵に向かって威嚇を仕掛けています」
ここの注目ポイントは何と言っても子供のケサイです。
雪で滑って転んだのか、それとも楽しくて雪で遊んでいるのか。
母親の足元でコロンと寝そべっている姿がとてもかわいいのです。
ぬいぐるみになってグッズとしても売られているそうですが、思わず持ち帰りたくなりますね。








展示だけでも大変楽しめますが、それ以外に図録や小物などのグッズ、それから食も注目です。
この特別展を通じて子供たちが古生物や世の中の不思議に興味を抱き、驚きと感動を体験し、いろいろなものに対する好奇心を育ててくれればと思います。
『化石ハンター展』以外にもたくさんの展示やイベントが夏休みにはあります。
残りわずかですが、チャンスを逃さず、豊かな心を持って、楽しい夏の思い出を作ってください。



























2022.08.09
もうすぐ夏休みも終わってしまいますよ!『毎週月曜日はTKKで宿題やるぞ!』来週は水曜日もやります!

暑い日が続きます。
暑さに負けて毎日をだらだら過ごしていませんか。
夏休みの宿題は順調に進んでいますか。
気づけばもう夏休みも半分終わっていますよ。
今年は8月25日まで。
大丈夫ですか?
宿題終わりますか。
そこで、葛西TKKアカデミーの夏休み企画『毎週月曜日はTKKで宿題やるぞ!』ですが、来週は特別に水曜日も実施します。
夏休みの宿題が思うように進んでいない人は是非参加してください。








『毎週月曜日はTKKで宿題やるぞ!』
毎週月曜日、午前10時~午後4時まで、葛西TKKアカデミーが教室を開放し、皆さんの夏休みの宿題をお助けします。
来週は特別に8/15(月)と8/17(水)の二日間!
事前予約制で参加希望者はメールにてご予約お願いいたします。
tkkac2016@gmail.com
お問い合わせもこちらまで。
基本的に参加は無料ですが、工作等材料費がかかる場合はそちらを請求することがあります。
また、生徒たちの代わりに葛西TKKアカデミーが宿題をするのではありませんので、誤解のないように。
あくまでも宿題をするのは本人です。
葛西TKKアカデミーは皆さんが早く終われるように、少しでも良いものができるように、手伝ったりヒントを与えたり相談にのったりします。
次のような人は是非ご参加ください。
1.毎年宿題のワークやドリルが終わらない
そんな人は、このイベントを毎週利用して、勉強の環境の整った葛西TKKアカデミーの涼しい教室で集中して勉強に取り組むことができます。
しかも、分からないときはTKKアカデミーの先生に直接質問して教えてもらうことができます。
最初に計画を立てて、毎週のノルマを決めてやると、宿題が遅れることなく進みますよ。
2.自由研究に何をしていいか分からない
自由研究何をしていいか分からないという生徒は非常に多く、アイデアを出すのに一苦労です。
そこでTKKアカデミーがどんな自由研究にするか、本人と相談しながら考えてくれます。
その研究方法やレポートの書き方までアドバイスしてくれますよ。
3.工作や絵などの作品を作りたい
葛西TKKアカデミーの経験豊富な先生がちょっと変わった工作や絵画のアイデアを出してくれます。
そして、一緒に作品を作るお手伝いをします。
他の人と一味違うものを作りたいなら、是非お知らせください。
4.読書感想文が苦手
読書感想文は毎年夏休みの宿題として定番です。
しかし、本を読んでもどう書いていいか分からず、悩む生徒もとてもたくさんいます。
そこで葛西TKKアカデミーの先生が、読書感想文を書くためのフォーマットを用意し、その指示に従ってメモ書きをするだけで、何を書けばいいか分かるように指導してくれます。
また、作文の書き方も教えてくれますし、書いた作文を添削してより素晴らしいものに仕上げてくれます。
他にも夏休みの宿題でお困りの方は、この機会にお問い合わせください。








毎日の猛暑で勉強をする気になれないかも知れません。
それでも夏休みの宿題はやらなくてはいけません。
そうであれば、少しでも効率よく、人より秀でたものにしたいものです。
葛西TKKアカデミーならきっと皆さんのお役に立つことができると確信しております。
夏休みも終盤になって手遅れになる前に、葛西TKKアカデミーで夏休みの宿題を終わらせて、悠々自適なゆとりのある夏休みを過ごしませんか。
皆様の参加をお待ちしております。






















2022.07.27
プラモデル紹介『ENTRY GRADE RX-78-2 ガンダム』勉強と関係あるのですか?え、えぇ、まあ・・・



昔から指先を使うことで、脳への刺激が増え、神経ネットワークの発達が促されると言われています。
確かに工作など器用に作る生徒は、勉強の成績も良い印象がありますよね。
そこで、今回は手先を動かし脳の発達を促すツールとして、あるプラモデルを紹介したいと思います。
その名も『ENTRY GRADE RX-78-2 ガンダム』!
とある事情で小学生二年生に作らせたのですが、このキットがあまりにも素晴らしすぎるので紹介せずにはいられませんでした。
『ENTRY GRADE RX-78-2 ガンダム』へのリンクはこちら









脅威のメカニズム!小二が一時間で作る!
上のガンダム、実は上にの男の子が、お姉さんの授業が終わるのを待っている間に作りました。
トータル1時間程度です。
それでこのクオリティとは信じられません。
ガンダムのプラモデルと言うと、私が子供のときにブームになり、みんなこぞって作っていました。
その後もプラモデルは進化し続け、今では非常に品質の高いガンプラがたくさんあります。
改良に改良が重ねられたギミックとプロポーション。
細かい造形に、リアリティの追及、そして見えないところまで作り込まれたこだわりなど、バンダイ制作陣の情熱が伝わってくるくらい、素晴らしい商品がたくさん販売されています。
しかし、その結果としてプラモデルが複雑化し、値段も何千円、中には一万円を超えるものもざらにあります。
そして今のガンプラは熟練者の欲求を満たす反面、初心者には難しく敷居が高いものとなりました。
そこでバンダイが新たに発売したのが、この『エントリーグレード』のシリーズです。
この商品の素晴らしい点は、特に必要な道具もなく、初心者でも簡単に、しかも見栄えのいいガンダムが作れるという点です。
これまでランナーから本体を切り離すには、ニッパーなどの道具が必要でしたが、この『エントリーグレード ガンダム』は手でパチッと軽く押すだけで切り離すことができます。
しかも、パーツは色ごとに分割されているので、塗装をしなくてそのまま組むだけで、きちんと色分けも成されるようになっています。
更に、初心者でも作りやすいように、パーツ数も少なめに分かりやすくできています。
それでありながら可動域は広く、上の写真のようなポーズもできます。
昔のガンダムでは考えられません。
特に顔などを見てもらえると分かるのですが、それでいてディテールまでしっかり作り込まれていて、出来上がると初心者が作ったとは信じられないくらい素晴らしいガンダムが手軽に完成するのです。
しかも、770円(税込)と値段もお手頃!
私自身も小学生二年生の彼が作るのを見て驚き、今度は自分自身用に一つほしくなりました。
さすがバンダイ、これならプラモデル未経験の人でも簡単に作れ満足を得られますね。
これまで興味なかった人もきっとプラモデル作りに引き込まれるでしょう。
因みに、私はバンダイの回し者ではありません。
勉強とどう関わるの?
ここで終わっては単なる趣味のニュースになってしまいますので、勉強にどう役立つか考えてみます。
よく言われるのが、手先で細かい作業をすることによって、脳への刺激が増え、神経が複雑に絡み、ネットワークが構築されるということです。
勉強における思考力や発想力、想像力などは神経ネットワークが密になればなるほど高くなると言われていますので、プラモデル作りを通して指先をたくさん使うことは、脳の発達にとてもいいのです。
更に、説明書を見て作る訳ですが、説明書を読み取る力というのも勉強には非常に役立ちます。
プラモデルの作り方が書いてある説明書は図を使って説明していますので、先ず、図形の読み取り、空間を認知する能力が要求されます。
プラモデルが作れるということは、空間認知能力が備わっている、またはそれを鍛錬し習得しているということになるので、プラモデル作りはやはり勉強の役に立ちます。
ただ平面上の立体そのものを理解するだけでなく、その立体同士をどのように組み合わせるか、どのような順でつなぎ合わせていくかなどの指示も理解しないといけません。
説明書を読みながらプラモデルを作るということは、指示を正確に読み取る訓練にもなります。
これからの新しい日本の教育において、これも重要な力になります。
現在教育改革で文科省が目標とする学習能力が単なる暗記だけではなく、情報を読み取り分析し自身の知識経験なども踏まえて結論を導き出すレベルにまで引き上げられています。
その結果、普段の授業や入試などで、(数学に限らず様々な教科で)図などの資料を用いた問題が非常に増えています。
空間認知能力や図形の読み取りができないと正解が出せませんし、問題に書かれている指示や内容を正確に理解しないとどのように解くのか分かりません。
プラモデルという子供たちが取り掛かりやすいものを通じて、これらの能力を伸ばすのは勉強にとても有益だと考えます。









今回は偶然にも出会ったガンダムのプラモデルが素晴らしすぎたので、そのお話になりました。
人間、その気になれば色々なものから学ぶことができます。
一見勉強と関係ないように思えるものでも、実は非常に勉強に役立ち、知らず知らずのうちに子供の潜在能力を引き延ばすことがあります。
子供に勉強が敬遠されることが多いですが、このように本人が興味を持ちそうなもの、楽しめそうなものから学べると、考え方も変わってくるのではないでしょうか。
今はちょうど夏休みで時間的にゆとりがあると思います。
この機会に普段できないようなことに挑戦し、新しい学びの扉を開いてみるのもいいのではないでしょうか。
また、学びは五教科だけではありません。
それ以外にも人生の糧になることが身の回りにはたくさんあると思います。
暑い日が続いていますが、ダラダラと過ごさず、どうか積極的に行動してたくさんのことを学んでください。






















2022.07.20
葛西TKKアカデミーの夏休み企画第二弾!『毎週月曜日はTKKで宿題やるぞ!』

いよいよ夏休みがスタート。
遊ぶ計画もたくさん立てていることでしょう。
しかし、うかうかしていると長いはずの夏休みもあっという間に終わってしまいます。
二学期直前に慌てて夏休みの宿題に取り掛かる、なんてことはよくありますよね。
そんなことにならないように、葛西TKKアカデミーが皆さんの夏休みの宿題をお手伝いします。








先日ご案内した『デジタルアート体験』に次ぐ、葛西TKKアカデミーの夏休み企画第二弾!
『毎週月曜日はTKKで宿題やるぞ!』
毎週月曜日、午前10時~午後4時まで、葛西TKKアカデミーが教室を開放し、皆さんの夏休みの宿題をお助けします。
事前予約制で参加希望者はメールにてご予約お願いいたします。
tkkac2016@gmail.com
お問い合わせもこちらまで。
基本的に参加は無料ですが、工作等材料費がかかる場合はそちらを請求することがあります。
また、生徒たちの代わりに葛西TKKアカデミーが宿題をするのではありませんので、誤解のないように。
あくまでも宿題をするのは本人です。
葛西TKKアカデミーは皆さんが早く終われるように、少しでも良いものができるように、手伝ったりヒントを与えたり相談にのったりします。
次のような人は是非ご参加ください。
1.毎年宿題のワークやドリルが終わらない
そんな人は、このイベントを毎週利用して、勉強の環境の整った葛西TKKアカデミーの涼しい教室で集中して勉強に取り組むことができます。
しかも、分からないときはTKKアカデミーの先生に直接質問して教えてもらうことができます。
最初に計画を立てて、毎週のノルマを決めてやると、宿題が遅れることなく進みますよ。
2.自由研究に何をしていいか分からない
自由研究何をしていいか分からないという生徒は非常に多く、アイデアを出すのに一苦労です。
そこでTKKアカデミーがどんな自由研究にするか、本人と相談しながら考えてくれます。
その研究方法やレポートの書き方までアドバイスしてくれますよ。
3.工作や絵などの作品を作りたい
葛西TKKアカデミーの経験豊富な先生がちょっと変わった工作や絵画のアイデアを出してくれます。
そして、一緒に作品を作るお手伝いをします。
他の人と一味違うものを作りたいなら、是非お知らせください。
4.読書感想文が苦手
読書感想文は毎年夏休みの宿題として定番です。
しかし、本を読んでもどう書いていいか分からず、悩む生徒もとてもたくさんいます。
そこで葛西TKKアカデミーの先生が、読書感想文を書くためのフォーマットを用意し、その指示に従ってメモ書きをするだけで、何を書けばいいか分かるように指導してくれます。
また、作文の書き方も教えてくれますし、書いた作文を添削してより素晴らしいものに仕上げてくれます。
他にも夏休みの宿題でお困りの方は、この機会にお問い合わせください。








大雨が降ったりものすごく暑かったりと、今年の夏は勉強に向かないような予感さえします。

それでも夏休みの宿題はやらなくてはいけません。
そうであれば、少しでも効率よく、人より秀でたものにしたいものです。
葛西TKKアカデミーならきっと皆さんのお役に立つことができると確信しております。
夏休みも終盤になって手遅れになる前に、葛西TKKアカデミーと一緒に夏休みの宿題を終わらせて、悠々自適なゆとりのある夏休みを過ごしませんか。
皆様の参加をお待ちしております。






















2022.07.20
明日は終業式、通知表を上手く使って学習改善と意欲向上!
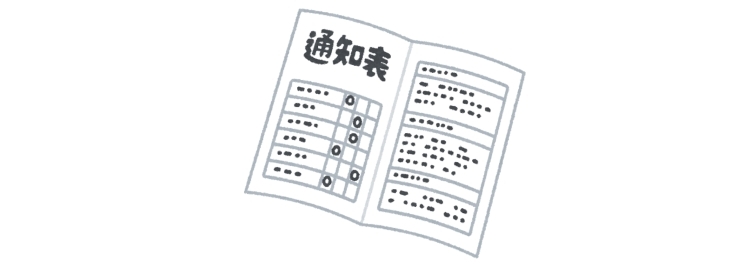
明日が終業式の学校も多いことと思います。
そして、各学期の終わりに手渡されるものに通知表があります。
その学期の学校での活動の総括です。
今、成績が気になってドキドキしている人もたくさんいると思います。
でも、結果を見て、よかった悪かったと一喜一憂して終わりではあまり意味がありません。
この通知表をどのように見て、子供たちと共有するかで、今後の学習が左右されます。
通知表を上手に使って、今後の成績アップにつなげましょう。








普段からなかなか勉強せず苛立っているところに、この通知表を証拠物件として取り上げ、ひたすら子供の勉強に対する怠慢を責めるだけでは、子供の勉強に対する姿勢、能力は向上しません。
反って勉強に対する拒絶を強めるだけです。
そんな子供は大抵自分が十分やらなかったことは分かっているのです。
自分でも内心反省しているところに、傷口に塩を塗られるように攻め立てられると、嫌になってやる気にもなりません。
通知表は子供を責めるための道具ではありません。
通知表は学習の記録であり、良い点悪い点を明確にし、今後の勉強の向上に役立つ資料なのです。
よって、もらった通知表をどのように生かすかが大事です。
的確に分析し上手にアドバイスすれば、子供のやる気を出させ成績を伸ばすことができます。








では、通知表をどのように扱えばいいのでしょうか。
もらった通知表を子供と一緒に見ながら、話し合ってください。
まずは良い点を褒めてあげましょう。
以前と比べて何が良くなったか、どんなことができているかを読み取りましょう。
そして、言葉で明確に子供に伝えてください。
どんなに些細なことでも構いません。
褒めることは、子供の努力を認め、本人を肯定することになります。
子供はうれしくなり更なる努力をするでしょうし、自己肯定感が高まれば自身にもつながります。
そして、褒めるのはどんなに小さなことでも構いません。
具体的であればより分かりやすく、効果も大きくなります。
「今までできなかった九九が完璧に言えるようになったね。」という感じで。
逆に、本人を否定するような言葉はやめましょう。
自分はそのつもりでなくても、本人がそのように捉える場合があります。
だから、否定的な言葉に対しては慎重になってください。
通知表は学校生活における本人の評価の一部であって、全ての能力や人格を評価するものではありません。
でも、通知表の結果だけで「ダメだね。」と言われると、自己否定につながり、心が傷つきもう勉強もしたくなっても仕方ありません。
先ほどと逆になりますが、これは通知表の意図するところ、教育の望むところではありません。
また、他者と比較するのもよくありません。
「○○ちゃんはできるのに。」とか「お兄ちゃんはできるのに、どうしてあなたはできないの。」などと言うのもいけません。
人間の成長は人それぞれで、必ずしもみんなと同じではありません。
できるのが遅れているからと言って、能力が無いわけではありません。
自分が最大限の努力をして出した結果を他者との比較で否定されるのも、本人の自己否定につながり、今後の学習に悪影響を及ぼします。








でも、褒めるだけではいけません。
やはり、本人の向上のためにも悪かったところもしっかり分析し、どうすればいいか対策を一緒に考えるべきです。
上手にアドバイスすれば、成績も伸びることでしょう。
その際は、親はカウンセラーに徹した方がいいです。
ああしろこうしろと指図するのは、子供に不快感を与えると同時に、親に言われたからと自分に責任を持たなくなります。
一緒に考え、本人がどうするかを決める。
これが大事です。
「どうしてこうなったと思う。」
「こうなったのはなぜかな。」
「もしこうだったら、どうなっていたと思う。」
などと質問しながら会話を促すのが役割です。
質問に答えるうちに本人も原因がだんだん明確になり、どんな解決法がいいかが分かってきます。
問答の中でもよい点が見つかれば、欠かさず褒めてください。
そして、無理のない目標や対策を自分で立てれば、誰にも強要されたわけではないので責任もってやるしかありません。
このようにして改善することができます。








通知表を有効に使うことで勉強の向上が図られます。
ただ結果を見るだけでなく、共有し努力と成果をほめ、改善すべきことを見つけ話し合い対策を立てる。
これが成績アップのためのいい機会です。
そして、新しく立てた目標に向かって長期の休みを活用し、今後の学習生活が有意義に過ごせるように頑張ってください。






















