塾長ブログ
2022.07.18
夏休みの宿題で苦戦する読書感想文はどう書けばいいのでしょうか

皆様のお役に立てる個別指導塾を目指す葛西TKKアカデミーは、通常の五教科の指導の他に、読書感想文や自由研究のお手伝いもします。
夏休みの宿題で子供たちが嫌がるのもが読書感想文です。
読むのが面倒くさくて後回しにしていたら、いつの間にか夏休みも終わり。
慌てて読もうとしても時間が足りず、提出期限に間に合わないなんてことはよくあります。
そうならないように早めに手を付けた方がいいでしょう。
本日は、読書感想文の書き方とコツをご説明します。








当然本を読む訳ですから、最初に本を選ばないといけません。
普段から本に親しんでいるお子様ならいくつか心当たりがあるでしょうが、そうでないと一から探さないといけません。
本屋の店頭にもたくさんあって、どれを選べばいいか分からない。
特にこだわりがないのであれば、本は何でもいいと思います。
分からないときは、読書感想文の推薦図書や本屋の店頭にあるポップで決めると、だいたい間違いはありません。
友達が勧めた者でもいいし、テレビで話題になっているものでもいい。
映画やドラマの原作であれば、先に映像を見て読むと分かりやすかったりします。
それでも分からないときは表紙の絵や色で決めてもいいと思います。
つまり、こちらがどのように書くかが問題であって、そのもとになるお話は何でもいいのです。








次に本を実際に読むのですが、ただ読んでいると何も印象に残らず、後で何のお話か、何を書いていいか分からなくなります。
だから、読みながらメモを取るようにしてください。
メモすることは、あらすじや印象に残った場面や言葉、登場人物の行動や気持ちなど、感想文を書くときの助けになると思ったことです。
要約して書いてもいいし、抜き出しても構いません。
ページ数と行を書いておくと、後で見直すときも便利です。
また、読んでいるときの自分の気持ちもいい材料になりますから、メモしましょう。








こうして読み終え、各材料が集まったら、内容を決めましょう。
何をどのくらい書くか決めるのです。
それに基づき、使えそうな材料をメモから見つけます。
メモをつなぎ合わせ大筋を決め、細かいところを書いていきます。
この時、ページが書いてあればすぐに本を参照できるので便利です。
基本的構成は小学生の場合、「はじめ」「なか」「おわり」が一般的です。
「はじめ」にはどうしてその本を読もうと思ったか、きっかけやあらすじなどを書き、読み手に本の紹介をします。
「なか」では、印象に残った場面に触れ、どうしてそこが印象に残ったか説明します。
自分の感想や、その場面から分かったこと、学んだことを書くといいでしょう。
「わたしだったら…」というのもいい書き方です。
分量にもよりますが、ふつうは印象に残った場面を二つぐらい触れれば十分でしょう。
1200字であれば、「はじめ」150字、「なか」800字、「おわり」200字ぐらいが目安になると思います。








こうして一通り書けたら、必ず読み直しましょう。
主語述語の不一致や、文末表現の不統一、誤字脱字などないか確認しましょう。
原稿用紙の使い方は適切ですか。
時間があれば他の人に読んでもらってください。
意見、感想、こうしたらもっと良くなるというアドバイスがもらえます。
こうしてより良い感想文に仕上げましょう。








慣れないと面倒くさく思えるかもしれませんが、書いてみると意外と面白かったりします。
これをきっかけに物書きに目覚めるかもしれません。
いずれにしても「書く」という行為は社会生活において非常に重要な行為です。
様々なきっかけを有効に活用して、子供たちの「書く」技術を磨いてほしいと思います。
























2022.07.11
TKKアカデミーの夏のイベント!今年は『デジタルアート体験』です
2022/07/11

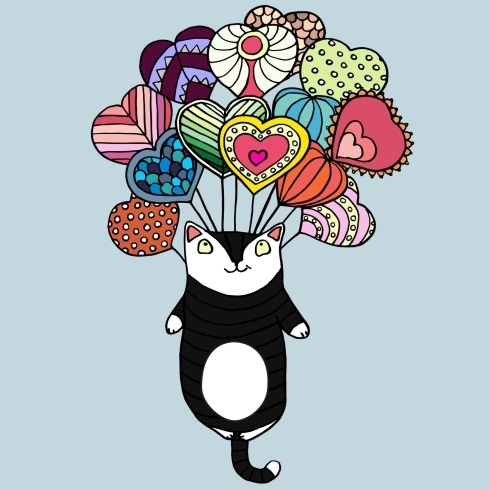


もうすぐ夏休みですね。
今年も猛暑になりそうな感じですが、葛西TKKアカデミーではオリジナルの夏のイベントとして『デジタルアート体験』を行います。
コロナ禍の影響でGIGAスクール構想が前倒しされ、既に生徒一人ひとりにデジタル端末が配布されました。
もう子供が自宅にiPadなどを持ち帰って、リモートの練習をしたりしているのではないでしょうか。
実際にiPadで問題を解いたり、インターネットで調べたり、プレゼンテーション用のスライドを作ったりと、学校教育のデジタル化は進み、我々には想像つかないくらい学校の日常に入り込んでいます。
このようにデジタルな環境は子供に身近なものとなっていますので、今年の葛西TKKアカデミーはデジタルツールを使って何かできないかと考え、夏の企画として『デジタルアート体験』を実施することにしました。








葛西TKKアカデミーの『デジタルアート体験』!
日時:8月5日 12:00~17:00
場所:葛西TKKアカデミー
料金:500円
内容:
iPadを使ったお絵描き教室です。
事前予約制で所要時間1時間を予定しております(実際はそれほどかからないと予想しています)。
専任の先生がついて、一対一でお絵描きをサポートしてくれます。
絵のジャンルとしては次の3つです。
1.コラージュ:用意してある素材やその場で撮った写真を取り込んで、貼り付けたりしながら絵を完成させます。
2.塗り絵:既に描かれている絵に、自由に色を塗っていきます。
3.キャライラスト:自分の好きなキャラクターを自由に描いていただきます。
予約の段階でどれを描きたいか決めていただきます。
出来上がった作品はその場でプリントアウトしてお持ち帰りいただけます。
希望があれば作品をメールに添付してお送りします。








暑いので、葛西TKKアカデミーの涼しい教室で過ごすこのイベントは最適です。
一時間に一組しかできないので、席が埋まってしまうことも考えられます。
予約はお早めに。
デジタルアートと言うと「難しそう」と思うかも知れませんが、実は意外と簡単にできます。
学校でも使い子供たちも扱いに慣れてきたと思うので、このイベントを通じてICTで何ができるか実感し、楽しみ、新しい可能性を感じ取ってもらえれば幸いです。






















2022.07.09
勉強ができなくなってしまった生徒たちの共通する経験とは

葛西TKKアカデミーでは勉強をしたくてもできない生徒たち、勉強をどうにかしたいけどどうやっていいか分からない生徒たちを多く見てきました。
普通の塾のように教材さえ与えておけば自分で勉強でき、ある程度の結果が出せる生徒とは違い、一筋縄ではいかない生徒をたくさ思い出しますす。
普通の塾なら見放される(例え表立って言われなくても実際にそうされている)生徒でも、本人のやる気さえあれば他のことは度外視してでも受け入れ、何とかしてあげたいと努力してまいりました。
そのような生徒とたくさん出会う中で、彼らが勉強ができなくなってしなった原因、勉強をあきらめてしまった理由には似た点があることが分かりました。










小学校の一年生のときは基本的にみんな勉強が好きです。
憧れの学校に入り、新しく勉強というものができることが喜びでした。
しかし、学年が上がり学習内容が難しくなっていくにつれ、これまではよく理解できた勉強が、簡単に解けた問題ができないようになってくるという現実にぶち当たります。
それは授業で先生の言っていることが分からないとか、宿題の問題がどうしても解けないといった経験から悟ったり、できたつもりでも実際にテストをしてみると点数が悪かったという結果から実感したりします。
そうしてどうすればいいか分からなくなります。
そんなとき、適切に生徒が分かるように説明し導いてくれる人がいればいいのですが、単純に「なんでできないの。」と怒鳴ったり、「頭悪いんじゃないの。」と非難されたりすると、子供たちは救われず、勉強に対する情熱が一気に冷めてしまいます。
そして、「自分はダメな人間だ。」と卑下し、勉強が嫌になっていきます。
子供たちの成長は決して一定ではなく、ある程度の早い遅いはあります。
だけど、日本の場合、一定の年代の生徒は皆一様に同じ勉強ができていないといけないという暗黙の了解があるようです。
だから、そこから少しでも離脱してしまうと不安になり、もう挽回のチャンスはないと感じるようです。
これは親も同じで、自分の子供が一般的な生徒と同じように勉強ができないと非常に焦って、なんとかしようと勉強を教えます。
しかし、子供たちの性質を無視して一方的に押し付けるような教え方では、当然生徒はいつまで経ってもできるようにはなりませんし、親も一生懸命だからこそ、いつまで経ってもできるようにならない我が子に焦り苛立ちます。
そして、ついつい大声を出してしまうと、もう親子関係までもぎくしゃくし何もいいことがありません。
親や先生に「できない子」のレッテルを貼られ、徹底的に心を傷つけられた子供たちは立ち直れなくなり、「いくら勉強をしても非難されるばかりなら、ひたすらつらい思いをするだけなので、もう勉強は諦めて逃げよう。」と考えます。
せっかくできる可能性があるのに、自分から逃避するのです。
それは周囲が生徒たちに希望を感じさせてやれないことが大きな原因の一つと私は考えます。
私の経験から思い出されるのは、こちらが質問した時に「答えたくありません。」と言った生徒です。
彼女はこれまでテストなどで間違える度にさんざん責められ心を痛めました。
自分が間違えることを公にされるのが怖くて、答えないという普通あり得ない選択肢を取るのです。
答えなければ「間違い」とは言われず、自分の体面が保たれると考えるのでしょう。
そうして自分を守ろうとしたのです。
でも、間違えることができない生徒は悲劇です。
なぜなら、人間は間違えの中にこそ学びのチャンスがあるからです。
他にもいろいろ理屈をこねて勉強をしないことを正当化しようとする生徒、しなくてはいけないのは分かっているが、自分は頭が悪いので努力しても無駄、言い換えると勉強ができないのは自分の努力が足りないのではなく、先天的なものだから仕方ないと主張する生徒(大人が「バカバカ」と言ったことを逆手に取ったいいわけですね、だから要因は大人にあります)。
様々な方法で逃げようとします。
でも、彼らは未熟でまだ分からないことも多く、心が十分に育っていないから非常にナイーブなのです。
大人はそこも含めて寛容に彼らに接してあげられるほどの器の大きさが要求されるのではないでしょうか。
しかし、実際はそれができず(親も成長中ですから)親子とも苦しい思いをします。
子育ては楽ではないので、それを含めて子育てと思えるくらいのゆとりが心にあればいいのですが、大人であっても難しいですよね。
そして、不思議なことに、このように勉強ができなくなった生徒ですが、その多くがもう一度頑張ってみようと思うときがあります。
最初、彼らが勉強に迷ったときに適切に対処できなかった場合、これは最後のチャンスです。
ここを見逃さず対応できれば挽回も可能でしょう。
多くの勉強ができない生徒は知能が低くて勉強ができなのではありません。
これまでやってこなかったからできないだけです。
一から根気強く教えれば徐々にできるようになり、場合によっては一気に目が開いて、あっという間に多くの穂コアの生徒を追い越す者もいます。
勉強ができなくなったときも、勉強をしなくてはいけない、やろうと思ったときも、子供たちは何らかの兆し、ヒントを出しています。
それを私たちは見逃さないように注意しないといけません。
言い換えるなら、すぐに感受できるように彼らに寄り添い、常にアンテナを広げてなくてはいけないのです。
そして、その信号をキャッチしたなら、どうか今度は過ちを繰り返さないでください。
分からないときは自分だけでどうにかしようとするのではなく、誰かに遠慮なく助けの手を伸ばしてください。
子育ては楽ではありません。
みんなで手分けして、上手に負担を減らすことが、親だけでなく子供にとってもストレス低減につながります。
そして、葛西TKKアカデミーはいつでも子供たちを応援していることを覚えておいてください。










勉強は一度嫌いになってしまうと大変です。
なぜなら生徒たちを勉強にもう一度向き合わせるところから始めなければならず、実はこれが非常にエネルギーを必要とするのです。
人間でも一度嫌いになってしまえば、口もききたくなくなりますよね。
そんな状態で人間関係が修復できる訳がありません。
勉強も同じです。
願わくば、勉強が嫌いになる前に手を打ってください。
「勉強は好きにならなくてもいいから嫌いにならないでください。」
これは私がよく生徒たちに投げかける言葉です。
まとめるとポイントは大きく二つ。
一つ目は、勉強ができなくなったときに本人を責めるのではなく、一緒に悩み支えてあげること。
二つ目は、再び本人がやってみようと思ったとき(思えそうなとき)を逃さず、焦らず長い目で見て適切にサポートすること。
多くの勉強に悩む生徒たちを見てきた経験上、この二点が勉強ができない生徒たちを救い出す重要なポイントだと思います。



























2022.07.07
11月の高校入試のスピーキングテストに備えよう!葛西TKKアカデミーで対策講座&模試が受けられます!
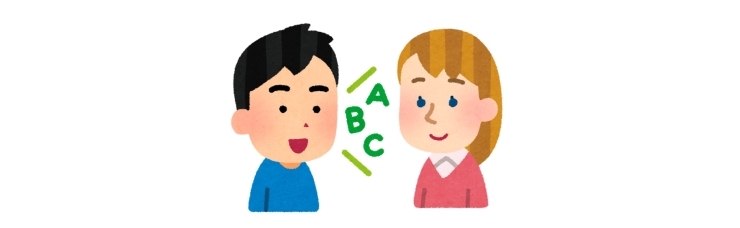
今年から都立高校入試でスピーキングテストが課せられるのはご存知でしょうか。
しかも、テストは一般の都立入試よりずっと早く11月です。
つまり、早く準備をしないといけないということです。
葛西TKKアカデミーでは、この新しいテストに対応すべく対策講座と模擬テスト二回分をセットにして実施します。
特に学校がなく比較的時間にゆとりのある夏休みは対策をするチャンスです。
この機会を逃さないでください!
詳しくは、葛西TKKアカデミーまでお問い合わせください。
初めての試みなので、いきなりぶっつけ本番をやると絶対にうまくいきません。
是非、万全の態勢でテストに臨みましょう!









都立入試でのスピーキングテスト『ESAT-J』とは
東京都では都立高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加することになりました。
このスピーキングテストは『ESAT-J』と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します
イメージとしては英検の二次試験の内容を対人ではなく、パソコンやタブレット端末などを利用して行う感じです。
注意しなくてはならないのが試験日です。
今年は11月27日(日)です。
つまり、都立高校の入試より約三か月早く試験があるのです。
入試本番と同じと勘違いしていると、準備のないままスピーキングテストを受ける羽目になります。
試験内容
テストは四つのパートから成り、パートAは、カードに書かれた短い英文を読みます。
全部で2問あり、解答時間はそれぞれ30秒。
発声して答える前に30秒の準備時間があるので、この間に英文に目を通して、読む内容を確認したり、心の中で読む練習ができます。
本当に書かれてある英文が正しく読めるかどうかだけのテストです。
パートBでは図やイラスト、簡単な掲示物やチラシなどのビジュアルマテリアルを利用した問題になります。
全部で4問あり、そのうち3問はカードに関する質問に答える問題です。
解答時間は10秒で、その前に準備時間が10秒あるので、準備時間にできるだけマテリアルの内容を把握し、必要な情報がどこにあるかを確認できるといいです。
時間が短い分、質問に対する答えも簡潔なものになっているので、比較的答えやすいかもしれません。
例えばマテリアルを見ながら、明日の天気は何か答えるような問題です。
最後の1問はカードを基に受験生にミッションが与えられます。
自分の持っている英語力を駆使して、目的を達成するには何と言えばいいか答えなくてはいけません。
例えば、自分のほしい買い物をするには店員に何と言えばいいか答えます。
こちらも同様に、準備時間、解答時間共に10秒となっています。
パートCは4コマイラストの問題です。
この4コマのイラストを見て、英語で何が起こっているか答えなくてはいけません。
30秒の準備時間の後、40秒の解答時間が与えられています。
準備時間の間にどのようなストーリーかイラストから読み取って答えてください。
解答としては、各コマ一文ずつの英語で答えられるといいのではないでしょうか。
最後のパートDでは、質問が書かれたカードが与えられるので、それを読んで英語で答えます。
ここでは質問に対しての自分の意見とその理由が求められます。
例えば、「あなたが学校の一番好きな行事は何か、その理由も答えなさい」のような問題です。
こちらは準備時間が1分、解答時間が40秒となっています。
こちらも準備時間内で自分の意見をまとめておく必要があります。
以上が、現段階での試験内容になります。
例えばパートA、パートBは英検3級の二次試験に出てくる形式ですし、パートC、パートDは英検準2級以上の二次試験の形式になっています。
ただ、受けるのが幅広い学力差のある中学三年生なので、試験の難易度はかなり下げてあります。
これもコツさえ分かっていれば、それほど難しくないと感じています。
実施に当たっては、それぞれの決められた試験会場で、タブレット端末などにヘッドフォンマイクを通して音声を録音する形になるようです。
ESAT-Jの都立高校入試における評価法
ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。
試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。
この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。
評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。
そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。
送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。
つまり、調査書点に加えられるのですね。
その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。
これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。
・学力検査の得点
各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。
・調査書点
中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。
これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。
1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。
入試は1点で合否が分かれます。
だから、例え1点でも疎かにできません。
ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。
尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。
スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。










ESAT-J向け特別講座&スピーキングテスト
葛西TKKアカデミーでは、このスピーキングテストに対応するための短期集中の対策講座を用意しております。
本番ではどのようなテストが出されるのか、パートごとに解説し、実際に問題に挑戦してもらいます。
テストの性格上、講座は一度に一名までとなります。
よって、早めに申し込まないと席がなくなる可能性がありますのでご注意ください。
そして、この講座を受けられると、育伸社が提供する『STE(スピーキングテスト for ESAT-J』を利用することができます。
本番と同じように端末を使い、生徒が実際に問題をやって、自分の言葉で解答したものを録音し、約一週間でテスト結果が出ます。
100点満点で総合点が出され、パートごとの到達度が分かります。
そして、それぞれにアドバイスが付いているので、それを参考に今後の学習に役立てることができます。
対策講座のテキストとスピーキングテスト二回分がセットになった特別企画です。
時間的にゆとりのある夏休み中に受けられることをお勧めします。
何もしないでいきなり本番にチャレンジするのは危険です。
不慣れな状態で危機の使い方も分からにようでは、試験中に操作でオロオロして実力は出せません。
事前に練習し、試験の内容と流れを理解して本番に臨んでください。
そのためには(他の教科も同じですが)模試を受けるのが一番です。
しかも、結果の評価とアドバイスまでもらえるので、これはお得です。
詳しくは葛西TKKアカデミーまでお問合せください。








都立高校入試においてスピーキングテストが現実のものとなってきました。
しかし、多くの生徒や保護者はまだ知らないことが多く、どうしていいか戸惑っていることと思います。
しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。
そのためにも葛西TKKアカデミーで行う『STE』をご利用ください。
現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。
この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。
未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば問題ありません。
逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。
いろいろ分からないこと、不安なことがあると思いますが、そんな時はどうか葛西TKKアカデミーまでご相談ください。




























2022.07.06
明日は七夕!日本古来からの年中行事は実は受験でもよく出ます

明日は七夕。
今年は梅雨明けが早く、明日の天気も良さそうです。
有名な織姫と彦星のロマンス、明日はどうなるのでしょうか。
笹に短冊を飾ったりできなくても、せめて家庭で話題にして家族同士の会話をしてみませんか。
こうやって思い出と結びつけることで、子供たちの記憶にも刻まれ、日本文化への理解もより深まります。
そして、年中行事は学校の教育の中でも大いに活用されます。
だから、勉強のためにも明日は七夕を楽しみましょう。









実は、七夕に限らず日本の年中行事は入試や学力テストなどでよく出てきます。
国語や社会で問題の話題として、また、常識として聞かれることもあります。
伝統的な年中行事を通して日本的な考え方を知ることは、日本人というものを考え直すよい機会にもなります。
更に、今後ますます活発になるであろう国際交流においても、日本の伝統文化を紹介できることは重要になってくるでしょう。
試験のためという枠に縛られることなく、純粋に多彩な日本の行事を楽しみ、日本人の教養としてその意義を理解してほしいと思います。
また、親子間の会話のきっかけとしても年中行事は役立ちます。
年中行事を通し経験を共有し会話をすれば、親子間の距離も縮まり相互理解も深まります。
いじめなど子供が抱える問題の早期発見にもつながるので、親子の交流のためにも是非年中行事を家族でもやってほしいと思います。
最近はなかなか個人で年中行事をやることも少なくなってきています。
小学校や保育園でイベントとしてやったり、先生から教わったりしますが、せっかく日本人として素晴らしい伝統文化があるのだから、しっかりそれを活用し家庭の円満につなげられるといいと思います。
ただ楽しむのではなく、行事の意味や由来を理解し、日本人としての教養を深めるといいと思います。








因みに七夕はどうして行われるようになったのでしょうか。
7月7日は、あの有名な『織姫と彦星』の話で年に一回、二人が天の川を超えて合うことを許される日です。
そして、この『織姫と彦星』のお話はもともとは中国の民間伝承となっています。
それが奈良時代に日本に伝わり、機織りの上手な織姫にあやかり、手芸や裁縫が上達するようにと願ったのが現在の笹に願い事を書いて結びつける習慣になったようです。
時代が下り、願い事が機織りから学芸の上達に変わり、現在では全ての子供たちが自分たちの夢や願いを星に祈っています。









ところで、織姫星と呼ばれる織女星はこと座のベガ、彦星と呼ばれる牽牛星はわし座のアルタイルを指し、どちらも一等星で夏の夜空に明るく目立つ星です。
日本では7月上旬から見えやすくなり、9月上旬ぐらいまでよく観察できます。
七夕のころだと、20~22時ごろ、東の空の下の方に見え始めます。
この時期は農業に適した季節で、その季節に合わせて明るく輝いてくるので、農業や養蚕などをつかさどる星とも考えられました。
この二つの星にはくちょう座のデネブを加えて、「夏の大三角」と呼ばれ、この辺は理科の勉強で習うかもしれませんね。









七夕に食べるものとして、伝統的なものの一つが「索餅」です。
これは小麦粉や餅粉をひねって揚げたお菓子で、唐の時代に日本に伝わりました。
これを食べるのが習慣のようですが、皆さんあまり食べませんよね。
というか、そんなものがあるなんて知らなかった人が多いのではないでしょうか。
実はこれがどんどん進化していって、現在では「そうめん」を七夕に食べるという地域もあります。
また、「索餅」に似たお菓子として「かりんとう」を食べるところもあります。









このように「七夕」一つとってもいろいろと楽しい会話が生まれるのではないでしょうか。
今まで知らなかった知識としてだけでなく、親が自分たちの子供のころどう過ごしたかなんて話すのも面白いかもしれませんね。
日本の伝統行事を家族で楽しんでください。
そして、子供時代の思い出を豊かにしてあげると、将来きっと役に立つし、強く楽しく生きていけると思います。
それでは、明日、少しの間でもいいから雲間に天の川が見えて織姫と彦星が会えますようにと祈りつつ、今日は終わりにしたいと思います。

























2022.07.04
これから高校の見学会や学校説明会が多く行われるので注意点を挙げます

もうすぐ夏休み。
夏休みは大学、高校、中学の学校見学会、説明会がたくさんあります。
コロナウイルスの影響で一堂に集まっての説明会ではなく、小グループでの学校見学ツアーであったり、オンラインのバーチャル見学会であったり、各学校で見学や説明会の方法が違っていますので事前によく調べましょう。
今回は高校の学校見学について気をつけることをお話します。
進学を控えたお子様をお持ちの家庭は、色々な高校に出向くことも多いでしょう。
今回はその時に注意すべき点をお話します。
1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認
入れるならどこでもいいというわけではありません。
入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認するのがいいでしょう。
資料を見てコースやカリキュラムについて分からないことは必ず確認しましょう。
授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。
直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。
2.学校の施設や設備を確認
プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。
部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。
図書館やパソコンも大事です。
特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。
IOTの推進を文科省はうたっていますが、現実にはまだ整っていない学校がたくさんあります。
また、適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。
3.構内掲示や清掃状況を確認
掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。
掲示物がきちんと整理され見やすいか。
廊下や教室が綺麗に掃除されているか。
生徒の日常の営みが現れます。
また部活の賞状などは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。
新しい大学入試制度では当日の試験の点数だけでなく、高校時代での様々な活動への参加などが評価に大きく関わってきます。
学内外の活動に積極的な学校かどうかは、大学受験の大きな要素の一つになります。
4.公開授業は見た方がいいです
公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。
公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。
よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。
だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。
そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。
案外正直に話してくれるものです。
ダメ元で試してみるのもいいでしょう。










学校見学は高校を知る重要な機会です。
事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。
後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。
まめに学校見学などに参加することで、学校の名簿に名前が残ります。
それで学校は自分たちに関心が高いと判断し、入試に有利に評価してくれることが多々あります。
面倒くさがらず、これも受験の一部だと考えて大事にしてください。



























2022.06.26
気温がぐんぐん上昇30度を超え!熱中症対策をしましょう

夏が近づき気温もどんどん上がってきています。
コロナ禍のせいで学校では、生徒たちはマスクをつけなければならず、感染予防と熱中症予防を同時にやらなくてはならないという過酷な環境にいます。
マスクをすれば体温がこもりやすく上がり気味になります。
息苦しさが熱中症を助長することもあります。
また、コロナウイルス感染防止のため学校では窓を開け換気をしているので、教室にエアコンがあったとしても使えないことがあります。
そうなると猛暑の中で勉強しなくてはならない生徒たちが健康を害さないか心配です。
ましてやエアコンがない学校では、勉強どころではありません。
毎年ニュースで熱中症による死者が報じられるなど命にもかかわる問題なので、本日は熱中症について考えてみます。









いろいろ調べてみると、熱中症とは高温多湿の環境に置かれたときに起きる様々な症状の総称とわかります。
その症状はめまい、吐き気、顔のほてり、筋肉のけいれんなどがあります。
対処法としては、こまめな水分補給が第一です。
最近では学校でも水筒を持参させ、いつでも水分補給ができるようになっているところもあります。
ただの水よりスポーツ飲料のような塩分や糖分を含むものがいいでしょう。
汗を活発にかき、知らず知らずのうちに水分や塩分は失われていくので、喉が渇いてなくても水分補給をしましょう。
取り過ぎはいけませんが、食事で失われた塩分を取るように気をつけましょう。
また、暑さに負けない体を作るためにも、普段の食事に気を遣い、バランスの取れた食事をしましょう。
体力を維持するためにも十分な睡眠は大切です。
暑くて夜眠れないようでしたら、エアコンや扇風機を付け、通気性のよい寝具を使いましょう。
これは寝ている間の熱中症の予防にもなります。
直射日光を避け、風通しの良い環境を作りましょう。
服装も通気性のよいものを選び、下着は吸水性や速乾性のよいものにしてください。
冷却シートのような体を冷やす製品を活用するのも有効です。
体育などでどうしても炎天下に出ないといけない場合は、こまめに休憩を取り水分補給をしましょう。
実際に学校では、今は体育の時間はマスクをしていないようです。
文科相も感染防止に留意した上で、体育などの運動のときはマスクを外してよいと言っています。
実際にはなかなか難しいかもしれませんが、気温などに注意しながら熱中症の予防を心がけてください。









もし熱中症にかかったと思ったら、すぐに風通しの良い日陰やエアコンの利いた部屋に行って安静にしましょう。
衣服を脱いで、首の両側や脇、足の付け根を保冷材などで冷やすと体温が下がります。
水で体を濡らしうちわであおぐのも体を冷やします。
水分補給ですが、できればスポーツドリンクの方が塩分も同時に補給できるのでいいでしょう。
症状がひどい場合は救急車を呼んで、病院に行きましょう。









東京はもう真夏のような暑さです。
ここ数日比較的涼しかっただけに、今日のように急激に気温が上がると体調を崩しやすいです。
まだ体も十分に暑さに慣れておらず、この時期は特に注意が必要と思われます。
こんな厳しい環境で勉強をしなくてはならない生徒たちは大変ですが、健康に注意しながら頑張ってください。
勉強も大事ですが特に受験生は体調を崩しさないように気をつけてください。
この時期に病気などで勉強に手がつけられなくなると、受験に大きく響きます。
過酷な環境で無理をしないで、少しでも熱中症対策をして暑さを乗り切ってください。
葛西TKKアカデミーのエアコンの効いた涼しく勉強しやすい教室も利用してください。
いろいろな観点から、いつも皆様の勉強をサポートします。
























2022.06.24
期末テストの後は夏休み!夏期講習受講生募集中!新規生は何と無料!

期末テストも終わった学校が多いと思います。
テストはいかがだったでしょうか。
そして来月には夏休みが始まります。
この長期休暇を利用して、これまで勉強で分からなかったところを徹底攻略しませんか。
または、二学期に向けて先取り学習をして、他の生徒に一歩差をつけませんか。
現在、葛西TKKアカデミーでは夏期講習の受講生を募集中です。








猛暑で勉強するには決していい時期とは言い難い夏休みですが、ここ葛西TKKアカデミーならば涼しくリラックスした空間で快適に勉強に集中できます。
しかも、個別に勉強を分かるまで根気強く見てもらえるので、より深く学べます。
更に、個別指導の塾なので生徒一人一人の状況に合わせた勉強ができます。
生徒たちの学びたい気持ちを大切にしたい。
その強い意志があれば十分です。
後のことは何も心配しないでください。
この夏に葛西TKKアカデミーを体験して、他の塾にはない良さを実感してください。









葛西TKKアカデミーでは夏期講習受講生を募集中
個別指導の葛西TKKアカデミーは一人ひとりの要望に合わせた授業が行えます。
一対一の授業で集中して、これまでに十分にできなかった勉強をしっかりすることができます。
学校の課題を取り組んでもいいですし、学校とは別に自分だけの勉強に取り組むこともできます。
二学期の勉強を先取りして、学校が始まってもゆとりをもって勉強ができるようにするのもいいでしょう。
また、受験生は夏休みをいかに過ごすかで受験の合否が決まります。
公立高校の入試では、今年から英語のスピーキングテストが導入されます。
他の試験と違い実施日は11月なので、早く準備した方がいいです。
このようなスピーキングテストに対応した授業も用意しております。
勉強だけでなく、受験の仕組みを説明してもらえたり、勉強の計画を考えてくれたりもします。
受験生やその保護者の方々の相談にも乗りますよ。
もちろん授業のない日でも利用できますので、どんどん来て自習に使ってください。
家では勉強しにくいし、図書館などはいっぱいで席がなかなか空きませんからね。
ファミレスや喫茶店はお金がかかりますが、葛西TKKアカデミーなら自習は無料でし放題!
静かで快適な環境で勉強し、休憩には用意してあるお菓子でリフレッシュ。
小規模個別指導塾なのでコロナウイルス感染の危険性もありません。
希望があればアプリを使ったオンライン授業もできます。
家にいながら授業が受けられるので、感染の可能性はゼロです。
安心して勉強ができます。
双方向のコミュニケーションツールなので、分からなければいつでも質問できます。
全ての生徒の勉強のお手伝いをしたい葛西TKKアカデミーではただ今夏期講習受付中です。











〈特別キャンペーン情報!〉
お問い合わせの際に「ホームページのブログを見た。」とおっしゃってください。
もれなく次の特典がついてきます。
 今だけお得、五大特典
今だけお得、五大特典
・新規生徒は夏期講習1セット(授業5回分)の授業を無料で行います!
・ご兄弟、友人紹介で1人に付き2000円、2人で5000円、3人で8000円、授業料を割引!
・入会費無料!
・施設利用料無料!
・自習し放題!
葛西駅より徒歩3分、アクセスも便利な個別指導塾、葛西TKKアカデミーの夏期講習
80分授業5回を1セットとして、一人の先生に対し最大2名(たいていは1対1になっています)までの生徒を指導します。
授業内容はこれまでの復習、二学期に向けた予習、学校の課題など、それぞれの希望にお応えします。
一緒に話し合いながら各々に合わせた授業を用意しますので、どんなことでもご相談ください。
五教科の勉強だけでなく、読書感想文や工作や自由研究、何で承ります。
小学生から高校生まで、すべての教科に対応します。
特に中学三年生には受験に向けた授業を準備いたします。
今年は非常に困難な状況ですが、葛西TKKアカデミーが全力でサポートしますから安心ください。
夏休み中に、いかにたくさん学校の授業内容を身に付けるかで、受験結果が大きく変わりますよ。
進路相談も承りますので、進学にお悩みの方は気軽に葛西TKKアカデミーまでお問合せください。




















2022.06.23
勉強がめんどうくさい時の対処法

勉強をしなくてはいけないのに、なかなか取り掛かれない生徒がたくさんいます。
理由は様々ですが、「面倒くさい」をよく口にすることがあります。
そこで今回は、勉強を面倒くさいと感じているときの対処法を考えてみたいと思います。








どうして勉強は面倒くさいのか
人にもよりますが、同じ勉強でも教科によって「面倒くさい」と感じたり感じなかったりしますよね。
ゲームや遊んでいるときも「面倒くさい」と感じたり感じなかったり。
では、この両者の感じ方の違いは何が原因なのでしょうか。
好きなことを夢中でやっているときは、どんなに手間がかかって煩雑なことでも「面倒くさい」とは感じません。
でも、ゲームをやっていても単調で退屈な作業をやっているときは「面倒くさい」と感じることがあります。
また、緊急性の高さも「面倒くさい」と感じるかどうかに関わってきます。
今すぐやらないと生活が脅かされる、身体に危険が迫るなど切羽詰まった状況では、つまらない作業でも「面倒くさい」とは感じません。
勉強も同様に「今何とかしないとマズイ!」というときは、「面倒くさい」なんて言ってられなくなります。
つまり、勉強を「面倒くさい」と思うのは、「やらなくてはいけないのは分かっているのだけれど、やる気になれない」ときだということになります。
好きでもないことで今すぐやる必要性が無ければ、当然後回しにしたいですよね。
ましてや嫌なことであれば、取り掛かろうというアクションを起こすまでに心理的抵抗があり、それを乗り越えるだけで非常に多くの精神的エネルギーを使うので、余計に腰が重くなります。
このように緊急性を感じず好きでもなければ、なかなか手がつかないのは理解できますが、そこに環境という条件が加わると、「面倒くさい」という心理が更に強まります。
自分が勉強するのにふさわしいと考える環境でないと、それを理由に始めるのがもっと遅れます。
環境は勉強に適した形に整えないと、テレビやゲーム、携帯電話が勉強を妨げる誘惑になり、それに引きずられ勉強に手がつかなくなります。
例えば、机や部屋の整理や片付けを始めて、気づけばそれだけで時間が過ぎてしまい、肝心の勉強する時間が無くなったとか。
ここでも本題の勉強に入る前に莫大なエネルギーを必要とするので、実行するまでに面倒くさいと感じずにはいられません。
子は親の鏡
よく子供がどうしてこんな言動をするのかと考えたとき、実は自分たち大人が同じ言動をしていたということはありませんか。
「子は親の鏡」とはよく言ったもので、「面倒くさい」に限らずいろいろなことで、子供は大人から影響を受けています。
子供は大人を実はよく見ていて(大人が見られていないだろうと思うときでも)、よく大人のまねをします。
これは成長において普通にあることですが、良いことだけまねしてくれればいいのですが、悪いことも(悪いことの方が)子供はまねをしてしまいます。
だから、自分がやりたくないことで大人が「面倒くさい」と言ってやらないと、子供は「面倒くさい=やらなくてもいい」と勘違いします(本当は面倒くさくても、やらなくてはいけないことはやらなくてはいけないのですが)。
ましてや、それが嫌な勉強をしなくて済む魔法の言葉だとすればなおさらです。
言葉はやがて行動や思考として子供たちにこびりつき、変えようとしても変えられないくらいに深くこびりついてしまいます。
そうなると周囲はもちろん、本人自身も変えたくても変えられなくなります。
直すには多くの時間と労力、そして時には費用が掛かってしまいます。
それでも成功するかどうか分かりません。
よって、このような余計な手間と負担を避けるためにも、実は大人が自分を律しいつ子供に見られても見本となれるように言動に注意しないといけません。
勉強が「面倒くさい」ときの対処法
先ほど述べたように、「面倒くさい」と感じる原因の一つが、「勉強が楽しくない(好きではない)」なので、勉強を面白く、興味と好奇心を持ってできるようになるといいです。
しかし、基本的に「面倒くさい」と言う生徒は勉強が嫌いなため、何とか勉強を楽しんでもらおうとしても難しいものがあります。
でも、楽しませることは出来なくても、「これまでできなかった問題が解けた!」「全く分からなかったことが少しずつ分かるようになった!」というような具体的なプラスの経験を積み重ねられるようにしてください。
最初は小さなことからでいいです。
「数学の基本問題が解けた」「英単語を10個覚えた」「夜空の星の動きが理解できるようになった」などプラスの体験が増えると、勉強に対する嫌悪感も和らぎ、「面倒くさい」と言うことも減ってきます。
とは言え、これは教える側の技量が大きくものを言うので、一般的にはなかなかできないかも知れませんね(必要な時は専門家に任せる方がいいかも)。
では、二番目の要因であった「緊急性が感じられない」はどうでしょうか。
はっきりと課題に対して期限を設けると「間に合わないからやらなくては」と思うようになるかも知れません。
「いっそのこと勉強を強要しないでおく」という方法もあります。
やらない自分に不安を感じ焦り勉強をやがて始めるという論理です。
「周囲の環境」も「面倒くさい」と言う理由の一つでした。
いつもきちんと整理整頓して勉強に適した環境を整えてあればいいのですが、実際に家で勉強するには難しいものがあります。
そんな時は喫茶店や図書館など、場所を変えてみるのもいいです。
学校や塾の自習スペースなどが利用できれば、それもいいです。
しかし、これらには利用時間の制限がどうしてもあるので、できるなら家の片づけをしてから家庭学習する方がいいでしょう。
それ以外の対策として、家での勉強を習慣化するという方法もあります。
いつも決まった時間に決まった場所で勉強します。
最初は短い時間でいいです。
少しずつならして時間を伸ばしましょう。
習慣化してしまえば、歯磨きをするように、周囲から言われなくても自然と机に向かうようになれます。
それから、自分の得意な教科、好きな科目、やりやすい勉強から始めるといいです。
最初から嫌な教科をだらだらとやるのは苦痛です。
できるところからやって、調子が載ってきて心理的にゆとりができてから、苦手な教科をやると心理的負担も軽くなります。









以上、勉強が「面倒くさい」理由と対処法を考えてみました。
これ以外にも対処法はありますし、人によって適した方法は違います。
やってみたけど上手くいかないこともあります。
そんな時は一人で考えないで、人に相談するのが一番です。
葛西TKKアカデミーでも、皆様のご相談に応じ、一緒に良い方法を考え見つけたいと思います。
「面倒くさい」と言えば勉強をしなくても済むと考えているのであれば、その生徒は不幸です。
人生は面倒くさいことばかりですし、その都度言い訳して避けていけば仕事なんぞできません。
将来を生きるためにも、精神的強さは必要です。
「面倒くさい」ことは、実は試練なのかも知れません。
乗り越えれば一つ大きく成長できるチャンスです。
だから、「面倒くさい」ことでもやらなくてはならないものは責任もってできるようになってください。
こうやって身に付いた心の強さは、子供たちの将来にきっと役に立つと思います。





















2022.06.20
家庭学習の勧め!親が教えられなくても一緒に悩むことで信頼が深まります!

コロナウイルスによる混乱が続く中、家庭学習の果たす役割はますます大きくなっています。
現在学校に通っていても、感染防止などの理由で生徒には以前のような十分な学校教育が提供できていません。
そして、学校で十分にできなかった部分は家庭で補うしかありません。
だから、先手を取って親が子供のために先生になって対応する家庭も多いです。
しかし、親が勉強を教えるとき、どうしても自分の子供が言うことを聞かず、基本的なことすらできないでイライラしてしまう、挙句の果てにはケンカになり、お互いに気分が悪くなっておしまいということを経験した人も多いのではないでしょうか。
または、保護者の中には「自分が勉強を教えるなんて無理」という方もいるでしょう。
それでも、家庭学習で親が家庭で教えることの意義とちょっとしたコツについてお話します。
(万が一、勉強を教えることが困難な場合は、安心してください、葛西TKKアカデミーが必ずお力になります。
コロナウイルスでも安心なオンライン授業もありますし、小規模個別指導塾なので「3密」にもなりません。)
困ったときは外部の支援を利用するのもいいですが、先ずは家庭学習にチャレンジしてみませんか。
家庭学習で見せる親のその姿勢が子供に単なる知識の習得以上のメッセージを伝えます。












「自分は勉強ができないから子供に教えることができない。だから家庭学習なんて無理。」
このようにお嘆きの家庭も多いと思います。
だから、自分が教えられない分は塾で教えてもらう。
それはそれで間違っていません。
親が勉強を見られたら何の問題もないでしょう。
でも、それができないから家庭学習をしないというのは少し違います。
なぜなら、家庭学習には勉強を学ぶ以外の効果があると思うからです。
家庭学習のメリット:親子関係を改善し、子供の問題に早く対応できる
家庭学習が持つ最大の強みは親子が時間を共有できることにあります。
同じ問題に取り組み、一緒に悩み、色々話しあって解決に向かう。
この経験を共有することが、親子間の信頼や親密な関係を育てるのです。
これこそが家庭学習の最大の意義だと思います。
分からなくていいのです。
お互いにアイデアを出したり、時には本やインターネットで調べてみる。
解けなければ、塾や学校の先生に子供が聞いて、帰ってから親に説明する。(この説明する行為も子供の習得に役立ちます。)
こうして共通の話題を持つことで、何でも話し合える環境を作ります。
このことは、外部からは分かりにくいいじめなどの学校で子供たちが抱える問題の早期発見につながります。
家庭学習を通して勉強だけでなく、子供の置かれている状況や考え方を把握し、必要な時は迅速な対応が取れることは非常に大事です。
子供が孤立してしまうと問題はどんどん大きくなり、気づけば取り返しのつかないことになりかねません。
そうしないためにも親子で健全な人間関係を築くことは大事です。
自分たちで子供に教えるので、塾のような料金が当然かかりません。
夜遅くに通塾する必要もないので、子供たちの身の安全を守るという意味では非常にいいです。
また、家にいるので、子供たちは分からないことをすぐに聞けるというのも家庭学習の利点になります。
子供が分からないときに教えてくれる人が周りにおらず、後で聞こうと置いておくと大抵機を逸して聞かないまま終わることが多いです。
そうして「分からない」を放置したまま勉強が進むと、自分の分からないところが増え挽回不可能に思えて、勉強するのが嫌になって「勉強嫌い」が生まれてしまいます。
よって、家庭学習で初動を適切に行えば、その後の勉強において問題になることはあまりないでしょう。
家庭学習の注意点
「分からないから自分でやりなさい。」、「先生に聞きなさい。」と言われると、子供たちは突き放されたような気持ちになります。
面倒かもしれませんが、子供たちに付き合ってあげてください。
コツとしては時間を決めることです。
そうすれば、お互いにだらだらを時間をかけることもなくなります。
1時間だけでもいいので、一緒に考えてあげてください。
この経験が先ほど述べた信頼を築くのであれば、十分にやる価値はあります。
こうして小さい時から習慣として家庭学習ができると、学年が上がって家での勉強がより必要になるとき、子供たちは苦しむことなく自然に勉強に取り掛かることができるのです。
こうして大きくなっても、親子で無意識に何でも話せる関係を維持できるのです。
学習内容は技術の進歩や学術的新発見、教育パラダイムの変化などで大きく変わります。
「自分たちが習ったときと違う」「自分たちはそんなこと習わなかった」なんてことはよくあります。
だから、親が自分の学んだことで教える前に、今の学校の勉強が自分たちのときと同じかどうか確認する必要があります。
自分たちが子供のころに勉強した内容をそのまま押し付けると、子供たちは学校で学んだことと違うので、反って分からなくなったり混乱してしたりします。
よって、親が教える前には必ず、子供たちの教科書などを見て自分たちのやり方で間違っていないか、やり方が古くなっていないかチェックしてください。
それから、教え方にも注意してください。
自分が教えられるから、問題が解けるからと言って一方的に問題を解いてみせ、子供たちに考えるチャンスを与えないのはNGです。
勉強を教えるプロではないので難しいかも知れませんが、基本はヒントを与え誘導し、子供たちに考えさせ、自ら解けるようにするのが理想です。
そうでないと子供たちは全く頭を使っていないので、理解も浅く記憶としても残りません。
また、「勉強が分からないときは全て教えてもらおう」という依存体質を作ってしまい、自分から考えることができなくなってしまいます。
できるからと言って得意になって何でも教えてあげたくなる気持ちは分かりますが、子供のことを考えるならば少し抑えて、彼らの自分から考える機会も与えてあげるのがコツです。








子供は成長に伴い、様々な壁にぶつかります。
そんな時、周りに信頼できる大人がいることが大きな救いになります。
そのための準備として家庭学習をお勧めします。
「やりなさい」と言うだけでなく、一緒に寄り添ってあげてください。
時間を共有することで子供たちの勉強を手伝うことができるばかりでなく、子供たち自身のことも多く知ることができます。
そういう意味でも家庭学習の果たす役割は大きいです。
しかし、勉強を教えるということは簡単ではありません。
特に専門家ではない保護者にとって、どうすれば子供にとって一番効果的な学習をさせてあげられるかという問題は難しいかも知れません。
教えるときの注意点に気をつけながら、子供と一緒に親自身も何らかの成長や学びがあるといいでしょう。
それでも、勉強を教えることが難しいようでしたら、専門家にお願するのも一つの手です。
葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
いつでも皆様の力になれるように準備しております。































