塾長ブログ
2021.05.08
コロナウイルスで学校や塾が休みになる中、オンライン授業に注目が集まっていますが、オンライン授業ってどんなものでしょうか。オンライン授業だから全く問題ないという訳でもなく注意が必要です。

コロナウイルス感染の恐れから、外出して人と接することなく、家にいながら授業が受けられるオンライン授業に注目が集まっています。
文科省も以前から計画していたGIGAスクール構想を前倒しにして、新年度が始まるまでに全ての小中学生に一人一端末割り当てられるように配布しています。
しかし、現実にはただ端末を配ればうまくいくというものではなく(まだ全ての生徒に届いていない学校もあるそうですが)、その使用に関してはWi-Fiなどの設備、使用に関するルール、実際に実用可能か教員と生徒の両者のトレーニングなど、まだまだ課題は多く、今回の緊急事態宣言でもオンライン授業を滞りなくできたところは少ないようです。
そこで、本日はオンライン授業とは何か、そしてその注意点についてお話したいと思います。










オンライン授業には大きく二つのタイプがあります。
1.同時双方向型
これはZoomやSkypeなどのアプリを使い、生の授業を行うものです。
簡単に言えばいつもの教室で行う授業と同じですが、オンラインを使うことで同じ空間にいなくてもいいというものです。
リアルタイムで授業が配信され、先生の授業を聞きながら、時には先生の問いに答えたり、先生に質問したりできます。
場合によっては何十人、何百人が同時に授業を受けることも可能です。
画面に映る先生を見ながら講義を受け、時には画面を切り替えて問題を解いたり資料となる動画や画像を見ることもできます。
一人の先生に対して多数の生徒が授業を受ける場合、双方向と言っても実際に生徒から質問できるかというとそうでもないようです。
よって、一方的な講義になることが多いです。
一人の先生が複数の生徒に授業を提供できますが、先生は分割された画面を通して生徒を見ているので、人数が多ければ多いほど生徒一人ひとりに目が行き届かなくなります。
つまり、授業についてこられる生徒、授業に関心を持って積極的に取り組む生徒はいいのですが、そうでない生徒は放置されやすく、先生も気づけない場合が多いです。
先生がオンライン授業に不慣れであると、やはり授業が分かりにくくなり生徒は勉強への意欲を失います。
特に技術的な面でもたもたしたり、途中で回線が切れたりすると勉強への集中力も切れ、授業がつまらなく感じる、イライラする生徒も出てくるでしょう。
技術的な面といえば、一度に多くの生徒がアクセスするとサーバーがダウンしたり、そうでなくてもバグや様々なトラブルが起こり、授業自体が続けられないというアクシデントも予想できます。
先生自体が機械の操作をよく理解できておらず、思うように操作できなかったり、本来の機能を十分に使いこなせないこともあります。
また、塾や予備校では授業の時間はその先生を拘束することになるので授業料が高くなります。
そして、場所は選ばないと言っても時間は決められているので、授業を受けるためには必ずその時間にスマホやパソコンなどの前にいなくてはなりません。
学校や塾という専用の環境でなく、本来勉強の場でない自宅でのオンラインを介した授業なのでどうしても緊張感に欠けてしまいます。
周りには誘惑も多いでしょうし、どうしても勉強に集中できないこともあります。
勉強が嫌ならば他のことをすることだって可能です。
自宅で受けられる授業はある意味便利ですが、先生と生徒がツールを十分に使いこなせるか、生徒が自覚をもって真剣に授業に取り組めるかで成果は大きく変わってきます。
一般の授業以上に生徒次第の部分が大きくなることに注意しなければなりません。
2.オンデマンド型
こちらはアプリなどを利用し、あらかじめ用意された教材を使って勉強するものです。
よくあるのは録画した講義のビデオ、音声付きパワーポイント、問題を実際に解けるドリル、その他関連資料となる動画や画像などです。
多くの塾や無料アプリで提供されるオンライン授業はこのタイプです。
一般的には最初に講義を動画で見て、その後実際に問題を解いて理解を確認する形で行われます。
問題の成績は記録され、塾など管理者はそれを見て生徒の勉強の進み具合を確認することができます。
それを見て生徒に個別指導することもありますが、授業以外にも仕事の多い学校の先生はそこまで手が回らないでしょう。
教材はあらかじめ用意されたもので、それを生徒は見たり解答するだけなので、費用が低く抑えられます。
また、場所だけでなく時間も自由で、自分のペースで勉強を進めることができます。
でも、それは自分がやりたくなければいくらでも後回しにできるということでもあり、自己管理能力が求められます。
分からないときは何度でも繰り返し動画を見たりできますが、双方向ではないので質問したくてもできません。
問題にも限りがあり用意されたものをやりつくすと、それ以上の学習は期待できません。
つまり、一般の授業のように状況に応じて柔軟に授業内容が広がらないので、生徒によってはつまらなく感じるかもしれません。
このタイプのオンライン授業はあらかじめ決まっているものなので、一人ひとりのレベルに合わせられません。
学力が低い生徒にはついていけないし、学力が高い生徒には物足りないものになるかもしれません。
いずれにしても、このオンライン授業だけで全てが足りると思わない方がいいです。
十分に理解し習得するには補足の勉強が必要で、結局先生に相談することになります。
こちらも生徒がどれほど自覚しツールを有効に使って勉強を進められるかが問題になります。
これまでの一般的授業以上に学習結果が生徒次第で左右されることになります。
最後にどちらのタイプでもインターネットに接続できる設備が必要です。
スマホやパソコンなどを必ずしも全ての生徒が使用できるとは限りません。
常に誰もがインターネットへのアクセスが可能な環境をどのように整えるかもオンライン授業を実践するための大きな課題です。
それは道具の提供だけでなく、利用者が不自由なく使いこなせるようになる訓練も含みます。










以上、簡単にオンライン授業とはどのようなものか、そして、その長所と短所に触れました。
実際にコロナウイルスで学校が休校になり、オンライン授業が受けられる学校とそうでない学校の間に教育格差が生じました。
そこでオンライン授業が注目されているのですが、オンライン授業ならば問題ないと盲目的に思うのはいけません。
何でもそうですが、オンライン授業もツールである以上、関係者がいかに上手に使いこなせるかで結果が変わってきます。
これまでの通常授業になかった注意点があります。
特に生徒の勉強に取り組む姿勢が、これまで以上に成否を分けます。
しかし、これがなかなか難しい問題です。
現在ブームのようになっているオンライン授業ですが、決して万能ではないということを十分理解し、心して活用してほしいと思います。
葛西TKKアカデミーもオンライン授業を提供しています。
こちらに関しても後日ご紹介する予定です。
少しでも興味関心をお持ちでしたらお問合せいただいても構いません。
TKKアカデミーは皆様の味方です。
いつでも全力をもってサポートする用意があります。
生徒たちには非常に厳しい状況ですが頑張ってください。
応援しています。



























2021.05.07
書籍紹介『名前のないことば辞典』皆さんが考えている辞典とは違い、様々な動物たちが織り成す物語の中で言葉を紹介している絵本のような、一風変わった辞典です。
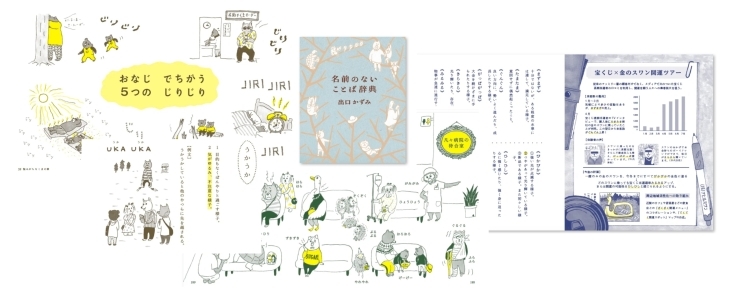
事典というと分厚く、どんな知りたい言葉でもしっかり説明されているイメージですが、今回ご紹介する『名前のないことば辞典』(出口 かずみ)は違います。
こちらの事典はオノマトペ(擬音語・擬態語)を扱ったものなのですが、普通の辞典のようにそれぞれの単語が見出しとなって、そこに語の説明がついているという形式にはなっていません。
「では、どうやって言葉を理解するの。」と思われることでしょう。
実は、絵を使って状況を描写しながら、オノマトペを分かりやすく示しています。
同じ「じりじり」でも色々な意味があるんだな、病院など特定の場面でよく使うオノマトペにはどのようなものがあるのだろう、なんてことがイラストを使って理解しやすく表現されています。
しかも、ただイラストが並んでいるのではなく、一つのお話となっているので、辞書を引くというより、物語を読みながら言葉を理解するという工夫がされています。
しかも、登場しているキャラクターは全て動物でとてもかわいく、それがコメディーのように様々な事件や出来事を繰り広げているので、本当に面白い読み物として読むことができます。
大人だけではなくお子様もきっと楽しく、そして、夢中になって読むことでしょう。









オノマトペと言うのは日本語の特徴の一つで、その豊富さは他の言語を圧倒します。
言葉が豊かということは微妙な違いやニュアンスも表現できるということで、日本という独特な空間で長い歴史をかけて培われた言語だからこそできる技です。
オノマトペもそんな背景から発達したもので、日本人なら当たり前のように表現していますが、実は外国語で同様に表現しようと思うと非常に難しく苦労します。
しかも、この感覚は言葉を知れば分かるものではなく、日本という社会の中で生活し自分の経験を積み重ねることで初めて習得し理解できるものです。
日本語が多言語より難解と言われる理由はそこにあります。
単語や文法を知るだけでなく、文化的背景や社会的側面、人間関係の在り方などと直接日本語は結びついているのです。
日本人なら誰でも感覚的に理解できる「ヒューヒュー」と「ピューピュー」の違いも、日本語を学ぼうとする外国人には非常に大きな壁となって彼らの前に立ちはだかります。
普通の辞典のように言葉だけで分かればいいのですが、本書のようにイラストになった方が視覚的になって理解しやすいと思います。
しかも、ストーリーになっているので、使用の文脈など、一般辞書では書かれないことも理解できます。
楽しいイラストと面白いストーリーで、これはまさしく読む辞典です。
堅い勉強ではなく愉快な余暇の感覚で、オノマトペについて知識を深められる最高の一冊だと思います。









この本は遊泳社が出版する“言葉を楽しむ辞典”として立ち上げた「YUEISHA DICTIONARY」というシリーズの中の一冊です。
他にも『悪魔の辞典』『ロマンスの辞典』『言の葉連想辞典』があり、こちらも同様に非常に面白い辞典になっています。
本当に面白いので、こちらも後日、紹介させていただきます。
葛西TKKアカデミーではこのように楽しく学べる機会を重視しています。
勉強が苦しみではなく楽しみなのだと分かってくれることを願います。
























2021.05.06
図表問題を解けるようになろう。教育改革に伴いこれからは与えられた資料から情報を読み取り、その意味を考える問題が増えていきます。そんなときも臆することなく答えられるようになりましょう。
葛西TKKアカデミーのニュース

教育改革により、これまでのような暗記中心の教育が見直され、これまで学んだことを使って自分で問題を分析し、自分で解答を考えなければならない問題がテストでもたくさん出されるようになります。
生徒の中には、表や図を見て何を示しているのか理解できず、または図表があるというだけで挑戦しようともせず投げ出してしまう人がいます。
しかし、文科省の方針に従えば今後、図や表、グラフなどを利用した問題は数学や理科だけでなく様々な教科で導入されることは明白です。
よって、これらを苦手とする生徒はテストや試験では非常に不利になることが見込まれます。
では、これらの問題にどのように取り組めばいいのでしょうか。









1.先ずは問題をよく読む
何に答えるか。
これは全ての問題に共通していますが、正しく答えるためには、先ずは正確に問題を読み取り、出題者の要求する者が何かを把握しなくてはいけません。
例え図や表をきちんと読み取れても、問題の意図を読み違えて求められていない解答をすればバツになります。
基本的に問題の前半は条件、後半は何を答えてほしいのかが書いてあります。
従って、問題の条件部分から自分が何に注目して図表を見ないといけないか理解し、そこから図表の何を捉えなければならないか、後半部分から考えます。
例えば、「グラブの2000年と2010年を比較し」とあればこの二つのグラフのみに注目し、他の年は見てはいけません。
更に、「石油の輸入が全体で何パーセント減りましたか」と書かれてあれば、輸入量ではなく全体に対する割合を出して答えないといけないということです。
しかも、「パーセント」でないといけません。
2.グラフや表そのものを見る前に、その周りを見る
図や表を見て考えなければいけないのですが、その前にそれらの周囲に書かれているものを見ましょう。
タイトルには何の話題についてのものか、何を示そうとして書かれたものかが書いてあります。
数量の単位や何が図表内に示されているか正確に分かっていないといけません。
縦軸、横軸が何を示しているかも大切です。
このように図表そのものが何を表しているかを理解しましょう。
3.グラフや表の特徴を知りましょう。
いろいろな図や表がありますが、それぞれに特徴があり、何を示すのに適しているかが違います。
例えば、時間的変化を表すなら折れ線グラフや棒グラフが適していますし、全体に対する割合を見たいなら帯グラフや円グラフが適しています。
二つの要素による組み合わせの結果を見たいなら二項対立の表が分かりやすいです。
また、地図もたくさん種類がありますが、距離や面積、方角など何が正確で何が不正確かが違います(実物である地球は空間上の球体で、これを平面で表すには必ずゆがみが生じ、何かを犠牲にしないといけません)。
何が正確に描かれているかが分かれば、不正確なものからは解答は出ないので、問題を解くヒントになります。
このように図表の特徴を理解していれば、問題がこれらを使って何を示し何を要求しようとしているのか分かります。
そうすれば問題に対して的確に答えることができます。
4.図表が示している特徴や変化を読み取る。
基本的に問題は図表から読み取れる特徴や変化を問うものが多いです。
最も多いものは何か、最も少ないものは何か。
時間が経つにつれ増えているのか減っているのか。
あるものが多い地域は他のものも多い。
あるものの増減は他のものの増減と一致している、または逆になっている。
このような特徴や変化、関連性を見つけましょう。
そんなに複雑に考える必要はありません。
問題に要求されているものが一つ分かればいいのです。
5.必要であれば図表内の要素同士、またはこれまで学んで得た知識から関連性を考える。
図表の読み取りだけを目的としている問題であれば4までで十分ですが、中には図表から分かることに基づきその関連性や因果関係を考えさせる問題もあります。
予備知識がなくても問題ないの図表の特徴から推測できるものもありますが、問題内に書かれていない、これまで自分が学んできた知識を使って考えさせるものもあります。
問題内の情報から推測可能な問題は是非チャレンジしてほしいです。
なぜなら、学校で習ってなくても、たくさんの知識がなくても、図表の読み取りができれば解ける問題だからです。
また、学習で得た知識を必要とする問題も、その問題の意図が理解できれば、「ああ、学校で習ったこのことを答えさせたいのだな。」と分かるので、その知識を図表と関連付けすれば簡単に答えられます。
例えば、「時代が経過するにつれて日本の産業は第一次産業から第二次、第三次産業へ移行していく」ということを学んで知っていて、問題内のグラフで産業構造の変化が示されていれば、「グラフから分かることとして、あれを答えればいいのだな」と分かります。
ただ、稀に予備知識と異なる事実を示す図表をわざと出して、それに気づけるかを問う問題もありますので、注意してください。
答える時はあくまでも図表に基づいて答えるのが基本です。









図表を使った問題はこれからどんどん増えていくことが予想されます。
文科相がそのように示しているからです。
でも、コツさえ分かっていれば意外と答えるのは簡単です。
図表から分かる単純な情報の一つを読み取る問題が多いので、図表を見ただけで最初から難しそうとあきらめるのは止めましょう。
慣れないうちは大変ですが、それは何でも同じです。
方法を理解し練習するだけです。
練習としてはテレビや新聞、ネットにあるニュースを利用することをお勧めします。
その時々で実際に話題になっていることの図表なのでより身近で理解もしやすいからです。
そして、親子でその話題について話し合い、どうしてそうなるのか一緒に考えれば、図表の問題を解く練習になるだけでなく、話題に関する知識も深まり一石二鳥です。
更に、親子の会話も生まれ、家庭内の人間関係も良好になっていくでしょう。
また、議論の中から自分の意見を確立することもこれからの教育で求められ重要になっていきますので、これを機に、何を根拠にどうして自分はそう考えるか、相手はそう考えるのかということを理解できるように訓練するのもいいと思います。
もちろん、うちで指導するのは難しいというご家庭は葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
こちらで親切丁寧に指導してまいります。
























2021.05.05
「何か詳しくは知らないけど、聞いたことあるなあ」これがあると勉強により取り組みやすくなります。これからの勉強のために、ゆるくていいのでつながりを増やしましょう!

新学年が始まり一ヶ月、学校生活にも慣れてきた頃でしょうか。
コロナで外出は自粛で窮屈なゴールデンウィークとなっていると思いますが、学校がまとまった休みだからこそできることをしていただけるといいかと思います。
一緒に料理を作るとか、一緒に散歩がてら公園の花を見てみるとか、インターネットで動画を見てみるとか、コロナの危険を避けつつ、何か家族でできる活動ができるといいですね。
どこも行けないから家でじっとして何もしないのはもったいないです。
ゴールデンウィークだからという訳ではないのですが、子供のうちに色々な体験をさせることは非常に重要です。
それが直接勉強に関わっていなくても大丈夫です。
経験の豊かさは、子供たちの思考の豊かさにつながり、ひいては人生の豊かさにもつながります。
葛西TKKアカデミーも子供たちに様々な体験を持たせることをお勧めしますが、一応塾なので、「勉強に役立つから」という観点でお話します。









人間というものは未知のものには警戒感を抱き、距離を置きたくなるものです。
この感情を乗り越えて手を伸ばそうとするには、よほど強い意志や勇気が必要です。
(好奇心が強く、不用心に手を出す人もいますが )
)
実は勉強も同じで、子供たちは日々新しい、未知のものに挑戦しないといけません。
いつも授業で新しい知識を習う訳ですが、その時、新出事項が全く未知のものであればどうしても敬遠し距離を置いてしまいます。
「なかなかとっつきにくい。」「訳が分からない。」というような感情が起こり、勉強に対して軽い抵抗感、拒否反応が起こるかもしれません。
そうなると、それを改善してから勉強に取り組まなくてはならず、余計なエネルギーが必要となってしまいます。
そうなると楽しくなくなりますし、嫌な気分になるかもしれません。
勉強に対する壁ができてしまうと勉強の効率が悪くなります。
それを回避するためにはちょっとした予備知識やささやかな親近感があればいいのです。
これはその勉強に関する知識を前もって全て知っていなくてはならないというものではありません。
そこまですでに分かっているのなら、その単元はもう勉強する必要はありません。
ここで言いたいのはわずかなつながりがあれば、それをきっかけに親しみがわき、未知の分野に対する壁がなくなっていくということです。
つまりどういうことかというと、例えば微生物の勉強をするとき、微生物のことはよく知らなくても、以前に図鑑でミジンコやミドリムシの写真を見たというつながりがあれば、それだけで全く未知という訳ではなくなるので、その勉強に取り組みやすくなるということです。
この予備知識や体験がその勉強に深くかかわっていればいるほど、新しい学習に対する理解度は上がります。
だから一番いいのは、お子様の教科書を見て、何を新しく勉強するかを把握して、日常の会話や活動の中にそれらの話題を盛り込むことです。
関連のあるイベントや展示会、博物館などに一緒に行くのもいいでしょう。
(例年であればゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇期間中はこれらが沢山なるのですが、コロナ禍の現在では少し難しいかもしれません。)
または、インターネトや動画、本、雑誌、新聞などを利用して子供たちと一緒に見たり話したりしてあげるのもいい方法です。
こうしてこれから習うことに関連した経験や思い出を作っておけば、学校で学習するときに役に立ちますし、勉強に対する抵抗も少なくなります。
抵抗なく親しみが持てれば、新しい学習内容の習得もうまくいきます。









このように学校の学習内容に合わせて子供たちに経験や話し合いを促すのは効率的でありますが、実は与えるべき経験は学校の教科書に即したものでなくてもいいのです。
大事なのはいろいろなことに触れ、いろいろなこと浅い深いに関係なくつながりを持つことです。
なぜなら勉強において、どこでどのように経験が結びつくか分からないからです。
経験の範囲が広ければ広いほど勉強とつながる可能性が高くなります。
だから、お父さんの趣味の釣りでも構いません、お母さんの趣味のお菓子作りでも構いません。
何でも体験させてあげてください。
何がどのように子供たちに影響を与えるか分からないので、豊かな経験をさせてあげることは子供たちの人生に大いに役立ちます。
受験や検定試験の英語の問題でよく文化や歴史、科学が話題になることがあるのですが、例えば、長文問題でアインシュタインの相対性理論の話が出たとしましょう。
英語で何が書かれているのかよく分からなくても、相対性理論のことを本などで読んで理解していれば、だいたい何が書いてあるのか想像がつきます。
しかも、なじみがあるというだけで問題に取り組みやすくなります。
(逆になければ、相対性理論という言葉だけで白旗を上げてしまうかもしれません。)
これはテストにおいて大きなアドバンテージです。
私も指導において様々なことに興味を持ち、色々なことに触れるようにと伝えています。
それは以上のような理由があるのです。









ゴールデンウィークも後わずかですが、せっかく家族でいる機会があるのであれば、このようにお子様を誘っていろんなことにチャレンジしたり、一緒に話し合ったりするのもいいでしょう。
もちろんゴールデンウィークや長期休暇にこだわることはなく、少しでも子供が興味持ちそうだな、子供の役に立ちそうだなと思えばいつでも経験させてください。
それは難しく苦労することでも構いません。
成功しても失敗しても何らかの得るものはあるはずですし、後で思い返すと楽しい思い出になります。
勉強のためでもありますが、子供たちの豊かな人生のためにも、どのようなことでも貪欲に手を出し、可能な限りやらせてあげましょう。
























2021.05.04
五月病に注意!適切に対処しないと学校に行けなくなり、不登校のきっかけにもなります。

ゴールデンウィークが明けると社会人と同様に、子供たちの間にも「五月病」が広まります。
個別指導塾葛西TKKアカデミーでは、五月病などをきっかけに不登校になった生徒にも指導を行い、学校に行けない状況でも学力が落ちないようにお手伝いできます。









新しい環境に慣れるために4月は緊張状態が続きます。
特に現在はコロナウイルスの影響で、これまでのように自由な生活が送れていないこともあり、例年以上に緊張を多くの生徒は強いられています。
そんな過度なストレスにさらされ、新年度になっても新しい人間関係がなかなかうまく築けない。
結果、意欲が低下し無気力になり、一種のうつ病のような状態になることを「五月病」と呼びます。
五月病の睡眠障害は特に深刻で、免疫力の低下や偏頭痛やめまい、食欲不振になります。
精神的にもやる気の喪失、気分の落ち込み、情緒不安定、焦りと不安、イライラが起きます。
辛い4月を過ぎ、5月に長期の連休になり圧迫環境から解放され気が緩み、体のあちこちに不調が現れます。
そして、連休が終わるとき再び元の環境に戻れなくなります。
例えそれほどの精神的不安がなくても、ゴールデンウィークの間に生活リズムが壊れ、元の規則正しい生活に戻れないこともあります。
子供の場合、新入生は今までとは異なる学校生活に適応できなかったり、勉強も急に高度になりついていけなくなったり、友達や先生、先輩などの人間関係と様々な不安がのしかかります。
そこにパワハラやいじめなどの問題が絡むと、事態はより一層深刻になります。
それまでいじめなど、学校で嫌な思いをしてきた生徒にとってはゴールデンウィークや学校の長期休暇は、そんな悪夢から逃避できる時間でしたが、学校が再開すればまた辛く苦しい日々がやってくると思えば、やはり精神的に病み学校に復帰するのができない生徒もいます。
本人に自覚がなくても、家を出る時に腹痛になったり、朝が起きれなくなります。
起立性調節障害などと呼ばれることもありますが、つまり、体が無意識に学校に行くことを拒否するのです。










対処法としては病院に行き医師と相談することですが、現代の医療でも正確に症状と原因を把握することはできず、様々な薬や治療と試しながら様子を見、最も効果的なものを手探りで探すような場合がほとんどです。
治療とは別に一般に行われている対処法としては、本人にプレッシャーを与えないというものがあります。
焦って無理やり学校に行かせたりすると、かえってストレスが強まり症状を悪化させることがあります。
できるだけ本人のペースで、先ず生活リズムを整えることに集中するのがいいそうです。
そして、家に閉じこもってばかりいるのではなく、外に出て適度に運動をすることも大切です。
これは体内時計を整えたり、体力の維持につながります。
何であれ体力は必要ですから。
それから、子供との対話を増やすのも大事です。
対話がストレスの発散になり、相互理解を深め、安心感を与えます。
そうすると、気持ちも楽になり復帰もしやすくなります。
学校をしばらく休むことにもなりますので、家庭や学校、病院が密に連絡を取り合い、協力して生徒の回復に努める必要があります。
誰かに押し付けたり、本人をほったらかしにしてはいけません。
様々なアクターの連携が、子供たちを五月病から回復させるカギになります。









五月病は子供たちの性格や考え方など、精神面の影響が非常に大きいです。
まじめで頑張り屋さんに限ってなることが多いです。
何ら悪い生徒ではないのに、本人も学校に行きたいのに行けない。
これは本当に不幸な話です。
初期対応を誤ると長引き、いつまで経っても学校に戻れなくなります。
当然、学力や出席日数など、受験にも影響が出ます。
希望通りの進路を断念しなくてはならなくなることもあります。
それは可哀想過ぎます。
そんな生徒を生み出したくはない。
葛西TKKアカデミーは生徒のために可能な限り力になる用意があります。
早めの対応に越したことはありません。
少しでも不安があれば気軽にご連絡ください。



























2021.05.01
ゴールデンウィークは実体験をするチャンス。実体験の豊かさが勉強で必要な抽象概念の理解に役立ちます。様々な活動をして経験を増やしましょう。

ゴールデンウィークです。
学校が休みになり、普段できない経験をするには良いチャンスです。
今年はコロナ禍で外出するにもままならない状況ですが、工夫をすればいろいろ経験ができます。
そして、多くの経験を積むことが子供の成長に良い影響を与えます。
今回は学校の勉強でも生徒たちが苦戦する抽象的概念に関連してお話したいと思います。










学年が上がると、学校の勉強で抽象概念を多く学びます。
しかしその時、はっきりしたものでないので、何を言っているのか分からず、多くの生徒が挫折してしまいます。
そんな時役立つのが具体的経験です。
「例え」などがそのいい例ですが、よく分からないものを具体的なもので示すことによって理解しやすくする手法です。
分数は小学生や中学生がよく分からなくなるものの一つです。
しかし分数を考える時、実際に「ケーキをみんなで等しく切り分けた経験」があれば、分数の理解がより簡単になります。
具体的経験により抽象的概念がイメージとしてとらえやすくなります。
また、抽象的概念が理解できれば、別の具体的事例に当てはめることができます。
このようにして具体的経験と抽象的概念は、お互いを補う形で理解をより深めるのです。










最近は学びにおいては「砂漠の時代」と言われています。
便利になり何でも簡単に調べられる代わりに、知識が印象に残らない。
バーチャルな空間でいろいろ見聞きすることはできても、体を使った実感として知ることができない。
このような現状を指して、そのように言われています。
環境が変わり、昔当り前であったことを経験していないのです。
頭で知っているだけで、本当に理解していないのです。
本来脳は刺激を多く受けることで、神経細胞のネットワークを密にして、思考を高めていきます。
この刺激は苦労することで強まるのですが、便利なツールにあふれ、面倒くさいことが悪いことのように扱われる環境では、なかなか神経ネットワークも発達しません。
知識が深く根付いていないのですぐに忘れてしまう。










ゴールデンウィークなので普段できない体験を家族や友人と一緒にたくさん積んでください。
そこでは発見や驚き、喜びや共感、様々な刺激が満ち溢れています。
これらの出来事は思い出として心に残るだけでなく、その後の学びにおいて非常に有益なものになります。
外に飛び出して、自然や社会に触れ、実感をたくさんしましょう。






























2021.04.29
中学で習うメンデルの遺伝の法則。その中の「優勢の法則」ですが、今年度から用語が変わるそうです。
葛西TKKアカデミーのニュース

皆さんは中学のとき遺伝の勉強で「メンデルの遺伝の法則」を勉強したことを覚えていますか。
修道院のメンデルという人がえんどう豆を使って交配実験をし、遺伝の基礎となる法則を発見した話は有名です。
彼が発見した「優勢の法則」「分離の法則」「独立の法則」は現在でも通用しますし、多くの中高生が学校で学ぶ項目となっています。
ところで、今回話題になっているのは、メンデルの遺伝の法則の中の「優勢の法則」です。
今年から新しい学習指導要領になり、学校の多くの場面で変化が起こっています。
中学の教科書も新しくなり、その中の理科では「優勢の法則」に関して、これまで使っていた「優勢・劣勢」の言葉が見直され、「顕性・潜性」という言葉に変わります。










「優勢・劣勢」とは何かというと、生物が親から受け継いだ、その形の特徴を生み出すのに遺伝子が大きなファクターとしてはたらきます。
その時、表れやすい形質と表れにくい形質があります。
その表れやすい方の形質を「優勢」、表れにくい方を「劣勢」と呼びます。
例えば、天然パーマの髪とストレートの髪では、天然パーマの方が「優勢」、ストレートの方が「劣勢」となり、親のどちらかが天然パーマの場合、子供の髪質も天然パーマになる可能性が高くなります。
しかし、「優勢」だからと言って、天然パーマの方が優れている訳ではありませんし、ストレートヘアーは「劣勢」だからと言って劣っている訳ではありません。
あくまでも形質の出やすさにおいて「優勢」であり、「劣勢」であるということです。
ところがこの「優勢」「劣勢」の表現が誤解を招くとして随分前から指摘されていました。
まあ、きちんと理解していれば優劣を言っているのではないことは簡単に分かるのですが。
「優性遺伝子の方が優れているから優秀だ」という誤ったイメージを持たせるとかねてより言われていました。
私が中学生のときも、生物の先生に「優勢」「劣勢」という言葉はミスリーディングを引き起こすから変えた方がいいと言われたのを覚えています。
遺伝に関する科学的な考え方は、元々、外国からもたらされたもので、それを訳して日本国内に普及させました。
当然外国語なので日本語に置き換えなくてはならないのですが、当時数々ある訳語の中から「優勢・劣勢」が一般的に中学の教科書で扱われる用語となりました。
(因みに、英語では「adominant」「recessive」となっています)
このような経緯から、「優勢・劣勢」という表現は差別的という批判がかねてよりあり、それがようやく改訂されることです。
「優勢・劣勢」よりも「顕性」「潜性」の方が優劣のイメージがなく、表に出ているか潜っているかという意味なので分かりやすいという意見もあります。
これまで何年、何十年も「優勢・劣勢」で慣れてきたものからすれば違和感があるかもしれませんが、これから勉強する生徒たちにとってはそんなものはなく、他の用語と同じように受け入れられるのではないでしょうか。
ただ、これからお子様と以前の話をするときは「優勢・劣勢」と言わず「顕性・潜性」と言うように気をつけましょう。









学問というものは日々進化し変化することがしばしばあります。
今回の遺伝の話は単純な用語の変更ですが、新しい発見や新しい考え方が生まれると、それまでの科学的常識と思っていたものが、ガラッと変わることもあります。
かつては地球は平らで世界の中心と考えられていたのに、天文学や科学技術の進歩により、今では多くの人がそうではないと考えています。
遺伝などの科学的分野に限らず、社会的理念、歴史的事実など多くのことが何かをきっかけに間違いと分かり、正しいものに変更される。
そして、学校ではこれまでと違う新しい考え方が教えられます。
そうして、世代間の知識も実は少し異なるのです。
もっと身近な例を挙げると、「いい国作ろう鎌倉幕府」なんて覚えていた鎌倉幕府の成立(1192年)が今では「いい箱(1185年)作ろう」になっています。
「仁徳天皇陵古墳」も今では「大仙陵古墳」となっています。
(実は埋葬されているのが誰かははっきりしないため)
このように学問は日々変化し、時には我々が習ったことと今、生徒たちが学んでいることが違っている場合があります。
教える側としては知識を常に最新のものにアップデートしないといけないということです。
家庭においては「お父さん、お母さんが習ったときはこう言っていたんだよ」なんて話して勉強を通して親子の交流を深めるのもいいかも知れませんね。
または、一緒に学ぶということで子供の勉強を促すこともできますね。
知識のギャップを上手く利用して、子供の勉強を進めていくのもよい方法です。

























2021.04.25
去年の児童生徒の自殺が過去最多になったそうです。その裏にはコロナウイルスが関わっているのでしょうか。

警視庁によると去年の小中高生の自殺が、統計を昭和55年に始めて以来、過去最多になったそうです。
自殺者の内訳は小学生14人、中学生146人、高校生339人でいずれも前年より急増していました。
女子高生の自殺の増加が目立ち、特に8月は令和元年では3人の自殺者に対して令和2年では23人と大幅に増えています。
これらも含めた未成年者の自殺は777人で、その原因はうつ病などの精神疾患に加え、進路の悩みや学業不振が多かったみたいです。
長期休校が終わった6月からは毎月自殺者数が前年を大きく上回っているので、コロナ禍での学校再開が影響しているのではないかと考えられています。
厚生労働省の分析では、コロナ禍で学校が長く休みになったことに加え、外出の自粛が求められる中、家族との時間が増え、学業や進路、家族間の不和などで悩む人が増えたからではないかとみられています。
子供たちに限らず去年の自殺者数は増えており、特に女性の自殺者数の増加が際立っているようです。
つまり、子供や女性などの自殺が増えていることから、現代社会の彼らに対する姿勢や状況が(特にコロナ禍という特殊な状況において)、彼ら社会的弱者に対して厳しく、救いの手を十分に差し伸べていないのではないかと考えられます。









学校の卒業直前に一斉休校となり、これまで親しんだ友達と最後の思い出を奪われ、更に新年度もしばらくは休校が続いたため、新しい人間関係がうまく作れず、友達を作るタイミングを逃して孤立。
先行きが見えない学校生活が怖くて、ストレスから体調を崩し登校できなくなる。
学校に行っても様々な制限や要求をされ、これまでのように学校生活も楽しめない。
年中行事は中止か縮小、普段の友達との遊びや交友もあまりできない。
しかも、休校中の勉強の遅れを取り戻すため、長期休暇が削られ、休日登校もさせられ、通常以上のスピードで勉強をあおられ、このまま学校生活が送れるのか不安になる。
勉強の遅れに加え、他校の生徒との勉強格差でまともに受験が戦えるか自信がなくなり、進学をあきらめる。
コロナウイルスを理由とした新たないじめに悩まされる。
など等、学校問題が生徒を自殺に追いやる理由になりえることは十分理解できます。
一方家庭でも、コロナ禍で親の仕事がなくなり収入がなくなると、大人のストレスも上昇します。
外出自粛で発散もできず、イラついたまま家庭内で家族同士が顔を会させる場面が増える。
結果、子供たちの悪い点ばかり目が言って、ゆとりのないイライラからついつい子供たちに当たってしまう。
このように家族が共にする時間が増えることで反って衝突が増え、家庭問題が子供たちの心を大きく傷つけ、自殺に至るケースもあるようです。
また、逆にコロナ禍で大人は日々の生活に追われ、子供に気を配る余裕がなくなって、子供のSOSを見逃したり、殻らが困っているときに的確にアドバイスをしてあげられなくて、孤独になった子供たちが自殺をしてしまったということも指摘されています。
コロナ禍での収入の激減は家計を圧迫し、子供たちが楽しみにしている習い事を継続させてあげられなくなったり、勉強で助けてくれる塾などをやめなくてはならなくなったりして、やはり不安やストレスを強める要因になっています。
本当はもっと習いたいのに、お金がないから断念しないといけない。
正に、教育という基本的人権が保障できない状況が生まれています。
これは大問題です。
学校と家庭、家族と友人、様々な場面でコロナウイルスは子供たちの希望を奪い不安にさせ、将来が見通せなくなり孤独になってしまって、自分はこの世から消え去るしか救いがないように感じてしまう。
子供たちがこんな風に考えてしまう世の中は不幸ですし、彼らが将来に希望を見出せないような状況は大人としてどうにかしないといけませんが、肝心の大人も自分のことで精一杯で子供たちに手が回らない。









多くの可能性を秘めた生徒たちが命を絶つのは、私としては非常に心が痛いです。
できることなら何とか力になって自殺を食い止めたいと強く考えます。
苦しいのは分かりますが、絶望しないでほしい。
大人たちが子供たちを守れるように、コロナ禍であっても大人も子供も支えらえる仕組みを作ってほしいのですが、肝心の行政はどうも頼りなく、結局個々で対応するしかない。
これは本当によくありません。
コロナ禍はいつになったら終わるのか、全く見通しが立ちません。
これまでも散々疲弊しているのに、政府はまだ国民に負担を強いるこうなことしかできない。
これからも子供たちの自殺が増えることが懸念されます。
今の生活、自分の人生に悩み苦しんでいる生徒、もしくはそんな生徒をお持ちの家庭がありましたら、遠慮なく葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
皆さんの力になる準備があります。
自分は一人ではない、他の人とつながっていて、お互いに助け合って苦難を乗り越える仲間がいることを分かってください。
未来はいつも明るいものと信じて頑張って共に生きていきましょう。
























2021.04.24
暖かな春がやってきました。花が咲き、緑が芽吹き、虫や動物が現れ始めます。自然に敏感であれば新たな発見もいっぱい。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは季節の変化を感じ取る感覚を大切にします。

昼間は結構暑いのに夜は冷える。
しかし、春は確実にやってきています。
私の周りも桜が咲き、その他様々な花が満開です。
冬の間冬眠していた虫や小動物も動き始めます。
少し注意すれば自然の変化に気づくことができます。
そんな小さな発見が日々になんだか幸せを感じてしまいます。
季節の変化を感じられる環境にいることに感謝です。










季節の変化に限らず、日常の何気ない生活の中にも小さな発見がたくさんあります。
そこに喜びや疑問を抱き、探求を深めることは、学びの面白さを実感する良い機会です。
葛西TKKアカデミーでは、生徒たちの些細な疑問や発見(学校の勉強と関係ないことでも)を尊重し大切にします。
小さな塾ですが、入り口に観葉植物を置いているのもそのためです。
生徒たちが入ってくるときに何か変化に気づき興味を持ってほしいと思っています。
「なんか暖かくなって葉っぱが増えてきたなあ。」とか。
正直、もう少し利益が出れば小動物でも飼ってみたいなとも思っています。
このような知的好奇心をくすぐる経験をすれば、学校の勉強でも自主的に取り組めると考えます。
そして、自主的に探究する姿勢は、現在進行している教育改革で行われるアクティブラーニングの要になります。
今までのように知識だけあればいいという教育方針から大きく転換し、身に付けた知識を活用して未体験の問題に対応できる人材育成を文科省は目指しています。
それに伴い教育制度も大きく変わり、学校でも日頃から調査研究そして発表を要求されるようになります。
そのような探求の第一歩は出された条件を正確に分析できる目を持ち、積極的に考え調べる能力です。
これは教えられてできるようになるものではなく、経験が大きくものを言います。
従って、普段から身の回りをよく観察し気づける訓練が必要です。
そういう意味では、自然の変化が分かりやすい日本はうってつけです。
伝統的にも自然を愛で感じ取ってきた日本人には、血の中にそのような感覚が備わっていると言えるでしょう。
忙しさに忘れがちですが、時には立ち止まり、道端にある自然の変化に目を向けるのもいいでしょう。






























2021.04.22
緊急事態宣言がまた出るようです。その時学校はどうなるのでしょうか。行き当たりばったりの行政にまた振り回されるのでしょうか。
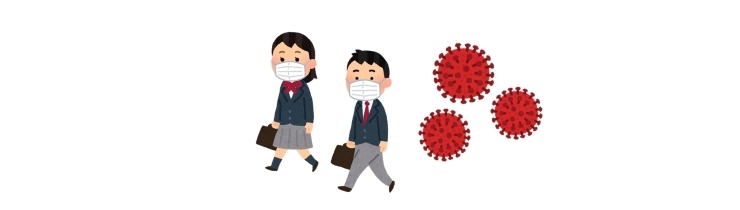
緊急事態宣言を解除したばかりだというのに、新規感染者数はうなぎのぼり。
変異株が大阪を中心に猛威を振るっていますが、東京はじめ関東でもウイルスが変異株に変わっているようです。
蔓延防止等重点処置が有効な手立てとならず、再び緊急事態宣言が出されるようです。
そして、今回の緊急事態宣言。
大阪の吉村知事は、感染拡大を防ぐためかなり強力な措置にするようで、飲食業はもちろん百貨店やテーマパークも休業要請をする気でいるみたいです。
東京でもゴールデンウィークを中心に宣言を出し、人の流れを止めて、コロナウイルスの拡大を防ごうとしているみたいです。
しかし、生活の保障なしに休業や自粛と言われても、これまでの散々の要請に、もう人々にはそれが出いるほどの余裕がないのではないでしょうか。
政治家の言うことはちぐはぐで明確で有効な対策もなく、国民に負担をお願いするばかりで、国民を助けよう、生活を何とか守ろうという姿勢が感じられません。
人々は疲弊し、信用もしていないので、今回の宣言がいかほどの成果を上げるのか、はなはだ疑問です。









それでは学校はどうなるのでしょうか。
最初の緊急事態宣言では突然の一斉休校で学校は大混乱で、生徒たちへも多くの問題をもたらしました。
前回の緊急事態宣言では休校にはならないものの、学校行事が中止されたり縮小されたり、子供たちの学校生活もいろいろと制限され、とても窮屈でつまらない毎日を送っているのではないかと案じております。
今回の緊急事態宣言を受けて文科相は、一斉休校は真に必要な場合に限ってすべきと述べています。
オンライン授業についても文科省は、学校を閉めるのではなく、対面授業を取り混ぜて実施するのが望ましいとの見方を示しています。
これを受けてのことでしょうか、感染が最も進んでいる大阪では、当初一斉休校ということでしたが、方針を急遽転換し、次のようなとんでもない方針を打ち出しました。
それは「オンラインと対面授業の両立」。
政治家の皆さん、長期にわたるコロナウイルス対策でとうとう頭がおかしくなってしまったのでしょうか。
大阪市によると小学生は、1限、2限は自宅でオンライン学習をし、その後、登校して内容の確認やプリント学習、給食を食べて、午後に授業のある生徒は自宅に戻ってオンライン学習だそうです。
中学生は、午前中は自宅でオンライン学習、その後登校して給食、午後は学校でオンライン学習の内容確認などを行うそうです。
部活は原則休止。
これに対して学校の教員や保護者からは大批判。
通常授業の準備だけでも大変なのにオンライン学習の用意もしなくてはならず、現場の負担はかなり大きくなる。
給食が一番感染リスクが高いのに、わざわざ給食を食べに学校に行くような案に理解ができない。
端末は配布してあるかもしれないが、この1年は後れを取り戻すのが精いっぱいで、端末を使った授業などやってる余裕はなく、それをオンラインで有効に使いこなせるスキルが生徒にも先生にも備わっていない。
オンライン学習の効果は学年が下がるほど薄く、まだ実行できる段階ではない。
二度手間だし、結局、登校するなら変わらない。
まだ、端末が行き届いていないし、利用のためのルールや補償などまだ決めなければならないことも山ほどあるのに、すぐにオンライン学習と言われても無理。
などなど多くの声が出ています。
これも現場との連携を取らず、ただ一方的に中央から方針を示すだけで、具体的な実施方法や対処は現場任せの体質の表れで、これは教育改革に伴う混乱を見ればよく分かります。
行政は本当に真剣に子供たちのことを考え最善を尽くしているのでしょうか。









では、東京はどうでしょうか。
先ず、部活は原則中止です。
(これにはオリンピックがOKでなぜ部活がダメなのかという疑問が多く出ているようです。)
一斉登校を防ぐためオンライン授業や分散登校をすることが考えられているようです。
今のところ、私の知る限りではこの程度しか出てきません。
大阪の様子を見ながら決めていくような感じになるのでしょうか。
緊急事態宣言は4/25~5/11になるようですが、早くどうするか決めないと、いきなり言われては現場が混乱するばかりで、当の生徒や保護者、教員が困ります。
本当にどうするつもりなのでしょうか。
そして、本当に子供たちを守れるのでしょうか。
変異株は感染力が強い上に、若者も重症化するそうです。
いつまでも他人事のような振る舞いはやめて、真剣にコロナ対策に取り組んでください。
ここで力を発揮できないようでは、今の行政は必要ありません。


























