塾長ブログ
2022.06.19
勉強が面倒くさいのは当り前!面倒くさいは勉強しない口実にはなりません!

子供に何か指示した時、「面倒くさい」と言われて拒否されたことはありませんか。
その時、きちんと面倒くさくてもやらないといけないことを説明できたでしょうか。
特に勉強したくないとき、子供たちはよくこのセリフを言うような気がします。
そこで今回は子供の「面倒くさい」をキーワードに、議論をしてみたいと思います。








なぜ勉強は面倒くさいのか
勉強は面倒くさいもの。
「面倒くさい」と感じる心理的な話もありますが、それはまた別の機会に致します。
今回は勉強の目的に注目して考えてみます。
「なぜ勉強は面倒くさいのか」
それはそうできているからです。
勉強の目的を考えたとき、勉強は面倒くさくないといけないのです。
面倒くさく困難な時こそ人間は考えるのです。
問題に挑戦し試行錯誤しながら、脳へ多くの刺激を与えます。
その刺激は脳細胞のネットワークを広げ複雑化させ、より高度な思考ができるようになります。
だから勉強はわざと面倒くさく作られているのです。
面倒くさくて当たり前です。
適度な面倒くささ
簡単で既にできることであれば、脳は発達する必要がありません。
でも、問題が難しすぎて自分の能力をはるかに超えるときも、脳はなかなか発達しません。
どうやっていいか思いもつかない、理解の範疇を超えている場合は人間諦めてしまいますから。
脳の成長のためには適度な困難さが不可欠です。
一般によく言われるのが「α+1」です。
αは現在の自分の力で、これに1プラスしたくらいの難易度で勉強を進めていくと、脳も無理なく課題をこなし成長することができます。
学校の教育体系はよくできたもので、このような「α+1」の積み重ねによって生徒たちの能力が育つように工夫されてできています。
しかし、この「+1」も生徒によって様々で、多くの生徒にとって「+1」であることが、ある生徒にとっては「+10」くらいになるかも知れません。
そういう時はサポートが必要です。
生徒が分からない内容にぶつかったとき、周囲がいかに助け「分からない」を解消して次の学習内容に進められるかが大きなカギとなります。
生徒が勉強嫌いになる原因の大きなものとして「分からない」を放置し、どんどん勉強がついていけなくなるというものがあります。
だから、周囲も生徒の様子をよく注意して観察し、分からないときは迅速に対応してあげることが必須です。
対応が遅くなればなるほど問題も大きくなり、手遅れになってしまいます。
「面倒くさい」は単に勉強を回避するための言い訳?
よく勉強嫌いの生徒は「なんで勉強しなくてはいけないの」とか「こんなこと意味ないよ」などと理屈をこねて、納得のいく勉強の意義を大人に求めようとします。
そうでなければ勉強する意義がないと。
普通答えられません。
本人たちもそれを知っていて、あえて聞いてくるのです。
本心は勉強をしないための言い逃れです。
(この点についてはいつかまた議論します。)
このような言い逃れに「面倒くさい」が利用されることがあります。
現在の世の中は効率が重視され、手間のかかることは敬遠される傾向があります。
皆さんも何かにつけ「面倒くさい」と不平不満を口にしたことはありませんか。
そして、時には「面倒くさい」理由にやらなかったりしたことはありませんか。
子供たちは大人の言動をよく見ています。
大人たちのこのような言動から「面倒くさい=悪」と理解し、「悪」はいけないことだから面倒くさい勉強も「悪」。
このように論理を展開し、「だから、『面倒くさい』と言えば勉強をしなくて済む十分な理由になる」と結論付けます。
いつもやらない理由を聞くと「面倒くさい」と言う生徒がいますが、彼らはこのように考えているようです。
そこに我々大人の日頃の何気ない言動が影響していると考えると、子供たちのことをとやかく言う前に、自分たちの発言や振る舞いを見直し、気をつけて改める必要があるでしょう。
「面倒くさい」=「しなくてよい」ではありません
しかし、ここで生徒が大きく誤解していることは、「面倒くさい」=「しなくてよい」ということではないということです。
どんなに面倒くさくても、しなければならないことはしないといけません。
学校の勉強はしなくてはいけないことであり、「面倒くさい」と言う理由で免除されるものではありません。
むしろ、面倒くさいからこそ、余計に時間をかけて取り組まないといけないのですが、なかなかそれを分かろうとしないことが多いです。
(受け入れてしまえば、せっかくの自分に都合のよさそうな言い訳をなくしてしまうので。)
日常的に多くの大人が「面倒くさい」を理由にして様々なことをやらないのを目の当たりにしているので、「面倒くさい」=「しなくてよい」と言う公式が正しいと考えます(人間は自分の望むように物事を見ます)。
しかも、実際にこの公式が自分のやりたくないことに対する言い訳として通用してしまったとき、彼らは勉強のみならずあらゆる拒絶に利用します。
ここで心配なのは、このような自分勝手が大人の世界で通用しないこと。
面倒くさかろうがそうでなかろうが、社会に出たらやらなければならないことはやらないといけません。
その時、この生徒は大変苦しむと思います。
勉強だけでなく、子育てという点からも「面倒くさいことはしない」という癖は直してあげた方が本人のためであります。









「面倒くさい」という言葉を発する生徒はたくさんいます。
しかし、上記のように歪曲した考え方で生徒が使っているときは注意が必要です。
きちんと説明し、どんなに面倒くさいことでもやれる耐性をつけないと、将来社会人として大変苦労するでしょう。
周囲の大人たちも、嫌なことで「面倒くさい」を理由にやらないような振る舞いは控え、自分が自分を律することができる見本となりましょう。
大人は子供の良い手本となれるように努めてください。
子供は良くも悪くもしっかり見て学んでいますから。
少なくとも勉強に関しては、「面倒くさい」でやらない理由にはならないことを理解させてあげましょう。





















2022.06.15
宿題はやればいいというものではありません

学校の宿題は何のためにあるのか。
先生がいじわるをして生徒から遊ぶ時間を奪うために出しているのではありません。
学校で学んだことを自分のものとして、より確実に定着させるためにあります。
従って、やはり宿題はきちんとするのがいいです。
毎回の宿題を正しくやって、その時その時しっかりと勉強を身に付ければ、定期テストや入試で慌てる必要は全くありません。








小学校低学年
小学校低学年での宿題の役割は授業の復習というのもありますが、家庭での毎日の勉強習慣を付けることも目的のようです。
これから学年が上がるにつれ毎日の宿題の量も増えますが、そんな時も抵抗なく学習態勢に入れるように、意識しなくても一定時間勉強できるように、体を慣れさせ勉強に対する肉体的精神的体力をつけます。
先生がおっしゃる宿題を難なく受け入れやれる(先生との約束を守れる)ような習慣を身に付けさせます。
これが基礎となって、その後難しい宿題が出たときもこなせる耐性を得るのです。
小学校低学年で宿題をやらない癖をつけてしまうと、勉強ができなくなるだけでなく、定期試験や入試などで、自分から家庭学習をしないといけないとき、精神的に勉強に耐えることができず集中力も続かなくなります。
小さい時から出された宿題をきちんとやることはこういう意味でも大切です。
勉強を確実に身に付けるための宿題
家庭での学習習慣が身に付き学年が上がってくると、いよいよ本格的に勉強としての宿題をすることになります。
授業では時間的制約があるので、時には内容の説明で終わり実際に問題に取り組む時間が十分にないことがあります。
これを補うために宿題が出されます。
学校で習ったことを本当に理解し、実際に使いこなせるかを試し確認するのです。
より多くの問題に触れることで練習を増やし、学習内容の習得をより確実なものとします。
ここで注意しないといけないことは、ただ問題を解くだけではダメだということです。
授業で習ったことに従って問題を解いてみる。
そして、それが正しいか丸つけをして確認する。
ここで終わる生徒が多いですが、本当の勉強は実はここからなのです。
丸つけをして自分が解けなかった問題がはっきりしたら、解答の解説や先生や友達に教えてもらって、自分のどこが悪かったのか、何が足りなかったのかを分析します。
そして、できなかった原因を突き止め、正しい答えの導き方を覚えもう一度問題を解く。
これを繰り返し、全ての問題が解けたら初めて宿題が終わるのです。
丸つけだけで終われば、それは自分の力を伸ばすことにはつながりません。
とは言え、家での限られた時間内に全てをするのは難しいでしょう。
しかし、理想を目指して努力することが大事なのです。
こうして毎回の宿題を着実にこなし、勉強をきちんと身に付ければ、後で慌てて同じところを勉強する必要がなくなります。
これは特に受験勉強のときに大きくものを言うので、日頃から心がけて宿題をしましょう。
やってはいけないこと
これは特に勉強できない(しない?)生徒に多いのですが、答えを丸写しにして宿題や課題をやったことにするのはやめましょう。
形式的には宿題をしたように見えますが、何も勉強が身に付いていません。
だから、結局テスト前などにもう一度やらないといけないのです。
もう一度やってくれればいいのですが、このような生徒の多くはそれもしません。
テスト結果が悪いのは当然です。
この解答丸写しの勉強で、勉強してなくてもごまかせると味をしめてしまった生徒は不幸です。
自分から勉強しなくてはという気持ちもなくなり、どんどん勉強しなくなります。
勉強しないから解けないし期限に間に合わない→解答を丸写しする→ごまかせたと安堵する→実は何も身に付いていないので問題が解けない→解答を丸写しする・・・
こんな風な負の連鎖に陥ってしまいます。
そうなると抜け出すのは至難の業で大変苦労します。
しかも、勉強ができなくなるだけでなく、丸写しの目的である「ごまかし」も実はできていないのです。
先生方は生徒たちが本当に考えて解いたか、単に答えを写しただけか、すぐに分かります。
あまりにも完全無欠で綺麗な解答は高らかにごまかしているといわんばかりです。
先生は生徒一人一人をよく知っているので、「この生徒がこんな解答できるはずがない」とすぐに分かります。
また、テストの結果を見れば、その生徒が勉強しないで解答を写しただけというのは簡単にバレます。
それをあえて言わないのは、それは生徒の自己責任であり、後で困るのは本人だということを知っているからです。
テストで成績が悪く評価が下がるのが分かっているからです。
勉強が身に付かないし、後でまたやらないといけないし(やる生徒はまだましです)、実はごまかしも成立していない。
それならば解答を丸写しする意味は何なのでしょうか。
ちょっとしたその場しのぎになるだけで、後で自分を窮地に追い込むことは間違いありません。
ある意味可哀想でもあります。
宿題をやるタイミング
宿題はいつするのがいいのでしょうか。
その日に習ったことをその日のうちに習得するのが一番です。
よく授業から何日か過ぎて宿題をする生徒がいますが、これはお勧めできません。
なぜなら時間が経てば経つほど記憶があいまいになり、授業でやったことを思い出せなくなるからです。
教育に関して、よく「忘却曲線」に触れられることがありますが、これは「記憶というのは時間が経つほど失われる」というのをグラフで示したもので、右肩下がりの曲線ができます。
しかし、記憶の新しいうちにもう一度やる、または何度か繰り返すと忘却曲線下降が緩やかになることが分かっています。
つまり、授業で習ってすぐ宿題をした方が勉強を習得しやすいということです。
本当のことを言うと、宿題は一度で終わりにするのではなく、次の授業までに2、3回やるのが理想です。
時間を置いてできるか確認して、できない分を補強すれば、学習内容がよりしっかりと身に付きます。
時間を置いて繰り返すというのは非常に良い勉強方法です。
なぜなら、勉強は教わるインプットだけでは不十分で、実際に問題をやってアウトプットしてみることでより定着し理解が深まるからです。









毎日の授業は前回やったことが基になって新しいことを学ぶ場合がほとんどです。
よって、授業は前にやった内容が習得できることを前提としているので、例えば問題が解けなかったりすれば、できるようになるまでやらなくてはいけません。
宿題をせず、ごまかして分からないままで授業を受けては、内容がさっぱり理解できません。
前出の勉強ができてなければ当然新出事項も分からず、「できない」がどんどん増えていき成績も下がり、勉強をするのが嫌になり脱落していくのです。
そうならないためにも、毎日の宿題をできるだけ早くコツコツ真面目に取り組み、分からないことがあったら解説を見たり、人に聞いたりして全て解決しましょう。
面倒かも知れませんが、勉強は「面倒な」ものです。
だから、ごまかしたりせず正しくすることが、実は自分にとって一番有益なのです。






















2022.06.12
都立高校入試で今年からスピーキングテストが加わります
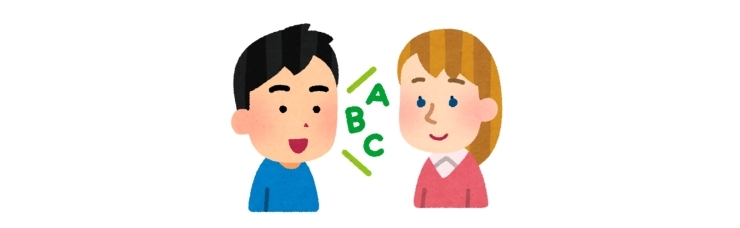
今年から都立高校入試の英語で「スピーキングテスト」が導入されます。
これまで何回かの試行テストも行われ、いよいよ実施の運びとなりました。
この試行テストや文科省の発表からスピーキングテストの概要や日程などが明らかになってきました。
そこで今回は現在分かる範囲で、スピーキングテストについて説明したいと思います。










スピーキングテストに関して、文科省は大学入試で導入を試みましたが、世間の理解を十分に得られないことなどから、本来スタートする予定だった共通テストの開始年度である2020年度の実施を諦め延期としました。
スピーキングテスト自体は廃止になった訳ではなく、将来的には導入される予定になっているので、自分が受けるであろう受験生は準備を進める必要があります。
いずれにしても、初の試みをいきなり全国規模の大学入試で行うということに、多くの反発と不理解を生じたのは仕方ないことだと思います。
私見を提供する側としても準備不足と説明不足は否めないと考えます。
そこで規模を縮小し、大学受験でのスピーキングテスト導入に向けた実証実験と言う意味合いも、都立高校入試のスピーキングテスト導入には含まれていると思います。
都立高校でスピーキングテストを既成事実にして、大学入試での導入も正当化しようという意図があるのではないでしょうか。
公には、これまでの英語の「聞く」「読む」「書く」の三技能に加えて、「話す」も試験に導入することで、これまで指摘されてきた日本人の英語コミュニケーション能力の低さを克服しようという狙いがあります(実際の試験内容や学校教育の内容がそれに準じているかどうかは別として)となっています。
スピーキングテスト『EAST-J』の概要
東京都では事業者(ベネッセコーポレーション)と提携し、高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加します。
このスピーキングテストは「ESAT-J」と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します。
テストは大きく四つのパートからできています。
パートAでは与えられた短い文章を読む問題です。
5文(3行)くらいの画面に書かれた英文を読みます。
最初に簡単な状況説明と準備時間(30秒)が与えられます。
その後、30秒以内で文章を読み録音します。
パートBでは図や表などの資料が与えられます。
その資料を見ながら、音声で出される簡単な英語の質問に答える問題です。
簡単な状況の説明の後、10秒の準備時間があります。
そして、英語の質問を聞いて解答を10秒以内に行います。
パートCでは4コマのイラストがあり、それについてのストーリーを英語で話す問題です。
最初に簡単な状況説明があり、その後30秒の準備時間が与えられます。
そして、時間になったら40秒以内に全てのコマを英語で描写しながら、全体の話を完結させます。
最後は、パートDです。
ここではある質問に対して自分の意見とその理由を言う問題です。
1分の準備時間の後、40秒で自分の考えを録音します。
この時、質問が画面上に文字表記されるか、音声だけになるかは未定です。
表記される場合は文字を追って質問を理解できますが、音声だけの場合は、聞き取りを誤ると答えられないという危険性があります。
どの問題も問題の英語はそれほど難しくなく、普通に中学で英語の勉強をしていれば分からなくはないと思います。
答える方も、コツをつかむ必要はありますが、慣れてしまえば平易な英語で答えることができます。
よって難易度は高くありませんが、やはり十分な準備をしていないと戸惑うことも多く、高得点は期待できないと思います。
ESAT-Jの都立高校入試における評価法
ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。
試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。
この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。
評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。
そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。
送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。
つまり、調査書点に加えられるのですね。
その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。
これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。
・学力検査の得点
各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。
・調査書点
中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。
これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。
1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。
入試は1点で合否が分かれます。
だから、例え1点でも疎かにできません。
ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。
尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。
この処置が本当に公平かどうかは疑問です。
スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。
ESAT-Jのスケジュール
実際に入試でESAT-Jが使われるのは令和4年度以降、令和5年の高校入試からです。
現段階でのスケジュールは次のようになっています。
・令和4年7月下旬から9月上旬まで
ウェブによる申し込み、および特別処置申請
↓
・令和4年11月27日(日)
ESAT-J受験
↓
・令和4年12月18日(日)
ESAT-J受験予備日
↓
・令和5年1月中旬
個人及び中学校の結果帳表の受取
↓
・令和5年2月
都立高校入試選抜でのESAT-Jの結果活用
コロナウイルスの時勢柄、会場や使用機になどに対してガイドラインに基づく感染症対策が実施されるということです。
(手指消毒の徹底、マスク着用、関係者の検温、タブレット端末の除菌など)
ここで注意しないとけないことは、スピーキングテストの試験日が都立入試の本試験の前になっているということです。
11月末にはテストなので、他の勉強より早めの準備が必要です。
これを気づかず、後になって慌てても良い結果は得られません。
新しい試みだからこそ不測の事態も考えられますので、情報収集など怠りなく。
どうしていいか分からないときは、葛西TKKアカデミーまでお問合せください。










このように都立高校入試においてスピーキングテストがかなり現実的になってきましたが、多くの生徒や保護者はまだ詳しく知らない人が多いようです。
しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。
もちろん、葛西TKKアカデミーでも対策の授業を行い、実際に模試も受けられます。
事前にテストの内容と答え方を理解するだけでなく、テストに使う機器の操作にも慣れておく必要があります。
そのためにも、繰り返しになりますが、葛西TKKアカデミーのスピーキングテスト対策講座を受けてください。
模試も含めてご案内いたしております。
現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。
この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。
未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば大丈夫です。
逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。
いろいろ分からないこと、不安なことがあると思いますが、そんな時はどうか葛西TKKアカデミーまでご相談ください。




























2022.06.08
宿題を正しくやろう!ごまかしても最後に困るのは自分

生徒の中には宿題を勘違いしている人が多くいます。
「宿題は何のためにするのか」を理解せず、その場しのぎの勉強を続けていると、後でひどい目に遭います。
宿題をやっている過程にまで先生の目は届きません。
だからと言って、ごまかして形だけ整えて宿題や課題を提出しても、結局困るのは自分です。
その時その時、与えられた宿題を正しくやった方が、長い目で見たとき本人にとって一番いいのです。








宿題:親子でする→自分でする
長い学生生活の中で宿題というのは基本的に、学校に通い始める小学一年生からずっと出されるものです。
小学低学年の頃は学校で学んだことの練習と確認が宿題の目的の一つとなりますが、他に学校以外での勉強習慣の習得というのも宿題の目的になるでしょう。
親の前で音読してみたり、計算ドリルをやって親に丸つけしてもらったりするのは、子供一人では毎日の家庭学習をするのは難しので、親の手を借りながら(親が見ているという環境下で)確実に子供に家庭学習をさせ、その習慣を身に付けさせるという意味もあります。
まだこの時期は学習内容も難しくなく、子供自身も分からなくて宿題ができないということも少ないですし、親も子供の質問に答えられるので、この親子でやる宿題も比較的問題なくこなしていくことができます。
しかし、学年が上がり勉強の内容が高度化してくると、この共同作業が難しくなっていきます。
親が子供の質問に答えられなくなったり、宿題に費やす時間が長くなって親の仕事や家事の時間と衝突するようになると、これまでのような一緒に宿題をするということはできなくなってきます。
そこで子供たちは自分たちだけで宿題をしなくてはいけなくなります。
宿題をしなくてもしたことにできる画期的な方法!
こうして親の監視下を離れ、子供一人で宿題をしなくてはならなくなったとき、いろいろと問題が発生します。
誰からも見られていないので自由にできるということは、その気になれば手を抜いたりごまかしたりできるということです。
宿題の行程を見ていないので、結果(少なくとも見た目上は)が整っていてやったように見えれば、問題を解かなくても許されると気づくのです(勘違いする)。
特に解答が渡されているときはそれを丸写しし(そのために解答を渡している訳ではないのですが)、そうでないときは友達の宿題を写す。
そうして実際は自力で解いていない問題を、あたかもやりましたという体裁にして提出するのです。
小学高学年から中学になると生徒の中には勉強についていけず、勉強が嫌になると同時に遊びたいという気持ちが強くなる人が増えます。
そんな彼らが自分たちの欲求と満たしつつ、宿題をやっていることにして先生から叱られるのを回避する素晴らしい解決策が答え写しです。
学校の先生は生徒が答えを丸写ししていることを分かっていても、それを一人ひとりに指摘することはまずありません。
先生も多忙でそんな時間はないし、ごまかした宿題が本人にどんな結果をもたらすかは自己責任だからです。
しかし、生徒は何も言われないことをいいことに、このごまかしの宿題を続けてしまいます。
宿題のごまかしはトラップ!
いくら見た目をよくしても、きちんと宿題をやってなくては勉強が身に付きません。
だから、ごまかしの宿題をすれば学校の勉強はますます分からなくなり、宿題をきちんとやろうにもできない、でも提出はしないといけないから答えを丸写しする。
そして、分からない状態のまま学校の勉強は進み、宿題はできないけど提出しないとけないから、また答えを写すと言った悪循環に陥るのです。
勉強は前出の内容ができるようになっているという前提で進みます。
もし分からなければ、「分かりません」と声を上げ、分かるようになるまで教えてもらう必要があります。
子供には教育を受ける権利があるので、「分かりません」と言って教えてもらえないのは違法になります。
そうしてできるようになるまで、とことん教えてもらえばいいのです。
しかし、ごまかしの宿題をやってしまえば、先生も見た目上はできているので、その生徒は分かっていると判断し勉強を進めてしまいます。
ごまかしの宿題は生徒の「分からない」のメッセージを先生に伝えず、そのまま生徒を取り残してしまうのです。
これが最も愚かな点です。
「分からない」を放置してそれが積み重なって、最終的にそれは自分に反ってきます。
特に中学生になり高校を受験するとき、この愚行が大きく生徒を苦しめます。
その時その時はできているように見せても、ごまかしでは勉強は身に付いていないので、結局中学三年間の勉強を試される入試のときにバレてしまいます。
高校入試ではできるようになっていないといけないものが決まっています。
毎回の宿題をきちんとこなし、分からないところはその都度解決していれば、受験勉強を始めても、それまでの学習が身に付いているので、入試対策に全力を注げます。
しかし、ごまかしでこれまでの勉強が十分に身に付いていない生徒は、それを習得してから入試に向けた勉強をしないといけません。
つまり、放置していた「分からない」をカバーするのに時間を費やさないといけなく、必要な入試の勉強が十分にできないといった事態に陥るのです。
残された時間も限られ、多くの生徒にとっては初の人生の大きな分岐点に臨むという不安とプレッシャーの中、もう一度最初から勉強し直さないといけないというのは、非常に大きなハンデで絶望感で打ちのめされる生徒も多いでしょう。
この時になって「しまった」と思う人が多いですが、もう後の祭りです。
そうならないためにも毎回の宿題を正々堂々とやって、ごまかさない。
結局、これが一番自分のためでもあるのです。








宿題は自分の学びをより深く定着させ、学習内容をより確実に発揮できるようにする非常によいチャンスです。
学校が生徒を苦しめるために出すものではありません。
しかし、そのチャンスをやらないでごまかしてしまうと、後で困るのは生徒自身です。
いくらその時に面倒くさいからと言って、せっかくの勉強の習得のチャンスをふいにしてしまうと、結局後でやらないといけないので二度手間になります。
つまり、もっと面倒くさいことになるのです。
しかも、入試などで時間的制約のある中でやらないといけないとなると、心理的に追い詰められて効率のよい勉強はできません、入試対策の時間がその分減るので、受験にも不利になります。
毎回の小さな手間を惜しまず、コツコツ真面目にきちんと宿題をこなしていくのが、長期的に考えれば一番いいのです。





















2022.06.06
定期テストの勉強はこうしよう!

定期テストが近づいてきました。
勉強ははかどっていますか。
よく勉強の仕方が分からないと質問されます。
勉強の仕方は人それぞれで合う合わないがありますが、とりあえず基本的なことを話します。










基本は教科書とワーク
「何を勉強していいか分からない」と言いますが、定期テストの場合、テスト範囲も限られていますし、出題も教科書とワークがほとんどです。
数値が少し変わったり、中にはそのまんま出題されることもありますので、この二つをしっかりやれば6~7割くらいは取れます。
しかも、ワークは課題として出るので、ワークをきちんとすればテストもできるようになるとの意図で課題が出されます。
だから、いかに早く課題(ワーク)を終わらせるかが重要になります。
早く終われば残った時間を確認と練習に使え、学習内容の定着がより確かなものにできます。
一度やってできなかった問題だけをもう一度やる。
それでもできない問題をもう一度やる。
これを繰り返して最終的に全ての問題が解けるようになれば大丈夫です。
このようにできなかった問題ができるようになるには時間が掛かります。
だからこそ、最初の一回は早く終わらせた方がいいのです。
できればテスト発表があるまで待つのではなく、学校で習ったらその日のうち、遅くてもその週のうちに、ワークや教科書の問題をやってみて、自分が本当に解けるかどうかの確認をしてほしいです。
そうすれば、勉強内容の確認の時間が十分確保できますし、必要であれば更に高度な応用問題にさえ取り組むことができます。
結果、より高得点を狙えるのです。
いい加減な勉強やごまかしの勉強はかえって自分を困らせる
しかも、問題に取り組むときは一問一問丁寧に解きましょう。
よく本番じゃないからと言って書き方が雑だったり、正確に書かなかったり、書くことさえしなかったりする生徒がいます。
練習できちんとしない生徒はたいていテストでも同じようにいい加減な解答をして×にされます。
「ちゃんと本番ではできるから大丈夫」という生徒に限って間違えます。
練習でも本番と同じ気持ちで真剣にきちんと解きましょう。
また、ギリギリまで(テスト前日まで)何もせず、時間がないと言って焦って課題をやり、しかも答えを写すだけという生徒がいます。
自分で考えず答えを写しているだけなので、いくら体裁を整えてやっている風で提出していても、当然テストでは問題が解けません。
課題は全部○になっているからと言って、学校の先生はそれが本当に実力でやったのか解答を写しただけなのかは分かっています。
困るのは本人だからあえて言わないだけで、決してごまかせたとは思わないでください。
一生懸命考えてどうしても分からず、解答を参考にして理解するならいいのですが、そうでなければ何も身に付きません(この最初の「一生懸命考えて」という部分が肝心です)。
仮に前日に解答丸暗記で、定期テストを何とかやり過ごしたとしても、受験勉強の時に困ります。
焦った丸暗記はテストが終われば全て忘れてしまいます。
結局何も習得できていないので、また受験勉強で同じことを繰り返さないといけない。
入試という重要な試験前の時間が非常に足りないときに、またやり直さないといけないというのは、自分をかなり不利に追い込むことを意味します。
このような愚かしいことにならないためには、やはりその都度その都度の勉強をしっかり丁寧にそして確実にするしかありません。
そうすれば定期テストでいい点が取れ、受験においても無駄なく効率的に勉強ができるので、入試合格の可能性がぐんと上がります。
その場しのぎのごまかしの勉強は、後で自分を苦しめるというのを肝に銘じておいてください。
結局長い目で見ても、丁寧でコツコツの勉強が強いのです。
暗記型と積み上げ型
国語、理科、社会は暗記型で数学、英語は積み上げ型とよく言います(個人的にはこの分け方は好きではないのですが)。
暗記型の教科はいかにたくさんの用語などを覚えられるかが学習の中心になります。
この場合、その用語だけ(覚えなくてはいけないものだけ)を覚えようとしてもなかなかうまくいきません。
人間の脳は脈絡もなく一つのことを覚えるのは苦手です。
何かきっかけになるものや意味あるものと関連付けた方が、それをヒントにして思い出すことができます。
分かりやすい例が歴史の年号でしょう。
794年平安京の遷都を覚えようと「794年」ばかり考えるとなかなか覚えらません。
しかし、「鳴くよ(794)ウグイス平安京」とすれば簡単に覚えられます。
記憶を促すのは印象と回数です。
この両者を最大限にできれば、長期の記憶として残ります。
工夫をしてみてください。
「人に言ってもらう」というのも一つの良い方法です。
一方、積み上げ型は前のことが土台となり、新しいことを学ぶタイプです。
数学と英語が日本ではこの部類に入るようです。
前のことがベースになって今があるので、分からないときはずっと振り返り、立ち止まり、学び直さないと先に進めません。
よって分からない問題が出てきたとき、自分はどこまで戻る必要があるか考えないといけません。
その時は大変でも原点に戻り、一から理解していかないといけません。
もちろん、先生や友人に教えてもらってもいいです。
こうやって抜けているところを埋めていかないといけないのが、積み上げ型の特徴になります。
より高得点を狙うならワークと教科書だけではなく、授業でやったこともしっかり身に付けましょう
このようにワークと教科書が基本ですが、それはそれは基礎的な問題を解くためで、より高得点を狙うには不十分です。
更に学校のプリントや授業で先生が話したことなども復習しましょう。
よくプリントをなくしたり、ぐちゃぐちゃで使えなくなったりする生徒がいますが、プリントも大切な教材ですからクリアファイルに入れるなどして、しっかり保管してください。
また、授業中のノートも板書だけでなく、先生の話したことも大事だと思えば書き留めておきましょう。
ワークや教科書にないものだから失われると残りません。
これらがあるとないとでは大きな違いになります。
特に教科によっては、教科書をあまり使わず自分の作った教案に基づき授業を進める先生(理科、社会の先生が多いです)がいます。
そういう先生方のテストは教科書よりも授業中で話したこと、やった内容が重視され、そこから出題されることも多いので注意しましょう。
また、学校の教材ができるようになれば、追加で難易度の高い問題集などやってもいいでしょう。
ただ、個人的には他のものに手を出すよりは、今あるものをより完璧に仕上げた方が定期テストの場合はいいと思います。










以上、簡単に定期テスト対策としての勉強法を考えてみました。
後、もう一つアドバイスするなら、自分の好きな教科ばかりやるのではなく、苦手な教科もしっかりやりましょうということです。
好きな教科はやっていても楽しいし、苦手な教科はつまらなく苦しい。
でも、受験などを考えたとき、得意な教科を持っているより、苦手な教科がない方が強いのです。
これは五教科の総計で評価されるからです。
だから、点の取れない教科を嫌いにならず、頑張って何とか人並みにできる、少なくとも基礎は身に付けるようにしておくと後が非常に楽です。
定期テストはそのまま入試にもつながるということを忘れずに、毎回の定期テストをきちんとしましょう。
勉強の仕方が分からない、勉強を教えてほしい、新しい問題を解きたいなど要望があれば、気軽にご連絡ください。
葛西TKKアカデミーはただ今、定期テスト前で全ての生徒(塾生でなくても可)に塾を開放しています。
勉強しやすい環境で、分からないことはすぐに聞ける葛西TKKアカデミーを存分に利用してください。
皆さんのご健闘をお祈り申し上げます。




























2022.06.05
英語の定期テストでいい点を取るための勉強法

生徒の中で苦手が多い教科の一つが英語です。
小学校の英語活動のような、英語を使ったゲームや挨拶などの簡単な会話ならば楽しく苦痛でもないのですが、中学に入り文法などを始め本格的な「勉強」となった場合、感覚ではなく理詰めで考えなくてはならず(一般の中学の授業がそのようにこれまでデザインされていたからなのですが)、難解な暗号解読のようになり感じられ、その出来不出来が即座に数字となって評価される。
そして、その数字で自分の人格すら判断されてしまう。
そうやってレッテルを張られれば、楽しみはすぐに消し飛び頑張ろうという気力さえなくなることもあります。
そうならないように、生徒が英語に興味を持ち楽しみながら学べる授業を葛西TKKアカデミーでは目指しているのですが、現実に学校という存在がある限り、なかなかそのような理想的な授業も行えず、妥協して学校の勉強に即した授業になってしまうのが悩みです。
そこで今回は学校の定期テストに向けた英語の勉強法についてお話します。









勉強は千差万別、一人ひとりに適した方法があり、万人に通用するものはありません。
だから、個人個人に合わせて勉強を考え教えていかないといけないのです。
しかし、個々の事例を上げればきりがないので、ここでは一般論としての勉強法を紹介します。
これでうまくいかないからと言って心配する必要はありません。
その時は自分に合った勉強方法を見つければいいのです。
その際は葛西TKKアカデミーが力になりますので、是非、ご相談ください。
英語は毎日触れ、慣れることが大事
外国で生活をした経験がある方なら分かると思いますが、言語は毎日使っていないと驚くほど忘れてしまうものです。
海外の生活が長いと、ある日、自分の言いたいことが日本語で出てこないことがあります
逆に日本に帰ってしばらくたつと、海外で生活していた時は何の問題もなく使えた英語が口から出てこない。
この傾向は特に子供に強く、ちいさい子供は言葉を覚えるのが早いですが、忘れるのも早いです。
つまり、言語学習では毎日その言葉に触れることが大切です。
英語を日常で使う機会の少ない日本では、生徒たちが自分から積極的に英語に触れようとしないといけません。
幸いにして現在はYouTubeやその他動画サイトなど、その気になれば英語に触れる機会はたくさんあります。
DVDやブルーレイで映画などを見るときにも英語の吹き替えや字幕を付けることもできます。
そうやって英語を聞く場を設けてください。
最初はよく分かりませんが、映像を見れば言っていることがなんとなくわかってきたり、単語をいくつか聞き取れたりできるようになります。
そうやって聞き取りが少しずつできるようになると、英語を聞くのも楽しくなります。
基本文で覚える
英語を勉強するとき「単語を覚えさえすればいい」という人がいますが、これは間違いです。
言葉は単語が単独に漂っている訳ではなく、単語同士が有機的につながり、文脈において的確に使われなくてはいけません。
つまり、文となって初めて言葉は意味を成してくるのです。
単語だけ覚えては使い方が分かりません。
だから、英語を勉強するときは単語で覚えるのではなく、文で覚えることをお勧めします。
文の方が長いので、これは効率が悪いように思えるかもしれません。
でも、人間の脳を考えると、脈絡もなく単語を覚えるよりも、他と関連付けて、それをヒントに覚えていく方が覚えやすいです。
このような基本文をたくさん覚えることが英語の理解を深め、実際に使える英語につながります。
基本文は簡単な言葉で作って構いません。
大事なのはポイントが分かる分の構造です。
「この分から、英語の過去形はこう作ればいいんだ」と理解してくれればいいです。
こうして基本文を身に付けたら、後はその中の単語を置き換えるだけで表現の幅が広がります。
文法用語は極力避ける
英語を勉強するとき、学校の先生の中には言葉の意味も十分に説明せず、やたら文法用語を使う人がいます。
これは教える方が楽なだけで、学ぶ側が決して簡単という訳でもありません。
むしろ、言語とは別に余計な用語を覚えなくてはいけないので、人によっては余計に混乱するかもしれません。
しかも、運の悪いことに英語で使っている文法用語の中には、国語の文法用語と同じものがあります。
しかし、日本語文法と違い国語文法は母語話者が自分の言葉を分析するために用いられるものなので、同じ用語でも意味が違ったりします。
これも混乱の原因となりえますので、できれば文法用語に頼るのは状況をよく分析してからにしましょう。
生徒の中には文法用語を聞いただけでアレルギーを起こしてしまい、「もう難しい、分らない」と思い込んでしまう者もいます。
特に子供の場合、その心理状況が学習に与える影響は大きいので注意が必要です。
本分を繰り返し読む
特に定期テストという観点で考えるなら、基本はやっぱり教科書です。
だから、教科書をしっかり勉強しなくてはなりません。
その際、色々理屈を考えながら分析しながら英語を科学的に理解するのもいいですが、言語という性質を考慮するなら「読む」ことは基本でしょう。
声を出して読めば(より多くの間隔を使うので)単語やいろいろな表現を早く覚えることができます。
その時注意しなくてはならないのは、発音をいい加減にしないということです。
あいにく日本の英語教育は発音を疎かにする傾向がありますが、人間の思考は脳内で音で行われていることを鑑みるならば、きちんと教え学ぶべきです。
そして、最初はよく分からないかもしれませんが、何回も何回も繰り返し読んでいくうちに、不思議なことに、だんだんと分かるようになってきます。
「読書百遍自ずから知る」とはよく言ったものです。
やっぱり学校のワークと教科書
定期テストでは多くの問題が教科書やワークから出ます。
そして、これらは事前にやれば解き方が分かるし、答え合わせをすれば確認もできます。
一回やったら間違ったところだけをもう一回やる。
これを繰り返し、全ての問題が丸になるまで頑張りましょう。
これでテストの半分以上は取れるようになります。
しかし、多くのできない生徒はこれをいい加減にやっています。
面倒くさいからと言ってきちんと問題を解かず、答えを写すだけ。
形式上は丸がついてやったように見えますが、結局何も身に付いていないので、当然テストでは解けません。
更に、高校入試では中学三年間の勉強が全て対象となるので、ここできちんとやらないとまた同じことを勉強しないといけません。
結局二度手間で、長い目で見るならやはり、ごまかしの勉強はすべきではありません。
後でもっと面倒くさいことになります。
勉強はテスト前にやるのではない
最後によくいるのが、テスト範囲が発表されるまで勉強しない生徒です。
「範囲が発表されないと何を勉強していいか分からない」ということらしいですが、そんなことはありません。
前回のテスト範囲の次から普通出されますし、今やっているところまでは確実にテスト範囲になります。
だから、発表されなくても既にやってしまうのがいいです。
早く課題を終わらせれば、その分学習内容の確認とテストの準備に費やす時間が増えます。
そうすれば、成績もきっと上がるでしょう。
わざわざ待つ必要はないのです。
毎日の余裕のあるうちに勉強に取り掛かり、ゆとりを持ってテスト勉強をすればより効率よく勉強が身に付きます。











今、テスト期間の学校があります。
もう少し後の学校もあります。
いずれにしても定期テストは必ず行われるので、それにどう対処するかが大きな分かれ目です。
英語ということで話しましたが、今回のチップはほかの教科でも通じるものがあります。
テスト頑張ってください。
すこしでも勉強に困ったときは、気軽に葛西TKKアカデミーにお知らせください。
必ず皆さんのお役に立ちます。



























2022.06.04
SNSで受験勉強の英雄になろう!

現代の子供の勉強における大きな議論に「スマホ問題」があります。
確かに連絡を取ったり、調べものをしたり、息抜きや余暇に便利なのですが、実際には勉強の妨げになっていることが多いようです。
国際機関のWHOがゲーム依存症を現代の病として認知するほど事態は深刻ですし、「スマホ依存症」という言葉も聞かれるようになって久しいです。
他にもSNSをしながらの勉強がどれほど勉強にマイナス効果をもたらすかという研究や、スマホを使った調べものが本当に学習の役に立っているのかという研究は山ほどあり、その多くが負の影響を指摘しています。
実際に多くの家庭で子供がスマホを手放せなく、勉強が十分にできないという声もたくさん聞きます。
そういう場合は話し合いでスマホのルールを決めるのが一番なのですが、これもなかなか難しい。
理由の一つはスマホが本人一人のものではなく、友達をはじめ多くの人間とつながっている点があげられます。
多くの人が関わっているのだから、一人を規制するだけでは難しいという訳です。
そこで今回は、特に受験を控えた生徒とその家庭へのご提案です。
この多くの人(時には不特定多数)とつながっているスマホの特性を生かして、受験勉強に役立てようというお話です。








道具は使いよう
「スマホ」は道具であり、上手く使えば我々の生活をこれまでにないほど豊かにできます。
しかし、スマホを上手に使いこなすことができず、反って不利益をもたらすことも多々ありま多々
この新しいツールはまだ社会としても適切な使用が定まっておらず、大人でさえ間違った使い方をして困った状況に陥ることがあります。
ましてや、人生経験も浅く、精神的にも理性的にも未熟な子供たちが、スマホを的確に使いこなすことはとても困難です。
「道具は使いよう」とはよく言ったもので、スマホ自体は良くも悪くもないのですが、要は使う人間の問題ということです。
そこで、この「スマホ」のSNS機能を上手く使って、「受験勉強の英雄」になり自分だけでなく、友達の受験生もやる気にさせる方法を考えます。
実はみんなもスマホを手放したい、でも手放せない
学年が上がり、いよいよ入試が迫り本格的に受験勉強をしなければならないときに、「スマホ」が手放せず勉強が文字通り「手につかな」生徒がたくさんします。
「勉強を始める前にちょっとゲームをして、気分を上げて勉強しよう」と思って、数分間ゲームをしてから勉強するつもりが、「あと少し、あと少し」とあっという間に一時間、二時間過ぎてしまい、もう寝むくなって「明日からやろう」と誓いつつ、あくる日も同じことを繰り返す。
机に向かって勉強を始めると、友達からLINEがきて返信をする。
「よしやるぞ」と本を開くと、また別の友達からLINEがきて返信をする。
そのうちLINEが盛り上がり、着信返信で勉強が進まず、合間に何とか勉強したことも、後で振り返ると何も残っていない。
このような経験をしたことのある生徒は本当にたくさんいます。
勉強をしなければならないのは分かっているが、スマホを置いていると一向に勉強ができない。
でも、そうかと言ってスマホを消してSNSを遮断すると、その間に何が起こっているか気になってしまう。
一種の中毒症状のような感じですね。
実際に、今の生徒にはLINEなどのグループアカウントはとても重要らしく、返事をしないとそのグループからのけ者にされたり、いじめの対象にされたりするのを恐れています。
本当の友達とはそのようなものではないのですが、人生経験の浅い彼らにはこの不安と恐怖は非常に耐えがたいもののようです。
だから、誰も「スマホ」を離せないのです。
「このままスマホを傍らに置いておいては、受験勉強ができない。だから何とかしないといけないのだが、そうすると友達を失い、グループから攻撃されてひとりぼっちになってしまう。毎日の学校生活が、いじめられて嫌なものになってしまう。」
こうして子供たちは受験勉強とスマホの間で悩み苦しむのです。
我々が子供の時にはなかった問題で、彼らにはある意味、不幸な時代になってしまったと言えるかもしれません。
このような心理は本人だけでなく、実は他の生徒も同じように感じているのです。
「スマホを何とかしたいけど手放せない」
「勉強しないといけないのは分かっているけど、それでSNSを断つと仲間外れにされるんじゃないか」
「みんなもLINEをやってあまり勉強していないみたいだから、きっと自分も大丈夫」
最初の二つは受験勉強のため何とかしないといけないのに、行動する勇気やきっかけが無くて動けないことを表しています。
最後のは、受験勉強をやっていない自分に対して言い訳をして、自己正当化を図っています。
こうやってグループ全体がお互いに甘えて勉強しないまま、みんな道連れとなって受験を失敗するのです。
君が最初の一人になろう
このようにスマホは子供自身も何とかしたい問題なのです。
だから、誰かが動き始めないといけません。
勇気を出して、この最初の「誰か」に是非なってほしいと思います。
やり方は簡単です。
SNSに「受験勉強があるから、自分は18時以降はスマホの電源を切る!」などと、みんなの前で宣言すればいいだけです。
こうしてみんなに知らしめて自らの退路を断つと、もう前に進むしかありません。
時間になったら電源を切って、実行します。
最初は難しいかも知れませんので、その場合は親が声を掛けてください。
スマホの時間が無くなれば、勉強の時間が増え、スマホを気にする必要もなくなるので、勉強により集中でき効率も上がります。
いろいろ心配はあると思いますが、やって慣れてしまえば意外と快適に勉強ができます。
「そんなことすれば友達をなくすのでは」と思うかも知れませんが、それでなくすようではその人は本当の友達ではないですし、今後の人生で新しい友達はいくらでもできます。
少なくとも学校に行けば会えるのだから、問題はありません。
このように「宣言」で受験生の自分に利点が生じると同時に、この「宣言」は友達をもスマホの呪縛から解き放つきっかけを作ります。
「宣言」を見て「あの子がやるなら自分も同じように受験勉強をしなくては」と考え、同様にスマホを切って勉強に励むでしょう。
先ほど互いに甘えてみんな道連れで受験に失敗すると言いましたが、それと反対のことが起きるのです。
他の人がするなら自分も勉強しなくてはと頑張り、お互いに励ましあい、分からないときは助け合い、勉強がより高度になっていくのです。
こうしてみんなが合格すれば最高ですし、みんながwin-winの関係になって友達としても意義が出てきます。
こうして一人の勇気ある「宣言」が自分のみならず友達も救う、まさに「受験の英雄」の誕生になるのです。
さらにSNSを使って、友達と受験勉強を促進させよう
さらにSNSを上手く使って、受験勉強をより推し進める提案を一つしましょう。
それは毎日の自分のした勉強(書き込んだワークやノート)を写メに取りSNSに毎日アップすることです。
このように自分の学習記録を取り、多くの人の目に触れるようにすることで、自分の努力を明確にし頑張りを実感できるので、自分に対する勉強の自信につながります。
また、人に見てもらうので、やらなくてはという義務や責任感も生まれるでしょう。
その上、自分の勉強を公に開示する別の効果として、友達の勉強の促進剤にもなるという点があげられます。
「あいつはこんなにやったのか、自分も頑張らなくては」と言った感じです。
お互いの頑張りが見えることによって、いい意味でのライバル心に火がつき、自他ともに学力が上がることが期待できます。









スマホというのは我々が彼らの年頃にはなかった、新しい現代に特有の現象です。
有効な活用はまだ広く確立していません。
しかし、スマホが道具である以上、良くするも悪くするも使う人次第ということは言えます。
そこでスマホを利用して、受験勉強に上手くいかせないか考えてみました。
いかがでしょうか。
しかし、まだ成長過程にある子供が自分だけでうまくやれるかというと不安はあります。
だからこそ、周囲の大人が上手に接し支える必要があります。
こうしてスマホをチャンスに勉強の輪が広がれば、来年の春にはみんなが笑って新年度を迎えることができるでしょう。
入試まで後9ヶ月を切っています。
頑張ってください。
受験でお困りの方は遠慮なく葛西TKKアカデミーまでご相談ください。






















2022.05.19
中学の英語を勉強するときのポイント

生徒の中で苦手が多い教科の一つが英語です。
小学校の英語活動のような、英語を使ったゲームや挨拶などの簡単な会話ならば楽しく、英語が好きという児童も結構います。
しかし、中学に入り文法など本格的な「勉強」となった場合、感覚ではなく理詰めで考えなくてはならず(一般の中学の授業がそのようにこれまでデザインされているので仕方ないですが)、難解な暗号解読のようになり感じられ、成績が付けられる。
そうするとこれまでの楽しみはすぐに消し飛び、頑張ろうという気力さえなくなることもあります。
そうならないように、生徒が英語に興味を持ち楽しみながら学べる授業を葛西TKKアカデミーでは目指しているのですが、現実に学校という存在がある限り、なかなかそのような理想的な授業も行えず、妥協して学校の勉強に即した授業になってしまうのが悩みです。
そこで今回は学校の定期テストに向けた英語の勉強法についてお話します。









勉強は千差万別、一人ひとりに適した方法があり、万人に通用するものはありません。
だから、個人個人に合わせて勉強を考え教えていかないといけないのです。
しかし、個々の事例を上げればきりがないので、ここでは一般論としての勉強法を紹介します。
これでうまくいかないからと言って心配する必要はありません。
その時は自分に合った勉強方法を見つければいいのです。
その際は葛西TKKアカデミーが力になりますので、是非、ご相談ください。
英語は毎日触れ、慣れることが大事
外国で生活をした経験がある方なら分かると思いますが、言語は毎日使っていないと驚くほど忘れてしまうものです。
海外の生活が長いと、ある日、自分の言いたいことが日本語で出てこないことがあります。
逆に日本に帰ってしばらくたつと、海外で生活していた時は何の問題もなく使えた英語が口から出てこない。
この傾向は特に子供に強く、小さい子供は言葉を覚えるのが早いですが、忘れるのも早いです。
つまり、言語学習では毎日その言葉に触れることが大切です。
英語を日常で使う機会の少ない日本では、生徒たちが自分から積極的に英語に触れようとしないといけません。
幸いにして現在はYouTubeやその他動画サイトなど、その気になれば英語に触れる機会はたくさんあります。
DVDやブルーレイで映画などを見るときにも英語の吹き替えや字幕を付けることもできます。
そうやって英語を聞く場を設けてください。
最初はよく分かりませんが、映像を見れば言っていることがなんとなくわかってきたり、単語をいくつか聞き取れたりできるようになります。
そうやって聞き取りが少しずつできるようになると、英語を聞くのも楽しくなります。
基本文で覚える
英語を勉強するとき「単語を覚えさえすればいい」という人がいますが、これは間違いです。
言葉は単語が単独に漂っている訳ではなく、単語同士が有機的につながり、文脈において的確に使われなくてはいけません。
つまり、文となって初めて言葉は意味を成してくるのです。
単語だけ覚えては使い方が分かりません。
だから、英語を勉強するときは単語で覚えるのではなく、文で覚えることをお勧めします。
文の方が長いので、これは効率が悪いように思えるかもしれません。
でも、人間の脳を考えると、脈絡もなく単語を覚えるよりも、他と関連付けて、それをヒントに覚えていく方が覚えやすいです。
このような基本文をたくさん覚えることが英語の理解を深め、実際に使える英語につながります。
基本文は簡単な言葉で作って構いません。
大事なのはポイントが分かる分の構造です。
「この分から、英語の過去形はこう作ればいいんだ」と理解してくれればいいです。
こうして基本文を身に付けたら、後はその中の単語を置き換えるだけで表現の幅が広がります。
文法用語は極力避ける
英語を勉強するとき、学校の先生の中には言葉の意味も十分に説明せず、やたら文法用語を使う人がいます。
これは教える方が楽なだけで、学ぶ側が決して簡単という訳でもありません。
むしろ、言語とは別に余計な用語を覚えなくてはいけないので、人によっては余計に混乱するかもしれません。
しかも、運の悪いことに英語で使っている文法用語の中には、国語の文法用語と同じものがあります。
しかし、日本語文法と違い国語文法は母語話者が自分の言葉を分析するために用いられるものなので、同じ用語でも意味が違ったりします。
これも混乱の原因となりえますので、できれば文法用語に頼るのは状況をよく分析してからにしましょう。
生徒の中には文法用語を聞いただけでアレルギーを起こしてしまい、「もう難しい、分らない」と思い込んでしまう者もいます。
特に子供の場合、その心理状況が学習に与える影響は大きいので注意が必要です。
本分を繰り返し読む
特に定期テストという観点で考えるなら、基本はやっぱり教科書です。
だから、教科書をしっかり勉強しなくてはなりません。
その際、色々理屈を考えながら分析しながら英語を科学的に理解するのもいいですが、言語という性質を考慮するなら「読む」ことは基本でしょう。
声を出して読めば(より多くの間隔を使うので)単語やいろいろな表現を早く覚えることができます。
その時注意しなくてはならないのは、発音をいい加減にしないということです。
あいにく日本の英語教育は発音を疎かにする傾向がありますが、人間の思考は脳内で音で行われていることを鑑みるならば、きちんと教え学ぶべきです。
そして、最初はよく分からないかもしれませんが、何回も何回も繰り返し読んでいくうちに、不思議なことに、だんだんと分かるようになってきます。
「読書百遍自ずから知る」とはよく言ったものです。
やっぱり学校のワークと教科書
定期テストでは多くの問題が教科書やワークから出ます。
そして、これらは事前にやれば解き方が分かるし、答え合わせをすれば確認もできます。
一回やったら間違ったところだけをもう一回やる。
これを繰り返し、全ての問題が丸になるまで頑張りましょう。
これでテストの半分以上は取れるようになります。
しかし、多くのできない生徒はこれをいい加減にやっています。
面倒くさいからと言ってきちんと問題を解かず、答えを写すだけ。
形式上は丸がついてやったように見えますが、結局何も身に付いていないので、当然テストでは解けません。
更に、高校入試では中学三年間の勉強が全て対象となるので、ここできちんとやらないとまた同じことを勉強しないといけません。
結局二度手間で、長い目で見るならやはり、ごまかしの勉強はすべきではありません。
後でもっと面倒くさいことになります。
勉強はテスト前にやるのではない
最後に、よくいるのが、テスト範囲が発表されるまで勉強しない生徒です。
「範囲が発表されないと何を勉強していいか分からない」ということらしいですが、そんなことはありません。
前回のテスト範囲の次から普通出されますし、今やっているところまでは確実にテスト範囲になります。
だから、発表されなくても既にやってしまうのがいいです。
早く課題を終わらせれば、その分学習内容の確認とテストの準備に費やす時間が増えます。
そうすれば、成績もきっと上がるでしょう。
わざわざ待つ必要はないのです。
毎日の余裕のあるうちに勉強に取り掛かり、ゆとりを持ってテスト勉強をすればより効率よく勉強が身に付きます。











中学では定期テストが成績の重要な部分を占めます。
だから、定期テストも視野に入れて中学では勉強しないといけません。
定期テストは必ず行われるので、それにどう対処するかが大きな分かれ目です。
英語ということで話しましたが、今回のポイントはほかの教科でも通じるものがあります。
すこしでも勉強に困ったときは、気軽に葛西TKKアカデミーにお知らせください。
必ず皆さんのお役に立ちます。



























2022.05.17
毎日の家での勉強時間はどのくらい?

「自分の子供は他の子供に比べ勉強時間が足りないのではないか」「今の勉強時間で本当に大丈夫なのか」という質問をよくされます。
実際に他の家の子が何時間勉強しているなど聞く機会もあまりありませんし、不安に思うのも無理はありません。
学校の宿題も含めて子供たちは毎日どのくらいの時間勉強すればいいのでしょうか。









家庭学習は必要?
「学校の授業さえ受けていれば勉強は大丈夫」「学校は必要な勉強を全て教えてくれるから、それ以外のことをわざわざしなくてもいい」などと考えている人は間違いです。
子供が学校に通う長い年月、勉強というものは生活の重要な部分を占め、欠かすことのできない要素です。
学年が上がり学習内容が高度になるにつれ、勉強を身に付け自分の能力として使いこなせるようになるには、学校の授業だけでは足りなくなっていきます。
そこで、授業で足りない分の勉強を補うために学校以外の勉強が必要となります。
宿題は家庭学習を明確にし、生徒がやるべき最低限の内容を学校が示したものと言えます。
しかも、学校の授業は前出の内容が身に付いているという前提でどんどん進んでいくので、授業や宿題をやっても身に付いていない分は、生徒が責任を持って何とかしないといけません。
それを怠って「分からない」を放置すれば、当然新しい勉強の内容も分からないので、ますます勉強に取り残されてしまいます。
「勉強が分からない」が「勉強ができない」になり「勉強が嫌い」になれば、遅れを挽回することは非常に困難となります。
そうならないためにも毎日の家庭学習が重要となってくるのです。約
また、学年が終わりに近づくと年間で予定された通り勉強が進まず、学校の授業でも「先生が教科書をざっと読んで終わり」とか、「後は生徒に自分で教科書を読ませて終わり」なんてこともあります。
特に中三の受験生などは、学校の進度で勉強をしていると三年の内容が終わらないで入試を受ける、または十分に受験べ強できないまま本番に臨む、ということもあります。
そうならないためにも、受験勉強は自分でどうにかしないといけません。
だから、受験生はそれまで以上の家庭学習が必要となります。
みんなは毎日、何時間家で勉強する?
ある調査によると、中学生の家での勉強時間の平均は約90分らしいです。
ほとんどしない生徒から3時間以上する生徒まで、その分布は非常に広がっています。
そのうち学校の宿題に費やす時間は平均40分くらいです。
つまり、多くの生徒が宿題以外の勉強を家でやっているということです。
恐らく塾や親から出される勉強をしているのでしょう。
中三になると入試もあって、家庭学習の時間はぐっと伸びます。
平均はおよそ2時間15分です。
学校の宿題は他の学年と変わりませんが、塾の勉強時間が大幅に増えます。
基本的に毎日塾に通っている生徒はいないので、それでも毎日の平均にした塾の勉強時間が二倍以上になるということは、実際に塾に行っているときの勉強時間がどれほど多いか分かります。
塾ではよく、学年+1時間は学校以外の勉強が必要と言います。
トップクラスの学校を目指す生徒はそうでしょうし、理想としてはそのくらい勉強してくれれば、学校の授業についていけないなどということもなく、クラスや学年でも上位を狙えるでしょう。
ただし、現実にそれをやっている生徒は多くなく、それは部活や他の習い事などで物理的に難しい場合もありますが、どうしてもゲームやSNSなどの誘惑に負けて勉強が手に付かない生徒も多いようです。
また、家で毎日勉強しているか調べてみると、「毎日勉強している」という生徒はおよそ40%だったそうです。
これに「週半分以上」という生徒を加えると全体の三分の二となります。
中学ではかなりの生徒がたくさん家庭学習をしていると言えるでしょう。
因みに、週一日以下の生徒も2割程度いるそうで、こういった家庭学習の実態の違いが、生徒間の学力格差の一因になっているともいえるかもしれません。
ただし、「長く家庭学習していれば勉強が身に付く」とは限りません。
この点に関して時間に関するデータだけでは分からないので注意が必要でしょう。
集中せずぼーっとしている時間が長いのかもしれません。
となると、勉強時間に加えて効率のよい勉強法というのも大事になってきます。
このことについてはまた別の機会に考えます。
小学生の家庭学習
小学生の毎日の家庭学習の時間についてはデータが見つかりませんでしたが、高学年では1時間ぐらいのようです。
小学生の場合、勉強の内容も難しくないので、小学校低学年であれば学校の宿題をするだけで十分でしょう。
この頃の子供は教科書の勉強も大事ですが、もっと体を動かして遊んだり、自然に触れていろいろな発見を経験することも大事です。
こうして基礎体力を養ったり、好奇心を育てるのです。
これ以外にもこの時期だからこそやっておいた方がいいことはたくさんあるので、できればそういった経験をたくさん積んでおくと、その後の人生の糧になります。
しかし、毎日の勉強の習慣は身に付けておくべきで、毎日5分や10分でいいので、家庭での勉強時間を設けた方がいいでしょう。
実は勉強の習慣づけは大切で、これがないと中学になって毎日のように勉強をしないといけなくなったときに非常に苦労になります。
歯磨きのように毎日のルーティーンにしてしまえば、やるのが当たり前になっているので適応も楽になります。
それから、たとえ小学生であっても、勉強で分からないことが出てきたときは、家庭学習で補う必要があります。
とにかく分からないときは早めに解決するのが一番です。
親が見て教えられるときは是非教えてあげてください。
どうしてもうまくいかないときは、家庭外にお願いするのも一つの方法です。
近くに知り合いのお兄さん、お姉さんがいればそれでもいいですし、塾などに行かせるのもいいでしょう(葛西TKKアカデミーは通塾していない生徒や児童でも、気軽に質問に来てもらっても構いませんので、遠慮なく利用してください)。








本日は家庭学習について考えてみました。
家で学校の宿題をするのは最低限の家庭学習なので、きちんとやりましょう。
そして、学校の宿題だけで足りないときは自主的に、時には外部から強制的にでも勉強をする必要があります。
どのように家庭学習をするかは大切な問題の一つですが、少なくとも毎日の習慣としての家庭学習はしておいた方がいいです。
特に受験になると嫌でも自分で勉強しないといけなくなるので、その時のためにも短くてもいいので、毎日の家庭学習を続けましょう。





















2022.05.16
文科省が進める”GIGAスクール構想”って何?

現在、日本の学校教育は従来の教育から大きく転換し、新時代に子供たちが困らないよう新しい教育体制へ移行しつつあります。
この度の大学入試におけるセンター試験から共通テストへの移行も、これら教育改革の中の一つです。
日本の教育が、その理念、方法、環境とあらゆる面で生まれ変わろうとしています。
その中で文科相が打ち出しているのが「GIGAスクール構想」です。
今回はこの文科省が目指す新しい教育スタイルについてご紹介します。









「GIGAスクール構想」とは
「GIGAスクール構想」は2020年に文科省が発表した新しい学校教育の在り方です。
これは学校のICT環境を整えて、高速大容量通信ネットワークを使い、日本全国全ての生徒が一人一つずつ端末を使えるようにすることで、特別支援を必要とする子供を始め様々な状況下にある子供全てを誰一人残すことなく、公正で最適化された教育を提供し、全員の資質と能力を育てる構想です。
これまで蓄積された教育実践におけるノウハウにICTを取り入れることで、学習活動がより充実し、主体的かつ対話的なより深い学びが得られる授業が受けらるとのことです。
調べものはインターネトを使って調べ、それらの情報を収集する過程で情報の整理分析取捨ができる能力が身に付く。
そして、パソコンを使うことでこれまでのような文章だけによる表現にとどまらず、写真、音声、動画などいろいろなメディアを使った発表、発信、作品ができるようになります。
更に、通信ネットワークを使うことで、遠距離や離島など地理的不利を解消すると同時に、これらのこれまで学習機会に触れるとが難しかった、もしくはできなかった生徒たちにも都心の生徒と同じように学習のチャンスに触れられます。
しかも、ネットワークの利用は学校内の枠を超え、リアルタイムで区域外、海外の生徒と共同して活動できるようになりますし、大学や専門機関との連携も可能となります。
デジタル教材を使い、誰もが分かりやすく興味を持ちやすい教材が提供でき、生徒一人ひとりの反応や考えを瞬時に捉えて、先生と生徒が双方向に発信しながら授業を進めることもできます。
しかも、小テストなども全てデジタル教材で行うので、クラス全体だけでなく生徒一人ひとりの学習習得状況も把握でき、それぞれの進度に合わせた学習教材支援を提供もできます。
更に驚くべきことは、これらの各教科の学習活動を横断的につなげSTEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)教育を実施することが可能で、実際の社会問題解決に向けた教育を行えるようになるそうです。
その探求の過程においてもICTを活用でき、課題の設定(社会もんだなどの現実にある問題を見つけ出す)、情報の収集(資料、文献の検索などICTを使っての情報を探す)、整理・分析(自分が集めた情報を統計や思考ツールなどで分かりやすくまとめ理解する)、まとめ・表現(自分たちの研究を論文にしたり、パソコンを使ってプレゼンテーションで発表したり、これらを多彩なメディアを通じて発信する)の全ての段階においてICTが有機的につながり、効率的に活動できるようになります。
また、これらの探求における、情報収集発信を通して情報に関するモラルも学べるということです。
以上が文科省が発表した「GIGAスクール構想」です。
文言だけ聞いてみると、まさに教育の理想形であり、教育における様々な問題を解決し、教育のレベルをこれまでにないくらいに押し上げてくれるように思えます。









「GIGAスクール構想」を進めるきっかけ
今回のコロナ禍では、ICTが整っていた多くの私立学校はそのまま一斉休校中でも学習を継続できた一方で、ICTがあまり進んでいなかった多くの公立学校では学習活動はほぼできなくなり、結果、両者に通っている生徒間の学習格差が広がったと指摘されています。
コロナ禍で休校が相次ぐ中、保護者や生徒からのオンライン学習の要望も高まり、文科省もGIGAスクール構想を前倒しして、公立学校全ての生徒への一人一端末を実現し、これらを使った授業やオンライン学習を実施しています(内容としてはまだまだ検討の余地がありますが)。
また、災害などの緊急事態でもICTを活用できれば、勉強を滞りなく進めることができるとも期待されています。
日本の学校におけるICTの利用はOECD諸国の中でも最下位で、ほとんど活用していないことが分かります。
当然、日本の教育はICTという観点において、諸外国から大幅に遅れを取っており、これも文科省が「GIGAスクール構想」を推し進めようという理由になっています。
更に付け加えるならば、これか技術が進みICT化がより身近になる世界において、これからの日本の若者が対応し、諸外国と対等にやりあえるようにしなければならないという、経済界からの要請もあるように思えます。
いずれにしても、これからの学校教育が大きく変わり、私たちがSFの映画やドラマで見ていた場面が、現実の教育現場で見られるようになると予想されます。








生徒の話を聞くと、確かに一人一端末は配られているようで、端末を家に持って帰ってオンラインのデモンストレーションをやったりもしているようです。
しかし、文科省が述べているような学習ができているかというと、まだ十分とは言い切れない感じです。
理由の一つは教員の訓練と経験が不十分であることだと思います。
制度が変わるとき、設備などのハードの面は比較的楽に整えることができますが、それらを生かし使いこなすノウハウや人材と言ったソフトの面の育成は時間が掛かります。
構想や設備は素晴らしくても、それらを上手く使いこなし、実際に生徒たちの教育に成果を出せなければ宝の持ち腐れです。
本来ならソフトの面もしっかりと準備した上で実行すればよかったのですが、コロナ禍や経済界の要求など様々な要因が絡んで見切り発車になった感は否めません。
生徒がGIGAスクール構想の利益を享受するまでには時間がまだかかりそうです。
そして、十分に生かされないままGIGAスクール構想が廃れて、これまでの費用が無駄にならないことを願います。

























