塾長ブログ
2022.05.15
創造的になろう!その方法と影響、そして注意点

創造的とはどういうことでしょうか。
単にいろいろなものを作り出せたり、いろいろなことを考えだしたりすることでしょうか。
確かにその通りです。
しかし、そうなるには様々な条件があるように思えます。
今日は、創造性について考え、それが勉強にどのようにプラスの効果をもたらすか見てみましょう。









「創造的」とは
創造的と言っても、それはしっかりした土台の上に築かれるものではありません。
歌舞伎などの伝統芸能など、伝統が重んじられ一見昔のままで不変のように見えますが、代々受け継いできた者たちが先代の型の上に新たな要素を付け加え常に発展し続けています。
新しく何かを生み出すには、しっかりとした基礎がないといけません。
この基本の「型」をなくして新しいものを作り出すのは「型なし」となり、見るに堪えないものになるでしょう。
学校教育は「創造的」?
勉強でも同じで、基本事項がしっかり身に付いていないと、新しい発想や発見の構築はできないでしょう。
しかし、今の学校教育は基礎的な学習事項を身に付けさせ、それを確認し、より高度な問題を解かせるようにはなっていますが、生徒自身が学んだことを基に創造的に作り出すようにはなっていません。
それは人数の多さや時間的制約、予算の問題などが原因でしょうが、学んだ生徒がゆっくり考え、自信を見つめ直しつつ新しいことを考える余裕はないように思われます。
間違いばかり指摘され、それができなければ人間としての価値がないまで言われることもある。
早く早くとせかされ、じっくり考え頭の中を整理して理解する時間さえ与えられない。
必然的に自分から考えるのではなく、与えられた道筋をいかにうまく歩めるかが大事となっていく。
それができず失敗やミス、嫌な経験が積み重なれば、自分は何をやってもダメだと感じ、困難を克服する気力まで失ってしまう。
実際に、葛西TKKアカデミーの生徒もこのように散々打ちのめされて心に傷を負った生徒が多いです。
少し話がそれてしまいましたが、言いたいことは「基礎応用を学ぶまではできても、現在の日本の教育は生徒による創造が難しい環境にある」ということです。
「創造的」になるには
では、どうすれば創造力が身に付くのでしょうか。
先ずは、自分の強み長所は何かを考え、そちらに焦点を当てることです。
今の教育は間違いばかり指摘し、弱点を克服させることに重きを置いているように思います。
人間、自分の弱いところには目をそむけたくなるのは当然です。
それを無理やり生徒に見せ、自分がダメなことを認めさせ、苦痛の中で克服せよというのです。
これでは委縮するのも無理ないです。
自分ができること、長所や強みに焦点を当て、それを生かすような教育ができれば、生徒たちは次々と結果を出し、そればプラスの影響を与え、生徒自身がもっと頑張ろうと努力するようになります。
そして、自分に自信がついてくれば、自分の苦手なことにも挑戦する心の余裕ができます。
成功の経験から得た自信をもって、失敗や間違いの恐怖心は弱まり、試行錯誤することも苦でなくなり、やがて自ら問題を克服するようになります。
このように自分に自信が持て、弱点も克服できて自分の能力があげられるようになれば、このことが色々なことに前向きにチャレンジする動機付けになります。
これまで否定的で周りを敵視したり、自分を否定したりする視点はなくなり、新たに広がった視野には喜びや希望、他者への感謝、自分への誇りなど今までと違ったものが感じ取れるようになるでしょう。
広い視点で落ち着いて客観的に物事を考えられるようになります。
そうすれば今まで見えていなかった可能性が自分の周りにたくさん見えるようになります。
この「可能性への気づき」が創造性の出発点になります。
つまり、プラスの感情(自己肯定感)が不可欠ということになります。
学校での先生の生徒への接し方、親が子に対する言動などは、果たして子供たちの自己肯定感を育んでいるのでしょうか。
子供たちの創造性を妨げているのは恐怖や恥ずかしいという誰もが普通に持つ感情です。
物心ついたばかりの子供たちは何も深く考えず、何でもやりたがり、些細なことでもできた喜びを十分に感じていました。
しかし、すぐに人前に出ることの恥ずかしさ、失敗することの恐怖を覚えるようになります。
そうすると、悪い結果を恐れて何もできなくなってしまい、創造性は育たなくなります。
創造的になるために周囲がすること
だから、このような不安や恐怖のない環境をいかに提供できるかが、子供が創造力を身に付けるカギになります。
それは周りの人間のサポートです。
失敗を非難するのではなく、一緒になってどうすれば解決できるが考えてあげる。
小さなことでも成功したことや人のためになったことをすれば褒めてあげる(実は褒めるというのは難しいのです)。
そして、本人が自分からやろうとすることは協力してあげる。
答えを教えるのではなくヒントを与え、目標にたどり着けるようにリードしてあげる。
時にはあえて失敗させるのも大事です。
人間は失敗から学ぶことは非常に多いのです。
失敗を非難するのではなく、許す寛容さをもってください。
目的は子供を責めることではなりません。
失敗から学べるようにサポートしてあげてください。









創造により成功やポジティブな経験が増えれば、前に進む強い動機となり、自分のなりたい姿が見えてくるでしょう。
そして、その目標に向かって自ら自信をもって進める。
当然、未熟な子供たちだから周りの人の支えは必要です。
この支えで子供の成長は大きく左右されます。
より前向きに進めるか、自信を無くして自分をあきらめてしまうか。
だから、彼らの周りにいる私たちは責任があり、その言動には十分注意してください。
























2022.05.13
各高校で行われる受験生とその保護者向けの見学会や説明会での注意点をお話します
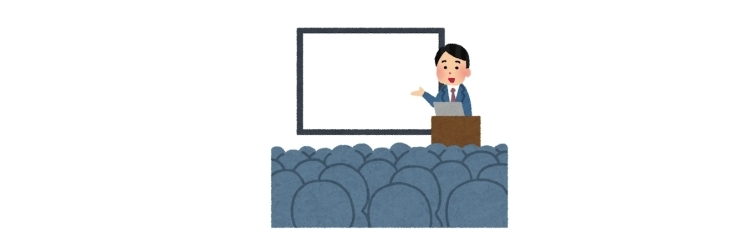
新年度が始まり、新しい学年にまだ馴染んでいない生徒もいるかと思います。
しかし、特に中学三年生は高校入試に向けて、少しでも早く準備をした方がいいです。
勉強もそうですが、自分の目指すべき高校を早めに決めることは大事です。
それは、早く目標が設定できればそれに向けた計画も立てられ、より長い準備期間を確保できるからです。
そして、自分の志望校を決めるうえで重要な要素となるのが、その学校の情報収集です。
「自分の行きたい学校はどこなのか」それを知る非常に良い機会が各学校が催す学校説明会や見学会です。
自分の目指す学校がどのような学校なのか、本当に自分の希望する通りの学校なのか知るためにも是非参加してください。
そして、そこに通う生徒、教える先生たちに実際に会い、生の声を聞きましょう。
後悔しない間違いのない高校選びのためにも重要なことです。
学校説明会や見学会が本格的に行われるのは夏休み以降になりますが、本日は少し早いですがこれらのイベントに参加するときのポイントを説明したいと思います。








コロナ禍の影響で最近はオンラインの学校説明会や学校見学を行っているところもあるので、こちらを利用してもいいでしょう。
しかし、本当に学校の雰囲気、学習状況、設備の充実度、通学の利便性など知るためには、やはり実際に自分の足で出向くのがいいと思います。
そこで、実際に訪れて学校が本当はどのようなものなのかを知る時に注意すべき点をお話します。
1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認
入れるならどこでもいいというわけではありません。
入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認するのがいいでしょう。
資料を見てコースやカリキュラムについて分からないことは必ず確認しましょう。
授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。
直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。
2.学校の施設や設備を確認
プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。
部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。
図書館やパソコンも大事です。
特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。
適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。
3.構内掲示や清掃状況を確認
掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。
掲示物がきちんと整理され見やすいか。
廊下や教室が綺麗に掃除されているか。
生徒の日常の営みが現れます。
また部活の賞状などは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。
4.公開授業は見た方がいいです
公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。
公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。
よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。
だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。
そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。
案外正直に話してくれるものです。
ダメ元で試してみるのもいいでしょう。









学校見学は高校を知る重要な機会です。
事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。
後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。
実際に学校に行って、授業風景を見たり、建物の中を歩いたり、先輩や先生の話を聞いて、それまで受験に関心がなかった生徒も現実のものとして進学を捉えられるようになります。
そして、試験に合格し晴れて高校生となった自分を想像し、奮起して受験勉強を取り組むようになる生徒もいます。
受験勉強の動機づけとしてもいいですよ。
最後に学校説明会や見学会についてもう一つ述べたいことがあります。
特に私立の高校では、まめに学校説明会や見学会に行くと入試に良い影響が出ると言われています。
何回も来てくれるということは、その学校に対する関心が高く熱意があると見なされるそうです。
繰り返し学校を訪れ、先生方に顔を覚えられると良い印象があるので優遇されるとかされないとか。








学校見学のシーズンはこれからですが、上記のことを気にしながら、しっかり学校を分析し、自分の志望校選びの参考にしていただければ幸いです。
また、葛西TKKアカデミーでは進路相談や受験勉強についてのアドバイスも行っています。
受験生をお持ちのご家庭は気軽な気持ちで構いませんので、是非ご相談ください。

























2022.05.12
今年から高校入試の英語でスピーキングテスト導入!葛西TKKアカデミーで模試が受けられます!
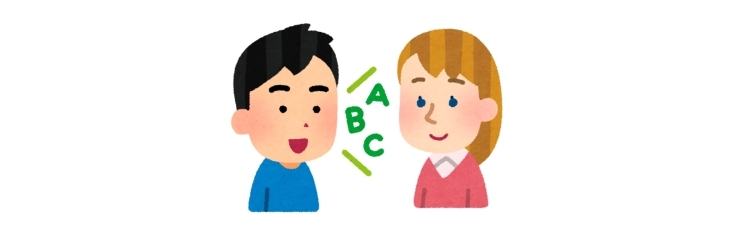
今年から都立高校入試でスピーキングテストが課せられます。
これまでの英語の「聞く」「読む」「書く」の三技能に加えて、「話す」も試験に導入することで、これまで指摘されてきた日本人の英語コミュニケーション能力の低さを克服しようという狙いがあると見えます。
初めての試みでまだ分からない点は多いのですが、今年から実施することは決定しています。
そこで葛西TKKアカデミーでは、このスピーキングテスト『EAST-J』に合わせた模試が受けられるようになりました。










都立入試でのスピーキングテスト『EAST-J』とは
東京都では都立高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加することになりました。
このスピーキングテストは『ESAT-J』と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します。
イメージとしては英検の二次試験の内容を対人ではなく、パソコンやタブレット端末などを利用して行う感じです。
試験内容
テストは四つのパートから成り、パートAは、カードに書かれた短い英文を読みます。
全部で2問あり、解答時間はそれぞれ30秒。
発声して答える前に30秒の準備時間があるので、この間に英文に目を通して、読む内容を確認したり、心の中で読む練習ができます。
本当に書かれてある英文が正しく読めるかどうかだけのテストです。
パートBでは図やイラスト、簡単な掲示物やチラシなどのビジュアルマテリアルを利用した問題になります。
全部で4問あり、そのうち3問はカードに関する質問に答える問題です。
解答時間は10秒で、その前に準備時間が10秒あるので、準備時間にできるだけマテリアルの内容を把握し、必要な情報がどこにあるかを確認できるといいです。
時間が短い分、質問に対する答えも簡潔なものになっているので、比較的答えやすいかもしれません。
例えばマテリアルを見ながら、明日の天気は何か答えるような問題です。
最後の1問はカードを基に受験生にミッションが与えられます。
自分の持っている英語力を駆使して、目的を達成するには何と言えばいいか答えなくてはいけません。
例えば、自分のほしい買い物をするには店員に何と言えばいいか答えます。
こちらも同様に、準備時間、解答時間共に10秒となっています。
パートCは4コマイラストの問題です。
この4コマのイラストを見て、英語で何が起こっているか答えなくてはいけません。
30秒の準備時間の後、40秒の解答時間が与えられています。
準備時間の間にどのようなストーリーかイラストから読み取って答えてください。
解答としては、各コマ一文ずつの英語で答えられるといいのではないでしょうか。
最後のパートDでは、質問が書かれたカードが与えられるので、それを読んで英語で答えます。
ここでは質問に対しての自分の意見とその理由が求められます。
例えば、「あなたが学校の一番好きな行事は何か、その理由も答えなさい」のような問題です。
こちらは準備時間が1分、解答時間が40秒となっています。
こちらも準備時間内で自分の意見をまとめておく必要があります。
以上が、現段階での試験内容になります。
例えばパートA、パートBは英検3級の二次試験に出てくる形式ですし、パートC、パートDは英検準2級以上の二次試験の形式になっています。
ただ、受けるのが幅広い学力差のある中学三年生なので、試験の難易度はかなり下げてあります。
これもコツさえ分かっていれば、それほど難しくないと感じています。
実施に当たっては、それぞれの決められた試験会場で、タブレット端末などにヘッドフォンマイクを通して音声を録音する形になるようです。
ESAT-Jの都立高校入試における評価法
ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。
試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。
この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。
評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。
そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。
送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。
つまり、調査書点に加えられるのですね。
その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。
これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。
・学力検査の得点
各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。
・調査書点
中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。
これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。
1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。
入試は1点で合否が分かれます。
だから、例え1点でも疎かにできません。
ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。
尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。
スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。










EAST-J向けスピーキングテスト
葛西TKKアカデミーでは、このスピーキングテストに対応するため、毎月『EAST-J』に向けたスピーキングテストを行います。
今月から受けられます!
育伸社が提供する『STE(スピーキングテスト for ESAT-J』を利用できます。
本番と同じように端末を使い、生徒が実際に問題をやって、自分の言葉で解答したものを録音し、約一週間でテスト結果が出ます。
100点満点で総合点が出され、パートごとの到達度が分かります。
そして、それぞれにアドバイスが付いているので、それを参考に今後の学習に役立てることができます。
何もしないでいきなり本番にチャレンジするのは危険です。
不慣れな状態で危機の使い方も分からにようでは、試験中に操作でオロオロして実力は出せません。
事前に練習し、試験の内容と流れを理解して本番に臨んでください。
そのためには(他の教科も同じですが)模試を受けるのが一番です。
しかも、結果の評価とアドバイスまでもらえるので、これはお得です。
更に、葛西TKKアカデミーではスピーキングテスト用の教材を用意し、スピーキングテストに向けた指導を受ける
こともできます。
スピーキングテストをより確実なものにするために、こちらの対策を受けることもお勧めします。
詳しくは葛西TKKアカデミーまでお問合せください。








このように都立高校入試においてスピーキングテストがかなり現実のものとなってきました。
しかし、多くの生徒や保護者はまだ知らないことが多く、どうしていいか戸惑っていることと思います。
しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。
そのためにも葛西TKKアカデミーで行う『STE』をご利用ください。
現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。
この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。
未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば問題ありません。
逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。
いろいろ分からないこと、不安なことがあると思いますが、そんな時はどうか葛西TKKアカデミーまでご相談ください。




























2022.05.08
葛西TKKアカデミーのICTを使った授業

コロナ禍で学校が一斉休校になったとき、その後もクラスターが発生し学級閉鎖が起きたとき、学校にICTが普及し活用しているかどうかで生徒たちの学習は大きく左右されました。
一般にオンライン学習などを既に活用していた多くの私立学校では生徒たちの勉強が継続されたのに対し、まだWI-FIや端末などすら十分に備えていなかった公立学校では生徒たちの学習が完全にストップしてしまうという事態になり、受験や進学などで大きな社会問題となりました。
これは多くの学習塾でも同じで、このようなICTの環境が整っていないたくさんの塾はやむなく休講となりました。
葛西TKKアカデミーにおいては、個々の多様なニーズに答えることがミッションの一つとなっており、そういう点においてコロナ禍以前からオンライン授業を提供していました。
更に、小規模個別指導塾という多くの生徒が交わらない個別対応が、対面式であっても十分な感染防止を可能とし、この混乱の中でも学びを中断することなく、全ての生徒にこれまで通りの授業を提供することができました。
そのような中で、今回は葛西TKKアカデミーが提供するICT教材を使った授業についてご説明したいと思います。
葛西TKKアカデミーが提供する多彩な授業オプションの一つとお考え下さい。








eboard
葛西TKKアカデミーでは、eboardを使った映像授業とデジタル教材を利用できます。
パソコンやタブレット端末などを使っていつでも、どこでも、何度でも勉強できる教材となっています。
1.映像授業
eboardでは毎回単元ごと、およそ5~10分の映像授業を見ることができます。
小学校から中学校まで、全主要教科に対応しています。
内容もコンパクトにまとめられており、とても分かりやすく基礎から自分で勉強できるように作られています。
よって、分からないときは何度でも戻って同じ授業を視聴することができますし、本人が望めば自分でどんどん先取りの勉強をすることもできます。
全ての映像授業には「やさしい字幕」がついており、傷害のある生徒やノンネイティブの生徒にも学びやすい工夫がなされています。
授業で先生の話を聞くだけよりも、視覚情報があった方が脳への刺激も多い分、学んだことが頭に残りやすくなります。
2.デジタル問題集
映像授業と連携してデジタル問題集も利用できます。
映像授業で学んだことの確認や定着を促します。
学習内容をすぐにアウトプットすることで、記憶の形成をより強固にします。
また、分からないときは「ヒント」ボタンがあるので、そこを押すことによって自動で関連する映像授業に戻ることができます。
生徒の取り組みは記録として残され、何をやったかだけではなく、実際にかかった時間や正答率も分析できます。
3.動画ノート
デジタルな授業や問題集に加え、紙に印刷された「動画ノート」も利用できます。
映像授業を見ながら、自分で動画ノートに書き込むことも可能です。
紙面に書かれている問題を解き、困ったときはそこにあるQRコードを読み込むとすぐに当てはまる映像授業を見ることができます。
こうして動画を見るだけでなく、書き込むという作業も加えることで、生徒の学習内容の定着を促進する効果があります。
このように三つの教材を組み合わせることで、自主的に生徒が勉強を進め、理解を深めることができます。
もちろん、これらの教材だけでは十分に習得できないときは、葛西TKKアカデミーの講師が一人ひとり丁寧に教えてくれるのでご安心ください。
また、生徒の学習状況は逐一記録され、生徒の弱点や必要な勉強を見極める貴重なデータとなります。
そして、生徒の学力診断として「ステップアップテスト」も用意され、実際の学力がどの程度のものか診断することができます。
これらのデータをもとに、定期テスト前などに生徒の実力を分析することで、適切なテスト対策や指導も可能となります。
注意点
注意点としては以下のようなことがあげられます。
第一に、この教材は教科書準拠ではないので、学校の教科書の内容を直接補完するようにはなっていないことです。
しかし、文科省の学習指導要領に従っていますので、必要な学習内容をカバーしています。
また、中学国語に関しては著作権の関係で、教科書にある現代文は扱っていません。
そして、英語場文法のみの取り扱いとなっています。
これらの点は注意する必要がありますが、学習内容は小中学生が学ぶべきものを網羅しており、内容も理解しやすく、取り組みやすい教材となっています。








デジタル教材を使ったICT教育は現在のトレンドで、多くの塾でも取り組まれています。
学校においても『ギガスクール構想』の下、WI-FIを利用したデジタル環境の整備が進んでいます。
そして、デジタル教科書も実用を目指して準備が進められて、やがてICT教育がこれまでの対面型教育を補完するようになるでしょう。
これまでのように決まられて特定空間(教室)で窮屈な状態の勉強から解放され、子供たちが興味を持ちやすい動画を配信することで、生徒の関心も強まり、より楽しくインパクトのある授業を受けることができます。
このように、葛西TKKアカデミーはeboardを使ったICT授業を提供することで、より安価に、より自由に生徒の学習を進めることができます。
詳しくは葛西TKKアカデミーまでお問合せください。





















2022.05.06
中学生から聞きいた”学校カースト”はこうやってできる
2022/05/06

以前、生徒が「学校カースト」について話してくれました。
興味深い話だったので、皆さんと共有したいと思います。
実際に現場にいる彼らの声なので、信憑性は高いと考えられます。
外部の人間には目につきにくいことで、貴重な話でした。










そもそも「学校カースト」という生徒間の上下関係は、特に決まったルールでできるものではないそうです。
小学から中学に進学した、新学年になったなどの節目に、生徒は必死にグループを作り、みんなその中に入ろうとします。
なぜなら、その中に入らないと孤独になると思うからです。
こうしてクラスの、学校のほぼ全ての生徒がどれかのグループに所属するようになります。
これらのメンバーシップは大抵LINEで行われます。
そして、メンバーの中で頂点に立つものが自然と生まれます。
偶然や成り行き、なんとなくみんながそう思うからという理由で、特定の生徒の発言力が強まりグループのトップになります。
決して財力や学力、身体的力で決まるものではないそうです。
むしろ、全体のなんとなくの雰囲気で決まります(興味深いですね)。
だから「学校カースト」の成立を阻止することは難しいのです。
こうなるとメンバーは、トップの気を損ねないことに尽力するようになります。
なぜなら、トップを怒らせることはグループからの報復、追放による孤立を生むからです。
トップを中心とした秩序が完成し、メンバーはトップの気持ちを忖度し(どこかで聞いたような言葉)組織が運営されます。
そして、トップの意に沿わない者、もしくは沿わないと思われる者は、グループ全体による攻撃対象になります。
これは事実ではなく憶測であっても行われるので、根も葉もない誤解や、陥れようとする謀略によっても攻撃されます。
攻撃は直接肉体的暴力ではなく、間接的な精神的ダメージを目的としたものが多いそうです。
LINEを始めとするSNSは強力な武器で、巧みに使って集団による言葉の攻撃や仲間外れなどをします。
その内容は残酷です。
言葉があまりにも思慮なしに簡単に行きかうので、「死ね」などの言葉も簡単に使われ、より攻撃された生徒を傷つけます。
でも、気軽にひどい言葉を簡単に使うので、攻撃する方はそこまで深く考えてはいません。
つまり、無自覚にいじめをしているのです。
生徒を言葉で追い詰め、もしくは策略を張り巡らせ、例えば標的の生徒が「死んでやる。」と言うように仕向ける。
すると、「あ、そう。良かったね。いつ死ぬの。何時何分?」と追い打ちをかける。
いじめる側はある種のゲーム、遊びのつもりでしょう(この点は従来のいじめと共通しています)。
いじめられた生徒を守るという正義感は、グループ内の空気が読めない野暮な奴となり攻撃の対象になりうるので機能しにくいようです。
むしろ、保身のために自分も攻撃に加わる。
なぜなら、傍観するのも空気の読めない野暮な奴だからみたいです。
攻撃を受けた生徒は逃げ場はなく、グループにとどまりいじめられ続けます。
抜けられない理由は、グループから抜け孤立することによる不利益が学校生活に与える影響を非常に恐れるからです。
こうしてSNSという閉鎖された空間で行われるので、外部の者には気づかれず事態は進行していきます。
例え外部の目に触れたとしても、生徒は巧みに隠語を使うなどして分からないようにしています。
外部には無意味でも、グループ内では非常に意味を持つ隠語の攻撃力はとても高いです。
もちろん、SNS内のいじめが現実世界でのいじめとして表面化することもあります。







まとめると、生徒はまずSNSを使い自主的にグループを作り加入することで学校生活の安寧を求めます。
その中で、なんとなくの雰囲気でトップが生まれ、それを中心とした秩序が生まれます。
そして、なんとなくの雰囲気でグループの馴染まないとみなされた者は、無自覚ゆえの残酷な攻撃の的となり、精神的苦痛を与えられます。
こうして攻撃する者、される者ができ、上下関係が生まれ「学校カースト」が誕生します。







注目すべきは「学校カースト」のトップにいても安心ができないということです。
なんとなくの雰囲気、空気でできている組織なので、なんとなくのきっかけで空気が変わるとトップも下層に落とされるそうです。
はっきりとした要因や仕組みでこうなるのではないので、本人たちも含む誰も防ぎようはないそうです。
つまり、生徒たち自身も何でこうなってしまうのか分からないのです。
そしてコントロールもできないのです。
それは、この仕組みを支配しているのが空気だからだそうです。
ここで述べたことは生徒の話に基づいた一例ではありますが、一考の価値はあると思います。






















2022.05.05
高校教育が変わります。ますます考える力が要求され、今までのように暗記だけでは太刀打ちできなくなります。

教育改革により日本の教育が大きく変わりつつあります。
ご存知の通り、大学受験でのセンター試験が廃止され、新たに共通テストになりました。
大学入試の変更は高校教育の変更に、そして高校教育の変化はそれに伴う高校入試の変化にもつながり、これまでのやり方ではますます受験に対応できなくなることが予想されます。








高校の科目が変わります
新しい指導要領では「世界史探究」「日本史探究」「地理探究」「理数探究」と「探究」の文字が入った科目が導入されます。
これまで「日本史B」「世界史B」などより深い内容を学習していた科目が変わったと考えていいでしょう。
しかし、これは単に名前が変わったのではなく、課題研究や課外活動を積極的に行うことが求められています。
自分で研究テーマなどを決め、調べ、結果を発表する。
つまり、高校時代の自分の活動成果を明示できるそうにさせるのです。
そして、その成果は大学受験でも合否を決める評価の一部として活用されます。
今までのように受け身で先生の言うことを聞くのではなく、自分から学ばなければならないのです。
それが出来なければどんどんおいていかれるという事態になるでしょう。
ますます考える力が要求され、日ごろから身の回りのことに問題意識を持ち探究する姿勢が求められます。
よって、高校入試でも文章を読ませ、それを踏まえて自分の意見を書かせる問題が増えていきます。
これは国語に限らず、数学や理科でも同様の問題が出されると予想されます。









単純な暗記では高校入試は難しくなる
よく英語を教えていると生徒が「英語は単語さえ覚えればいい。」と言います。
他の教科も同じで言葉だけ覚えればテストはいい点が取れると思っている生徒が多いです。
ある程度はそうだったかもしれませんが、これからは機械的な暗記や決まりきったテクニックだけでは高校入試は太刀打ちできなくなるだろうと思われます。
大学受験がそうであるように、高校受験でも資料から判断し自分の考えを組み立て表現する力を見られるようになるからです。
これは普段から訓練し慣れておかないと、一長一短では身につかないことです。
直前の一夜漬けでは対応しきれません。
まず出題された資料や文章を正確に読み取り、それをもとに自分はどう考えるか決めないといけません。
ここが最近の生徒の苦手なところで、「自分の意見がない」とよく困っています。
実際自分の意見が持てないということはないのですが、普段から考えることに慣れていないので、考える前に自分には無理と思ってチャレンジしないのです。
それから「一つの正解」を常に求められる教育なので「自分の意見が間違っている」のを恐れ、ちょっと考えて明確な正解が出ないときはすぐに諦めてしまいます。
しかし、これからの教育はますます正解のない問題に対応することが求められ、これまでの勉強への姿勢と考え方を変えないといけません。
そして自分の考えを文章にする表現力も大きく求められます。
これは国語に限らず、すべての教科でそうです。
これからは資料や状況を正しく「読み取り」、それをもとに自分の意見を組み立て「判断」し、それを文字や口頭で相手にわかるように「表現」することが大切になります。
「思考力」「判断力」「表現力」は一日にしてならず
以上、これからの教育では小手先の付け焼刃では対応できなくなることが見込まれます。
それに対応するには普段から把握し考え表現する経験を積まなければなりません。
これは学校の授業だけでなく日常の生活の中でも、そのような訓練をするような環境を作ることが大事です。
ニュースなどを見て子供と話し合ってみたり、家事をするときに子供と話し合ってどうするのがいいか考えさせたり。
学校でも部活や学校行事でも、子供たちに考えさせ決めさせることが大事です。
自分で決めるように導き、自分の意見を持たせるようにしなければなりません。
当然それにはじっくり考えるに十分な時間が必要になります。
ついつい急いでしまう世知がない現代ですが、イライラせず待つことが子供のこういった能力を育むことに重要です。
急いで、そして良かれと思ってつい大人は手を出しがちですが、そこは我慢です。
大人はこうすればいいと分かっているので、子供が同じでないとそれを否定し自分のやり方を押し付けてしまいます。
でも、これは新しく求められる力の成長を著しく阻害してしまいます。
分かっていても、時には失敗もさせることが大事です。
そして、その失敗を恥じではなく、新たな学びのもととして励ますくらいの器の大きさが大人にも求められます。
待つのはつらいですが、下手に気を使って先回りするのは逆効果です。









人間は考える動物です。
実は本能的に考えるのを楽しむ能力が人間には備わっているのではないかと考えています。
好きなことならいくらでも没頭します。
楽しいことばかりでなく(特に思春期の生徒には)悩み苦しむことも人生の大きな肥やしになります。
こうした本来当たり前の生活の中に、文科省の求める「思考力・判断力・表現力」を伸ばすチャンスはたくさんあります。
だからそれほど恐れる必要はありません。
ただ今まではそれに注目してきませんでした。
教育改革で状況が変わったので、その変化に対応する必要はあります。
大人としては、学校や家庭の生活の中で子供たちのチャレンジの機会を増やし、口を出しすぎないように注意しながら、子供たちの自分から考えるをサポートするのがいいかと思います。

























2022.04.28
「何か詳しくは知らないけど、聞いたことあるなあ」があると勉強により取り組みやすくなります。ゴールデンウィークにそんな経験を増やしましょう!

新学年が始まり一ヶ月、学校生活にも慣れてきた頃でしょうか。
コロナで外出は自粛で窮屈なゴールデンウィークとなっていると思いますが、学校がまとまった休みだからこそできることをしていただけるといいかと思います。
一緒に料理を作るとか、一緒に散歩がてら公園の花を見てみるとか、インターネットで動画を見てみるとか、コロナの危険を避けつつ、何か家族でできる活動ができるといいですね。
どこも行けないから家でじっとして何もしないのはもったいないです。
ゴールデンウィークだからという訳ではないのですが、子供のうちに色々な体験をさせることは非常に重要です。
それが直接勉強に関わっていなくても大丈夫です。
経験の豊かさは、子供たちの思考の豊かさにつながり、ひいては人生の豊かさにもつながります。
葛西TKKアカデミーも子供たちに様々な体験を持たせることをお勧めしますが、一応塾なので、「勉強に役立つから」という観点でお話します。









人間というものは未知のものには警戒感を抱き、距離を置きたくなるものです。
この感情を乗り越えて手を伸ばそうとするには、よほど強い意志や勇気が必要です。
(好奇心が強く、不用心に手を出す人もいますが )
)
実は勉強も同じで、子供たちは日々新しい、未知のものに挑戦しないといけません。
いつも授業で新しい知識を習う訳ですが、その時、新出事項が全く未知のものであればどうしても敬遠し距離を置いてしまいます。
「なかなかとっつきにくい。」「訳が分からない。」というような感情が起こり、勉強に対して軽い抵抗感、拒否反応が起こるかもしれません。
そうなると、それを改善してから勉強に取り組まなくてはならず、余計なエネルギーが必要となってしまいます。
そうなると楽しくなくなりますし、嫌な気分になるかもしれません。
勉強に対する壁ができてしまうと勉強の効率が悪くなります。
それを回避するためにはちょっとした予備知識やささやかな親近感があればいいのです。
これはその勉強に関する知識を前もって全て知っていなくてはならないというものではありません。
そこまですでに分かっているのなら、その単元はもう勉強する必要はありません。
ここで言いたいのはわずかなつながりがあれば、それをきっかけに親しみがわき、未知の分野に対する壁がなくなっていくということです。
つまりどういうことかというと、例えば微生物の勉強をするとき、微生物のことはよく知らなくても、以前に図鑑でミジンコやミドリムシの写真を見たというつながりがあれば、それだけで全く未知という訳ではなくなるので、その勉強に取り組みやすくなるということです。
この予備知識や体験がその勉強に深くかかわっていればいるほど、新しい学習に対する理解度は上がります。
だから一番いいのは、お子様の教科書を見て、何を新しく勉強するかを把握して、日常の会話や活動の中にそれらの話題を盛り込むことです。
関連のあるイベントや展示会、博物館などに一緒に行くのもいいでしょう。
(例年であればゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇期間中はこれらが沢山なるのですが、コロナ禍の現在では少し難しいかもしれません。)
または、インターネトや動画、本、雑誌、新聞などを利用して子供たちと一緒に見たり話したりしてあげるのもいい方法です。
こうしてこれから習うことに関連した経験や思い出を作っておけば、学校で学習するときに役に立ちますし、勉強に対する抵抗も少なくなります。
抵抗なく親しみが持てれば、新しい学習内容の習得もうまくいきます。









このように学校の学習内容に合わせて子供たちに経験や話し合いを促すのは効率的でありますが、実は与えるべき経験は学校の教科書に即したものでなくてもいいのです。
大事なのはいろいろなことに触れ、いろいろなこと浅い深いに関係なくつながりを持つことです。
なぜなら勉強において、どこでどのように経験が結びつくか分からないからです。
経験の範囲が広ければ広いほど勉強とつながる可能性が高くなります。
だから、お父さんの趣味の釣りでも構いません、お母さんの趣味のお菓子作りでも構いません。
何でも体験させてあげてください。
何がどのように子供たちに影響を与えるか分からないので、豊かな経験をさせてあげることは子供たちの人生に大いに役立ちます。
受験や検定試験の英語の問題でよく文化や歴史、科学が話題になることがあるのですが、例えば、長文問題でアインシュタインの相対性理論の話が出たとしましょう。
英語で何が書かれているのかよく分からなくても、相対性理論のことを本などで読んで理解していれば、だいたい何が書いてあるのか想像がつきます。
しかも、なじみがあるというだけで問題に取り組みやすくなります。
(逆になければ、相対性理論という言葉だけで白旗を上げてしまうかもしれません。)
これはテストにおいて大きなアドバンテージです。
私も指導において様々なことに興味を持ち、色々なことに触れるようにと伝えています。
それは以上のような理由があるのです。









ゴールデンウィーク、せっかく家族でいる機会があるのだから、このようにお子様を誘って色々なことにチャレンジしたり、一緒に話し合ったりするのもいいでしょう。
もちろんゴールデンウィークや長期休暇にこだわることはなく、少しでも子供が興味持ちそうだな、子供の役に立ちそうだなと思えばいつでも経験させてください。
それは難しく苦労することでも構いません。
成功しても失敗しても何らかの得るものはあるはずですし、後で思い返すと楽しい思い出になります。
勉強のためでもありますが、子供たちの豊かな人生のためにも、どのようなことでも貪欲に手を出し、可能な限りやらせてあげましょう。
























2022.04.25
通信制高校のメリット・デメリット
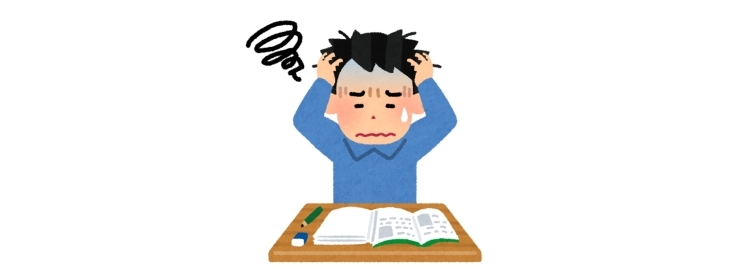
教育の多様化に伴い一般的な都立高校、私立高校だけでなく、通信制高校を選ぶ生徒も増えてきています。
不登校など、様々な理由で一般の生徒のように学校に通えず、内申や出席日数の問題で受験も受けられない生徒。
芸能活動など学業以外の活動をしている生徒。
どうしても進学先が見つからない生徒。
そんな生徒たちの受け皿として認知されることも多いようです。
受験生の中には通信制高校を考えている人もいるでしょう。
そこで通信制高校のメリットとデメリットを考えてみましょう。







メリット
通信制で良いところと言えば、色々な面で拘束が少ないこと。
履修や時間割を自分で決められるので、自分のペースで勉強ができます。
また、授業内容も中学生レベル、時には小学生レベルからやるので、中学についていけず脱落した生徒に一から教わるチャンスがあります。
様々な価値観が尊重されるので、あまり干渉されないのも特徴です。
拘束は少なく、これは自由と言えますが、自己責任とも言えます。
何でも自分から言わないといけないし、学校からいちいち言われることも少ないです。
授業は少人数制で、人見知りで人前で発表できないとか、大人数の組織に馴染めないという人には向いているでしょう。
しかも、毎日出席するわけではないので(だいたい週一回)、空いている時間を趣味やバイト、自分の目指すもの二使えるというのもメリットです。
一般の道を通ってこなかった生徒が多いので、新たな考えや価値観に触れることができるので、人間としての視野が広がります。
人数が少ないので、積極的に行動すれば先生との距離も近くなります。
学校による縛りが少ないので精神的にゆとりができますし、毎日毎日大人数の生徒が顔を会わせるわけではないので、スクールカーストもできにくいです。
元々そういう生徒の通う学校としての側面もあるので、病気で通学の困難な人に対する配慮があります。
デメリット
一方、それなりにできる生徒にとっては勉強の内容が易しすぎたり、授業の進度が遅いと感じることもあるでしょう。
学習が自分での勉強中心なので、大学受験などの高度な学習となると難しいです。
自分で計画的に勉強を進めていかないといけないのですが、怠けても何も言われないので、勉強へのモチベーションの維持と自己管理するのが大変とも言われます。
また、世間的に十分な理解が得られているわけではないので、通信制ということで周りからの偏見があり、負い目を感じることもあるようです。
一般の高校のように数も多くないので、学校が遠く通学が大変だったり、学費が高かたったりもします。
やはり、個人が尊重される分、勉強の結果も自分の責任なので、単位が取れずに進級できないということもあります。







いじめや不登校の問題が注目されるようになり、学校もフリースクールや通信制など、生徒の受け皿も多様になり、学業の選択の幅も広がりました。
そして、一般的な全日制の学校ではなく、その他のタイプの教育機関へ通う生徒も年々増えています。
しかし、一般的公教育でない教育機関では一般的生徒と同等の教育を提供することは非常に難しい状況になっています。
今回の通信制高校に関しても、高校卒業資格は手にできるでしょうが、大学受験となるとかなり難しくなります。
自分から自覚し積極的に勉強し、自分で受験制度を調べ、模試も自分で申し込まないといけません。
受験対策と言っても普通高校のそれに比べるとかなり見劣りします。
学校で使う教科書が中学生レベルからスタートするので(中学の学習内容も十分に身に付けていない生徒が多いため)、大学受験レベルには到底間に合いません。
学校で縛られなく自由な分、自制心と自己管理が不可欠となり、まだ十分に大人になりきっていない生徒に求めるのは酷です。
どうしても先延ばしにしたり、課題提出直前だけの勉強になったり、勉強以外のバイト、そしてそこで稼いだお金での遊びの方が優先になる場合が非常に多いです。
一般的学校ほど縛られない分、自分次第で良くもなれば悪くもなります。
しかも全てが自己責任で、周りは干渉しません。
良くも悪くもこれが通信制の特徴なので、高校卒業資格がもらえるからと安易に選ぶのではなく、本当にきちんとやる覚悟が自分にあるのか、一般的高校と比べ足りない部分をどのように補うのか、よく考える必要があります。
そして、考えたことが本当に実行できる仕組みを自ら課さなければなりません。
子どもがこれを一人でやるのは非常に難しいです。
ついつい自分の弱い心に流されてしまうなんてことはよくあります。
やはり外部のサポートがないと苦しいでしょう。
もちろん葛西TKKアカデミーはこのような子供たちのサポートを喜んでする用意がありますが、最終的に成功するかどうかは本人次第なのです。
















教育の多様化が起こっているということで、もう一点、気になっていることを話したいと思います。
フリースクールや通信制、自宅学習など普通の学校に馴染めない、諸事情で通えない生徒への受け皿が増えたことはいいことなのですが、受け皿があることで学校の無責任が助長されるようならば問題です。
学校で手に負えない、対応に非常に手間がかかる生徒に対して学校が教育を放棄し、これらの機関に押し付けるようなことがあってはいけません。
どんな生徒であれ学校は等しく教育を提供しなければなりません。
先ずは最善を尽くして生徒に取り組まなければなりませんが、多くの生徒を抱える学校がその努力を面倒くさがり、これらの受け皿に任せておけば責任から逃れられると考えるのであれば、これは全くの本末転倒です。
そのようなことが決してないように学校の先生にはお願したいものです。
教育というものは人の人生を左右するほど重大な影響があるのだから。









最後に簡単に今回の話をまとめると、通信制高校にはメリットとデメリットがあります。
多くの一般生徒とは異なる事情を抱え、普通の公教育自体を受けることが困難な生徒には適した選択肢となりえます。
自分のペースで基礎から(中学や時には小学レベルから)勉強を再チャレンジでき、高校卒業の資格を取ることはできますが、更にその先の高等教育を目指すなら、一般生徒以上の努力が必要になるでしょう。
それは学力だけではなく、自己管理など精神的な面にも及びます。
個々の責任と考えに従って勉強を進められるということは、通信制高校でどの程度の学力を身に付けるかも自分の責任となります。
一応、サポート体制は整っているとはうたっていますが、本当に一人ひとりの生徒が大学受験レベルまで力をつけるほど指導ができるかというと、少々疑問が残ります。
確かに、通信制高校は進学における選択肢の一つとして「あり」なのかも知れませんが、それをどの程度有効に生かせるかどうかは本人次第の部分が非常に大きいです。
つまり、うまくいかなかったときの責任は、全部生徒が被ることのないように、制度の充実が求められると思います。
単純に「大変な受験勉強を避けて高校卒業の資格を取るため」と飛びつかず、じっくり考えてから選んでください。
通信制高校に入ってはみたが、途中で挫折し本来の目的である高校卒業の資格すら得られなかったというケースも多く存在ますから。

























2022.04.24
五月病に注意!適切に対処しないと不登校のきっかけにもなります

ゴールデンウィークが明けると社会人と同様に、子供たちの間にも「五月病」が広まります。
昔からよく言われる五月病ですが、どのようなものなのでしょうか。
五月病が進行するとどのような結果が子供たちを待ち受けているのでしょうか。
今回は五月病について考えてみたいと思います。









新年度が始まる4月。
学年が変わるだけでなく、多くの生徒の中には進学して学校自体が新しくなり、これまで見たこともない新生活が全く予想できないという人もいるでしょう。
入学してすぐに、新しい学校についていろいろ教わると共に、これまでにない新しい環境への適応に苦労することと思います。
このように新しい環境に慣れるために、4月は非常に強い緊張状態が続きます。
過度なストレスにさらされ、新しい人間関係もなかなかうまく築けない。
全く知らない人ばかりの中で、新しい友達を作るのが苦手という生徒もたくさんいます。
忙しく苦しく、でもそのつらさを共有できる友達もいない。
結果、意欲が低下し無気力になり、一種のうつ病のような状態になることを「五月病」と呼びます。
五月病の睡眠障害は特に深刻で、免疫力の低下や偏頭痛やめまい、食欲不振になります。
精神的にもやる気の喪失、気分の落ち込み、情緒不安定、焦りと不安、イライラが起きます。
辛い4月を過ぎ、5月に長期の連休になり圧迫環境から解放され気が緩み、体のあちこちに不調が現れます。
そして、連休が終わるとき再び元の環境に戻れなくなります。
例えそれほどの精神的不安がなくても、ゴールデンウィークの間に生活リズムが壊れ、元の規則正しい生活に戻れないこともあります。








子供の場合、新入生は今までとは異なる学校生活に適応できなかったり、勉強も急に高度になりついていけなくなったり、友達や先生、先輩などの人間関係と様々な不安がのしかかります。
そこにパワハラやいじめなどの問題が絡むと、事態はより一層深刻になります。
本人に自覚がなくても、家を出る時に腹痛になったり、朝が起きれなくなります。
つまり、体が無意識に学校に行くことを拒否するのです。
最初は一時的なものとして学校を休むのですが、それが毎日のようになり、体が一般の生徒と同じようなリズムで動かなくなります。
朝、体が始動できず昼間で布団の中でダラダラ過ごす。
そうしているうちに午後になり、学校も行けなくなり、何もしないまま1日が終わってしまう。
昼間活発に活動していないので、夜になっても眠気が襲ってくることもなく、寝付けないので仕方なく動画やゲームをして時間を過ごす。
気づけば明け方になり、やっと眠気がやってくるが、こうなると他の生徒のように朝起きて学校に行くことは当然できません。
仕方ないので、また学校を休む。
こうして生活リズムは崩れ、昼夜が逆転し学校に復帰できなくなります。
不登校という状態になってしまいます。
勉強もどんどん遅れ、仮に体調が戻って登校できるようになったとしても、すぐに他の生徒と一緒に授業を受けることはできないでしょう。
実は、このように五月病になって、そのまま不登校になる生徒はとても多いです。
特に最近はコロナ禍の影響もあり、不登校生徒は毎年増加傾向にあります。










対処法としては病院に行き医師と相談することですが、現代の医療でも正確に症状と原因を把握することはできず、様々な薬や治療と試しながら様子を見、最も効果的なものを手探りで探すような場合がほとんどです。
治療とは別に一般に行われている対処法としては、本人にプレッシャーを与えないというものがあります。
焦って無理やり学校に行かせたりすると、かえってストレスが強まり症状を悪化させることがあります。
できるだけ本人のペースで、先ず生活リズムを整えることに集中するのがいいそうです。
そして、家に閉じこもってばかりいるのではなく、外に出て適度に運動をすることも大切です。
これは体内時計を整えたり、体力の維持につながります。
何であれ体力は必要ですから。
それから、子供との対話を増やすのも大事です。
対話がストレスの発散になり、相互理解を深め、安心感を与えます。
そうすると、気持ちも楽になり復帰もしやすくなります。
学校をしばらく休むことにもなりますので、家庭や学校、病院が密に連絡を取り合い、協力して生徒の回復に努める必要があります。
誰かに押し付けたり、本人をほったらかしにしてはいけません。
様々なアクターの連携が、子供たちを五月病から回復させるカギになります。









五月病は子供たちの性格や考え方など、精神面の影響が非常に大きいです。
まじめで頑張り屋さんに限ってなることが多いです。
何ら悪い生徒ではないのに、本人も学校に行きたいのに行けない。
これは本当に不幸な話です。
初期対応を誤ると長引き、いつまで経っても学校に戻れなくなります。
当然、学力や出席日数など、受験にも影響が出ます。
希望通りの進路を断念しなくてはならなくなることもあります。
それは可哀想過ぎます。
そんな生徒を生み出したくはない。
葛西TKKアカデミーは生徒のために可能な限り力になる用意があります。
早めの対応に越したことはありません。
少しでも不安があれば気軽にご連絡ください。



























2022.04.23
子供たちはどうして綺麗な字が書けなくなってしまうのか

字を綺麗に書くとはどういうことでしょうか。
書道家のような芸術的な文字を書くということではありません。
少なくとも学習においては、自分も含めた読み手が正確に読み取れる文字を書くということです。
実際、字を書くのが雑で、自分の書いた字でさえ読めなかったり、間違って読んだりする生徒もいます。











字がうまく書けない理由は大きく二つあるでしょう。
一つは、うまく書くことの必要性を感じないから。
もう一つは、上達の途中でうまく書けるレベルに達していないから。
前者は、「字を書くことは単なるメモで自分が分かればいい。丁寧に書く暇があったら課題をどんどん解決しなければならない。」と考えています。
メモと捉えているので、他者に見せ読んでもらうことは想定していない。
だから必要最小限の時間で済むように殴り書きになる。
よく高名な学者や作家の文字が読めないというのは、こういう理由だからでしょう。
でも、この姿勢に慣れてしまうと、いざ他者に読んでもらわなければならない文章を書くときに書けなくなってしまいます。
特に課題を提出して評価をしてもらったり、テストで採点をしてもらう必要のある生徒は、これではいけません。
社会人でも同じで、自分のためだけの文字とは別に、他人に読んでもらうための文字を持つことが必要です。
後者は、練習が十分に足りていないからうまく書けない状態です。
つまり、コツがわかり練習すればやがてうまくなるということです。
そもそも学校で字を教わるとき、字を覚え書けるように指導されることはあっても、どのように書けば綺麗な字になるかという指導はされないことが多いと思います。
だから、みんなが我流で書くので、自分のスタイルがうまくできないときは、他者から汚い字を見なされるのです。
こう考えると綺麗に書けなくても仕方ないという気がします。
よって、コツを覚え練習するのが解決法でしょう。
いずれにしても、自分の書いたものを読んでもらうという生徒の立場を考えれば、綺麗に書くということは必要です。
それは将来社会人になっても必要となるでしょう。
なぜなら、文字で人柄を判断されることがあるからです。
ところで、現在の生徒たちの特有な原因があります。
生徒を取り巻く生活環境の変化です。
技術の発達により、現代人(子供も含む)は字を表記する機会は多いですが、書く機会は少なくなっています。
SNSやメールの使用頻度は多く、友達との文でのやり取りは増えていますが、それは全てキーボードで行われます。
自分の手で書いてはいません。
英語圏であれば、課題は手書きではなく、タイピングすることを奨励されます。
しかし、日本の学校で(少なくとも小中学校では)はそれはないでしょう。
なぜなら、漢字の書き取りも評価の一つになるからです。
従って、手書きから逃れることは難しいでしょう。
この環境的要因に、「面倒くさい」と言う多くの生徒が口にするフレーズが絡み、手書きの文章に対する生徒の嫌悪と機会の消失がますます強まってきます。
(因みに、文字だけでなく文章の内容に関しても、この現代テクノロジーの生徒に与える影響は見逃せませんが、これはまた別のときに。)
以上、生徒の字を書くことに関する考察でした。
皆様はどう思われますか。































