塾長ブログ
2022.01.31
子供の睡眠障害についてしっかり睡眠を取るにはどうすればいいか

思春期の成長の中でホルモンバランスが崩れ、夜眠れず、昼間起きられずに学校の授業を受けられない生徒がいます。
私が子供のころには聞いたことなかったのですが、社会的に認知されてきたせいか、最近ではそのような生徒が多いようです。
朝起きられない、頭痛がする、腹痛がするなどの理由で学校を休まなければならない。
慢性的ではないにしても、時折このような症状で学校に行けない生徒がたくさんいます。
原因が必ずしも明確でなく、よってその対処法も人それぞれで確立していないみたいです。
病院での治療もありますが、薬だけでは子供に合わないなど、解決しないことも多いようです。
思春期の一時的ホルモンバランスの乱れが原因であるなら成長するうちに自然と治るそうです。
でも、今、学校で学ばなくてはいけない生徒に取って授業が受けられないのは非常に困ったことです。
授業を受けたいのに、体のせいで受けられないというのが厄介な所です。
また、これが成長期の一時的なものかどうかというのも、実は明確に分かっていないようです。








睡眠障害(睡眠のリズムが崩れたとき)の対処法
このように成長期の子供たちで睡眠障害に悩む人は多いようです。
そこで、寝付けないなどで悩んでいる場合、次にことをお試しください。
これは睡眠障害の子供に限らず一般の方にもお勧めです。
1.睡眠前の携帯、パソコンは厳禁
携帯電話やパソコンのスクリーンからの光は強烈で、睡眠前に見ると脳内の眠りのホルモンを乱してしまいます。
寝る2時間前には見ないようにしましょう。
とは言え、SNSなどで携帯の画面から目が離せないのが現代の生活となってしまっています。
難しいと思いますが、自分の健康のために行ってください。
家族やSNSの相手にはっきりと宣言し、寝る前は返事をしないと伝えることが大事です。
そうすれば、こちらの事情も分かり連絡もなくなるでしょう。
携帯を目の届かないところに置きましょう。
2.朝、窓を開け太陽の光を浴びる
人間の体内時計は朝日によってリセットされ、実際の日照のリズムと合うよう調整されます。
こうやって人間は毎日正確なリズムで生活できるようになっています。
いつまでもカーテンを閉め、布団にもぐらないことです。
パッと朝日を浴びると気分もスッキリします。
3.寝る前に足元を温める
特に女性の場合、足元が冷えて寝付けなくなることが多いようです。
これから暑くなってきますが、足元だけは布団をかけて温めましょう。
血液の循環もよくなります。
血液の循環がよくなると体温も上がり、眠りやすくなります。
4.毎日決まった時間に寝ましょう
毎日同じ時間に寝る習慣を付けると、体が自然にその時間に眠くなります。
最初は難しいと思うので、一日の計画表を作り、それに従うようにしましょう。
できれば家族もその時間に合わせて眠るようにすると、習慣づけが楽になります。
同様に起きる時間も決めましょう。
休みだからと言って、昼間で寝ることはよくありません。
そこで生活のリズムが崩れると、また整えるのが大変です。
ちなみに、休日の寝だめは効果ないそうです。
5.寝る前のルーティーンを決める
本を読むなど、寝る前のルーティーン(決まった行動・儀式)を決めるのも効果あります。
これが体に染みつくと、眠くなくてもこの行動をするだけで眠くなります。
6.寝る前のカフェインはやめる
お茶やコーヒーに含まれるカフェインに敏感な人がいます。
カフェインは脳を興奮させ、眠りにくくさせます。
そのような人は睡眠前にはカフェインを控えましょう。
7.どうしても眠れないときは無理に寝ようとしない
精神的原因で眠れないこともあります。
色々考えてしまう。
悩み事であったり、プレッシャーであったり。
寝よう、寝ようと焦ると反ってそれがストレスとなり目が冴えたりします。
そんなときは無理やり寝ようとしないことです。
気分を変えて読書をすると、目が疲れて眠くなるかもしれません。
それでも無理な時は、単純に横になって目を閉じてじっと静かにするだけでも構いません。
これでも体の70%は休まるそうです。









睡眠は特に勉強しなくてはならない生徒にとって重要です。
記憶は睡眠によって確立されると言われているからです。
例え勉強しても寝不足では覚えられません。
徹夜してもすぐに忘れてしまうのは、これが理由です。
現代は夜型社会になっているので、早寝早起きすることは難しいと思いますが、十分な睡眠を取ることは健康な生活を送る上で必要不可欠です。
上記の内容をよく読んで、なかなか眠れないときは参考にしてください。
実は、勉強がよくできる子供は睡眠も十分にとっているという統計もあります。
寝る子は育つ。
心身ともに健全な成長のため、睡眠について考えてみてください。

























2022.01.29
オミクロン株で学級閉鎖!休校が相次いで受験にも影響が
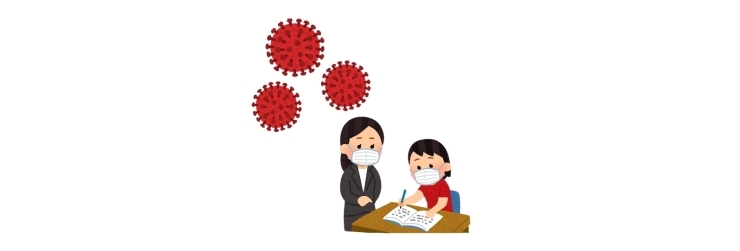
ご存知のように、新型コロナウィルスのオミクロン株による感染が急拡大しています。
これまでの株に比べてかなり強力な感染力を持ち、東京でも一ヶ月ほど前は二桁だった新規感染者が今は一万人を超えています。
これを受けて、東京でも21日から「万延防止等重点処置」が始まりました。
これまでにない急速な感染拡大が今回のオミクロン株の特徴の一つですが、若い世代の感染率も非常に高くなっている点で、教育現場でも早急の対応が迫られています。
更に悪いことに、この感染拡大が受験シーズンとも重なり、受験生への影響と入試を運営する学校側の対応が心配されています。









今回のオミクロン株は感染力が非常に高いことが一つの特徴であり、それは新型コロナのワクチンを打った人でさえ感染してしまうほどです。
そして、もう一つの特徴が、これまでは感染の少なかった10代以下の子供たちの間でも感染が広がっている(全体の25%)ということです。
今回の新型コロナウイルスの蔓延に伴い、ワクチン接種の年齢を12歳からと引き下げましたが、それでもオミクロン株の感染拡大は十分には止められそうにありません。
東京だけでなく全国各地で保育園を含む学校などの機関にクラスターが発生しており、状況に応じて休校や学級閉鎖、分散登校などを実施しています。
とは言え、個人ができることと言えば相変わらず「マスク、うがい、手洗い、3密を避ける」などで、これ以上の手の打ちどころがないのが現実で、学校などの施設側も「こまめな消毒、換気、会話や行動の制限、学校行事の中止または延期」とこちらもこれまで通りの新型コロナウイルスに対する対策しか取れません。
日本各地の教育機関でもクラスターが発生しており、自治体レベルでの休校や時差登校なども起こっており、子供たちの勉強への影響が心配されています。
しかし、文科省はこれまでの経験から第一波のような一斉休校は行うつもりはなく、それぞれの自治体や学校レベルでの判断にゆだねています。
更に、コロナ禍を受けて、オンライン授業をいち早く普及させ休校であっても生徒たちの勉強が止まらにように、既に「一人一端末」の号令の下、全ての生徒にはタブレット端末などで学校に行けなくても授業が受けられる仕組みができています。
実際にはWi-Fiなどのハード面に関する技術的な問題や授業を行う先生と生徒に関する技能的問題などあり、学校で行っている授業内容をそのまま継続できるいる訳ではありませんが、少なくとも形式上は教育をストップしなくてもよくなっています。
ところで、この休校や時差登校などの連絡は予告もなく突然に入ってくるかもしれません。
生徒を持つ家庭としては、このような状況になったとき家族はどのように対応するか(場合によってはご近所や生徒の友達の家庭とも協力して)、今のうちに話し合い決めておいた方がいいでしょう。
困ったときこそソーシャルネットワークやヒューマンネットワークがものを言います。
特にシングルマザーなど、容易に仕事が休めない家庭は何らかの助け合いの仕組みがあるといいですね。









今回のオミクロン株の感染拡大について最も不運だったのが受験生でしょう。
去年に引き続き生徒たちはコロナ禍で困難な勉強を強いられてきたのですが、その苦労を乗り越え、あと少しで自分の集大成を達成しようとするタイミングで、このような感染力の強いオミクロン株が流行してしまったのは非常に不幸なことです。
受験生においては、感染予防を引き続き厳として、同時に受験のタイミングに合わせてベストコンディションに持って行かなくてはいけません。
これは本人の努力のみでは難しく、家族を含む周囲の人間も、新型コロナウイルスに感染しないように注意しないといけません。
日常のあらゆる場面だけでなく、受験会場に向かう移動中も気をつけてください。
本人が感染してしまえばもちろん入試は受けられませんが、濃厚接触者でも別室受験など不利な状況での受験になる可能性があります。
感染しないのが一番ですが、これだけ新規感染者が拡大している今、こればかりは運次第という面も否めないでしょう。
入試を実施する大学をはじめとするあらゆる学校で、新型コロナウイルスへの対策は行われており、施設全体の消毒、試験監督や運営者の健康管理、受験生同士の座席の間隔を開けたり、決められた導線によって会場へ誘導するなどの処置が行われています。
いろいろ制約があり不便に思われますが、感染防止のためにみんなが甘んじていることなので、つらい思いをしているのは自分だけではないと自覚し、会場での指示に従い、安全な入試に協力してください。
各学校では状況に応じて試験日程や会場の変更など、逐一情報を更新し公開していますので、ホームページなどで情報チェックをまめにしましょう。
共通テストを始め多くの試験において、新型コロナウイルスに感染して受験できなかった生徒のために追試や予備日を設けています。
よって、感染してしまったからと慌て絶望するのではなく、受験先と連絡を取り合い、どのように対応すればいいかをきちんと確認してください。
このような状況なので、基本的にどの学校の何らかの救済処置は用意してあるはずです。









最初のコロナウィルスの混乱からかなり時間が経ちました。
社会全体として、新型コロナウイルスへの対応に関する知恵もついてきて、全くの未知であった第一波に比べ、誰もが比較的冷静な行動がとれるようになっていると思います。
それは学校や家庭も同じで、多くの学校で感染者が発生した場合の対応、クラスターが出た場合の対応が事前に準備され、問題が起こったときも子供たちの教育を止めない方策が練られています。
コロナ禍もかなり長期化し、出口も見えずにうんざりしている人も多いでしょう。
そして、現実にコロナ禍によってもたらされた困難で、子供の教育だけでなく家族の生活さえ維持していくのも難しい状況に陥った家庭も数多くあると考えます。
葛西TKKアカデミーは、勉強をしたくてもそれが難しい家庭の味方です。
困ったときは何でも遠慮なくご相談ください。
お待ちしております。
























2022.01.29
教育のデジタル化が手書き文化を衰退させる

日は前回途中で終わってしまった「手書き」に関する話の続きです。
日本は世界的に見て教育のIT化に大きく後れを取っています。
それでもコロナ禍があって、ようやく生徒たちに一人一端末の配布を終わらせたようです。
とは言え、これは端末を配っただけで、学校教育においてそれを有効に活用しているかというと、全くそういうことはありません。
この点はまた、生徒と話をしましたので後日お知らせします。
まだ教育のデジタル化が十分にできていない日本ですが、デジタルディバイスを上手く使い日本より何歩も先を進んでいる諸外国では、教育のデジタル化による弊害が報告されています。
その一つが「手書き離れによる教育効果への影響」です。









教育のデジタル化が進むと文章の作成や記録は主にパソコンなどで行うようになります。
当然、自分の手で文字を書くのではなく、パソコンのキーボードをたたくタイピングになります。
しかし、パソコンやダブレット端末を早くから導入している国々では、全ての文章をパソコンで書くのではなく、ある程度はあえて生徒たち自身の手で書くようにさせています。
キーボードを打つだけの方が文章は楽に早く書けます。
なのに、なぜこれらの国々では手書きをわざわざ残して、効率性を落としているのでしょうか。
それは手書きにはタイピングにない教育効果があると言われているからです。
例えば様々な報告によると手書きは、自分の頭の中で整理してから書き出す訓練になるそうです。
また、人間がノートを取るときは、黒板に書かれた情報を単に写し取っているのではなく、板書した状況をエピソード記憶として脳内に保存します。
覚えなければならないものそのものを思い出など他の要素と結びつけることにより、記憶はより深く強く残ります。
人間の脳は何かを関連づけることによって、記憶が思い出しやすくなります。
タイピングは単純なパンチングの繰り返しになるので、この点は弱くなります。
また、手書きは頭の中で書く内容をもう一度復唱しながら書いたり、どういうことかなと考えまとめながら進みます。
つまり、タイピングよりもずっと脳細胞の活動が活発になるのです。
そうして、書きながら頭の中で何度も反芻する勉強はより理解を深め分かりやすくなります。
一方、タイピングはスピードが速い分、脳内でじっくり考えながら書くことができません。
従って、タイピングだけでは深く考えるという練習にはならないのです。
先ほど、記憶を呼び起こすには手書きの方がいいと言いましたが、ある研究によると、スマホやタブレット端末より手書きは創造的な活動にも効果的だそうです。
この実験によると、紙とペンを使ったグループでは、言語、資格、記憶を処理する領域で脳が活発に活動し、紙に付随する写真や余白のメモなどが物理的映像としてより記憶できるそうです。








人間の脳は便利になれば教育効果が薄れます。
最近の教育(教育に限らず社会全体がそうですが)は、生徒に苦労させないことを売りにして、世間的にもそれが歓迎されています。
面倒くさいのは悪で、簡単なのが善と。
しかし、本来勉強は面倒くさいものです。
面倒くさいからこそいろいろ学べるのです。
個人的には、現代の苦労を敬遠する傾向は生徒にとって不幸なことだと思います。
なぜなら、人間の思考の余地が減っているからです。
昔は「若い時の苦労は買ってもせよ」と言ったものですが。
思うようにいかないから、どうすればいいか考え試行錯誤し、粘り強く繰り返し考えることで、脳は鍛えられ思考の成長につながるのです。
分からないときは検索してすぐに解答を見つけ、それを繰り返すだけでは自ら考える力はあまり育ちません。
手書きもそうです。
私は常々、勉強は肉体労働だと言っています。
ただ、目で見て読んで覚えて終わりが勉強ではありません。
手も足も顔も、体全体を使ってより多くの刺激をくみ取って、脳を活性化させた方がより勉強は身に付きます。
特に手が与える脳への刺激は大きく、やはり書くということは大事だと思います。
しかし、今の生徒や教育関係者はできるだけ最小限の仕事で結果(テストの点を上げる)を出そうとします。
確かに一見成績(テストの点)が上がったようになるかもしれませんが、それはテストという定められた問題に対して機械的に答えを返している(反応している)だけで、本当に考えて導き出した答えかどうかは怪しいです。
教育現場でデジタル教材を使えば大丈夫などと言われたときは要注意です。








技術の進歩に伴い学習スタイルも変化します。
しかし、何もかも変えてしまうことがいいとは限りません。
一見便利そうなデジタル教材が、これまでの学習スタイルよりも必ずしもいいとは言えません。
多くの人が経験則として紙とペンを使った方がよく覚えられたと言っていますし、多くの研究で「手書き」の脳に与える学習効果を再認識しています。
ついつい新しいものに飛びついて、それですべて安心と思いがちですが、教育に携わる者としては慎重にそこは見極め、それぞれの長所を上手く組み合わせて、生徒の置かれている環境を考慮しながら、教育方法を考えるのがいいでしょう。
要はバランスかもしれません。
デジタル化が進んでいる世界の教育を見てみると、「手書き」が100%なくなることはないようです。
不便で面倒くさくても、学習においてはその方が人間の脳は心地よいのでしょうか、苦労した方が脳が発達するとは皮肉というか、やはり人間はアナログなんだと改めて感じます。
私はそんな人間臭い、いや、人間味あふれるところが好きで、教育においては大切にしていきたいと思います。
これから日本の教育はどんどん変わり、私たち大人が経験したことのないものになっていくでしょう。
でも、デジタル化にあっても、その根底には人間教育があるんだということを忘れず、「手書き」を始めこれまでの長い教育の歴史の中で培われたアナログな勉強も大切にしていきたいと思います。
























2022.01.28
生徒たちの筆圧の弱くなりきちんと字が書かなくなった原因

皆さんが子供のとき、どの濃さの鉛筆を使っていましたか。
鉛筆は芯が基本的に固いものをH、柔らかいものをB、そして、添えられている数字がその度合いの大きさを表します。
私は他の人と同様にHBを使っていました。
しかし、今の生徒はHBを使わないのです。
何と2Bを使っています。
私のころは2Bを使うと、芯が柔らか過ぎて手が真っ黒になってしまうので、美術の時間以外は使っていませんでした。
では、なぜ、今、2Bを使うのでしょうか。
そして、これからITC授業などでますます鉛筆で書く機会が失われると予想されますが、その時、生徒たちの勉強にはどんな影響があるのでしょうか。









何で2B?
先ず、現在学校で2Bが奨励されている理由ですが、それは生徒たちの筆圧が非常に弱くなっているからです。
私も授業で生徒たちが鉛筆でノートを書くのを見ますが、とても力を抜いてノートの表面を軽く滑らせるように書きます。
「止め」や「はらい」など書き方の基本テクニックもなく、鉛筆を持ち上げることもないので、つながった曲線がダラダラ続いているような印象です。
しかも、非常に薄い。
ちょっとこすれれば、すぐに消えて読めなくなるくらいです。
学校の先生も苦労しているようで、テストなどで何を書いたのか分からず、採点ができないほど。
しかも、一画一画丁寧に書いていないので、文字そのものも判別できません。
更に悪いことに、書き順も無茶苦茶なので、バランスも悪く余計読めない。
先生もご苦労様です(他人事ではありませんね)。
文章でなくても、政界に○をつけなさいという問題でさえ、消しゴムで消して残った跡と、生徒が正解と選んでつけた〇の区別がつかないということもあるらしいです。
いまいちピンとこない人は自分のお子様の文やお友達の書いた文字を見てみてください。









生徒たちの文字が薄くなって読めなくなった原因
筆圧の弱さの原因は手の力の低下とみられています。
実際に体育などの体力測定では握力を始め腕力の低下が確認できます。
これは日常生活の中で手を使うことが減ってきているためと考えられています。
例えば、蛇口や瓶など固く閉まったものを開けることが少なくなっています。
それも一つの原因でしょうが、私が注目しているのは生徒たちが文字を書くときの姿勢です。
昔は、「背筋を伸ばして、左手でしっかり押さえて、文字を丁寧に書きましょう。」とよく言われました。
しかし、今の生徒は姿勢が悪くリラックスしすぎて、書くときに力を入れようとしません。
左手はノートを押さえずれないようにするのではなく、頬杖をついています(当然、ここから居眠りになってしまうのですが)。
だから、右手に強い力を入れて書くとノートが動いて上手く書けないので、片手で書いても動かない程度の弱い力で書こうとします。
また、鉛筆の持ち方も筆圧の弱い生徒は違います。
余計な力が入っているというか、鉛筆を握るように持つので、大して書かなくても疲れてしまいます。
腕力の低下に加え、余計な力が入っているので文章を長く書くのが苦手になります。
そして、書くのが面倒と。
「書く」という行為は勉強の一番基本の一つですが、これがきちんとできないので、成績も伸び悩みます。
これらのことは学校での指導の問題ではないかと思います。
先生も昔ほど口うるさう言わなくなったし、おそらく「書く姿勢」や「鉛筆の持ち方」「書き順」などを軽視しているのだと思います。
何でも基本は大事。
小学校に入って本格的に勉強をするようになる時、これらのことを先生はきちんと教え生徒も守っていかないと、結局長い学校生活において常に勉強に支障をきたし後悔することになるでしょう。









更に鉛筆文化を衰退させるトレンド
このように生徒は昔のように力を適切に入れて文字を書くことが減ってきましたが、現在、ある問題が更に生徒の手書き離れを促進させると考えられています。
それは教育のIT化です。
コロナ禍によりまともに学校に行けなくなったとき、子供たちの勉強を守る最後の砦としてオンライン授業が注目されました。
これにより文科省もそれまで計画していた『GIGAスクール構想』を前倒しし、今年度より生徒一人に一台必ず端末を利用できるようにしました。
こういったデジタルツールの導入はこれまでの学校での教授法を大きく変え、それに伴い生徒の学習活動も様変わりすることは容易に想像できます。
パソコンやタブレット端末を生徒に活用させるということは、授業のみならず様々な活動をこれらの端末で行い、もう鉛筆とノートを使うことはありません。
このように学校の近代化が生徒たちの鉛筆文化を衰退させることになります。
分かりにタイピングやタッチペンによる操作になり、書くこと自体が減ります。










ここで鉛筆で書くということがなくなったとして、生徒たちの勉強に影響がなければ何も問題はないのですが、どうも最近の研究によるとそうもいかないようです。
「手書きをしなくなったことで学力の低下が起こる」という発表もあるようです。
本日は長くなってしまったので、この続きはまた書きます。
楽しみにしていてください。
それでは今日はここまで。
























2022.01.28
時事問題を考えよう!コロナウイルスなど世間を騒がしている問題から学ぶ

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでは様々な角度から子どもたちの学びと成長を考えます。
世間ではコロナウイルスが話題となっています。
地球温暖化や消費税など時事問題は子供に世の中の仕組みを教え、深く考え、自分の意見を持たせるのにとても良い材料となります。
社会や理科の知識を増やすだけでなく、これから文科省の期待する、自ら考え問題に取り組む人間を育てることにもつながります。
時事問題(時事ネタ)を考えることの利点がいくつかあります。
本日はそのことについて考えていきます。











1.受験対策として
受験において時事問題が関係するのは、推薦入試などで行われる面接でしょう。
自分について、中学生活について、高校ではどのように過ごしたいかなど聞かれますが、時には時事問題について質問されることがあります。
そんな時に「分かりません。」では元も子もありません。
時事問題を知っているということに加え、自分なりの問題に対する意見が求められます。
また、一般の入試でも近現代史や現代文では時事問題に関係するもの(さすがに試験直前の時事問題とはいきませんが)が出たりします。
2020年度から変わる大学入試においては、思考力が重視されるので、時事ネタに絡めた問題が出されることは想像に難くありません。
その時に時事ネタに対する予備知識があれば、解答はかなり容易になります。
以上の点において、受験の準備として普段から新聞やテレビなどのニュースで時事問題に目を通し考えることは重要なのです。












2.コミュニケーション能力と論理的思考力の向上のために
時事問題とは大人も共通して見られるので、それをもとに親子や友人同士で議論するのもいいです。
ニュースなどから正確に情報を捉え、必要であれば様々なツールで情報収集する。
これらの力は学校生活のみならず、社会に出てからも必要となります。
また、自分の考えを間違えなく相手に伝える、相手の意見を正確に理解することも、人生の中で大切な能力です。
従って、時事ネタを利用して読解力が高められると同時に、論理的思考、判断力、表現力といった現在文科省が新制度の入試において求める力の鍛錬にもなります。
文章や資料を読めば、データや文章を読み解く能力が高まり、語彙も増えます。
更に、議論に参加することによりメンバー内の造語理解と絆が深まります。
普段分からなかったが、この人はそんな風に考えるのだと驚かされるかもしれません。
親子同士であれば、子供との壁が低くなり、子供が何かの問題に巻き込まれたときの早期発見につながります。











3.知的好奇心を高め、勉強に興味を持たせる
これは葛西TKKアカデミーでは最も重視することの一つですが、時事問題と通して知的好奇心を高めることができます。
常に「なぜ」「どうして」という姿勢で時事問題を見ると、物事に興味関心がわいてきます。
クイズを解くように、自身で問題を掘り下げ、その背景を知ることもできます。
このようにして、一つのことをきっかけに多くのことを学べるのです。
そして、謎が解けたとき、達成感と満足感が生まれ、プラスの循環を生み、もっと学ぼうと積極的になれるのです。
人から言われる勉強は苦痛です。
子供にそう仕向ける大人も苦痛です。
本人が自主的に学んでくれれば、お互いにストレスを抱えることなく良好な関係を保つことができます。
このとき大人は「聞き役」もしくは「アドバイザー」に徹してください。
下手に答えを与えたり、自分の考えを押し付けるのは決してよくありません。
学習意欲を減退させ、逆効果になります。
求められたときに「個人的な考えだけど、こんな風にも考えられるのじゃないかな」という具合で、考え方の一例として提示するのはいいと思います。
こうして知的探求心を育てれば、全ての分野において楽しく自分から学んでいけると思います。











日本では家庭内で政治や社会の話をするのは場違いのように思われることがよくあります。
欧米は逆に家庭で積極的に話し合い、子供たちが社会の現実と問題を学びます。
よって、ご家庭でも遠慮なくこのような話題をしていいと思います。
時事ネタを通して社会や理科、国語などの勉強を深めると同時に、人間としてこれからの社会を生きていく上で必要な能力を身に付けられます。
家庭で協力して、子供たちの成長の手助けになってください。






























2022.01.25
勉強で集中力が切れやる気が出ない!そんな時はこうしてみよう!
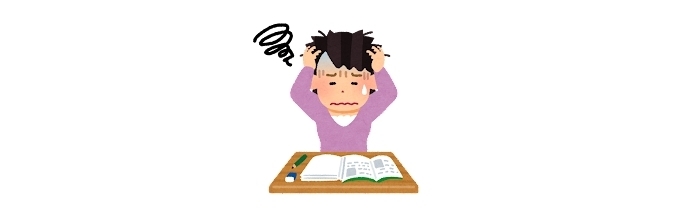
入試はいよいよ本番。
多くの受験生は最後の追い込みにいそしんでいることと思います。
そうでない生徒たちも勉強に頑張っていることでしょう。
しかし、いつも思う通りに勉強がはかどるとは限りません。
勉強はやらなければならないと分かっているんだけど、なかなかやる気になれない。
そんな時はどうすればいいのでしょうか。
ということで、今回は勉強に手が付かなくなったときの解決方法をいくつか提案してみたいと思います。










1.気分転換、息抜き
長時間続けて勉強するとやはり疲れてしまいます。
ふと疲労感に気づくと、疲れたということばかり気になってやる気がなくなってしまいます。
時間が限られているのは確かで、少しでも多く勉強しなくてはならないのは分かりますが、気分がのらないのに無理やりやるのも効率がよくありません。
ここは思い切って休憩をしましょう。
休むことで気分をリフレッシュし英気を新たに勉強に臨むと、より学んだものが頭に入ってきます。
人間の脳は運動によっても活性化されます。
ストレス解消と血行の促進により、記憶をつかさどる海馬という脳の部分が活性化します。
ただし、運動が激しすぎると肉体的に疲れ、反って勉強ができなくなるので、あくまでも軽い運動にとどめてください。
軽いストレッチや散歩などがいいでしょう。
ガム噛むと筋肉により脳が刺激され眠気を解消します。
また、英単語や漢字など「暗記学習」の場合には、身体を動かしながら暗記をすると、記憶に残りやすい場合があります。
これも、運動によって海馬が活性化されるためと言われています。
2.身の回りの整理整頓
勉強する環境も大事です。
身近に携帯やゲームなどが置いてあると、そちらに気がいってなかなか集中できません。
また、勉強に必要なものが散らかっていると、いざ必要な時にすぐに見つけられず時間を浪費してしまいます。
逆に、環境が整っていないと勉強できない(しない)言い訳になり、勉強しないことを正当化してしまいます。
そうなると、それを理由にやる気が出ないことも正当化してしまいます。
苦しい時に逃げる口実となって、勉強をしないことは仕方ないことと考えてしまいます。
これではいけません。
そうならないためにも勉強に適した環境を作ることは大切です。
3.現状を理解し計画を立てる
勉強をしようとしても何をやればいいのか分からない。
何からすればいいのか分からない。
そうなると勉強に手がつきません。
まず目標を確認し、次に自分のいる現状を考えます。
この二つをつなぎ、ゴールから逆算して自分の計画を作りましょう。
計画ができたら、それを守りましょう。
何をすればいいか分からないと、やる気を出す理由もなくなります。
毎日のスケジュールがあれば何をするか明確に分かります。
勉強にも取り掛かりやすくなります。
4.目標を達成した時のことを考える
よくスポーツ選手がしますが、目標を達成した自分をイメージするのです。
そうすると今勉強していることのメリットが分かります。
それがモチベーションを高め、やる気を出させてくれます。
メリットは大きなものでなくても構いません。
身近で手に入れやすいもの、小さなものでも結構です。
5.脳を休ませる
脳は体の中でも大量のエネルギーと消費する組織です。
長く勉強すればやはり疲れます。
だから脳を休めることは大切です。
脳の疲労がたまると勉強の効率も上がりません。
勉強が忙しくて時間もないのも分かりますが、十分な休憩は必要です。
長い目で見ると、脳のコンディションを整えた方が勉強ははかどります。
理想としては、どんなに忙しくても6時間睡眠はほしいです。
記憶のためにも十分な睡眠は必要です。
そうでなくても、休憩時間の10分や15分の睡眠が脳をリセットし、頭をすっきりさせることもあります。
後、糖分を取ることはエネルギーを補給にもなりますので、脳に新しい栄養を送り、次の勉強に取り掛かれる準備をしましょう。










本人のやる気が出ないとき、「勉強しなさい。」と強く言うのは逆効果です。
やらなくてはいけないのに自分が勉強をしていないことは本人がよく知っています。
「今やろうと思ったのに。もうやる気がなくなった。」とかえってやらないことを正当化する理由に使われますこともあります。
子供たちが勉強に手がつかないようでしたら、むしろ寄り添いその原因を一緒に考えてあげるのがいいでしょう。
明確に原因が分かれば対応策も考えられます。
分からなくても、一緒に悩んでくれた、苦しみを共有してくれたと思えば、安心感が生まれ勉強に取り掛かるようになるかもしれません。
子供たちが休憩し気晴らしをする相手になってあげるのもいいかも知れません。
「やれ、やれ」と無理強いするよりは、一旦勉強をやめ、態勢を整えてからもう一度取り組む方がいいです。
場合によっては、その日はもう勉強をしないで、就寝して早朝に残りの勉強をするのもよい方法です。
今だけの勉強に執着するのもいいですが、長い目で見たとき、案外やめて別の日に改めて勉強した方がいい場合もあります。
いろいろ試して、自分なりのスイッチを入れるジンクスやルーティーンが見つけましょう。






























2022.01.24
受験でもしうまくいかなかったら

受験シーズン真っただ中。
共通テストも終わり、私立高校、私立大学の入試があちこちで現在実施されています。
もうすぐ国公立大学、都立高校の本番になります。
みんなうまくいってくれることを願いばかりですが、なかなかそうはいかないものです。
万が一ということはあり得るのです。
そこで今日は、受験にうまくいかなかったときどうするか考えてみます。








親としては焦らずパニックにならないことです。
本人は当然落ち込むし、意気消沈という状況でしょう。
そんなときに肝心の親がパニックで当てにならないようでは困ります。
心が傷ついている時だからこそ誰かに頼りたいし、恥ずかしくて逃げ出したい気持ちだからこそ守ってほしと思います。
親は自分にとって一番の味方出会ってほしい時に取り乱しているようでは、子供は余計に苦しみ立ち直ることもできないでしょう。
この失敗が自分を一生価値のないものにしてしまうという恐怖。
そして、もう自分は生きていても意味のないものだと感じる自己否定。
このような感情が心を支配するかもしれません。
こういう時だからこそ、親はどっしりと構えて、今うまくいかなかったからと言って、それで人生終わりではないんだということを分からせてあげてください。
入試という点では失敗かもしれませんが、人間として否定されたのではありません。
むしろこの失敗から学び、今後の人生に役立てることが大事なのです。
これまで受験勉強を頑張って、それが全て無駄になったなんて思わないでください。
無駄かどうかは自分の心がけ次第です。
受験を失敗しても、この経験があったから自分は強くなれた、大きく成長できたという人はたくさんいます。
現状を見つめたうえで前向きに生きることが大切です。
その手助けをできるのが、経験を積んだ人生の先輩である親ではないでしょうか。








受験で合格させるために自分の全てを捧げる親がいます。
その熱意は悪くないのですが、その思いが強ければ強いほど、失敗した時の反動が大きい人がいます。
そして、子供に不用意な言葉を投げてしまう場合があるので、気をつけましょう。
自己犠牲に陶酔し、自分が何で子供に受験をさせるのか、その本当の意味を見失っている人がいます。
期待が大きくなり、不合格を自分への裏切りのように感じ、「なんで合格できないのよ。」とか「恥ずかしくて外を歩けない。」とか、そんな深い意味のつもりではなくても、つい子供に言ってしまうことがあります。
先ほど申し上げたように、親以上に本人もつらいのです。
だからこそ、それに追い打ちをかけるような言葉は、たとえ軽い気持ちとしても、いけません。
子供は大変傷つき、人生に大きな影を落とすかもしれません。
子供のためと言いながら、自分のための受験になっていませんか。
「世間から笑われる。」とか、「みんなのうわさになる。」なんて発言は、自分をよく見せたいという欲求を満たされなかったからこそ出てくる言葉です。
また、子供も「自分のために色々してくれた親に報いなければならない。」というプレッシャーを感じ、それに答えられなかったときは「自分はダメな人間だ。」と生きていくのも嫌になります。
親も子も受験を通して相互に期待・依存しているのです。
今一度、受験の意味と目的を考えてください。
受験は手段であり目的ではない。
上手くいかなければ他の方法を考えればいい。
そう思えば落ち着くし、冷静になれば今の現実において何が自分にとって最良かを判断するのは難しくありません。
周りの目を気にする必要は全くありません。
自分の人生だし、周りが言うことは無責任で大きなお世話と思えばいいのです。
大学に合格して四年間を遊んで暮らせば、その時間はその人には無意味だろうし、不合格でも別の道を見つけまい進すれば、そちらの方が人生には糧になるでしょう。
ものは考えようです。
結果だけを見つめるのではなく、結果が出た後をどう過ごすのかが大切です。
受験のために頑張ってきた根本的理由は何でしょう、自分が目指す目標は何でしょう。
それを一緒に考えられる存在、苦しい時に相談できる頼もしい存在であってください。
そうなれば子供たちもいち早く立ち直り、前向きな気持ちでこれからの人生を歩むことができるでしょう。









このような事態にならないように普段から受験生は頑張っているとは思いますが、入試である以上全員合格ということはあまりありません。
大抵、合格する者もいれば夢破れる者もいます。
合格をイメージし、それを糧に厳しい受験勉強を乗り切るのはいいのですが、少なくとも親や周囲の人間は万が一のことも想定した方がいいです。
何の準備もなく不合格になってしまい誤った対応をしてしまうと、子供たちに一生消えない心の傷を与え、人生が一気にネガティブになってしまうかも知れません。
今回のことを参考に、備えあれば憂いなしで、あらゆる状況を想定して受験生を見守ってあげてください。
苦しい受験勉強も後わずかです。
悔いのないように全力を尽くし、良い結果が訪れることをお祈りいたします。
























2022.01.23
塾の種類を知って自分に合った塾選びの参考にしよう

塾を選ぶ際、本人に合った塾はどこか悩むと思います。
実際に「塾」も千差万別で数もたくさんあります。
そんな中から自分の現状と目的に合ったものを選ばないといけません。
しかし、○○塾と言われても、それがどのようなものか分かりずらいこともあります。
そこで今回は様々な塾を、その形態、指導方法などにより分類しながら、その違いを説明したいと思います。









塾のタイプ
塾はその教える内容によって大きく進学塾、補習塾、総合学習塾、専門塾に分けることができます。
それぞれが目指す目的に合わせて、これらの塾の中から選んでいただくとよいでしょう。
1.進学塾
このタイプの塾は、小学校・中学校・高校・大学と、各段階の受験に特化しています。
学校の勉強より速いスピードで授業は進み、生徒の偏差値を上げ、難しい入試問題にも対応できるように指導します。
よって、現在の学校の授業は無視して、もう一つ別の学校に通うイメージでしょうか。
特に入試に関する情報を多く持ち、模試や進路指導、進路相談もしっかりとしてくれます。
入試を控え、万全の準備で合格を目指す生徒に適しています。
因みに、予備校は大学受験に特化した進学塾と考えてください。
2.補習塾
このタイプの塾では、日々の学校の勉強に遅れずついていけるように、学校の授業のフォローや定期テストでの成績アップに重点を置いています。
地域の学校を熟知しており、それぞれの学校の進度に合わせて授業を進めます。
部活や習い事で忙しく効率よく学校の勉強をしたい、純粋に学校の成績を上げたいという人に向いています。
3.総合学習塾
前述の二つを合わせたような塾になります。ここでは生徒たちの学習を総合的にサポートしてくれます。普段の学校のフォローや学校の定期テストなどの対策を行い、入試に向けた勉強、進路相談や内申点を上げる手伝いもしてくれます。
AO入試や推薦入試も含めた入試にも対応できるところが多いです。
現在の学校の授業だけでなく、入試も合わせて総合的に勉強を見てもらいたい生徒にお勧めです。
4.専門塾
ここは皆さんがごく普通に持っている塾のイメージとは違い、英会話やプログラミングなど、特定の分野、内容に特化した塾です。
昔からある習字やピアノの教室、スイミングスクールや最近はやりのダンス教室など、一般的に言われる「習い事」と呼ばれるものもここに入ると言えるでしょう。
最近ではパズル道場など数学的思考力を養うものや、ロボットを作るものなどバラエティーに富んできました。
学校の勉強とは別に、個人の趣味や好み、興味関心に基づいてやる人が多く、個人の技術や能力のアップを目指す場合に適しています。
また、特定の資格取得に向けたサポートを提供しているところも、ここに分類されます。









塾の規模
塾の規模によって区別することもできます。
大きく大手塾と個人塾に分けることができますが、一般的に前者は進学塾、後者は補習塾が多いようです。
いずれもメリット・デメリットがあります。
1.大手塾
テレビCMなどで全国的に知名度が高く、事業展開も都道府県レベルから全国レベルにまで校舎を広げています。
規模が大きく、情報量も多く、グループ内で統一された年間カリキュラムなどが用紙されており、全ての生徒がある程度同じような授業を受けることができます。
塾の知名度と実績を上げるために、どうしても上位の生徒に資源を集中させ、下位の生徒は取り残されることも多々見られます。
また、知名度が高いところ、有名な講師が所属しているところは、授業料が高額になるのでよく考えないといけません。
2.個人塾
個人が経営している塾で、校舎も一つか二つと数少なくなっています。
しかし、その分、地元への密着度が高く、地域の学校に特化した指導を行います。
小規模なので生徒一人一人に密接した深い関係を作り、企業のルールに縛られていないので、個人個人に対して柔軟な対応が可能です。
多くの生徒と交わるのが苦手な生徒には、個人塾の方が向いているでしょう。









クラスのタイプ
次に一クラス当たりの生徒数による分類をします。
1.集団授業
基本的に一人の先生に対して多くの生徒が一斉に授業を受けます。
学校でも目にする一般的な教室のイメージです。
その中でも一度に10人以上の生徒を教えるクラスを多人数制、10人以下の生徒を教えるクラスを少人数制と言います。
多人数制では毎回の小テストで席順が変わったりと、生徒間の競争を高めることで学習意欲を高めようとする塾もあります。
一度に多くの生徒を抱えているために、授業料は比較的安くなっています。
少人数制では多人数制より生徒数が少ない分、生徒が質問など発言がしやすく、より細かい指導を受けることができます。
いずれにしても、他の生徒と一緒に勉強するのが苦手な生徒はお勧めできません。
2.個別授業
一般的に一人の先生に対して、一度に一人から二人の生徒を指導します。
他の生徒のことを考慮する必要がないので、担当する一人ひとりの生徒の現状と目的に合わせたカリキュラムや授業を提供できます。
習い事などで忙しく集団授業に時間を合わせることができない、成績が悪く集団クラスではついて行けないという生徒たちに柔軟に合わせて授業を実施できるところが多いです。
生徒と先生の深い絆を作りやすく、学習以外にも共感共有しやすく、先生がそれぞれの生徒のことを深く知れるので、勉強以外のことでも相談したり協力してもらったりしやすくなっています。
ただ、基本的に授業料が集団指導よりは高くなる傾向にあります。
3.その他の授業
最近ではコロナ禍の影響でオンライン授業や映像授業と言った、新しいタイプの授業も盛んになってきています。
俗に言う「e-ラーニング」というものです。
オンライン授業は個人またはグループをオンラインでつなぎ、教室にいる先生の授業をライブで受けます。
または、アプリなどで提供される動画を個人が自分の好きな時間に見ながら、付属の問題を解いて学習を進めるものもあります。
こちらでは映像を繰り返すことで、自分が理解するまで何度も繰り返すことができるという利点がありますが、これを行うにはインターネットや端末などの環境を整えないといけないという欠点もあります。
映像を通した授業を見てプリントや冊子で与えられる問題を解いて、理解の確認や学習内容の定着を図ります。
特に最近注目され流行ってきているものに、「自立学習型」というものがあります。
ITやAIを活用したデジタル教材を使って、生徒が自分たちのペースで問題を解いていくというものです。
塾の先生は教えるというよりも、サービス提供や進路相談が主な仕事となります。
どれも比較的リーズナブルな料金であることが多いですが、自分で好きなように進めることができる反面、よほどしっかり自己管理ができないと、結局誰も言う人がいないので、ずるずる怠けて失敗するということもあり得ます。









入塾を決める前に
以上、大まかな塾のタイプと授業スタイルについてお話しました。
これらを基に、自分に合った塾を探す参考にしてもらえればと思います。
ただし、塾を決定する前にはもう少しそれぞれの塾について調べた方がいいです。
一番大きいのは授業料でしょう。
通常授業の料金もそうですが、夏休みなどの長期休暇になればどの塾も特別講習を実施します。
テキスト代や模試代、その他経費もかかるでしょう。
お金の問題はしっかり事前に確認しないといけません。
時間割を調べて、自分が毎回きちんと通えるかも考えなくてはいけません。
受講は何科目できるのか、先生はこちらから指名できるのか、どんなサポート体制や設備があるのか、しっかり調べたり問い合わせたりしてください。
いくら良い環境で自分に合った内容の塾に思えても、実際通い始めると何か違うということはよくあります。
そこは「相性」というものがあり、これは個人の落ち度でも塾の問題でもなく、仕方ないものです。
だから、基本的に塾には入る前に「体験授業」というものがあります。
生徒に合った雰囲気か、先生の熱意や塾の考え方が合っているか、実際に授業を受けてみて分かりやすいか。
これらは体験してみないと分からないものです。
だから、塾の形式だけでなく実感として入塾後も続けられるかも考慮して決めてください。









今は塾の種類や数も増えて、選択肢の多さが逆に塾を決めにくくしているかも知れません。
そんな時、自分の現状と目的を考えながら、これらを参考に塾選びをしていただければ幸いです。
因みに、葛西TKKアカデミーは個人の個別指導塾です。
授業内容はそれぞれの生徒に合わせて柔軟に対応できるのが強みです。
また、個人経営であるからこそ、各家庭の事情に合わせた授業料やプランを提案することが可能です。
大手塾でうまくいかないときは、是非一声かけてください。
全ての生徒の力になれるように、全力でサポートしてまいります。
























2022.01.22
コロナ禍で運動不足!体力が落ち怪我をしやすい子供が急増中

コロナウイルスの感染防止のため外出を控えるように言われ、子供同士の接触も極力避けるように言われてきました。
学校が再開してもやはりソーシャルディスタンスを取り、子供たちが休み時間に思いっ切り遊びまわったり、体育の時間に活発にサッカーなどの接触を伴うスポーツをしたりもできなくなりました。
スポーツジムも閉鎖され、サッカーや水泳などのスポーツに関する習い事も中断されたところも多かったようです。
部活動も制限され、学校が終わってからも外出自粛で友達と外で遊ぶ機会が少なくなりました。
その結果、体を動かす機会が奪われた子供たちの体力が非常に落ち、病気にもかかりやすくなったという報告もあるようです。
また、肉体的にも丈夫でなくなり、鬼ごっこをしていて骨折したというケースも見られます。
元々子供たちの体力は年々低下する傾向があるのですが、今年はコロナウイルスで外で体を活発に動かすことができず、子供たちの体がもろくなっているのではないでしょうか。
現場でも、実感として子供たちの体力が極端に落ちているという声が聞かれるみたいです。
特に成長期に当たる子供は、体を適度に動かさないと成長における骨と筋肉のバランスが悪くなり、その後の生活にも影響が出ることが危ぶまれます。
このようにコロナウイルスによる運動不足から体力が落ちているうえに、今年の猛暑は子供たちの健康を非常に危険な状態にさらすでしょう。
夏休みが終わり再び学校が始まったとき、体力が落ちた子供たちは熱中症になる危険性が非常に高くなります。
コロナウイルスの感染防止のためマスク着用が呼びかけられていますが、これは同時に呼吸を苦しくし、体内の熱を呼吸と共に体外へ排出するのを妨げます。
どちらの防止も重要ですが、その方法が丁度反対の方向を向いている感じです。
文科省はガイドラインを出し、人との十分な距離を取り不要な会話を避ければマスクを取って熱中症防止に努めるように呼び掛けています。
怪我や病気とまではいかなくても、落ちた体力で学校に行けばいつも以上に倦怠感疲労感に襲われ、勉強が十分に身に付かないという危険性も指摘されています。
長期休校期間や夏休みで外で運動する機会がなくなった子供たちは暇つぶしに、SNSやYouTubeなどの動画、ビデオゲームなどにいそしみ寝不足や精神的疲労、昼夜逆転の生活が解消されず、学校が始まってもまともに登校したり勉強したりできなくなる場合もあります。
この不健全な状態が精神にも影響し、イライラしたり不安感にさいなまれたり、怒りっぽくなったり、マイナス思考になり否定的な考えしかできなくなったりすることもあります。
最終的には他の生徒と一緒に勉強ができなくなり不登校になる人も多いようです。










このような状態になってしまった場合、落ちた体力の体にいきなり激しい運動が危ないので、軽い運動から徐々に時間をかけながら体力を戻していくことがいいと思われます。
無理のないように計画的にスケジュールを立て、少しずつ元の体力に戻るようにしましょう。
適度な運動は精神状態の改善にもつながり、気持ちがスッキリします。
そして、昼間の運動が適度な疲労感を体に与え、夜ぐっすりと眠れるようになります。
こうなれば休み期間中に乱れていた生活のリズムも戻るようになるでしょう。
暑さも気になる今日この頃ですが、それでも全く外に出ず体を動かさないというのもよくありません。
無理のない程度に適切な運動を適度にするように心がけましょう。
























2022.01.21
学校の勉強なんて社会に出たら役に立たないからやっても無駄!はNGワード

子供たちは毎日、周囲の人からたくさんの影響を受け、それを吸収して成長していきます。
時には、大人の何気ない行為や発言をしっかりとらえ、それが子供たちの人間形成に大きく影を落としたりします。
本当に、「そんなことまで聞いていたの」「そんなところも見ていたの」と驚かされることもしばしば。
だからこそ、大人は自分たちの振る舞いや言葉に細心の注意を払わないといけません。
子供に良い影響を与えるものならいいのですが、まだ分別がしっかりしていないこともに対しては見せたり聞かせたりしない方がいいものもあります(もう少し大きくなって物事が分かってきてからならいいのですが)。
その中で今回はこの言葉をNGワードとして考えてみたいと思います。
「学校の勉強なんで社会に出たら役に立たないからやっても無駄!」










子供はまだ経験が浅く、世の中のことをよく知りません。
これから学ぶことが沢山あり、だからこそ、無限の可能性に満ちた存在といえます。
確かに現実は厳しくつらいものかもしれません。
しかし、まだ幼いうちからそれを知り、妙に斜に構えるようにはなってほしくありません。
できれば、夢と希望に満ち溢れた未来を感じさせてあげたい、そんな風に私は願うのです。
しかし、多くの大人や親がこのNGワードを口にします。
自分自身がこれまで生きてきて実感としてそう思うから、正直に何の気なしに言うのかもしれません。
しかし、この言葉が子供にどんな影響を与えるか考えてみてください。
子育てが一気に難しくなるかもしれませんよ。
この言葉を聞いて、子供はどんなことを思うのでしょう。
勉強が楽しくてやる気に満ちた子供や、これから頑張ろうと思っている子供には、自分がやっている勉強は役に立たないんだと感じ、気持ちが挫けるかも知れません。
大人の他愛無い一言で子供のやる気を潰す必要はあるでしょうか。
また、単純に、「そうか、役に立たないんだったら、勉強する意味はないな。勉強やめよう」と考えるのではないでしょうか。
これは、子供に「勉強をしない」ことに対する免罪符を与えることになり、勉強放棄を正当化させる根拠になります。
そうなれば、いくら親が「勉強しないと将来困るよ」とか、「勉強しないといけないんだから早くしなさい」なんて言っても説得力はなく、言うことを聞かなくなるかもしれません。
勉強嫌いな子供にとっては、まさに伝家の宝刀で、口の達者な子供なら特に、これによって勉強という呪縛から逃れることができるのです。
この言葉を理由にされたら反論できる親は多くはないでしょう。
なぜなら自分(または自分と同じ大人)が自ら言った言葉だから、否定できないし、言葉に対する責任もありますから。









「貧困の再生産」という言葉があります。
教育の価値を理解できず、十分な教育を受けていない親は満足な仕事になかなかありつけず、貧困家庭に陥ってしまう(特に貧富の差が拡大しつつある現代においては、その数も増加傾向にあります)。
日本のような国は、社会的地位の流動には教育が大きく関わってくるのですが、上記のような家庭では、親が教育の価値を十分わかっておらず、子供にしっかりとした教育を受けさせない傾向が強く出てくるそうです。
そうなれば、子供も親と同様に貧困に陥る確率が高くなり、「貧しい家の子供はやはり貧しくなる」という現象が現れてきます。
これが「貧困の再生産」です。
(本来教育は基本的人権の一つであり憲法に保障されているのだから、出自が何であれ、本人が望むなら誰でも十分な教育を受けられないといけませんが、実際はそうではなく、これは由々しき問題ですが、この議論は別の機会に。)
このような家庭環境における親がよく口にする言葉が「学校の勉強なんで社会に出たら役に立たないからやっても無駄!」です。
この何気ない一言が、子供の将来における上昇志向に水を差し、自己肯定感をなくし後ろ向きな思考になるかもしれません。
そして、貧困に陥る可能性が非常に高くなります。
教育、そして子育ては子供の可能性を伸ばしていくものでなければなりません。
しかし、そのような可能性を一気に押しつぶすような、強力な影響を持つ言葉を大人たちはつい言ってしまいます。
本当に気をつけないといけません。
現実を子供に知らしめる親切心と言うかもしれませんが、大きなお世話です(すみません、言い過ぎました)。









そもそも教育とは、将来役に立つか立たないかで割り切る打算的なものなのでしょうか。
いいえ、違います。
方程式や国語文法、英語の仮定法など大人になって使わないからやる必要はないのでしょうか。
教育の目的は学んだことそのものを実社会に出たときに使うことではありません。
様々な側面があり、その手段の一つが学校で習う五教科であったり九教科であったりするのです。
確かに「学校の勉強なんで社会に出たら役に立たないからやっても無駄!」というのは人生の経験を積んできた大人にとって真実の一面であり、教訓だからこそ自分自身そう信じて子供に言うのでしょう。
確かに、現実社会は厳しく小中学校で勉強したことで太刀打ちできるほど簡単ではないでしょう。
「子供の将来のために」と思って勉強をさせている親はたくさんいるでしょう。
しかし、子供は自分の将来がはっきり見えていて、何を勉強しなくてはならないか分かって勉強している者はほとんどいないでしょう。
実際勉強ができる子供は、将来のこと云々ではなく、単純に知的好奇心や知識欲で、もしくはもっとストレートに問題が解けた達成感のようなゲーム的面白さで勉強をしている人が多いです。
それを「将来役立たないから無意味だ」と言われたら、せっかく面白い勉強もつまらなくなってしまいます。
また、勉強するは習ったことそのものを大人になって利用するというよりも、「学ぶ」という過程で知ること身に付けることが生きるうえで重要なことが沢山あります。
つまり、勉強は目的ではなく手段とも考えられるのです。
数学をやりながら論理的説明を理解したり、国語を勉強しながら相手にいかに明確に分かりやすく説明するかということを学んだりです。
問題を解く中で試行錯誤し、「ああでもない、こうでもない」と苦労しながら多面的に物事を見たり考えたり、どういう結果になるか想像や推測したり。
難しいからこそ、もがき考えるうちに忍耐力や根気が育ったり。
嫌な仕事でも最後までやり遂げられる強い意志が持てるようになったり。
実はこのような要素が実際に社会に出たときに不可欠となります。
これこそ勉強の真の目的の一つです。









「学校の勉強なんで社会に出たら役に立たないからやっても無駄!」と言うのは教育を表面的にしかとらえていない発言で、教育の真の意義を知らないのです。
子供たちの生活と心を豊かにしてくれるチケットです。
だから勉強は、こんな声明で価値をなくしてしまうような、そんな薄っぺらいものではありません。
その辺りをしっかり理解していただきたいと思います。
また、同時にこの言葉の持つインパクトを考えると、安易に子供に浴びせかけていいようにも思えません。
人生を長く生きてきた大人が実感を伴って思うことだからついつい口にしがちですが、子供に対していっていいものかよくよく考えてください。
葛西TKKアカデミーでは、ただテストのためとか受験のためではなく、本当に勉強を子供たちが楽しみ、教科書に書いている以上の知恵と教訓、そして学ぶ楽しさを知ってほしいと願います。











