塾長ブログ
2022.01.20
塾に行くメリットとは!?

多くの家庭が塾に通わすべきかどうか悩んでいます。
基本的に安くもない料金を支払っているのだから、やはりそれなりの成果はあってほしいところです。
塾に求めるものも、その家庭の事情によって様々です。
そんな悩みを抱えている保護者の方々の参考になるように、今日は一般的に言われる「塾に通うことのメリット」をご紹介したいと思います。









塾に行くメリット
塾に行くかどうかを決めるには、やはり「塾に行く価値があるか」どうかを判断しないといけません。
支払う授業料に対して十分な見返りがあるのならば、塾に通う決断をすればいいし、そうでなければいく必要はありません。
そこで今回は、先ずメリットに注目してご紹介したいと思います。
1.学校の勉強に遅れずついていける
やはり多くの家庭では子供の成績を上げるために塾に通わせるようです。
学校の授業だけでは、分からないときに質問したり、もっと勉強を深めるために何をすればいいか分からなかったりします。
学校では人数が多いので、個々の生徒の学習レベルに合わせて勉強を進めることが難しいです。
そうならないように、塾では質問もできますし、専門の先生が学校に先駆けて勉強を教え、専用教材を使って練習ができるようになっています。
個別指導の塾であれば、個人個人に合った学習計画を作成してくれて、必要であれば小学校の内容までさかのぼって教えてくれることもできます。
定期テスト前など必要であれば復習やテスト予想およびテスト範囲に合った問題を練習させてもらえたりします。
こうして、苦手教科を克服したり、基礎学力を充実させ学校の勉強について行けるようにして、成績を上げることができます。
2.様々な人と一緒に勉強することで学習意欲を高める
で一人で勉強しようと思ってもなかなか手が付かないことがあります。
一人だと何でもできるので、どうしても怠けてしまったり、周囲の誘惑に負けて勉強以外のことが気にかかり、集中できずに勉強が非常にしづらくなります。
しかし、塾にはいろいろな人がおり、勉強に励む仲間や熱心に教えてくれる先生に刺激され、自分も頑張らなくてはと学習意欲がわいてきます。
授業のない日でも自習できる塾が多いので、誘惑のない勉強に望ましい環境で、高まったモチベーションを維持しながら、勉強に打ち込むことができます。
3.受験対策がしっかりしていて、入試を有利に進められる。
塾では多くの受験生に対応するために、中学校から大学まで様々な受験対策を用意しています。
受験に必要な勉強ができると同時に、個人ではなかなか手に入らない情報も入手できます。
実際に入学した先輩の話、彼らがどのように受験勉強し、合格してどのような人生を送っているか、今年の受験生の傾向はどうなっているか。
また、受験日から逆算し、生徒たちの現在の実力からどのように勉強を進めていけばいいか、計画を立ててくれます。
それに基づき、目標の学校に入れるように授業や講習、プログラムを提供してくれます。
もちろん、模試も実施し、生徒が本番で自分の実力が出せるようにサポートもしてくれます。
4.定期テストの対策をしてくれる
先ほども述べたように、塾では定期テスト対策を行ってくれます。
学校の成績は色々な要素から成り立っていますが、その中の大きな部分を占めるのが定期テストの結果です。
塾に通わせる目的の一つが成績アップである以上、塾側としても生徒に何とか良い成績を取ってほしいと努力します。
テスト前には対策として特別な時間を設け、そのテストに特化した授業や勉強時間を提供してくれるところが多いです。
塾にはこれまで蓄積してきた過去の定期テストの問題がある場合もありますので、聞いてみれば問題をやらせてくれるかもしれません。
こうして予行練習ができるのは塾ならではで、塾に行かず家で一人で勉強する生徒にはできないことです。
当然塾の先生も学校のテスト範囲を見れば、何が重要で何ができていないといけないかということが分かりますから、要点に絞った勉強ができます。
学校では教えない解法やテクニックを教えてくれることもあります。
また、家で勉強する習慣がない、またはそれがうまくできない生徒にとっては、塾という勉強専門の環境が与えられるだけでもありがたいことです。
テスト勉強に集中でき、課題もどんどん進んで、十分な準備をしてテストに臨めます。
5.学校で勉強できないときの代替として
今回、コロナ禍で学校が一斉休校になり、生徒たちの学習が滞ったとき、学校の通常授業以外に学習のアクセスできる生徒とそうでない生徒の間に教育格差が生じたと言われています。
コロナ禍でなくても、教育の手段が一つしかないというのは心もとないものです。
そんな時、塾という選択肢を持っていると勉強の保険の一つとなります。
また、家庭の事情(例えば今回のコロナ禍での自主休校)や病気や学校の人間関係などによる不登校で学校に行けない生徒もいます。
そのような時にも、塾というもう一つの居場所があれば、子供たちの安全を守り勉強を継続させることができます。
6.有益な情報や良質の問題集が得られるため
次に塾のメリットとしては受験や勉強に対する豊富な知識や情報量でしょう。
毎年の入試傾向の分析、定期テストでの勉強のポイントやコツなども知っています。
特に現在、学校教育は大きな転換期で、これまでと教育の内容、方法、そして評価がかなり変わってきています。
親御さんのころのことを考えて勉強や受験を考えていると、かなり変わっていろいろ困った事態に陥るかもしれません。
そんな時、多くの情報が得られ対策が取れるということは、現代の教育(社会)においてかなり有利に働きます。
こういった情報は学校だけでは得られにくいものです。
また、塾で使用している教材も書店で販売されているものとは違い、良質のものが多いと言えます。
説明がまとまっていて分かりやすいテキスト、問題量と種類の豊富な問題集、いろいろなレベルの生徒に合わせた教材など、塾でしか手に入らないものが沢山あります。
7.勉強の動機づけとして
よくあるのが、「学校の勉強や宿題をやらなければならないのは分かっているのですが、どうしても一人だとやる気になれない。」「頑張って勉強したいけど、何をやればいいか分からない。」というものです。
勉強で何をどのくらいどのようにすればいいというのは生徒一人ではなかなか分からないものです。
塾はその点を十分に理解しているので、それぞれの目的に合わせて最適な教材、勉強量、勉強方法などを教えてくれるので、目標を持った勉強ができ、どこに向かっているのか全く分からないときよりも、生徒のやる気も上がります。
先生の指導を受けて、少し難しそうな問題、これまでできなかった問題が解けるようになるとモチベーションも上がり、もっと勉強に励むようになります。
また、一人ではできませんが、一緒に勉強する仲間がいれば、教えあい助け合ったり、他の生徒と比べることで競争意欲もわき、ライバルの存在がお互いを切磋琢磨させるきっかけにもなるでしょう。
8.広い範囲での自分の勉強の位置づけを知り、様々な刺激が得られる
よその生徒を知らず、自分のクラスや学校の中だけで生活しているとどうしても視野が狭くなってしまいます。
受験などで他校の生徒と競争しないといけないとき、自分の学校では優秀でも、実は他校の生徒はもっと優れていたなんてこともあります。
日頃から様々な学校の生徒と関わっていれば、自分の実力がもっと広い範囲においてどのくらいなのかが分かります。
そして、異なる学校の生徒と関係を持つことは、自分の世界観を広げ、互いに良い刺激になります。
中には自分の学校の生徒以上の友情が育まれることもあるでしょう。
ヒューマンネットワークが大きくなれば、それだけ自分に有利な情報が手に入ったり、いろいろ助け合うことができたりします。
このような学校の枠を超えた人間関係に基づく利点というのは、やはり塾に行けこそでしょう。









以上、塾に通うことのメリットを挙げてみました。
他にもあると思いますが、このようなメリットが期待に副うものであれば通塾も一考だと思います。
もちろん、お金を払っている訳なので、十分な対価があるか検討する必要があります。
今回はメリットだけを述べましたが、当然デメリットもあり、子供たちがデメリットを克服しメリットを享受できるか考えましょう。
多くの塾では入塾決定前に無料体験を行っているので、とりあえずそちらを受けて、担当の先生から話をよく聞いて決断すればいいと思います。
葛西TKKアカデミーにも無料体験があり、そちらを受けてから入塾するかどうか決めてもらうことになっています。
大手から個人経営、個別から集団、進学塾と学習塾と、塾の種類も様々ですし、その塾の理念や方針によっても教え方などが大きく異なってきます。
大事なのは、生徒に合っている塾はどこなのか、生徒に必要な塾はどこなのか知ることです。
いくら評判が良くても、自分の子供には合わないということはあります。
勉強は高度に個人的なものなので、みんながいいというから自分にもいいとはなりません。
例え今塾に通っていても、合わないようでしたら途中で変えることも大切です。
よく考えて、本当に生徒のために親身になってくれる塾を見つけてください。

























2022.01.20
漢字を覚えよう!子供たちが勉強でぶつかる壁の一つでその対策は!?
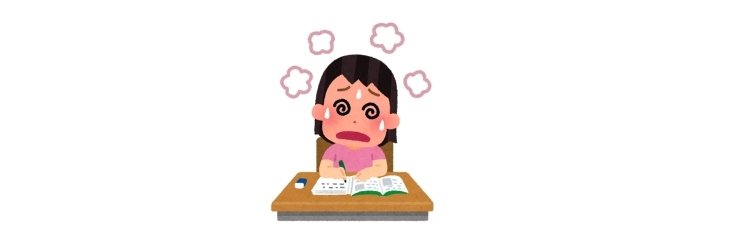
子供たちが勉強で最初にぶつかる壁の一つが「漢字」です。
当塾でも「漢字が覚えられない。」と嘆く生徒がたくさんいます。
ただやみ雲に覚えようとしても、なかなかうまくいきません。
やはりコツや工夫が必要です。
葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでも漢字の指導を行っています。










子供たちに聞くと「漢字が嫌い」という生徒がたくさんいます。
二年生までは学校でも一つ一つ丁寧に漢字を教えますが、学年が上がると他に学ばなければならないことが増え、「漢字は自分で覚えなさい。」と先生はおっしゃるのではないです。
または「ノートに漢字を10回から20回ずつ書いてきなさい。」なんていわれることもあるのでしょう。
苦行以外の何物でもなく、やがて生徒は嫌になって漢字を覚えようとしなくなる。
これは逆効果です。
そこで今回はいくつかコツをご紹介します。










漢字の成り立ちを知る
一般に漢字はその成り立ちから四つのタイプに分けることができます。
「象形文字」「指示文字」「会意文字」「形成文字」です。
「象形文字」は絵から作られたもので「山」「川」「日」など。
「指示文字」抽象的な概念を記号的に表したもので「一」「二」「三」「上」「下」など。
「形成文字」は複数の漢字を組み合わせ、そのもたらす意味を漢字にしたもので「明」「鳴」など。
これらはインターネットで検索すると簡単に見つけられます。
中には動画で紹介しているものもあるので、それらを参考にしてから勉強すると脳への刺激も増え、漢字が納得できるので覚えやすくなります。
以上の三タイプはシンプルなものが多く、小学校低学年で習うものが多いです。
これらの基本的な漢字の音と、意味を表す部首を組み合わせてできるのが「形成文字」です。
漢字を音と意味の組み合わせと考えると覚えやすくなります。
共通な部首などでまとめて覚える
これはゲーム感覚で親子や友達同士で競い合ってもいいと思います。
ニンベンやゴンベン、サンズイやシンニョウなど一つ部首を決めて、どちらが多く書けるか勝負すると楽しいです。
お互いに書いたものを見比べて、そこでも覚えられます。
また部首でなくても、「体に関する漢字」「植物に関する漢字」などテーマを決めてやってもいいです。
好きなことに関する文をたくさん読む
文章を読めば漢字に触れるチャンスも増えます。
本が好きなお子様ならば自主的に読むので、自然と漢字も覚えます。
そうでなくとも漢字に触れる機会を増やすことは大事なので、例えば好きなスポーツ選手の名前を読ませたり、趣味のものの説明書を読ませるのもいいでしょう。
ゲームの解説本や攻略本もお勧めです。
間違えやすいパターンを覚える
せっかく覚えても、漢字が不正確であったり混同していたりします。
子供たちの間違えやすいところはある程度決まっているので、そこを重点的に印象に残るよう指導するといいです。
例えば、「牛」と「午」を間違える生徒がいます。
私は「「牛」には角があるから出っ張るんだよ。」なんて教えたりします。
間違えやすいところを把握していれば、子供たちも書くときに気をつけるので正確に書けるようになります。
熟語は意味と構成からまとめる
熟語も子供たちが苦手とするところです。
やはり工夫が必要です。
熟語の作りにもいくつかのパターンがあります。
パターンを知るとまとめることができ覚えやすくなります。
・前→後(前から後ろに意味が成立)
例)病人=病の人、日没=日が沈む、新品=新しい品
・後→前(後から前に意味が成立)
例)帰国=国に帰る、入学=学校に入る、着地=地に着く
・前≒後(似た意味の漢字を並べる)
例)寒冷、豊富、勤務
・前⇔後(反対の意味の漢字を並べる)
例)多少、増減、強弱
熟語は意味を考えながらやると覚えやすいし、熟語から漢字を覚えることもできます。
三文字以上の熟語も同様に熟語の構成を考えるといいでしょう。










他にも工夫やコツはありますが、一般的に行われている「ただひたすら何回も書く」方法はあまり効率的ではありません。
上記のように、漢字そのもの以外の情報も関連付けて覚えると、脳への刺激が増え身に付きやすくなります。
面倒くさがらず、急がば回れです。
国語で言えば慣用句や故事成語なども同様に、言葉そのものを覚えるのではなく、工夫して脳への刺激を強めることが大切です。
子供たちの間で人気のある「うんこ漢字ドリル」もいいです。
当塾の生徒にもやらせましたが、他のドリルと違い、本人が楽しみながら自主的にやっていたのが印象的でした。
勉強は大変です。
でも、ちょっとしたコツや工夫があれば効率よく学ぶことができます。
葛西TKKアカデミーでは、先生がこれまでの経験をもとに分かりやすく指導してくれます。
遠慮なく、是非見学や体験に来てください。
勉強や子育て、進路や学校生活などの相談も受け付けています。
地域の皆様に開かれた塾ですので、いつでも気軽にお越しください。






























2022.01.18
数学検定を受けよう!そこにはメリットがたくさん!是非挑戦を!

英語検定は皆さんもご存知かと思います。
自分の英語のレベルを知る良い指針となると同時に、国内では権威ある技能検定なので、就職や受験などで優遇されることもあります。
同様に、最近は数学検定(実用数学技能検定)が注目されています。
今回は、数検がどのようなものか、そして、数検合格あるいはその過程でどんなメリットがあるか議論したいと思います。









数学検定とは
数学検定(実用数学技能検定)、通称「数検」ですが、これは日本数学検定協会により実施されている検定で、試験に合格するとそのレベルに合った数学力が認められます。
内容は、算数や数学の実用的な技能である計算を始め、作図、測定、統計、整理、証明、表現と家内広い分野の能力を測るもので、1級から5級までが「数学検定」、6級から11級までと『かず・かたち(ゴールドスター・シルバースター)』が算数検定となっています。
数学検定のレベルとしては、それぞれの学年で学校で習う内容に応じてして、例えば、高校受験をする生徒が受ける3級はちょうど中学3年程度の内容となっています。
テストは1次と2次から構成されており、先ほど触れた3級では1次が50分、2次が60分の試験時間となり、合格の基準は1次で全体の70%程度、2次で全体の60%程度が要求されます。
問題は示された範囲から幅広く出されます。
当然級が上がると問題も難しくなり、合格率もどんどん落ちていきます。
例えば、5級では70.3%の合格率も1級では5.7%にまで落ち込みます。
因みに、中学卒業レベルの3級は59.9%だそうです。
詳しくは日本数学検定協会のホームページをご覧ください。









数検のメリット
1.入試に有利
英検と同じように数検の最大のメリットは何と言っても「入試で優遇されることがある」点でしょう。
大学の推薦入試やAO入試で、学校によっては評価の対象として認めてくれるところがあります。
この制度を取り入れている学校は、短大や専門学校まで含めると500校近くになります。
自分が志望する学校に、数検を合否判定に含められるならば、受験をグッと有利に導くことができます。
また、私立高校の入試においても、学校によっては英検、数検、漢検の指定された級以上を持っていると内申点に1加えられることろがあります(この制度は都立高校にはないので注意)。
1点の違いが合否を分けることもある高校入試において、試験を受ける前に確実に与えられるこの追加点は非常に大きいと言えます。
最後に、数検2級以上に合格すれば、文科省が行う「高等学校卒業程度認定試験(かつての大検)」で数学が免除されます。
このように数検が入試の参考要素や推薦条件の一つとされたり、学校によっては単位として認定されることもありますので、数検を受ける価値は十分あると思われます。
2.自分の実力を知る指針となる
日々の勉強において自分がどの程度の実力を持っているかが分かれば、勉強に対する不安も和らぎます。
数学検定は、基礎的なものから高度なものまで幅広く問題が出ていますので、自分がどのレベルまで習得できているのか分かります。
全て記述式の問題なので、本当に数学の仕組みを理解し、しっかりとした論理展開ができることも要求されます。
数検と入試での出題範囲は一致するので、数検の勉強がそのまま受験勉強にもなりますから、受験勉強を数検勉強に置き換えてやるというのもよい方法だと思います。
数検を勉強すれば自動的に学校の数学の内容も習得でき、数検を合格して先ほど触れたように受験を有利にするので一石二鳥。
これは良い作戦です。
3.場合によっては就職にも役立つ
数検もある程度のレベルを合格していれば、それは特技・資格として履歴書に書くことができます。
特に理数系の会社を受けるならば書いて損はありません。
3級以上であれば、厚生労働省のYES-プログラム(若年者就職基礎能力習得支援事業)という企業の求める就職基礎能力の習得を促進するプログラムの証明書を手にすることができます。
アルバイトでも塾講師をやるなら、数検合格は採用の決定に一役買うでしょう。
一般の就職でも、面接官が数学に興味がある人であれば話が盛り上がり採用に有利になるかも知れません。
そうでなくても、数検○級というのがあれば、ないよりは伯が付きますし、なんか教養があってできる人間のように見えますよね。
数検の勉強が公務員試験や一般教養のテストで役に立つことは十分あります。









数検の勉強の仕方
先ずやらなくてはならないことは、学校の教科書の内容を早く終わらせることです。
数学が得意で、学校で教わるのを待たなくても自分で勉強が進められる人はどんどん進みましょう。
基礎からしっかり学び、少なくとも教科書の問題は、応用まで解けるようになっておく必要があります。
また、数検は上記のように、試験は記述式なので答えだけを出せばいいというものではありません。
記述の方法も確実に習得しながら、丁寧な勉強が肝心です。
面倒くさがって途中式を書かなかったり、暗算で解いてばかりだと、いつまで経っても上手に解けません。
数検の問題は暗算で全てできるほど甘くありませんし、文字にして目に見えるようにした方が、自分の間違っている点を探し出すのも容易ですし、論の進め方や思考の展開も分かりやすく正確になります。
記述は実際に書く経験を積むことによって、その要領が身に付き、徐々にどのように書いていけばいいのか分かってきます。
そして、分野の苦手を作らず、どの内容が出されても解けるようになってください。
得意不得意や好き嫌いを作ってしまうと、その時の気分や出題された問題によって正答率が大きく変化し安定しません。
確実な合格を目指すならば、どの分野も一応の結果は出せるようにしましょう。
ここまでで基礎内容を十分習得したならば、後はひたすら問題を解き、出題傾向になれ、出題形式に慣れましょう。
市販の教本をやり、過去問を何回も繰り返しやれば、だんだん多くの問題が解けるようになります。
この時、本番を意識して、時間の管理もきちんとしてください。
最初は時間内に終わらないかも知れません。
しかし、意識しながらやることで、徐々にスピードが付きできるようになります。
ここで注意してほしいことは、先ずは丁寧な解答を心がけること。
丁寧にやってさえいれば、回数を重ねることでスピードは後から付いてきます。
逆に最初にスピードばかり気にして雑な解答をしていると、いつまで経ってもきちんとした解答はできません。
友達と一緒に勉強するのもよい方法です。
一人だと、分からないときに行き詰まってしまうかも知れませんが、そばに誰かいれば質問もできますし、一緒に考えることもできます。
誰かと一緒の方が心強いし楽しいです。
こういう意味では、そばにいるのは親でも構わないのです。
ただし、親の場合特に多いのですが、子供ができなかったときにイライラしたり怒ったりしないように気をつけてください。
むしろ、できないときにこそ励ましが重要です。
周りにそんな人がいない場合は、学校や塾の先生でもいいでしょう。
葛西TKKアカデミーも利用可能出です。
きっと皆さまの力になりますよ。









以上、数検とそれを取得することにより発生するであろうメリット、そして、勉強法について述べてきました。
実際受けるかどうかは個人の判断ですが、どうせ数学の勉強をするのであれば、ついでに数検も取って損はないと思います。
自慢にもなり、自信も付きます。
数検を上手に活用すれば、受験を始め様々な場面で優位になることができると思います。
とりあえず、物は試しでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
葛西TKKアカデミーも数検合格に向けて、皆さまのお手伝いをする用意があります。
是非一緒に頑張りましょう。
























2022.01.18
ノートを見やすく分かりやすくするコツ!工夫して勉強の効率をアップ!

ノートは勉強で最も大切なものの一つ。
自分が勉強したことを習得するのに必要なだけでなく、自分のこれまでの努力の証でもあります。
生徒の中には「どうせノートは見ないから書かない。」なんて言う人もいますが、やはり学んだことをしっかり身に付けるにはノートは必須のアイテムです。
授業で先生が言ったことを書き留めるだけでなく、書かないよりも書いた方が脳により大きな刺激が起こるので記憶の促進と定着にも有効です。
後日、記録としてノートを見返せばテスト勉強にも大いに役立ちます。
なぜなら定期テストは学校の先生の授業が元になって作られることが多いからです。
しかし、せっかくとったノートも後で見て何が書いてあるのかよく分からないでは困ります。
ノートはどのように使うといいか考えてみましょう。









1.ノートは贅沢に大胆に使う
森林伐採などで資源を大切にしようと言われますが、勉強に関してはそこは少しご容赦いただきたい。
子どもたちがしっかり勉強すれば、それを補って余りある恩恵を自然にお返しできるでしょう。
だから、ノートを大きく使ってほしいと思います。
私のお勧めとしては、一行おきに書く。
この明けた行間に、後日更なる情報が追加できるようにです。
ノートは一回書いたら終わりではなく、復習などで繰り返し使ってほしいです。
その時に今までにない新しいことを学んだら書き込めるスペースを用意しておいた方がいいです。
時には付箋やメモを貼り付けるのもいいでしょう。
更に私がやっていたのは、学校では開いたノートの左ページだけ書き、右は自宅学習で書きこんで内容を充実させたり、補足情報やデータ、表などを書いたり貼ったりしていました。
このように後からどんどん拡張ができるようにすることで、学習をより深くすることが可能です。
(拡張と言う意味ではルーズリーフなんかもいいですね。)
2.各科目専用のノートを作る
荷物が多くなるのが嫌だからと何でもかんでも一つのノートに書く人がいます。
こうすると後で、何がどこに書いてあるのか分からず時間がかかったり見つけられなかったりします。
結局勉強の効率が悪くなり、ノートを取る意味があまりなくなってしまいます。
少なくとも1科目1冊にしましょう。
荷物が重くなってしまいますが、そこは勉強のため、体力をつけると思って割り切りましょう。
勉強は肉体労働です。
ノートの表紙には科目名の他に使い始めた日付と使い終わった日付を書きましょう。
各ページにも日付を書きましょう。
こうすることで後でどこに何が書いてあったか探す助けになります。
自分がどれだけ勉強したか分かりますし、ノートがそのまま自分の努力を反映しているので、ノートが自分の自信と達成感につながり大きな誇りとなります。
3.統一した自分のルールを決めよう
ただ思いつくまま書いてはまとまりがなく、見直したときに何のことかさっぱりわからないということになります。
自分なりのノートの使い方のルールを決めましょう。
ノートには勉強の内容以外に何を書くのか。
単元や日付、教科書のページなどは決まった場所に書くようにしましょう。
もったいないかもしれませんが、新しい単元に入るときは、どんなに余っていても次の新しいページから書き始めましょう。
文字やアンダーラインやハイライトなどの色も決めて何色が何を表しているか決めるといいです。
例えば「赤」は重要事項、公式は「青」など。
囲みも四角と丸で意味を変えてみたりするのも有効です。
4.可能であればコピーを活用
国語の古文や英語など、本文に訳を書いたりするときは教科書をコピーしたものを貼り付けるといいです。
長い文章を手書きで全部書いていったら時間が足りなくなってしまいます。
可能であれば学校の先生にお願したり、コンビニなどのコピー機を利用してください。
時間の節約にとても役立ちます。
社会や理科なら挿入されている表や絵、写真をコピーしてノートに貼るといいです。
特に絵を描くのが苦手な人にはいいかもしれませんね。
また、テストや問題集で出てきた問題をコピーして貼るのもいいです。










他にも様々な工夫があると思います。
皆様の工夫があれば教えていただけると勉強になります。
ノートは勉強に非常に大事なもの。
戦う武器です。
上手にノートを書くことが勉強の効率を高め、より良い成績を修めるのに重要です。
自分だけの素敵なノートを作り、本屋さんでそのまま陳列できるくらいになるといいですね。
勉強に関する悩みや分からない点があれば気軽に連絡ください。
これまでの経験から何かしらご提案できると思います。
勉強大変ですが頑張ってください。
























2022.01.16
勉強や人間関係など子供も相談したいが悩みに答えるにはコツが!

全国で再びコロナウィルスの感染が広がり、子供たちの窮屈な学校生活はいつまで続くか、未だ見通しもつきません。
友達と遊びたいのに活動を制限されたり、おしゃべりもできなかったり。
学校行事も短縮や中止、普段の授業でもいろいろ混乱が生じています。
このようなこれまでに経験したことのない状況に大人もそうですが、一番不安で心細く感じているのは子供たちかもしれません 。
。
そんな時に大人たちは頼りになる存在でありたい。
そうして子供たちに安心を与えられるようでなければなりません。
しかし、普段私たち大人は子供たちにどのように接しているでしょうか。
いつもと違う異常事態で、普段よりもストレスを感じ心に余裕がなく、ついつい子供に当たったりしていませんか。
これでは子供たちは助けを求めたくても声を上げることができません。
難しいですが子供の成長に関わる大人としては、冷静になり子供たちがいつでも話しやすい状況、人間関係を築くことが大切です。
では、どのように子供たちと関わればいいか考えていきましょう。











子供が成長する過程で、彼らはいろいろな壁にぶち当たります。
そして、どうしていいのか分からず、悩み苦しみます。


そんな時、子どもの成長に関わる大人としては、相談にのり道を示さなくてはなりません。
しかし、数学の問題とは違い、明確な答えのない悩みにはどのように対処すべきでしょうか。
私の経験上、いくつかのコツを今日はご紹介したいと思います。


1.いつも子供が心を開ける存在であること
特に思春期の子供たちは悩みが多くなります。
そんな時に大人が相談できる存在であることは重要です。
子供に信頼されている、少なくとも不信感を持たれないことが大切です。
付きつ離れつの適度な距離感を保ちましょう。
微妙な年頃なので口出ししすぎると、反って嫌がられます。
時には言いたくても我慢することが必要です。
でも、時には声を掛け、困ったことがないか聞きましょう。
いざという時は頼れる人がいるという安心感は、子供の精神安定の大きな助けとなります。
普段から他愛ない話をして、何でも気軽に話せる間柄を築きましょう。
2.まずは子供と同じ視点に立つこと
相談にのるとき、大人はつい自分が子供より経験豊富で知識もあるから、子供を無視して自分の考えを押し付けがちです。
しかし、押し付けは反って子供の反発を招きます。
いくら良いと分かっていても、自分が納得しなければ行動は難しいし、精神的負担も多いでしょう。
だから、最初は子供の視点に立って、問題に対する考えを共有することが第一歩です。
拒絶と否定は可能性を狭めます。
まずは子供を受け入れ、同じ立場で考えましょう。
そうすると子供も自分と同じ立場で考えてくれると安心し、見方として受け入れてくれます。
そうして同じ方向を向いて考え、もし道が間違っていれば少しずつ方向転換するように導きましょう。
誘導しつつ、子供が自分で答えを出せるように手助けをするのが相談役としての立場です。
答えを与えるのではなく、自分で考え出せるように促す。
その過程に子供の成長もあります。
3.文字や図にして目で見えるようにすること
よく口頭だけで話し合いをします。
しかし、口から出た言葉はすぐに消えてしまいます。
だから、文字や図などで紙に書いて目に見えるようにする(視覚化)とお互いに分かりやすくなります。
何が問題なのか、何が原因なのか、今後どのように対応するのか。
これらを全てはっきりと見える形にすると、考えもまとまりやすいし、お互いに共有もできます。
こうすれば問題解決もより簡単になります。
4.プレッシャーをかけ過ぎないこと
大人が子供であったころと今とでは環境がかなり違います。
自分たちの子供のころの経験が、そのまま当てはまらないことが多々あります。
大人にとっても未知の問題に子供たちが直面しているとき、大人は明確な答えが提示できないこともあるのです。
だから、自分が良かれと思って言った助言が必ずしも正しいとは限らないのです。
むしろ、そうしない方がうまくいったりすることもある。
「こうすればいいんだ。」「こうしないとダメなんだ。」とプレッシャーをかけるのは、子供の精神的負担を増やすだけでやらない方がいいでしょう。
逆に「これでうまくいかなければ別の方法をまた考えよう。」というくらいの軽い気持ちでいた方がいいです。
「今後もサポートするからね。」というメッセージにもなりますから。
そもそも子供は答えを求めているのではなく、一緒に考えてくれるという安心感を求めている場合が多いのです。
以上の点に気をつけて、子供が悩んでいるときは相談にのってみてはいかがでしょうか。











要するに「物は考えよう」と言うように、自分の気持ちを切り替えて友好的に接すればいいのです。
相手をコントロールするより自分が動いた方が楽ですからね。
そうして信頼関係を築ければ、子供の相談もうまく聞けると思います。
また、子供は解決方法を望んでいるのではなく、単純に自分を分かってほしい、悩みを共有して安心したいだけなのかもしれません。
そんな時は話を聞くだけでも、子供には大きな救いになるものです。
しかし、相手がいることなので、子供が頭から拒絶していればそれも難しいでしょう。
そのような親子関係にはそれに至るには経緯があるでしょうし、特に反抗期と呼ばれる子供には親がいるというだけで嫌がられ、相談どころではないかもしれません。
そんなときは自分一人でどうにかしようなんて考えず、外に助けを求めるのも大切です。
無理して事態を悪化させるより、自分は一歩引いて他人に任せてみるのも時には有効な手段になりえます。
「何を言うか」より「誰が言うか」で子供の態度がガラッと変わることもあります。
(同じことを言っても相手によって受け止め方が違ってくるということはよくあります)
もちろん、葛西TKKアカデミーはそんな存在の一つです。
困ったときは遠慮なくご相談ください。






























2022.01.15
へこたれない子供にするにはどうすればいいのか

最近の子供はすぐに音を上げると言われます。
一度やってできなければ「もうダメ。できない。」とか「無理。」とか言ってあきらめてしまいます。
しかし、初めてやって最初からできるなんて普通はありませんし、一度やってできないからとやめてしまえば、その子はそれ以上成長する可能性がなくなってしまいます。
どうしてすぐにあきらめてしまうのでしょうか。
簡単にへこたれない子供にするにはどうすればいいのでしょうか。
ちょっと面白い調査がありいましたので、その結果を踏まえて考えてみたいと思います。









私も子供たちと触れる中で、すぐに子供たちがあきらめてしまう経験を何度もしました。
最初に失敗をする、それ以前に失敗を恐れて初めてのことに挑戦すらしようとしない。
失敗するのは罪で恥、それを避けようと問題に手を付けること、答えを出すことすら拒否する。
こんな子供たちが非常に多いと感じます。
しかし、失敗を恐れて挑戦する力、失敗して落ち込んでもいつまでも引きずらず、また前向きに挑戦できる力は社会に出てからも非常に重要で、就職活動においても「打たれ強さ」に評価の重点を置く企業もたくさんあります。
つまり、「へこたれない力」と言うのは社会で生きるうえでもとても大事なのです。









ある機関が子供のころの経験が大人になった現在にどのような影響を与えているかを調べたもがあります。
その中の「社会を生き抜く資質・能力」として「意欲」「自己肯定感」「コミュニケーション力」に加え「へこたれない力」が含まれていました。
調査の結果によると年収800万円以上の家庭では「へこたれない力」の高い層が34.8%いるのに対し、年収200万円未満では20.2%でした。
つまり、年収が高いほど「へこたれない力」も高くなりやすいということが分かります。
また、子供時代と「へこたれない力」の関係を調べていくと、子供のころ親に厳しく叱られたり、褒められたりした経験が多いグループは「へこたれない力」の高い層が35.4%だったのに対し、これらの経験が少ないグループでは10.3%しかありませんでした。
これは親子の間だけでなく、先生や地域の大人との間に関しても同様の傾向がありました。
更に、親に多く褒められ叱られたことの少ないグループと、逆に褒められたことが少なく叱られたことが多いグループを比較すると前者では「へこたれない力」が高い層が30.9%だったのに対し、後者は20.1%でした。
これから子供のときに叱られるより褒められた経験の多い子供の方は「へこたれない力」が高いと考えられます。
子どものときに「基本的生活習慣」「お手伝い」「家族行事」などの経験が多いと「へこたれない力」も高くなり、公園で友達と遊ぶなどの「集団での外遊び」「自然のなかでの遊び」の経験が多くてもこの力は高まるという結果だ出ていました。
つまり、子供のときに様々な経験をし、同世代だけでなく異世代間の交流が多く、しかも比較的褒められる経験が多いと「へこたれない力」が育つように思えます。









都市部では自然が少なくその多様性も少なくなっています。
しかも、SNSやゲームなど外に出ないで特定の限られた人とだけ関わる環境が最近は整っています。
多様な経験を積むにはお金を出さないとできないことも多く、収入との関係もここから説明がつくと思います。
また、社会がスピードを求めるようになり、じっくり考える時間を与えないことも増えてきました。
しかも、テストのように結果はすぐに出て、間違えることを許さない。
何回も何回も失敗を積み重ねつつ、自分からコツや方法を発見したり習得する余裕を与えない。
そうすると最初に述べたように子供たちは間違えを恐れ、間違えると周囲にバカにされるから答えることすら拒否するようになるのも無理はないでしょう。
しかも、何でもスピードが求められ、煩雑なことは敬遠され簡単なものしか受け入れられない価値観が現在は主流となってきています。
だから、すぐにできないものはやらなくなるし、面倒なことは受け入れなくなります。
しかし、人間の成長は失敗の中から学ぶことで起こることが多く、便利さは子供の成長の機会を奪っているのです。
大人が「面倒くさい。」と言うのを聞いて、子供も「面倒くさい」ものを嫌がるようになり、先ほどの間違えが罪で自分のプライドが傷つけられるのが怖い気持ちと合わさって、根気がなるすぐにへこたれる子供が増えていると思います。
叱られ続けると自己否定になり「自分はダメな人間」と思い込み、自分の価値、生きる意味さえ見失うこともあります。
失敗しても挑戦する姿勢をたたえ褒める経験はこれらを防ぎ、失敗を恐れなくて済むから自己肯定感を育てます。
皆さんも子供がすぐにできないからイライラして、つい声を荒げることはありませんか。
「できないとダメ」と思うからそうなるのです。
むしろ、「最初はできなくて当然、できればラッキー、今はダメでのそのうちできるようになればいい。」くらいにいい意味でお気楽に接した方が子供もゆとりをもって学べると思います。
社会的にあくせくして余裕のない時代、便利すぎて時間をかけることに価値を見出さない世の中、お金をかけなければ人間同士も含めて多様な経験がしずらい環境。
なかなか子育てしにくい条件がそろっています。
だから、子供たちがすぐにへこたれるようになるもの無理はないと同情するところが多いです。
でも、これらの要因は大人の態度、工夫、考え方次第である程度軽減できます。
へこたれやすい子供に育つ原因もある程度わかっているので、逆にそうならないように心がけることも可能だと考えています。
葛西TKKアカデミーでは子供たちの間違えで人格を否定したりバカにすることはありません。
常に子供は発展途上であり、最終的に目標に達せられればいいという姿勢で接します。
勉強に限らず、子育てで困ったときは気軽にご相談ください。
テストの問題が解けるだけでなく、子供たちが人間としてプラスな存在になれるように尽力しています。





















2022.01.14
共通テストの次は都立高校の推薦入試!作文や面接や集団討論の対策が必須!

いろいろな意味で大変な今年の大学受験では共通テストがこれから行われます。
大学受験生の多くはその結果次第で志望校の最終決定をすることと思います。
一方、高校受験では都立高校の推薦入試が1月26日、27日にあります。
これが次の大きな入試日程になります。
一般の科目で試験をしない代わりに、作文や面接、集団討論などが課せられます。
「推薦だから大丈夫。」「5教科のテストじゃないから簡単。」なんて甘く見ると痛い目にあいます。
普段の勉強とは違うからこそ、しっかり準備しなくてはいけません。
逆に、しっかり準備さえすれば他の受験生よりも一歩先んじることができます。
直前の対策として、葛西TKKアカデミーで練習をしませんか。
何にもしないでまぐれで受かればラッキーと思っているなら受けない方がいいです。
絶対に合格しませんから。
倍率は非常に高いし、成績優秀で落ちないだろうと考えられていた生徒が現に落ちています。
個別指導塾葛西TKKアカデミーもそのような受験生に対応した指導も行っています。
もちろん、中学校でも面接の指導で入退場の仕方など教えてもらっていると思います。
しかし、それだけでは足りません。
今回は面接試験でより良い評価を得るための、私なりに考えるコツがあります。
そして面接は練習すればするほど上手になります。
その練習の繰り返しが自分をより深く考えることにつながり、更に自分の周囲とのつながりも考えることにつながります。
普段の生活ではなかなかこのようなことはできません。
専用の場を用意した方がいいです。
葛西TKKアカデミーは喜んで皆様のための練習場になりたいと考えています。
集団討論も同様です。
面接と同じく状況に瞬時に対応して答えなければ、一人だけ置いていかれ結局一言も話せなかったなんてことになりかねません。
そうなったらもうアウトです。
試験担当者は生徒一人ひとりを知りたいわけですから、黙っていると自分が何者なのか伝わりません。
恥ずかしいかもしれませんが、殻を打ち破ってどんどん前に出て自分をアピールしないといけません。
これも練習で場慣れする必要があります。
慣れてくると自分に自信もつきます。
より良い結果には欠かせません。
作文もある程度評価されるパターンがあります。
そこをしっかり理解し、どんなお題であってもきちんとまとまって相手に分かりやすい文章を書かなくてはなりません。
こちらも葛西TKKアカデミーならきちんと指導してもらえます。
これも練習を重ねれば重ねるほど上達します。











面接は何も準備しないと絶対にうまくいきません。
何をやったらいいのかよく分からない人も多いでしょう。
そんな時は葛西TKKアカデミーにご連絡ください。
安易に考えずに、一般入試と同じように万全の準備をしましょう。
繰り返しますが、受かればラッキーくらいの気持ちで臨むならやめましょう。
受かりません。
ならば、一般受験の勉強に集中した方がいいです。
気になる方はご相談ください。
皆さんの成功をお祈りしております。






























2022.01.13
今週末は共通テスト!試験前日の過ごし方についてお話します

いよいよ今週末は共通テストです。
センター試験から変わり、まだ要領も分からず心配な受験生も多いと思います。
しかも、コロナウイルスの混乱もあり、受験生にはいつも以上に不安で困難な入試になりそうです。
しかし、これはどの受験生も同じです。
条件が同じならば余計なことを考えず、今持っている自分の力を出し切ることに集中した方がいいです。
共通テストの結果は大学入試に大きく影響します。
中にはこの結果がそのまま大学合格の判定に利用されるところもあります。
そんな重要な試験の前日はどのように過ごせばいいか考えます。










ここまで来たら、もうやるしかありません。
腹をくくって明日に備える。
直前に不安になって、教科書を一から開いて夜更かししてはいけません。
そんな付け焼刃をしても、大して結果は変わりません。
むしろ、寝不足で実力が発揮できない方が問題です。
つまり、前日は万全の体調に整えることを第一に考えてください
しっかり睡眠を取り、精神を安定させて、ゆとりを持って試験に臨めるようにすることです。
先ず、睡眠です。
早寝をして翌朝はスッキリ目覚めるようにしてください。
人間の脳が本格的に働き始めるまでに、起きてから2時間かかると言われています。
試験開始から逆算して、その2時間前には起きていないといけません。
気になって勉強したくなるかもしれませんが、ここは自分を信じて勉強から離れましょう。
どうしても見直したいときは、夜ではなく早朝にしてください。
それも細かいところを逐一チェックするのではなく、ざっと目を通すくらいにしてください。
もし緊張や考え事で寝付けなくなったら、無理に寝ようとせず、目を閉じてじっと横になってください。
それだけでも体はかなり休まりますから。
次に食事です。
朝食は食べ過ぎないように、腹八分くらいがいいです。
こってりとしたものではなく、あっさりとして消化にいいものを食べてください。
食べ過ぎると苦しくなるし、血液も消化に取られ、頭の方に回らなくなります。
食べる時間も試験直前ではなく、余裕を持ってゆっくり噛みながら、落ち着いて食べられるようにしてください。
出発について。
持ち物や着替えは前日に用意し、全てそろっているかチェックしておいてください。
当日に慌てて忘れ物をしてはいけません。
受験票など忘れても試験は受けられますが、その事実が精神的にダメージを与え、本領発揮できなくなることもあります。
当日はそのまま出かけられるようにしましょう。
そして、出発時間ですが、これも余裕を持って早めにするのがいいです。
電車が止まったり遅れたりすることもあります。
どんなトラブルがあるかもしれません。
だから早めに家を出て、どのような状況にも対応できるようにしましょう。
もしトラブルに巻き込まれたら、落ち着いて試験会場か大学入試センターに連絡をしてください。
きちんと対応してくれるはずです。
会場には試験開始の30分から1時間前に付けるようにしてください。
テスト前に試験会場をぐるっと一周できるくらいの余裕があるといいです。
落ち着いて深呼吸して待ちましょう。
しかし、運悪く今はオミクロン株の感染者急増中ということもあり、できれば公共交通機関は利用しない方がいいでしょう。
どうしても電車やバスを利用しなくてはならないときは、時間をずらしたり人ごみの少ない車両を選んだり、可能な限り密な状況を避けるようにするしかないです。
マスクなどの防護も当然必要です。
また、会場についてもすぐに入場できるとは限らないので、事前にホームページや運営に問い合わすなどした方がいいでしょう。
去年に引き続きコロナウイルスの感染予防という項目が、入試対策に入っています。
試験を前に混乱しがちですが、いざと言うときは会場担当者に聞き指示に従えば大丈夫です。
難しいですが落ち着いて平常心でいられるようにしましょう。
最後に、繰り返しになりますが、直前にじたばたしても仕方ありません。
実力以上のことはできません。
だから、本番で実力を100%出すことに集中してください。
やれることをやればいいのです。
そう開き直ると気が楽になると思います。
そして、「自分はできる」と自分に言い聞かせてください。
精神の当たれる影響は非常に大きく、どのように気持ちを持っていくかで結果が左右されます。
スポーツ選手もイメージトレーニングで、本番に精神状態を最高に持っていきます。
受験生の皆さんもそうしてください。
そして、第一日目がうまくいかなくても気にしないでください。
気にして次の日もうまくいかなくなるのが一番いけません。
やってしまった試験の結果は変わりませんから、色々悔やんでも仕方ありません。
自分のやれることをしっかりやる。
それだけです。
「人事を尽くして天命を待つ」です。
しばらく寒くなります。
防寒もしっかりして、風邪などひかず万全の態勢でテストを受けてください。
葛西TKKアカデミーも受験生の皆さんを応援しています。
































2022.01.12
記述問題をあきらめない!知らなくても解けるサービス問題!白紙解答NG!

文科省の教育方針が変わり、入試や学力テストなどでも記述問題が非常に増えています。
それも国語だけではなく、五教科全てにおいて記述問題が目立って増えています。
しかし、記述問題を見ただけで、「もうだめだ。できない。あきらめよう。」と思って、問題すら見ずにやめてしまう生徒がとても多いです。
でも、実は記述問題は簡単に答えられるものが多いのです。
そして、選択問題のように0点か100点かの問題とは違い、部分点があります。
特に入試などの1点が合否を左右するような場合、この部分点が大きく結果に響いてくることもあります。
書かず白紙なら0点ですが、書けば1点でももらえる可能性がある。
ならばやらない手はありません。
少しでも結果を出したい、点数を伸ばしたいと考えるならば、記述問題をやりましょう。
しかも、コツさえ分かってしまえば、意外とすらすらと答えられます。










多くの生徒は記述問題が苦手と言います。
でも、それは文を書くことに慣れていないからで、多くの場合はある程度は書けます。
ある程度書ければ部分点がもらえるので、記述問題はそれで十分です(記述問題は満点を狙うのではなく、部分点を狙う問題です)。
そして、中には予備知識が必要なく、あまり深く考えなくても答える問題もあります。
自分の勝手な「記述問題は難しい」と言うイメージだけで、問題も見もしないで飛ばしてしまうのはもったいないです。
先ずはチャレンジしましょう。
そして、問題に慣れましょう。
つまり、テストを受けるまでにポイントをしっかり理解し実際に書きながら練習するのです。
ここで大事なのが「実際に書く」ということです。
多くの生徒は日本語なのだから書くのは簡単と考えています。
面倒くさがって書かない生徒が多いのですが、いざ書いてみると表現や語彙など適切に使われていない場合が多々あります。
母語だと高をくくっていると、意外と書けないものです。
記述問題をするときは頭で考えて「そうか、そうか」ではなく、実際に書くことが重要です。
日常生活の中でもきちんとした文を手で書く機会が減りつつある現在、受験勉強として時間を取ってしっかり自分の手で書いてください。
先にも述べましたが、文字にしてみると意外とうまく書けず、後で読み直してみると(できれば誰かに読んでもらって指摘してもらうといいのですが)意味が全く分からないなんてこともあります。
最初は模範解答を写すだけでも構いません。
そこから「こうやればいいのか。」「こう書けばいいのか。」と考えながら繰り返していると、だんだんコツが分かってきます。
また実際に書く重要性は書き方を身に付けるだけではありません。
以前指摘したように、最近の生徒は書く「力」、能力ではなく本当の体力としての「力」が衰えています。
すぐに疲れて書けなくなる。
力が無いからしっかり書けず、薄くミミズのはったような字になり読むことができない。
書き続けることに耐えられる力が無いので、すぐに疲れ精神的にも嫌になり集中力が続かない。
運動と同じように肉体トレーニングとしての意味合いもあります。










記述問題など文章を書く方法に関しては別の記事で既にふれたことがあるので、ここでは記述問題を答えるコツをいくつか話しましょう。
先ず、記述問題は難しいことを高尚な表現で書く必要は全くありません。
分かり切ったことをつまらない表現形式でシンプルに書けばいいのです。
文学作品のような芸術的な書き方はしなくていいです(解答に芸術点はありません)。
必要な情報を正確に伝えられればいいのです。
本当に「静岡のお茶の生産量が増えた。」とか「日の出の時刻が早くなった。」など、問題が求める内容をしっかり押さえていれば、極めてシンプルな構成の短い文でいいのです。
しかも、特に図表を使った問題は資料から読み取れる明確で単純な事実だけを聞かれることが多いです。
「日本各地のお茶の生産量の変化を示したグラフから読み取れることを書きなさい。」なんて問題であれば、グラフから生産量の変化がどうなのかだけ読み取り、「静岡のお茶の生産量が増えた。」などと書けばいいのです。
問題を複雑に考えすぎない、答え方を難しくしようとしない。
これで答えられる問題が結構あります。
これは図表さえ正しく読み取れれば勉強していなくても答えられるサービス問題で、これは是非取りにいきましょう。
もう一点だけコツを述べましょう。
問題に出てくる図表や資料は意味なく出されている訳ではありません。
何らかの意図があり、出題者は解答者がその意図を読み取り求める解答をしてくれることを期待しているのです。
だから、なぜこの資料があるのかを理解することが大事です。
この資料のどこの部分を使って答えさせたいのか、この資料が解答にどのようにつながっていくのかが分かれば、答えを書くことも簡単です。
例えば、グラフの変化から今後どのようなことが起こると予想できるか、資料のどの部分がきっかけで事件が起きたのか、この実験は何を知りたいから行ったのかなど。
解答者に資料から何を分かってほしいのかを出題者の立場で考えられるようになると、資料を見たときに「あ、これを言ってほしくてこの資料を出したんだな。」と分かってきます。
この部分は慣れも必要なので、やはり記述問題にたくさん当たること(質より量)が大切です。










以上の点を踏まえて、書き方をしっかり身に付け、後は繰り返し練習すれば記述問題は驚くほどできるようになっていきます。
短期に得点を上げたいと考えるなら、記述問題に着目するのもいいかもしれません。
どの問題もそうですが、最初の見た目に騙されてやる前から問題を諦めるのはやめましょう。
やってみると意外と簡単だったということはよくあります。
逆に点数の低い生徒は、戦う前から既に白旗をあげている人が多いように思えます。
頭がいい悪い以前の問題、心構えの問題で、やる前から自分の負けを認めている。
原因はその生徒のメンタル構造によるのですが、この点はまた別の記事で。
記述は難しいとよく言われますが、実は記述はそれほどでもありません。
むしろ勉強で覚えていなくても、資料の読み取りだけでできてしまうラッキー問題であることの方が多いのです。
なぜなら書き方は自由だし、書けば何点かもらえるかもしれないし(完璧な解答でなくてもいい)、図表や資料に書いてあることを素直に読み取れば単純な答えでいい場合もあるからです。
食わず嫌いはやめて、チャレンジしてみましょう。
分かってしまえば、どんどん解けるようになります。
どうしても記述問題に対する勉強の仕方などが分からないときは、葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
喜んでご指導いたします。



























2022.01.12
ゲームが手放せない子供が急増!長所と短所と注意点

スマホやパソコン、iPad、ゲーム機などが浸透するにつれ、これらのツールを使ったゲームにはまる子供たちが増えています。
特にコロナウイルスの拡大に伴い外出の自粛を求められるようになると、家で過ごす時間が増え手持無沙汰にゲームに手を出す子供がたくさんいます。
そして、私たちの子供のころと違って困ったことは、これらのゲームにはキリがない、ここでやめておこうという区切りがつけにくいことです。
そのままゲームを続け中毒性、依存性が増すと、ゲームなしでは生きていけないような、ビデオゲーム症候群に陥ってしまいます。
そして、そのまま生活リズムが崩れ、勉強も疎かになり、健康も害するようになるといけません。
今回はゲームが子供たちに与える影響と、大人として何に注意すべきか考えてみましょう。









最近、親が子供にスマホなどで動画を見せたりゲームをやらせて、そちらに子供が夢中になっている間に自分のしたいことをする場面をよく見かけます。
ゲームに子守をしてもらう訳です。
ゲームさえ与えておけば、子供は黙ってじっとゲームに集中しているので、親としては子供を見る必要が減り、自分のやりたいことができるという訳です。
これは特に若い親に多く、よってゲームをやっている子供も幼児であることが多いです。
つまり、早い子供では小学生になる前からゲームに染まるのです。
そして、早い段階でゲーム依存症になってしまえば、それを子供から取り上げるのは至難の業です。
確かにゲームは上手く使えばいい点もたくさんありますが、やはり、それよりも子供へ与える悪影響を心配する親御さんが多いことと思います。
先ずは、メリットとデメリットを簡単に考えてみましょう。
メリット
ゲームをやることのよい点としては友達関係があげられるでしょう。
同じゲームを通して対話が生まれ、ゲームで競い合うことで盛り上がったりします。
我々が幼いとき、教室で友達とテレビの話で盛り上がったように、ゲームを通じて共通の話題ができるのです。
ということは、逆にゲームをやらないと友達との話についていけないということになりかねません。
また、親も同じゲームをしていれば親子の会話も生まれ、一緒に楽しい時間を過ごすことができます。
ゲームを上手になろうといろいろ考えたり、努力して強くなろう、クリアできるようになろうと頑張ります。
難しい局面でもがんばれば乗り越えられるという経験は子供には良い影響になるでしょう。
デメリット
やはり、一番気になるのは健康への影響でしょう。
過度のプレイは視力を低下させ、手根管症候群など、手や指の関節に障害を与えます。
一時期ポケモンで問題となった「光過敏性発作」を引き起こすことも報告されています。
先ほども触れましたが、生活リズムが崩れ、昼夜が逆転したり、頭痛に悩まされたり、寝不足になったりします。
こうなるとまともな生活を送ることも困難になり、子供の中には学校に行けなくなって不登校になる者もいます。
また、心理的な影響も心配されます。
ゲームの内容によっては、子供の攻撃性が強くなる傾向が指摘されています。
焦燥感やうつが出やすくなったり、社交能力が低下、集中力が長く続かなくなることも問題です。
これがエスカレートすると、もうゲームを手放すことができず、やらないと禁断症状が表れ落ち着きがなくなるゲーム依存症になります。
他にも長所短所があると思いますが、とりあえずここまで。









では、これらメリットを伸ばし、デメリットを減らして良好なゲームとの関係を築くには何に注意すべきでしょうか。
一番大事なことはルールを決めることです。
ゲームを完全に禁止することは親とって簡単かもしれませんが、良い解決策ではありません。
ゲームをやっていい時間帯や長さなど、ゲームをするときのルールを一緒に話し合って、親と子の合意の上でルールを作りましょう。
一方的な押し付けは反発を招くし、親と子で同様のルールを課さないと、親はやっているのに自分はどうしてダメなのかと子供に不公平感が表れます。
思春期の子供には特に不公平感、理不尽は大きな問題です。
家族が揃って食事をするときはゲームを置いて一緒に食事するなど、ゲームをしていい時間と悪い時間、そして場所をきちんと決めましょう。
実は意外にも子供たちはルールをほしがっています。
葛西TKKアカデミーに来る生徒たちも勉強しなければいけないのは分かっているのに、どうしても携帯が手放せなくて困っています。
だから、ルールを作って勉強中は携帯禁止とか、塾にいるときは携帯を預けるという風にしてほしいとリクエストされたことがあります。
子供たちも彼らなりに、スマホなどの弊害を理解しているようです。
後、子供がどんなゲームをしているか把握することも大事。
暴力的なもの、性的なのも、課金を伴うものには注意が必要です。
そして、オンラインゲームなどではインターネットに関するトラブルも怒るかもしれないので、こちらも気をつけなければいけません。
有害サイトにアクセスしないようにフィルタリングを使ったり、クレジットカードや住所などの個人情報が流出が起きないように子供たちにも正しい使い方を共有しましょう。









今の時代、ゲームを始めてしまったら、もうやめさせることはできないと覚悟しましょう。
軽い気持ちで与えてしまいますが、その時はこれから子供がどのようにゲームと付き合えばいいかよく考えないといけません。
そうしなければ、親子間のいざこざの一つになってしまいます。
もちろん、道具である以上、ゲームにも良いところと悪いところがあります。
ゲームを通してストレス発散やリラクゼーション、想像力がついたり、クリアするために創意工夫をする練習にもなります。
しかし、度を越してしまえば、ゲームは害となり、子供の一番重要な勉強の妨げにもなります。
大事なのは節度ある使い方、メリハリです。
そして、それは親が一方的に決めるのではなく、祖互いに話し合い達した合意でなければいけないと思います。
ゲームでこれほど四苦八苦しなければならないのも時代でしょうか。
こんな時代で避けようがないのなら、いかに健全に利用するかを考えなければいけないとは、現代の子供たちも大変ですね。

























