塾長ブログ
2021.01.19
共通テストが終わりました。次は都立高校の推薦入試。作文や面接、集団討論など普段やらない内容が盛りだくさん。きちんと対策しないと受かりませんよ。葛西TKKアカデミーは推薦入試のための指導も行います。

いろいろな意味で大変な今年の大学受験では共通テストが終わったところ。
結果を踏まえて本試験をどうするか考えていることと思います。
一方、高校受験では都立高校の推薦入試が1月26日、27日にあります。
これが次の大きな入試日程になります。
一般の科目で試験をしない代わりに、作文や面接、集団討論などが課せられます。
「推薦だから大丈夫。」「5教科のテストじゃないから簡単。」なんて甘く見ると痛い目にあいます。
普段の勉強とは違うからこそ、しっかり準備しなくてはいけません。
逆に、しっかり準備さえすれば他の受験生よりも一歩先んじることができます。
直前の対策として、葛西TKKアカデミーで練習をしませんか。
何にもしないでまぐれで受かればラッキーと思っているなら受けない方がいいです。
絶対に合格しませんから。
倍率は非常に高いし、成績優秀で落ちないだろうと考えられていた生徒が現に落ちています。
個別指導塾葛西TKKアカデミーもそのような受験生に対応した指導も行っています。
もちろん、中学校でも面接の指導で入退場の仕方など教えてもらっていると思います。
しかし、それだけでは足りません。
今回は面接試験でより良い評価を得るための、私なりに考えるコツがあります。
そして面接は練習すればするほど上手になります。
その練習の繰り返しが自分をより深く考えることにつながり、更に自分の周囲とのつながりも考えることにつながります。
普段の生活ではなかなかこのようなことはできません。
専用の場を用意した方がいいです。
葛西TKKアカデミーは喜んで皆様のための練習場になりたいと考えています。
集団討論も同様です。
面接と同じく状況に瞬時に対応して答えなければ、一人だけ置いていかれ結局一言も話せなかったなんてことになりかねません。
そうなったらもうアウトです。
試験担当者は生徒一人ひとりを知りたいわけですから、黙っていると自分が何者なのか伝わりません。
恥ずかしいかもしれませんが、殻を打ち破ってどんどん前に出て自分をアピールしないといけません。
これも練習で場慣れする必要があります。
慣れてくると自分に自信もつきます。
より良い結果には欠かせません。
作文もある程度評価されるパターンがあります。
そこをしっかり理解し、どんなお題であってもきちんとまとまって相手に分かりやすい文章を書かなくてはなりません。
こちらも葛西TKKアカデミーならきちんと指導してもらえます。
これも練習を重ねれば重ねるほど上達します。











面接は何も準備しないと絶対にうまくいきません。
何をやったらいいのかよく分からない人も多いでしょう。
そんな時は葛西TKKアカデミーにご連絡ください。
安易に考えずに、一般入試と同じように万全の準備をしましょう。
繰り返しますが、受かればラッキーくらいの気持ちで臨むならやめましょう。
受かりません。
ならば、一般受験の勉強に集中した方がいいです。
気になる方はご相談ください。
皆さんの成功をお祈りしております。






























2021.01.19
共通テストお疲れ様でした。今日はゆっくり休んで次の試験に向けて準備しましょう。疲労回復法についてお話します。

受験生の皆さん、共通テストお疲れ様でした。
どうでしたか。
混乱続きで大変でしたが、自分の持てる力を発揮できたでしょうか。
悔いのないパフォーマンスができたことを願います。
試験の総括は後でするとして、今日は帰ってゆっくり休んでください。
大学受験生はこれから本試験になります。
そこで大学入試本番に向けてまずは疲労回復が必要です。
ということで、本日はどうすれば早く疲れから回復するか考えてみます。









疲労には肉体的疲労と精神的疲労がありますが、受験生は精神的疲労の方が問題でしょう。
当然、気分から体がだるく感じ、肉体も疲れているように感じられることもあります。
受験によるプレッシャーからのストレスは神的に疲れます。
特に試験本番では加えて集中力の持続など、より過度な負担が精神にかかります。
だから、今回の共通テストのような重要な試験を受けた後は疲労感がピークに達し、ヘトヘトになっているのではないでしょうか。
でも、いつまでもけだるい気分を引きずっていれば受験勉強や本試験でも成果が上がりません。
すみやかな回復が望まれます。









先ずは休養です。
そのためには睡眠が重要な役割を果たします。
寝ることでストレスから解放されるだけでなく、ホルモンが活発に分泌され、血液中の活性酸素を分解したり、免疫力を向上させたりします。
だから、しっかり今日は寝ましょう。
しかし、過度に睡眠を意識しすぎると今度は逆にストレスとなり眠れなくなったりします。
あまり、「8時間寝なくては。」などと決めつけて自分にプレッシャーをかけるのではなく、特に深く考えずに自然に眠りましょう。
適正な睡眠は体が知っているから安心して寝ましょう。
食事の大切。
いくら疲れたからと言って食べないで寝るのはよくありません。
タンパク質、脂質、炭水化物の三大栄養素に加え、ビタミンとミネラル(五大栄養素)をバランス良く、摂取することが大事です。
量よりバランスが大事です。
お腹が満腹になれば、眠気も増し寝つきが良くなります。
食後の入浴をしましょう。
入浴も疲労回復に効果的です。
入浴により血行が良くなれば、食事でとった栄養も体の隅々まで運ばれ疲労回復に効果的です。
38~40度のぬるめの湯船に入ると副交感神経がよりはたらき体がリラックスの状態になります。
副交感神経は体の修復に大切な自律神経なので、この神経をお風呂に入ることによって活発にし疲労回復を早めます。
ゆっくり湯船に浸かってリラックスすることで、ストレス解消につながります。









これらの疲労回復法は試験後だけでなく、普段の勉強や運動による疲労回復にも役に立ちますので、普段からやってみてください。
これ以外にも有効な疲労回復法はありますので、また別の機会にお話します。
実際に共通テストを受けて、うまくいった人、いかなかった人がいると思います。
いずれにしてももう結果は変わらないのでくよくよせず、気持ちを切り替え、次の試験で最高の結果を出せるようにすることだけを考えてください。
それから分かっていることとは思いますが、今はコロナウイルスの感染を始め、インフルエンザや風邪など病気には十分警戒が必要です。
予防に勝る治療はありません。
なってしまったときは慌てず、病院などの適切な指示に従い、正しい対応をしましょう。
受験先に大学にも問い合わせて、どのようにすればいいか聞くのが一番確実です。
もう少しです。
葛西TKKアカデミーいつでも受験生を応援していますし、必要であればどんな協力も惜しみません。
困ったときは気軽にご相談ください。
それでは、皆様のご健闘を願っています。






























2021.01.19
明日、明後日は共通テストです。試験前の過ごし方についてお話します。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは受験生の皆さんを応援します。

いよいよ明日、明後日は共通テストです。
センター試験から変わり最初のテストでまだ要領も分からず心配な受験生も多いと思います。
しかも、コロナウイルスの混乱もあり、受験生にはいつも以上に不安で困難な入試になりそうです。
しかし、これはどの受験生も同じです。
条件が同じならば余計なことを考えず、今持っている自分の力を出し切ることに集中した方がいいです。
共通テストの結果は大学入試に大きく影響します。
中にはこの結果がそのまま大学合格の判定に利用されるところもあります。
そんな重要な試験の前日です。
今日は、試験前日はどのように過ごせばいいか考えます。










ここまで来たら、もうやるしかありません。
腹をくくって明日に備える。
直前に不安になって、教科書を一から開いて夜更かししてはいけません。
そんな付け焼刃をしても、大して結果は変わりません。
むしろ、寝不足で実力が発揮できない方が問題です。
つまり、前日は万全の体調に整えることを第一に考えてください
しっかり睡眠を取り、精神を安定させて、ゆとりを持って試験に臨めるようにすることです。
先ず、睡眠です。
早寝をして翌朝はスッキリ目覚めるようにしてください。
人間の脳が本格的に働き始めるまでに、起きてから2時間かかると言われています。
試験開始から逆算して、その2時間前には起きていないといけません。
気になって勉強したくなるかもしれませんが、ここは自分を信じて勉強から離れましょう。
どうしても見直したいときは、夜ではなく早朝にしてください。
それも細かいところを逐一チェックするのではなく、ざっと目を通すくらいにしてください。
もし緊張や考え事で寝付けなくなったら、無理に寝ようとせず、目を閉じてじっと横になってください。
それだけでも体はかなり休まりますから。
次に食事です。
朝食は食べ過ぎないように、腹八分くらいがいいです。
こってりとしたものではなく、あっさりとして消化にいいものを食べてください。
食べ過ぎると苦しくなるし、血液も消化に取られ、頭の方に回らなくなります。
食べる時間も試験直前ではなく、余裕を持ってゆっくり噛みながら、落ち着いて食べられるようにしてください。
出発について。
持ち物や着替えは前日に用意し、全てそろっているかチェックしておいてください。
当日に慌てて忘れ物をしてはいけません。
受験票など忘れても試験は受けられますが、その事実が精神的にダメージを与え、本領発揮できなくなることもあります。
当日はそのまま出かけられるようにしましょう。
そして、出発時間ですが、これも余裕を持って早めにするのがいいです。
電車が止まったり遅れたりすることもあります。
どんなトラブルがあるかもしれません。
だから早めに家を出て、どのような状況にも対応できるようにしましょう。
もしトラブルに巻き込まれたら、落ち着いて試験会場か大学入試センターに連絡をしてください。
きちんと対応してくれるはずです。
会場には試験開始の30分から1時間前に付けるようにしてください。
テスト前に試験会場をぐるっと一周できるくらいの余裕があるといいです。
落ち着いて深呼吸して待ちましょう。
しかし、今年はコロナウイルスの感染者急増中ということもあり、できれば公共交通機関は利用しない方がいいでしょう。
どうしても電車やバスを利用しなくてはならないときは、時間をずらしたり人ごみの少ない車両を選んだり、可能な限り密な状況を避けるようにするしかないです。
マスクなどの防護も当然必要です。
また、会場についてもすぐに入場できるとは限らないので、事前にホームページや運営に問い合わすなどした方がいいでしょう。
本当に今年はコロナウイルスの感染予防という例年にない項目が入っています。
試験を前に混乱しがちですが、いざと言うときは会場担当者に聞き指示に従えば大丈夫です。
難しいですが落ち着いて平常心でいられるようにしましょう。
最後に、繰り返しになりますが、直前にじたばたしても仕方ありません。
実力以上のことはできません。
だから、本番で実力を100%出すことに集中してください。
やれることをやればいいのです。
そう開き直ると気が楽になると思います。
そして、「自分はできる」と自分に言い聞かせてください。
精神の当たれる影響は非常に大きく、どのように気持ちを持っていくかで結果が左右されます。
スポーツ選手もイメージトレーニングで、本番に精神状態を最高に持っていきます。
受験生の皆さんもそうしてください。
そして、明日うまくいかなくても気にしないでください。
気にして次の日もうまくいかなくなるのが一番いけません。
やってしまった試験の結果は変わりませんから、色々悔やんでも仕方ありません。
自分のやれることをしっかりやる。
それだけです。
「人事を尽くして天命を待つ」です。
しばらく寒くなります。
防寒もしっかりして、風邪などひかず万全の態勢でテストを受けてください。
葛西TKKアカデミーも受験生の皆さんを応援しています。
































2021.01.14
緊急事態宣言の中、入試シーズンがスタートしました。入試ではコロナウイルスに感染しにくいと言われていますがなぜでしょうか。

東京都を始め日本の様々な地域で入試が始まっています。
先週末の中学受験をスタートとして、来週にはいよいよ共通テストが行われます。
その後、私立大学の入試、都立高校の推薦入試、私立高校の入試、都立高校の入試、国公立大学入試と立て続けに入学試験が実施されます。
コロナウイルス感染を恐れ、中学受験では面接が中止された学校もあります。
共通テストでは大学入試センターが明確なガイドラインを提示していて、感染防止に努めています。
その他の入試でも各大学をはじめとする学校が、それそれにコロナウイルス対策をして受験生が感染の心配がないように準備しています。









よく専門家の間でも、入試では他の状況に比べコロナウイルスにかかりにくいと言われています。
文科相もどんなにコロナウイルスの感染が広がっても共通テストを中止するつもりはないと発言したのは、これが理由の一つでしょう。
なぜ入試ではコロナウイルスの感染リスクが少ないのでしょうか。
第一に、今回の入試において政府を始め各試験会場でも感染防止のために様々な対策をしていることがあります。
前日から会場の殺菌消毒を徹底し、会場によっては当日入場時に検温をする。
マスクは常につけ、試験当日に忘れた受験生がいたら、会場がマスクを提供する。
導線を決め受験生がむやみに拡散しないようにする。
入場退場時には時差を設け、一度に受験生が集まって密にならないようにする。
休憩中は窓を開け換気をする。
昼食は個々が間隔を空け、おしゃべりせずに食べる。
他にもありますが、このように感染防止に向けた取り組みをしっかり行っているので感染しにくいということです。
それにもともとカンニング防止のため受験生同士の間は広くとられており、見知らぬ受験生が多く参加するので、積極的におしゃべりすることもあまりありません。
自分のことに集中して、他人のことまで気が回らないのです。
つまり、入試会場は元来、飛沫感染しにくい環境だということです。









また、感染者の年齢と重症化した人を比べると、若者は比較的感染しにくく、しても無症状だったり、軽度の症状で済むことが多いというのも理由にあげられています。
これが今回のコロナウイルスの厄介な所でもあるのですが、感染者が表立って分かりにくいのです。
結果、無意識にウイルスを広めてしまったという面もあるのですが、かかっても特に症状が出なければ本人の受験には支
障がないように思えます(ただ、自分が大丈夫でも人に移して、相手が重症化する危険性はあるのですが)。
また、受験生を持つ家庭は、一般の家庭以上にコロナウイルスの感染に気を遣い、あらゆる手段で自分の子供を感染させないように努力するところが多いです。
同じ家族でも離れて食事をし、家の中でもマスクをし、外から帰ったら手洗いうがい。
お風呂は受験生を最初に入れて、親からうつさないようにする。
タオルや使う道具も各自が別々のものを使い、使いまわしは極力避ける。
学校も受験生に気を遣い感染防止策を実行していますが、それでも登下校中の感染を恐れ、中には学校を休ませる家もあります。
また、外に出ることが多い父親をホテルに宿泊させ、受験生と接触しないようにするという話も聞きます。
感染経路も家庭内感染が一番多いようで、どうしても神経質になるのでしょう。
ここまで徹底するとすごいとしか言えませんが、本人のこれまでの努力、一生のかかった本番を無にしないようにするにはこのぐらいしてもちょうどいいくらいでしょう。









とは言え、コロナウイルス感染のリスクが全くないわけでなく、少しでもそのような不安を抱えて受験しないといけない生徒たちに同情を覚えます。
政府を始め大人たちの対応が適切であれば、もっと早い段階で終息し、今頃はこのような心配なく試験に集中できたのではないかと思うと非常に悔しく感じます。
いくら会場の感染防止を徹底しても、会場への行き帰りでは街中で多くの人と接触するわけだし、試験後に友達と会えば、その開放感から当然お話に夢中になることでしょう。
都心の受験生はまだ自宅から試験会場に通えるから、感染リスクは少ないでしょうが、例えば地方から上京し、更に宿泊もしなくてはならない受験生は、これらの受験生より感染リスクは高まり、慣れないところでの宿泊は不安を一層あおり、実力が十分に発揮できない可能性もあります。
無症状キャリアーが怖いと申し上げましたが、これだけの重大な試験になるとどうしても受験生は具合が少々悪くても、無理をして試験を受けようとするものが少なからずいるでしょう。
その時、他の受験生にウイルスをうつすかもしれません。
また、若者はコロナウイルスに対して比較的感染しにくい、症状が軽いと言いましたが、実際に小中校問わずクラスターは発生しており、重症になっている人もいます。
しかも、毎日のように何百人何千人と新規感染者が発生している状況では、どこに感染者がいてもおかしくなく、更に感染力の強い変異株もあるとのこと。
いつどこで誰が感染してもおかしくないのです。
実際、非常に注意して感染予防を徹底していた人がかかったという事例もあります。
家から出ただけで危険と言っても過言ではないでしょう。
更に、今のような医療機関が圧迫されている状況では、感染したからと言ってすぐに適切な治療を受けられるとは保障できません。
後、受験生ばかり目が行きがちですが、試験には試験監督を始め準備や運営に多くの人々が関わっており、これらの若者ではない人々の感染も考える必要があります。









以上のように入試においてコロナウイルス感染のリスクは比較的低いとはいえ、全くないわけでなく、そこまでの危険を冒してまで受験をしなければならないか、正直疑問が残ります。
もう少し工夫して、こんな危険な状況下で受験をしなくてもいいようにできなかったのか。
文科省を始め多くの人はもう日程を変更することなく、このまま危険な炎の中を突っ切ることに(実際突っ切るのは受験生ですが)しています。
とにかくやって終わらせたいということでしょうか。
そこには本当に受験生の健康や命を重んじた考えはあるのでしょうか。
もう直前で状況は変わらないでしょう。
嘆いても仕方ないのは分かっているのですが、もっとどうにかできたはずと思うと悔しくてたまりません。
このような状況になってしまったことに対し、全ての受験生に向け謝りたい気持ちです。
本当に今年の受験生は例年以上に苦難や困難があり、それでもめげずに頑張って勉強したことに敬意を表します。
とにかく、みんな大変ですが、自分を信じ、持てる力を全て出し切って後悔のない受験にしてほしいです。
非力ながら応援しています。

























2021.01.07
今日は七草粥を食べよう!実は日本の伝統的行事は受験など勉強でも重要な事柄。年中行事に対する実践が希薄な今だからこそ子供たちに経験させましょう。


今日は一月七日。
そう、七草粥を食べる日です。
正月、節分など日本の伝統的な年中行事は受験などで非常に重要な学習事項なのです。
一般常識や教養として国語や社会、英語に出てきますし、中学受験では面接で聞かれることもあります。
受験などの出題者は日本の伝統的な内容を扱うのが好きなようです。
学校の授業であまりやらないからこそ、自分たちで年中行事は何がありどんなことをするのか、どうしてそうするのかを知っておかなければなりません。
現代社会では伝統的な風習が薄れてきていますので、家庭が積極的に拘るようにしましょう。
家庭でも意識的に注意しカレンダーを見ながらやっていただきたいし、無理ならば子供と話し合うだけでも違います。
体験があるとないとでは大違いですし、知っているといないとでもかなり違ってきます。
因みにスーパーやデパートなどお店は年中行事を利用してビジネスチャンスを広げようとしているので、意外と年中行事について敏感です。
「正月」「恵方巻」「節分」「土用丑の日」「冬至のゆず湯」など、その時節に合わせてコーナーを設けて特別販売をしています。
子どもと買い物に行ったとき、これらを利用して親子で年中行事について語ったり、家でやってみるのもいいでしょう。
子どもの教養がつくと同時に親子の会話が増えつながりが強くなり、楽しい思い出作りにもなります。
いいことたくさん。
面倒くさい、どうでもいいなんて言わず、是非お勧めしますのでやってみてください。









「七草粥」についてお話します。
ご存知ですか。
実は一月七日は人日の節句。
元々中国の風習で、この日は犯罪者に対する刑罰を行わない日でした。
また、この日には七種類のあつものを食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草粥となりました。
正月で美味しいものをいっぱい食べ弱った胃を整えると同時に冬に不足しがちな栄養素を取るのです。
そして、無病息災を願うのです。
私も今朝、七草粥を食べてきました。
細かく刻まれていたのでそれほど薬味はありませんでしたが、たまにはお粥もいいもので、おいしくいただきました。
これで元気になって頑張れるといいです。
ところで七草には何があるか知っていますか。
これが問題に出ることもあるので、干支や九九のように呪文みたいに覚えましょう。
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、スズナ、スズシロ、ホトケノザです。
七草粥の作り方
1のお米に対して7のお水を加え炊きます。
七草は細かく刻んで下茹でをします。
葉っぱ系のものは茹でてから刻むといいです。
お粥と一緒に食べたとき、違和感がなくなるぐらい柔らかくなるまで茹でましょう。
40分ぐらいお米を茹でるとお粥の完成です。
塩を加え味を調え、七草を加え混ぜましょう。
これで出来上がり。
冷める前に召し上がって下さい。
皆様の一年が健康で良い年でありますように。
























2021.01.02
コロナウィルスで収入が減り、子供たちの学びの機会が失われています。葛西TKKアカデミーが力になります。お金のことは心配しないでください。彼らの将来のために!
葛西TKKアカデミーのニュース
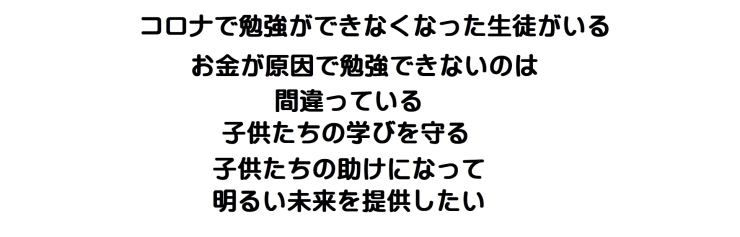
コロナウィルスで収入が減り、子供たちを塾へ行かせてあげられない。
心配しないでください。
葛西TKKアカデミーがついています。
勉強したいのに、お金で勉強できないのは可哀想です。
各家庭の状況に応じて対応します。
だから、決して学びをあきらめないでください。









昨年より新型コロナウイルスの影響で仕事が激減し、収入が大幅に減ってしまった家庭が急増中です。
何とか家計をやりくりしてもお金が足りない。
節約し、時には何か支出をカットしないと生活を維持できない。
コロナウイルスは終息するどころか最近では逆に拡大の一方。
政府の対策や支援も期待できるものではなく、経済回復の見通しも全く立たない。
いつまでこんな生活を続けていかなくてはならないのか。
先行き不安だらけです。
これは子供たちも同じで、コロナウィルスのせいで学校生活にも多くの制限がかかり、楽しい友達との交流やイベントも減り、授業でも休校中の遅れを取り戻すべく生徒がついていけるか関係なく、ただ学習事項を終わらせたという形式を作るためだけにどんどん進んでいく。
じっくり考え教えてもらう時間もなく、分からなくても置いてきぼりで勉強がますます面白くなくなる。
本当はもっと学んで勉強ができるようになりたいのに。
家計が苦しくなっていることは生徒たちも理解しており、これまで行っていた塾や習い事のお金が出せずやめなくてはならない者も多く出ています。
そして、ますます勉強が分からなくなり、ストレスがたまると同時に希望も見えなくなって、日々悶々と過ごす。
楽しみもなくなり家庭では親もイライラ。
家庭内の不和は学校でのいじめとなり(実際にいじめが急増しているようです)子供たちの心をむしばむ。









全てこの一年間のコロナウイルスの流行とそれに対して適切な対応を取れなかった大人たちの帰結による社会的混乱。
そして、その影響を子供たちが受け、彼らが学びをあきらめなくてはならないことに非常に憤りを感じます。
これまでも、コロナウイルスのせいで進学をあきらめた、勉強したいのに塾をやめるしかなかった、仕事がなくなり遠くへ引っ越さないといけなくなった、など子供たちから学びの機会が大きく損なわれている声を聞きました。
権利として認められている教育が受けられないのは許しがたいことです。
今までも葛西TKKアカデミーは大手塾で置いていかれる生徒など、教育的弱者を特に気にして、彼らの学びの場となれるように努力をしてきました。
お金が原因で勉強できないのは可哀想。
もちろん葛西TKKアカデミーもゆとりがある訳ではないのですが、それでも彼らの学びを守りたい、勉強への意欲を尊重したいと家庭の事情に応じて、時には授業料を大幅免除をすることもありました。
そこまでしても子供たちの将来のために、勉強をあきらめてほしくないのです。
そして、現在のような状況になり、学びたいのに学べない生徒が増えていることを悲しく感じ、彼らのために何かできないかと考えています。
葛西TKKアカデミーは私が経営する私塾であり、大手の大規模塾と違いいろいろな面で融通が利きます。
授業料はもちろん、時間や内容まで気軽にご相談ができ、可能な限りお応えする用意があります。
このような時代です。
困っている生徒は見捨てられません。
私がどんなに苦しくても、葛西TKKアカデミーが力になります。
お金のことは心配しないでください。
生徒に学びたい気持ちがあるのなら、いくらでも応え支えてまいります。
実際、今、葛西TKKアカデミーに通っている生徒には授業料が半額、それ以下でお受けしている生徒もいます。
また、個別指導なのでコロナウィルスの感染リスクも低く、それでも心配な場合はオンライン授業もあります。
あらゆる方法で支えになりますので、勉強に困ったときは気軽に葛西TKKアカデミーまでご相談ください。
力を合わせてこの苦難を乗り越えましょう。
























2021.01.01
新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは1月1日より授業を行っております。

新年あけましておめでとうございます。
本年もこれまで同様、一人でも多くの子供たちの力になるべく頑張ります。








去年はコロナ禍で、生徒だけでなく社会全体が大きな影響を受けました。
特に受験生は入試制度の変更という未知なるものへの挑戦に加えこの混乱ですがから、非常に厳しい思いをしていると思います。
それでも歯を食いしばって頑張っていると思うと、本当に何とかしてあげられないものかと考えます。
特にコロナウィルスによってもたらされた経済への打撃は多くの家計を打撃し、失業や倒産、レイオフなどシングルマザーを始めとする社会的に弱い地位にある家庭を中心に収入の激減、またはゼロという事態を招いています。
その結果、塾や習い事など生徒の学びの機会をあきらめないといけないとう状況が多発しています。
以前にも話しましたが、お金が理由で彼らの学びが損なわれるのは非常に可哀想で許せないことだと感じています。
葛西TKKアカデミーが何とかできないかと考え、明日、その対策を発表したいと思います。
一人でも多くの子供たちの学びを守りたい、彼らを支え明るい未来を迎えてほしい。
希望ある人生が提供できるように、葛西TKKアカデミーはいかなる努力も惜しまない所存です。









本日一日より授業を行っています。
それは、今日から頑張りたいという生徒の意思があるからです。
そして、彼らの勉強したい気持ちに応えるべく、正月返上でやっています。
このように葛西TKKアカデミーは要望があればどんどん受け入れ、それを叶えたいと考えています。
これは小規模個別指導塾だからこそできることで、それぞれの事情に合わせ、授業内容から料金、時間帯まで、柔軟に対応できます。
これが葛西TKKアカデミーの強みです。
そして、小規模だからこそ、生徒と先生、そして家庭との距離が近く、細かいところまで目が届きます。
一人ひとりを大切にし親身になって考えることができす。
塾と生徒と家庭が互いにコミュニケーションを取り合い、生徒が直面する様々な問題に対応するのが葛西TKKアカデミーの流儀です。
そして、それは時には勉強だけにとどまらず学生生活や家庭での過ごし方、子育て全般まで及びます。
どんなことでも気軽に相談できます。
まだコロナ禍も収まる気配を見せず、先行きが見えず不安な日常が続きますが、これに屈することなく生徒が少しでも充実した楽しい日々を送れるように全力を尽くしていきたいと思います。
今年も葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーを宜しくお願い申し上げます












2021.01.01
今年一年、多くの方々に支えられてきました。大変ありがとうございました。年明けすぐに受験を控えています。個別指導塾葛西TKKアカデミーはこれまで同様、来年も生徒を第一に考え全力でサポートしてまいります。

本年中は多くの方々に支えれれ、誠にありがとうございました。
まだまだ十分ではありませんが、生徒たちの力になれたことを感謝しております。
特に今年は教育改革に伴う混乱に加えて、コロナ禍で生徒たちには苦しく厳しく混乱に満ちた一年となりました。
少しでも早くこの混乱が収まり、以前にも増して幸せな生活が彼らに戻ってくれることを願うと同時に、葛西TKKアカデミーとしても非力ながら来年も皆様のお役に立ちたいと考えています。









常に生徒のことを考え、彼らの勉強したい気持ちを尊重し、親密に関わりながら勉強の指導をしてまいりました。
各家庭の事情や生徒の要望などを踏まえ、できるだけ希望に沿うように尽力しました。
コロナウイルスは日本経済と社会を直撃し、多くの家庭が収入の減少と困窮に陥り、生徒の願いに反し学びをあきらめなければならない事態に遭遇しました。
実際、葛西TKKアカデミーにもそのような家庭があり、そのような場合は本来の授業料から大きく割り引いた金額で学業の指導をさせていただいています。
学びたい意思があるのにお金のために勉強ができないなんて可哀そうすぎますし、学ぶ権利としてしっかり守ってあげないといけないと思います。
子供たちの将来のため、学習指導という窓口を通して葛西TKKアカデミーが何らかの助けになれればと常に努力してまいります。
この姿勢は今後も変わりません。








因みに大晦日の今日も冬期講習の授業を受ける生徒がいます。
そして、明日、元日も。
みんな頑張っていますね。
そして、年が明ければ早々に入試があります。
今年は大学入試も高校入試も例年以上に厳しい受験になりそうです。
個別指導塾葛西TKKアカデミーの受験生たちも最後の追い込みに入っております。
何とか全員の夢がかなうように、私も全力を尽くす所存です。
来年もまた多くの方々のご愛顧をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
葛西TKKアカデミー
塾長 溝渕 正樹
























2020.12.30
受験生にはいよいよ本番間近。この時期は何に注意して過ごすべきかお話しましょう。

冬休みが終わり新学期になれば、特に受験生にとっては本番の時期です。
大学を目指す生徒には今年が最初の共通テストが行われます。
中学高校受験生も推薦入試や本試験があります。
本番直前のこの時期はどのように過ごすべきか考えましょう。










一番大切なのは健康管理です。
どんなに勉強で頑張ってきても、体調を崩し本番で力を発揮できなければ意味がありません。
風邪などを引きやすい季節なので、マスクをしたり、うがい手洗いをして予防をしっかりしましょう。
また、少しでも体調が変だなと思えば無理せず、病院に行き、しっかり体を休めましょう。
特に今年は新型コロナウイルスの脅威が未だ収まらず、むしろ拡大しています。
感染力がより強力な変異株も見つかっており、いつどこで誰が感染してもおかしくない状況です。
我々一般市民ができることは非常に限られています。
今、若い世代における感染者が最も多く、しかも家庭内感染という身近な者からの感染が多いので、受験生本人だけでなく、その家族や周囲の人々も積極的に感染予防しないといけません。
マスク、うがい、手洗いなどの基本的なことに加えて、不必要な外出を控え、人ごみを避け、最大限の警戒が必要です。
それでも感染する人がたくさんいるので厄介です。









コロナウイルスに関しては非常に多くの場面で語られているので、そちらを参考にしていただくとして、それ以外にも以下のような事柄に注意しましょう。
生活のリズムを整え朝型にしましょう。
睡眠時間をしっかり取り、本番当日のことを考え、午前中に頭が回転するように調整してください。
どうしても勉強をしないといけないときは早朝にするのがいいです。
暴飲暴食を避け、食事も健康的で栄養のあるものにしましょう。
部屋に閉じこもってばかりでなく、適度に外に出て軽い運動をした方が頭が冴えます。
成功した自分を想像したり、合格した後何をするかなど、ポジティブで楽しいことを考えましょう。
イメージすることは大切で心の安定につながります。
常に自分に「できる」と言い聞かせ、自分自身に自信を持たせるようにしましょう。
とにかく普段以上に健康に気を遣い、心身ともに最高な状態に持っていってください。










勉強に関しても、この時期に慌てて新しいことを覚えようなどとしないでください。
今自分が身に付けていることを100%本番で出せるようにすることに集中した方がいいです。
今までやった問題集などを開き、ざっと目を通して自分がどの程度できるかの確認をしてください。
一度やった問題を繰り返すというのは、実は非常に良い勉強方法です。
新しい本を買う必要はありません。
一度やったからやる意味ないとは思わないでください。
意外とできないものです。
パッと見て「分かるな」と思えばやらなくていいです。
「あれ、どうかな」「不安だな」「分からない」と感じた問題だけやってください。
できればいいし、できなければ教科書や解答を見て確認してください。
こうやって自分のあいまいなところを直していくことに残りの時間を費やしましょう。
これが手軽で実力をつける勉強法です。











受験は本当に苦しいものです。
でも、そのくらいやらないと本番で実力が出ないし、後悔します。
自分の持てるものは全て出し切れば、必ずうまくいきます。
だから、付け焼刃で慌てて新しいことを勉強するのではなく、今まで頑張った自分を信じ、自分の力を全て出せるようにコンディションを整えることに尽力してください。
これがこの時期受験生がすべきことです。
あと少し。
頑張ってください。
応援しています。

































2020.12.28
子供たちの学びの機会が失われています。コロナ禍の影響で失業、倒産、給料激減と家計が厳しい状況に陥っている家庭が急増。結果、塾や習い事、進学をあきらめなければならないことも。
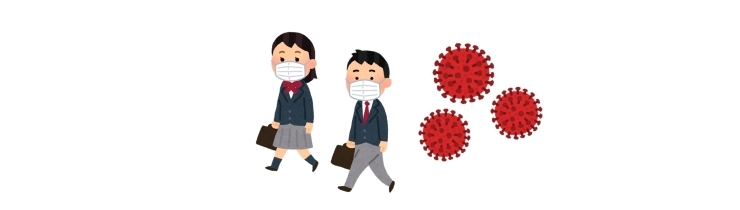
コロナウイルスが猛威を振るって随分長くなっています。
ワクチンが開発され、いよいよ摂取も始まると言いますが、未知の事態なのでまだ安心はできません。
現に感染者の増加は歯止めがきかず、更に感染力の強い変異株も確認されています。
第一波で緊急事態宣言が出され、外出自粛、経済活動の大幅な停止により中小企業を中心に倒産が多発し、シングルマザーやパートタイマーなど社会的弱者を中心に失業、仕事がない状況が続き家計は大きな打撃を受けました。
そして、今、第三波でこれまで以上に感染が広がって、これまで以上に人々の生活は厳しくなっています。
「GoToキャンペーン」で経済回復を期待していた会社は、だからこそ経営悪化は致命的でまたも倒産は広がる一方です。
倒産、失業、収入激減は当然子供たちの学びにも響いて来ています。
文科相によると、4月から10月でコロナウイルスのせいで退学した大学生、大学院生は1000人を超え、同じく休学したものは4200人を超えたそうです。
回復の見通しの立たないまま、この数字は増加すると見込まれます。
親の仕送りも難しくなり、バイトもコロナウイルスのせいで会社の売り上げが伸びない以上バイト切りに会い、学費と生活費が払えないという状況に追い込まれた学生が多く存在します。
かと言って、奨学金は借金のようで借りたくない。
一時学業を中断し、その間に十分なお金をため復帰することができればまだいいのですが、現実としてそれも難しく、結局退学という道を選ばざると得ない学生もいます。
そして、今は在学中の学生も退学や休学を考えている人が少なくありません。
憲法でも認められている「学ぶ権利」が大きく損なわれているのです。
この事態はかなり深刻なのですが、政府は本当に事の重大性を理解しているのか疑わしいです。









コロナによる家計の悪化は大学生ばかりに打撃を与えているわけではありません。
高校三年生の中には今年から変わる大学入試制度に不安を覚え戸惑っている者が多くいました。
それでも頑張ろうとした矢先に、コロナウイルスによる混乱。
受験の大事な時期に学校が一斉休校となり勉強がままならなくなりました。
塾や予備校は感染拡大防止のため、休校になってしまいました。
それでも経済的にゆとりのある家庭は、オンライン授業や個別指導など、勉強が滞るのを回避する方法がありますが、コロナにより減収となった家庭では何もしてあげられません。
多くの生徒が、コロナがとどめとなって進学をあきらめたと言っています。
受験生でなくても、私立学校に通う生徒はオンライン授業などで勉強を進めることができましたが、家計がぜい弱で公立学校に通っている生徒は三か月も勉強がまともにできず、止まったままになりました。
そして、学校が再開しても、感染防止のために多くの制限が学校生活にかかり、遅れた勉強を取り戻すために(感染拡大防止の意味もあるのですが)学校行事を中止または縮小し、長期休みも削られ、突貫で勉強を強いられる。
これまでにないスピードで進む授業に追いつけない生徒が多く発生し、いつものような学校生活の中の楽しみも削られ精神的に参ってしまう生徒も少なくありません。
収入が十分あれば、それでも塾でついていけない分を補習することもできますが、コロナによる収入の減少は授業料の捻出を難しくし、不本意ながらも塾をやめるざるを得ない生徒をたくさんうみました。
そして、学校の勉強から取り残されていくのです。









私の身の回りでもこのような生徒の話は聞きます。
大学進学をあきらめた生徒。
今までの生活を維持できず、やむえず転居しなくてはならない家庭。
塾の授業料が払えずやめてしまった生徒。
子供たちにとってもコロナウイルスは災難です。
いくら社会が困難な状況であっても、最低限子供たちの学びは保障できないものでしょうか。
お金で彼らの大事な勉強の機会が損なわれるのは本当に悲しいし、あってはならないと考えます。
将来の日本を考えるなら、彼らのことを第一に考え、社会として何か手を打たなければなりません。
もちろん葛西TKKアカデミーは困窮している生徒のためにあらゆる手を尽くす準備があります。
困ったときはご連絡ください。
一緒に親身になって解決法を考えます。
学びを決してあきらめないでください。
希望はまだあると信じましょう。


























