塾長ブログ
2024.02.09
大きな字を書こう!なぜ生徒は小さくて読めない字を書くのでしょうか?

そのようなことの中から、今回は字の大きさについてお話したいと思います。








文字を書くことは勉強において日常茶飯事だし、ICT化が進んでいるとは言え、未だに学校ではテストを始め多くの場面で手書きが行われています。
それは教育において「手書き」がある一定の有効性をもっているとの認識からなのでしょう。
しかし、スマホなど頻繁に文字入力変換を行っているいわゆるZ世代には、「手書き」はとても面倒で苦痛のようです。
Z世代でなくても、子供のころ「手書き」は苦手だったという人は多いと思います。
だから、こちらが言わないとノートを取らない生徒が非常に多くなっています。
ノートを取ることは勉強の基本ですから、これをする習慣のない生徒は当然成績も悪くなってしまいます。
「手書き」に関してはいろいろ申し上げたいことはあるのですが、今回はその中でも「非常に小さい字を書く」という点に関して議論してみたいと思います。
どうして「非常に小さい字を書く」のか?
本当に小さくて、文字がつぶれて何が書いてあるか分からないくらいです。
書いた本人も含めて誰も読めない字を書くということは、そもそも書く意味をなさないわけですが、どうしてそのような文字を書いてしまうのでしょうか。
先ず考えられる理由としては、小さい字は大きい字に比べ書く量が少なくてすむため早く書けるという点があります。
書くのが嫌いな生徒にとって、少しでも苦痛な「手書き」の時間を短くしたいという気持ちがあるのでしょう。
それから小さい字を書くと、鉛筆を動かく範囲も小さくてすむので書いていても疲れにくいという点も挙げられると思います。
最近の生徒たちは筆圧が弱く、文字を書く体力がなくなっています。
これは最近の生徒たちの体質の問題ではなく、生活環境の問題だと思うのですが、驚くかも知れませんがこれは明らかな事実です。
このように「時短」と「省エネ」が非常に小さい文字を書く要因の一つと考えられます。
もう一つ、個人的にはこちらの方が気になるのですが、考えられる理由としては、「生徒たちの自信のなさの表れ」です。
生徒は文字を書かなくてはなりません。
しかし、書いたものに自信が持てず、周囲からの批判を恐れるならば、小さい文字が言い訳になるのです。
「自分は書くことは書いたから義務は果たした。でも、不正解になったのは字が小さくて読んでもらえなかったからだ。」
多くの生徒はナイーブで、自分を批判され悪く見られること、心が傷つけられることを非常に嫌がります。
まともに書いて間違ってしまえば、周囲から自分は「ダメ人間」のレッテルがはられると思うのです。
不正解が自分の答えのせいでなく文字のせいであれば、「自分の解答が間違っていた」という批判はごまかすことができます。
自分が「間違える」ことが人に知られることを恐れる生徒はとても多いです。
しかも、書くことは書いたのだから、最低限やるべきことはやっていると自分を正当化できるのです。
また、字を小さく書けば「文字そのものに対する自信のなさ」をごまかすこともできます。
自分の字に対するコンプレックスがある生徒は、小さな字を書くことで字の上手い下手が判断できないようにしているのです。
小さければ文字のバランスも分かりにくく、どれも同じように見えてしまうので、なんとなく上手く書けているような錯覚に陥ります。
更に、漢字の間違いも小さい文字で書いてしまえば、画数の多い漢字は黒くつぶれてしまうので、点を打ったのか打っていないのか、棒を引いたのか引いていないのかよく分からなくなります。
だから、自分が漢字を正しく書いていなくてもバレにくくなります。
以上、字を書くという苦痛から逃れるため、そして、自信のなさを隠すために小さな文字を書いているのだと推測できます。
どうすれば小さな字を書かなくなるか
また、「自信」のなさを隠すごまかしにすぎないのであれば、いずれごまかしはバレ、特にテストなどにおいては何の良い結果ももたらさないので、小さな字を書く利点はありません。
先ずはこの二点をしっかり生徒たちに自覚させ、小さな文字を書いても何の得もないことを分からせる必要があります。
この点においては親さ先生などの指導者の説得が重要になってきます。
小さな文字を書くことのマイナス面を教えると共に、大きな字を書いたときはしっかり褒めてあげてください。
字そのものが汚いとか、書くのに時間がかかるとかは次の段階の問題なので、最初は日頃から大きな字を書く習慣を身に付けさせることです。
普段からメモや書き写し、日記など、日々の生活の中に書く機会を増やす工夫をしてください。
書く内容は勉強に限る必要はありません。
ちょっとした気づきや感動、自分の書きやすいもので構いません。
それから、すぐに書くのに疲れてしまう生徒は書く体力の無さもありますが、書く姿勢が悪い可能性もあります。
正しい姿勢で書けば体への負担も少なく疲れにくくなります。
このように書く時間を増やして、書くことに慣れさせ、書くことに耐え得る体力をつけましょう。
「自分の解答に対する自信のなさ」は「間違えることは決して悪いことではない」ことをしっかり話してあげましょう。
実際に学習において「間違い」というのは非常に重要なことで、むしろ「間違い」から多くを学べるので、「間違い」を責めないで次につながる大きなプラスであると考えましょう。
こうして「間違い」に対する恐怖心を取り除いてあげてください。
そして、「文字そのものに対する自信のなさ」は一つ一つ丁寧に漢字をさらえる必要があります。
最初はつらいかも知れませんが、漢字というのはパーツの組み合わせと考えれば、ある程度覚えてくると自然と新しい漢字も覚えられるようになります。
それまでは忍耐強く頑張るしかありません。
このとき、周囲のサポートが大きく影響しますから、可能な限り誰かが寄り添ってあげらえるようにしてあげましょう。
こうして一歩ずつ改善してあげてください。
一度身に付いてしまった習慣は、変えるのがとても大変です。
だから、できれば「小さい字を書いているな」と気づいたときにすぐ対応し、それが身に付いてしまう前に対処するのがいいです。
しかし、すでにそうなってしまった場合は、焦らず地道に頑張りましょう。
大きな字を書く利点
当然、大きな字は読んでくれている相手に分かりやすいので、自分の伝えたいことが伝わりやすいという点があげられます。
テストでは採点者にある程度の裁量が認められているので、小さく何を書いている分からない解答は読まれる前にバツになってしまいます。
せっかく書いたのだから、採点者にきちんと読んでもらい正しく判定してもらうためにも文字は大きく書きましょう。
次に、大きな文字で書けば自分でも何を書いたか目に入りやすくなるので、自分の計算や思考の過程がはっきり分かります。
そうすると間違ったところもすぐに見つかり訂正も簡単です。
そして、学習の内容も頭の中に入ってきやすく、記憶にも残りやすくなります。
そして、大きな文字を書くと、自分の書いていることがよく分かるので、書くことに集中でき勉強の効率も上がります。
先ほどの記憶に残りやすいという効果も含めて、勉強には非常に有効なことです。
また、無心で手を動かして「書く」という行為に没頭すると、周囲のストレスから解放され脳がリラックスします。
心に浮かぶことを書き記すことで、自分の考えを整理し脳内をすっきり整えることができます。
大きな文字を書くと外部からの印象も変わってきます。
大きく読みやすく伸び伸びとした字は、おおらかで外交的な印象を与えます。
人が親しみやすいと感じるでしょう。
また、高齢者など目の不自由な方に対して大きな字を書けば、それだけで相手に対する配慮があると好感度が上がります。








小さな字を書く生徒が気になり、今回はこのことに関していろいろ考えてみました。
字の大きさ以前に、「手書き」そのものの機会も減ってきているので、「字を書く」こと自体が苦手という生徒がたくさんいます。
しかし、勉強するうえで「手書き」という行為は現状では完全に逃れることはできず、日常生活においても同様です。
今は非常に小さい範囲て生活している生徒たちも、やがて大きくなり様々な人と交わり世界が広がっていきます。
そのとき、やはり「書く」という行為がきちんと身に付いていないと、大人として大きな恥をかくことになります。
したがって、生徒たちには勉強のためだけでなく将来のためにも、「書く」ことを嫌がらず正面から取り組んでほしいと思います。
とりあえず、字の大きさを大きくすることを心がけてください。
そして、「書く」ことに慣れ「書く」ことを楽しめるようになると、とても素敵です。
























2024.02.02
都立高校推薦入試合格おめでとう!

葛西TKKアカデミーでも二名の生徒が挑戦し、推薦入試に向けた対策講座でこれまで頑張ってきました。
そして、本日二人とも見事合格の連絡が入ってきました。
本当にすばらしい。
心からおめでとうと申し上げます。
これもひとえに生徒たちの努力の賜物です。
本人の頑張りがなければ決してなしえないことでした。
そういう意味では、彼らは堂々と自信を誇れる存在であると言えます。










上々の結果
そこで葛西TKKアカデミーでは、文章の書き方から面接の振る舞い、回答の仕方など試される意義と目的も含めこと細かく説明してまいりました。
そうして理論を確立した上で、実戦を積み重ねるという方法で指導してまいりました。
同じ推薦入試を受ける者同士、お互いに見あって批評することで、自分の短所に気づき、他者の長所に学び自分にも取り入れるというやり方で、相互に技術を高めあってきました。
そうして臨んだ今回の推薦入試ですが、いい意味で予想を裏切られました。
先ほども述べた通り、推薦入試は狭き門であり、よほど大丈夫であろうと思える生徒でさえ落ちることがあります。
だから、今回の結果は非常に嬉しい誤算でした。
二人とも合格とは上出来です。
あまりにも嬉しいので今回ここで共有させていただくことにしました。
残りの一般受験の生徒も頑張れ!
これで残りの一般入試の受験生も合格してくれれば何も言うことなしなのですが、こればかりはふたを開けてみないと分かりません。
とにかく先のことをとやかく考えても仕方ないので、入試直前の数週間を目の前の課題にしっかり取り組み、その積み重ねが合格につながるのだと信じて、毎日一歩ずつ勉強に励んでほしいと思います。
ここで気を抜かないように!
確かにこれまでの苦労が報われ困難から解放されたのだから、羽目を外したい気持ちも分かりますし、自分たちの努力に見合う分だけ楽しい思いをしてもいいと思います。
しかし、気をつけてほしいのは、これで全て終わりではないということです。
いや、むしろこれからが始まりなのだということ。
推薦や私立に合格し早々と受験勉強を終了した生徒によくあることなのですが、受験が終わったからといって完全に勉強を忘れてしまい、遊びまくる生徒がよくいます。
でも、このような人が高校に入ってから苦労します。
高校の勉強は当然中学の勉強が基礎となっているので、その中学の勉強を忘れてしまうと、高校の新学期が始まったとたん落ちこぼれてしまう場合が非常に多いのです。
中学のとき優秀で推薦入試を合格した生徒が、高校が始まると意外と振るわなくなるのは、このような事情があるからです。
そうならないためにも勉強の習慣は継続し、むしろこのゆとりのある期間をチャンスとして利用して、これまでの中学の勉強を充実させ高校の勉強を先取りし、より他の生徒に差をつけるくらいになってほしいと思います。
また、未だに多くの受験生は受験勉強に頑張っているので、彼らへの配慮もお忘れなく。
もし逆の立場だったらと考えれば分かりやすいと思います。
浮かれる気持ちは分かりますが、彼らへの敬意と配慮も十分にお願いします。










何はともあれ、生徒が希望する進路に進めることは非常に喜ばしいことであります。
みんな本当によくやりました。
これでこれまでの厳しい日々から解放され一息つけます。
とりあえず今日はゆっくり休み心も体も整えて、希望満ちる新生活に向かって新たな一歩を歩み出してほしいと思います。
このようにこれまで苦楽を共にしてきた生徒が自分の望みをかなえ、更なる人生に向かって進んでくれることが分かると、私自身の苦労も報われたような気がして嬉しくもあります。
皆さんは素晴らしい生徒です。
今後の皆さんの人生が輝かしいものになることを祈っています。
そして、非力ではありますが、まだ私にできることがあればいつでも遠慮なく相談してください。
いつでも力になる用意があります。






























2024.02.01
現在小学4年生が算数検定6級(小6相当)にチャレンジ中!

そこで、今回は算数大好きな小学4年生のお話をしたいと思います。










この生徒は学ぶことが楽しいらしく、算数以外に英語の勉強もしています。
とても素直ないい生徒です。
昔から算数が大好きで、学校の教科書にある内容だけでなく、つるかめ算や旅人算など特殊な算数も自分から勉強してきました。
こちらから指示する必要もなく、自分からどんどん与えられた問題集を進めていくタイプです。
もちろんなんでも理解してできるという訳ではなく、初見問題の中には一人では解けない問題もたくさんあります。
そんな時は葛西TKKアカデミーで質問するのですが、こちらが説明するときはきちんと耳を傾けて理解してくれます。
そうすると授業前には解けなかった問題も、授業後には自力で解けるようになります。
「おかしいな」「どういうことかな」「よく分からないな」と言うときは自分から進んで質問してくれるので、教える側としては非常にやりやすい生徒です。
そうやっているうちに小学6年生の内容も自分から勉強するようになりました。
そこで「せっかくだから自分の頑張った成果を形にしてはどうでしょうか」と提案しました。
自分の努力が目に見える形で残るというのは、非常に分かりやすく自信にもつながるからです。
このような経緯から来月に「算数検定」を受けることになりました。
レベルは6級で、小学6年生に相当します。
小学4年生の彼が合格すれば、それは十分に自慢できるほどの快挙であり、その可能性は非常に高いと考えています。
そういうことで今月から算数検定6級を目指した勉強に入っています。
算数検定6級は小学6年生程度の内容の問題を50分で30問解きます。
70%以上の正解で合格となります。
問題の9割が小学5年生、6年生の学習内容なので、小学4年生のこの生徒には決して楽な挑戦ではありませんが、これまで好きな算数を楽しんで自主的に勉強し、ご両親もこの子のそんな意思を尊重して算数の勉強をサポートしてきた思いもありますので、これまでの成果の結実として何とか合格できるように支えていきたいと思います。










今回のお話でお伝えしたいことは二つあります。
第一は、何であれ子どもが興味を持ったり、楽しいと感じたものは可能な限りさせてあげた方がいいということです。
自分の好きなことであれば自主的に行動し、自分なりに多くのことを考えます。
子どものうちは多くの経験を積むことや考えることが、彼ら自身の心と体の成長を促し、大人になったときに大いに役立つということです。
それは勉強だけに限る必要はありません。
生産的なものであれば、スポーツでも趣味でも何でも構いません。
本人が一心不乱に打ち込める何かを見つけられるということが大事です。
とは言え、それが簡単に見つからないの場合が多いと思いますので、親としてはいろいろな方面に情報を張り巡らし、どんなことでもいいから体験できそうなものがあれば、情報を提供し経験させてあげるように心がけましょう。
二つ目は、目に見える成果を与えることです。
勉強を始め多くの生徒たちが取り組んでいることは、幼い彼らにとってはよく意味の分からないものが非常に多いです。
時には苦痛でしかないように感じるかもしれません。
「何でこんなことをやっているのだろう」「頑張っているのに誰も分かってくれない」と自分の頑張りを疑い始めてしまうと、せっかくの情熱も冷めてしまうかも知れません。
よく分からないから、いまいちやる気が出ないということもあり得ます。
だから、何か漠然としてよく分からないものは、はっきり見える形にすることが大切です。
そうすると周囲の人間も分かるし、本人も自分の成果が分かるので自信につながります。
これは賞状やトロフィー、証書だけではありません。
日頃から子供たちをよく見つめ、その頑張りを称える周囲の人間の温かい言葉、できれば後にはっきり残る手紙やメッセージ、でも構いません。
ケーキやお菓子などのちょっとしたご褒美でもいいでしょう。
美味しい料理を食べたという楽しい思い出も悪くありません。
人間何かよく分からないことに対峙した時は、分かりやすい形に置き換えるのが一番です。
このように自分のことを正しく評価してくれる人がいると分かれば子供たちも安心して努力できますし、その信頼感が励みにもなります。
このように物事を可視化具現化することはとても重要なことなのです。










このように葛西TKKアカデミーでは日々、生徒たちが頑張れるように創意工夫をしています。
また、それぞれの生徒に合った授業、それぞれの生徒が希望する授業を提供できるように努めております。
今回のように算数検定を始め、英語検定や漢字検定を目指した授業も可能です。
色々な意味で皆様の要望に柔軟に対応できるのが、葛西TKKアカデミーの強みを自負しております。
どのようなことでも構いません。
こんな風にしてほしいななんてことがありましたら、遠慮なくお申し付けください。
皆様の力になれる葛西TKKアカデミーを目指しております。






























2024.01.27
受験生の中にはすでに合格した人も!しかし注意してほしいことがあります

最近は東京都の高校の授業料無償化の政策により、私立高校を第一志望に見据えている受験生も多くなってきました。
そのような受験生たちの中で私立高校合格が決まった生徒は、長く苦しい受験勉強から解放されるわけです。
同様に先日都立高校の推薦入試も実施され、間もなくそちらの結果も発表される予定です。
こちらの受験生も合格すれば受験勉強から解放されるわけです。
しかし、高校合格が決まった生徒に注意してもらいたいことがあります。
今回はこの点に関してお話したいと思います。










1.受験勉強は終わりましたが、学業はまだ終わりではありません
一つの区切りがついただけで、新たなスタートが待っていることを忘れないでください。
長く苦しかった受験勉強が終わり、これまで抑えてきた遊びたいという欲求をもう我慢しなくてもいいと考え、何もかも忘れて新生活が始まるまで遊んでしまう生徒がよくいます。
確かにこれまでの努力が報われたのだから、ご褒美として遊びに出かけるものいいでしょう。
自分のやりたいことをするのもいいでしょう。
しかし、だからと言って高校入学までの約二か月間を全く勉強せず、これまで学んできたことを全て忘れてしまっては大変です。
高校の勉強は中学とは比べ物にならないくらい内容が難しくスピードが速いです。
毎日の授業をきちんとその都度理解し身に付けていかないと、授業に追いついていけなくなります。
そして、高校の授業は、一年生の時は特に、中学の内容を完全に分かっている前提で進められますので、それができていないからと言って、授業を中断し一から教えてもらうことはありません(そんなことをしていたら高校でやるべき学習項目が終わりません)。
だから、分からないときは自分で何とかしないといけません。
特に進学したてのときは、中学と大きく異なる高校生活に慣れるだけでも大変なので、勉強で余計なことをする余裕はありません。
推薦や私立で合格した生徒には本当によくあるのですが、何も勉強でしないでいた二ヶ月のブランクのせいで、高校の勉強のしょっぱなからつまずき、それ以降挽回できずに高校生活が苦しくなる生徒が非常に多いです。
是非気をつけてください。
そうならないためには、合格したからといって完全に勉強から離れるのでなく、ある程度日々勉強に触れるように意識しないといけません。
特に一般入試で入学してきた生徒は、空白の時間が短く、これらの生徒以上に長い勉強時間を過ごしてきたので、学力差が大きく開いてしまっていることがあります。
そうなると成績評価がかんばしくなくなることも想像に難くないでしょう。
もちろん遊ぶなといっているわけではありませんし、むしろ受験の苦労を考えるならば娯楽も心身ともに健康であるためには必要です。
ただ、完全に勉強を忘れるということはないようにと忠告したいのです。
2.入学までの時間をチャンスに
むしろ、この猶予期間をチャンスと捉えることが大事です。
これまで中学で勉強して苦手だった内容の克服に時間を費やしましょう。
特に英語はどの分野に進むにも必要となりますし、高校の授業でも多くの時間が割かれ、科目も多くに分かれます。
英語で苦戦すると高校の勉強が大きく不利になり、進学も難しくなるので注意してください。
数学も多くの高校一年生がつまずく教科なので、しっかり基礎の確認をしてください。
そして、中学の内容に問題がなければ是非高校の勉強に取り掛かってください。
全教科でなくてもいいです。
少なくとも英語と数学の予習ができれば勉強に余裕ができるので、高校生活に適応するのがかなり楽になります。
他の受験生が一般入試で手いっぱいのときに、彼らに先んじて高校の勉強を始めらえるということは、高校生になったときに大きなアドバンテージとなり、その後の学校生活や大学進学をとても有利にすることができます。
最初が肝心です。
中学の復習と高校の予習に関して、葛西TKKアカデミーでもお手伝いができますので、気になった方は気軽にお問合せください。
3.まだ受験勉強中の生徒に配慮を
確かに自分はもう苦しい思いをしなくてもいいので、気分がウキウキするのも理解できますが、まだ必死で勉強している生徒もたくさんいます。
彼らへの配慮なく、「明日はどこに遊びに行こうか」「今度○○に遊びに行くんだ」などと言うのはやめましょう。
相手の立場になって考えれば分かると思いますが、自分たちへの当てつけのようで非常に不快になります。
そうでなくても受験勉強で精神的にイライラしている時期なので、彼らの気持ちを逆なでするのはよくありません。
これからの楽しいイベントに踊る気持ちは分かりますが、ここは自制して思いやりを持って接し、むしろ彼らを応援し勉強を手伝ってあげるくらいであるといいです。
ここは人としての振る舞いの問題です。










入試に合格した人には心よりお祝い申し上げたいと思います。
苦難を乗り越えた自分を誇り、それに価する報酬は当然あっていいと思います。
苦しいだけでの人生は良くないです。
しかし、これで全てが終わったわけではなく、これからも続く長い人生を考えるならば、むしろ受験が終わったこの時期をいかに過ごすかが非常に重要となります。
新生活を順調に始めるためには、むしろ今こそ勉強に励むべきとも言えます。
受験生は高校がどのようなものか知らないのですが、中学とは大きく違うということだけは肝に銘じておいてください。
新しい学校に適応するのはとても大変なので、このゆとりある時間を使って少しでも高校に向けた準備をするのが賢明です。
周りの受験勉強にまだ頑張っている仲間のことも配慮しつつ、自分の実力を伸ばしてほしいと願います。
合格できた皆さん、本当にお疲れ様でした。






























2024.01.22
最近のTKK:推薦入試対策が本格化!生徒も積極的に練習に励んでいます!葛西第三中、葛西中、東葛西中の生徒が最後の追い込みで猛勉強中
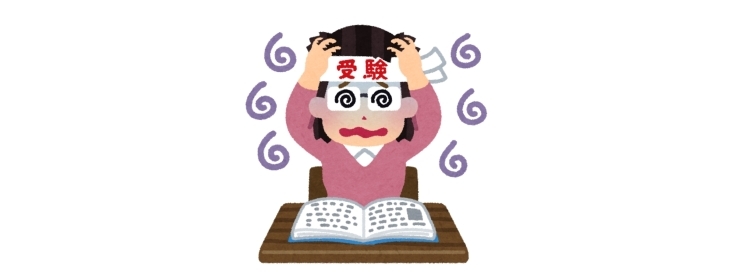
特に今年の葛西TKKアカデミーは、推薦入試を受ける生徒が多く、今月25、26日の推薦入試に向けた準備で大変です。








推薦入試は一般入試と違い、5教科の学力試験がないので簡単に思われる人もいますが、実はそれは大きな間違いです。
学校で日常的に勉強している5教科ではない部分を試験されるので、そもそも何をどうすればいいか、明確な唯一の正しい回答もないので、何も準備しないと戸惑い必ず失敗します。
テストで決められたやり方で一つの解答を見つけ出すことに慣らされている生徒には、実際受けてみると一般受験以上に難易度が高いと感じられるようです。
このような困った事態に陥らないように、葛西TKKアカデミーは推薦入試を受ける生徒には特別に推薦入試対策を実施しています。
推薦入試は調査書点と作文・小論文と面接によって合否が決まるので、そう既に決まっている調査書点以外の部分の指導を行います。
作文・小論文対策では、作文・小論文がどのようなもので何を目的として実施されるのか、そしてどのように書けばいいのか解説し、実際に与えられた課題に従って受験生に書いてもらいます。
そして、それらを一つずつ添削し、どこが間違っていて、どのようにすれば改善できるかを一人ひとり個別に指導していきます。
この対策講座を受けた生徒たちは皆、「思ったよりうまく書けなかった」と口にしています。
そうです、意外と文章って書けないものなのです。
だから、きちんと準備をし練習しないと本番では絶対にいいものは書けません。
逆に、練習をすればするほど上達するので、自ら心がけてたくさん書いてほしいと思います。
現に、ある生徒は試験当日まで毎日一つずつ課題を出してもらって、その課題に基づき小論文を書くと宣言しました。
この生徒の受ける高校はグラフなどの資料を出して、それについて議論させる形の論文形式なので、こちらも問題に出そうな話題についてのデータを集めなくてはならず、しかも毎日なのでとても大変ですが、せっかく生徒がやる気を見せているのですからそれに応えたいという一心で頑張って課題作ってあげています。
また、面接対策もしなくてはなりません。
こちらも中学生では面接を受けた経験はほぼないと思いますので、葛西TKKアカデミーで特別に指導をしています。
面接をする目的を説明し、どのようにすれば高評価を得られるのか解説します。
入退室や試験中の振る舞いや態度から、想定される質問にどのように答えるかまで細かく教えます。
面接では受験生がどのような人物かを聞かれるので、それぞれに自分が何者であるかを与えられたテーマに沿って書かせます。
こうして文字にして視覚化することで、自分をより深く考え見つめ直すことができるようにします。
そして、自分を知ることができれば、それをどのように表現すれば相手に伝わるかを指導していきます。
こうしてある程度の想定問答を作ると、次は実際に面接のリハーサルをします。
私が試験官になって、実際に生徒の入退室から面接中の態度、質疑応答まで細かくチェックします。
その後、リハーサルでの気づきや注意点、改善策を話していきます。
人に見てもらうということはとても重要で、自分では気づかない癖などを指摘してもらえます。
言われるからこそ気づけて、自分の悪い癖が意識できるので改善することが可能となります。
リハーサルでは、私以外にも他の受験生も立ち会ってもらいます。
理由は自分以外の人の面接を見ることで、お互いのとても参考になるからです。
人のいい点悪い点が分かれば、自分もどのようにすればいいか、何を注意しなくてはいけないのかが分かります。
このように受験生同士でも助け合って、共に合格を目指していきます。
こちらも生徒が「対策講座以外の時間にも練習させてほしい」と自主的に申し出てくれています。
せっかくのやる気に答えるためにも、何とか時間を作り対応しています。
面接に関しては推薦入試の受験生だけでなく、私立入試の受験生も参加しています。
こちらも面接を実施している高校がありますので、しっかり準備して少しでも合格に近づけるようサポートしております。








本日、都立高校の推薦入試の倍率が発表されました。
一般入試と違い推薦入試は倍率が高く、2倍3倍はざらです。
難しくはありますが、生徒が挑戦したいと頑張っている以上、こちらも何とかこの狭き門をくぐられるように全力で指導しています。
本番まであとわずか。
最後まで希望を信じて努めたいと考えます。
























2024.01.10
今週末は共通テスト!試験前日の過ごし方

センター試験から変わり、まだ要領も分からず心配な受験生も多いと思います。
しかし、これはどの受験生も同じで、不安であるのは普通のことです。
それならば条件は同じ。
余計なことを考えず、今持っている自分の力を出し切ることに集中しましょう。
共通テストの結果は大学入試に大きく影響します。
中にはこの結果がそのまま大学合格の判定に利用されるところもあります。
そんな重要な試験の前日はどのように過ごせばいいか考えます。











ここまで来たら、もうやるしかありません。
腹をくくって明日に備える。
直前に不安で教科書を一から開いて夜更かしなんてもってのほかです。
そんな付け焼刃をしても、大して結果は変わりません。
むしろ、寝不足で実力が発揮できない方が問題です。
つまり、前日は万全の体調に整えることを第一に考えてください。
しっかり睡眠を取り、精神を安定させて、ゆとりを持って試験に臨めるようにすることです。
睡眠
人間の脳が本格的に働き始めるまでに、起きてから2時間かかると言われています。
つまり、試験開始から逆算して、その2時間前には起きていないといけないのです。
試験が気になって勉強したくなるかもしれませんが、ここは自分を信じて勉強から離れましょう。
どうしても見直したいときは、夜ではなく早朝にしてください。
それも細かいところを逐一チェックするのではなく、ざっと目を通すくらいにしてください。

それだけでも体はかなり休まりますから。
食事
こってりとしたものではなく、あっさりとして消化にいいものを食べてください。

食べ過ぎると苦しくなるし、血液も消化に取られ、頭の方に回らなくなります。
食べる時間も試験直前ではなく、余裕を持ってゆっくり噛みながら、落ち着いて食べられるようにしてください。
出発
当日に慌てて忘れ物をしてはいけません。
受験票など忘れても試験は受けられますが、その事実が精神的にダメージを与え、本領発揮できなくなることもあります。
当日はそのまま出かけられるようにしましょう。
そして、出発時間ですが、これも余裕を持って早めにするのがいいです。
電車が止まったり遅れたりすることもあります。

どんなトラブルがあるかもしれません。
だから早めに家を出て、どのような状況にも対応できるようにしましょう。
もしトラブルに巻き込まれたら、落ち着いて試験会場か大学入試センターに連絡をしてください。

きちんと対応してくれるはずです。
テスト前に試験会場をぐるっと一周できるくらいの余裕があるといいです。
落ち着いて深呼吸して待ちましょう。
最後に
実力以上のことはできません。
だから、本番で実力を100%出すことに集中してください。

やれることをやればいいのです。
そう開き直ると気が楽になると思います。
そして、「自分はできる」と自分に言い聞かせてください。

精神の当たれる影響は非常に大きく、どのように気持ちを持っていくかで結果が左右されます。
スポーツ選手もイメージトレーニングで、本番に精神状態を最高に持っていきます。
受験生の皆さんもそうしてください。
そして、第一日目がうまくいかなくても気にしないでください。
気にして次の日もうまくいかなくなるのが一番いけません。
やってしまった試験の結果は変わりませんから、色々悔やんでも仕方ありません。
自分のやれることをしっかりやる。
それだけです。
「人事を尽くして天命を待つ」です。
しばらく寒くなります。
防寒もしっかりして、風邪などひかず万全の態勢でテストを受けてください。
葛西TKKアカデミーも受験生の皆さんを応援しています。

































2024.01.08
今年の正月は…(葛西TKKアカデミー塾長の場合)
早いもので年が明けてもうすぐ一週間になろうとしています。
今年は受験生が都立の一般入試のみならず、推薦入試、私立入試も受けますので、その準備に忙しくしております。
そのせいか例年よりも時間の過ぎるのが早いような気もします(そうでなくても毎年早く感じるのですが)。
今回は私の正月に関する私的な報告になります。










今年も大晦日まで、授業や授業の準備で忙しくいしておりました。
そして、元日は珍しく一日仕事がない日でしたので家族サービスをしました。
普段あまり構ってあげられないので、せめてもの償いです。
本来ならば初詣に出かけたいところですが、インフルエンザのこともあり人ごみはどうしても避けたいので、我が家では正月三が日はお参りには行きません。
今度の週末かその次あたりに遅めの初詣に出かけるつもりです。










子供にどこに行きたいか聞いたところ、『ゲゲゲの鬼太郎』の映画を見たいということなので、調べてみると「ららぽーと東京ベイ」のTOHOシネマで14時から上映の回がちょうどいいということになり、それに合わせて家族みんなで出かけることにしました。
よって、出かけるまでの午前中は家で過ごすことにしました。
ベリーパイ作り
実は、去年パイを作ろうと思い、冷凍のパイ生地とフルーツを買ったのですが、作らないままずっと冷凍室に入ったままになっていました。
そこで、家にいる午前中にこの生地を使って、娘とベリーパイを作ることにしました。
箱を開けてみると思った以上にパイ生地が小さく、アルミ皿に余ってしまうので、何枚かつなげてアルミ皿のサイズに合わせることにしました。
今回は出来合いのパイ生地でしたが、次回は粉から作りたいと思います。
パイ生地に冷凍のベリーを敷き詰めて、細く切ったパイ生地を上に乗せて卵の黄身を全体に塗りました。
妻の誕生日が1月4日なのでそのお祝いの意味も込めて写真のように「ママ、オメ」とパイ生地で書きました。
そして、オーブンで焼くこと20分。
表面がいい具合に色付いて、写真のようにおいしそうなベリーパイが完成しました。

しかし、焼きあがるとパイの柄と同じ茶色だったので混ざって目立たず、せっかくの「ママ、オメ」文字が目立たなくなってしまいました。
出来上がりを妻に見せたとき、特に言及がなかったので、恐らく文字は気づかなかったのかも知れません。
まあ、それもご愛嬌、いい思い出になります。
出来たてのパイは、まだぐつぐつといっていました。
ホカホカのベリーパイをみんなでパクリといただきました。
甘酸っぱくてとてもおいしかったです。

映画『ゲゲゲの鬼太郎 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』鑑賞
こうして午前中を過ごし、軽い食事をして映画に出かけました。
元日ではありましたが、恒例の福袋目当てのせいでしょうか、意外とららぽーとは混んでいました。
妻は映画が得意ではなく、どんな映画も大抵途中で寝てしまうので、別行動でぶらぶらウィンドーショッピング。
実はこの映画、以前に娘と妻の二人で見に行っていたんですね。
娘は気に入ったのか、もう一度見たいということで決めました。
だから、私と娘の二人で今度は見ることにしました。
毎月一日は映画が割引の日なので、この日も安くチケットが買えました。
娘が楽しみにしていた「チョリトス」と「スナックじゃが」、そしてソフトドリンクを買って映画館に入りました。
ファーストデイの割引と休日ということもあって、席は結構埋まっていました。
それでも、劇場の中央の席が取れたので、娘と二人で映画鑑賞しました。
長く長く人々に愛されている『ゲゲゲの鬼太郎』ですが、この年になって再び映画館で見るようになるとは思いもしませんでした。
誘ってくれた娘に感謝!
話の内容は、鬼太郎がメインではなく、鬼太郎のお父さんが「目玉おやじ」になる前の話です。
終戦直後の日本が復興してこれから勢いづいて成長しようとしている時期、その復興を表に裏に支え妖怪を利用して日本を牛耳ろうとする財閥一族に、その闇の真実を知ってしまったしがない記者の水木が鬼太郎の父と共に挑む話です。
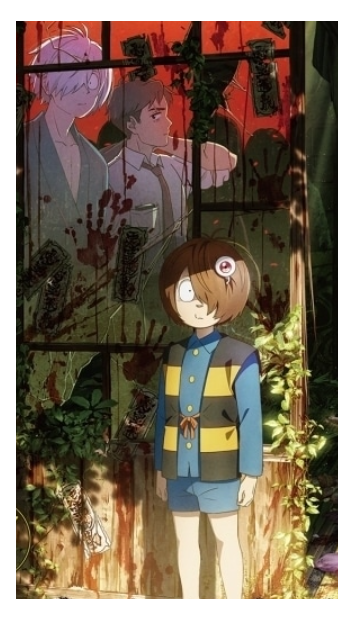
映画『ゲゲゲの鬼太郎 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』へのリンクはこちら
鬼太郎の誕生秘話も含まれ、ストーリーも二転三転し、妖怪よりもずっと怖い人間の剛が描かれています。
最初は子供向けかと思っていましたが、見てみるとよく作り込まれていて、大人でも単なるホラーとしてだけではなく、ミステリーやサスペンスとしても十分楽しめる映画でした。
隠れたお勧め映画です。
皆さんも是非一度ご覧になってはいかがでしょうか。
クレーンゲームと外食、買い物
娘との映画に満足し、次は娘がやりたがっていたクレーンゲームへ。
やり始めるときりがないので、上限を決めてチャレンジしました。
あまり欲しい景品がなかったのと、クレーンゲームが難しかったのもあって、何もゲットすることなく終了となりました。
一応遊べたので、それでとりあえず満足したようです。
その後、久しぶりに家族そろっての外食をしました。
早めの夕食だったので、レストランもそこそこすいていました。
みんなそれぞれ注文し、お代わりもしながら食事を楽しむことができました。
食事を終えると、もう閉店時間が近づいていました。
正月なので早く閉まるようです。
最後に私は塾で使う本が欲しかったので、本屋に行きました。
娘もついて来て、それぞれ本を探しました。
私が目的の本を入手した後、娘もマンガを一冊買いたかったようなので、お年玉代わりに買ってあげました。
そうしていると閉店時間になり、帰宅することにしました。
家に着くと20時前でしたが、日頃の疲れもあり早めに就寝することにしました。
休みだからと言って毎日の生活のリズムを崩すのも良くないので、娘と一緒に早寝の正月でした。
久しぶりの家族みんなでのお出かけでしたが、とても充実した一日を過ごすことができました。
正月っぽくはあまりありませんでしたが、まあ、それはそれでいいでしょう。










この時期は受験の追い込みや冬期講習もあって、非常にバタバタして心身ともに疲労困ぱいする時期でもあります。
今年も都立の一般受験のみならず推薦入試、私立受験まで指導しなくてはならず、睡眠や休息も十分に取れず本当に忙しい毎日です。
しかし、それでも空いた貴重な一日でしたので、何とかみんなの思い出になる一日にしたかったです。
できれば旅行で何泊かしたいところですが、現状では無理なので、何ができるかと常に悩むところであります。
今年は大したお出かけではありませんでしたが、みんなで一緒に時間を共有できることが大切かなと思い、このような正月となりました。
今年は早速二日から授業があり、その準備等でまた忙しい毎日がスタートしました。
生徒たちが頑張るというのなら、何があろうとそれに応える必要があります。
その分家族には迷惑や苦労も掛けますが、理解してくれていることに心から感謝しています。
また新たな一年が始まりましたが、今年も子供たちの明るい未来作りを全力でサポートしてまいりたいと考えています。
皆様の子育てや子供たちの勉強に貢献できるよう頑張りますので、今年もよろしくお願いいたします。
私にできることがあれば気軽にお声がけ下さい。
この一年が皆様にとっても良い年であるようお祈りいたします。






























2024.01.07
今日は七草粥を食べよう!伝統的行事は受験でも大事!ただ今、葛西第三中、葛西中、東葛西中の受験生が最後の追い込み中!

今日一月七日は、そう、七草粥を食べる日です。
七草が何か全部言えますか?
最近ではスーパーでもセットで売られていますよね。
だから馴染みのある人も多いかも知れません。
しばしば触れるように、正月や節分などの日本の伝統的な年中行事は受験などで非常によく問われる重要な学習事項です。
一般常識や教養として国語や社会、英語に出てきますし、中学受験では面接で聞かれることもあります。
どうも受験の出題者は日本の伝統的な内容を扱うのが好きなようです。
学校の授業であまりやらないからこそ、自分たちで年中行事は何がありどんなことをするのか、どうしてそうするのかを勉強しておかなければなりません。
現代社会、特に都会では伝統的な風習が薄れてきていますので、家庭が積極的に関わるように意識しないと、子どもたちも年中行事に触れる機会が少なくなってしまいます。
家庭で意識的に注意し、カレンダーを見ながら今月はどんな行事があるのか確認していただきたいし、実際に行事を行うのが無理ならば子供と話し合うだけでもやっていただきたいと思います。
体験があるとないとでは大違いですし、知っているといないとでもかなり違ってきます。
因みに、スーパーやデパートなどのお店は年中行事を利用してビジネスチャンスを広げようとしているので、意外と年中行事について敏感です。
「正月」「恵方巻」「節分」「土用丑の日」「冬至のゆず湯」など、その時節に合わせてコーナーを設けて特別販売をしています。
子どもと買い物に行ったとき、これらを利用して親子で年中行事について語ったり、家でやってみるのもいいでしょう。
子どもに教養が身に付くと同時に親子の会話が増え、つながりが強くなり楽しい思い出作りにもなります。
いいことたくさん。
「面倒くさい。どうでもいい」なんて言わず、是非やってみてください。
強くお勧めします。









「七草粥」についてお話します。
ご存知ですか。
実は一月七日は人日の節句。
元々中国の風習で、この日は犯罪者に対する刑罰を行わない日でした。
また、この日には七種類のあつものを食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草粥となりました。
正月で美味しいものをいっぱい食べ弱った胃を整えると同時に冬に不足しがちな栄養素を取るのです。
そして、無病息災を願うのです。
私も今朝、七草粥を食べてきました。
細かく刻まれていたのでそれほど薬味はありませんでしたが、たまにはお粥もいいもので、おいしくいただきました。
これで元気になって頑張れるといいです。
ところで、先ほども質問しましたが、七草には何があるか知っていますか。
これが試験問題に出ることもあるので、干支や九九のように呪文みたいに覚えましょう。
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、スズナ、スズシロ、ホトケノザです。
七草粥の作り方
最後に七草粥の作り方を書いておきますね。
1のお米に対して7のお水を加え炊きます。
七草は細かく刻んで下茹でをします。
葉っぱ系のものは茹でてから刻むといいです。
お粥と一緒に食べたとき、違和感がなくなるぐらい柔らかくなるまで茹でましょう。
40分ぐらいお米を茹でるとお粥の完成です。
塩を加え味を調え、七草を加え混ぜましょう。
これで出来上がり。
冷める前に召し上がって下さい。
七草粥を食べて、皆様の一年が健康で良い年でありますように。
























2024.01.01
新年あけましておめでとうございます!本年も宜しくお願い致します

昨年は多くの方々に支えていただきありがとうございました。
本年もこれまで同様、一人でも多くの子供たちの力になるべく尽力してまいりたいと思います。
新年明ければ早速、推薦入試が待っています。
本格的な入試シーズンのスタートです。
推薦入試は一般入試と違い特殊なので、それに合わせた準備が必要です。
何もしないで受ければ、先ず合格しません。
葛西TKKアカデミーでは推薦入試に向けたコースも用意してありますので、興味を持たれた方は是非ご連絡ください。
また、その後に始まる一般入試に関する準備や情報提供もできますので、こちらも気になる方はご連絡ください。
受験に限らず一般の授業でも新規生徒を受け付けています。
小規模個別指導塾だからこそ、それぞれの事情に合わせ、授業内容から料金、時間帯まで、柔軟に対応できます。
これが葛西TKKアカデミーの強みです。
今年も葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーを宜しくお願い申し上げます












2023.12.31
今年もありがとうございました!来年も全力で子供たちを支えます!

心よりお礼申し上げます。
まだまだ十分ではありませんが、生徒たちの力になれたことを感謝しております。
葛西TKKアカデミーとして来年も、非力ながらも引き続き皆様のお役に立てることを願っております。
今年は通常授業だけでなく、外国人のゲスト先生を呼んだり、イベントで多くの生徒に工作を教えたりしました。
また、通塾している生徒の中にはオリジナルの物語を作成中の人もいます。
内容はほぼ完成しているので、挿絵を入れて表紙をつけて一冊の本にして生徒に渡すつもりです。
このように自分の努力の成果が形になれば、生徒たちもやりがいを感じられると思います。
同様に数検や英検を頑張っている生徒もいますので、2024年には合格させて彼ら自身に「やればできるんだ」という自信を持たせてやりたいと考えています。
このように来年は、生徒たちの努力が目に見える形で残すことを目標の一つにします。
そして、今年も高校受験に励んでいる生徒たちがいます。
年が明ければすぐ、推薦入試、私立高校入試、そして都立高校入試と続きます。
受験勉強もクライマックスです。
模試や授業でも問題をたくさん解いて、みんな実力を身に付けてきました。
油断することなく最後の追い込みを頑張ってほしいです。
もちろん私も全力で支えていきます。
どの受験生も、そして彼らを支える家庭も苦しい時期です。
しかし、受験勉強を人生の一つの試練を考えるならば、この苦難を乗り越えた先には生徒たちの人間としての成長があり、その後の人生の大きな糧となります。
試験の合否も大事ですがそれだけではなく、自分を鍛えるチャンスとしてもこの苦難に打ち勝ってほしいです。
そして、そのために必要な助けは、葛西TKKアカデミーが惜しむことなくいくらでも提供いたします。
この苦難を乗り越えることができれば、みんなきっとかけがえのないものを手に入れることができます。
もう少しです。
共に頑張りましょう。









常に生徒のことを考え、彼らの勉強したい気持ちを尊重し、親密に関わりながら勉強の指導をしてまいりました。
各家庭の事情や生徒の要望などを踏まえ、できるだけ希望に沿うように尽力しました。
勉強面はもちろん、子育てについての悩み相談を受けたり、家計の厳しい家庭には金銭面で譲歩してあげたり。
せっかく子供たちが勉強したいときにお金のことでできないのは可哀想ですから。
子供たちの学ぶ権利を守るため、できることは何でもしたいと考えております。
新しいホームページにも記載しましたが、「必要なものは他にない、本気で勉強したい意思だけあればいい」が葛西TKKアカデミーの合言葉!
葛西TKKアカデミーのホームページへのリンクはこちら
少しでも多くの家庭が子供の成長にプラスの結果がもたらすことができるようにと尽力してまいりました。
子供たちの将来のため、学習指導という窓口を通して葛西TKKアカデミーが何らかの助けになれればと常に活動しております。
そして、子供たちが明るい将来を迎えられれば、それは社会の将来も明るいことを意味します。
その目標が実現できるように、葛西TKKアカデミーは日々努力しております。
この姿勢は今後も決して変わることはありません。








因みに、大晦日の今日も冬期講習の授業があります。
みんな頑張っていますね。
そして、年が明ければ早々に入試があります。
今年も大学入試、高校入試共に厳しい受験になりそうです。
先ほども述べましたが、個別指導塾葛西TKKアカデミーの受験生も最後の追い込みに入っております。
何とか夢がかなうように、私も全力で臨む所存です。
来年もまた多くの方々のご愛顧をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
お体に気をつけて、素晴らしい新年をお迎えください。
葛西TKKアカデミー
塾長 溝渕 正樹


























