塾長ブログ
2021.11.07
高校入試におけるスピーキングテストの導入。新しい情報が入りましたのでお知らせします。
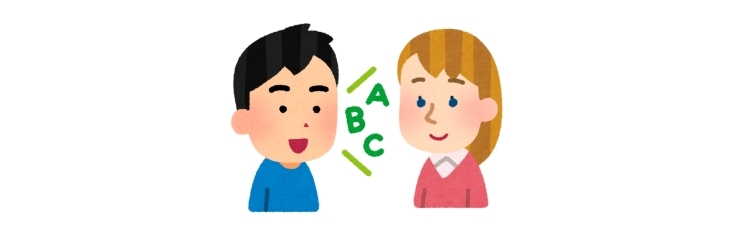
何度かここの記事でも触れたことがあるのですが、東京都教育委員会は高校入試においてスピーキングテストを導入する方向で、着々と準備を進めています。
これまでの英語の「聞く」「読む」「書く」の三技能に加えて、「話す」も試験に導入することで、これまで指摘されてきた日本人の英語コミュニケーション能力の低さを克服しようという狙いがあると見えます(実際の試験内容や学校教育の内容がそれに準じているかどうかは別として)。










大学入試での導入はとん挫しましたが(とは言え、文科省は近いうちに大学入試でもスピーキングテストを実施することを決定しています)、東京都では事業者(ベネッセコーポレーション)と提携し、高校入試の点数の中に英語の「スピーキングテスト」の点数を追加します。
このスピーキングテストは「ESAT-J」と呼ばれ、タブレット端末、ヘッドフォン、マイクを使って、受験生が実際に話した英語を録音し、それを評価します。
テスト内容は以前に話しましたので、ここでは新しい情報として、テスト結果がどのように入試の得点に反映させられるか、ESAT-Jのスケジュールについてお伝えします。
ESAT-Jの都立高校入試における評価法
ESAT-Jのテストは基本的に都内の中学校が会場になる予定です。
試験監督および採点は事業者であるベネッセコーポレーションが行い、受験生が解答した音声を録音したものを使って採点します。
この結果は100点満点で示されますが、入試ではこれを20点満点6段階評価(4点ごとに段階分け)に換算して利用されます。
評価Aは20点、Bは16点、Cは12点と順次点数が付けられ、最低ランクのFは0点となります。
そして、この結果は各学校及び自治体に提供されます。
送られた結果は受験生の調査書に記載され、志願先の都立高校へ提出されます。
つまり、調査書点に加えられるのですね。
その結果、都立高校の合否判定に関わる点数はどのように変わるのでしょうか。
これまで都立高校の合否は、調査書にある内申点に基づく調査書点と試験当日の学力検査の点の総合点で行われてきました。
・学力検査の得点
各教科100点満点の五教科の合計点500点満点で評価されたものを700点満点(一部都立高校、分割後期、二次募集は600点満点)に換算したもの。
・調査書点
中学校での成績表にある5段階評価の数字をそのまま得点とした内申点(ただし実技4教科は2倍で評価されます)65点満点を300点満点(一部都立高校、分割後期二次募集は400点満点)に換算したもの。
これら合計1000点満点でこれまでは判定されていましたが、これにESAT-J枠として20点満点が追加され、合計1020点満点で評価されるようになります。
1020点満点中の20点と甘く見ない方がいいです。
入試は1点で合否が分かれます。
だから、例え1点でも疎かにできません。
ましてや、スピーキングテストができるとできないでは20点もの差がつくので、これは合否を左右すると言っても過言ではない事態です。
尚、ESAT-Jを受けられなかった受験生は、入試において不利にならないように学力検査の英語の得点(受験当日の得点)から仮のESAT-Jのスコアを出し、総合点に加算するそうです。
この処置が本当に公平かどうかは疑問です。
スピーキングが苦手な受験生はあえてESAT-Jを受けないで、当日試験に集中してより高得点を出した方が有利かもしれません。
令和4年度以降のESAT-Jのスケジュール
実際に入試でESAT-Jが使われるのは令和4年度以降、令和5年の高校入試からの予定です。
現段階でのスケジュールは次のようになっています。
・令和4年7月下旬から9月上旬まで
ウェブによる申し込み、および特別処置申請
↓
・令和4年11月27日(日)
ESAT-J受験
↓
・令和4年12月18日(日)
ESAT-J受験予備日
↓
・令和5年1月中旬
個人及び中学校の結果帳表の受取
↓
・令和5年2月
都立高校入試選抜でのESAT-Jの結果活用
コロナウイルスの時勢柄、会場や使用機になどに対してガイドラインに基づく感染症対策が実施されるということです。
(手指消毒の徹底、マスク着用、関係者の検温、タブレット端末の除菌など)










このように都立高校入試においてスピーキングテストがかなり現実的になってきました。
しかし、多くの生徒や保護者はまだ知らない人が多いかもしれませんね。
しっかり情報収集をして早目の対策をお勧めします。
もちろん、葛西TKKアカデミーでも要望があれば対策を行います。
現在、日本の学校教育で行われている教育改革は非常に大規模で、これまで親御さんが経験したことのない教育になっていきます。
この変化にいかに対応できるかどうかが、これからの学校生活、受験、そして人生の成功への大きな鍵となるでしょう。
未知のことで不安もあるかと思いますが、要はきちんと対策ができていれば大丈夫です。
逆にできない人は落ちこぼれてしまい、各家庭、個人、及び学校にどれだけ対応能力があるかで、その後の生徒たちの人生が変わってくると考えられます。
いろいろ分からないこと、不安なことがあると思いますが、そんな時はどうか葛西TKKアカデミーまでご相談ください。




























2021.11.04
今週も葛西TKKアカデミーでテスト勉強しましょう!塾無料開放!塾生でなくても大歓迎!

テスト勉強は順調に進んでいますか。
期末テストが近づいてきました。
家で一人でやろうと思っても、いろいろ誘惑があったりして思うように勉強がはかどらないのではないでしょうか。
まだテスト発表がなくても、毎回学校のワークは出されるので、既に取り掛かっていいですよ(テスト発表まで待つ必要はありません)。
定期テストには早目の準備が肝心!
課題を早く終わらせ、テスト範囲の確認と練習をする時間さえ取れれば、定期テストは悪い結果にはなりません。
時間にゆとりがあれば、何回も繰り返し勉強ができ、より深く理解し、より難しい問題も解けるようになりますよ。
特に中学三年生は今回の結果がそのまま内申点に大きく影響するので、気合を入れて頑張りましょう。
もちろん、葛西TKKアカデミーもお手伝いします。
葛西TKKアカデミーに来てくれれば、静かに集中できる空間があり、分からなければいくらでも先生に質問ができます。
ここで勉強すれば効率も上がり、テストでより良い結果が出せるでしょう。










そこでお馴染み、葛西TKKアカデミーの定期テスト前イベント、「塾無料開放」!!!
誰でも(葛西TKKアカデミーの塾生でなくても)無料で塾が利用できます。
自由に自習ができ、分からないところはもちろん葛西TKKアカデミーの先生に質問できます。
しかも無料なのだから、利用しない手はありませんよ。
どうか皆さんふるってご参加ください。
きっといいことがあります。
ご利用の際は、事前にメールをいただけると幸いです。
e-mail:tkkac2016@gmail.com
葛西TKKアカデミーで勉強してよい結果を出しましょう!!!









そこで、葛西TKKアカデミーでは恒例の『テスト前、塾無料開放』を行います。
全ての中学生のために塾を開放しています。
葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。
気軽に来て、勉強してください。
家ではなかなか勉強しづらいと思います。
ここなら集中してできるでしょう。
いらした全ての中学生の勉強のサポートを行います。
5教科全てに対応し、指導します。
何でも遠慮なく質問してください。
しかも無料!!!
「学校で習ったけどよく分からなかった。」
「休んで抜けてしまった。」
「分かっているつもりだけど、確認したい。」
「学校の課題をする場所がほしい。」
「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」
など思っている生徒は是非訪ねてください。
皆さま大歓迎です。
学校帰りに立ち寄って、勉強してから帰っても構いません。
土日は昼からテスト対策を行います。
事前にメールいただければ、どなた様でも利用可能です。
e-mail:tkkac2016@gmail.com
葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。
この機会をお見逃しなく。









葛西TKKアカデミーで学校の課題を終わらせよう
課題はきちんとやらないといけません。
理解を深めるのはもちろん、実は提出物は成績(平常点)の大きな部分を占めるので、もし遅れたり出さなかったりすると成績が大幅ダウンしてしまいます。
いくらテストの点が良くても提出物が出ていないと大幅減点になりますよ。
かと言ってその場しのぎの答え丸写しはダメですけどね。
課題を軽んじることなく、早いうちから取り組み、提出日には出せるように、余裕をもって計画し終わらせましょう。
そして、定期テストの大半は学校のワークや教科書の問題です。
だから、課題をしっかりやっていれば、それだけでかなり高得点が取れることが予想できます。
だから、きちんとやって、分からないところ、間違ったところは解決して、ワークや教科書の問題を繰り返しやって、完ぺきにできるようになれば安心です。
とは言っても、家ではなかなか集中して勉強できないのではないでしょうか。
ゲームやテレビ、携帯やYouTube。
誘惑が多すぎて、勉強が手につかない。
そんな人は是非葛西TKKアカデミーへ。
誰でも無料で利用できます。
もちろん、葛西TKKアカデミーの塾生でなくても大丈夫。
勉強しやすい環境が整っているので、自分でコツコツ課題をやれますし、分からないときはいつでも先生に質問し、教えてもらいましょう。
























2021.11.02
塾は行かないといけないのですか?いいえ、でも行った方がいい理由もあります。(その一)

「塾は行かなければならないのですか?」と質問を受けることがあります。
答えから言うと、必ずしも行かなければならないということではありません。
でも、やはり行った方がいい理由があります。
もちろん考え方は家庭ごと個人ごとに違うので、最終的に行くかどうかの判断はそれぞれがすればいいと思います。
いずれにしても塾に行く利点を理解するのは悪いことではありません。










「勉強で分からないところを分かるようにする。」「テストで良い点数を取りたい。」などが一般的な理由でしょう。
それ以外のいく理由やメリットをご紹介しましょう。
入試に間に合わない学校の進度への対策として
学校の勉強できちんと理解でき、自分で自主的に勉強ができる生徒であれば何の問題もないでしょう。
定期テストでもしっかりとした結果を出すことと思います。
しかし、それでも解決できない問題があります。
それは学校のペースで勉強していたら受験に間に合わないということです。
学校は学習項目を既定の期間内に終了できればいいので、入試を見越した進度(受験に対応した勉強をする時間を確保する)に必ずしもなってはいません。
社会などは特にその傾向が強いのですが、三学期になって教科書の全てが終わる、または、終わらないから授業では教科書を読むだけでやったことにするなんてことがあります。
つまり、学校の学習事項が全て終わるのは入試の後、なんてこともあり得ます。
形式的に内容を触れたから全て教えたということにして、実際に生徒が理解して習得しているかどうかは関係ない(先生の立場が守られればOK)。
学校としてはこれで責務は果たされたことになりますから。
学校としてはそれでいいかも知れませんが、受験生としてはそれでは困ります。
残った未習の部分を入試に向けて計画的に、しかも生徒が一人で学ぶのは非常に難しいし効率がよくありません。
こんな時はやはり塾が便利です。
塾は入試結果を重視するので、それに向けたノウハウも知っていますし、いつまでに何を学習しておかなくてはならないかもわかっています。
だから、一般的に塾では遅くとも三年生の夏休みまでには三年間の内容を終わらせ、残りの受験日までの日数を受験勉強に費やします。
このように十分時間をかけて入試に向けた準備ができるので、目標校に合格する可能性は高まります。
このように学校任せでは間に合わない受験勉強の対応として塾は有効です。
ただし、いくら入試対策ができると言っても、あまりにも残り時間が少なくなってしまえば、それは物理的に非常に困難になります。
受験対策は早ければ早いほどいいです。
この点をお考えの家庭は、早目に相談してください。
できれば、二年生のうちに。
学校で勉強できないときの第二の教室として
今回、コロナ禍で学校が一斉休校になり、生徒たちの学習が滞ったとき、学校の通常授業以外に学習のアクセスできる生徒とそうでない生徒の間に教育格差が生じたと言われています。
コロナ禍でなくても、教育の手段が一つしかないというのは心もとないものです。
そんな時、塾という選択肢を持っていると勉強の保険の一つとなります。
また、家庭の事情(例えば今回のコロナ禍での自主休校)や病気や学校の人間関係などによる不登校で学校に行けない生徒もいます。
そのような時にも、塾というもう一つの居場所があれば、子供たちの安全を守り勉強を継続させることができます。
特に個別指導塾は、個人一人ひとりの事情に合わせてくれるところが多いのでお勧めです。
不登校対策として保健室登校などもありますが、こちらは勉強を教えてくれるわけではないので、勉強を維持して学校に遅れないようにするには塾の方がいいでしょう(とは言え、それぞれ事情が違いますので一概には言えませんが)。
学校という勉強のチャンネルが失われたときは、少しでも早く(もしくは失われる前に)塾を選択肢の一つとしてお考えいただければと思います。
有益な情報や良質の問題集が得られるため
次に塾のメリットとしては受験や勉強に対する豊富な知識や情報量でしょう。
毎年、入試の傾向を分析し対策を練ります。
定期テストでも点数が上がるように、勉強のポイントやコツなども教えてもらえます。
これは学習に特化した機関だからこそできることです。
特に現在、学校教育は大きな転換期に当たります。
これまでと教育の内容、方法、そして評価がかなり変わってきています。
親御さんのころのことを考えて勉強や受験を考えていると、いろいろ困った事態に陥るかもしれません。
そうでなくても、多くの情報が得られ対策が取れるということは、現代の教育(社会)においてかなり有利に働きます。
こういった情報は学校だけでは得られにくいものです。
また、塾で使用している教材も書店で販売されているものとは違い、良質のものが多いと言えます。
説明がまとまっていて分かりやすいテキスト、問題量と種類の豊富な問題集、いろいろなレベルの生徒に合わせた教材など、塾でしか手に入らないものが沢山あります。
これらを利用することで効率のよい勉強ができます。
このように一般にはなかなか分からない情報、適切で良質の教材を手にできるというのも、塾に通う大きなメリットになります。











学校の勉強の補習や先取りとして、勉強が分からなくならないようにして成績を上げる以外にも、塾には様々な利点があります。
塾は公教育ではないので、必ずしも行かなくてはならないものではありません。
しかし、行った方が良い場合もあります。
だから、生徒や家庭の状況をよく考え、塾のメリットも考慮して、本当に行かなくてはならないのかどうか判断するといいと思います。
必要なければ無理に行く必要はありません。
今回、塾に行く理由をいくつか挙げましたが、もう少しありますので、こちらは後日お話します。
塾選びも含めて、塾に行かせるかどうか悩んでいるときは葛西TKKアカデミーまで気軽にご相談ください。
喜んでお力になります。
ただ、一つ言いたいのは事態が悪化する前に何らかの対策を立てた方がいいです。
その点も合わせてご連絡いただければと思います。



























2021.11.01
来年度から始まる新教科「公共」って何?

学習指導要領が新しくなり、勉強の内容も入試の方法も大きく変わっています。
新しい変化は勉強に限らず、課外活動や学校生活にまで及びます。
そんな教育改革の時期にコロナ禍が重なり、現場の教師や生徒は大混乱。
そして、この変化は今後も段階的に進みます。
今回は来年度より新たに実施される必修科目「公共」に注目してみたいと思います。










この必修科目「公共」は「現代社会」の廃止に伴い新しく設置されました。
この科目では、社会に出たときに必要となる基本的な知識や現状を知り、現実の社会で直面する課題にどう取り組むかと考えます。
裁判や選挙を授業の中で実際に模して体験し、政治や社会への参加、働く意義、安楽死問題など当事者の立場で捉え多面的に学習します。
このような性質を持つ科目なので、授業の内容もこれまでの知識主体暗記型の勉強とは大きく異なります。
単に用語や経緯、考え方を解説し記憶させるだけではなく、「どうしたらワークライフバランスが取れるか」「政権にはどのような政党の組み合わせが望ましいか」などこれまでの「現代社会」にはなかった思考力が求められる内容や、テーマに基づいて生徒たちが考え議論ができるような内容となっています。
こうして現代社会の課題に取り組み解決できる人材の育成を目指し、自己と社会との関係を理解し主体的に社会に参加し、他者と協力してよりよい社会ができるようにします。
学習活動としては、実際にインタビューをして地域の課題を探り、問題解決に向けて請願書を書いてみるなど実践を伴ったものとなっています。
その際、情報収集や処理、プレゼンテーション作成に当たっては学校のコンピューターなどの設備を利用し、生徒が主体的にICTなどを活用できるようにします。
当然、その際には情報モラルやメディアリテラシーについても指導するようで、高校教育のみならず日本の教育全体で活発に導入が進められているITC教育との連携が期待されています。










このように生徒が主体的に考え、自分たちの意見を発表させる機会が増えることが予想され、それは現在文科省が推し進めているアクティブラーニングの流れとも合致します。
先ほど触れた模擬裁判や模擬選挙など生徒たちに実際に体験させるだけでなく、討論やディベート、プレゼンテーションや外部への発信など、かなり時間のかかる活動も含まれ(特にこのような活動に不慣れな生徒たちがどれだけこなせるかは大きな疑問として残りますが)、きちんと与えられた期間内に全て学習できるのか心配です。
これだけ濃い内容ですので全てに触れることは不可能と思われますので、恐らく学校側がカリキュラムにおいて学習内容の取捨選択をするのではないかと思います。
これらの学習内容の選択に加え、担当教員を始めとする学校側の提供できる教育の質によっても、生徒が何をいかに学べるかが変わってくると考えられます。
つまり、学校によって教育のムラに差ができ、同じ「公共」の単位を取得しても、学校によって生徒が身に付けたスキルに大きな違いが生じると思われます。
教育の平等性と公平性に疑問が抱かれます。
特にアクティブラーニングの導入は教える側の技量によって、生徒の学びにこれまで以上に差が生じることから、生徒の学力が学校で決まるという命題がますます明確になっていく気がします(これは新しい教育全体に言えること)。
また、外部のリソースへのアクセスが可能かどうかでも、生徒が学べる内容に差が生じるでしょう。










このような「公共」の特性を鑑みるに、単純にペーパーテストで答えがあっていればマルという、これまでのような評価法はこの科目には馴染まない気がします。
プレゼンテーションや授業外での活動、個人個人の思考(意見は個人の自由であり明確な正解はない)をどうすれば公平に評価でき数値化できるのでしょうか。
生徒たちの成績を数字をもって決めるという、これまでの古い評価法はそのままで、でも、学習内容はどんどんそれに合わなくなっている。
この矛盾をどう解消するかが一つの課題であり、現在進行中の教育改革の成否に大きく関わる問題だとおもいます。
アクティブラーニングの評価は相対的なものではなく絶対的なものが望ましく、公正な判断のできる裁定者の主観で判断するのがベストでしょう。
しかし、この方法ではどうしても公平性に欠けるという指摘は免れないでしょうし、結局、試験などの序列を要求される教育体系においては上手くいかないでしょう。
結果として、妥協的なものとなり、文科省の掲げる理想には届かず、かと言ってこれまで暗記型教育が担保していた教育水準にも届かないという事態が起こるのではないかと危惧しています。










指導要領の改訂により「公共」の他に「情報Ⅰ」「言語文化」「地理総合」「歴史総合」「総合的な探求の時間」など新しくできた必修科目(選択科目も加えるとかなりの量となります)についても後日触れたいと思います。
「公共」を含め必修となる科目は当然大学入試でも出題される範囲で、そうなるとやはり教育を提供する立場の者はもっとしっかり考える必要があります。
教育は今、激動と混乱の時代を迎えています。
落ち着くまでには数年から何十年かかるかもしれません。
しかし、その間にも多くの生徒が教育を受け、例えそれが不十分な内容であっても、彼らには他に選択肢はないのです。
そして、十分でない教育であっても彼らはそれを基に受験を闘い、将来の人生に向けて歩んでいかないといけないのです。
人の人生を左右する大きな課題、その意味を自覚し文科省を始めとする日本の公教育は、責任ある教育の提供にいそしんでほしいと思います。



























2021.10.31
英語の定期テストでいい点を取るためにどのような勉強をすればいいのでしょうか。ポイントをいくつか挙げてみます。

生徒の中で苦手が多い教科の一つが英語です。
小学校の英語活動のような、英語を使ったゲームや挨拶などの簡単な会話ならば楽しく苦痛でもないのですが、中学に入り文法などを始め本格的な「勉強」となった場合、感覚ではなく理詰めで考えなくてはならず(一般の中学の授業がそのようにこれまでデザインされていたからなのですが)、難解な暗号解読のようになり感じられ、その出来不出来が即座に数字となって評価される。
そして、その数字で自分の人格すら判断されてしまう。
そうやってレッテルを張られれば、楽しみはすぐに消し飛び頑張ろうという気力さえなくなることもあります。
そうならないように、生徒が英語に興味を持ち楽しみながら学べる授業を葛西TKKアカデミーでは目指しているのですが、現実に学校という存在がある限り、なかなかそのような理想的な授業も行えず、妥協して学校の勉強に即した授業になってしまうのが悩みです。
そこで今回は学校の定期テストに向けた英語の勉強法についてお話します。









勉強は千差万別、一人ひとりに適した方法があり、万人に通用するものはありません。
だから、個人個人に合わせて勉強を考え教えていかないといけないのです。
しかし、個々の事例を上げればきりがないので、ここでは一般論としての勉強法を紹介します。
これでうまくいかないからと言って心配する必要はありません。
その時は自分に合った勉強方法を見つければいいのです。
その際は葛西TKKアカデミーが力になりますので、是非、ご相談ください。
英語は毎日触れ、慣れることが大事
外国で生活をした経験がある方なら分かると思いますが、言語は毎日使っていないと驚くほど忘れてしまうものです。
海外の生活が長いと、ある日、自分の言いたいことが日本語で出てこないことがあります。
逆に日本に帰ってしばらくたつと、海外で生活していた時は何の問題もなく使えた英語が口から出てこない。
この傾向は特に子供に強く、ちいさい子供は言葉を覚えるのが早いですが、忘れるのも早いです。
つまり、言語学習では毎日その言葉に触れることが大切です。
英語を日常で使う機会の少ない日本では、生徒たちが自分から積極的に英語に触れようとしないといけません。
幸いにして現在はYouTubeやその他動画サイトなど、その気になれば英語に触れる機会はたくさんあります。
DVDやブルーレイで映画などを見るときにも英語の吹き替えや字幕を付けることもできます。
そうやって英語を聞く場を設けてください。
最初はよく分かりませんが、映像を見れば言っていることがなんとなくわかってきたり、単語をいくつか聞き取れたりできるようになります。
そうやって聞き取りが少しずつできるようになると、英語を聞くのも楽しくなります。
基本文で覚える
英語を勉強するとき「単語を覚えさえすればいい」という人がいますが、これは間違いです。
言葉は単語が単独に漂っている訳ではなく、単語同士が有機的につながり、文脈において的確に使われなくてはいけません。
つまり、文となって初めて言葉は意味を成してくるのです。
単語だけ覚えては使い方が分かりません。
だから、英語を勉強するときは単語で覚えるのではなく、文で覚えることをお勧めします。
文の方が長いので、これは効率が悪いように思えるかもしれません。
でも、人間の脳を考えると、脈絡もなく単語を覚えるよりも、他と関連付けて、それをヒントに覚えていく方が覚えやすいです。
このような基本文をたくさん覚えることが英語の理解を深め、実際に使える英語につながります。
基本文は簡単な言葉で作って構いません。
大事なのはポイントが分かる分の構造です。
「この分から、英語の過去形はこう作ればいいんだ」と理解してくれればいいです。
こうして基本文を身に付けたら、後はその中の単語を置き換えるだけで表現の幅が広がります。
文法用語は極力避ける
英語を勉強するとき、学校の先生の中には言葉の意味も十分に説明せず、やたら文法用語を使う人がいます。
これは教える方が楽なだけで、学ぶ側が決して簡単という訳でもありません。
むしろ、言語とは別に余計な用語を覚えなくてはいけないので、人によっては余計に混乱するかもしれません。
しかも、運の悪いことに英語で使っている文法用語の中には、国語の文法用語と同じものがあります。
しかし、日本語文法と違い国語文法は母語話者が自分の言葉を分析するために用いられるものなので、同じ用語でも意味が違ったりします。
これも混乱の原因となりえますので、できれば文法用語に頼るのは状況をよく分析してからにしましょう。
生徒の中には文法用語を聞いただけでアレルギーを起こしてしまい、「もう難しい、分らない」と思い込んでしまう者もいます。
特に子供の場合、その心理状況が学習に与える影響は大きいので注意が必要です。
本分を繰り返し読む
特に定期テストという観点で考えるなら、基本はやっぱり教科書です。
だから、教科書をしっかり勉強しなくてはなりません。
その際、色々理屈を考えながら分析しながら英語を科学的に理解するのもいいですが、言語という性質を考慮するなら「読む」ことは基本でしょう。
声を出して読めば(より多くの間隔を使うので)単語やいろいろな表現を早く覚えることができます。
その時注意しなくてはならないのは、発音をいい加減にしないということです。
あいにく日本の英語教育は発音を疎かにする傾向がありますが、人間の思考は脳内で音で行われていることを鑑みるならば、きちんと教え学ぶべきです。
そして、最初はよく分からないかもしれませんが、何回も何回も繰り返し読んでいくうちに、不思議なことに、だんだんと分かるようになってきます。
「読書百遍自ずから知る」とはよく言ったものです。
やっぱり学校のワークと教科書
定期テストでは多くの問題が教科書やワークから出ます。
そして、これらは事前にやれば解き方が分かるし、答え合わせをすれば確認もできます。
一回やったら間違ったところだけをもう一回やる。
これを繰り返し、全ての問題が丸になるまで頑張りましょう。
これでテストの半分以上は取れるようになります。
しかし、多くのできない生徒はこれをいい加減にやっています。
面倒くさいからと言ってきちんと問題を解かず、答えを写すだけ。
形式上は丸がついてやったように見えますが、結局何も身に付いていないので、当然テストでは解けません。
更に、高校入試では中学三年間の勉強が全て対象となるので、ここできちんとやらないとまた同じことを勉強しないといけません。
結局二度手間で、長い目で見るならやはり、ごまかしの勉強はすべきではありません。
後でもっと面倒くさいことになります。
勉強はテスト前にやるのではない
最後によくいるのが、テスト範囲が発表されるまで勉強しない生徒です。
「範囲が発表されないと何を勉強していいか分からない」ということらしいですが、そんなことはありません。
前回のテスト範囲の次から普通出されますし、今やっているところまでは確実にテスト範囲になります。
だから、発表されなくても既にやってしまうのがいいです。
早く課題を終わらせれば、その分学習内容の確認とテストの準備に費やす時間が増えます。
そうすれば、成績もきっと上がるでしょう。
わざわざ待つ必要はないのです。
毎日の余裕のあるうちに勉強に取り掛かり、ゆとりを持ってテスト勉強をすればより効率よく勉強が身に付きます。











今、テスト期間の学校があります。
もう少し後の学校もあります。
いずれにしても定期テストは必ず行われるので、それにどう対処するかが大きな分かれ目です。
英語ということで話しましたが、今回のチップはほかの教科でも通じるものがあります。
テスト頑張ってください。
すこしでも勉強に困ったときは、気軽に葛西TKKアカデミーにお知らせください。
必ず皆さんのお役に立ちます。



























2021.10.27
コロナの影響でいじめが減少、そして自殺、不登校は増加?!子供たちの精神状態も不安定に。

文科省によると、「問題行動・不登校調査」でいじめは前年度より前年度より15.6%減少したそうです。
いじめの件数の減少は7年ぶりで、その要因としてコロナウイルスが指摘されています。
一斉休校で授業日数が減り部活も制限された結果、生徒間のコミュニケーションが減ったことがいじめの減少につながったと分析しています。
「冷やかし、からかい、悪口」と言って一見ふざけている、または軽い気持ちでのいじめが一番多くなっています。
そして、今話題のSNSを通したいじめも過去最多となりました。
その一方で、不登校による欠席をした生徒数も毎年増え続け、こちらも今年が過去最多となっています。
こちらの要因としては、コロナ禍による休校などで日常生活に制限が加えられたことによるストレス、生活リズムの乱れが考えられています。
外出の自粛が求められ、自由に遊びに行けないので家に閉じこもり、暇を持て余してゲームをしたり、動画を見たり、友達とSNSをして、夜遅くまで起きていたり、中には気がついたら夜が明けてしまったなどということになってしまう。
結果、昼夜が逆転し昼間は眠いのに夜は目が冴えて眠れない。
こうやって、昼間に学校に行くことさえ困難となり、とうとう不登校になってしまうなんて例は枚挙にいとまがありません。
学校に行っているときは否応なくいろいろな生徒に会わなくてはならず、中には自分の苦手としている生徒とも会わないといけない。
しかし、幸か不幸かコロナ禍で学校に行く機会が減ると、当然嫌な生徒たちとも会わないで済むので、学校でいじめにあっている生徒には好都合なのかもしれません。
しかし、永久に学校に行かないわけにもいかず、登校しなくてはならない日が来ます。
そんな時、もう体が無意識に反応し、頭ではいかなくてはと思いつつも、頭痛や腹痛が起きて学校に行くことができなくなります。
休んでいいとなると治るのですが、また行くとなると病気になる。
このように不登校となる生徒も多いようです。









コロナ禍で在宅期間が伸びると、親との接触の機会も増え、親子が互いに緊張とストレスを感じることが多くなってきているようです。
それを反映してか、小中高生の自殺は前年度前年度の317人から大幅に増え、415人となり調査が始まって以来最多となりました。
理由は家庭不和や親からの叱責、学業不振、進路の問題などがあり、先ほど述べたように、コロナ禍による家庭での時間(テレワークや自主休校など)の増加が子供たちの自殺を増幅させたのではないかと考えられています。
また、不登校の児童生徒も増え合わせると20万人に迫る勢いで、8年連続して増加しています。
そのうちの55%は90日以上学校に行かない、深刻な状況にあります。
これまでのいじめや学校に馴染めないなどの理由に加え、感染を恐れ「感染回避」を理由に休んでいる生徒も今年はたくさんいます。この感染回避を理由に30日以上学校に行かなかった子供たちは3万人とかなり多くなっています。
学校に行くこと自体が減ったのに加え、例え登校しても人との接触が制限されたりして、子供たちは友達などの人間関係を構築しずらい環境にあり、悩みや苦しみを打ち明けたり共有できる存在がいないのも、子供たちの精神を守り安らぎを与えにくい理由になるでしょう。
これまでのように決まったリズムで生活できず、コロナ禍によりSNSやゲーム、動画などの時間が増え、当然とされる日常生活が過ごせなくなる事例も多く報告されています。
このように、コロナ禍は子供たちの物理的距離を開き、いじめは減少させたが、彼らをより孤独にさせたり、精神的ストレスをリリースさせる機会を減らしたので自殺と不登校は増加したと文科省は考えているようです。










この手の調査は表面に現れにくい問題も多く、その結果をそのままうのみにすることはできませんが、一つの示唆を与えてくれます。
子供たちとの接触においては、コロナ禍が彼らの心や体にどのような影響を与えているかを十分に考慮する必要があるでしょう。
とは言え、ここに出てきている数字は「学校が認知したもの」に限られているので、「認知されないもの」、または「認知されていても隠蔽されたもの、重大と見なされていないもの」があると思って、その修正を加えなければ現実は見えてこないかもしれません。
例えば、SNSの誹謗中傷は本人や大人の知らないところでどんどん進行している可能性があります。
葛西TKKアカデミーは子供たちを守りたいと思っています。
学校の制約下で悩み苦しんでいるならば、葛西TKKアカデミーが安心して彼らの心を開ける場になります。
勉強のことは心配しなくても大丈夫です。
葛西TKKアカデミーが何とかします。
でも、失われてしまえば命は戻ってきません。
その前に何とか思いとどまれるように、希望など与えられればと願っています。
傷ついた心も、癒えるには時間と労力が必要でしょう。
そのような場面でも葛西TKKアカデミーがお役に立てればと考えています。
コロナ禍の状況では、学校で健全な人間関係は築きにくいかもしれませんが、そんな時は気軽に葛西TKKアカデミーにご相談ください。
子供たちのより良い日々のために。



























2021.10.16
テストや問題集は自分のできるを確認するため?いえ、自分の何ができないを知るため!このパラダイムシフトが勉強を変える。勉強が苦手な生徒、時間の少ない受験生にお勧め!

皆さんは勉強でテストや問題集をどうしてすると考えますか。
多くの人は自分が何点取れるか、どれだけ丸がもらえるかを気にします。
自分の実力の確認ですね。
「○○点取った!」「丸が○○個もらえた!」と一喜一憂します。
結果が良ければそれで気分が良くなり満足、悪ければがっかりして悲しんで終わり。
それも一つの見方ですが、このテストや問題集との向き合い方をちょっと変えると、学習が変わってきます。
これは勉強が苦手な生徒、入試で時間のない受験生にお勧めです。










テストや問題集は「何ができるか」を知るためでなく「何ができないか」を知るため
先ほど述べたように、多くの生徒はテストの点数や問題集の丸の数を気にします。
これは今の自分の実力を示す指標になり、周囲の人間もこの指標で生徒を評価するからです。
しかし、勉強はそこで終わりではありません。
勉強は生きている限り続くとも言えますし、短い期間に限ってもゴールはその後にあります。
例え今、良い結果が出せなくても、勝負は一番最後の入学試験と考えるなら、それまでに十分な力をつければいいのです。
逆に、ここで終わってしまえば、それ以上自分の力を伸ばすことができる、最後の最後で泣くことになります。
だから長い目で見て、今の失敗(間違いやできない)を成功(分かる、できる)に導くことが本当の勝利への道となります。
そう考えるなら、テストや問題集は終わりではなく、むしろ勉強の始まり、きっかけだと思ってください。
テストや問題集をすることによって、自分に何が足りないかが分かります。
そうであるなら、その足りないものを集中して勉強すればいい。
やみくもに一から順に全てやらなくてもいいので、勉強としても効率のよい方法となります。
だからこそ、入試を控え時間が残り少ない受験生にもお勧めするのです。
失敗から学ぶというのは、漠然と勉強するより学習効果が高いと言われています。
それは、失敗と言う経験が脳により大きな刺激となり、そこから学んだことはより強い印象として残るからです。
記憶は「回数×インパクト」です。
掛け算の九九や年号など意味の薄い数字の暗記も回数を増やすことで覚えることができます。
また、一度だけでも交通事故のようなトラウマ級の場面を見てしまえば一生忘れることができなくなることもあります。
テストなどでうまくいかなかったという経験も、エピソード記憶となり、脳へより大きな刺激となるので、学習の習得のチャンスです。
だから、間違いから学ぶときは印象が弱くなる前に、できるだけすぐに勉強に取り掛かった方がいいです。
失敗は成功の基。
こうして勉強はあらゆることを学びのチャンスにすることが一つのコツです。










自分の置かれた現実に目を背けず前向きに勉強できる強さ
勉強が苦手な生徒は、テストや問題集が終わったら、その開放感ですぐに遊びに行ってしまいます。
でも、テストや問題集を有効に利用すれば、学びのチャンスは非常に大きいのです。
実はできる子は、このことを知っており、失敗から学ぶので自分の実力を伸ばすことができるのです。
とは言え、自分のできないことを直視することはあまり気分のいいことではありません。
できない事実を見ないで、知らないふりでごまかして何もしない方が気が楽です。
しかし、それでは失敗は失敗のままで、何も学べず同じ失敗を繰り返すだけです。
そうならないためにも、自分の置かれた客観的現実を受け入れなくてはいけません。
でも、これは自分で自分の欠陥を認めるようなもので、自尊心(特に思春期の生徒はこれが非常に重要で)を傷つけ辛いので、生徒はなかなかやりません。
だからこそ、周囲のサポートが大きな意味を持ちます。
悪い結果に対して避難しても何の得にもなりません。
かえって勉強をしなくなります。
「間違えれば怒られる」とインプットされれば、「間違えないために勉強する」ではなく「間違えを認めないために答えない」なります(自分のプライドで「できない」だけは認められない、答えなければ「できない」ではなく「言わない」だけで自分のプライドは守られる)。
これでは本人は勉強からますます遠ざかってしまいます。
最初は間違えが沢山あり、勉強しなければならない内容もたくさんあるでしょうが、それは徐々に減り、ある程度やっていくとどんどんできるようになります。
だから、そうなるまで本人の心が折れないようにサポートしましょう。
この苦難を乗り越えてできるようになると自分に自信がつき、逆に自分から進んでこの勉強法を行うようになります。
大事なのは周囲の励まし。
自分にはまだ可能性があると感じさせ、やればできるという自信と確信を持たせることです。
これは周囲の人間の対応で大きく変わります。
テストや問題集を終着点ではなく、むしろ出発点と考えるなら単なる非難ではなく、結果を受け止め、どうしてそうなったか調べ、これからどうしていけばいいかを一緒に考えてあげるべきです。
勉強はよく分からないというのであれば、ここは私のような専門家にお願するのもいいと思います。
親が全てする必要はありません。
適材適所、自分のできる役割をこなせばよく、足りないところは外部に助けを求めてもいいと思います。
本来子育ては親だけがするものではなく、親せきや近所の大人たち、先生やその他の先輩たちなど、多くの人々と協力してやるのがふさわしいと思います。
こうすれば自分一人で子育てのプレッシャーを受ける必要もなくなり、親としても精神的余裕が生まれ、そうなればもっと冷静な判断もできるようになります。










時間のない受験生もテストや問題集を上手に利用し、効率のよい勉強を
今、受験勉強で大変な生徒もいるでしょう。
この時期であればもう基礎固めは完全に終わって、本番に向けた応用問題に取り掛かっていないといけません。
しかし、自分はどうしても不安だという人も多いでしょう。
こんな時、教科書や参考書を開き、最初のページから順番にやっていっては時間が足りなくなってしまいます。
そんな時もこれまでやったテスト、模試、問題集、ワークなど、実際にやった問題集を取り組むのがいいです。
受験生であれば特に、過去問を集中的にやるのが一番。
過去問は実際に入試で出された問題であり、出題者も真剣に考え抜いた良問が沢山あります。
そして、実際に出たということは、またに多様な問題が出るということでもあります(過去に出た問題と同じような問題が出た例はいくつもあります)。
過去問を解くことで勉強をより深めることができるし、そこから学ぶことも多いのです。
そして、過去問をやって事前に失敗していれば、本番では失敗からの教訓を学んでいるので、気づき間違えることはなくなります。
だから、過去問や模試の問題を解くことは、この時期の受験生にはお勧めです。
しかし、よく聞くのは「自分はまだ準備ができていないから、先ずは教科書や参考書をやって、それから確信のために過去問をする」と言う意見です。
でも、もうそんな時期は過ぎ、今は時間との勝負です。
悠長なことはやっていられません。
だから先ほど述べたように、過去問を自分に何ができるかを知る指標にするのではなく、自分に足りないものを見つけ、それを補うためのきっかけにするのがいいです。
こうすればできないところだけ(できているつもりでも実は身に付いていなかったところも分かります)を勉強するので時間の節約になります。
実戦を通して学ぶのです。
過去問を20回やれば、たいていの分野は出尽くすので、全ての範囲のフォローになります。
少なくとも10回(入試問題や模試の最近の3年分)はやってほしいです。
これだけやれば自分の勉強の穴が分かり、後はそこだけ確認すればいいのです。
最初はきついかもしれませんが、ある時期を過ぎるとだんだんできるようになります。
それまで自分を信じ、根気強く頑張ってほしいです。
そして、ここでも周囲のサポートが大きくものを言うので注意しましょう。










このようにテストや問題集に対する考え方を変えると、そこには学びのチャンスがたくさん存在することに気づきます。
結果が悪いということは「学ぶチャンスが多い」ということ。
結果が良いということは「学べるものがない」ということ。
そのように見直し、テストや問題集をやった結果のマイナスをプラスに転じられるような勉強をしましょう。
そうすれば、学習と定着が促進され、生徒たちの実力も延びていくことと思います。
勉強に関して困ったことがあればどんなことでも構いません。
いつでも気軽に葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
一緒になってどうすればいいか考えます。
葛西TKKアカデミーはいつでも、全ての生徒の力になれることを望んでいます。




























2021.10.13
記述問題をあきらめないで!実は知らなくても解けるサービス問題もあります。部分点があるかもしれないので、記述で白紙解答はやめましょう!

文科省の教育方針が変わり、入試や学力テストなどでも記述問題が非常に増えています。
それも国語だけではなく、五教科全てにおいて記述問題が目立って増えています。
しかし、記述問題を見ただけで、「もうだめだ。できない。あきらめよう。」と思って、問題すら見ずにやめてしまう生徒がとても多いです。
でも、実は記述問題は簡単に答えられるものが多いのです。
そして、選択問題のように0点か100点かの問題とは違い、部分点があります。
特に入試などの1点が合否を左右するような場合、この部分点が大きく結果に響いてくることもあります。
書かず白紙なら0点ですが、書けば1点でももらえる可能性がある。
ならばやらない手はありません。
少しでも結果を出したい、点数を伸ばしたいと考えるならば、記述問題をやりましょう。
しかも、コツさえ分かってしまえば、意外とすらすらと答えられます。










多くの生徒は記述問題が苦手と言います。
でも、それは文を書くことに慣れていないからで、多くの場合はある程度は書けます。
ある程度書ければ部分点がもらえるので、記述問題はそれで十分です(記述問題は満点を狙うのではなく、部分点を狙う問題です)。
そして、中には予備知識が必要なく、あまり深く考えなくても答える問題もあります。
自分の勝手な「記述問題は難しい」と言うイメージだけで、問題も見もしないで飛ばしてしまうのはもったいないです。
先ずはチャレンジしましょう。
そして、問題に慣れましょう。
つまり、テストを受けるまでにポイントをしっかり理解し実際に書きながら練習するのです。
ここで大事なのが「実際に書く」ということです。
多くの生徒は日本語なのだから書くのは簡単と考えています。
面倒くさがって書かない生徒が多いのですが、いざ書いてみると表現や語彙など適切に使われていない場合が多々あります。
母語だと高をくくっていると、意外と書けないものです。
記述問題をするときは頭で考えて「そうか、そうか」ではなく、実際に書くことが重要です。
日常生活の中でもきちんとした文を手で書く機会が減りつつある現在、受験勉強として時間を取ってしっかり自分の手で書いてください。
先にも述べましたが、文字にしてみると意外とうまく書けず、後で読み直してみると(できれば誰かに読んでもらって指摘してもらうといいのですが)意味が全く分からないなんてこともあります。
最初は模範解答を写すだけでも構いません。
そこから「こうやればいいのか。」「こう書けばいいのか。」と考えながら繰り返していると、だんだんコツが分かってきます。
また実際に書く重要性は書き方を身に付けるだけではありません。
以前指摘したように、最近の生徒は書く「力」、能力ではなく本当の体力としての「力」が衰えています。
すぐに疲れて書けなくなる。
力が無いからしっかり書けず、薄くミミズのはったような字になり読むことができない。
書き続けることに耐えられる力が無いので、すぐに疲れ精神的にも嫌になり集中力が続かない。
運動と同じように肉体トレーニングとしての意味合いもあります。










記述問題など文章を書く方法に関しては別の記事で既にふれたことがあるので、ここでは記述問題を答えるコツをいくつか話しましょう。
先ず、記述問題は難しいことを高尚な表現で書く必要は全くありません。
分かり切ったことをつまらない表現形式でシンプルに書けばいいのです。
文学作品のような芸術的な書き方はしなくていいです(解答に芸術点はありません)。
必要な情報を正確に伝えられればいいのです。
本当に「静岡のお茶の生産量が増えた。」とか「日の出の時刻が早くなった。」など、問題が求める内容をしっかり押さえていれば、極めてシンプルな構成の短い文でいいのです。
しかも、特に図表を使った問題は資料から読み取れる明確で単純な事実だけを聞かれることが多いです。
「日本各地のお茶の生産量の変化を示したグラフから読み取れることを書きなさい。」なんて問題であれば、グラフから生産量の変化がどうなのかだけ読み取り、「静岡のお茶の生産量が増えた。」などと書けばいいのです。
問題を複雑に考えすぎない、答え方を難しくしようとしない。
これで答えられる問題が結構あります。
これは図表さえ正しく読み取れれば勉強していなくても答えられるサービス問題で、これは是非取りにいきましょう。
もう一点だけコツを述べましょう。
問題に出てくる図表や資料は意味なく出されている訳ではありません。
何らかの意図があり、出題者は解答者がその意図を読み取り求める解答をしてくれることを期待しているのです。
だから、なぜこの資料があるのかを理解することが大事です。
この資料のどこの部分を使って答えさせたいのか、この資料が解答にどのようにつながっていくのかが分かれば、答えを書くことも簡単です。
例えば、グラフの変化から今後どのようなことが起こると予想できるか、資料のどの部分がきっかけで事件が起きたのか、この実験は何を知りたいから行ったのかなど。
解答者に資料から何を分かってほしいのかを出題者の立場で考えられるようになると、資料を見たときに「あ、これを言ってほしくてこの資料を出したんだな。」と分かってきます。
この部分は慣れも必要なので、やはり記述問題にたくさん当たること(質より量)が大切です。










以上の点を踏まえて、書き方をしっかり身に付け、後は繰り返し練習すれば記述問題は驚くほどできるようになっていきます。
短期に得点を上げたいと考えるなら、記述問題に着目するのもいいかもしれません。
どの問題もそうですが、最初の見た目に騙されてやる前から問題を諦めるのはやめましょう。
やってみると意外と簡単だったということはよくあります。
逆に点数の低い生徒は、戦う前から既に白旗をあげている人が多いように思えます。
頭がいい悪い以前の問題、心構えの問題で、やる前から自分の負けを認めている。
原因はその生徒のメンタル構造によるのですが、この点はまた別の記事で。
記述は難しいとよく言われますが、実は記述はそれほどでもありません。
むしろ勉強で覚えていなくても、資料の読み取りだけでできてしまうラッキー問題であることの方が多いのです。
なぜなら書き方は自由だし、書けば何点かもらえるかもしれないし(完璧な解答でなくてもいい)、図表や資料に書いてあることを素直に読み取れば単純な答えでいい場合もあるからです。
食わず嫌いはやめて、チャレンジしてみましょう。
分かってしまえば、どんどん解けるようになります。
どうしても記述問題に対する勉強の仕方などが分からないときは、葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
喜んでご指導いたします。



























2021.10.05
学校が生徒に配布したタブレット端末によるいじめで小6の生徒が自殺した問題について考えます。(その二)

以前お話したこの事件ですが、教育のICT化問題といじめの問題に区別して考える必要があると述べました。
そこで前回はICT運用の観点からこの事件の問題点は何か、防ぐことはできなかったのか検証していきました。
今回は第二弾として、この事件をいじめの問題と捉え、学校の対応などの面から適切であったか考えてみたいと思います。










先ずは事件の概要をざっと見てみましょう。
去年の11月に町田の小学6年生がいじめを苦に自殺をしました。
この小学校は20年前からタブレット端末を導入し授業や家庭学習、課外活動などに積極的に活用していて、日本の教育のICT化の先駆けとなって注目されていました。
しかし、ICTの運用にあたってはほぼ児童任せで、パスワードが全員同じであったり、IDが簡単に分かるなど、セキュリティや使用制限の面では問題が指摘されています(児童たちは容易に暴力的コンテンツやゲームなどにアクセスできました)。
実際にSNS上に特定児童への誹謗中傷が書かれ、しかも誰でも他人のIDを使ってログインできることから、なりすましによる悪意ある発言もあったようです。
今回自殺した生徒も学校配布のタブレット端末使ったSNSへの誹謗中傷が原因の一つと考えられています。
以上のような経緯から、タブレット端末を児童全員に配ることへの疑問が持たれ、GIGAスクール構想にも大きな影を落とすことから、文科省も事態を深刻に受け止め調査に入りました。
タブレット端末の使い方などICT教育の問題としての議論は前回しましたので、今回は主に学校側の対応を中心にいじめ問題として考えてみたいと思います。










このような児童生徒の自殺はこれまでも何度も何度も起き、その都度問題視されてきましたが、未だに改善されているようには見えません。
問題の起きた学校はたいてい自殺の全段階であるいじめの段階で把握していました。
しかし、そのいじめの対応は紋切り型で、例えば当事者同士を教員の前で話し合わせ、加害者が被害者に謝罪(形式的であれ)させて問題解決として終わり。
被害者がどれほどの苦痛を味わい、加害者が本当に自分の行いを理解し悔い改めようとしているかは全くお構いなし。
基本的に外部に知られないように隠蔽に走り、当事者をなだめ卒業するまで表沙汰にならないようにするのに苦心する。
このような対応が頻繁に行われます。
学校は閉ざされた空間になりやすく、外部からは何が起こっているのか非常に見えづらくなっています。
だから、「問題を解決しようとするより、卒業して無関係となるまでなんとか問題を抑え込んでので無罪放免になるのを待つ」方が楽なのでしょう。
下手にまともに受けて外部から責任追及の圧力を受けては昇進にも関わる。
そうやって問題を直視しないで、その場しのぎでごまかしてきたからこそ、いじめとそれを苦にした自殺の問題が今も改善しないのです。










今回の事件もこのような隠蔽、ごまかしが見られました。
そこにICTの利用が絡み、この小学六年生の自殺がより注目されるようになりました。
元々、この女子がいじめにあっていることは自殺の2か月前に当たる九月の段階で学校は把握(校内アンケートで発覚)していたようです。
学校はいじめを行ったとこの女児から名指しされた児童に謝罪をさせて、この問題は解決済みとしました。
そして、この女児がいじめにあっていたという事実は保護者には伝えられなかったそうです。
タブレット端末に彼女への誹謗中傷が書き込まれていたことは、何人かの友人や他の保護者には知られていたようで、学校もこの女児の殺し方と書かれたノートも保管しているそうです。
しかし、肝心の彼女の親には伝えられていませんでした。
親としては普通に問題なく学校に通っていると思っていた矢先の突然の自殺となり、そのショックは計り知れないものと想像できます。
自殺が発覚後、両親は学校に情報公開を依頼しましたが、当初は解決済みの問題と受け付けなかったようです。
その後、学校はこの両親に経緯など説明しましたが、肝心のタブレット端末に書き込まれていたという女児への悪口は何者かによって消去されていたそうです。
この点に関しては以前話したようにセキュリティの問題から誰でもSNSにアクセスでき(なりすましが横行)、学校関係者(児童、教員、保護者)の誰かがログインして削除したと思われますが、学校の説明は「ハッキングに遭い、不思議なことに彼女への悪口が消えてしまった」というお粗末なものでした。
システム上、削除された内容の復元は可能だそうですが、パスワードが共有されているので、誰が書いたかの特定まではできないそうです。
自殺してしまった児童が残した遺書が、ことの顛末を知る信頼できるの主な手掛かりと言うのはとても悲しすぎます。
自殺後、学校は女児の死亡について他の児童に明確に説明しませんでしたし、加害者への追及も行いませんでした。
それは今回の事件についえ追及することで加害者の児童も自殺することを恐れたためだそうです。
この点に関しては、被害者を守ろうとしないで加害者を守ろうとするという指摘(いじめの問題が起きたときはよく指摘されること)もありました。
保護者を集めての説明会もあったようですが、自殺した児童の親からそっとしてほしいという希望があった(これは嘘)との理由で死亡したことは伝えましたが、それが自殺とは伝えなかったそうです(今流行っているコロナウイルスによる死亡と考えた保護者もいたようです)。
また、いじめの問題は既に解決済み(実際は解決していなかったのだが)で、児童の自殺といじめの関係はないという説明も今年の三月の保護者会までしてきたようです。
このように学校は自殺とつまびらかにすることを避け、できるだけ先延ばしにしようとした姿勢がうかがえます。
そして、今回メディアを通してニュースが流れた訳です。
「一人一端末」を達成したタイミングでのこのニュースに文科省も調査に乗り出すとしています。
因みに、当時この学校の校長を務めは、教育のICT化の先駆けとしての実績が評価され、現在は区の教育長に栄転されたそうです。










いじめ問題として考えた場合、このように学校の対応は、これまで問題となった他校とさほど変わることはありませんでした。
そこにタブレット端末が絡み、タブレット端末の配布の是非も議論されるようになりました。
多くの意見では配布の中止は行き過ぎだが、何らかの制限、ルール作りやICTの扱いに関する情報モラルの教育の必要性が論じされました。
しかし、教育のICT化が人殺しに使われたのは事実です。
タブレット端末の全員配布、学校のITC化とうたい文句ばかり先走って、中身をしっかり本気で構築していないのが最大の問題点だと思います。
功を焦るばかりに、尊い児童の命を犠牲にしてしまったという自覚が文科省を始め学校教育関係者にどれほどあるのでしょうか(命の軽視は、今回のコロナ禍でも政府の対応の中に見られました)。
このような先端技術は、先生を飛び越して生徒の方が長けている場合が多くあります。
日常業務の多忙に加えてプロではない先生が教育のICT化にどれほどついていけているのでしょうか。
これは直接生徒に関わる現場には深刻な問題です。
よく考え対応していく必要があります。
そして、これまでもそうだったように、いじめと自殺の問題に対して、その場しのぎやごまかしでなく、教育者なら自分の保身よりも先に、本気で生徒と向き合い若い命を全力で守ってほしかった。
毎度のことになりますが、このような悲劇が二度と起きないように願います。
最後に、葛西TKKアカデミーは将来のある子供たちが、自分の人生をあきらめてしまうことを非常に残念で悔しく思います。
非力ではありますが、もしこちらで何らかの力になれるようでしたら遠慮なくご連絡ください。
喜んでご協力致します。
何より命が大切です。




























2021.09.30
勉強ができない子の特徴

長い間いろいろな生徒と触れていると、勉強のできない生徒の特長がいくつか見えてきます。
今回はそのような特徴をあげながらお話したいと思います。










1.質問に正しく答えない
よくあるのが質問に正しく答えないということです。
これは答えが間違っているという訳ではなく、こちらの質問で聞かれていることに対して答えていないということです。
例えば、花壇に咲いている花の本数を答えるために、こちらが先ず「チューリップは何本咲いていますか。」と質問します。
そして、咲いているチューリップの本数を答えてくれればいいのですが、いきなり全体の咲いている花の本数を答える。
確かに最終的には全体の本数を答えるのですが、今質問しているのはチューリップの本数だからチューリップの本数を答えてほしいです。
「そんな細かいことどうでもいいじゃないか。」「最終的な解答にたどり着いたのだからいいじゃないか。」という人がいるかもしれません。
でも、実はこの「聞かれたことに答える」と言うのが勉強においては非常に重要になります。
今回の例は非常に簡単なので大丈夫ですが、これから入試など高度な問題に取り組むとき、日頃から聞かれたことに正確に答える癖をつけていないと、問題で何が聞かれているのか分からず、自分の勝手な思考がどんどん進み、頭の中が混乱して問題の意味すら分からなくなってしまいます。
落ち着いて一つの質問に一つの答えを出して、一歩ずつ着実に正解に向かって解き進められるようになればこのようなこともなくなるでしょう。
これは日常の会話の中でも訓練できます。
子供に質問した時、こちらが求めている回答になっているか確認し、なっていなかった場合は注意してあげましょう。
こうすれば会話がかみ合わないことも防げます。
特に慌て者で答えをせく生徒に、質問の二歩三歩答えてしまう傾向が強いです。
じっくり会話ができるように時間のゆとりがある生活を心がけましょう。
2.ノートをきちんと取らない
次によくあるのがノートを取らないことです。
ノートを取るのは勉強の基本で、授業で習ったことを忘れないようにメモし整理し、後で見直してやった内容を確認し定着させます。
少なくとも黒板に書いてあることぐらいはノートに書くと思いますが、勉強のできない子はノートを取らないで、ただ座って聞いているだけ。
それも集中して一言一句逃さないように聞いているならまだましですが、ぼーっと聞いて結局何を話したか全く頭の中に残っていないということがよくあります。
「勉強でノートを取る」と言う基礎的なことができていないのです。
これは知らないという場合もあるでしょうが、多くの場合は面倒くさがって書かないようです。
こちらが言って何とか書かせても、日頃から書くことに慣れていないので、すぐに疲れ、ノートもまとまりがなく、あちこちに飛んだり、じがぐちゃぐちゃで本人ですら読めなかったりします。
これでは何の役にも立ちません。
また、ノートを書くということは学んだ情報を視聴覚だけでなく、手を使ってより多くの刺激と感覚で覚えるので学習内容が頭に残りやすくなります。
また、書くとき頭の中で復唱しながら書くので、先生の言ったことや書いたことへの理解が深まります。
とにかく勉強は肉体労働であり、体全体を使い、より多くの刺激を与えた方が身に付きます。
また、書くことはテストの記述問題でも必要なスキルなので、ノートを取るということはこういう点においてもよい練習になります。
3.余計なことを考えすぎ、すぐに勉強に取り掛かれない
勉強は先ずやること、やらなきゃ始まらない。
しかし、勉強ができない生徒はこの「やる」にたどり着くまでが一苦労のようです。
何も考えず言われた問題を解く、言われたところを読むなどすればいいのですが、それをする前に「なぜ自分は勉強をしなくてはいけないのか。」「友達と○○したいな。」「明日の天気はどうなっているのだろう。」と余計なことばかり考え勉強まで手が回らなくなってしまいます。
「なぜ勉強しないといけないのか。」「勉強にどんな意味があるのか。」などと言うのは特に女子に多いように見えますが、男子にもいます。
これは勉強に対する拒絶反応を正当化すべく行っていることで、明確な答えが出ないのを分かっていてわざと考えているように思えます。
こちらとしては「そんなのどうでもいいから早く勉強しない。」と言いたいところですが、「勉強するに十分な納得のいく理由が示されない限り、自分が勉強しないことは正当化される。」、そういう期待で思考を巡らせているのかもしれません。
非常に厄介で、一緒にまともに考えていたら時間が過ぎ、勉強ができなくなります。
明確な答えがあればそれで問題解決ですが、そうでないなら一度じっくり親子で一緒に話し合う時間を設けることも大事です。
4.授業の勉強で終わりと思っている
勉強は授業でやればそれで終わりで、後は勉強しなくてもいいと思っているようです。
だから、家に帰ればもう勉強はしない。
宿題も提出という体裁だけ整えて、自力で解かないで答えを写す。
しかし、授業でやった内容は一発で完全に習得できるものではありません。
学年に上がれば上がるほどそうですが、未だに小学校低学年のような感覚で、授業以外で勉強をする必要はないと考えます。
だから、次の授業までに前回学んだことがほとんど(全く?)記憶に残っていません。
勉強は積み重ねなので、前述のことをマスターしなければ先に進めないという基本的なことが分かっていない(分かっていてもそうできない)のです。
結局前回習ったことが「ゼロ」だから、もう一度やってもやはり授業だけでは身に付かず「ゼロ」のまま。
なので、何回やっても最初のところから先に進めず、いつまで経っても勉強のできないままです。
今回習った内容は次の授業までにきちんと覚える。
これの積み重ねが大きな差を生みます。
5.自分はできないと思い込んでいる
勉強できない子は自分を信じていない子が多いようです。
自分はできないんだから勉強しても無駄。
でも、これは実は勉強しない口実だったりするのです。
自分が勉強できないのは生まれながらの能力のなさが原因で、いくら頑張ったところでできないのだから勉強する意味がない。
だから勉強はしなくてもいいと自分を正当化して、勉強をやらなくてはならない圧力から逃れようとするのです。
しかも、この論法であれば勉強できない原因は自分の持って生まれた才能のなさであり、自分自身のせいではないと言えるので、あえて自分ができると信じないのです。
信じてできるようになってしまうと、今以上に勉強させられると恐れているのです。
しかし、一見正しそうに見えるこの理屈ではいくつかの矛盾点もあり、本当は正当化できないのですが、この点に関しては別の記事にて。
自分はできないと言い張って、それを口実に勉強から逃避したいので、自分を信じないようにしていると考えます。
厄介なことは、単純に信じないのではなく、自主的に信じていない点です。
前者であれば、小さな成功経験を積ませれば自信がついて、やがて自主的に勉強に取り組めるようになり、成績も上がるでしょう。
しかし、後者であれば、よほどのことがない限り、「頑張れば勉強ができるようになる」ことを受け入れさせるのは困難です。










以上、勉強ができない生徒の特長を五つご紹介しました。
もちろん、他にもありますが、今回はここまで(また機会があればいずれ)。
いずれも正すには骨が折れる代物です。
でも、生徒の心理をよく理解して個別に対応するしかないでしょう。
全ての生徒に効く特効薬はありません。
一人でどうにかしようとするとどうしても限界があるので、様々な人の意見などを参考にして指導に当たるのがいいです。
なぜなら、より多くの選択肢の中からいろいろ試して、より最適な対応策を見つけられるからです。
その際は葛西TKKアカデミーも考慮に入れていただけるとありがたいです。






























