塾長ブログ
2020.07.05
コロナ禍で受験生は大変と思いますが、確実に入試に合格するためにも高校見学に参加することは必須です。今回は高校説明会で注意すべき点についてお話します。

葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーは高校進学の相談も承ります。
今年はコロナウイルスの影響で今後の学校のスケジュールもはっきりしない部分が多いです。
学校行事の多くが中止、または縮小になり、夏休みや冬休みも縮小される見込み。
土曜登校もささやかれ、学校はコロナウイルスでの長期休校で生じた勉強の遅れを取り戻すのに必死です。
(ただし、その圧迫した学校スケジュールが生徒にどんな影響を及ぼすかはあまり考慮されていないようですが、少なくとも授業時間を確保し満たすように、数字合わせしているだけのようにも思えます。)
例年であればもうそろそろ高校の公開授業や学校見学、学校説明会の日程が発表されているのですが、今回の混乱でまだ高校側もしっかり準備ができていないところが多いようです。
夏休みは8月の2週間ほどに縮められるようなので、この間に集中して学校説明会などのイベントが行われるのではないかと思います。
このような事態になり受験生は分からないことだらけで不安がいっぱいと思いますが、自分の目標を明確にし何が必要かをしっかり理解するためにも、いい加減な気持ちでいかず、この貴重な機会を有効に活用して情報収集し、自分のものにしていただきたいと願います。








短いとは言え今年も、夏休みは高校の学校見学会、説明会がたくさんあります。
進学を控えたお子様をお持ちの家庭は、色々な高校に出向くことも多いでしょう。
今回はその時に注意すべきポイントをお話します。
1.コースやカリキュラム、卒業後の進路について確認
入れるならどこでもいいというわけではありません。
入学した後の学校生活、卒業後の進路まで見据えて学校に確認するのがいいでしょう。
資料を見てコースやカリキュラムについて分からないことは必ず確認しましょう。
授業に関するその学校の特色(単位制など)や特別プログラム(海外研修、国際交流など)も説明を受けましょう。
直接学校の先生と話すことはいろいろな意味で利点があります。
2.学校の施設や設備を確認
プールや体育館、教室の空調など、生徒が実際に学校生活を送る上で快適な環境かどうかを確認しましょう。
部活に興味があるのなら、それに関連したもの(備品やコートなど)も見ましょう。
図書館やパソコンも大事です。
特に最近はタブレット端末や電子黒板を導入している学校もあり、生徒が使いこなせるか、先生が使いこなせているか知る必要があります。
適切な進路相談ができ、そのための資料が十分整っているかも見ましょう。
特に今回の件で、学校が休校になっても授業が保障されるオンライン設備が整っているかどうかは非常に重要な意味を持つようになってきました。
あらゆる事態に対処できる環境が整っているか、ぜひ確認してください。
3.構内掲示や清掃状況を確認
掲示物や清掃状況はその学校の普段の姿を知る手がかりにまります。
掲示物がきちんと整理され見やすいか。
廊下や教室が綺麗に掃除されているか。
生徒の日常の営みが現れます。
また部活の賞状などは、その学校がどんな課外活動に力を入れているかが分かります。
4.公開授業は見た方がいいです
公開授業は学校生活の実態を知る上で役に立ちます。
公開と分かってそれ用に繕っていても、何十人もいる生徒が全てが演じることができません。
よく見るとどうしても普段の癖が出るものです。
だから、公開授業は普段の生徒の姿を見るのにはいい機会です。
そして、できれば生徒の生の声を聞いてみてください。
案外正直に話してくれるものです。
ダメ元で試してみるのもいいでしょう。
学校見学は高校を知る重要な機会です。
事前連絡すれば、説明会の日でなくても学校を見せてもらえることもあります。
後悔しないためにも学校選びは慎重にし、正確な選択をするために少しでも多くの情報を集めましょう。
特に今年のような特殊な状況においては入試の出題範囲が短くなるなど、特別な処置がなされると思います。
無駄なく準備し、効率よく合格するためにも積極的に説明会に参加し、誰でもいいので学校の先生と顔見知りになり、より多くの情報を得るように心がけましょう。





















2020.07.04
多くの学校では今月下旬に定期テストがあるようです。コロナで大変ですが、頑張ってよい成績を修めましょう。塾生でなくても大丈夫、全ての生徒のために無料でテスト対策します。
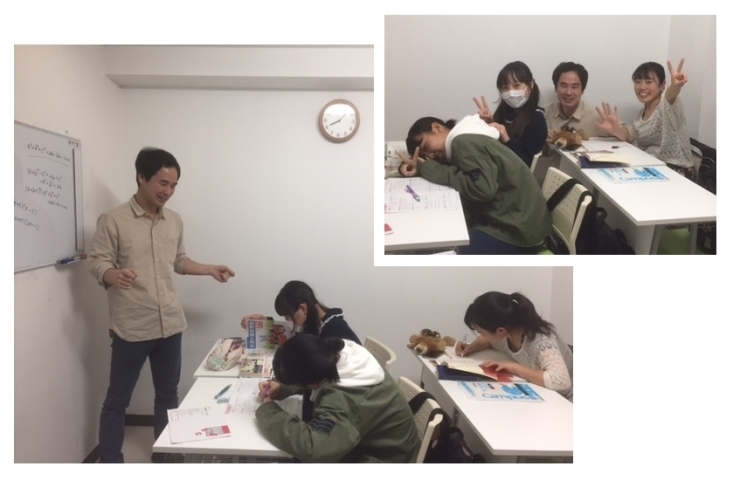
コロナウィルスによる混乱で生徒たちは非常に大変な思いをしていますが、今月下旬には多くの学校で定期テストが実施されるようです。
勉強が遅れたり、不自由な学校生活で不安なのはみんな一緒。
だから、心配しないでください。
やるべきことをきちんとやれば必ず結果は出ます。
葛西駅そば、個別指導塾葛西TKKアカデミーでは全ての中学生、高校生の力になり、生徒たちに安心と自信を持たせたいと思います。
よって、全生徒のために塾を無料開放します。
塾生でなくても大丈夫。
頑張ろうとする人は誰でも大歓迎です。
勉強に集中できる快適な環境でテスト勉強ができ、分からないときはいつでも先生に質問できます。
自分の勉強専用の部屋ができたと思ってもらえるとありがたいです。
どうか、この機会に葛西TKKアカデミーを利用してみませんか。
小規模個別指導塾なので、コロナウィルスの心配もありません。
平日だけでなく週末もやっています。
葛西駅の近くまで通うのが難しい生徒にはオンライン授業も受けられます。
ZOOMを使って自宅から気軽に勉強を教えてもらったり、分からないところを質問できます。
また、スケジュールさえ空いていれば自宅出張もできますよ。
とにかく利用してもらって、葛西TKKアカデミーの良さを知ってもらいたい、そして、一人でも多くの生徒たちの力になりたいと願っています。








コロナウィルスの長い休校が終わったら、もう定期テストの時期となってしまいました。
準備はできていますか。
今回は十分な学習ができにくい中でのテストとなります。
とても不安と思いますが、安心してください。
葛西TKKアカデミーに任せれば大丈夫。
ここでしっかり勉強すれば、定期テストも問題なくクリアできます。
葛西TKKアカデミーではテスト対策と称して全ての中学生、高校生のために塾を開放しています。
葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。
気軽に来て、勉強してください。
家ではなかなか勉強しづらいと思います。
ここなら集中してできるでしょう。
いらした全ての中学生の勉強のサポートを行います。
中学5教科全てに対応し、指導します。
分からないとき、困ったときは何でも遠慮なく質問してください。
しかも無料!!!
「学校で習ったけどよく分からなかった。」
「休んで抜けてしまった。」
「分かっているつもりだけど、確認したい。」
「学校の課題をする場所がほしい。」
「だいたい分かったから、もっと練習問題を解きたい。」
など思っている生徒は是非訪ねてくださいね。
皆さま大歓迎です。
葛西TKKアカデミーに在籍していなくても構いません。
事前連絡いただければ、席を用意して待っております。
葛西TKKアカデミーを利用して、テストでいい成績を残しましょう。
この機会をお見逃しなく。





















2020.06.30
中学生から聞きました。「学校カースト」はこうやってできる

葛西駅から徒歩3分、個別指導塾葛西TKKアカデミーは
勉強を教えるだけでなく、生徒が直面する様々な問題を考えます。
先日、生徒が「学校カースト」について話してくれました。
実際に現場にいる彼らの声なので、信憑性は高いをと考えられます。
外の人間には目につきにくいことで、貴重な話でした。
そもそも「学校カースト」という生徒間の上下関係は、特に決まった法則に従ってできるものではないそうです。
小学から中学に進学した、新学年になったなどの節目に、生徒は必死にグループを作り、みんなその中に入ろうとします。
なぜなら、その中に入らないと孤独になると思うからです。
こうしてクラスの、学校のほぼ全ての生徒がどれかのグループに所属するようになります。
これらのメンバーシップは大抵lineで行われます。
そして、メンバーの中で頂点に立つものが自然と生まれます。
偶然や成り行き、なんとなくみんながそう思うからという理由で、特定の生徒の発言力が強まりグループのトップになります。
決して財力や学力、身体的力で決まるものではないそうです。
むしろ、全体のなんとなくの雰囲気で決まります。
だから「学校カースト」の成立を阻止することは難しいのです。
こうなるとメンバーは、トップの気を損ねないことに尽力するようになります。
なぜなら、トップを怒らせることはグループからの報復、追放による孤立を生むからです。
トップを中心とした秩序が完成し、メンバーはトップの気持ちを忖度し(どこかで聞いたような言葉)組織が運営されます。
そして、トップの意に沿わない者、もしくは沿わないと思われる者は、グループ全体による攻撃対象になります。
これは事実ではなく憶測であっても行われるので、根も葉もない誤解や、陥れようとする謀略によっても攻撃されます。
攻撃は直接肉体的暴力ではなく、間接的な精神的ダメージを目的としたものになります。
lineを始めとするSNSは強力な武器で、巧みに使って集団による言葉の攻撃や仲間外れなどをします。
その内容は残酷です。
言葉があまりにも思慮なしに簡単に行きかうので、「死ね」などの言葉も簡単に使われ、より攻撃された生徒を傷つけます。
でも、気軽にひどい言葉を簡単に使うので、攻撃する方はそこまで深く考えてはいません。
つまり、無自覚にいじめをしているのです。
生徒を言葉で追い詰め、もしくは策略を張り巡らせ、例えば標的の生徒が「死んでやる。」と言うように仕向ける。
すると、「あ、そう。良かったね。いつ死ぬの。何時何分?」と追い打ちをかける。
いじめる側はある種のゲーム、遊びのつもりでしょう。
(この点は従来のいじめと共通しています)
いじめられた生徒を守るという正義感は、グループ内の空気が読めない野暮な奴となり攻撃の対象になりうる。
だから、保身のために自分も攻撃に加わる。
なぜなら、傍観するのも空気の読めない野暮な奴だからです。
攻撃を受けた生徒は逃げ場はなく、グループにとどまりいじめられ続けます。
なぜなら、グループから抜け孤立することによる不利益が学校生活に与える影響を非常に恐れるからです。
SNSという閉鎖された空間で行われるので、外部の者には気づかれず事態は進行していきます。
例え外部の目に触れたとしても、生徒は巧みに隠語を使うなどして分からないようにしています。
外部には無意味でも、グループ内では非常に意味を持つ隠語の攻撃力はとても高いです。
もちろん、SNS内のいじめが現実世界でのいじめとして表面化することもあります。




















まとめると、生徒はまずSNSを使い自主的にグループを作り加入することで学校生活の安寧を求めます。
その中で、なんとなくの雰囲気でトップが生まれ、それを中心とした秩序が生まれます。
そして、なんとなくの雰囲気でグループの馴染まないとみなされた者は、無自覚ゆえの残酷な攻撃の的となり、精神的苦痛を与えられます。
こうして攻撃する者、される者ができ、上下関係が生まれ「学校カースト」が誕生します。




















注目すべきは、「学校カースト」のトップにいても安心ができないということです。
なんとなくの雰囲気、空気でできている組織なので、なんとなくのきっかけで空気が変わるとトップも下層に落とされるそうです。
はっきりとして要因や仕組みでこうなるのではないので、誰も防ぎようはないそうです。
つまり、生徒たち自身も何でこうなってしまうのか分からないのです。
そしてコントロールもできないのです。
それは、この仕組みを支配しているのが空気だからです。
ここで述べたことは生徒の話に基づいた一例ではありますが、一考の価値はあると思います。
2020.06.27
コロナウイルス対策にマスクは必要?!でも、これからの酷暑に熱中症も心配。ということで文科省が学校向けマニュアルを一部改訂。そのポイントを見てみます。

コロナウイルスの感染リスクがゼロとならないまま学校は再開しました。
文科省の方針としては感染防止に全力を尽くしつつ学校生活を行うというものです。
そこで文科省は感染防止の具体的対策を示したマニュアルを発表しています。
学校ではマスクをする、生徒同士の間隔をあける、施設をこまめに消毒する、会話は極力避けるなど。
しかし、これから予想される猛暑に対して、これまでのマニュアルに従っていると今度は熱中症の危険が指摘されています。
そこで文科省はこのマニュアルを改訂しました。









コロナウイルスにより三か月学校が休みになり、停止していた分の授業の遅れを取り戻すべく、夏休みは大幅に短くなり(例年の半分の期間)、本来猛暑の中での授業を避けるために設けてある夏休みであった期間にも学校に行かなくてはならなくなりました。
多くの公立学校にはエアコンがなく、例えあったとしてもコロナウイルスの感染のために窓は開けっぱなしにするのでエアコンは使えそうにありません。
さらに学校にいるときは一日中マスクを着用しなくてはならず、これらの理由で今度は熱中症のリスクが高まると指摘されています。
以上の点を踏まえ、文科省は先日、この学校向けマニュアルを一部改訂しました。
そのポイントは次のようになっています。
・暑さで息苦しいときは本人の判断(先生の指示を待たなくてもよい)でマスクを外せる。
・熱中症のリスクが高い場合は、距離の確保が難しくても熱中症の対応を優先。
・登下校中は距離が十分保たれていればマスクを外してもよい。
・しかし、公共交通機関を利用しているときはマスクを着用する。
・マスクの取り外しは活動内容や子供たちの様子を踏まえて現場で臨機応変に対応する。
このように熱中症の危険があるときは熱中症対策を優先するように示しています。
マスク着用は必須ではなくなって場合によっては自ら外してよい。
マスクは飛沫感染を防ぐためのもので、十分な距離が確保でき飛沫感染の恐れがない場合はマスクはつけなくてもいいということになっています。
よって、体育の授業や部活など、体を活発に動かし多くの吸気が必要な時は、条件をきちんと守ってさえいればマスクなしで活動してもよく、熱中症防止を心掛けるようとしています。
また、状況を見ながら現場の判断で柔軟に対応することも示され、必ずしもマニュアル通りのコロナウイルス防止策を行使しなくてもよいということです。









とは言え、生徒や児童が自分でマスクをつけるべきか外すべきかを判断することは難しいかもしれません。
特に低学年の子供たちは臨機応変と言ってもそのさじ加減が分からず、つらくてもひたすら先生の言いつけを守る傾向があります。
変にすれていないので親が「マスク外してもいいよ。」と言っても「先生に言われたから。」と言って外さないこともあるでしょう。
だから、低学年生に対しては学校の先生がどういうときマスクを外していいか具体的に細かく示してくれた方がいいと思います。
また、普段からコロナウイルスだけでなく、熱中症の恐ろしさも家庭で話し合って、熱中症がどのようなものでなぜ危険か、防止するにはどうすればいいかなど、熱中症に対する知識と理解を深めていくもの大事です。
これから勉強には厳しい季節になります。
コロナウイルス対策をしながら大変だと思いますが、頑張ってください。
葛西TKKアカデミーには快適な環境で勉強ができる空間があります。
どうかこちらも利用してください。
厳しい状況で頑張る子供たちを応援し、支えてゆきたいと考えています。
いつでも気軽にお問い合わせください。
























2020.06.26
学校再開からもうすぐ一か月ですが、やはり生徒たちのコロナウイルス感染が各地で確認されています。

6月24日、埼玉県は中学生の女子がコロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。
本人は特に症状は出ていないようですが、同居している父親の感染が分かったことからPCR検査を受けたそうです。
学校での感染ではないようですが、23日まで無自覚のまま登校していたと考えると、他の生徒に感染したかどうか心配されます。
学校は本日から2日間休校するそうです。
同じく群馬県でも高校生男子の感染が確認されました。
こちらは17日から37度台の熱と喉の痛みなどの症状があり、熱はずっと続いたようです。
24日に民間検査機関によるPCR検査の結果、陽性と判明しました。
この生徒は17日から学校を休んでいるそうです。
23日県の小学生と中学生の姉妹のコロナウイルス感染が判明。
この姉妹の兄も21日に感染が確認されており、家庭内で感染したと思われます。
姉妹が通う学校は3日間臨時休校になりました。
市は独自に二人のクラスメートや担任ら関係者のPCR検査をし、臨時休校中に両校の消毒を行うと発表しました。









他にも日本各地で生徒や児童のコロナウイルス感染が確認されたり、学校や保育園などの教職員の感染も明らかになっています。
緊急事態宣言が解除され、人々の動きが基に戻ってくれば当然、コロナウイルスの拡散が再び起こることはわかっていました。
現に最近の東京都の新たな感染者は高い水準を保っています。
東京都や国は再び規制を厳しくする考えはないようで、以前にもまして市民一人一人の行動が問題となります。
しかし、実際にはコロナウイルスのことを気にしていないように見受けられる人々がかなり増えてきています。
今回の学校関係者の感染は学校内でうつされたのではないようですが、一歩間違えば学校内でのクラスター発生もあり得たでしょう。
どの学校も臨時休校の処置をとったようですが、休校期間が2、3日というのが少し疑問です。
この間に校内消毒をするのが目的のようです。
しかし、生徒の安全を考えると校内での感染がないことを確認できるまで休校にした方がいいと思います。
コロナウイルスが終息するまで待つのではなく、感染リスクを最小限に抑えながら学校生活を再開させるというのが文科省の方針です。
これ以上休校で子供たちの勉強が遅れるのが心配という声に配慮してのことですが、当然予想される校内での感染が発生した時の対策は明確ではないような気がします(感染防止の対策は示されているのですが)。
今回のコロナウイルスの混乱で、学校はコロナウイルスで登校できなくなっても勉強が継続できる体制を作ることが重要だと認識しているはずです。
しかし、三か月に及ぶ休校期間においてもオンライン授業など、その体制を整えること、準備することさえできていません。
子供たちに保障されている「学ぶ権利」を守ってあげられるように我々大人は最大限の努力と実行をしないといけません。
教育の選択肢を増やすことはコロナウイルスへの対策だけでなく、今後起こる災害発生時や不登校など様々な理由で学校に通えない生徒たちを守ることにもつながります。
これは非常に大事なことで、文科省は新たな教育体制を成立させるのに出し惜しみはしないでほしいと思います。
日本は先進国の中でも、個人が子供の教育に掛ける出費の割合が非常に大きいのが特徴とされています。
つまり、塾などどれだけ子供に投資できるかという家庭の経済状況が、子供の教育の機会に大きく関わるのです。
予測していない危機、混乱に対して、生徒たちの住む地域の違いだけでなく、公立学校か私立学校か、オンライン環境が整っているかいないか、塾や家庭教師などの出費が可能かそうでないか。
そして、家庭状況による教育格差という問題が今回のコロナウイルスによってより鮮明に表れたと思います。










全ての子供たちは等しく教育を受ける権利を有し、誰もが公平に学ぶ機会を保障しないといけません。
しかし、日本の教育はこの問題に十分に取り組んでいるとは言えません。
どこか人任せなのです。
政府はコロナ禍をきっかけにもっと教育を真剣に考え、子供たちが明るい将来を迎えられるように行動してほしいと思います。
教育は未来の日本への投資であり、その見返りは非常に大きい。
だから、日本はもっともっと教育にお金をかけるべきです。
人が日本の最大の力であり、子供は日本の宝です。
葛西TKKアカデミーはもちろん子供の教育を真剣に考えています。
どのような子供でも、本人が望む限り学びをしっかり支えたいと考えます。
そして、彼らの夢を叶えてあげたいと思います。
























2020.06.21
学校再開、でも子供たちには心身ともにへとへと?!

ようやく学校が再開され、長い休みから一変、生徒たちは規則正しい生活を求められるようになりました。
休みの間会えなかった友達と再会したり、新しいクラスにワクワクしたり。
待ちに待った学校がやっと始まり喜ぶ生徒がいる反面、新しい環境に不安だったり馴染めなかったりする生徒も多くいます。
特に未だにコロナウイルスの脅威は去っておらず、感染リスクを抱えながらの学校ということで、あれやこれや規制や強制も多く、子供たちの自由も大きく制限されストレスがたまりやすい中での学校生活に心身ともに早くも疲弊している生徒もいます。
休校でできなかった分の授業を補うため夏休みなどが大幅に削られ、学校行事も縮小されたり中止になったり。
学校での楽しい時間が奪われています。
コロナウイルスの脅威の下、体を休めたりリラックスして自分の時間を楽しむこともなかなかできない。
本来猛暑の中での勉強を避けるための夏休みもなくなり、これから生徒たちは酷暑の中、エアコンもない教室で勉強をしなければならなかったり、仮にエアコンが備わっていても感染防止のため窓を開け換気をしなくてはいけないので、快適な環境下での勉強は無理のようです。
休み期間中にゲームやSNSに没頭し夜もしっかり睡眠を取らず生活のリズムを崩してしまった生徒は、元の生活に戻るのにとても苦労しています。
また、外出自粛で外で遊んだり十分な運動ができていないので、生徒たちは体力が落ちで病気にもなりがちです。
コロナウイルスという異例の事態とそれからの学校復帰で、すでに心も体もつかれている生徒がたくさんいます。
このような子供たちに対して大人はどのように接すればいいのでしょうか。








先ずは学校というプレッシャーから解放される家庭ではせめてリラックスできるようにしてあげましょう。
確かに家庭でも勉強しないといけないでしょうが、可能な限り心と体を休めるように心がけましょう。
あまり勉強勉強と追い詰めると子供たちはいよいよ逃げ場を失い、ストレスが爆発して取り返しのつかない事態が発生するかもしれません。
家庭を癒しの空間、もしくはあえて意識的に何かしようとしなくても、素直な自分でいられる場所にしましょう。
親子のコミュニケーションを上手に図り、子供たちが安心して心を開ける関係を作りましょう。
大人として時にはアドバイスや励ましを与え、子供と共感できる立ち位置に立てるといいです。








学校としては、学校が子供たちにとって楽しく希望に満ちた場所であるように努めなくてはなりません。
「学校が好き。」「先生が好き。」「勉強が楽しく早く学校に行きたい。」
こんな風に生徒が思えるようにすることが最優先です。
コロナウイルスの感染、勉強の遅れなどいつも以上に大変ですが、かと言って形式だけで中身のない授業をしたり、生徒をどんどん追い込むような学校生活にしてはいけません。
先生はやることが増え、なかなかゆとりも持てないでしょうが、文科省を始め期間が努力し現状に合った対応(教員を増やすとか、外部に援助を求めるとか)をすればいくらか軽減ができます。
しかし、生徒は本人以外に代われる人はいません。
先生は授業数が増えればその分をヘルプの先生にお願いできるでしょうが、生徒は増えた分の授業は全て自分一人で受けなくてはいけないのです。
このような立場の違いをきちんと理解し、それらに対する配慮は十分に行わないといけません。
時には生徒が何もせずぼーっとしているのも許してあげましょう。
このように何も考えない時間も大事です。
勉強の遅れなど親として心配で、教師として責任もって挽回しなくてはならないのは理解できますが、だからと言って無理を強いると必ず子供に反動が来ます。
そうでなくても異常事態にストレスをため込んで切るのに、更なる負荷をかけると様々な弊害が現れるでしょう。
心身症やうつ、いじめも発生するかもしれないので、周囲の大人は十分な注意を怠ってはいけません。
大人の一方的な考えを押し付けるのではなく、子供の立場に立って考える必要があります。








最後にもう一つ注意しないといけないのが子供同士の人間関係です。
最初のころは新しいクラスで生徒たちはお互いに様子を見つつ人間関係を築いていくのですが、一定期間が過ぎるとこれらの関係は固定化され学校カーストなどと呼ばれる状態になりいじめや様々なトラブルが発生するようになります。
特に以前から心配されているように、コロナウイルスに関係したいじめも出てくるでしょう。
学校でもこのようないじめはしないようにと強く言っているようですが、保護者や周りの大人も気をつけなくてはいけません。
生徒一人ひとりをよく観察して、子供たちを決して一人にせず、彼らが何でも気楽に話せる関係を作っておくことはいじめや自殺を防止するのに非常に大切です。
独りぼっちになってしまうとどうしても自分の内側にばかり目が行くようになり、外の明るい可能性が見えなくなります。
大人たちは子供たちとコミュニケーションをしっかり取り、異変にいち早く気づけるようにし、いつでも相談しやすい人間でいてほしいと思います。





















2020.06.20
文科省が来年の大学入試の日程を発表しました。コロナウイルスの影響を受けた受験生の救済策はあるのか。まだ不透明で問題点も指摘されています。

コロナウイルスによる混乱で休校になり勉強に著しく影響を受けた現高校三年生ですが、文科省はいつまでも先が見えない状況は受験生によくないとして、17日に大学に入試日程を決定しました。
それによると日程はほぼ例年通りとなり、共通テストは1月16日、17日となっています。
注目すべきは、コロナウイルスでの休校により発生した勉強の遅れを配慮して、これを理由に1月30日、31日に定められた追試験を選択することも可能となったことです。
そして、追試日のさらに二週間後にも予備日を設けています。
私立大学の受験は2月1日から始まり、2月25日以降には国公立大学の前期試験が行われます。
3月8日から公立大中期試験、3月12日から国公立後期試験と入試スケジュールは変わりません。
また、9月から始まる総合型選抜(これまでのAO入試)は出願時期を2週間繰り下げ9月15日、11月1日からの学校推薦型選抜(推薦入試)の出願が始まるということも決まりました。
出題範囲に関しては共通テストでは特に配慮しないそうです。
各大学の個別試験では、高校3年で学習することが多い数学や理科、社会の科目で問題を選べるようにするなど、出題範囲を工夫するよう強く要請しています。
さらに、コロナウイルスに感染した受験生向けて、大学が個別試験で追試を設定するといった救済策も特に強制ではなく、大学が行わなかったからと言ってペナルティがあるわけでもないので、実行性にはかなり疑問が持たれます。
また、コロナウイルスの感染の再拡大などで秋以降に再び休校した場合、高校卒業や大学入学時期が4月以降にずれこむ可能性があることも述べられています。
万が一そうなれば入試日程を大幅に変える方針も確認されました。
以上が発表された内容ですが、この日程ですと追試を受けた受験生は、すぐに私立大学の入試になりますし、予備日を使えば私立入試の後になることもあります。
共通テストの成績を利用した評価が難しくなることが考えられます。
国公立入試でも間が短く、共通テストの結果(受験生は自己採点によるので正確な点数は分からないのですが、しかも、共通テストでは自己採点の得点と本当の得点の差が大きく、大学選びが非常に難しくなるという傾向が報告されています)から志望校を決めるまで非常に猶予がない日程になっています。
スケジュールとしてはかなりタイトなものとなったことは否定できません。
また、追試験についても誰がコロナウイルスにより学習が遅れたのかを判断するのか、浪人生は利用できるのかなど疑問の声も上がっています。








コロナウイルスにより一部の受験生は勉強を大きく阻害され、オンライン授業が受けられる生徒とそうでない生徒、コロナウイルスによる休校期間が短い学校と長い学校、生じた勉強の遅れを様々な手段で補うことができるほど経済的にゆとりのある家庭とそうでない家庭。
高校三年生の大事な時期に勉強が十分にできず、置かれた環境により受験生間に学力差が生じ、入試で最も重要な公平性が保たれるのか不安の声も上がっています。
そのような状況の中で受験生の救済策として「9月入学」(これは学校制度全体を9月入学にするのではなく、コロナウイルスにより失われた時間と学習を取り戻し、受験生だけを対象にし彼らが公平に入試を受けられるための特例的提案だったのですが、文科省をはじめ世間はなぜか前者の方向で議論をし、受験生を救う議論はなく消滅したのですが)もなくなり、少なくとも一か月程度日程をずらそうという意見も、大学をはじめ各機関が日程調整や手続き上の問題、高校による休校期間の差異などのため結局消えてしまいました。
いつまでも日程が決まらずあいまいな状況では受験生も不安だし、計画も立てられないだろうと日程の決定となり、世間からは一定の評価が得られています。
しかし、同時にコロナウイルスにより多大な不利益を被った受験生への配慮は十分と言い難く、「文科省は受験生を見捨てた。」との非難も出ています。








今の高校三年生は入試改革による新制度での初めての受験生となります。
しかし、この新しい入試制度は多くの批判や疑問を浴びてきましたが、文科省は的確な回答を避け実施を半ば強引に進めようとしました。
しかし、入試改革の目玉であった英語の民間試験活用も数学・国語の記述問題も多くの反対意見及び文科相の不適発言(実際は後者の理由が大なのでしょう)によりとりあえず来年は実施しないことになりました。
誰がどう考えても不適切で準備不足な制度を来年に推し進めようとしたのは今年がオリンピックイヤーだったからで、受験生への配慮でもなんでもなく、新制度を来年からしなければならない絶対の理由はありませんでした(現にオリンピックも今年はやらないことになり、ますます来年にこだわる意味がなくなってきました)。
この機会にいったん歩みを止め、入試改革を含む教育改革全体を見直した方がいいと思います。
本当に生徒にとって最善の教育とは何か。
それに加えて今回のコロナウイルス。
今年の受験生は不運としか言いようがありません。
とは言え、不幸を嘆いても文科省は己を顧みて生徒たちのことを真剣に考え制度全体を考え直そうとはしないでしょう。
遺憾ながらどんなに理不尽な制度でも生徒はその枠組みの中で戦うしかないのです。
残念ながら…。
だからこそ、葛西TKKアカデミーは生徒たちのためにできることは何でもしたいと考えています。
いつでも生徒たちのために力になり支える準備があります。
どんなこともでも構いません。
まずはご相談ください。
そして、一緒に考え目標に向かっていきましょう。
受験生の皆さん頑張ってください。
葛西TKKアカデミーはいつでも皆さんを応援しています。





















2020.06.17
コロナウイルスのせいで子供たちにもスマホを持たせることに肯定的な家庭が増えてきました。しかし、注意しないと「スマホ依存症」の危険性も。どのように回避すればいいのでしょうか。

コロナウイルスの影響で学校が停止した時、オンラインを利用して授業を提供できる私立学校とインターネット端末やwifi環境の整っていない公立学校との間に大きな勉強格差が生じたことが問題となっています。
オンライン授業にアクセス可能な私立学校の生徒たちは3か月の休校期間中も勉強を進めることができました。
しかし、ICTの普及率がわずか5%の公立学校では多くの生徒が学習を進めることができず、復習中心のプリントやワークをやるにとどまりました。
ICT化を進めて近代的な教育を提供すると言いつつ、遅々として進めなかった公教育の怠慢と言ってもいいでしょう。
これを教訓にICTが公立学校にも大きく広がるといいのですが、残念ながら先行きははっきりしません。
今回の混乱でICTの有効性を感じた家庭も多く、子供たちにスマホを持たせようという意見が増えています。
しかし、むやみにスマホを子供たちに与えるのは注意が必要です。
なぜなら、こちらの期待通り勉強に有効活用してくれればいいのですが、実際はゲームやSNSなど子供たちが興味のあることのみに使うようになってしまうことが多いです。
スマホが手放せなくなり、スマホに依存した状態になる。
当然他のことは何もできなくなり、一日中スマホをいじり気づけば朝になっていたなんてこともよくある話です。
スマホのゲームなどは利用者が簡単にやめられないようにできています(そうすることでゲーム会社は利益を増やす目論見ですが)。
昼夜関係なくスマホをいじることで、生活のリズムが狂いとうとう学校にも行けなくなる例もたくさんあります。
オンラインゲームがやめられなくなると脳の前頭前夜の機能が低下し、衝動や欲求のコントロールがうまくできなくなります。
この事態を重く見たWHOは「ゲーム障害」という新しい疾患と認定したほどです。










今の世の中、スマホなしでは生活できないほど、スマホは生活に深く根付いています。
ある調査によると、2018年では小学生のスマホ保有率は都市部で小学校三年生を境とし半数以上にもなるそうです。
ベビーカーに乗った赤ちゃんがスマホをいじる姿も最近はよく見かけます。
だから、このようにスマホネイティブと言っていい彼らに、安易に「スマホ禁止」としてもなかなか解決できません。
スマホは道具です。
道具は正しく使うと大きな利益をもたらしてくれます。
全面禁止にするよりも、いかにうまくスマホと付き合えるかを考えた方が有意義な気がします。
やはりルール作りが大切
将来的にもスマホを十分活用して世の中を生きていけるように、子供のスマホの基本は「制限」よりも「判断力の育成」に重点が置かれるようになっています。
スマホが手放せない子供たちを一方的に責めたり、親の考えを押し付けたりするのはよくありません。
本人がスマホの危険性を自覚し、どのように接すればいいか考えるように促すのが大人の立場としてはふさわしいと言われています。
だから、スマホのルール作りが大切になります。
では、どうやってルールを作ればいいのでしょうか。
大人が勝ってに決めて押し付けても、子供はことの重要性を理解していないので、ルールを大切に思わず守ろうとはしません。
先ずはスマホのいい点と悪い点を話し合ってみましょう。
スマホが使えることでどんないいことがあるか、逆に悪いことがあるか、何ができるようになり、その反面どのような危険性が潜んでいるか、親子でしっかり話し合い、書き出して目に見える形にしましょう。
そして、スマホの問題点を考えながら、どうすれば解決できるか、どうすれば問題点を最小限に抑えられるか、子供と一緒に考えましょう。
一番問題になっていくことは利用時間でしょう。
親子でスマホの利用時間を記録し調べ、一日何時間使っていいのか、いつからいつまで使っていいのか、休日はどのようにするか話し合いましょう。
スマホを利用する場所もできれば子供一人にするのではなく、親の目が届くところにするのが安心です。
当然、子供だけルールを決めて制限するのでは、子供は不公平を感じ守ろうとしないかもしれません。
同時に親に対してのルールを決め、親もそのルールを守るのがスマホの管理を成功させる大きなポイントになりえるでしょう。
また、守れなかったときはどうするか決めるもの大事です。
更に、スマホでやってはいけないことも決めなくてはなりません。
これは犯罪に巻き込まれないようにするためにも重要です。
個人情報をネットに載せない。
SNSなどで悪口や嘘、不満などを書かない。
他人の個人情報を勝手に教えない。
危険なサイト(薬物、暴力、大人向けサイトなど)にはアクセスしない。
有料なものもあるので勝手にダウンロードしない。
これらの項目は子供自身を守り家庭を守るためにも大切です。
最近はスマホにフィルタリングなど色々機能がついているので、これらを活用するのもいい手段です。
最後に「○○をしたからスマホの時間を増やして。」や「○○してくれたからスマホをもっと使ってもいいよ。」なんて取引するのは止めましょう。
これを許してしまうと、せっかく一緒に作ったルールがどんどん崩れていきます。
それはそれ、これはこれときちんと割り切って対応しましょう。
もちろん、きちんと使っていれば褒めてあげることも大切ですし、定期的に利用状況を顧みてルールを変えていくことも大事です。










スマホは我々が子供のときにはなかったツールなので、大人としてもどう対応していけばいいかよく分からないのも当然です。
時代はどんどん変化し、これからも私たちが経験したことがなく何が正解か分からない事態を扱わなくてはならないようになるでしょう。
何事にも正負の両面があります。
良い点を生かし、悪い点を抑えることで、子供たちにこれまで以上の可能性が生まれます。
これらの点を踏まえて、親が一方的に決めるのではなく、子供と一緒に話し合い、お互いに納得し守っていける道具の使い方を考えていくことが肝心です。
それが子供の成長を促し、守ることにもつながります。
























2020.06.14
現中学三年生が来年受ける都立高校入試の日程及び出題範囲について東京都教育委員会から発表がありました。

コロナウィルスによる休校等の混乱の中、受験生及びその保護者をやきもきさせていた高校入試の内容が東京都教育委員会から発表がありました。
先ず日程ですが、例年とほぼ変わらず次のようになっています。
推薦に基づく選抜
・入学願書受付日
令和3年1月21日(木曜日)
※現在、郵送等による出願について検討中であり、郵送等となった場合、変更が生じることがある。
・実施日
令和3年1月26日(火曜日)・27日(水曜日)
・合格発表日
令和3年2月2日(火曜日)
学力検査に基づく選抜
・入学願書受付日
令和3年2月5日(金曜日)・8日(月曜日)
※現在、郵送等による出願について検討中であり、郵送等となった場合、変更が生じることがある。
・実施日
令和3年2月21日(日曜日)
・合格発表日
令和3年3月2日(火曜日)
その他の入試日程については今回割愛させて頂きます(必要な方はお問合せください)。
また、今回のコロナウィルスによる臨時休校により入試の出題内容に関して次のような配慮がなされることになりました。
推薦に基づく選抜
文化・スポーツ等特別推薦では、出願に関わる「推薦の基準」に、大会の実績や、資格・検定試験等の成績に関わる内容を含めず、「実績等を証明する書類等の写し」の提出も求めない。選考は、実施要綱に従って実技検査等により行う。
学力検査に基づく選抜
学力検査については、中学1、2年生の学習内容に加え、各教科における中学3年生の1年間の学習内容のうち、おおむね7か月程度で学習可能な分量を出題範囲とする。
したがって、次の表の内容について出題範囲から除外する。
・国語
中学3年生の教科書で学習する漢字
・数学
中学3年生で学習する内容のうち、次に挙げる内容
三平方の定理、標本調査
・英語
関係代名詞のうち、主格のthat、which、who及び目的格のthat、whichの制限的用法
※ 同様の働きをもつ接触節も出題しない
・社会
公民的分野のうち、次に挙げる内容
『私たちと経済』の「国民の生活と政府の役割」、『私たちと国際社会の諸課題』
・理科各分野のうち、次に挙げる内容
第1分野-『運動とエネルギー』の「力学的エネルギー」、『科学技術と人間』
第2分野-『地球と宇宙』の「太陽系と恒星」、『自然と人間』









日程に関して例年通りなのは夏休みや冬休みの縮小、土曜登校、7時限目の実施等で、休校分の授業数が確保できるという考えからでしょう。
しかし、短期に集中して詰め込むのでは本当に生徒たちの学習に影響ないのか疑問です。
単なる数字合わせになっていないか心配です。
来週から分散登校ではなく通常の時間割(6時間)になるようです。
しかし、コロナウィルスはなくなった訳ではなく、感染予防をしながらの学校運営となります。
当然、クラスター発生の可能性も否定できず、予防のために多くの負担を生徒と職員、および保護者に強いることになります。
このような状態で本当に通常通りの授業ができるのか、本当に身に付く学びができるのか。
これまでの休校により喪失感や絶望感、学習意欲の低下などこれまでとは生徒の心理もかなり違ってきており、それらをきちんとケアできるのか。
問いたいことは多々ありますが、とにかく生徒のことを第一に考え、彼らにとってどうするのが一番いいのか真剣に考えてほしいと思います。
因みに、第二波が発生した場合はまた変更等あり得るようです。(今のところ9月入学の線は消えています)。
入試範囲が一部除外された点ですが、入試に入らないとなると学校ではやらないということになるでしょう。
除外範囲は例年の学習順序で最後に来るもので、休校した分前から順番にやると時間切れでできなくなる内容という意味で除外にしたのでしょう。
しかし、三平方の定理や関係代名詞など、これらの内容は決して不要なものではなく、どこかでフォローするべきです。
確かに失われた時間を考慮して学習内容の精査は必要ですが、それは決して順番で後だから省くというものではありません。
学習内容の重要度に基づいてなされるべきで、今回の対応は安直な気がします。
とは言え、明確に入試に関して教育委員会が示したことはよかったと思います。
受験生も教員も保護者もいつまでも曖昧でどうしていいか分からないという状況から抜け出せたので、これから入試対策を行うことができます。
詳細についての検討は後日行いたいと思っています。
入試に関するご相談、お問合せはいつでも受け付けています。
葛西TKKアカデミーは全ての生徒の味方です。
どんなことでも気軽にお話ください。
必ずお力になります。
























2020.06.12
学校再開。しかし、学校に行こうとすると急に具合が悪くなる生徒が増えているそうです。どうしてなのでしょうか。

コロナウイルスにより長い間休みになっていた学校がいよいよ再開しました。
待ちに待った登校。
しかし、生徒の中にはなぜか学校に行こうとすると急に体調を崩す者が増えているみたいです。
これはなぜでしょうか。









それまでは何事もなく学校に行く準備をしていたのに、いざ行こうとすると急にお腹が痛くなる、頭が痛くなる、吐き気を催す、気持ちが悪くなる、熱が出る。
実は通常でもこのような症状を表す生徒はいますが、コロナウイルスが流行した今年はより多くなっているようです。
これは精神的ストレスによるものだそうです。
科学的にはストレスが自律神経やホルモン分泌に影響を与え、このような症状を出させるようです。
コロナウィルスによる長期の休校のせいで学校の勉強に対する不安も例年より大きいようです。
長い間他の生徒と合うこともなく、自宅学習によってできる生徒はどんどん進み、自分は追い付けないくらい遅れて落ちこぼれになるのではないか。
新年度が始まってもずっと自宅にこもりっきりで新しいクラスメイトや先生とこれから仲良くなれるか心配。
感染防止のためみんなと一緒に思いっ切り遊ぶことも、ワイワイ話しながら楽しく給食を食べることもできない。
楽しみにしていた学校行事も縮小または中止となり、学校が全くつまらない。
実際につまらないから学校に行きたくないという生徒は非常に多いです。
あれもダメ、これもダメ。
あれをしなさい、これをしなさい。
指示ばっかりで周囲の大人の監視の目が怖い。
のびのびと体を動かして友達と楽しい時間を過ごしたい子供たちにとっては(子供の健全な成長にはこれらは非常に重要なのですが)まさにストレス。
普段でもいじめなどのストレスから学校に行けない生徒はいるのですが、加えて今回はコロナウィルスだからこそ余計なストレスも増えているようです。
とは言え、しばらく家で安静にしていると体調も戻るのですが、また家を出ようとすると同じ症状にさいなまれることもあります。
頭では意識していなくても心の奥に感じるストレスに体は敏感に反応します。
人生経験を積んだ大人ならある程度対処法も自分なりに見出しているかもしれませんが、子供たちにはそうはいきません。
大人にとっては何でもないことが子供にとっては大きな問題であったりします。
本人はそんなことないと思っていても、ストレス反応が出たときは適切に大人は対応しなくてはいけません。
ましてや仮病なんて疑うのはもってのほかで、子供のストレスとより大きくし病状を悪化させます。
また同じ生徒同士でも同じ状況に対するストレスは違います。
これは本人たちの特性によるもので、ひとによっては怒ったり、落ち込んだり、大して気にも留めなかったり。
性格という点が大きく影響してきます。
人間の性格を変えることは難しいですが、ストレスを軽減する有効な方法として周囲の人間のサポートがあります。
自分の味方になってくれる。
悩みを打ち明けられる。
このようなことを本人が感じられれば安心感が生じ、ストレスもグッと減ってきます。
「コロナウィルスで疲れるよね。無理しないで。」なんて優しい言葉をかけ、時には小さなことを褒めてあげる。
話を聞いてもらえるだけでも子供たちは気持ちが楽になります。
一人じゃない。
支えてくれる人がいて君を守ってくれるよ。
何も怖がる必要はない。
このようなメッセージが子供たちの心に届けばいいです。
コロナウィルスという未だかつて経験のない混乱の中、大人でさえ不安や悩み、苦しみなどからストレスを感じます。
子供ならなおさらです。
そこで大事になってくるのが親や先生など周りの大人の対応です。
学校に行けないことを責めるのではなく、また学校に行けない本人から大丈夫何とかなくという安心と希望を与える声掛けをしてください。
小さなことに気づいてあげて「偉いね。」と褒めてあげるのもいい方法です。









最後に、自分だけで何とかしなくればならないとは決して思わないでください。
必要ならば他の人や、その道のプロに協力を求めるのも重要です。
その方が効率的であることもあります。
子供のストレスに引っぱられて自分もストレスになってはいけません。
もちろん、葛西TKKアカデミーはいつでもお手伝いする用意があります。


























