塾長ブログ
2023.09.19
コロナとインフルのダブル流行⁉受験生は特に注意を!

新型コロナウイルスの話題も最近はあまり聞かれなくなりました。
しかし、新型コロナウイルスの脅威は去ったわけではなく、実はまだ続いているのです。
7月あたりから感染者数が急増し、各医療機関も徐々に圧迫されており、第9波に入ったと言われています。
そして、今回の流行で懸念されている点として、インフルエンザとの同時流行が言及されています。
以前からその兆しはあったのですが、今回はそれが更に明確になったようです。
新型コロナウイルスもインフルエンザもかかってしまっては大変です。
特に受験生は、人生に大きく影響する入試を控えているので、細心の注意が必要です。
しかも、新型コロナウイルスが5類になって国としての対策が行われなくなった現在、これまでのように感染者に対して特別処置を取って再受験させてくれる可能性は非常に低くなっています。
従って、これまでの受験生以上にこれらのウイルスに対する警戒が必要です。








新型コロナウイルスが5類になって、これまでのように全集調査が行われなくなりました。
感染者数がはっきりと出なくなり、ニュースでも取り上げられなくなったせいか、新型コロナウイルス対する警戒感はかなり下がってきました。
しかし、その陰で感染者数は確実に増え、明確な数値こそ示されませんが、感染者数は第8波に迫る規模になると予想されています。
しかし、新型コロナウイルスの脅威は去ったわけではなく、実はまだ続いているのです。
7月あたりから感染者数が急増し、各医療機関も徐々に圧迫されており、第9波に入ったと言われています。
そして、今回の流行で懸念されている点として、インフルエンザとの同時流行が言及されています。
以前からその兆しはあったのですが、今回はそれが更に明確になったようです。
新型コロナウイルスもインフルエンザもかかってしまっては大変です。
特に受験生は、人生に大きく影響する入試を控えているので、細心の注意が必要です。
しかも、新型コロナウイルスが5類になって国としての対策が行われなくなった現在、これまでのように感染者に対して特別処置を取って再受験させてくれる可能性は非常に低くなっています。
従って、これまでの受験生以上にこれらのウイルスに対する警戒が必要です。








新型コロナウイルスが5類になって、これまでのように全集調査が行われなくなりました。
感染者数がはっきりと出なくなり、ニュースでも取り上げられなくなったせいか、新型コロナウイルス対する警戒感はかなり下がってきました。
しかし、その陰で感染者数は確実に増え、明確な数値こそ示されませんが、感染者数は第8波に迫る規模になると予想されています。
エリス株とインフルエンザのダブル流行
新型コロナウイルスはその変異の激しさが特徴ですが、現在流行しているウイルスの4割が新しい変異株である「エリス」と言われています。
これはこれまでのものと比べ感染力が高くなっていますが、重症化のリスクは低いとみられています。
また、インフルエンザも同時に流行し始めています。
インフルエンザの流行開始の目安となる一週間の患者広告数の1.0人を既に大幅に超えて、5.95人となっているそうです。
本来インフルエンザは冬に流行するものですが、まだ暑いこの時期にこれほど感染者がいるのは極めて異例です。
これはこれまでのものと比べ感染力が高くなっていますが、重症化のリスクは低いとみられています。
また、インフルエンザも同時に流行し始めています。
インフルエンザの流行開始の目安となる一週間の患者広告数の1.0人を既に大幅に超えて、5.95人となっているそうです。
本来インフルエンザは冬に流行するものですが、まだ暑いこの時期にこれほど感染者がいるのは極めて異例です。
学級閉鎖
都内では既に多くの小中高の学校で学級閉鎖などの臨時休校が起きています。
二学期が始まってから学級閉鎖となったクラスは全国で増え続け、今月8日の時点で新型コロナウイルスとインフルエンザ合わせて約700クラスに上っています。
都内でも小学校を中心に、のべ数で約100校で学級閉鎖のクラスが出ています。
既に医療機関でも感染者数の増加が施設を圧迫し始めており、患者受け入れができない事例が多く発生しています。
生徒たちがウイルスに感染しても十分な治療が受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
新型コロナウイルスとインフルエンザのダブル流行の原因は、コロナ禍の予防でインフルエンザに対する免疫をもっている人が減ったことだそうです。
また、ワクチンの効果が切れる時期が重なったことも挙げられます。
そこで、多くの生徒が集まる学校では換気や手洗い、マスクなどこれまで通りの基本的な感染対策が求められています。
これまでと同じく、不必要な外出をしない、人ごみを避けることも重要です。
そして、各家庭でも油断することなく予防を心がけてください。
二学期が始まってから学級閉鎖となったクラスは全国で増え続け、今月8日の時点で新型コロナウイルスとインフルエンザ合わせて約700クラスに上っています。
都内でも小学校を中心に、のべ数で約100校で学級閉鎖のクラスが出ています。
既に医療機関でも感染者数の増加が施設を圧迫し始めており、患者受け入れができない事例が多く発生しています。
生徒たちがウイルスに感染しても十分な治療が受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
新型コロナウイルスとインフルエンザのダブル流行の原因は、コロナ禍の予防でインフルエンザに対する免疫をもっている人が減ったことだそうです。
また、ワクチンの効果が切れる時期が重なったことも挙げられます。
そこで、多くの生徒が集まる学校では換気や手洗い、マスクなどこれまで通りの基本的な感染対策が求められています。
これまでと同じく、不必要な外出をしない、人ごみを避けることも重要です。
そして、各家庭でも油断することなく予防を心がけてください。
特に受験生は注意!これまでのような救済はない⁉
病気になってしまうのは、ある意味仕方ないことです。
いくら予防しても、病気になってしまうときはなってしまうのです。
しかし、ならないに越したことはありません。
病気になれば勉強ができず、学習が大きく遅れてしまいます。
このように生徒たちにとって病気にかかってしまうことは大きな痛手になるのですが、その中でも特に受験生は気をつけなければなりません。
受験生は入試に向けて毎日しっかり勉強をする必要があります。
しかし、病気で勉強ができない日が続くと、その分受験勉強が遅れ、志望校が遠のいてしまうかも知れません。
よって、受験生は他の生徒以上に新型コロナウイルスやインフルエンザにかからないよう、しっかり予防しないといけません。
でも、今回受験する生徒は前回の受験生よりもっと新型コロナウイルスの感染に注意しなくてはならない理由がもう一つあります。
今年の5月から新型コロナウイルスが「5類」に分類されるようになりました。
これは季節性のインフルエンザと同じです。
つまり、これまでのように政府が国全体の問題として対策を進めるのではなく、各自治体や医療機関での対応がメインになります。
感染症としての深刻度が下げられたということです。
これは受験に関しても同じで、これまで新型コロナウイルスに感染した受験生及び濃厚接触者は別室で受験したり、別日に受験したりと救済処置がなされてきました。
しかし、5類になって一般のインフルエンザと同じ扱いになると、これらの救済処置は実施されないことが予想されます。
そうであれば、今回の受験生はこれまでのコロナ禍での受験生より、新型コロナウイルスに感染してはいけないということになります。
これまでのようなセカンドチャンスはなく、感染して入学試験を受けられなければそれで終わりです。








以前のように毎日感染者の全数が発表されるわけでなく、報道でもあまりふれられなくなったため、世間的に新型コロナウイルス脅威は去ったかのように誤解されますが、実は現在全国で進行中の第9波の感染者数は今月10日までの一週間で約15000人と言われています。
すなわち、以前のように明確な数字が出ないから余計に危機感を持ちにくい状況で、実際の感染者数は非常に多くなってきているのです。
従って、感染に対する脅威は依然とさほど変わらないと考えた方がよさそうです。
用心に越したことはありません。
学校でも以前のようにマスクの着用が義務化されなくなり、修学旅行や運動会文化祭など多くの生徒が密になって活動する機会も増えました。
いつかは平常に戻らなくてはいけないのですが、新型コロナウイルスの第9波とインフルエンザの同時流行という現実を鑑みたとき、まだまだ油断してはいけないと考えられます。
特に受験生は、今回から以前のような新型コロナウイルスに対する救済処置がなされなくなると予想されるので、これまでの受験生と同様に厳とした警戒が必要です。
これまで行ってきた基本的感染対策をしっかり行い、何としても感染して受験できない事態は避けないといけません。
そして、感染を避ける努力は、受験生自身だけに留まらず、家族や学校関係者など周囲の人間にも及びます。
みんなで協力して、受験生がつつがなく入試本番で全力を出し切り、悔いのない受験ができるように努めなくてはなりません。
























いくら予防しても、病気になってしまうときはなってしまうのです。
しかし、ならないに越したことはありません。
病気になれば勉強ができず、学習が大きく遅れてしまいます。
このように生徒たちにとって病気にかかってしまうことは大きな痛手になるのですが、その中でも特に受験生は気をつけなければなりません。
受験生は入試に向けて毎日しっかり勉強をする必要があります。
しかし、病気で勉強ができない日が続くと、その分受験勉強が遅れ、志望校が遠のいてしまうかも知れません。
よって、受験生は他の生徒以上に新型コロナウイルスやインフルエンザにかからないよう、しっかり予防しないといけません。
でも、今回受験する生徒は前回の受験生よりもっと新型コロナウイルスの感染に注意しなくてはならない理由がもう一つあります。
今年の5月から新型コロナウイルスが「5類」に分類されるようになりました。
これは季節性のインフルエンザと同じです。
つまり、これまでのように政府が国全体の問題として対策を進めるのではなく、各自治体や医療機関での対応がメインになります。
感染症としての深刻度が下げられたということです。
これは受験に関しても同じで、これまで新型コロナウイルスに感染した受験生及び濃厚接触者は別室で受験したり、別日に受験したりと救済処置がなされてきました。
しかし、5類になって一般のインフルエンザと同じ扱いになると、これらの救済処置は実施されないことが予想されます。
そうであれば、今回の受験生はこれまでのコロナ禍での受験生より、新型コロナウイルスに感染してはいけないということになります。
これまでのようなセカンドチャンスはなく、感染して入学試験を受けられなければそれで終わりです。








以前のように毎日感染者の全数が発表されるわけでなく、報道でもあまりふれられなくなったため、世間的に新型コロナウイルス脅威は去ったかのように誤解されますが、実は現在全国で進行中の第9波の感染者数は今月10日までの一週間で約15000人と言われています。
すなわち、以前のように明確な数字が出ないから余計に危機感を持ちにくい状況で、実際の感染者数は非常に多くなってきているのです。
従って、感染に対する脅威は依然とさほど変わらないと考えた方がよさそうです。
用心に越したことはありません。
学校でも以前のようにマスクの着用が義務化されなくなり、修学旅行や運動会文化祭など多くの生徒が密になって活動する機会も増えました。
いつかは平常に戻らなくてはいけないのですが、新型コロナウイルスの第9波とインフルエンザの同時流行という現実を鑑みたとき、まだまだ油断してはいけないと考えられます。
特に受験生は、今回から以前のような新型コロナウイルスに対する救済処置がなされなくなると予想されるので、これまでの受験生と同様に厳とした警戒が必要です。
これまで行ってきた基本的感染対策をしっかり行い、何としても感染して受験できない事態は避けないといけません。
そして、感染を避ける努力は、受験生自身だけに留まらず、家族や学校関係者など周囲の人間にも及びます。
みんなで協力して、受験生がつつがなく入試本番で全力を出し切り、悔いのない受験ができるように努めなくてはなりません。
























2023.09.14
手抜きの勉強はかえってたくさんやる羽目になり成績も伸びません

勉強ができない生徒を見ていると、個人の能力不足というより個人の勉強に対する考え方ややり方に問題がある場合が非常に多いです。
特にいろいろな物事に対して丁寧にやらず雑にササっとすまれる生徒は、勉強に対してもやり方がいい加減で、その結果、勉強がうまく身に付いていないことが多いです。
しかし、きちんと勉強が身に付いていなくては、後々勉強が更に分からなくなり、同じ勉強を何回もやり直さなくてはいけなくなってしまいます。
「早く終わらせたい」と思って手抜きの勉強をすると、反ってもっとたくさん勉強しなくてはならないということです。
今回はそんな雑な勉強について考えてみたいと思います。
つぎのような勉強の仕方では、二度手間になる可能性が高いので注意しましょう。








特にいろいろな物事に対して丁寧にやらず雑にササっとすまれる生徒は、勉強に対してもやり方がいい加減で、その結果、勉強がうまく身に付いていないことが多いです。
しかし、きちんと勉強が身に付いていなくては、後々勉強が更に分からなくなり、同じ勉強を何回もやり直さなくてはいけなくなってしまいます。
「早く終わらせたい」と思って手抜きの勉強をすると、反ってもっとたくさん勉強しなくてはならないということです。
今回はそんな雑な勉強について考えてみたいと思います。
つぎのような勉強の仕方では、二度手間になる可能性が高いので注意しましょう。








1.問題をやっただけ
勉強は問題を解いたら終わりではありません。
なぜ間違えたのかを明確にし、その原因を正さないといつまで経っても勉強ができるようにはなりません。
ワークやドリルなどの問題集、テストなど〇×をつけて、その結果に一喜一憂して終わりでは勉強する意味はあまりありません。
結果は自分の勉強の習得具合を示しているものだから、自分の勉強で明らかになった足りない部分を補ってこそ、勉強はより完璧に近づきます。
つまり、テストなどの結果は勉強の終わりではなく、むしろ始まりなのです。
ここを取り違えて、問題を解いてしまったらもう何もしない生徒はその後も繰り返し同じ間違いをします。
なぜ間違えたのかを明確にし、その原因を正さないといつまで経っても勉強ができるようにはなりません。
ワークやドリルなどの問題集、テストなど〇×をつけて、その結果に一喜一憂して終わりでは勉強する意味はあまりありません。
結果は自分の勉強の習得具合を示しているものだから、自分の勉強で明らかになった足りない部分を補ってこそ、勉強はより完璧に近づきます。
つまり、テストなどの結果は勉強の終わりではなく、むしろ始まりなのです。
ここを取り違えて、問題を解いてしまったらもう何もしない生徒はその後も繰り返し同じ間違いをします。
2.自尊心が間違いを許さない
どうも勉強で間違えることは罪のように考えている生徒がいます。
だから、間違えを許容できない。
それが、間違えをしないように事前の勉強に対する努力へとつながればいいのですが、むしろ逆にできる問題しかしない、もしくは問題を解くことすらしない方向に向かう生徒がいます。
そもそも問題を解かなければ間違いではない、できないのではなくやらないだけという論法です。
でも、これは本人にとってどれほどのメリットがあるでしょうか。
自尊心を守るための言い訳にしか過ぎないのですが、これで勉強しないことを正当化できると考えているようです。
しかし、間違いを恐れて勉強から逃げても実力はつかず、それは高校入試など後で明確になり、結局足りない学力を補うために勉強しなくてはならなくなります。
むしろ、期限が決まっている以上時間的余裕はなくなり、最終的に間に合わなくなる。
このように自尊心を守り実力不足をごまかしても何の意味もないのです。
むしろ、自分のできない現実を素直に受け入れ、その時その時に問題を解決していた方が何度も同じ勉強を繰り返す必要がなく、効率的で良い結果も出せるようになります。
だから、間違えを許容できない。
それが、間違えをしないように事前の勉強に対する努力へとつながればいいのですが、むしろ逆にできる問題しかしない、もしくは問題を解くことすらしない方向に向かう生徒がいます。
そもそも問題を解かなければ間違いではない、できないのではなくやらないだけという論法です。
でも、これは本人にとってどれほどのメリットがあるでしょうか。
自尊心を守るための言い訳にしか過ぎないのですが、これで勉強しないことを正当化できると考えているようです。
しかし、間違いを恐れて勉強から逃げても実力はつかず、それは高校入試など後で明確になり、結局足りない学力を補うために勉強しなくてはならなくなります。
むしろ、期限が決まっている以上時間的余裕はなくなり、最終的に間に合わなくなる。
このように自尊心を守り実力不足をごまかしても何の意味もないのです。
むしろ、自分のできない現実を素直に受け入れ、その時その時に問題を解決していた方が何度も同じ勉強を繰り返す必要がなく、効率的で良い結果も出せるようになります。
3.書くことを嫌がる
とにかく書くことを嫌がる生徒がいます。
できれば書かないで楽をしたい気持ちは理解できなくもないですが、書くということが勉強に与える効果を考えると、書かないということは結局自分を不利にしていることに気づいてほしいです。
「別に後で見ないから書かない」と言われたこともありますが、「書く」ということは単に後で見直すためだけではありません。
記憶や思考には、脳への刺激が重要になります。
より多くの刺激を与えられれば、それだけ脳は活性化し勉強も身に付きます。
よく漢字や英単語を覚えるのに本を見ているだけの生徒がいました。
テストをすると一つも書けませんでした。
そんな生徒が書いてみると、たくさん答えられるという経験があります。
「書く」ことが脳へ与える影響は大きいのです。
書くのを嫌がる生徒は日常的に書くことを回避する傾向があります。
つまり、勉強だけでなく生活全般において書かないのです。
普段から書くことに慣れている生徒なら生活の一部となっているので、書くことは何でもないのですが、そうでない生徒にとっては非常に苦痛のようです。
そうなってしまうと直すのは大変なので、できればそうなる前に書く習慣を身に付けさせてあげましょう。
小学生のときは勉強がそれほど難しくなく、ノートを取らなくても勉強できたかも知れませんが、学年が上がり勉強が複雑になると頭の中だけでは情報を処理しきれなくなります。
このとき、書く習慣が身に付いていない生徒は書くこと自体に違和感と抵抗感を持ち、意地になって書かなくなります。
でも、これは本人のためになりません。
これまでのようにできなくなってしまった自分を受け入れがたいのはとても分かります。
しかし、一時的な本人のプライドを通して勉強が分からなくなるよりも、長期的な視点で勉強のできない自分を受け入れる強さをもって、素直に「書く」ことができれば、勉強は必ずできるようになります。
実は、勉強は生徒の知識の問題ではなく、個人の考え方や心理、周囲の環境の問題であることの方が多いのです。
できれば書かないで楽をしたい気持ちは理解できなくもないですが、書くということが勉強に与える効果を考えると、書かないということは結局自分を不利にしていることに気づいてほしいです。
「別に後で見ないから書かない」と言われたこともありますが、「書く」ということは単に後で見直すためだけではありません。
記憶や思考には、脳への刺激が重要になります。
より多くの刺激を与えられれば、それだけ脳は活性化し勉強も身に付きます。
よく漢字や英単語を覚えるのに本を見ているだけの生徒がいました。
テストをすると一つも書けませんでした。
そんな生徒が書いてみると、たくさん答えられるという経験があります。
「書く」ことが脳へ与える影響は大きいのです。
書くのを嫌がる生徒は日常的に書くことを回避する傾向があります。
つまり、勉強だけでなく生活全般において書かないのです。
普段から書くことに慣れている生徒なら生活の一部となっているので、書くことは何でもないのですが、そうでない生徒にとっては非常に苦痛のようです。
そうなってしまうと直すのは大変なので、できればそうなる前に書く習慣を身に付けさせてあげましょう。
小学生のときは勉強がそれほど難しくなく、ノートを取らなくても勉強できたかも知れませんが、学年が上がり勉強が複雑になると頭の中だけでは情報を処理しきれなくなります。
このとき、書く習慣が身に付いていない生徒は書くこと自体に違和感と抵抗感を持ち、意地になって書かなくなります。
でも、これは本人のためになりません。
これまでのようにできなくなってしまった自分を受け入れがたいのはとても分かります。
しかし、一時的な本人のプライドを通して勉強が分からなくなるよりも、長期的な視点で勉強のできない自分を受け入れる強さをもって、素直に「書く」ことができれば、勉強は必ずできるようになります。
実は、勉強は生徒の知識の問題ではなく、個人の考え方や心理、周囲の環境の問題であることの方が多いのです。
4.とにかく早く終わらせたい
勉強嫌いの生徒は、とにかく勉強から逃れたいという気持ちが強く、見てくれだけ整えて早々に勉強を終わらせます。
でも、これは結局何も身に付いていないので、テストなどをしてみればすぐにやっていないことが分かります。
勉強は積み重ねなので、前出の内容が理解できていなければ新出の内容も理解できません。
従って、前やった内容をもう一度勉強し直さなくてはならなくなります。
逃げても結局やらなくてはいけなくなるし、やらなければ勉強がどんどんできなくなります。
「早く終わらせたい」というその場しのぎの感情が、後でより勉強しなくてはならなくさせるのです。
むしろ、その都度その都度の勉強をきちんとやって何回も繰り返さなくてもいいようにしましょう。
そうすれば、嫌いな勉強に余計に関わる必要がなくなります。
でも、これは結局何も身に付いていないので、テストなどをしてみればすぐにやっていないことが分かります。
勉強は積み重ねなので、前出の内容が理解できていなければ新出の内容も理解できません。
従って、前やった内容をもう一度勉強し直さなくてはならなくなります。
逃げても結局やらなくてはいけなくなるし、やらなければ勉強がどんどんできなくなります。
「早く終わらせたい」というその場しのぎの感情が、後でより勉強しなくてはならなくさせるのです。
むしろ、その都度その都度の勉強をきちんとやって何回も繰り返さなくてもいいようにしましょう。
そうすれば、嫌いな勉強に余計に関わる必要がなくなります。
5.途中式、図を書かない
数学で途中式を書かず暗算でやったり、図を書かないで適当に答えたりする生徒がたくさんいます。
このような生徒はよく間違えます。
暗算でやると「7×8」が「7×9」になったり、繰上り繰り下がりを忘れたりします。
これは頭の中では文字が固定されないからです。
頭の中は知らないうちに文字が他のものに置き換わったりします。
このような間違いをする生徒はよく「ケアレスミス」と言いますが、これは言い訳で何の改善策も見いだせないので、同じ過ちを繰り返します。
それを防ぐには、文字にして考えていることを視覚化し固定することが大事です。
だから、途中式や図を描くことは必要なのです。
更に、書けば見直しをしたときに、どこで間違ったか特定することも容易で、自分の間違いの原因を探ることもできます。
原因が分かれば改善ができ、勉強をより強化できます。
勉強のひと手間を惜しんで間違えるくらいなら、ほんの少しの苦労を惜しまず正確に勉強しましょう。
このような生徒はよく間違えます。
暗算でやると「7×8」が「7×9」になったり、繰上り繰り下がりを忘れたりします。
これは頭の中では文字が固定されないからです。
頭の中は知らないうちに文字が他のものに置き換わったりします。
このような間違いをする生徒はよく「ケアレスミス」と言いますが、これは言い訳で何の改善策も見いだせないので、同じ過ちを繰り返します。
それを防ぐには、文字にして考えていることを視覚化し固定することが大事です。
だから、途中式や図を描くことは必要なのです。
更に、書けば見直しをしたときに、どこで間違ったか特定することも容易で、自分の間違いの原因を探ることもできます。
原因が分かれば改善ができ、勉強をより強化できます。
勉強のひと手間を惜しんで間違えるくらいなら、ほんの少しの苦労を惜しまず正確に勉強しましょう。
6.正確に覚えない、なんとなく理解している
勉強嫌いの生徒はとにかく早く勉強を終わらせようとします。
彼らにとって最も重要なのは「早く終わらせること」で「勉強を習得すること」ではありません。
だから、性格に覚えているかどうかはさほど問題ではないのです。
しかし、なんとなくの雑な覚え方をすれば、正確性を要求されるテストで確実に正解を出すことはできません。
よって、もしよい成績を修めたいなら、もう一度覚えないといけなくなります。
一時的感情からその場しのぎの勉強をしても、長い目で見るといずれどこかでもう一度やらないといけなくなるのです。
どうせ覚えなければならないこと、理解しなくてはならないことならば、最初からきちんとした方が嫌な勉強を繰り返さずに済みます。
彼らにとって最も重要なのは「早く終わらせること」で「勉強を習得すること」ではありません。
だから、性格に覚えているかどうかはさほど問題ではないのです。
しかし、なんとなくの雑な覚え方をすれば、正確性を要求されるテストで確実に正解を出すことはできません。
よって、もしよい成績を修めたいなら、もう一度覚えないといけなくなります。
一時的感情からその場しのぎの勉強をしても、長い目で見るといずれどこかでもう一度やらないといけなくなるのです。
どうせ覚えなければならないこと、理解しなくてはならないことならば、最初からきちんとした方が嫌な勉強を繰り返さずに済みます。
7.よく考えずに当てずっぽう
ここまで来るともはや勉強とは言えません。
でも、勉強が嫌いでいい加減な勉強をする生徒にはよくあることです。
こういう生徒は非常に多くの間違い失敗をしますが、稀に偶然正解になることがあります。
この非常に稀だけど自分に都合の良いケースをよりどころに、当てずっぽうを正当化します。
冷静に考えれば間違える確率の方が多いのだから、勉強方法としては成立しないのは明らかなのですが、少しでも勉強したくない生徒はその事実に目を背けます。
自分の見たいものしか見ない、信じたいものしか信じないなどという心理は理解できますが、それでは問題は解決しません。
不確実な当てずっぽうより、ちゃんと勉強して正しく問題を解く方がより確実に結果が出せます。
強い心をもって現実と向き合いう勇気を持ちましょう。








学生である以上、勉強から逃れることはできません。
逃げたいからと言ってすぐに終わるような雑な勉強をしても、それはやっていないのとほぼ同じです。
やっていないのなら、いずれかの段階で勉強し直さないといけなくなります。
遅かれ早かれやらなくてはいけないのであれば、最初から嫌がらず素直にきちんと勉強しましょう。
その方が嫌なことを繰り返さずに済み、成績も上がるので、生徒自身にとっても得です。
逃げたい気持ち、できない自分を認めたくない気持ちを乗り越えて、自分にとって一番やらなければならないことをきちんとやる。
これが最も近道であり、手抜きの勉強はかえって自分を苦しめることを分かってください。
























でも、勉強が嫌いでいい加減な勉強をする生徒にはよくあることです。
こういう生徒は非常に多くの間違い失敗をしますが、稀に偶然正解になることがあります。
この非常に稀だけど自分に都合の良いケースをよりどころに、当てずっぽうを正当化します。
冷静に考えれば間違える確率の方が多いのだから、勉強方法としては成立しないのは明らかなのですが、少しでも勉強したくない生徒はその事実に目を背けます。
自分の見たいものしか見ない、信じたいものしか信じないなどという心理は理解できますが、それでは問題は解決しません。
不確実な当てずっぽうより、ちゃんと勉強して正しく問題を解く方がより確実に結果が出せます。
強い心をもって現実と向き合いう勇気を持ちましょう。








学生である以上、勉強から逃れることはできません。
逃げたいからと言ってすぐに終わるような雑な勉強をしても、それはやっていないのとほぼ同じです。
やっていないのなら、いずれかの段階で勉強し直さないといけなくなります。
遅かれ早かれやらなくてはいけないのであれば、最初から嫌がらず素直にきちんと勉強しましょう。
その方が嫌なことを繰り返さずに済み、成績も上がるので、生徒自身にとっても得です。
逃げたい気持ち、できない自分を認めたくない気持ちを乗り越えて、自分にとって一番やらなければならないことをきちんとやる。
これが最も近道であり、手抜きの勉強はかえって自分を苦しめることを分かってください。
























2023.08.26
英字新聞や英語ニュー英字新聞や英語ニュースで英語の勉強をしよう!
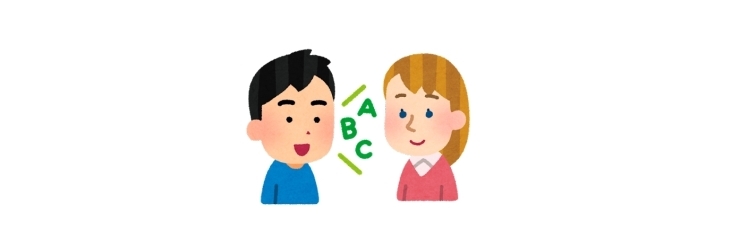
英語は多くの生徒にとって苦手な教科です。
理由はいろいろありますが、日常で触れることが少ないということも一つでしょう。
あまりにも日常から離れすぎでよく分からない、英語に触れなくても毎日の生活に何の影響もない。
こういった事情が英語を生徒にとって「なじみのない訳の分からないもの」という印象を抱かせ、「理解できないから苦手」という意識を持たせるのかも知れません。
しかし、現在はインターネットが発達しており、そこから英字新聞や英語ニュースなどをかんたんに入手することができます。
そこで今回は英字新聞を使った英語の勉強について考えてみたいと思います。








理由はいろいろありますが、日常で触れることが少ないということも一つでしょう。
あまりにも日常から離れすぎでよく分からない、英語に触れなくても毎日の生活に何の影響もない。
こういった事情が英語を生徒にとって「なじみのない訳の分からないもの」という印象を抱かせ、「理解できないから苦手」という意識を持たせるのかも知れません。
しかし、現在はインターネットが発達しており、そこから英字新聞や英語ニュースなどをかんたんに入手することができます。
そこで今回は英字新聞を使った英語の勉強について考えてみたいと思います。








お勧めの英字新聞や英語ニュースサイト
英字新聞や英語ニュースと聞くと難しそうに思われますが、中には中学生や小学生向け、英語初心者向けの英字新聞やニュースサイトもありますから、そこから英語の勉強を始めるといいでしょう。
1.『やさしく読める英語ニュース』
『やさしく読める英語ニュース』へのリンクはこちら
こちらは英語教員のためのポータルサイトである『えいごネット』の中のコンテンツになります。
掲載されている記事は短めになっているので、英語初心者でも読みやすくなっています。
語彙も中学生レベルで読めるようになっており、読みながら英語の実力をつけていくにはちょうど良い内容になっています。
ニュースはジャンル別に分けられているので、最初のうちは自分の興味関心のあるものだけ読んでも構いません。
慣れてくれば幅を広げていき、偏りのない英語力をつけてくれればいいでしょう。
日本語訳もついており、見比べることで対訳も分かりやすくなっています。
重要な語彙は赤字になっており、別枠で説明もついているので、本当に分かりやすいです。
しかも音声までついているので、ネイティブの発音を聴きながらリスニングとスピーキングの勉強にもなります。
プリントアウトもできるので、自分の読んだ記事を集めてスクラップブックのようにして、英語の練習や参考書のように利用するのも良い方法かと考えます。
こちらは英語教員のためのポータルサイトである『えいごネット』の中のコンテンツになります。
掲載されている記事は短めになっているので、英語初心者でも読みやすくなっています。
語彙も中学生レベルで読めるようになっており、読みながら英語の実力をつけていくにはちょうど良い内容になっています。
ニュースはジャンル別に分けられているので、最初のうちは自分の興味関心のあるものだけ読んでも構いません。
慣れてくれば幅を広げていき、偏りのない英語力をつけてくれればいいでしょう。
日本語訳もついており、見比べることで対訳も分かりやすくなっています。
重要な語彙は赤字になっており、別枠で説明もついているので、本当に分かりやすいです。
しかも音声までついているので、ネイティブの発音を聴きながらリスニングとスピーキングの勉強にもなります。
プリントアウトもできるので、自分の読んだ記事を集めてスクラップブックのようにして、英語の練習や参考書のように利用するのも良い方法かと考えます。
2.NHK WORLD-JAPAN
『NHK WORLD-JAPAN』へのリンクはこちら
こちらはNHKが提供するサイトになります。
NHKが放送しているニュースと同じ内容になっていますので、日本語のニュースを見てから英語のニュースを見ると分かりやすいかも知れません。
動画を見ながら英語を聞くので、より内容をつかみやすくなります。
また、英文もついていますので、読み取りの練習もできます。
更にこのサイトのいいところはニュース以外のコンテンツもあるところです。
オンデマンドではアニメやドキュメンタリーなど、多岐に渡る内容の番組を見ることができます。
個人的に注目するのは『Learn Japanese』で、外国の方が日本語の勉強に役立つ内容となっております。
確かに外国人向けですが、日本語の初歩が学べます。
これは同時に英語を勉強するのにも利用できます。
簡単な日本語を英語で何と言うのか、どのように表現するのかが分かります。
そういう意味では英語の勉強にも役立つコーナーとなっております。
こちらはNHKが提供するサイトになります。
NHKが放送しているニュースと同じ内容になっていますので、日本語のニュースを見てから英語のニュースを見ると分かりやすいかも知れません。
動画を見ながら英語を聞くので、より内容をつかみやすくなります。
また、英文もついていますので、読み取りの練習もできます。
更にこのサイトのいいところはニュース以外のコンテンツもあるところです。
オンデマンドではアニメやドキュメンタリーなど、多岐に渡る内容の番組を見ることができます。
個人的に注目するのは『Learn Japanese』で、外国の方が日本語の勉強に役立つ内容となっております。
確かに外国人向けですが、日本語の初歩が学べます。
これは同時に英語を勉強するのにも利用できます。
簡単な日本語を英語で何と言うのか、どのように表現するのかが分かります。
そういう意味では英語の勉強にも役立つコーナーとなっております。
英字新聞や英語ニュースを見るメリット
1.簡潔で正しい英語を学べる
ニュースは正確で分かりやすくなければなりません。
そのため正しい英語が使われます。
そして、長々と書くと読者も疲れてしまいますので、簡潔でまとまった文章になっています。
ニュースで使われている表現や書き方を身に付けると、レポートやプレゼンテーション、相手への説明などをするとき上手にできます。
学校でも文章を書く機会は増えていますので、是非、身に付けてほしいスキルでもあります。
そのため正しい英語が使われます。
そして、長々と書くと読者も疲れてしまいますので、簡潔でまとまった文章になっています。
ニュースで使われている表現や書き方を身に付けると、レポートやプレゼンテーション、相手への説明などをするとき上手にできます。
学校でも文章を書く機会は増えていますので、是非、身に付けてほしいスキルでもあります。
2.常に新しい英文に触れ語彙力が上がる
ニュースなので毎日のように新しい文章が書かれます。
つまり、様々な内容と表現にである機会があるということです。
多様な英文に触れることで語彙力や表現力がつきます。
例えば「地球温暖化」や「持続可能な発展」など、少し専門的な用語はニュースにはよく出てくるので、ニュースを通してたくさん覚えることができます。
重要な表現や基礎的な言葉は何度も繰り返し出てきますので、自然と覚えることもできます。
また、ニュースは人に説明するという使命があるので、英語で物事を描写し伝える能力も身に付きます。
そして、いつも新しいことに触れるので、英文を読んだり聞いたりして飽きることがありません。
つまり、様々な内容と表現にである機会があるということです。
多様な英文に触れることで語彙力や表現力がつきます。
例えば「地球温暖化」や「持続可能な発展」など、少し専門的な用語はニュースにはよく出てくるので、ニュースを通してたくさん覚えることができます。
重要な表現や基礎的な言葉は何度も繰り返し出てきますので、自然と覚えることもできます。
また、ニュースは人に説明するという使命があるので、英語で物事を描写し伝える能力も身に付きます。
そして、いつも新しいことに触れるので、英文を読んだり聞いたりして飽きることがありません。
3.四技能が上達する
特に動画や音声と組み合わせることで、英語を理解しやすくなりますし、「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能全てを訓練することができます。
ネイティブの英語に触れることで、より自然な英語が身に付きます。
高校入試で「スピーキングテスト」が導入され、今後ますます「話す」力も重視されます。
これまではあまり力点を置かれていませんでしたが、これからはTOEFLのように総合的な英語力が要求されます。
そして、これら四技能すべてをバランスよく学ぶには英字新聞や英語ニュースがとても良い練習になります。
特にニュースはネイティブの自然なスピードで話されるので、聞き取りや発話のときのスピードアップにつながります。
ネイティブの英語に触れることで、より自然な英語が身に付きます。
高校入試で「スピーキングテスト」が導入され、今後ますます「話す」力も重視されます。
これまではあまり力点を置かれていませんでしたが、これからはTOEFLのように総合的な英語力が要求されます。
そして、これら四技能すべてをバランスよく学ぶには英字新聞や英語ニュースがとても良い練習になります。
特にニュースはネイティブの自然なスピードで話されるので、聞き取りや発話のときのスピードアップにつながります。
4.英語を使って知識が増える
環境問題などニュースに出てくる話題を通して様々な話題に触れ、その知識を増やすことができます。
しかも、英語で説明されますので、英語での理解ができるようになります。
英語や国語などで長文の問題をするとき、その内容についての予備知識があると親しみがわき、問題を解くのにも苦痛が和らぎます。
予備知識があれば分からない部分を自分で補うことができるので、実際に書かれていることが分からなくても内容理解ができます。
こうなればテストや勉強で問題を解くのも楽になります。
そのためにはどのようなトピックでもある程度分かるように、自分の雑学を広げる必要があります。
自分の知っている領域を増やすためにも、英語のニュースや記事を聴いたり読んだりすることは非常に有効な勉強になります。
しかも、英語で説明されますので、英語での理解ができるようになります。
英語や国語などで長文の問題をするとき、その内容についての予備知識があると親しみがわき、問題を解くのにも苦痛が和らぎます。
予備知識があれば分からない部分を自分で補うことができるので、実際に書かれていることが分からなくても内容理解ができます。
こうなればテストや勉強で問題を解くのも楽になります。
そのためにはどのようなトピックでもある程度分かるように、自分の雑学を広げる必要があります。
自分の知っている領域を増やすためにも、英語のニュースや記事を聴いたり読んだりすることは非常に有効な勉強になります。
英字新聞や英語ニュースで勉強するときの注意点
一番重要なことは「自分に合った英字新聞や英語ニュースを見つける」ことです。
一般的に英字新聞やニュースはネイティブの人が利用しているものなので、英語レベルとしては少し高いものとなっています。
従って、初級者には難しすぎる場合があります。
自分の英語レベルをよく理解し、中学生など英語力がまだ十分についていない人は、子供向けの新聞やニュース、日本の中学生向けのものを選んでください。
始めから高すぎる英語に挑戦するのは、反って英語力がつかず、うまくいかない経験は英語そのものに対する嫌悪感につながることがあります。
最初は無理せず、簡単なものから取り組んでみましょう。
次に、新聞やニュースは毎日更新され、常に新鮮な英語に触れることができます。
だから、短いもので構いませんので毎日続けるようにしましょう。
一日10分でもいいので、新聞の英語を読んだりニュースを聞いたりしましょう。
そうして、毎日英語に触れる習慣を身に付ければ、日常に英語の馴染みのない日本の生活でも、英語を身近なものとして学習することができます。
更に、受動的に英語を見たり聞いたりするだけでなく、ニュースの内容から一言でいいから、自分の考えをまとめたり説明したりできると素晴らしいです。
このような練習は今話題のスピーキングテスト対策になると同時に、英語をより実践的なものとして習得することができるでしょう。
可能ならばいっしょに英語の記事やニュースを見る仲間を作り、その人たちと意見交換(難しければ最初は日本語でも構いません)できると、より英語力を発達させることができます。








今回は英字新聞や英語ニュースを利用しての英語の勉強を考えてみました。
現代はインターネットが発達しているので、これらのメディアに触れることが非常に簡単になっています。
無料のものも多く、インプットだけでなくアウトプットもうまく組み合わせれば、英語力がますますアップするでしょう。
しかも、このやり方では英語が上達するだけでなく、より多くの一般的知識を身に付けることもできます。
つまり、単純な英語の勉強としてだけでなく、人間としての厚みを増すことにもつながることです。
最初は手間取るかも知れませんが、慣れてくればきっと内容が理解できるようになり、楽しく勉強できると思います。
明るい話題や考えさせられるトピックなど多岐に渡る話に触れることができるので、思考の発達が促されるでしょう。
確かに注意すべき点もありますが、これらのメディアを上手く使って英語の勉強に役立ててみてはいかがでしょうか。
























一般的に英字新聞やニュースはネイティブの人が利用しているものなので、英語レベルとしては少し高いものとなっています。
従って、初級者には難しすぎる場合があります。
自分の英語レベルをよく理解し、中学生など英語力がまだ十分についていない人は、子供向けの新聞やニュース、日本の中学生向けのものを選んでください。
始めから高すぎる英語に挑戦するのは、反って英語力がつかず、うまくいかない経験は英語そのものに対する嫌悪感につながることがあります。
最初は無理せず、簡単なものから取り組んでみましょう。
次に、新聞やニュースは毎日更新され、常に新鮮な英語に触れることができます。
だから、短いもので構いませんので毎日続けるようにしましょう。
一日10分でもいいので、新聞の英語を読んだりニュースを聞いたりしましょう。
そうして、毎日英語に触れる習慣を身に付ければ、日常に英語の馴染みのない日本の生活でも、英語を身近なものとして学習することができます。
更に、受動的に英語を見たり聞いたりするだけでなく、ニュースの内容から一言でいいから、自分の考えをまとめたり説明したりできると素晴らしいです。
このような練習は今話題のスピーキングテスト対策になると同時に、英語をより実践的なものとして習得することができるでしょう。
可能ならばいっしょに英語の記事やニュースを見る仲間を作り、その人たちと意見交換(難しければ最初は日本語でも構いません)できると、より英語力を発達させることができます。








今回は英字新聞や英語ニュースを利用しての英語の勉強を考えてみました。
現代はインターネットが発達しているので、これらのメディアに触れることが非常に簡単になっています。
無料のものも多く、インプットだけでなくアウトプットもうまく組み合わせれば、英語力がますますアップするでしょう。
しかも、このやり方では英語が上達するだけでなく、より多くの一般的知識を身に付けることもできます。
つまり、単純な英語の勉強としてだけでなく、人間としての厚みを増すことにもつながることです。
最初は手間取るかも知れませんが、慣れてくればきっと内容が理解できるようになり、楽しく勉強できると思います。
明るい話題や考えさせられるトピックなど多岐に渡る話に触れることができるので、思考の発達が促されるでしょう。
確かに注意すべき点もありますが、これらのメディアを上手く使って英語の勉強に役立ててみてはいかがでしょうか。
























2023.08.08
言語学習で行われるシャドーイングとは
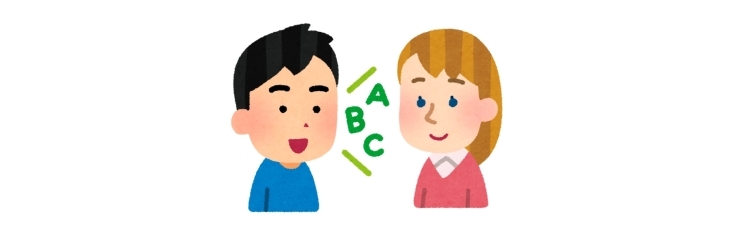
今や小学校から英語が正式教科になっています。
これまでの知識としての英語から、実際にコミュニケーションを通じて海外の人たちと交流できる使える英語へと、学校の英語教育も変わってきています。
「読む」「書く」が中心だった英語学習も、「聴く」から「話す」まで含めた総合的なものが求められています。
特に、「聴く」「話す」能力となると、これまでの学校教育を受けてきた先生方にとって、非常に指導しづらいものであります。
そこで今回は、英語に限らず言語学習の場でよく使われている学習法であるシャドーイングについてお話したいと思います。









これまでの知識としての英語から、実際にコミュニケーションを通じて海外の人たちと交流できる使える英語へと、学校の英語教育も変わってきています。
「読む」「書く」が中心だった英語学習も、「聴く」から「話す」まで含めた総合的なものが求められています。
特に、「聴く」「話す」能力となると、これまでの学校教育を受けてきた先生方にとって、非常に指導しづらいものであります。
そこで今回は、英語に限らず言語学習の場でよく使われている学習法であるシャドーイングについてお話したいと思います。









シャドーイングとは
シャドーイングとは、音声を聞きながらその音声を真似て発音する学習法です。
音声を影のようにぴったりついていきながら、自分も発音するのでシャドーイングと言います。
特徴としては、音を聞いてから発音するのではなく、「聴きながら発音する」点です。
「聴く」というインプットと「話す」というアウトプットを同時にやるので効率よく練習ができるのです。
よって、リスニングとスピーキングの両方を鍛えたい人にはお勧めです。
特に最近では、都立高校入試にスピーキングテストが導入されましたが、学校も含めその指導は十分に確立していないのが現状です。
だから、受験生は自分たちで何とかしないといけないのですが、そんな時にもシャドーイングは役に立つでしょう。
音声を影のようにぴったりついていきながら、自分も発音するのでシャドーイングと言います。
特徴としては、音を聞いてから発音するのではなく、「聴きながら発音する」点です。
「聴く」というインプットと「話す」というアウトプットを同時にやるので効率よく練習ができるのです。
よって、リスニングとスピーキングの両方を鍛えたい人にはお勧めです。
特に最近では、都立高校入試にスピーキングテストが導入されましたが、学校も含めその指導は十分に確立していないのが現状です。
だから、受験生は自分たちで何とかしないといけないのですが、そんな時にもシャドーイングは役に立つでしょう。
シャドーイングのやり方
ただ聴いた英語をそのまま自分の頭の中で聞こえたように発音すづだけではいけません。
それでは正確な発音は身に付かない恐れがあります(俗に言う「そら耳」です)。
従って、最初から段階的にシャドーイングを強化していくのがいいでしょう。
それでは正確な発音は身に付かない恐れがあります(俗に言う「そら耳」です)。
従って、最初から段階的にシャドーイングを強化していくのがいいでしょう。
1.音声を聴いて原稿と見比べる
先ずは音声を聴いてみます。
その後、その音声の原稿を見て、自分がどこを聴き取れていなかったか確認します。
原稿を見て理解できた部分は聴き取りの弱い部分、原稿を見ても理解できなかった部分はそもそも英語力不足だった部分です。
こうして自分の弱点をあらかじめ知っておくということは、効率よい勉強には必要です。
その後、その音声の原稿を見て、自分がどこを聴き取れていなかったか確認します。
原稿を見て理解できた部分は聴き取りの弱い部分、原稿を見ても理解できなかった部分はそもそも英語力不足だった部分です。
こうして自分の弱点をあらかじめ知っておくということは、効率よい勉強には必要です。
2.区切りながら発音してみる
シャドーイングは音声を聴きながら発音しなくてはいけないのですが、いきなりそれをしろというのは酷な話です。
先ずは、一文ずつに区切って練習しましょう。
この時、文法などの細かい点にこだわって理解するのではなく、一文全体として伝えていことを理解するようにしましょう。
知らない単語があれば覚えないといけないし、音声を聴いて正しい発音を身に付けなければなりません。
このようにして英語の基礎的な語彙などを増やして、シャドーイングの土台を作ります。
先ずは、一文ずつに区切って練習しましょう。
この時、文法などの細かい点にこだわって理解するのではなく、一文全体として伝えていことを理解するようにしましょう。
知らない単語があれば覚えないといけないし、音声を聴いて正しい発音を身に付けなければなりません。
このようにして英語の基礎的な語彙などを増やして、シャドーイングの土台を作ります。
3.聴きながら読みながら発音してみる
いよいよ音声を聴きながら発音してみます。
原稿を指差ししながら文字を追って、自分なりに英語を発音していきましょう。
音声がどのように話しているかに注意しつつ、自分も同じように話してみます。
この時に意味も考えられるといいです。
文字と音声の二つのサポートがあるので、意味の理解はそれほど難しくはないと思います。
発音がどうしても追いつかないときは「口パク」でも構いません。
原稿を指差ししながら文字を追って、自分なりに英語を発音していきましょう。
音声がどのように話しているかに注意しつつ、自分も同じように話してみます。
この時に意味も考えられるといいです。
文字と音声の二つのサポートがあるので、意味の理解はそれほど難しくはないと思います。
発音がどうしても追いつかないときは「口パク」でも構いません。
4.音源だけを聴きながら発音する
慣れてきたら原稿を閉じて、音声だけを頼りに発音してみましょう。
上手くいかなければ音声のスピードを落としてみたり、もう一度原稿を見て発音するところまで戻って練習してください。
上手くいかなければ音声のスピードを落としてみたり、もう一度原稿を見て発音するところまで戻って練習してください。
シャドーイングのメリット
シャドーイングのメリットとしては、その言語独特のリズム、音のまとまりと区切り、アクセントやイントネーションを習得できることです。
これは「読む」「書く」だけの勉強では身に付きにくい点です。
そして、言語をそのまま聴いて理解するので、リスニングも頭から言葉を理解できるようになり、よりネイティブに近い思考で言語運用ができるようになります。
これまでの文法中心の英語学習では日本語に訳すことが重視され、その時に英語を日本語の語順に置き換えて理解していました。
しかし、テンポよい言葉のキャッチボールが求められる実践の場では、これではコミュニケーションがうまくできません。
シャドーイングでは、ネイティブのように聴いた言葉を、そのままその言語で理解するので、よりスピーディーな会話もできるようになります。
そして、その言語の音声的特徴を理解し、音声そのままの聴き取りができるということは、同様にその言語の話者と同じように話すこともできるということになります。
つまり、シャドーイングでリスニングが強化されると、自然にスピーキングも強化されるということです。
この時も、ネイティブと同じようにその言語でそのまま考えることができるようになるため、より実践的で自然な発音とコミュニケーション能力が身に付きます。
シャドーイングをすれば音声で単語やフレーズに多く触れるようになるので、ただ見て覚えるより語彙が定着しやすくなります。
ネイティブのように考えることができるようになると、その言語の仕組みも分かり文法力も上がります。
これは「読む」「書く」だけの勉強では身に付きにくい点です。
そして、言語をそのまま聴いて理解するので、リスニングも頭から言葉を理解できるようになり、よりネイティブに近い思考で言語運用ができるようになります。
これまでの文法中心の英語学習では日本語に訳すことが重視され、その時に英語を日本語の語順に置き換えて理解していました。
しかし、テンポよい言葉のキャッチボールが求められる実践の場では、これではコミュニケーションがうまくできません。
シャドーイングでは、ネイティブのように聴いた言葉を、そのままその言語で理解するので、よりスピーディーな会話もできるようになります。
そして、その言語の音声的特徴を理解し、音声そのままの聴き取りができるということは、同様にその言語の話者と同じように話すこともできるということになります。
つまり、シャドーイングでリスニングが強化されると、自然にスピーキングも強化されるということです。
この時も、ネイティブと同じようにその言語でそのまま考えることができるようになるため、より実践的で自然な発音とコミュニケーション能力が身に付きます。
シャドーイングをすれば音声で単語やフレーズに多く触れるようになるので、ただ見て覚えるより語彙が定着しやすくなります。
ネイティブのように考えることができるようになると、その言語の仕組みも分かり文法力も上がります。
シャドーイングの注意点
このようにシャドーイングを活用すれば、リスニングとスピーキングが上達し、語彙力や文法、英語的思考も身に付くわけですが、その運用には注意も必要です。
先ず、最大の注意点として、いきなりシャドーイングをしてはいけないという点があります。
聞きながら理解しながら話すわけで、それができるようになるにはある程度の英語の下地ができていないといけません。
よって、初心者がいきなりシャドーイングを始めるのはあまり効果が期待できません。
もし初心者が試みるなら、初心者に相応しい、短く分かりやすいものを選びましょう。
そして、シャドーイングも全て分かろうとするのではなく、最初は単語レベルから聞き取れれば上出来です。
慣れてくれば、フレーズレベル、文レベル、文章レベルとだんだんできるようになります。
焦ってはいけません。
先ほどのことと関連しますが、自分に合った音声を選ぶことも重要です。
難しすぎても簡単すぎても行けません。
「α+1」とよく言われますが、現在の自分の能力に1だけプラスした程度がちょうど良いとされています。
そして、教材選びもわざわざシャドーイング専用のものを探す必要はありません。
最近は一般的な長文の問題集でもQRコードがついており、スマホやアプリを利用して音声を聴くことができます。
しかも、音声の速度を調整する機能がついているものも多いので、自分の英語力に合わせて調整できます。
また、Youtubeや専用アプリを使ってシャドーイングをすることも可能です。
最後の注意点として、必ず誰かに聴いてもらう機会を設けましょう。
自分一人で進めると間違ったアクセントや発音があっても気づきにくいものです。
これまで頑張ってきた成果をチェックしてもらって、「自分は本当に正しくシャドーイングができているか」「スピーキングが自己流になっていないか」など確認しましょう。









以上、シャドーイングの説明でした。
確かにシャドーイングは初級レベルの生徒たちには活用が難しいかも知れません。
しかし、やり方のコツと意義をきちんと理解すれば、英語上達に大きな力となるでしょう。
最初は上手くいかないかもしれませんが、自分を信じて根気よく毎日練習するといいでしょう。
そして、うまくいった暁には、ネイティブに近い英語力が身に付くはずです。
勉強は人によって千差万別、向き不向きがあります。
どれがうまくいくかはやってみないと分からない部分が多くあります。
だからこそ、様々な方法を試して自分に最も合った勉強法を見つける必要があります。
今回のシャドーイングは、結果を出せれば自分の能力を大幅にアップすることができますので、是非お試しいただきたいと考えます。
もし勉強で困ったことや分からないことがあれば、いつでも葛西TKKアカデミーまでご相談ください。
お待ちしております。



























先ず、最大の注意点として、いきなりシャドーイングをしてはいけないという点があります。
聞きながら理解しながら話すわけで、それができるようになるにはある程度の英語の下地ができていないといけません。
よって、初心者がいきなりシャドーイングを始めるのはあまり効果が期待できません。
もし初心者が試みるなら、初心者に相応しい、短く分かりやすいものを選びましょう。
そして、シャドーイングも全て分かろうとするのではなく、最初は単語レベルから聞き取れれば上出来です。
慣れてくれば、フレーズレベル、文レベル、文章レベルとだんだんできるようになります。
焦ってはいけません。
先ほどのことと関連しますが、自分に合った音声を選ぶことも重要です。
難しすぎても簡単すぎても行けません。
「α+1」とよく言われますが、現在の自分の能力に1だけプラスした程度がちょうど良いとされています。
そして、教材選びもわざわざシャドーイング専用のものを探す必要はありません。
最近は一般的な長文の問題集でもQRコードがついており、スマホやアプリを利用して音声を聴くことができます。
しかも、音声の速度を調整する機能がついているものも多いので、自分の英語力に合わせて調整できます。
また、Youtubeや専用アプリを使ってシャドーイングをすることも可能です。
最後の注意点として、必ず誰かに聴いてもらう機会を設けましょう。
自分一人で進めると間違ったアクセントや発音があっても気づきにくいものです。
これまで頑張ってきた成果をチェックしてもらって、「自分は本当に正しくシャドーイングができているか」「スピーキングが自己流になっていないか」など確認しましょう。









以上、シャドーイングの説明でした。
確かにシャドーイングは初級レベルの生徒たちには活用が難しいかも知れません。
しかし、やり方のコツと意義をきちんと理解すれば、英語上達に大きな力となるでしょう。
最初は上手くいかないかもしれませんが、自分を信じて根気よく毎日練習するといいでしょう。
そして、うまくいった暁には、ネイティブに近い英語力が身に付くはずです。
勉強は人によって千差万別、向き不向きがあります。
どれがうまくいくかはやってみないと分からない部分が多くあります。
だからこそ、様々な方法を試して自分に最も合った勉強法を見つける必要があります。
今回のシャドーイングは、結果を出せれば自分の能力を大幅にアップすることができますので、是非お試しいただきたいと考えます。
もし勉強で困ったことや分からないことがあれば、いつでも葛西TKKアカデミーまでご相談ください。
お待ちしております。



























2023.08.06
夏休みの宿題をゆとりを持って終わらせよう

八月に入り、「まだ夏休みが終わるまで余裕がある」と油断していませんか。
そう思って気づけば夏休み終了一週間前、慌ててバタバタと課題をやるけどいい作品は出来ず、その場しのぎのみすぼらしい提出物ではよい評価は得られません。
みすぼらしくても期限に提出できればいいのですが、中には物理的に考えて絶対無理な状況に陥ってしまうこともあります。
そうなれば、良い評価どころか減点になり、成績にも大きく響いてしまいます。
そうならないためにも夏休みの宿題はゆとりを持って終わらせたいものです。
しかし、現実には分かっていてもなかなかできません。
特に小学生(時には中学生や高校生でもそうですが)は、自己管理がまだしっかりできず、自分一人で計画的に夏休みの宿題を終わらせるのは非常に難しいでしょう。
そこで、今回は夏休みの宿題をゆとりを持って終わらせるにはどうすればいいか考えてみたいと思います。










そう思って気づけば夏休み終了一週間前、慌ててバタバタと課題をやるけどいい作品は出来ず、その場しのぎのみすぼらしい提出物ではよい評価は得られません。
みすぼらしくても期限に提出できればいいのですが、中には物理的に考えて絶対無理な状況に陥ってしまうこともあります。
そうなれば、良い評価どころか減点になり、成績にも大きく響いてしまいます。
そうならないためにも夏休みの宿題はゆとりを持って終わらせたいものです。
しかし、現実には分かっていてもなかなかできません。
特に小学生(時には中学生や高校生でもそうですが)は、自己管理がまだしっかりできず、自分一人で計画的に夏休みの宿題を終わらせるのは非常に難しいでしょう。
そこで、今回は夏休みの宿題をゆとりを持って終わらせるにはどうすればいいか考えてみたいと思います。










周囲のサポートは必要
夏休みの宿題は自分でやるものだから、最初から最後まで一人で終わらせるのが理想です。
学校側もその建前で宿題を出しているのでしょうが、現実にはそこまで期待はしていないでしょう。
特に低学年で完璧な自己管理を求めるのが酷なことは学校も分かっています。
だから、周囲の人間が子供の宿題に手や口を出してはいけないという訳ではありません。
もちろん、宿題をやる主体は本人でないといけませんが、宿題をより有効に終わらせるには、時には周囲の人間が声掛けをしたり、アドバイスを与えたり、場合によっては手伝ったりすることも必要です。
こういう交流も一つの学びであり、そこから多くのことを子供たちが勉強できれば、それはそれで十分価値があると思います。
したがって、親や周囲の人間は手を出してはいけないという訳ではないことを理解していただきたいと思います。
何でもかんでも本人の責任と放置するのは、反って夏休みの宿題の意義を失わせて、実りの少ない結果につながってしまいます。
皆さんもお忙しいとは思いますが、子供の学びと成長のためにも夏休みの宿題に関わってほしいです。
どうしても忙しすぎてできないときは、葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
お手伝いいたします。
学校側もその建前で宿題を出しているのでしょうが、現実にはそこまで期待はしていないでしょう。
特に低学年で完璧な自己管理を求めるのが酷なことは学校も分かっています。
だから、周囲の人間が子供の宿題に手や口を出してはいけないという訳ではありません。
もちろん、宿題をやる主体は本人でないといけませんが、宿題をより有効に終わらせるには、時には周囲の人間が声掛けをしたり、アドバイスを与えたり、場合によっては手伝ったりすることも必要です。
こういう交流も一つの学びであり、そこから多くのことを子供たちが勉強できれば、それはそれで十分価値があると思います。
したがって、親や周囲の人間は手を出してはいけないという訳ではないことを理解していただきたいと思います。
何でもかんでも本人の責任と放置するのは、反って夏休みの宿題の意義を失わせて、実りの少ない結果につながってしまいます。
皆さんもお忙しいとは思いますが、子供の学びと成長のためにも夏休みの宿題に関わってほしいです。
どうしても忙しすぎてできないときは、葛西TKKアカデミーまでご連絡ください。
お手伝いいたします。
夏休みの宿題がなかなか終わらない理由
夏休みの宿題がなかなか終わらないのはどうしてでしょうか。
学校が無茶な量の宿題を押し付けているのでしょうか。
そんなことはありません。
毎日きちんとやれば終わる、妥当な量だと思います。
では、なぜ終わらないのでしょうか。
それは前提の「毎日きちんとやれば」というところが、現実になかなか難しいのです。
何もなく本人にまかせっきりでは、宿題をちゃんと終わらせることは、ほぼ不可能でしょう。
子供たちは経験も浅く、何をいつどの程度やらないといけないかを上手く理解することはできません。
「夏休みだからこそ、普段できないことをしたい」
「学校がないから、いつもよりたくさん遊びたい」
「40日もあるのだから、慌てて取り掛からなくても大丈夫」
このような心理(油断と願望)は理解できなくはありませんが、それに任せて子供たちの行動を放任すれば、気づいた時には時間が足らず手遅れという事態に陥るでしょう。
余談ですが、そもそも「夏休み」という言葉が、子供たちに「勉強しないで遊んでいい」という発想をもたらすのではないでしょうか。
「休み」となれば、仕事をしないで自分の好きなように過ごしていいという解釈に至るのは当然です。
いっそ「夏の長期家庭学習」なんてした方が、少しは良くなる気がしますが。
いずれにしても「休み」というイメージが、子供を勉強に向かいづらくしているのは確かかも知れません。
また、やる気はあったも何をどうすればいいか分からないという生徒もたくさんいます。
ワークのような、自分がしなくてはいけない内容がはっきりしている場合はまだいいのですが、夏休みの宿題の中には自由研究や作文、工作やポスターなど、明確に細かくこうしなさいと指示されないものが沢山あります。
自分たちで何をどうやって完成させるか考えないといけない宿題です。
こういった場合は、人生経験の少ない多く子供たちは手づまりになってしまいます。
何をしていいか全く思い浮かばないのです。
時には思いも及ばない素晴らしいアイデアがひらめくこともありますが、それはどちらかというとマイナーなケースです。
この最初の一歩でつまづいて先に進めないため、何をしていいか分からないまま時間だけが過ぎ、気づけば夏休みも終わりとなってしまうのです。
学校が無茶な量の宿題を押し付けているのでしょうか。
そんなことはありません。
毎日きちんとやれば終わる、妥当な量だと思います。
では、なぜ終わらないのでしょうか。
それは前提の「毎日きちんとやれば」というところが、現実になかなか難しいのです。
何もなく本人にまかせっきりでは、宿題をちゃんと終わらせることは、ほぼ不可能でしょう。
子供たちは経験も浅く、何をいつどの程度やらないといけないかを上手く理解することはできません。
「夏休みだからこそ、普段できないことをしたい」
「学校がないから、いつもよりたくさん遊びたい」
「40日もあるのだから、慌てて取り掛からなくても大丈夫」
このような心理(油断と願望)は理解できなくはありませんが、それに任せて子供たちの行動を放任すれば、気づいた時には時間が足らず手遅れという事態に陥るでしょう。
余談ですが、そもそも「夏休み」という言葉が、子供たちに「勉強しないで遊んでいい」という発想をもたらすのではないでしょうか。
「休み」となれば、仕事をしないで自分の好きなように過ごしていいという解釈に至るのは当然です。
いっそ「夏の長期家庭学習」なんてした方が、少しは良くなる気がしますが。
いずれにしても「休み」というイメージが、子供を勉強に向かいづらくしているのは確かかも知れません。
また、やる気はあったも何をどうすればいいか分からないという生徒もたくさんいます。
ワークのような、自分がしなくてはいけない内容がはっきりしている場合はまだいいのですが、夏休みの宿題の中には自由研究や作文、工作やポスターなど、明確に細かくこうしなさいと指示されないものが沢山あります。
自分たちで何をどうやって完成させるか考えないといけない宿題です。
こういった場合は、人生経験の少ない多く子供たちは手づまりになってしまいます。
何をしていいか全く思い浮かばないのです。
時には思いも及ばない素晴らしいアイデアがひらめくこともありますが、それはどちらかというとマイナーなケースです。
この最初の一歩でつまづいて先に進めないため、何をしていいか分からないまま時間だけが過ぎ、気づけば夏休みも終わりとなってしまうのです。
夏休みの宿題をゆとりを持って終わらせるには
それでは夏休みの宿題をゆとりをもって終わらせるにはどうすればいいのでしょうか。
これまで見てきたように、基本となるポイントは2点。
先ず、子供たちには自己管理がまだできないこと、そして、何をどうすればいいか分からないこと。
前者に関しては、子供と一緒に夏休みがなぜあるのか、どのように過ごせばいいのかなど、夏休みというものについて根本的に見直してみます。
そうすることで好き勝手にだらだら過ごして良いものではないことが理解できるでしょう。
もちろん夏休みという時間的に余裕のある時だからこそできることもありますし、外に出て友達と一緒に遊ぶのも子供時代の良い経験として必要です。
だから、すべての時間を夏休みの宿題に捧げろという訳ではありません。
大事なのはバランスよく、計画的に毎日を過ごすことです。
ここにおいて大人の経験やアドバイスは重要です。
よく分からないからこそ、大人の意見を参考に自分でどうすればいいか考えるのです。
そして、一緒に夏休みの計画を作ります。
休みの間を通しての長期的計画ももちろんですが、毎日の生活スケジュールも大事です。
子どもと一緒によく話し合って、本人も納得した上で責任もって計画を実行するようにしましょう。
そして、その計画を家族みんなが見える所に貼りましょう。
このように視覚化することと誰もが共有できるようにすることが重要です。
こうして家族全員が分かれば、お互いに計画を守れるように声掛けをすることもできます。
子どもにとっても一番嫌な、「やろうと思ったところで言われる」「今は遊びの時間で勉強の時間になればやろうと思っていたのに」などという事態を回避できるのでいいです。
このように毎日をメリハリをつけて生活すれば、精神的にもゆとりができ、余裕をもって夏休みの宿題も終わらせることができます。
また、後者に関しては、知識や経験の乏しい子供たちに自分だけで何かを考え付くことは難しいと思います。
だから、それらを補える大人がアイデアを出してあげる必要があります。
本人の好みや希望を聞きながら、自分の経験、インターネットや書籍を参考に、どんなことができるが考えましょう。
調べていくとどんどん新しいことに出会い、子供たちも楽しくなってやる気が出るように上手に誘導してあげましょう。
意外と「自分が小学生の時はこんなことをしたよ」などという話は子供も興味を持ち、自由研究をより深めるいいきっかけになります。
そして、大人自身が子供のときに経験済みならば、本当に良いアドバイスを与えられ、良い作品が出来上がることでしょう。
また、夏休みによくある特別展や旅行企画、地域のイベントなどに参加することも、自由研究のアイデアが浮かぶよいきっかけになります。
これらは子供の興味を引くように工夫されていますから、そこから刺激を受け、より詳しく調べたいという知的好奇心に導かれながら研究を自主的に進めることができるでしょう。
とにかく閉じこもっていては始まらないので、ある程度の話し合いをしたら積極的に行動してみましょう。
ただし、自由研究や工作、ポスターや読書感想文などの課題はどうしても時間が掛かってしまいます。
だから、早めに取り掛かり(遅くとも八月上旬には)、大人が間に合うように進んでいるかチェックしてあげることも大事です。










特に年齢の低い子供たちは、自分たちだけで夏休みの宿題をちゃんと終わらせるというのは難しい問題です。
だからこそ、周囲の人間の手助けが必要となります。
最初に計画し、それを守るように声掛けなどでサポートしましょう。
勉強と遊びのバランスを考えつつメリハリのある生活を送れるように支えてあげましょう。
「やれやれ」というばかりではなく、よく頑張ったらときにはご褒美を上げるのもいいことです。
「やればいいことがある」と分かれば、本人のモチベーションも上がりますから。
そして、夏休みの課題で壁にぶつかったときは、子供のできないことを責めるのではなく、どうすれば終わらせることができるかを一緒に考えてあげてください。
いつも前向きな気持ちを持ちづづけられるように、励ましてあげることが肝心です。
いろいろお話しましたが、それでもなかなかうまくいかないというときは、葛西TKKアカデミーにご相談ください。
一緒に考え、子供たちの宿題がきちんと終わるようにお手伝いいたします。






























これまで見てきたように、基本となるポイントは2点。
先ず、子供たちには自己管理がまだできないこと、そして、何をどうすればいいか分からないこと。
前者に関しては、子供と一緒に夏休みがなぜあるのか、どのように過ごせばいいのかなど、夏休みというものについて根本的に見直してみます。
そうすることで好き勝手にだらだら過ごして良いものではないことが理解できるでしょう。
もちろん夏休みという時間的に余裕のある時だからこそできることもありますし、外に出て友達と一緒に遊ぶのも子供時代の良い経験として必要です。
だから、すべての時間を夏休みの宿題に捧げろという訳ではありません。
大事なのはバランスよく、計画的に毎日を過ごすことです。
ここにおいて大人の経験やアドバイスは重要です。
よく分からないからこそ、大人の意見を参考に自分でどうすればいいか考えるのです。
そして、一緒に夏休みの計画を作ります。
休みの間を通しての長期的計画ももちろんですが、毎日の生活スケジュールも大事です。
子どもと一緒によく話し合って、本人も納得した上で責任もって計画を実行するようにしましょう。
そして、その計画を家族みんなが見える所に貼りましょう。
このように視覚化することと誰もが共有できるようにすることが重要です。
こうして家族全員が分かれば、お互いに計画を守れるように声掛けをすることもできます。
子どもにとっても一番嫌な、「やろうと思ったところで言われる」「今は遊びの時間で勉強の時間になればやろうと思っていたのに」などという事態を回避できるのでいいです。
このように毎日をメリハリをつけて生活すれば、精神的にもゆとりができ、余裕をもって夏休みの宿題も終わらせることができます。
また、後者に関しては、知識や経験の乏しい子供たちに自分だけで何かを考え付くことは難しいと思います。
だから、それらを補える大人がアイデアを出してあげる必要があります。
本人の好みや希望を聞きながら、自分の経験、インターネットや書籍を参考に、どんなことができるが考えましょう。
調べていくとどんどん新しいことに出会い、子供たちも楽しくなってやる気が出るように上手に誘導してあげましょう。
意外と「自分が小学生の時はこんなことをしたよ」などという話は子供も興味を持ち、自由研究をより深めるいいきっかけになります。
そして、大人自身が子供のときに経験済みならば、本当に良いアドバイスを与えられ、良い作品が出来上がることでしょう。
また、夏休みによくある特別展や旅行企画、地域のイベントなどに参加することも、自由研究のアイデアが浮かぶよいきっかけになります。
これらは子供の興味を引くように工夫されていますから、そこから刺激を受け、より詳しく調べたいという知的好奇心に導かれながら研究を自主的に進めることができるでしょう。
とにかく閉じこもっていては始まらないので、ある程度の話し合いをしたら積極的に行動してみましょう。
ただし、自由研究や工作、ポスターや読書感想文などの課題はどうしても時間が掛かってしまいます。
だから、早めに取り掛かり(遅くとも八月上旬には)、大人が間に合うように進んでいるかチェックしてあげることも大事です。










特に年齢の低い子供たちは、自分たちだけで夏休みの宿題をちゃんと終わらせるというのは難しい問題です。
だからこそ、周囲の人間の手助けが必要となります。
最初に計画し、それを守るように声掛けなどでサポートしましょう。
勉強と遊びのバランスを考えつつメリハリのある生活を送れるように支えてあげましょう。
「やれやれ」というばかりではなく、よく頑張ったらときにはご褒美を上げるのもいいことです。
「やればいいことがある」と分かれば、本人のモチベーションも上がりますから。
そして、夏休みの課題で壁にぶつかったときは、子供のできないことを責めるのではなく、どうすれば終わらせることができるかを一緒に考えてあげてください。
いつも前向きな気持ちを持ちづづけられるように、励ましてあげることが肝心です。
いろいろお話しましたが、それでもなかなかうまくいかないというときは、葛西TKKアカデミーにご相談ください。
一緒に考え、子供たちの宿題がきちんと終わるようにお手伝いいたします。






























2023.07.28
高校入試の英語のスピーキングテストについて(私見を含む)

夏休みに入り今年もいよいよ受験勉強に本腰を入れないといけない時期になりました。
受験生にとって、これほどまとまった時間を自由に使える夏休みは、自分の実力を大きく伸ばす最後のチャンスだと思ってください。
(冬休みは実力を伸ばす時期ではなく定着させる時期なので、新しいことを覚えるときではありません。)
この貴重な時間を無駄にして後悔することのないように、猛暑ではありますが、毎日を過ごしてください。
ところで、このように時間のある時だからこそ、普段できない勉強をするにも最適です。
中でも去年から導入された英語のスピーキングテストの対策は、学校のある時ではなかなかできないでしょう。
「何をどう勉強すればいいか分からない」という人も多いと思います。
そういう人は是非葛西TKKアカデミーにご相談ください。
こちらでしっかりご指導いたします。
また、夏休みにスピーキングテストの対策をした方が良い理由がもう一つあります。
それはスピーキングテストが他の学力テストに先んじて行われるということです。
今年は11月26日の予定です。
つまり、二学期の半ばにテストが実施されるのです。
学校の日常に忙しい二学期は到底しっかり準備することはできないでしょう。
だから、今のうちにスピーキングテストの対策をしましょう。









ところで本日のお話ですが、先ほど触れたスピーキングテストについて考えてみます。
ご存知の方も多いと思いますが、東京都教育委員会では教育改革に伴い、高校の入試制度の見直しを行いました。
そこで新たに導入されたのが、英語の話す力も評価するスピーキングテストです。
これは大学入試でも導入が図られましたが、その公平性の不安から多くの反対の声が上がり、実施直前で延期となりました。
では、なぜ高校入試で実施されるのでしょうか。
これは指摘されている問題点が解決したから実施されるのではなく、大学入試という全国規模のテストでは合意が得られなかったので、先ずは東京都という限定された範囲で実施し、そこから既成事実を作り上げることにより、大学入試での導入を実現しようという目論見が見え隠れします。
受験生にとって、これほどまとまった時間を自由に使える夏休みは、自分の実力を大きく伸ばす最後のチャンスだと思ってください。
(冬休みは実力を伸ばす時期ではなく定着させる時期なので、新しいことを覚えるときではありません。)
この貴重な時間を無駄にして後悔することのないように、猛暑ではありますが、毎日を過ごしてください。
ところで、このように時間のある時だからこそ、普段できない勉強をするにも最適です。
中でも去年から導入された英語のスピーキングテストの対策は、学校のある時ではなかなかできないでしょう。
「何をどう勉強すればいいか分からない」という人も多いと思います。
そういう人は是非葛西TKKアカデミーにご相談ください。
こちらでしっかりご指導いたします。
また、夏休みにスピーキングテストの対策をした方が良い理由がもう一つあります。
それはスピーキングテストが他の学力テストに先んじて行われるということです。
今年は11月26日の予定です。
つまり、二学期の半ばにテストが実施されるのです。
学校の日常に忙しい二学期は到底しっかり準備することはできないでしょう。
だから、今のうちにスピーキングテストの対策をしましょう。









ところで本日のお話ですが、先ほど触れたスピーキングテストについて考えてみます。
ご存知の方も多いと思いますが、東京都教育委員会では教育改革に伴い、高校の入試制度の見直しを行いました。
そこで新たに導入されたのが、英語の話す力も評価するスピーキングテストです。
これは大学入試でも導入が図られましたが、その公平性の不安から多くの反対の声が上がり、実施直前で延期となりました。
では、なぜ高校入試で実施されるのでしょうか。
これは指摘されている問題点が解決したから実施されるのではなく、大学入試という全国規模のテストでは合意が得られなかったので、先ずは東京都という限定された範囲で実施し、そこから既成事実を作り上げることにより、大学入試での導入を実現しようという目論見が見え隠れします。
スピーキングテストとは
以上のように問題のあるテストではありますが、東京都が決定したからには受験生はそのテストを甘んじて受けるしかないのですが、では、実際行われたスピーキングテストはどのようなものだったのでしょうか。
試験当日、受験生は指定された時間に各会場に集まります。
そして、受験生は指定された席に座り、そこに用意されている端末についているヘッドフォンとマイクを装着します。
時間になると一斉に試験が開始されます。
一応録音に関しては他の生徒の音声が混入することはないようになっているようです。
テストはこの端末の指示に従い行われ、受験生が発した音声は端末に記録され、それを基にスピーキングテストの結果が出ます。
だから、事前に機器の操作や試験の概要を把握することは必須で、いきなりぶっつけ本番では絶対に上手くいきません。
テスト前に十分な準備をすることが高得点のカギです。
テストはA~Dの四つのパートに分かれていて、パートAは短めの英語の文章を読む問題、バートBは図表を見ながら質問に答える問題、パートCは4コマで示されているお話を英語で説明する問題、パートDは答えが限定されないオープンクエスチョンに対し理由も含めて自分の考えを答える問題です。
端末で録音された音声が母語話者である採点者に送られ、最終的にはA~Fの6段階で評価され、それぞれのランクに合わせAが20点、Bが16点と4点刻みでFは0点となります。
試験当日、受験生は指定された時間に各会場に集まります。
そして、受験生は指定された席に座り、そこに用意されている端末についているヘッドフォンとマイクを装着します。
時間になると一斉に試験が開始されます。
一応録音に関しては他の生徒の音声が混入することはないようになっているようです。
テストはこの端末の指示に従い行われ、受験生が発した音声は端末に記録され、それを基にスピーキングテストの結果が出ます。
だから、事前に機器の操作や試験の概要を把握することは必須で、いきなりぶっつけ本番では絶対に上手くいきません。
テスト前に十分な準備をすることが高得点のカギです。
テストはA~Dの四つのパートに分かれていて、パートAは短めの英語の文章を読む問題、バートBは図表を見ながら質問に答える問題、パートCは4コマで示されているお話を英語で説明する問題、パートDは答えが限定されないオープンクエスチョンに対し理由も含めて自分の考えを答える問題です。
端末で録音された音声が母語話者である採点者に送られ、最終的にはA~Fの6段階で評価され、それぞれのランクに合わせAが20点、Bが16点と4点刻みでFは0点となります。
スピーキングテストの問題点
大学入試のときもそうですが、英語のスピーキングテストの導入には多くの反対の声があります。
それはこのテストが問題ありと感じている人が多いからです。
一番多い懸念はスピーキングテストの公平さと公正さが保障されないというものです。
音声を録音するわけですから、みんな等しく好条件の環境で録音できるのかという問題。
実際に去年のテストでは、「他の受験生が解答する声が聞こえカンニングもできる状況だった」たという話も聞かれました。
例えばテストの開始のボタンを押すタイミングを少しずらせば、他の人の解答を聞いてから自分の解答を録音できる可能性があります。
出題の音量を下げれば周囲の音を聞くことは出来たそうです。
テストは前半後半に受験生を分けて行われたそうです。
これは一つの端末を二人の受験生で利用するためで、前半組がテストを受けた後、教室に控えていた後半組が前半組の使っていた端末を使って受験をします。
前半組と後半組の教室は隣同士になっていたらしく、後半組の受験生は前半組の受験生の漏れ聞こえる解答から問題を推測することができたし、間の休み時間に問題に関する情報が提供されていたという報告も聞かれています。
そして、それより最も気にかかるのがやはり受験生の「話す力」を公平かつ公正に採点できているかという点です。
ネイティブで研修を受けた者が一人の受験生の解答に対し二人が当たり採点することになります。
しかし、人間が耳で聞いて各自が判断するわけですから、採点の厳しい人と甘い人が出るのは否めないでしょう。
つまり、どの採点者に当たるかで評価が大きく変わる可能性があるということです。
この点に関しては上記のように研修等で評価の均一性を図ることになっていますが、それ以上のことは出てきていません。
最終的には採点者の判断にゆだねるということです。
また、「採点内容の開示はしない」という点も、多くの人に疑念を抱かせています。
言い換えれば、採点ミスがあったとしても誰も指摘できないということです。
点数としての結果しか出ないので、自分のどこが悪くどのように減点されたのかも分かりません。
更に、スピーキングテストを受けなかった受験生には見込みの評価が与えられるという、重要な試験ではありえないような方法が取られていることも疑問視されている。
テストを受けなかった生徒は本来なら点数がもらえないはずだが、周囲の受験生の点数分布と当人の学力テストの結果から見込みの評価がもらえます。
だから、スピーキングテストが苦手な受験生はわざとテストを受けない方が良い結果になる可能性があるのです。
これではスピーキングテストを実施する根本の意味が失われます。
このように多くの問題点の指摘があるのですが、東京都教育委員会は今年も同様にスピーキングテストを実施することを決定しております。
それはこのテストが問題ありと感じている人が多いからです。
一番多い懸念はスピーキングテストの公平さと公正さが保障されないというものです。
音声を録音するわけですから、みんな等しく好条件の環境で録音できるのかという問題。
実際に去年のテストでは、「他の受験生が解答する声が聞こえカンニングもできる状況だった」たという話も聞かれました。
例えばテストの開始のボタンを押すタイミングを少しずらせば、他の人の解答を聞いてから自分の解答を録音できる可能性があります。
出題の音量を下げれば周囲の音を聞くことは出来たそうです。
テストは前半後半に受験生を分けて行われたそうです。
これは一つの端末を二人の受験生で利用するためで、前半組がテストを受けた後、教室に控えていた後半組が前半組の使っていた端末を使って受験をします。
前半組と後半組の教室は隣同士になっていたらしく、後半組の受験生は前半組の受験生の漏れ聞こえる解答から問題を推測することができたし、間の休み時間に問題に関する情報が提供されていたという報告も聞かれています。
そして、それより最も気にかかるのがやはり受験生の「話す力」を公平かつ公正に採点できているかという点です。
ネイティブで研修を受けた者が一人の受験生の解答に対し二人が当たり採点することになります。
しかし、人間が耳で聞いて各自が判断するわけですから、採点の厳しい人と甘い人が出るのは否めないでしょう。
つまり、どの採点者に当たるかで評価が大きく変わる可能性があるということです。
この点に関しては上記のように研修等で評価の均一性を図ることになっていますが、それ以上のことは出てきていません。
最終的には採点者の判断にゆだねるということです。
また、「採点内容の開示はしない」という点も、多くの人に疑念を抱かせています。
言い換えれば、採点ミスがあったとしても誰も指摘できないということです。
点数としての結果しか出ないので、自分のどこが悪くどのように減点されたのかも分かりません。
更に、スピーキングテストを受けなかった受験生には見込みの評価が与えられるという、重要な試験ではありえないような方法が取られていることも疑問視されている。
テストを受けなかった生徒は本来なら点数がもらえないはずだが、周囲の受験生の点数分布と当人の学力テストの結果から見込みの評価がもらえます。
だから、スピーキングテストが苦手な受験生はわざとテストを受けない方が良い結果になる可能性があるのです。
これではスピーキングテストを実施する根本の意味が失われます。
このように多くの問題点の指摘があるのですが、東京都教育委員会は今年も同様にスピーキングテストを実施することを決定しております。
去年の結果を見て思うこと(私見)
ESAT-Jではテスト結果をA(20点)、B(16点)、C(12点)、D(8点)、E(4点)、F(0点)の6段階に評価します。
そして、色々問題点を抱えながらも強行されたスピーキングテストですが、結果は次のようになりました。
なんとA~Cの評価を受けた受験生が73.8%にも上ったのです。
これはどういうことでしょうか。
「これは受験生がものすごく頑張った結果だ」と好意的に捉えている人もいるようですが、私はそうは思いません。
普段生徒たちが英語を読んだり話したりするのを聞いても、これほど「話す力」がすぐれているとは思いません。
受験生も初めて実施されるスピーキングテストで過去問もない状態で、本当にしっかりまとも対策ができたのかというと、そんなことはないと言わざるを得ません。
それは現場で実際に生徒を指導する立場にある私がよく分かります。
対策するにも誰も受けたことのないテストに対して、ある程度の情報が提供されていると言っても、手探りでやっている感は否定できません。
だから、十分にこのテストに対して準備できていたかというと、はなはだ疑問です。
では、この結果はどのように捉えるべきでしょうか。
私は単純に「採点者が甘かった」「画一的で本来求められている評価ができなかった」からだと考えます。
初めてのテストで採点を厳しくし全体の平均点が下がると、当然テストの内容に関して多くの疑問の声が寄せられるでしょう。
先の述べたように「採点内容の開示はしない」のであって、唯一外部へ提供されるものがテスト結果です。
それが低ければだれもが不満を持ち、テストに対して懐疑的になります。
それよりは、甘く点をつけておけば、疑問を持っていたとしても高得点をもらっているので、反対の声は上げづらくなります。
採点者自身も厳しくつけたことで受験生や関係者から批判を受けるのを恐れ、採点が甘くなってしまったというのも人の道理でしょう。
もう一点の「画一的で本来求められている評価ができなかった」に関しては次のような意味です。
四技能の中でも「話す力」は明確に評価の基準を作りづらいので、採点者の裁量に任せる所が多くなりがちです。
例えば、「上手に話す」と言っても、それは発音がネイティブに近いという意味なのでしょうか。
それとも「コミュニケーションが的確で自分の意思を言葉で相手に正確に伝えられる」ということでしょうか。
そして、両者とも客観的な数値化はできないので、評価そのものの判断は採点者の感じ方次第ということになります。
これがしばしば指摘されている「公平性の欠如」という問題です。
そこで、これを回避するために画一的な基準でスピーキングテストの評価を行ったのではないかと考えたのです。
どういうことかというと、例えば「Do you ~?」の質問に対しては「Yes, I do.」か「No, I don't.」と答えなければいけないとすることです。
こうすれば明確に○×が付けられます。
しかし、これにも疑問点があります。
「話す力」を評価するということですが、実際の英会話の中でネイティブの人たちは「Do you ~?」の質問に対しては必ずしも「Yes, I do.」か「No, I don't.」で答えている訳ではないということ。
このように形式だけに縛って評価することが、生徒たちの「話す力」を伸ばすことにつながるのだろうか。
また、このような画一的基準で評価するならば、それはスピーキングテストでなくライティングテストでも十分だということ。
つまり、これではスピーキングテストをする意味がないということです。
以上が私の感じる問題点です。
スピーキングテストをすること自体は悪いことではないと思います。
これによって「話す力」に対する重要性が認識されれば、それはいいことです。
しかし、これまで議論したように、的確な評価方法が確立されていない現状では、スピーキングテストを入試という人生において重要で、だからこそ厳格に公平性という公正性が求められる試験に導入するには時期尚早と言わざると得ないと思います。
いろいろ大人の事情が見え隠れしているようですが、そのようなことで生徒たちを巻き込んでくれないでほしいというのが本音であります。









今年もスピーキングテストはあります。
しかも、他の試験よりずっと早い11月です。
勘違いして準備を怠ることのないようにお願い申し上げます。
葛西TKKアカデミーでも、このスピーキングテストの対策講座を実施していますので、関心のある方は是非お問合せください。
受験生の皆さん、この夏休みが勝負ですよ!
酷暑に大変でしょうが、何とか踏ん張って、後悔ないように毎日の勉強を進めてください。



























そして、色々問題点を抱えながらも強行されたスピーキングテストですが、結果は次のようになりました。
なんとA~Cの評価を受けた受験生が73.8%にも上ったのです。
これはどういうことでしょうか。
「これは受験生がものすごく頑張った結果だ」と好意的に捉えている人もいるようですが、私はそうは思いません。
普段生徒たちが英語を読んだり話したりするのを聞いても、これほど「話す力」がすぐれているとは思いません。
受験生も初めて実施されるスピーキングテストで過去問もない状態で、本当にしっかりまとも対策ができたのかというと、そんなことはないと言わざるを得ません。
それは現場で実際に生徒を指導する立場にある私がよく分かります。
対策するにも誰も受けたことのないテストに対して、ある程度の情報が提供されていると言っても、手探りでやっている感は否定できません。
だから、十分にこのテストに対して準備できていたかというと、はなはだ疑問です。
では、この結果はどのように捉えるべきでしょうか。
私は単純に「採点者が甘かった」「画一的で本来求められている評価ができなかった」からだと考えます。
初めてのテストで採点を厳しくし全体の平均点が下がると、当然テストの内容に関して多くの疑問の声が寄せられるでしょう。
先の述べたように「採点内容の開示はしない」のであって、唯一外部へ提供されるものがテスト結果です。
それが低ければだれもが不満を持ち、テストに対して懐疑的になります。
それよりは、甘く点をつけておけば、疑問を持っていたとしても高得点をもらっているので、反対の声は上げづらくなります。
採点者自身も厳しくつけたことで受験生や関係者から批判を受けるのを恐れ、採点が甘くなってしまったというのも人の道理でしょう。
もう一点の「画一的で本来求められている評価ができなかった」に関しては次のような意味です。
四技能の中でも「話す力」は明確に評価の基準を作りづらいので、採点者の裁量に任せる所が多くなりがちです。
例えば、「上手に話す」と言っても、それは発音がネイティブに近いという意味なのでしょうか。
それとも「コミュニケーションが的確で自分の意思を言葉で相手に正確に伝えられる」ということでしょうか。
そして、両者とも客観的な数値化はできないので、評価そのものの判断は採点者の感じ方次第ということになります。
これがしばしば指摘されている「公平性の欠如」という問題です。
そこで、これを回避するために画一的な基準でスピーキングテストの評価を行ったのではないかと考えたのです。
どういうことかというと、例えば「Do you ~?」の質問に対しては「Yes, I do.」か「No, I don't.」と答えなければいけないとすることです。
こうすれば明確に○×が付けられます。
しかし、これにも疑問点があります。
「話す力」を評価するということですが、実際の英会話の中でネイティブの人たちは「Do you ~?」の質問に対しては必ずしも「Yes, I do.」か「No, I don't.」で答えている訳ではないということ。
このように形式だけに縛って評価することが、生徒たちの「話す力」を伸ばすことにつながるのだろうか。
また、このような画一的基準で評価するならば、それはスピーキングテストでなくライティングテストでも十分だということ。
つまり、これではスピーキングテストをする意味がないということです。
以上が私の感じる問題点です。
スピーキングテストをすること自体は悪いことではないと思います。
これによって「話す力」に対する重要性が認識されれば、それはいいことです。
しかし、これまで議論したように、的確な評価方法が確立されていない現状では、スピーキングテストを入試という人生において重要で、だからこそ厳格に公平性という公正性が求められる試験に導入するには時期尚早と言わざると得ないと思います。
いろいろ大人の事情が見え隠れしているようですが、そのようなことで生徒たちを巻き込んでくれないでほしいというのが本音であります。









今年もスピーキングテストはあります。
しかも、他の試験よりずっと早い11月です。
勘違いして準備を怠ることのないようにお願い申し上げます。
葛西TKKアカデミーでも、このスピーキングテストの対策講座を実施していますので、関心のある方は是非お問合せください。
受験生の皆さん、この夏休みが勝負ですよ!
酷暑に大変でしょうが、何とか踏ん張って、後悔ないように毎日の勉強を進めてください。



























2023.07.26
vイベント紹介『スケスケ展』今年の夏も特別展に出かけて新発見をしようv

もうすぐ夏休みですね。
夏休みといえば、毎年「恐竜展」や「昆虫展」など子供たちが興味を持ちそうな特別展示が各地で行われます。
せっかくの休みなので時間を有効に使って、このようなイベントに参加し、普段体験できないようなことをやってみたり、今まで知らなかった新しい発見をしてみたりするのも楽しいです。
そして、これらの経験が子供たちの好奇心を刺激し、更なる知的探求を進めるきっかけになればと考えています。
ということで、今年行われる都内の参加しやすいイベントの中から、私のお勧めを一つ選んでみました。
ご都合が合えば足を運んでみてはどうでしょうか。









今回ご紹介したい夏休みのイベントは『スケスケ展』です。
7月7日から8月27日まで、東京ドームシティで平日は10:00~17:00、土日祝は10:00~18:00で開催されています。
都心でアクセスもしやすいので、比較的容易に出かけることができます。
全国でも既に12か所で巡回され、累計35万人を突破した今話題の展示です。
東京が最後の開催都市となります。
これで『スケスケ展』は終わりとなってしまうので、見逃すことのないようにお願いします。
『スケスケ展』へのリンクはこちら
この展示は生物から非生物まで、とにかく透けさせて中身を見てみようというイベントです。
そこには見た目からは想像できないような、メカニズムが隠されています。
普段隠れて見えないものに触れることで、いろいろな生き物やモノの仕組みを理解したり新発見したりするのです。
毎日の生活の中では決して目にすることもない貴重な内部構造を見ることで、子供たちの大きな驚きと関心を高めることでしょう。
誰もが持つ「見えないものを見てみたい」という欲求に応えるように、様々な機械や構造物だけでなく、生物なども含めて、最新の映像技術を駆使して、普段見えないものを透かして刺激的に視覚に届けてくれます。
夏休みといえば、毎年「恐竜展」や「昆虫展」など子供たちが興味を持ちそうな特別展示が各地で行われます。
せっかくの休みなので時間を有効に使って、このようなイベントに参加し、普段体験できないようなことをやってみたり、今まで知らなかった新しい発見をしてみたりするのも楽しいです。
そして、これらの経験が子供たちの好奇心を刺激し、更なる知的探求を進めるきっかけになればと考えています。
ということで、今年行われる都内の参加しやすいイベントの中から、私のお勧めを一つ選んでみました。
ご都合が合えば足を運んでみてはどうでしょうか。









今回ご紹介したい夏休みのイベントは『スケスケ展』です。
7月7日から8月27日まで、東京ドームシティで平日は10:00~17:00、土日祝は10:00~18:00で開催されています。
都心でアクセスもしやすいので、比較的容易に出かけることができます。
全国でも既に12か所で巡回され、累計35万人を突破した今話題の展示です。
東京が最後の開催都市となります。
これで『スケスケ展』は終わりとなってしまうので、見逃すことのないようにお願いします。
『スケスケ展』へのリンクはこちら
この展示は生物から非生物まで、とにかく透けさせて中身を見てみようというイベントです。
そこには見た目からは想像できないような、メカニズムが隠されています。
普段隠れて見えないものに触れることで、いろいろな生き物やモノの仕組みを理解したり新発見したりするのです。
毎日の生活の中では決して目にすることもない貴重な内部構造を見ることで、子供たちの大きな驚きと関心を高めることでしょう。
誰もが持つ「見えないものを見てみたい」という欲求に応えるように、様々な機械や構造物だけでなく、生物なども含めて、最新の映像技術を駆使して、普段見えないものを透かして刺激的に視覚に届けてくれます。
展示物
身近な機械や製品をスケスケ
身の回りにある機械や製品を透明なアクリルにしたり、部品の一部を切り取りむき出しにしたりして中身が見えるように展示。
ピアノやレーシングカー、自動販売機にいろいろなボールの中身が見えるだけでなく、実際に自分の手で触り乗ることができ、動かしながらその仕組みを見ることができます。
ピアノやレーシングカー、自動販売機にいろいろなボールの中身が見えるだけでなく、実際に自分の手で触り乗ることができ、動かしながらその仕組みを見ることができます。
水棲生物をスケスケ
水に関係の深い生き物を集め、その中でも体が透けているものを展示してあります。
カエルや魚、クラゲなど透明な体を持つ不思議な生き物の、生きている体内を見ることができます。
解剖や図解と違い、心臓の拍動や血液の循環など生命活動をライブで見ることができ、これはもうインパクト大です。
また、少し変わったものとして、普段は頑丈で全く中身が見えないヤドカリの殻を透明なものに置き換え、彼らどのように殻の家の中で暮らしているのか分かります。
透明な殻を担いで動く様は少しかわいくもあります。
カエルや魚、クラゲなど透明な体を持つ不思議な生き物の、生きている体内を見ることができます。
解剖や図解と違い、心臓の拍動や血液の循環など生命活動をライブで見ることができ、これはもうインパクト大です。
また、少し変わったものとして、普段は頑丈で全く中身が見えないヤドカリの殻を透明なものに置き換え、彼らどのように殻の家の中で暮らしているのか分かります。
透明な殻を担いで動く様は少しかわいくもあります。
最新技術を使ってスケスケ
有機物や無機物の展示だけでなく、最新の映像技術を駆使して様々なものをスケスケにしてくれます。
例えば、スクリーンの前に立つと自分の体が透けているように体内が写し出されます。
これは単に映し出すだけでなく、自分たちの動きに合わせて映像もリアルタイムで動くので、本当に自分の体が透けて見えるように感じます。
また、動物の骨格から何の動物か想像し、後で重ねて正解の動物を見せてくれるコーナーもあります。
分かるようで意外と分からない。
「ここの部分には骨がなかったんだ」など驚きもたくさんあります。
他にも箱の中身をさわったりにおいをかいだりして当てるコーナーや、不思議なメガネをかけると中身が見える画面など、いろいろ楽しい展示が用意されています。
イラストにあるものの中味を自分で考えて描くお絵描きや、ブラックライトで浮かび上がる特別なペンで絵を描くコーナーも子供たちに人気です。








せっかくの夏休みですから、家族そろって出かけてみてはいかがでしょうか。
数々の驚きの展示に、きっと忘れられない家族の思い出になるでしょう。
特に、東京ではここだけのAIロボットを使った案内によるガイドツアーもあるそうなので、一度訪ねてみてはどうでしょう。
これまで見えなかったものが見えて、新しい発見に心を躍らせると、知的好奇心が芽生え、知りたい欲求が高まります。
そのような探求心は勉強でもきっと大いに役に立つはずです。
究極の「A-ha!」体験を『スケスケ展』で!





















例えば、スクリーンの前に立つと自分の体が透けているように体内が写し出されます。
これは単に映し出すだけでなく、自分たちの動きに合わせて映像もリアルタイムで動くので、本当に自分の体が透けて見えるように感じます。
また、動物の骨格から何の動物か想像し、後で重ねて正解の動物を見せてくれるコーナーもあります。
分かるようで意外と分からない。
「ここの部分には骨がなかったんだ」など驚きもたくさんあります。
他にも箱の中身をさわったりにおいをかいだりして当てるコーナーや、不思議なメガネをかけると中身が見える画面など、いろいろ楽しい展示が用意されています。
イラストにあるものの中味を自分で考えて描くお絵描きや、ブラックライトで浮かび上がる特別なペンで絵を描くコーナーも子供たちに人気です。








せっかくの夏休みですから、家族そろって出かけてみてはいかがでしょうか。
数々の驚きの展示に、きっと忘れられない家族の思い出になるでしょう。
特に、東京ではここだけのAIロボットを使った案内によるガイドツアーもあるそうなので、一度訪ねてみてはどうでしょう。
これまで見えなかったものが見えて、新しい発見に心を躍らせると、知的好奇心が芽生え、知りたい欲求が高まります。
そのような探求心は勉強でもきっと大いに役に立つはずです。
究極の「A-ha!」体験を『スケスケ展』で!





















2023.06.28
「チャンツ」って何?英語の練習法の一つです

「チャンツ」という言葉をご存じですか。
これは英語の練習に行う方法の一つです。
ノリの良いリズムに合わせて英語の単語や文を発音します。
音楽に合わせて発音するので、単語や文が格段に覚えやすくなります。
そして、英語特有の抑揚やリズムも身に付き、普段ネイティブの人が話す英語の速さでも英語が聞き取れるようになります。
このように口と耳を自然な英語のスピードとリズムに慣れさせることで、英語が日本人にありがちな「カタカナ英語」ならないようにします。
今回は、このような「チャンツ」についてご紹介いたします。








これは英語の練習に行う方法の一つです。
ノリの良いリズムに合わせて英語の単語や文を発音します。
音楽に合わせて発音するので、単語や文が格段に覚えやすくなります。
そして、英語特有の抑揚やリズムも身に付き、普段ネイティブの人が話す英語の速さでも英語が聞き取れるようになります。
このように口と耳を自然な英語のスピードとリズムに慣れさせることで、英語が日本人にありがちな「カタカナ英語」ならないようにします。
今回は、このような「チャンツ」についてご紹介いたします。








どのような人に適した練習法か
音楽にのせて自然なスピードでネイティブの発音を聞きながら、リズムに合わせて自分も発音してみるチャンツは特に、まだ勉強を理屈で理解するより感覚的に理解する低学年の生徒の英語教育に適しています。
もちろん高学年や大人だからチャンツが役に立たないという訳ではありません。
これらの人たちも興味があれば是非チャレンジしてほしい練習方法です。
先ほども述べたように、英語が持つ独特の抑揚やリズム、そして発音を自然な速さで理解し話せるようになります。
もちろん高学年や大人だからチャンツが役に立たないという訳ではありません。
これらの人たちも興味があれば是非チャレンジしてほしい練習方法です。
先ほども述べたように、英語が持つ独特の抑揚やリズム、そして発音を自然な速さで理解し話せるようになります。
「英語の歌」との違いは?
このようなチャンツですが、英語の歌で英語の練習するのと何が違うのでしょうか。
確かにリズムに合わせて英語を発音する点では似ていますが、チャンツの場合、基本的にメロディーはありません。
だから、音楽に馴染みのない生徒や歌が苦手な生徒でも発音することができます。
チャンツの歌詞ですが、単語だけのものや対話など形式的決まっているもの、シンプルで短い文になっているものがほとんどです。
一文が非常に短く内容もシンプルなので、各文や語が覚えやすく単純で分かりやすいです。
一方、歌の歌詞は文章になっていたりストーリーが組み込まれていたりと、低学年の生徒には難しすぎて時には理解できないことがあります。
文法的に複雑な文も出てきますし、前後の文脈や歌の背景まで知らないと分からないこともあります。
よって、低学年の生徒を始めとする英語初心者にはチャンツで練習した方が楽で分かりやすく英語も身に付きやすいでしょう。
確かにリズムに合わせて英語を発音する点では似ていますが、チャンツの場合、基本的にメロディーはありません。
だから、音楽に馴染みのない生徒や歌が苦手な生徒でも発音することができます。
チャンツの歌詞ですが、単語だけのものや対話など形式的決まっているもの、シンプルで短い文になっているものがほとんどです。
一文が非常に短く内容もシンプルなので、各文や語が覚えやすく単純で分かりやすいです。
一方、歌の歌詞は文章になっていたりストーリーが組み込まれていたりと、低学年の生徒には難しすぎて時には理解できないことがあります。
文法的に複雑な文も出てきますし、前後の文脈や歌の背景まで知らないと分からないこともあります。
よって、低学年の生徒を始めとする英語初心者にはチャンツで練習した方が楽で分かりやすく英語も身に付きやすいでしょう。
「チャンツ」の利点
1.とにかく楽しく英語初心者でも簡単にできる
これまでの繰り返しにはなりますが、音楽を使ってリズムに合わせて練習するチャンツはとても楽しく、英語そのものになじみがなくよく分からない人でも簡単に練習できるという利点があります。
テンポよく楽しみながらやっているうちに自然とネイティブのような発音と話し方が身に付きます。
特に幼児は体を動かすことが好きなので、チャンツに合わせて跳ねたり踊ったりすると、遊び感覚でキャッキャ言いながら夢中で発音してくれます。
低年齢から外国語を学ばせたいときは、その導入としてチャンツはぴったりです。
こうして英語に対して好印象を持つようになると、その後の英語の勉強や実践においても積極的になり、さらに言語習得が加速するでしょう。
ただ書いたり読んだりするだけの勉強は、どうしても単調になりがちで、特にまだ忍耐力が十分に育っていない低学年の生徒にはつまらないものになってしまいます。
結果、せっかく勉強していても飽きて集中力が泣くなり、退屈で面白くないものに感じられてきます。
やがてモチベーションも下がり、最悪の場合、英語が嫌いになってしまうかも知れません。
よって、英語の習い始めはチャンツでやった方が有効かもしれません。
テンポよく楽しみながらやっているうちに自然とネイティブのような発音と話し方が身に付きます。
特に幼児は体を動かすことが好きなので、チャンツに合わせて跳ねたり踊ったりすると、遊び感覚でキャッキャ言いながら夢中で発音してくれます。
低年齢から外国語を学ばせたいときは、その導入としてチャンツはぴったりです。
こうして英語に対して好印象を持つようになると、その後の英語の勉強や実践においても積極的になり、さらに言語習得が加速するでしょう。
ただ書いたり読んだりするだけの勉強は、どうしても単調になりがちで、特にまだ忍耐力が十分に育っていない低学年の生徒にはつまらないものになってしまいます。
結果、せっかく勉強していても飽きて集中力が泣くなり、退屈で面白くないものに感じられてきます。
やがてモチベーションも下がり、最悪の場合、英語が嫌いになってしまうかも知れません。
よって、英語の習い始めはチャンツでやった方が有効かもしれません。
2.自然な英語が身に付きやすい
日本人が英語を学ぶときの問題点の一つとして発音があります。
日本語以外の言語に馴染みのあまりない日本人は、他言語を学習するときどうしても日本語に当てはめてしまうという欠点があります。
しかし、英語を始めとして多くの他言語は日本語と直接関わりがないことが多く、発音体系が日本語と大きく異なることがほとんどです。
そのような言語に日本語の発音形態を無理やり押し込めても、その言語本来の発音が習得できる訳でなく、「カタカナ英語」のような不自然な英語になってしまいます。
そうなると当然ネイティブの人に英語が伝わらないだけでなく、相手の話す英語の聞き取りもできなくなってしまいます。
これは英語に実際触れる機会の少ない日本という環境を考えると仕方ない部分もありますが、それに甘んじていては本来の英語は身に付きません。
そこは工夫が必要です。
そのような時に「チャンツ」を使った練習法は有効です。
ネイティブの人発音する音を聞きながら、英語独特の発音法、抑揚、リズムをまねるだけで自然と身に付いてきます。
音や語彙、意味のかたまりとして英語を捉えることができるようになり、よりネイティブの聞き取りや発話に近づくことができます。
リズムに合わせてテンポよく反復するうちに、無意識のうちに自然なイントネーションや音を覚えていきます。
日本語以外の言語に馴染みのあまりない日本人は、他言語を学習するときどうしても日本語に当てはめてしまうという欠点があります。
しかし、英語を始めとして多くの他言語は日本語と直接関わりがないことが多く、発音体系が日本語と大きく異なることがほとんどです。
そのような言語に日本語の発音形態を無理やり押し込めても、その言語本来の発音が習得できる訳でなく、「カタカナ英語」のような不自然な英語になってしまいます。
そうなると当然ネイティブの人に英語が伝わらないだけでなく、相手の話す英語の聞き取りもできなくなってしまいます。
これは英語に実際触れる機会の少ない日本という環境を考えると仕方ない部分もありますが、それに甘んじていては本来の英語は身に付きません。
そこは工夫が必要です。
そのような時に「チャンツ」を使った練習法は有効です。
ネイティブの人発音する音を聞きながら、英語独特の発音法、抑揚、リズムをまねるだけで自然と身に付いてきます。
音や語彙、意味のかたまりとして英語を捉えることができるようになり、よりネイティブの聞き取りや発話に近づくことができます。
リズムに合わせてテンポよく反復するうちに、無意識のうちに自然なイントネーションや音を覚えていきます。
「チャンツ」の注意点
1.「チャンツ」の前に「フォニックス」
チャンツはリズム良い音楽を聴きながら繰り返すことで自然とネイティブのような英語を練習する方法ですが、音を聞いたからといって必ずしも正しい発音ができるようになるとは限りません。
例えは日本人の苦手な「L」と「R」の発音ですが、仮に違うことは分かっても、どのように違いどうすればそれぞれ正しく発音できるか分からないかも知れません。
同様に「TH」の発音も日本語の中にはないので、最初はどのように音を出せばいいのかさえ分からないでしょう。
従って、最初は正しい発音の仕方を口の形や舌の使い方、息の出し方をきちんと教える必要があります。
このような発音の仕方を「フォニックス」というのですが、チャンツをする前には必ずフォニックスの確認をしましょう。
例えは日本人の苦手な「L」と「R」の発音ですが、仮に違うことは分かっても、どのように違いどうすればそれぞれ正しく発音できるか分からないかも知れません。
同様に「TH」の発音も日本語の中にはないので、最初はどのように音を出せばいいのかさえ分からないでしょう。
従って、最初は正しい発音の仕方を口の形や舌の使い方、息の出し方をきちんと教える必要があります。
このような発音の仕方を「フォニックス」というのですが、チャンツをする前には必ずフォニックスの確認をしましょう。
2.量をたくさんこなす
また、チャンツは何度も繰り返しながら英語を勉強するのですが、一つ一つのチャンツは表現も限定的で何でも自分の言いたいことが言えるようになるという訳ではありません。
よって、一つのチャンツができるようになったから終わりではなく、より多様で多くのチャンツに触れることで、この限界を広げなければいけません。
幸いにして最近では書籍だけでなくユーチューブなどのメディアでもチャンツを手軽に聞くことができますので、できるだけ多くのチャンツを聞いて表現のバリエーションを広げてください。
語彙も増え、英会話でも役に立ちます。
よって、一つのチャンツができるようになったから終わりではなく、より多様で多くのチャンツに触れることで、この限界を広げなければいけません。
幸いにして最近では書籍だけでなくユーチューブなどのメディアでもチャンツを手軽に聞くことができますので、できるだけ多くのチャンツを聞いて表現のバリエーションを広げてください。
語彙も増え、英会話でも役に立ちます。
3.高学年の生徒には注意
多くの場合、低学年の生徒にはさほど問題ないのですが、学年が上がり自我がしっかりしてきて周囲の目が気になるようになってくると、単純に音楽を聴きながら楽しく声を出して発音するのが難しくなってきます。
言語である以上音声を発するのは非常に大事なのですが、どうしても恥ずかしがってできない、もしくは格好をつけて大声を出さないということがあります。
聞いて音を出すことで英語の自然な発音が身に付くので、それができなくなるとチャンツの効果も半減してしまいます。
一人でチャンツを練習できるのであればいいのですが、そうでなければ他の練習方法を試した方がいいかも知れません。
もちろんチャンツに年齢制限がある訳ではないので、低学年から高学年、そして大人であっても英語を習得する大きな助けになりますが、年齢が上がるほど上記のように「声を出す」ことに対する抵抗感が生じがちなので注意しましょう。
その生徒がチャンツでの練習に適しているかどうかの判断が要求されます。
言語である以上音声を発するのは非常に大事なのですが、どうしても恥ずかしがってできない、もしくは格好をつけて大声を出さないということがあります。
聞いて音を出すことで英語の自然な発音が身に付くので、それができなくなるとチャンツの効果も半減してしまいます。
一人でチャンツを練習できるのであればいいのですが、そうでなければ他の練習方法を試した方がいいかも知れません。
もちろんチャンツに年齢制限がある訳ではないので、低学年から高学年、そして大人であっても英語を習得する大きな助けになりますが、年齢が上がるほど上記のように「声を出す」ことに対する抵抗感が生じがちなので注意しましょう。
その生徒がチャンツでの練習に適しているかどうかの判断が要求されます。
4.できれば発音だけでなくジェスチャーもつけて
テンポの良いリズムに合わせてダンスしながらチャンツをするのは良い方法です。
振付があれば楽しく踊れますし、特に決めなくても体が自然に動いてしまうものです。
体を動かせば、大脳が刺激されよく働くと言われています。
こうすれば英語らしいイントネーションやリズム、発音が身に付きやすくなります。
内容に合わせたジェスチャーをつけると理解しやすくなり、フレーズを覚えるのも楽になります。
従って、チャンツをするときはただ声を出すだけでなく、体全体を使って練習しましょう。








チャンツは日本の英語教育においても注目されていて、最近教科化が進む小学校の英語教育でもたくさん取り入れられています。
特に低年齢層の英語学習に向いているということで、小学校の英語の授業に非常に適しています。
また、チャンツは上手に使えば単純なフレーズだけでなく、長い文や複雑な文法に応用することも可能です。
このようにチャンツの持つ可能性はとても大きいと言えます。
都立高校のお入試ではスピーキングテストが既に導入され、大学入試においても文科省はスピーキングテストを実施することを念頭に現在準備を進めています。
このように英語教育では今後ますます「話す力」が要求されます。
そのような時にも、チャンツを使った練習は非常に有効です。
英語は多くの生徒が不得意としますが、その入り口でチャンツを利用して苦手意識をなくし、楽しみながら自然な英語を身に付けましょう。






















振付があれば楽しく踊れますし、特に決めなくても体が自然に動いてしまうものです。
体を動かせば、大脳が刺激されよく働くと言われています。
こうすれば英語らしいイントネーションやリズム、発音が身に付きやすくなります。
内容に合わせたジェスチャーをつけると理解しやすくなり、フレーズを覚えるのも楽になります。
従って、チャンツをするときはただ声を出すだけでなく、体全体を使って練習しましょう。








チャンツは日本の英語教育においても注目されていて、最近教科化が進む小学校の英語教育でもたくさん取り入れられています。
特に低年齢層の英語学習に向いているということで、小学校の英語の授業に非常に適しています。
また、チャンツは上手に使えば単純なフレーズだけでなく、長い文や複雑な文法に応用することも可能です。
このようにチャンツの持つ可能性はとても大きいと言えます。
都立高校のお入試ではスピーキングテストが既に導入され、大学入試においても文科省はスピーキングテストを実施することを念頭に現在準備を進めています。
このように英語教育では今後ますます「話す力」が要求されます。
そのような時にも、チャンツを使った練習は非常に有効です。
英語は多くの生徒が不得意としますが、その入り口でチャンツを利用して苦手意識をなくし、楽しみながら自然な英語を身に付けましょう。






















2023.06.23
6月新規入塾生特別キャンペーン!残りあとわずか!

前日告知した通り、葛西TKKアカデミーでは新規入塾生に向けた特別キャンペーンを実施中です。
勉強が難しくなってきて、だんだん授業についていけなくなり不安を抱える生徒が増えるこの時期。
そんな生徒たちが葛西TKKアカデミーをより利用しやすいようにと行っている特別企画です。
ちょうど定期試験も終わり、思ったより点数が取れていないと感じた生徒は早々に手を打つ必要があります。
今までは一人で何とかなった勉強も、徐々にそうはいかなくなってきた人も多いことでしょう。
そんな時は無理して自分で何とかしようとせず、素直に外部に助けを求めるのはとても良い方法です。
人に頼ることは決して悪いことではありませんし、時間などを考えるととても効率のより解決策でもあります。
「一人で悩まず、相談してほしい」という気持ちを込めて、だれでも気軽に塾に行けるようにと願っています。
勉強が分からなくなったとき、絶対に問題を先送りにしてはいけません。
勉強を分からないまま放置しておくと次の勉強も分からなくなり、ますます勉強が嫌になってしまいます。
勉強嫌いになってしまったら、勉強嫌いを直すのは相当に大変です。
だから、そうなる前に手を打ちましょう。
そのための、6月新規入塾生特別キャンペーンです。








葛西TKKアカデミーは、勉強に悩む生徒がより手軽に塾という選択ができるように『6月新規入塾生特別キャンペーン』を実施します。
内容は次の通りです。
中高校生で、6月中に体験授業を申込いただき入塾を決定されると、毎月の授業料から3000円値引きさせていただきます。
高校入試を控えた中学三年生は、入試対策週5コマのコース料金から5000円値引きさせていただきます。
学校の勉強がだんだん難しくなりついていくのも大変になるこの時期に、少しでも経済的負担を減らし、お手軽に塾で勉強ができるようにと実施するお得なキャンペーンです。
このチャンスをお見逃しなく!!!








勉強は対応が遅れれば遅れるほど、リカバリーが困難になります。
まだそれほど問題が深刻化する前に、対策を取りましょう。
皆様の勉強に少しでもお役に立ちたい葛西TKKアカデミーが贈る、めったにないキャンペーンです。
今月いっぱいの特別企画ですので、残りわずかです。
このチャンスをお見逃しなく!!!





















勉強が難しくなってきて、だんだん授業についていけなくなり不安を抱える生徒が増えるこの時期。
そんな生徒たちが葛西TKKアカデミーをより利用しやすいようにと行っている特別企画です。
ちょうど定期試験も終わり、思ったより点数が取れていないと感じた生徒は早々に手を打つ必要があります。
今までは一人で何とかなった勉強も、徐々にそうはいかなくなってきた人も多いことでしょう。
そんな時は無理して自分で何とかしようとせず、素直に外部に助けを求めるのはとても良い方法です。
人に頼ることは決して悪いことではありませんし、時間などを考えるととても効率のより解決策でもあります。
「一人で悩まず、相談してほしい」という気持ちを込めて、だれでも気軽に塾に行けるようにと願っています。
勉強が分からなくなったとき、絶対に問題を先送りにしてはいけません。
勉強を分からないまま放置しておくと次の勉強も分からなくなり、ますます勉強が嫌になってしまいます。
勉強嫌いになってしまったら、勉強嫌いを直すのは相当に大変です。
だから、そうなる前に手を打ちましょう。
そのための、6月新規入塾生特別キャンペーンです。








葛西TKKアカデミーは、勉強に悩む生徒がより手軽に塾という選択ができるように『6月新規入塾生特別キャンペーン』を実施します。
内容は次の通りです。
中高校生で、6月中に体験授業を申込いただき入塾を決定されると、毎月の授業料から3000円値引きさせていただきます。
高校入試を控えた中学三年生は、入試対策週5コマのコース料金から5000円値引きさせていただきます。
学校の勉強がだんだん難しくなりついていくのも大変になるこの時期に、少しでも経済的負担を減らし、お手軽に塾で勉強ができるようにと実施するお得なキャンペーンです。
このチャンスをお見逃しなく!!!








勉強は対応が遅れれば遅れるほど、リカバリーが困難になります。
まだそれほど問題が深刻化する前に、対策を取りましょう。
皆様の勉強に少しでもお役に立ちたい葛西TKKアカデミーが贈る、めったにないキャンペーンです。
今月いっぱいの特別企画ですので、残りわずかです。
このチャンスをお見逃しなく!!!





















2023.06.22
昨日は夏至!二十四節気の一つで理科でもよく触れられる日です

昨日は夏至でした。
昨日投稿の予定でしたが間に合わなかったので、本日となりました。
夏至は二十四節気の一つで、北半球においては一年の中で太陽の出ている時間が最も長い日となります。
逆に、冬至は北半球での昼間の時間が一番短くなる日です。








昨日投稿の予定でしたが間に合わなかったので、本日となりました。
夏至は二十四節気の一つで、北半球においては一年の中で太陽の出ている時間が最も長い日となります。
逆に、冬至は北半球での昼間の時間が一番短くなる日です。








世界各地の夏至
このように夏至は一年の中でも特別な日でありますから、古来より世界中で夏至にまつわる風習やお祭り、儀式などがあります。
また、多くの古代遺跡が夏至と何らかの関係をつけられて建てられたとも言われています。
例えば、有名なイギリスのストーンヘンジは夏至を祝うために紀元前2500年頃に神殿として作られたという説があります。
夏至の日になると、中央の祭壇とヒールストーンを結ぶ直線状に朝日が昇ります。
このことから、ストーンヘンジは人々に夏至を知らせる設備ではないかと考えられています。
同様にエジプトの三大ピラミッドやインカの遺跡の多くも夏至と関係があると言われています。
また、多くの文化でも夏至は特別な日としてお祝いされます。
特に太陽の恵みの乏しい北欧では、最も長く日を浴びることのできる夏至は非常に喜ばしいものであり、大々的なイベントが行われます。
スウェーデンでは「夏至祭り」としてクリスマスより盛大にお祝いするそうですし、デンマークでは様々な場所で焚火が焚かれ、お酒を片手にみんなで楽しい時間を過ごすそうです。
また、多くの古代遺跡が夏至と何らかの関係をつけられて建てられたとも言われています。
例えば、有名なイギリスのストーンヘンジは夏至を祝うために紀元前2500年頃に神殿として作られたという説があります。
夏至の日になると、中央の祭壇とヒールストーンを結ぶ直線状に朝日が昇ります。
このことから、ストーンヘンジは人々に夏至を知らせる設備ではないかと考えられています。
同様にエジプトの三大ピラミッドやインカの遺跡の多くも夏至と関係があると言われています。
また、多くの文化でも夏至は特別な日としてお祝いされます。
特に太陽の恵みの乏しい北欧では、最も長く日を浴びることのできる夏至は非常に喜ばしいものであり、大々的なイベントが行われます。
スウェーデンでは「夏至祭り」としてクリスマスより盛大にお祝いするそうですし、デンマークでは様々な場所で焚火が焚かれ、お酒を片手にみんなで楽しい時間を過ごすそうです。
日本と夏至
日本では、夏至を過ぎると本格的な夏になると言われています。
そして、季節の節目でもあるこの日に、日本各地ではその地域に根差した風習やイベントが行われます。
例えば、関東地方では夏至に「小麦餅」と食べたりお供えをしたりする風習があります。
関西では、この日にタコを食べるという習慣があります。
これはタコのように稲がしっかりと根を張り豊作になるようにと願ってのことだそうです。
夏至から半夏生にかけて田植えや畑仕事を終える目安とされ、農作業の追い込みの時期でもあり、そういう意味でも農耕が盛んな日本にとって意味深い日となっています。
また、多くの神社では「夏越の祓」が行われて、これは茅の輪を神前に立てて、それを3回くぐりながら心身を清める儀式が行われています。
そして、季節の節目でもあるこの日に、日本各地ではその地域に根差した風習やイベントが行われます。
例えば、関東地方では夏至に「小麦餅」と食べたりお供えをしたりする風習があります。
関西では、この日にタコを食べるという習慣があります。
これはタコのように稲がしっかりと根を張り豊作になるようにと願ってのことだそうです。
夏至から半夏生にかけて田植えや畑仕事を終える目安とされ、農作業の追い込みの時期でもあり、そういう意味でも農耕が盛んな日本にとって意味深い日となっています。
また、多くの神社では「夏越の祓」が行われて、これは茅の輪を神前に立てて、それを3回くぐりながら心身を清める儀式が行われています。
学校の勉強と夏至
夏至は学校の勉強でも重要な日で、特に理科の太陽の年周運動で触れられます。
地球は太陽の周りを公転しており、一年で一周するので地球から見ると一年を通して一定の運動を繰り返しているように見えます。
また、地球は地軸が公転面に対して23.4度傾いているので、太陽の日の出日の入りの位置と南中高度(真南を通るときの高さで、一日に太陽が最も高くなる高度)は日々変化します。
夏至では、太陽は最も北側から昇り、一年で南中高度が最も高くなり、そして、最も北に沈みます。
このコースを通るときが、太陽は一番長く日が出ていて、日本の南中高度は最大約78度にもなります。
逆に、日が一番短い冬至では、太陽は最も南から出て南中高度は最小の32度になり、最も南に沈みます。
因みに、春分と秋分は昼と夜の長さが等しくなり、夏至、冬至、春分、秋分が四つの代表的な日として、地球から見える太陽の軌道や地球と太陽との位置関係を考えさせる問題が良く出ます。








夏至を始めとする年中行事は、学校の授業や入試でも度々触れられます。
それぞれの年中行事の意味を深く理解することは、日本人としてその文化を担うと同時に教養としても大きな意味を持ちます。
予め年中行事のことを知っていれば、テストで出てきても慌てることなく親しみを持って取り掛かれるので、問題が解きやすくなります。
従って、家庭でも年中行事を意識して、家族で話題にして子供に理解させることは非常に有益です。
このような行事を実際にやってみると、子供の中で思い出として残り、家族の絆も深まることでしょう。
最近は季節や年中行事を意識することも少なくなってきましたが、機会があるごとに伝統的な文化や風習を見直してみはいかがでしょうか。





















地球は太陽の周りを公転しており、一年で一周するので地球から見ると一年を通して一定の運動を繰り返しているように見えます。
また、地球は地軸が公転面に対して23.4度傾いているので、太陽の日の出日の入りの位置と南中高度(真南を通るときの高さで、一日に太陽が最も高くなる高度)は日々変化します。
夏至では、太陽は最も北側から昇り、一年で南中高度が最も高くなり、そして、最も北に沈みます。
このコースを通るときが、太陽は一番長く日が出ていて、日本の南中高度は最大約78度にもなります。
逆に、日が一番短い冬至では、太陽は最も南から出て南中高度は最小の32度になり、最も南に沈みます。
因みに、春分と秋分は昼と夜の長さが等しくなり、夏至、冬至、春分、秋分が四つの代表的な日として、地球から見える太陽の軌道や地球と太陽との位置関係を考えさせる問題が良く出ます。








夏至を始めとする年中行事は、学校の授業や入試でも度々触れられます。
それぞれの年中行事の意味を深く理解することは、日本人としてその文化を担うと同時に教養としても大きな意味を持ちます。
予め年中行事のことを知っていれば、テストで出てきても慌てることなく親しみを持って取り掛かれるので、問題が解きやすくなります。
従って、家庭でも年中行事を意識して、家族で話題にして子供に理解させることは非常に有益です。
このような行事を実際にやってみると、子供の中で思い出として残り、家族の絆も深まることでしょう。
最近は季節や年中行事を意識することも少なくなってきましたが、機会があるごとに伝統的な文化や風習を見直してみはいかがでしょうか。






















